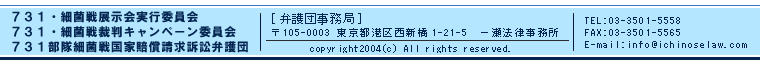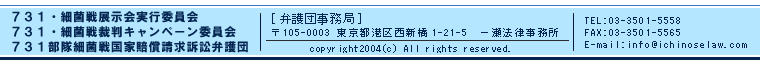|
|
平成14年(ネ)第4815号
控訴人 程秀芝ほか179名
被控訴人 国
準 備 書 面(4)
平成16年7月20日
東京高等裁判所第2民事部 御中
被控訴人指定代理人
宮 田 誠 司
石 川 さ お り
藤 澤 祐 介
峯 金 容 子
高 橋 一 雄
山 田 聡
原 克 好
松 島 晋
第1 はじめに
第2 国家無答責の法理に関する判示内容の誤りについて
1 新潟地裁判決の国家無答責の法理に関する判示内容の要旨
2 控訴人の反論
(1) 反論の要旨
(2) 国家無答責の法理が訴訟法上の制約にすぎない旨の判示について
(3) 本件に国家無答責の法理を適用することは著しく正義・公平に反するから、
その適用は許されない旨の判示について
第3 日中共同声明等の解釈に関する判示内容の誤りについて
1 新潟地裁判決の日中共同声明等の解釈に関する判示内容の要旨
2 被控訴人の反論
(1) 中華人民共和国と中華民国を別個に検討すべきではないこと
(2) 中国及びその国民の請求権は、日華平和条約により、
サン・フランシスコ平和条約の相当規定に従って放棄されていること
ア 日華平和条約の締結
イ 日中共同声明署名時の処理
(3) 個人の損害賠償請求権を国家が放棄し得ること
(4) 中国要人の発言について
被控訴人は,本準備書面において,控訴人らの2004年(平成16年)5月 25日付け第6準備書面(以下「控訴人ら準備書面(6)」という。)に おける主張に対し,必要と認める範囲で反論する。なお,略語等は, 特に断るほか従前の例による。
第1 はじめに
1 新潟地方裁判所平成16年3月26日判決(以下「新潟地裁判決」という。)は,中国国民である原告らが,第二次世界大戦中に当時の日本政府の政策に基づき日本に強制連行され,被告国及び訴外会杜によって新潟港での強制労働に従事させられる等したとして,被告国及び訴外会杜の権利義務を承継した被告会杜に対し,損害賠償及び謝罪広告を請求した事案につき,①国家賠償法施行前の公務員の公権力の行使についても民法709条,715条の適用の可能性を認めるとともに,②中国国民個人が被った損害についての国に対する損害賠償請求権が日中共同声明によって放棄されたとは解し難い旨判示した。控訴人らは,控訴人ら準備書面(6)において,新潟地裁判決の上記判示内容を指摘した上,これらを根拠として,本件に国家無答責の法理を適用することはできない旨及び日中共同声明等により原告ら個人の損害賠償請求権が放棄されたとは考えられない旨を主張する(同準備書面6ないし13ぺ一ジ)。
2 しかし,上記①の判示は,明らかに国家無答責の法理に対する理解を誤ったものであり,また,上記②の判示は,日華平和条約・日中共同声明等に関する判断を誤り,条約の解釈権限を有する政府(憲法73条2,3号,外務省設置法4条4,5号)の見解を正解しないだけでなく,日中間の戦後処理が法的に未解決であるとするに等しく,国際的にみても,異例な判断といわざるを得ない。したがって,新潟地裁判決のこれら誤った判示部分を根拠とする控訴人らの主張もまた失当といわざるを得ない。以下,新潟地裁判決の上記各問題点について詳述する。
第2 国家無答責の法理に関する判示内容の誤りについて
1 新潟地裁判決の国家無答責の法理に関する判示内容の要旨
新潟地裁判決は,原告らが,「国家無答責の法理の適用は,違憲無効で,その埒外でもあり,かつ,正義公平の観点から許されず,被告国は,民法の規定にのっとって,原告らに対して誠意を持って謝罪し,損害賠償に応ずる責務があると言わねばならない。」と主張したのに対し,次のとおり判示した。
① 「戦前においては,行政裁判所法が「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」と定め(同法16条),司法裁判所も国による公権力の行使に関連する行為については民法の不法行為に関する規定を適用しないとしており,司法裁判所及び行政裁判所ともに国の公権力の行使に関連する不法行為に基づく損害賠償請求を受理しなかったため,そのような請求を行うことはできなかった。」
② 「しかし,このようにして,国に対する損害賠償請求を否定する考え方自体が,行政裁判所が廃止され,公法関係及び私法関係の訴訟の全てが司法裁判所で審理されることとなった現行法下においては,合理性・正当性を見出し難い。」
③ 「また,国の公権力の行使が,人間性を無視するような方法(例えば,奴隷的扱い)で行われ,それによって損害が生じたような場合にまで,日本国憲法施行前,国家賠償法施行前の損害であるという一事をもって,国に対して民事責任を追及できないとする解釈・運用は,著しく正義・公平に反するものといわなければならない。本件は,被告国が政策として,法律上・人道上およそ許されない強制連行・強制労働を実施したという悪質な事案であり,これに従事した日本兵らの行為については微塵の要保護性も存在しない。また,・・・被告国は,強制連行・強制労働の事実を隠蔽するために,外務省報告書等を焼却するなど極めて悪質な行為を行っているのである。このような事情を総合すると,現行の憲法及び法律下において,本件強制連行・強制労働のような重大な人権侵害が行われた事案について,裁判所が国家賠償法施行前の法体系下における民法の不法行為の規定の解釈・適用を行うにあたって,公権力の行使には民法の適用がないという戦前の法理を適用することは,正義・公平の観点から著しく相当性を欠くといわなければならない。」
④ 「以上より,少なくとも本件事案において国家無答責の法理を適用することは許されないというべきであるから,国家賠償法附則6項の「従前の例」によることを前提にしても,被告国の行為について民法の不法行為に関する規定が適用されることとなる。」
新潟地裁判決は,上記のように判示して,国賠法施行前の公務員の公権力の行使についても民法709条,715条の適用の可能性を認め,同条に基づく損害賠償責任の成立を認めた。その上で,同判決は,かかる損害賠償請求権は,民法724条後段の除斥期間の規定の適用によって,遅くとも昭和40年11月末日の経過により消減したと判示した。
2 被控訴人の反論
(1) 反論の要旨
新潟地裁判決は,東京高裁平成15年7月判決と同様に,明治23年に国家無答責の法理が当時の基本的法政策として採用された根拠及び行政裁判所法16条,旧民法等の立法経緯についての理解を誤り,国家無答責の法理が単なる訴訟法上の制約ではなく,実体法上の法理であることを正解しておらず,失当である。
そして,新潟地裁判決は,国家無答責の法理について,「正義・公平の観点」という抽象的概念をもってその適用を制限したが,これは法解釈の名に値するものではない。
(2) 国家無答責の法理が訴訟法上の制約にすぎない旨の判示について
ア 新潟地裁判決は,「戦前においては,・・・司法裁判所及び行政裁判所ともに国の公権力の行使に関連する不法行為に基づく損害賠償請求を受理しなかったため,そのような請求を行うことはできなかった。しかし,このようにして,国に対する損害賠償請求を否定する考え方自体が,行政裁判所が廃止され,公法関係及び私法関係の訴訟の全てが司法裁判所で審理されることとなった現行法下においては,合理性・正当性を見出し難しい。」と判示するところ,これは要するに,実体法上,国の権力的作用に基づく損害についても,民法の適用があり,損害賠償請求権が発生するが,国家無答責の法理は,行政裁判所及び司法裁判所に対し,その賠償を求める訴訟が提起できなかったことによる訴訟法上の制約にすぎないとするものである。
イ しかし,被控訴人が従前から繰り返し指摘しているとおり,国家無答責の法理は,国の権力的作用に基づく損害について,民法の不法行為規定の適用がなく,国賠法施行前は,損害賠償責任を認める一般的規定がなかったことによる実体法上の法理であって(最高裁昭和25年判決参照),単なる訴訟制度上の問題ではない。この点に関しては,被控訴人準備書面(3)第1,2,(3),イで述べた東京高裁平成15年7月判決に対する批判がそのまま妥当するので,これを援用する。
(3) 本件に国家無答責の法理を適用することは著しく正義・公平に反するから,その適用は許されない旨の判示について
ア 新潟地裁判決は,「国の公権力の行使が,人間性を無視するような方法(例えば,奴隷的扱い)で行われ,それによって損害が生じたような場合にまで,日本国憲法施行前,国家賠償法施行前の損害であるという一事をもって,国に対して民事責任を追及できないとする解釈・運用は,著しく正義・公平に反するものといわなければならない。」とした上,本件に国家無答責の法理を適用することは著しく正義・公平に反するから,その適用は許されず,被告国の行為について民法の不法行為に関する規定が適用される旨判示した。
イ しかし,前記のとおり,国の権力的作用については国家無答責の法理が妥当するのであり,最高裁昭和25年判決の判示するように,国家無答責の法理は「公権力の行使に関しては当然には民法の適用」がなく,「一般的に国の賠償責任を認めた法律もなかった」ことによるものであるから,この法理の「適用を制限」したからといって,国の賠償責任を認める法律が出現するわけではない。
にもかかわらず,新潟地裁判決は,同法理の適用制限を理由に,直ちに民法の不法行為に関する規定が適用されるとしており,この点で既に失当といわなければならない。「正義・公平の観点」を持ち出したところで,本来民法が適用されることのない法分野について,民法の適用があると結論づけることはできないはずであり,論理に甚だしい飛躍がある。
ウ また,単に「正義・公平の観点」から相当性を欠くとの理由のみで,これを排除ないし制限するとするならば,それは法解釈ではなく,単なる感情論と何ら異なるところはない。「正義・公平の観点」は,その内容が一義的に定まるものではないことから,正義・公平の基準の置き方いかんによっては常にその濫用のおそれを伴う概念であって,安易に「正義・公平の観点」による裁判がされるべきでないのはいうまでもない。
特に,本件のような戦争による被害について,正義・公平を論じ,個別的救済を図ろうとすることは適切でない。被控訴人が,被控訴人準備書面(1),第8で詳述したように,戦争による被害は,戦争の勝敗とは無関係に,戦争当事国のみならず,その当事国相互の国民に広範囲に発生するものであり,特に第一次世界大戦後の近代の戦争は,国家間の全面戦争の形態をとり,その被害は,全国民が被る結果となっている。中国との関係においても,日本国民は,中国が1945年10月に公布した「日僑財産処理弁法」によって,財産を没収されるなど様々な被害を被るに至った。こうした戦争によって生じた被害の賠償問題は,戦後の講和条約によって解決が図られ,我が国においては,サン・フランシスコ平和条約その他二国間の平和条約及びその他関連する条約によって法的に解決したのである(サン・フランシスコ平和条約が和解と信頼の講和であることにつき,横田喜三郎・平和條約の特色(平和條約の綜合研究上巻39ページ・乙第102号証))。
この点に関し,東京高等裁判所平成13年10月11日判決(判例時報1769号61ページ)は,「国家のみに損害賠償請求権を認めることによってこそ,賠償の問題を,被害者間に公平に,また,戦後世界の実情に即して適正に解決することができるというべきである。また,戦争による被害の解決というものは,戦争状態を終わらせて,戦争状態にあった国家及びその国民の間に平和的な関係を築くためにもされるのであるが,そのような公益を実現するためにも,国家が被害を一体としてとらえて,統一的に相手国に賠償を請求し,外交交渉を経て,合意に達することの方が,はるかにその目的に沿うのである。もし,被害者が,それぞれ個別に請求できるとすると,国家は,個別に委任を受けたものに限り,被害者を代理して相手国との交渉に望まねばならない。しかし,それでは,全ての被害者の被害について,一挙に解決することができない。そのために,戦争状態にあった国家及び国民の間で戦争状態を終わらせることが,極めて困難になるであろう。戦争状態の終結は,交戦当事者のみならず,多数の関係国とその国民にとっても必要なことである。それは戦後世界にとって,重要な公益であって,それが,一部の者の私益を優先することによって,害されてはならない。そうすると,被害者個人に加害国に対する直接の賠償請求権を認めることは,かえって問題を複雑にするというべきである。」と判示している(該当箇所同号70ページ4段目から71ページ1段目)。
工 以上のとおり,国家無答責の法理について,「正義・公平の観点」という漠然とした根拠をもってその適用を制限した新潟地裁判決は,失当というほかない。
第3 日中共同声明等の解釈に関する判示内容の誤りについて
1 新潟地裁判決の日中共同声明等の解釈に関する判示内容の要旨
新潟地裁判決は,①中華人民共和国と中華民国との関係からして,両国との間の問題は,明確に分けて別個に検討されなければならないこと,②「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」という日中共同声明5項の文言上,中華人民共和国が個人の被害賠償まで放棄したとは直ちには解し難いこと,③戦争による国民個人の被害についての損害賠償請求権という権利の性質上,当該個人が所属する国家がこれを放棄し得るかどうかにつき疑義が残る上,日中共同声明の署名にもかかわらず,中国国民は戦争被害について何らの補償,代替措置を受けていないこと,④中国要人が,日中共同声明により中国が個人の被害賠償まで放棄したと認識しているとは必ずしもいえないことなどにかんがみれば,日本政府の認識のいかんにかかわらず,中国国民個人が被った損害についての控訴人国に対する損害賠償請求権,特に,安全配慮義務違反という債務不履行に基づく損害賠償請求権までが,日中共同声明によって放棄されたとは解し難いと判示した。
しかしながら,新潟地裁判決の上記判断はいずれも根拠がなく,到底承服できるものではない。以下,詳論する。
2 被控訴人の反論
(1) 中華人民共和国と中華民国を別個に検討すべきではないこと(上記1,①について)
新潟地裁判決は,中華人民共和国と中華民国との関係からして,両国との間の問題は,明確に分けて別個に検討しなければならないと判示する。
しかしながら,新潟地裁判決は,そのように別個に検討すべきものとする根拠を明らかにしていないばかりか,我が国と中華民国及び中華人民共和国との関係を正解しておらず,失当である。
そもそも一国の内部で政府の変動があり,いずれの政府が当該国を代表するのかが問題となる場合には,当該国は第三国との関係で同一性をもって存続する。その際,一国内で二つの政権が革命,内戦により対立抗争しそれぞれ一定の地域を実効的に支配している間に,対立政権が第三国との関係で行った約束その他の行為については,後に全国的支配を確立した新政府が原則としてこれを承継する義務を負うとされている(山本草二「国際法(新版)」314ページ)。
そして,1972年(昭和47年)の日中国交正常化は,国家としての中国を代表する政府の承認の切替えであるから,中華人民共和国と中華民国を全く別個に検討することはあり得ない。すなわち,我が国は,1952年(昭和27年)当時,中国を代表する唯一,合法の政府であった中華民国政府との間で日華平和条約を締結し,同条約によって我が国と国家としての中国との間の戦争状態を終結させ,先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題を完全かつ最終的に解決した。1972年(昭和47年),日中共同声明の発出により,我が国はそれまで中華民国政府を中国を代表する唯一,合法の政府としてしていたことを改め,中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認したのである。
このように,我が国は中華人民共和国と中華民国が別個の国であると認識したことは一度もなく,1972年(昭和47年)の日中国交正常化においては,我が国は国家としての中国を代表する政府の承認の切替えをしたのである。したがって,新潟地裁判決の上記判示は失当である。
(2) 中国及びその国民の請求権は,日華平和条約により,サンフランシスコ平和条約の相当規定に従って放棄されていること(上記1,②について)
新潟地裁判決は,日中共同声明5項の文言上,中華人民共和国が個人の被害賠償まで放棄したとは直ちには解し難いとし,1952年(昭和27年)の日華平和条約に関する検討を一切行っていないが,以下のとおり,我が国と国家としての中国との間の賠償並びに財産及び請求権の問題は日華平和条約によって法的に完全かつ最終的に解決している。
ア 日華平和条約の締結
中国は,連合国の一国として,サンフランシスコ講和会議に招待されるべきであったが,1949年の中華人民共和国政府の成立や1950年の朝鮮戦争の勃発など当時の政治的及び国際的状況のため,中華人民共和国政府及び中華民国政府のいずれも講和会議には招待されなかった。その結果,日本はいずれの政府と外交関係を結ぶかが問題となり,米国にとっても非常に大きな政治問題となった。昭和26年暮れに,米国政府の中で対日平和条約問題を担当するダレス特使が来日し,同特使が,吉田茂総理大臣に対して,わが国が中華民国政府と平和条約を締結するのでなければ,サンフランシスコ平和条約自体が米国議会の承認を得られないと説得したため,吉田総理もこれに応じ,いわゆる吉田書簡を発出し,日本は中華民国政府と平和条約を締結することを約束した。
このようにして,1952年,我が国は,中華民国政府をもって中国を代表する正統政府であると承認して,国家としての中国と日本との戦争状態の終結等の問題を解決するために日華平和条約を締結した。この条約は,その前文にあるとおり,「歴史的及び文化的のきずなと地理的の近さにかんがみ,善隣関係を相互に希望することを考慮し,その共通の福祉の増進並びに国際の平和及び安全の維持のための緊密な協力が重要である」との考えの下,両国間の戦争状態を終了させ,賠償並びに財産及び請求権の問題を解決したものである。
そして,日華平和条約11条は,「この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外,日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は,サン・フランシスコ条約の相当規定に従って解決するものとする。」と規定しており,ここにいうサンフランシスコ条約の相当規定には,サンフランシスコ平和条約14条(b)も含まれるので,戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた中国及びその国民の請求権は放棄されたこととなる。
イ 日中共同声明署名時の処理
このようにして締結された日華平和条約の後20年を経て,日本政府は1972年(昭和47年)に中華人民共和国政府との間で日中共同声明に署名した。その際,日華平和条約についての両国の立場の違いから戦争状態の終了や賠償並びに財産及び請求権が問題となったが,困難な交渉の結果,以下に述べるとおり,日中共同声明は,両国の立場それぞれと相容れるものとして作成されている。
すなわち,戦争状態の終了については,日華平和条約1条において,「日本国と中華民国との間の戦争状態は,この条約が効力を生ずる日に終了する。」と規定されているとおり,日中間の戦争状態は,日華平和条約により終了したというのが,我が国の一貫した立場である。
これは,戦争状態の終了は,一度限りの処分行為であり,法律的には,当時中国を代表する合法政府であった中華民国政府との間で,国と国との関係を律する事項として処理済みであるという考え方に基づくものである。これに対して,中華人民共和国は,日華平和条約は当初から無効であるとの立場であり,我が国の考え方とは基本的に異なるものであった。戦争状態の終結の問題は,このような日中双方の基本的立場に関連する困難な法的問題であったが,日中双方の交渉努力の結果,共同声明1項において,「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は,この共同声明が発出される日に終了する。」と規定されることとなった。「不正常な状態」とは,これまで我が国と中華人民共和国との間の国交がなかった状態を指すというのが我が国の理解であり,日中間の戦争状態は日華平和条約によって終結しているとの我が国の立場と何ら矛盾しない。このような表現によって,日中関係がいかなる意味においても正常化されたという点についての日中双方の認識の一致を図ったものである。
賠償並びに財産及び請求権の問題についても,戦争状態の終結と同様,このような一度限りの処分行為については,日華平和条約によって法的に処理済みであるというのが,我が国の立場であり,日華平和条約の有効性についての中華人民共和国政府との基本的立場の違いを解決する必要があった。この点についても,日中双方が交渉を重ねた結果,日中共同声明5項においては,「中華人民共和国政府は,中日両国国民の友好のために,日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」と規定された。日中両国政府は,お互いの立場の違いを十分理解した上で,実体としてこの問題の完全かつ最終的な解決を図るべく,このような規定ぶりにつき一致したものであり,その結果は日華平和条約による処理と同じであることを意図したものである。
このように,戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた中国及びその国民の請求権は,日華平和条約により,サンフランシスコ平和条約の相当規定に従って,放棄されている。そしてこのような請求権については,日本国及びその国民は,これに基づく請求に応じるべき法律上の義務は消滅しているので,救済が拒否され,裁判上の請求も容認される余地はない。
そして,新潟地裁事件において,被告国は,本件における被控訴人の主張と同様,中国は1つであり,また,仮に原告らに被告国に対する請求権が発生していたとしても,サンフランシスコ平和条約14条(b)を引用する日華平和条約11条により,我が国がこれに応じる法的義務は消滅し,裁判上の請求が認容される余地はない旨主張していたのである(日中共同声明5項によってかかる法律上の義務が消減したという主張ではない。)。
これに対し,新潟地裁判決が,中華人民共和国と中華民国とを別個に検討しなければならないとする点は,我が国と両国との関係に関する歴史的経緯や日中共同声明成立の経緯及びこれらに関する我が国政府の認識について完全に誤解したものであり,被告国の主張についての判断を脱漏したものといわざるを得ない。
したがって,新潟地裁判決の上記判断は失当である。
(3) 個人の損害賠償請求権を国家が放棄し得ること(上記1,③について)
ア 新潟地裁判決は,戦争による国民個人の被害についての損害賠償請求権という性質上,国家がこれを放棄し得るか否かにつき疑義が残ると判示する。
新潟地裁判決のいう「放棄」がいかなる意味であるかは必ずしも明確ではないが,要するに,国家の権利と国民の権利は別であり,国と国民は別の法主体であるから,国家は,所属国民の権利を法的に処理するという意味での「放棄」をすることができないとするものと解される。
しかしながら,かかる判断は,国際法の基本的な理解を欠くものである。
イ すなわち,条約は国家間の合意であり,我が国においては条約の締結に国会の承認を要し,憲法98条2項は条約の誠実遵守の必要性を規定している。こうしたことから,我が国における法律と条約との間の国内法的効力における優劣関係に関しては,条約が法律に優位すると解されている(樋口陽一ほか「注釈日本国憲法下巻」1500ページ,乙第103号証・櫻井充君質問主意書に対する平成14年12月6日政府答弁書)。
国家は,国内の立法手続により,国民の私法上の権利・義務の設定,変更,消滅を行うことが可能なのであるから,我が国国会の承認を得た条約によって国民の私法上の権利・義務の設定,変更,消滅を行うことが可能であることは当然である。
また,従来から,国家がその国民の他国又はその国民との間の財産及び請求権の問題を解決するために国際約束を締結することは国際法上可能であるとして,各国が実行を積み重ねてきたのであり(乙第104号証・平成14年12月20日付け衆議院議員近藤昭一君提出朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書),戦後の講和条約によって,個々の国民の相手国に対する請求権について,国家が法的に処理することは可能であって,新潟地裁判決は,かかる国際法の基本的枠組みを全く理解していないといわざるを得ない。
このような近代戦争における戦後処理の枠組みの在り方に関しては,オランダ国民が,先の大戦中に日本軍の行為によって被害を受けたとして,日本国に対し損害賠償を請求した事案について,東京高等裁判所平成13年10月11日判決(判例時報1769号61ページ)は,「現在のように民主的な国家同士の間でほとんど戦争が起こらなくなってくると,戦争をそれによって生じる被害の側面からのみ観察する傾向が生じる。」(該当箇所同号66ページ1段目),「法は,個人の利益主張のすべてをそのまま容認するのではない。社会の,そして個人の活動に関する社会的な共存関係の総和が法であり,その調整の結果である規制の限度でのみ,個人の利益主張を容認するのである。そして,国際社会では,法は,・・・政治的単位の利益主張の中にしか存在しないのである。そのため,国際社会で,個人の利益主張に関する法が定められている場合には,個人の利益主張のうちどれをどの範囲で容認するか,そして,それを実現する方法として,どのような機関の判定に委ね,その際の手続をどうするかも,すべて政治的単位である国家間の外交交渉と,その成果である合意(条約)によって定められる。」(該当箇所同号66ページ3段目),「個人の被害を救済するかどうか,救済するとして,どの程度の救済をするか,また,救済方法をどうするかについては,すべて,国際社会において,国家間の外交交渉によって,その利害の調整を経て決定されるべきものである。」(該当箇所同号69ページ1段目),「国家のみに損害賠償請求権を認めることによってこそ,賠償の問題を,被害者間に公平に,また,戦後世界の実情に即して適正に解決することができるというべきである。また,戦争による被害の解決というものは,戦争状態を終わらせて,戦争状態にあった国家及びその国民の間に平和的な関係を築くためにもされるのであるが,そのような公益を実現するためにも,国家が被害を一体としてとらえて,統一的に相手国に賠償を請求し,外交交渉を経て,合意に達することの方が,はるかにその目的に沿うのである。もし,被害者が,それぞれ個別に請求できるとすると,国家は,個別に委任を受けたものに限り,被害者を代理して相手国との交渉に望まねばならない。しかし,それでは,全ての被害者の被害について,一挙に解決することができない。そのために,戦争状態にあった国家及び国民の間で戦争状態を終わらせることが,極めて困難になるであろう。戦争状態の終結は,交戦当事者のみならず,多数の関係国とその国民にとっても必要なことである。それは戦後世界にとって,重要な公益であって,それが,一部の者の私益を優先することによって,害されてはならない。そうすると,被害者個人に加害国に対する直接の賠償請求権を認めることは,かえって問題を複雑にするというべきである。」と判示され(該当箇所同号70ページ4段目から71ページ1段目),同様の理解が示されている(なお,同判決に対しては,これを不服とする一審原告らから上告受理の申立てがされたが,最高裁平成16年3月30日第三小法廷決定(乙第105号証)は,上告不受理決定をした。)。
このように,我が国は,先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題について,個人の請求権も含めて,サンフランシスコ平和条約,二国間の平和条約及びその他の関連する条約等により終局的な解決を図ったのであり,これら条約等の一部の当事国の国民の請求権が解決済みでないと解することはできない。
もちろん,このような一連の解決のために我が国国民が払った代償も大きい。例えば,いわゆるシベリア抑留の問題に関する最高裁判所平成9年3月13日第一小法廷判決(民集51巻3号1233ページ)は,「我が国がポツダム宣言を受諾し,降伏文書に調印したことにより,上告人らを含む多くの軍人・軍属が,ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり,シベリア地域の収容所等に送られ,その後長期間にわたり,満足な食料も与えられず,劣悪な環境の中で抑留された上,過酷な強制労働を課され,その結果,多くの人命が失われ,あるいは身体に重い障害を残すなど,筆舌に尽くし難い辛苦を味わされ,肉体的,精神的,経済的に多大の損害を被った」としつつも,「日ソ共同宣言は,(中略)終戦処理の一環として,いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって,(中略)我が国が同宣言6項後段において請求権放棄を合意したことは,誠にやむを得ないところであったというべきである」とし,原告の請求を戦争犠牲ないし戦争損害として退けた。
また,我が国国民が中国大陸に有していた財産は接収されたが,これについても,昭和56年11月26日の衆議院内閣委員会恩給等に関する小委員会における池田政府委員(アジア局中国課長)の答弁(乙第106号証)に見られるとおり,「中国大陸におきます補償問題につきましては,サンフランシスコ平和条約第14条の規定がございます。この14条(a)の2の規定によりますと,各連合国はその管轄のもとにあるものを差し押さえ,留置し,清算することができるということを規定いたしておりまして,そういう意味におきまして,このサンフランシスコ平和条約の規定というものが非常に明確に,この中国大陸におきます日本人の財産の法的な問題についての規定を行っているわけでございます。・・・したがいまして,わが国といたしましては,中国がこの第14条の規定に従いまして日本国民の財産に関してすでにとった措置につきましては,異議を唱える立場にはないわけでございます。」とされている。
このように,戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた中国を含む連合国及びその国民の請求権が放棄され,平和条約が締結されたのは,わが国及びその国民が多大な代償を払った結果であり,戦後60年近く経って中国の国民に限ってその請求権は放棄されていないと解することは著しく不当といわざるを得ない。
前掲東京高裁判決が指摘するように,「連合国国民の個人としての請求権を含めて,一切の請求権が放棄されたのは,我が国が,敗戦により,海外の領土の没収だけでなく,連合国内のみならず,中国,台湾,朝鮮等にあった一般国民の在外資産まで接収され,さらに中立国にあった日本国民の財産までもが賠償の原資とされるといった過酷な負担の見返りであった」(該当箇所前同号73ページ2段目)のである。
ウ さらに,新潟地裁判決は,日中共同声明の署名にもかかわらず,中国国民は戦争被害について何らの補償,代償措置を受けていないともいうが,国家が自国民の相手国に対する個々の請求権を「放棄」したことにより生じる不利益をどのように処理するかは,当該条約に特別の規定がない限り,当該国家の国内法の問題であって,当該国家が何らかの国内法的な代替措置をとらないからといって,国家間の請求権処理の条約自体の効力に影響を与えることはない。条約を締結した後に,相手国が国内的にいかなる措置を採ったかによって条約の効力が左右されるなどという解釈は,当事国の信頼や条約の安定性を著しく害するものであって,到底承服できない。
したがって,新潟地裁判決の上記判断は失当である。
(4) 中国要人の発言について(上記1,④について)
新潟地裁判決は,特に銭外交部長の発言等からすれば,中国要人が,日中共同声明により中国が個人の被害賠償まで放棄したと認識しているとは必ずしもいえないから,日本政府の認識の如何にかかわらず,中国国民個人が被った損害についての被告国に対する損害賠償請求権,特に,安全配慮義務違反という債務不履行に基づく損害賠償請求権までが,日中共同声明によって放棄されたとは解し難いと判示する。
しかしながら,新潟地裁判決にいうところの銭外交部長(当時)の発言は,報道されたものにすぎず,中華人民共和国政府によって確認されたわけではなく,かかる一部の報道のみをとりあげて,同政府の公式な見解であるかのごとく判示することは誤りである。また,そもそも,以下の諸点が示すとおり,先の大戦にかかる日中間の賠償並びに財産及び請求権の問題について,中華人民共和国政府の見解も我が国政府と同様であることは明らかである。
すなわち,①1995年5月3日,陳健中国外交部新聞司長は,記者から「国交正常化以来,中国政府は日本に対する賠償請求を正式に放棄したが,最近民間組織が賠償請求を提起している。これに対する見解如何。」と問われたのに対し,「賠償問題は既に解決している。この問題におけるわれわれの立場には変化はない。」旨発言している。②また,銭外交部長自身,1992年3月の記者会見において,記者より民間賠償請求の動きについての考え方を問われたのに対し,戦争によってもたらされた幾つかの複雑な問題に対し,日本側は適切に処理を行うべきであると述べつつ,戦争賠償の問題については,中国政府は1972年の日中共同声明の中で明確に表明を行っており,かかる立場に変化はないと表明している(乙第70号証)。
以上によれば,先の大戦に係る日中間の請求権の問題についての日中間の認識は一致していることに疑念の余地はないと考えるべきである。なお,新潟地裁判決は,「特に,安全配慮義務違反という債務不履行に基づく損害賠償請求権までが,日中共同声明によって放棄されたとは解し難い。」と判示し,損害賠償請求権を不法行為(国家賠償を含む。以下同じ)に基づくものと債務不履行(安全配慮義務違反。以下同じ)に基づくものとに区別して,とりわけ後者については,放棄の対象とならないと解しているようである。
しかし,前記のとおり,請求権の放棄はサンフランシスコ平和条約14条(b)を引用する日華平和条約11条に基づくものであるところ,サンフランシスコ平和条約14条(b)による放棄の対象は,「戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権」とされており,これに該当するものであれば,不法行為に基づくものであれ,債務不履行に基づくものであれ,その法律構成のいかんを問わず放棄の対象となるのである。
したがって,上記安全配慮義務違反を根拠とする債務不履行損害賠償請求権についても,仮にこれがあるとしても,放棄されたものとなり,新潟地裁判決の上記判断は失当であることが明らかである。
以 上

|