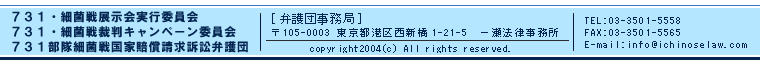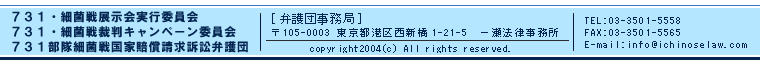�����P�S�N�i�l�j��S�W�P�T��
�T�i�l ���G�łق��P�V�X��
��T�i�l�@��
���@���@���@�ʁi�T�j
��P�@���Ɩ����ӂ̖@����ے肵���Ƃ���鉺���R�ٔ���ɂ���
�P�@�͂��߂�
�Q�@�������ٕ����P�Q�N�P�P�������ɂ���
�R�@���s�n�قP�������ɂ���
(�P)�@���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��锻��
(�Q)�@���Ɩ����ӂ̖@���͕ی삷�ׂ������݂̂ɓK�p�����Ƃ���_�ɂ���
(�R)�@�����̂��߂̌��͍�p�ɓ�����Ȃ��s�ׂɂ͖��@��̕s�@�s�אӔC������
����Ƃ���_�ɂ���
�S�@�������ٔ����ɂ���
(�P)�@�������ٔ����̍��Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��锻��
(�Q)�@�����@�{�s�O�ɂ����鍑�Ɩ����ӂ̖@���Ɩ��@���߂Ƃ̊W�ɂ���
(�R)�@���̌����͂̍s�g�Ɋւ����R�@����̕ϑJ�ɂ���
(�S)�@���Ɩ����ӂ̖@����ے肷��w���̑��݂ɂ���
(�T)�@���`�E�����̗��O�Ɋ�Â����Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�����ɂ���
��Q�@���Ɩ����ӂ̖@���͎���@��̍����������Ƃ���_�ɂ���
�P�@�s���ٔ��@�P�U�����u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�ƋK�肷�邱�Ƃɂ���
�Q�@�ٔ����\���@����̉ߒ��Ŏi�@�ٔ��������ƐӔC�Ɋւ���i�ׂ����閾���̋K�肪���Ă���폜���ꂽ���Ƃɂ���
�R�@�����@�R�V�R�𐧒�ɓ������ă{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�ƐӔC�K�肪 �폜���ꂽ���Ƃɂ���
�S�@���s���@�V�P�T���̐���o�߂ɂ���
��R�@���Ɩ����ӂ̖@���͖@�߂ɂ���Č������t�^���ꂽ�s�ׂ݂̂ɓK�p�����
�Ƃ���_�ɂ���
��S�@���Ɩ����ӂ̖@���͓��{���̓������̋y�Ȃ��O���l�ɂ͓K�p����Ȃ�
�Ƃ���_�ɂ���
��T�i�l�́A�{�������ʂɂ����āA���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��鉪�c���������̂Q�O�O�S�N(�����P�U�N)�V���P�R���t���Ӓ菑(�b��T�O�Q���A�ȉ��u���c�Ӓ菑�v�Ƃ����B)�ɂ�����ӌ��ɑ��A�K�v�ƔF�߂�͈͂Ŕ��_����B�Ȃ��A���ꓙ�́A���ɒf��Ȃ�����]�O�̗�ɂ��B
��P�@���Ɩ����ӂ̖@����ے肵���Ƃ���鉺���R�ٔ���ɂ���
�P�@�͂��߂�
���c�Ӓ菑�́A���Ɩ����ӂ̖@����ے肵���ߔN�̉����R�ٔ���Ƃ��āA���������ٔ��������P�Q�N�P�P���R�O������(�����P�V�S�P���S�O�y�[�W�A�ȉ��u�������ٕ����P�Q�N�P�P�������v�Ƃ����B)�A���s�n���ٔ��������P�T�N�P���P�T������(�����P�W�Q�Q���W�R�y�[�W�A�ȉ��u���s�n�قP�������v�Ƃ����B)�A�����n�قR�������A�������ٕ����P�T�N�V�������A�V���n�ٔ����y�ѕ��������ٔ��������P�U�N�T���Q�S������(�ȉ��u�������ٔ����v�Ƃ����B)��������(���c�Ӓ菑�S�y�[�W)�B
�������A�������ٕ����P�Q�N�P�P�������͍��Ɩ����ӂ̖@�������F���Ă��邩��A�����ے肵���ٔ���Ƃ��ē������������邱�Ƃ͌��ł���B�܂��A�����n�قR�������A�������ٕ����P�T�N�V�������y�ѐV���n�ٔ������A���Ɩ����ӂ̖@���ɑ��闝������������̂ł��邱�Ƃɂ��ẮA���ꂼ���T�i�l��������(�P)�S�S�y�[�W�ȉ��A��(�R)�Q�y�[�W�ȉ��y�ѓ�(�S)�Q�y�[�W�ȉ��ɂ����āA�ڍׂɎw�E�����Ƃ���ł���B�����āA���s�n�قP�������y�ѕ������ٔ������A���l�ɍ��Ɩ����ӂ̖@���ɑ��闝�������A���̌��ʂƂ��āA�����@�����U���Ɉᔽ����ƂƂ��ɁA�ō��ُ��a�Q�T�N�����Ƒ������锻�f�������B���������āA�����̉����R�ٔ��Ⴊ�A���Ɩ����ӂ̖@����ے肷�鍪���ƂȂ蓾�Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�ȉ��A�������ٕ����P�Q�N�P�P�������A���s�n�قP�������y�ѕ������ٔ����̍��Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��锻�����e�ɂ��ďq�ׁA�������ٕ����P�Q�N�P�P�������Ɋւ��鉪�c�Ӓ菑�̎w�E�̌��̂ق��A���s�n�قP�������y�ѕ������ٔ����̔������e�̌��𖾂炩�ɂ���B
�Q�@�������ٕ����P�Q�N�P�P�������ɂ���
���c�Ӓ菑�́A�������ٕ����P�Q�N�P�P���������A�u���Ɩ����ӂ̖@���͎���@��̍����������Ă��炸�A�����K�p�ł���@���ł͂Ȃ��v(���c�Ӓ菑�S�y�[�W)�Ɣ��������ٔ���ł���Ǝw�E����B
�������A�������ٕ����P�Q�N�P�P�������́A���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��A�u���a�Q�Q�N�Ɏ{�s���ꂽ���Ɣ����@�́A�����͂̍s�g���ɂ�鑹�Q�̔����Ɋւ��鍑���͒n�������c�̂̐ӔC���߂���̂ł���Ƃ���A���̕����U���́A���@�{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��Ă͂Ȃ��]�O�̗�ɂ��ƋK�肵�Ă��邩��A�E�@���̎{�s�O�̌����͂̍s�g���ɂ�鑹�Q�ɂ��ẮA���s���ٔ��@�P�U���̋K��(�u�s���ٔ��n���Q�v���m�i���Z�X�v)�ɂ��A�������̌����͂̍s�g�ɋN������s�@�s�ד��̔��������̑i���́A�s���ٔ��葱�ɂ�錠���ی�v�����������̂Ƃ��Ă�������e���ꂸ�A�����������͂̍s�g�������͍�p�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă͖��@�̕s�@�s�ׂ̓K�p�͂Ȃ����Ƃ��@���Ƃ��Ċm�����Ă���(�����鍑�Ɩ����ӂ̌���)�B�v�Ɣ������A���Ɩ����ӂ̖@�������F�������̂ł���A���c�Ӓ菑���f������e�ȂLj�ؔ������Ă��Ȃ��B
���������āA���c�Ӓ菑�̏�L�w�E�͖��炩�Ɍ��ł���B
�R�@���s�n�قP�������ɂ���
(�P)�@���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��锻��
���s�n�قP�������́A�����n�قR��������V���n�ٔ����Ɠ��l�A�����l�������Ƃ��邢���鋭���A�s�E�����J�������Ɋւ�����̂ł��邪�A���Ɩ����ӂ̖@���̓��e�ɂ��A�u�����Ŗ��Ƃ���鍑�Ƃ̍s�ׂ������̂��߂̌��͍�p�ł���ꍇ�ɁA���Y������ی삷�邽�߂̂��̂ł����āA���Y�s�ׂ������̂��߂̌��͍�p�ɂ�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̍s�ׂɂ��Ă����@��̕s�@�s�אӔC���������邱�ƂR�̂��ƂƂ��Ă�����̂ł���B���������āA���Ɩ����ӂ̖@�����K�p����鍑�Ƃ̌��͍s�ׂ����đ��݂������Ƃ��A��ʘ_�Ƃ��Ă͍m��ł���Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ�������U���ɑ��鋭���s�ׂ́A���Ɍ��������Ƃ���s�@�s�ׂł����āA�ی삷�ׂ����͍�p�ł͂Ȃ���������A�퍐���̎咣�́A���̑O������������ł���v�Ɣ�������B
(�Q)�@���Ɩ����ӂ̖@���͕ی삷�ׂ������݂̂ɓK�p�����Ƃ���_�ɂ���
���s�n�قP�������́A���Ɩ����ӂ̖@���͌�����ی삷����̂ł��邩��A���̓K�p�͈͂�ی삷�ׂ��������ۂ��ɂ���ĉ悵�A�����{�R�͂��̗D�z�I���͂Ɋ�Â��������͂�g�D�I�ɍs�g�������A�@�I�������Ȃ�����ی삷�ׂ����Ƃ̌��͓I��p�Ƃ͂������A���Ɩ����ӂ̖@�����K�p����Ȃ��|���f�������̂ł���B
�������A���Ɩ����ӂ̖@���́A���̔����ӔC��F�߂��K�肪���݂��Ȃ����̂ɍ��������`����Ȃ��Ƃ������̂ł���A���Ƃ���Ă��錠�͓I��p�ɖ@�I���������邩�ۂ��͑S�����ƂȂ�Ȃ��B
���������A�s�@�s��(��@�s��)�́A�@�ɂ�苖����Ȃ��s�ׂł���A�@�ɂ���ĕی삷�ׂ��s�ׂƂ͂������A�ʏ�́A�����y�ьY���ӔC����������̂ł���B�������A�������@���ł́A���̈�@�s�ׂ����Ƃ̌��͓I��p�ł������A���@�̕s�@�s�K��̓K�p��r�����A���ɍ��ɔ����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ��������Ƃ��獑�̔����ӔC���ے肳�ꂽ���̂ł���B
���������āA���s�n�قP���������A�ی삷�ׂ����͍�p�łȂ������Ƃ��āA���Ɩ����ӂ̖@����K�p�����A���@��K�p���ׂ��ł���Ɣ��f�����̂́A��L�̍��Ɩ����ӂ̖@����S���������Ă��Ȃ��؍��ł���B
���ɁA�������������s�ׂ��A�@�I�ɕی삳���ׂ��s�ׂł���A����͓K�@�s�ׂł����āA���Q����(���Ɣ���)�̖��͐������A�����⏞�̖�肪������ɂ����Ȃ���(�F�ꍎ��E���ƕ⏞�@�R�y�[�W�Q��)�A�s�@�s�ׂ�����ی삷��K�v���Ȃ��Ƃ��Ă��A���ꂪ���̌��͓I��p�ɂ��ꍇ�́A���@�̓K�p���r������A���͑��Q�����`����Ȃ��̂ł���B
���ǁA���������E���Ɋւ��čs�����s�@�s�ׂ����Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�ΏۂƂ����邩�ۂ��́A���̍s�ׂ̐��������͓I��p�ł��邩�ۂ��Ō�������̂ł����āA���̍s�ׂɖ@�I���������邩�ۂ��Ō���������̂ł͂Ȃ��̂ł���B
���̓_�ɂ��ẮA���ɍō��ُ��a�Q�T�N�������������Ă���Ƃ���ł���B���Ȃ킿�A�������́A�u�_�|�͌������͖{�i�������͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�̔��������߂���̂ł���Ƃ��Ȃ���A���̌��͂��@���Ȃ���@��̖@�K���͏����ɂ���Ċ�b�Â����Ă��邩�𖾂��ɂ��Ă��Ȃ��Ǝ咣����̂ł���B�E�E�E�����āA�㍐�l�͌��R�����٘_�ɂ����Ă����ΉE�j��s�ׂ���@�Ȍ����͂̍s�g�ł��邱�Ƃ��咣���Ă���̂ł����āA���R�����咣�Ɋ�{�i�������͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�̔��������߂���̂ł���Ƃ����͓̂��R�ł���B(�����E�j��s�ׂ������͂̍s�g�ł͂Ȃ����_�x�@���̎��l�Ƃ��Ă̍s�ׂł���Ȃ����ɂ��č��ɑ��Q�����𐿋������Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ����ꂾ���Ŗ{�i�����͗��R�Ȃ����̂ƂȂ�ł��炤)�����āA���R�����̔����������R�ɂ���āA�{�i���������p���邽�߂ɂ́A���_�̂悤�ɔ@���Ȃ�@�ߖ��͏����ɍ�����������������K�v���Ȃ��̂ŁA�������ɂ͉�����@�͂Ȃ��B�_�|�͖��������͖{�������͂̍s�g����@�ł��邩�ۂ������Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł��邪�A���Ƃ��{���Ɖ��̔j��@�ł����Ă��A���������ӔC���ׂ����̂łȂ����Ƃ͌�q�̂Ƃ���ł��邩��A���ɑ��đ��Q�̔��������߂�{�i�ɂ����ẮA���̕s�@�ł��邩�Ȃ���������K�v�͂Ȃ��̂ł����āA�_�|�͗��R�͂Ȃ��B�v(�����͈��p��)�Ɣ������Ă���B
�ȏ�ɏq�ׂ��悤�ɁA���s�n�قP�������́A���Ɩ����ӂ̖@���y�эō��ُ��a�Q�T�N�����𐳉����Ă��炸�A�����ł���B
�Ȃ��A���c�Ӓ菑�́A�ō��ُ��a�Q�T�N�������A�u�܂����������e�ł��邩�画��Ƃ͂����Ȃ��v(���c�Ӓ菑�S�O�y�[�W)�Ɣᔻ���邪�A����͉��獪���̂Ȃ��ᔻ�ł����Ċw�҂Ƃ��Ă̈ӌ�������̂ł͂Ȃ��B�ō��ٔ������a�Q�V�N�P���Q�T����@�쌈��(�W�����X�g�V���S�P�y�[�W)�́A�u���Ɣ����@�{�s�O�ɂ����ẮA�������̕s�@�s�ׂɂ��č��Ƃ������ӔC��Ȃ����Ƃ͓��ٔ����̔���Ƃ���Ƃ���ł���(���a�Q�S�N�i�I�j��Q�U�W�����a�Q�T�N�S���P�P����O���@�씻���Q��)�B�v�Ɣ������A�ō��ُ��a�Q�T�N�����y�ѓ������Ɏ�����Ă��鍑�Ɩ����ӂ̖@���ɂ��Ĕ���Ƃ��Ă̈ʒu�Â���^���Ă���Ƃ���ł���B
(�R)�@�����̂��߂̌��͍�p�ɓ�����Ȃ��s�ׂɂ͖��@��̕s�@�s�אӔC����������Ƃ���_�ɂ���
�܂��A���s�n�قP�������́A�u���Y�s�ׂ������̂��߂̌��͍�p�ɂ�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̍s�ׂɂ��Ă����@��̕s�@�s�אӔC���������邱�ƂR�̂��ƂƂ��Ă���v�Ɣ�������B
�������A���������s�����s�ׂ������̂��߂̌��͓I��p�ɓ�����Ȃ��Ȃ�A���͂⍑�̍s�ׂƂ͂����Ȃ��̂ł����āA�������l�̍s�ׂƂ��āA���Y���������l�ӔC��H���Α���邱�ƂƂȂ�B���̓_�ɂ��āA�ō��ُ��a�Q�T�N�������A�u�Ⴕ����Ɍx�@���������͂̍s�g�ɖ�������A�E���𗔗p���Ė{���Ɖ���j�����̂ł���Ƃ���A���ꓙ�x�@�������@��̕s�@�s�ׂ̐ӔC�����Ƃ͂��邩���m��Ȃ����A���̏ꍇ�E�̍s�ׂ͂��͂⍑�̍s�ׂƌ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����āA���X���������ӔC�����R�͂Ȃ��̂ł���B�v�Ɣ������Ă���Ƃ���ł���B
�����{���ɑ����Ă����ƁA���ɋ����{�R�l�炪�A����@�I�������Ȃ��A�T�i�l��̎咣����悤�ȍs�ׂ������ꍇ�ɂ́A�����������͂̍s�g�ɖ�����čs�����E������E����s�ׂł����āA���͂⊯���Ƃ��Ă̍s�ׂƂ݂邱�Ƃ͂ł����A���̍s�ׂƂ͂����Ȃ�����A�����������Ƃɑ��鑹�Q�����̖��͐������A�܂��A���ɖ@���E���߂����s����ɓ������čs��ꂽ�Ƃ��������̍s�ׂ̊O�`���獑�̍s�ׂƂ݂�ׂ��ł���Ƃ���A���̍s�ׂ͌��͓I��p�ł��邩��A���@�̕s�@�s�K��̓K�p�͂Ȃ��A���͔����ӔC��Ȃ��̂ł���(�������ٕ����P�S�N�R���Q�W�������E�ז�����S�X���P�Q���R�O�S�P�y�[�W�Q��)�B
���s�n�قP�������́A�������{�I�ȗ��������������Ă���Ƃ��킴��Ȃ��B
�S�@�������ٔ����ɂ���
(�P)�@�������ٔ����̍��Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��锻��
�������ٔ����́A���������ł���T�i�l�炪�A����E��풆�A��������������{�����ɋ����A�s����A��T�i�l��Ђ��o�c����Y�B�ŋ����J���ɏ]��������ꂽ�Ƃ��āA��T�i�l���y�є�T�i�l��Ђɑ��A���Q�����𐿋��������Ăɂ��A�T�i�l�炪�A�u���Ɩ����ӂ̖@���͔���̏��Y�ɂ������A�ٔ����̔��f����ʓI�ɍS��������̂ł͂Ȃ��B�v�A�u�{���ɂ����ẮA���ɁA��T�i�l�����Ȃ����s�@�s�ׂ����Ɩ����ӂ̖@���̗v�������Ƃ��Ă��A���`�E�����̌�������A��T�i�l�������@���̓K�p���咣���邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�v�ȂǂƎ咣�����̂ɑ��A���̂Ƃ��蔻������(�������P�P�W�Ȃ����P�Q�S�y�[�W)�B
�@�@�u�����@��(���m�ɂ͍����@�{�s�O�B�ȉ������B)�ɂ����āA�����̎���ɂ����āA��R�@����́A���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K��͌������̌��͓I��p�ɂ͓K�p���Ȃ��Ƃ̉��߂��Ƃ�A���Ƃ̌��͓I��p�Ɋ�Â��A�l�ɑ��Q�������Ă��A���ɕs�@�s�אӔC��F�߂Ă��Ȃ��������Ƃ͔�T�i�l���̎咣����Ƃ���ł��v��A�u�����@�̗��@�ߒ��ɂ����鏔�c�_�y�і��@�V�P�T���̗��@�ߒ��ɂ����鏔�c�_�������āA���ʖ@��݂��ĐӔC��F�߂Ȃ������ȏ�A���ƂɐӔC��F�߂�]�n�͂Ȃ��Ƃ����T�i�l���̎咣�ɂ͌X�����ׂ����̂�����B�v
�A�@�������A�u���@�V�P�T�����������̌��͓I��p�Ɋ�Â��s�@�s�אӔC�̔�������]�n����r�˂��Ă��炸�A�s���ٔ��@�P�U���͂Ƃ������A���̖@�Ƃ��Ă̓��ʖ@�����肳��Ă��Ȃ��ȏ�A�������̌��͓I��p�Ɋ�Â��s�@�s�ׂɂ��Ė��@�V�P�T����K�p���邩�ۂ��̉��߂́A�����@�{�s�O�ɂ����Ă��A����ɂ䂾�˂�ꂽ���̂Ɖ�������Ȃ��B�v�A�u��R�@�̔��Ⴊ�A�����͌��͓I��p�Ɣ͓I��p���킸�A���o�ύ�p���������ׂĂ̌������̍s�ׂɐӔC��F�߂Ă��Ȃ������̂ɁA�吳�T�N�̗V���~�_���������ȗ��A�͓I��p�ɂ��Ă͖��@�̓K�p��F�߁A�s�@�s�אӔC���m�肷��悤�ɕϑJ���Ă������Ƃ��A���̂悤�ɉ����ď��߂č����I�ɐ���������B�v�A�u��O�̗L�͂Ȋw�����A���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��A��v���Ďx�����Ă����킯�ł��Ȃ���A�٘_���Ȃ������킯�ł��Ȃ��B�v
�B�@�u�ȏ�ɂ��A�����@���ɂ����鎖��ł����Ă��A���ׂĂ̌��͓I��p�Ɋ�Â��s�ׂɂ��Ė��@���K�p����Ȃ��Ƃ���@�����������Ƃ����̂͑����łȂ��A��O�̔���@����O��Ƃ��Ă��A���i�̎������ꍇ�ɂ́A���͕s�@�s�אӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɖ��߂���]�n�͎c����Ă����Ɖ�����̂������ł���B�v
�C�u�{�������A�s�E�����J���́A�������̌��͓I��p�Ɋ�Â��s�ׂł͂��邪�A���`�E�����̗��O�ɒ����������A�s�ד����̖@�߂ƌ����ɏƂ炵�Ă�������Ȃ���@�s�ׂł���B���Ɩ����ӂ̖@����K�p���ĐӔC���Ȃ��Ƃ����͕̂s���ł���A���@�ɂ��s�@�s�אӔC���F�߂���ׂ����̂ł���B�v�������ٔ����́A��L�̂悤�ɔ������āA�����@�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă����@�V�O�X���A�V�P�T���̓K�p�̉\����F�߁A�����Ɋ�Â����Q�����ӔC�̐�����F�߂��B���̏�ŁA�������́A�����鑹�Q�����������́A���@�V�Q�S����i�̏��ˊ��Ԃ̋K��̓K�p�ɂ���āA�x���Ƃ������P�Q�N�T���P�O���O�ɏ��ł����Ɣ��������B
�������A�������ٔ����́A�����n�قR�������Ɠ��l�ɁA�����Q�R�N�ɍ��Ɩ����ӂ̖@�����̗p���ꂽ�����y�эs���ٔ��@�P�U���A�����@���̗��@�o�܂ɂ��Ă̗��������A���Ɩ����ӂ̖@�����P�Ȃ锻��@���ł͂Ȃ��A�����̊�{�I�@����Ƃ��č̗p���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ𐳉����Ă��炸�A�����ł���B�܂��A�������ٔ����́A�V���n�ٔ����Ɠ��l�A���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��āA�u���`�E�����̊ϓ_�v�Ƃ������ۓI�T�O�������Ă��̓K�p�𐧌��������A����͖@���߂̖��ɒl������̂ł͂Ȃ��B�ȉ��A�ڏq����B
(�Q)�@�����@�{�s�O�ɂ����鍑�Ɩ����ӂ̖@���Ɩ��@���߂Ƃ̊W�ɂ���
�������ٔ����́A�u�������̌��͓I��p�Ɋ�Â��s�@�s�ׂɂ��Ė��@�V�P�T����K�p���邩�ۂ��̉��߂́A�����@�{�s�O�ɂ����Ă��A����ɂ䂾�˂�ꂽ���̂Ɖ�������Ȃ��B�v�|��������B
�������A��T�i�l���]�O����J��Ԃ��q�ׂ�Ƃ���A�����@�{�s�O�ɂ����āA���Ɩ����ӂ̖@���́A�s���ٔ��@�Ƌ����@�����z���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ŁA���̌��͓I��p�ɂ��č��������ӔC���|�̖@�K�͐��肹���A�܂��A���@�̕s�@�s�ׂ̋K��͂���ɓK�p���Ȃ��Ƃ����@���̗p���ꂽ�̂ł���A�����@�{�s�O�ɂ����āA���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��đ��Q�������ے肳�ꂽ�̂́A������@����Ɋ�Â����ɑ��Q������F�߂鍪���K���u���Ȃ����ƂƂ������߂ł��邩��A���@�̉��ߖ�肪������]�n�͂Ȃ��B���̓_�Ɋւ��ẮA��T�i�l��������(�P)�S�X�y�[�W�ȉ��ŏq�ׂ������n�قR�������ɑ���ᔻ�����̂܂ܑÓ�����̂ŁA��������p����B
(�R)�@���̌����͂̍s�g�Ɋւ����R�@����̕ϑJ�ɂ���
�������ٔ����́A���Ɩ����ӂ̖@��������@���ɂ����Ȃ����Ƃ̍����Ƃ��āA�u��R�@�̔��Ⴊ�A�����͌��͓I��p�Ɣ͓I��p���킸�A���o�ύ�p���������ׂĂ̌������̍s�ׂɐӔC��F�߂Ă��Ȃ������̂ɁA�吳�T�N�̗V���~�_���������ȗ��A�͓I��p�ɂ��Ă͖��@�̓K�p��F�߁A�s�@�s�אӔC���m�肷��悤�ɕϑJ���Ă������Ƃ��A���̂悤�ɉ����ď��߂č����I�ɐ���������B�v�Ɣ�������B
�������Ȃ���A��L�����͎����ł���B
��R�@�̔���́A���@�҂��A���m�ɍ��̐ӔC��ے肵�Ă������͓I��p�ɂ��ẮA��т��āA�@���ɓ��ʂ̋K�肪�Ȃ����薯�@�̕s�@�s�ז@�̓K�p���Ȃ�(���@�͑Γ��Ȏ��l�Ԃ̖@���W�Ɋւ���@�ł���A���Ǝ��l�Ƃ̌��͓I�W�ɖ{���K�p�������̂ł͂Ȃ�)���̂Ƃ��āA���̔����ӔC��ے肵�Ă���B
���@�҈ӎv���K���������m�łȂ������͓I��p�ɂ��Ă��A�Â��́A�����Ȏ��o�ύ�p(���������p�i�̍w���E���������̒��ؓ�)�ȊO�ɂ��Ă͍��̔����ӔC��ے肵�Ă����B�Ƃ��낪�A�吳�T�N�U���P���̂����铿���s�����w�Z�V���~�؎����̑�R�@�����́A�����w�Z�̎{�݂̉��r�ɂ�鑹�Q�ɂ��āA���w�Z�̊Ǘ��͍s���̔����ł��邪�A���̊Ǘ����ɕ�܂��鏬�w�Z�Z�ɂ̎{�݂ɑ����L���͌��@��̌��͊W�ɑ�������̂ł͂Ȃ��A�u�S�N���l�J��L�X���g���l�m�n�ʃj���e����L���׃��m�v�Ɣ������āA���@�V�P�V���̓K�p��F�߂č��̐ӔC��F�߂��B
�������A���̔����ɂ��ẮA�u���͍�p�������ӁA���o�ύ�p�����@��̐ӔC�Ƃ�����{�I�g�g�݂�ύX�����킯�ł͂Ȃ��A���o�ύ�p�̊O�����g�債���ɂƂǂ܂�B�v�Ƃ���Ă���(�F�ꍎ��E���ƐӔC�@�̕��͂S�P�W�y�[�W)�A���ǁA��R�@�́A���@�҈ӎv�����m�ɖ����ӂƂ��Ă��Ȃ��������̌��͓I��p�ȊO�ɂ��č��̐ӔC��F�߂��ɉ߂����A���̌��͓I��p�Ɋւ��ẮA���Ɩ����ӂ̖@�����O��Ƃ���Ă����̂ł���B
(�S)�@���Ɩ����ӂ̖@����ے肷��w���̑��݂ɂ���
�������ٔ����́A���Ɩ����ӂ̖@��������@���ɂ����Ȃ����Ƃ̍����Ƃ��āA�u��O�̗L�͂Ȋw�����A���Ɩ����ӂ̖@���ɂ��A��v���Ďx�����Ă����킯�ł��Ȃ���A�٘_���Ȃ������킯�ł��Ȃ��B�v�|��������B
�������A��L�����̕\���U�肩������炩�ȂƂ���A���͓I�s�ׂɂ��Ė��@�̓K�p�Ȃ����ސ��K�p��F�߂錩���͏������ł���A�������A���{�����@���̔���ɂ����Ă��A�����錩���͖��m�ɔے肳��Ă���B
���Ȃ킿�A�ō��ُ��a�Q�T�N�����́A���Ɣ����@�{�s�O�ɐ������x�@���̖h��@�Ɋ�Â��Ɖ��j��̕s�@�𗝗R�ɒ�N�������Ɣ������������Ɋւ��A�㍐���R���L�ڂ́u�]�O�̔���w�����{���̔@���ꍇ�ɏ㍐�l�ɐ������Ȃ��Ƃ�����̂������������͎����ł��邪�A�����Ȃ������������Ƃ���w�����������B�ʐ��K�������^�Ȃ炸�B�v�Ƃ���㍐�l�̎咣�ɑ��A�u�{���Ɖ��̔j��s�ׂ��A���̎��l�Ɠ��l�̊W�ɗ��o�ϓI�����̐�����тт���̂łȂ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����Č����͂̍s�g�Ɋւ��Ă͓��R�ɂ͖��@�̓K�p�̂Ȃ����ƌ������̐�������Ƃ���ł����āA�����@���ɂ����ẮA��ʓI�ɍ��̔����ӔC��F�߂��@���͂Ȃ������̂ł��邩��A�{���j��s�ׂɂ��č��������ӔC�����R�͂Ȃ��B�v�A�u�]�O�Ƃ����ǂ��������̕s�@�s�ׂɑ��A���������ӔC���ׂ����̂ł����āA�V���@�͂����@���������ɉ߂��Ȃ��Ǝ咣����̂ł��邪�A���Ɣ����@�{�s�ȑO�ɂ����ẮA��ʓI�ɍ��ɔ����ӔC��F�߂�@�ߏ�̍����̂Ȃ��������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł����āA��R�@���������̈�@�Ȍ����͂̍s�g�Ɋւ��āA��ɍ��ɔ����ӔC�̂Ȃ����Ƃ����ė����̂ł���B�v�Ƃ�����ŁA�u�������ɘ_�|�̂悤�Ȋw�����������Ƃ��Ă��A�����ɂ͂��̂悤�Ȋw���͍s���Ȃ������̂ł���B�v�Ɣ������Ă���B
���������āA���Ɩ����ӂ̖@����ے肷��w���̑��݂������ɍ��Ɩ����ӂ̖@����@���ɂ����Ȃ��Ƃ��镟�����ٔ����̏�L�����́A�����ł���B
(�T)�@���`�E�����̗��O�Ɋ�Â����Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�����ɂ���
�������ٔ����́A�u�{�������A�s�E�����J���́A�������̌��͓I��p�Ɋ�Â��s�ׂł͂��邪�A���`�E�����̗��O�ɒ����������A�s�ד����̖@�߂ƌ����ɏƂ炵�Ă�������Ȃ���@�s�ׂł���B���Ɩ����ӂ̖@����K�p���ĐӔC���Ȃ��Ƃ����͕̂s���ł���A���@�ɂ��s�@�s�אӔC���F�߂���ׂ����̂ł���B�v�Ɣ��������B
�������A�O�L�̂Ƃ���A���Ɩ����ӂ̖@���́A���̌����͂̍s�g�ɂ��Ă͖��@�̓K�p���Ȃ��A���̑����̔����ӔC��F�߂��@�����Ȃ��������Ƃɂ����̂ł��邩��A���̖@���̓K�p�𐧌���������Ƃ����āA���̔����ӔC��F�߂�@�����o������킯�ł͂Ȃ��B���̓_�Ɋւ��ẮA��T�i�l�̕����P�U�N�V���Q�O���t����������(�S)�Q�y�[�W�ȉ��ŏq�ׂ��V���n�ٔ����ɑ���ᔻ�����̂܂ܑÓ�����̂ŁA��������p����B
��Q�@���Ɩ����ӂ̖@���͎���@��̍����������Ƃ���_�ɂ���
�P�@�s���ٔ��@�P�U�����u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�ƋK�肷�邱�Ƃɂ���
(�P)�@���c�Ӓ菑�́A�s���ٔ��@�P�U���ɂ��āA�u���Ă̌����i�K�Łu�@���j���m�����A���v��Ƃ��āu�X�֓d�M�S�����j�փX�����m�v���A�u�@���j�������{�j�����m�`�������t�ҁv�̗�Ƃ��āu��@�m�ߕߎ�n���Y����փX�����m�v���������Ă��邱�Ƃ��l����A�����̍��Ɣ����̖��Ƃ͂��Ȃ�قȂ��肪�_�����Ă��邱�Ƃ������ł���B�v(���c�Ӓ菑�W�A�X�؈�W)�ȂǂƂ��A�u�s���ٔ��@�P�U���ɂ����u���Q�v���m�i�ׁv�Ƃ͎�Ƃ��đ����⏞�ɂ������⏞�����i�ׂł���B�v(���P�O�y�[�W)�Ƃ���B���̎�|�͕K���������炩�łȂ����A�s���ٔ��@�P�U���͍��Ɩ����ӂ̖@���Ƃ͖��W�ł��邩��A���@���̍����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����̂Ǝv����B
(�Q)�@�������A��T�i�l��������(�P)�Q�y�[�W�ȉ��ŏq�ׂ��Ƃ���A�s���ٔ��@�P�U���́A���Ɩ����ӂ̖@���R�̑O��Ƃ��āA�s���ٔ����̑��Q�������������ɌW�鎖���NJ��͈̔͂��߂����̂ł���B
�s���ٔ��@�Ă̍쐬�ɓ�����A�挈�I�ɉ������ׂ����Ƃ��āA�����Ȃ��肪��������A���������ꂽ���ɂ��ẮA�ɓ��������Ҏ[�����u����萌W�����v�����́u�s���ٔ����ݒu�m���v�Ƒ肷�鎑��(����Q�U����)�ɂ�������邱�Ƃ��ł��邪�A����ɂ��A�s���ٔ��@�̐���ߒ��ɂ����āA���{�̎匠�Ɋ�Â����u���Ȃ킿�����͂̍s�g�ɊY������[�u�ɂ���Đ��������Q�ɂ��ẮA���@�w�㓖����ʂɐ��F����Ă������Ɩ����ӂ̖@���ɂ��A�l�́A�����Ƃ��čs���ٔ����ɑ��đ��Q�����̑i�����N�ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���B
�܂��A�s���ٔ��@�Ă̌��Ă��쐬�������b�Z�́A���̕s�@�s�אӔC��ے肵�A�i�@�ٔ����݂̂Ȃ炸�A�s���ٔ����ɂ����Ă��A���̕s�@�s�אӔC��₢���Ȃ��Ƃ��Ă����B���Ȃ킿�A���b�Z�́A�u���m���@�㑹�Q�����`���j�փX���ӌ��v�Ƒ肷�铚�c�ɂ����āA����������̊������s���ꍇ�ɂ́A���͖��@�ɏ]���ĐӔC���A�����ٔ����ɑ��Q���������i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���Ƃ���(�X�ցA�d�M�A�S�����Ɋւ��A���ʂ̐ӔC�K�肪����A����͖��@�ɗD�悵�ēK�p�����)���A���������������s����ɍۂ��A�`���ᔽ�̏��u�Ⴕ���͑Ӗ��ɂ���O�҂ɉ��������Q�ɑ����Y��ӔC��Ȃ��Əq�ׂĂ���B���������āA���b�Z�́A���o�ώ�̂Ƃ��Ă̍��Ƃƌ����͎�̂Ƃ��Ă̍��ƂƂ���ʂ��A�O�҂ɂ��Ă͎��l�Ɠ��l�̐ӔC�����A��҂ɂ��Ă͖����ӂƂ������߂��̂��Ă����̂ł���(�F��E�O�f���ƐӔC�@�̕��͂S�O�X�A�S�P�X�A�S�Q�O�y�[�W�A�u���b�Z�����m���@�㑹�Q�����`���j萃X���ӌ��v�E����R�P���S�V�S�Ȃ����S�V�V�y�[�W)�B
�ȏ�̂��Ƃ��炷��A�s���ٔ��@�P�U���ɂ����u���Q�v���m�i�ׁv�́A�����鑹���⏞�ł͂Ȃ����Ɣ����̑i�����w�����̂ŁA�������A���Ɩ����ӂ̖@���R�̑O��Ƃ��āA�s���ٔ����͂�����i�����ł��Ȃ��|���K�肵�����̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
(�R)�@����ɑ��A���c�Ӓ菑�́A���b�Z���s���ٔ��@�P�U���ɂ����u���Q�v���m�i�ׁv�̗�Ƃ��āu�X�֓d�M�S�����j�փX�����m�v��u��@�m�ߕߎ�n���Y���j�փX�����m�v�������Ă���Ƃ��A����������ɁA�u�����̍��Ɣ����̖��Ƃ͂��Ȃ�قȂ��肪�_�����Ă��邱�Ƃ������ł���B�v(���c�Ӓ菑�X�y�[�W)�Ƃ��邪�A���炩�Ɍ��ł���B
���b�Z�������������́A�u(��)���n���@��m����ਃX�ꍇ�j�����@�l���@萃m�|�u�j�t�����X���ӔC���K��X�����@�㌴���j�˃e���Ӄj�C�X�@���ӔC�m���R�n���@�j�R�e���X�����m�i���n�����ٔ����m�����j���X�@�O�L�m�����n���ʃm�@��(�X�֓d�M�S�����j�փX�����m)���ȃe�����m�K�胒�݃P�T���g�L�j���������A���g�X�v�A�u(��)���n���������������s�X���j�ۃV�`���w���m�|�u��N�n�Ӗ��j�˃���O�҃j���w�^�����Q�j���V���Y���㑴�Ӄj�C�Z�X�A���ʃm�@����K��(��@�m�ߕߎ�n�|�Y���j�փX�����m)���ȃe�V�����F�V�^���ꍇ�n�@�����j�݃��X�v(�u���b�Z�����m���@�㑹�Q�����`���j萃X���ӌ��v�E����R�P���S�V�V�y�[�W)�Ƃ������̂ł���B���̂悤�ɁA���b�Z�́A���o�ώ�̂Ƃ��Ă̍��Ƃ̊����ƌ����͎�̂Ƃ��Ă̍��Ƃ̊�������ʂ�����ŁA�O�҂̗�Ƃ��āu�X�֓d�M�S�����j�փX�����m�v���A��҂̗�Ƃ��āu��@�m�ߕߎ�n�|�Y���j�փX�����m�v�������Ă���̂ł���B
�����āA���b�Z�������͎�̂Ƃ��Ă̍��Ƃ̊����ɂ�邽�ߖ����ӂƂ�����̂́A���Ƃ́u�������������s�X���j�ۃV�`���w���m�|�u��N�n�Ӗ��j�˃���O�҃j���w�^�����Q�v�ł���A����́A�u��@�m�ߕߎ�n�|�Y���j�փX�����m�v���Ꭶ����Ă��邱�Ƃ��疾�炩�ȂƂ���A�����鑹���⏞�ł͂Ȃ��A���ɍ����ł������Ɣ����̖��ł���B
(�S)�@�ȏ�̂Ƃ���A�s���ٔ��@�P�U���ɂ����u���Q�v���m�i�ׁv�������⏞���w���|�̉��c�ӌ����̌����͍����̂Ȃ��Ǝ��̉��߂Ƃ��킴����A��������߂Ɋ�Â��A�����͍��Ɩ����ӂ̖@���̍����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��鉪�c�ӌ����̈ӌ��́A�����Ƃ����ق��Ȃ��B
�Q�@�ٔ����\���@����̉ߒ��Ŏi�@�ٔ��������ƐӔC�Ɋւ���i�ׂ����閾���̋K�肪���Ă���폜���ꂽ���Ƃɂ���
(�P)�@�ٔ����\���@�́A�����Q�O�N�T���Ƀ��h���t�����S�ƂȂ��đ��Ă��N�����A�@���撲�ψ���Ō����C�����āA�����Q�R�N�ɖ@���Ƃ��ꂽ���̂ŁA�@���撲�ψ����(�鍑�i�@�ٔ����\���@����)�̂R�R���ŁA�u�n���ٔ����n�����i�׃j���e���m�����j�t�ٔ������L�X�v�Ƃ��āA�u���@���R�g�V�e(�C)���z��N�n���z�j�S���X���{(�������{�g���z���m�����g����n�X)�����׃V���n�V�j�V�e�׃X���e�m�����@(��)���z��N�n���z�j�S�n���X�����j�V�e�׃X���e�m�����A�������������������^�����j�����@(�n)������ٔ�����N�n���ʍٔ����j�ꑮ�X�����m�����L���e�m�����v�Ƃ���Ă�����(���R�l��E�l���ƍs���~�ϖ@�U�W�y�[�W)�A���B���ӌ���(�ٔ��\���@�Ĉӌ��E���B���j���ё��U�P�S�y�[�W�E����Q�X����)���o���A��L�̂����A���ƐӔC�Ɋւ���i�ׂ����閾���̋K�肪���Ă���폜����邱�ƂƂȂ���(�c������ҁE�̌n���@���T�R�U�T�y�[�W�ȉ�)�B
���̂��ƂɊւ��A���c�Ӓ菑�́A�u�ٔ����\���@����̉ߒ��ō��ɑ��閯���ٔ��̕�I�NJ��K�肪�폜���ꂽ���Ƃ́A���Ɩ����ӂ̖@��������@��Ŋm�����ꂽ�Ƃ������Ƃ̍����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�v(���c�Ӓ菑�P�S�؈�W)�Ƃ���B
(�Q)�@�������A��T�i�l��������(�P)�S�y�[�W�ȉ��ŏq�ׂ��Ƃ���A���B�́A���Ɩ����ӂ̖@���������ɁA���Ɣ��������i�ׂ��i�@�ٔ����ɒ�N�ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���A���̈��B�̈ӌ����q�ϓI�ɒʂ����`�ōٔ����\���@�����肳�ꂽ�̂ł���(���R�l��E�l���ƍs���~�ϖ@�U�W�Ȃ����U�X�y�[�W�B���|�������ٕ����P�S�N�R���Q�W�������E����R�O����)�B
���������āA�ٔ����\���@����̉ߒ��ŁA�i�@�ٔ��������ƐӔC�Ɋւ���i�ׂ�����|�̖����̋K�肪���Ă���폜���ꂽ���Ƃ́A���Ɩ����ӂ̖@������{�I�@����Ƃ��č̗p���ꂽ���Ƃ̏؍��Ƃ����ׂ��ł���B
(�R)�@����ɑ��A���c�Ӓ菑�́A�u�s���ٔ��@�P�U���ɂ����u���Q�v���m�i�ׂƂ͎�Ƃ��đ����⏞�ɂ������⏞�����i�ׂł���B���B�̌����ɂ��A�����⏞�̐����i�ׂ͍s���ٔ����ŏ��������ׂ��ł����āA����@�ŔF�߂��Ă��Ȃ�����i�@�ٔ����̊NJ��O�Ƃ����ׂ����̂ł������B(����)����Ƃ̑Ή��W�ŁA�i�@�������ɑ���i�ׂ̂��ׂĂ��NJ����邱�Ƃɔ������̂ł���B�v(���c�Ӓ菑�P�R�y�[�W)�Ƃ���B
�������A�O�L�P�ŏq�ׂ��Ƃ���A�s���ٔ��@�P�U���ɂ����u���Q�v���m�i�ׁv�́A�����鑹���⏞�ł͂Ȃ����Ɣ����̑i�����w���̂ł����āA���ꂪ�����⏞�̑i�����w���|�̉��c�ӌ����̌����́A�����̂Ȃ��Ǝ��̉��߂Ƃ��킴��Ȃ��B���̓_�ŁA���c�Ӓ菑�̏�L�ӌ��́A�O��Ɍ�肪����Ƃ��킴����A�����ł���B
�܂��A���B����L�ӌ����Ŏ������ӌ��́A�u���@���j���X���i�׃m���@�u���N�X�g�������ܕщ]�n�N���X���i�׃n�����g嫃��V�����i�X�R�g�\�n�X�W�V���m�@�@���������ٔ��X���m�@�܃i�P���n�i���g�̓�p���e�N��y�q���{�X���m�i�׃n�B�X����j�R���e�����m�������^����n���e�ٔ�����N���R�g�����@�����甪�S�O�\��N�\�l���m�t�߉]�n�N�N��m���i�j���e�b���g�m�ԃj�ٌ����v�X���m�ܗ��m�������X���m���i�N���V�����ٌ��X���m�܌��A���ٔ����n�S���j�ꃂ���X���R�g�i�V�g�@���{�j���X���i�׃n�Ո�j���e���܃g���ʃV�^�����Y��m�i�����V�^���m�~�j�V�e�d���j���j���X���i�׃g�V�e�V�������V�^���u�m�v���A���R�g�i�V���{�ăj���j���X���i�׃��ȃe�ٔ����m�ܓ��jV�^���n���m�c�����U���m�~�i���Y���������O���l�m�ږ{���{�j���X���i�׃mਃj�n��ਃX�҃i���v�A�u��O�@�����m�����j���V�e�n�v���X���R�g�����X���g�i���n���m�����n���܃m�ꕔ�j�V�e���܃n���@��m�ӔC�i�L�҃i���n�i�������j���X���m�v���n���m�����m�����g�V�e�i�t���҃j�����w�V��O�\��(�n)�m�ꍇ�n���@�m�呥�j�w�N���v(���p�Ғ��E��L��O�\�Ƃ́A�鍑�i�@�ٔ����\���@���ĂR�R���ɑ�������B)�Ƃ������̂ł���B
�����̋L�q�A��ɁA�u��O�����m�����j���V�e�n�v���X���R�g�����X���g�i���n���m�����n���܃m�ꕔ�j�V�e���܃n���@��m�ӔC�i�L�҃i���n�i���v�Ƃ̋L�q�ɂ��݂�A���B���A���Ɩ����ӂ̖@���������ɁA���Ɣ����̑i�����i�@�ٔ����ɒ�N�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ͖��炩�ł���B���������āA���B�������⏞�̑i���݂̂�O���ɒu���A������i�@�ٔ��������邱�Ƃɔ������ɂ����Ȃ��|�̉��c�Ӓ菑�̌����́A���Ƃ��킴��Ȃ��B
(�S)�@�ȏ�̂Ƃ���A�ٔ����\���@����̉ߒ��ŁA���ƐӔC�Ɋւ���i�ׂ�����|�̖����̋K�肪���Ă���폜���ꂽ���Ƃ́A���Ɩ����ӂ̖@������{�I�@����Ƃ��č̗p���ꂽ���Ƃ̏؍��Ƃ����ׂ��ł���A��������Ɩ����ӂ̖@���̍����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��鉪�c�Ӓ菑�̈ӌ��́A���������������ł���B
�R�@�����@�R�V�R�𐧒�ɓ������ă{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�ƐӔC�K�肪�폜���ꂽ���Ƃɂ���
(�P)�@���c�Ӓ菑�́A�����@�R�V�R�𐧒�ɓ������ă{�A�\�i�[�h���@���Ă��獑�ƐӔC�K�肪�폜���ꂽ���Ƃɂ��āA�u�����̕s�@�s�ׂɂ��č��͔����ӔC��Ȃ��Ă����ꍇ�����邪�A�ǂ̂悤�ȏꍇ������ɊY�����邩�͎���@�ł͖��������ɁA����Ɉς˂�Ƃ�����|�ł�(����)�v(���c�Ӓ菑�P�U�y�[�W)�Ƃ���B
(�Q)�@�������A�O�L�P�y�тQ�ŏq�ׂ��Ƃ���A�s���ٔ��@�y�эٔ����\���@�̗��@�҈ӎv�́A���Ɩ����ӂ̖@���������Ƃ��āA�s���ٔ����y�юi�@�ٔ����́A����������Ɣ��������i�ׂ����Ȃ��Ƃ��Ă������̂ŁA�ɂ�������炸�A���̖@�ł��閯�@�ɂ����āA���̌��͓I��p�ɂ��Ĕ����ӔC��F�߂���K�肷�邱�Ƃ͖����ł���B
���������āA�{�A�\�i�[�h���@���ĂR�V�R�����獑�Ɣ����ӔC��F�߂镶�����폜�����̂́A���Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ă������߂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
(�R)�@�܂��A��T�i�l��������(�P)�U�y�[�W�ȉ��ŏq�ׂ��Ƃ���A�����@�R�V�R���̐R�c�̉ߒ��ɂ����āA�N����(�{�A�\�i�[�h)�́A�����Ɂu���m�������m�ӔC�v���K�肵�����R�ɂ��A�����͌����c�̂̌��͓I��p�ɂ����@��K�p���ׂ����Ƃ̓t�����X���̑��̏����ɂ����Ă��٘_�̂Ȃ��Ƃ���ł��邩��A���{�ɂ����Ă����l�Ƃ��ׂ��ł���Ƃ��A������āA�����ψ��́A�@���ɐӔC��Ə�����K���u���ȊO�́A�����͌����c�͔̂����ӔC���ׂ��Ƃ̏C���Ă̈ӌ����������B���̏C���ẮA�{�A�\�i�[�h���@���ĂR�V�R�𒆁A�u�����m�v�̂R�������폜���A�V���ɁA�u���A�{�A�p�A���A���j���{���m�K�胒�K�p�X�A�@�����ȃe���j�ӔC���Ə��X���ꍇ�n�����j�Ѓ��X�v�Ƃ̏�����lj�����Ƃ������̂ŁA�����{���ɂ�荑�Ɣ����ӔC���ׂ����Ƃ�������̂ł�����(����R�P���R�X�W�y�[�W)�B
�����ψ��̌����́A���ƂƊ������ϑ��҂Ǝ���҂̊W�ɂ���A���Ƃ͂��̊����̕s�@�s�ׂɂ��Ė��@�ɂ�蔅���ӔC���A���A�����̍s�ׂ̐������킸�A���ƂƊ����͏�Ɉϑ��҂Ǝ���҂̊W�ɂ��邩��A���ǁA�{���͊����̕s�@�s�ׂɂ��ď�ɓK�p����A���Ƃ͔����ӔC���Ƃ������̂�(����P�O�V���R�X�y�[�W)�A����ɂ��A�u���A�{�A�p�A���A���j���{���m�K�胒�K�p�X�v�Ƃ̋K���lj�����K�v�͂Ȃ��B���̂��Ƃɉ����A��L�C���Ă��A�����̍s�ׂ������͂̍s�g�ɓ�����ꍇ�͖��@�̓K�p�͂Ȃ��A���Ƃ͖Ɛӂ����Ƃ̌����܂�����ō쐬���ꂽ����(����P�O�V���R�W�Ȃ����S�O�y�[�W)���l������ƁA�u���A�{�A�p�A���A���j���{���m�K�胒�K�p�X�v�Ƃ̋K��́A�{�������̂悤�ȏꍇ���܂߂ēK�p����邱�Ƃm�ɂ��邽�߁A�����āA�lj����ꂽ���̂Ǝv����B
�������A���ǁA�u���A�{�A�p�A���A���j���{���m�K�胒�K�p�X�v�Ƃ̋K��͒lj����ꂸ�A�{�A�\�i�[�h���@���ĂR�V�R�����獑�ƐӔC�̋K�肪�폜���ꂽ�ɂƂǂ܂����̂ł���B
������o�܂܂���A���B�����m�ɏq�ׂ�Ƃ���A���Ɩ����ӂ̖@�����̗p���ׂ����Ƃ������ɁA���ƐӔC��F�߂Ă����{�A�\�i�[�h���@���Ă̋K����폜�������̂Ƃ����ׂ��ł���(����R�R���X�V�O�A�X�V�S�A�X�V�T�y�[�W)�B
(�S)�@����ɑ��A���c�Ӓ菑�́A���ƐӔC���폜�������R�Ɋւ��閯�@�ψ��̈ӌ�(����R�P���R�X�W�A�R�X�X�y�[�W)���w�E���A����Ɋ�Â��A�u�����̕s�@�s�ׂɂ��č��͔����ӔC��Ȃ��Ă����ꍇ�����邪�A�ǂ̂悤�ȏꍇ������ɊY�����邩�͎���@�ł͖��������ɁA����Ɉς˂�Ƃ�����|�ł�(����)�v(���c�Ӓ菑�P�U�y�[�W)�Ƃ���B
�������A���c�Ӓ菑�̎w�E�����L�ӌ��́A�����ψ��̑O�L�C���Ăɑ��鑼�̈ψ��̗l�X�Ȉӌ����Љ����A�u���@�ψ��e�n(����)�����m�������m�ӔC�A���R�g�������Z�X�v(����R�P���R�X�W�A�R�X�X�y�[�W�A�����͈��p��)�ȂǂƂ�����̂ŁA�������������Ȃ鎞�_�ŕ\�����ꂽ�N�̈ӌ��ł��邩���疾�炩�łȂ��A�܂��Ė@���撲�ψ���S�̂̈ӌ��Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ�(���̂悤�Ȉӌ��ł��邱�Ƃ��������킹��L�q���S���Ȃ��B)�B�@�Ă̐R�c�ߒ��ɂ����ẮA�l�X�ȗ��ꂩ��c�_���Ȃ����̂ł���A���̂����̈�������āA�����ɗ��@�҈ӎv�̂��Ƃ��Ƃ炦�邱�Ƃ́A���Ƃ����ׂ��ł���B�@���߂́A�@�̐���o�߂̑S�̂̂ق��A�c�_�̍ŏI�I�Ȍ��ʂƂ��ċK�肳�ꂽ�̕����ɂ���ĂȂ����ׂ��Ƃ���A���̂悤�Ȋϓ_���猟������A�s���ٔ��@�Ƌ����@���{�s���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ɂ����āA�����͍s�g�ɂ��č��Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ƃ̊�{�I�@���m�������Ƃ݂�ׂ����Ƃ́A��T�i�l��������(�P)�Q�Ȃ����P�Q�y�[�W�ŏڏq�����Ƃ���ł���B
�܂��A���c�Ӓ菑�̎w�E�����L�ӌ��́A�u���{���K�J���������j�V�ϑ�҃^���m���i���L�X���ꍇ�j���e�n���������m�ߎ��m�Ӄj�C�X(����)���e�@���i���ꍇ�j���e���{���K�J�ϑ�҃i�����ۃm���n�����m���g�V�e�i�@���m���f�j�σX�v�Ƃ������̂ł���B���Ȃ킿�A���ƂƊ������ϑ��҂Ǝ���҂̊W�ɂ���A���Ƃ͂��̊����̕s�@�s�ׂɂ��Ė��@�ɂ�蔅���ӔC��(���̂悤�ȊW�ɂȂ���ΖƐӂ����)�Ƃ�����A�����̓���̕s�@�s�ׂɊւ��č��ƂƂ��̊������ϑ��҂Ǝ���҂̊W�ɂ��邩�ۂ��͖@�I���f�ł͂Ȃ��A���Ă��Ƃ̎����F��̖��ł��邩��A���̔��f�͎i�@�ٔ����ɂ䂾�˂�Ƃ�����̂ɂ������A�����āA���@�̓K�p�͈͂ɂ������@�I���f�ł��鍑�Ɩ����ӂ̖@���̍̔ۂ��u����Ɉς˂�v(���c�Ӓ菑�P�U�y�[�W)���̂ł͂Ȃ��B
(�T)�@�ȏ�̂Ƃ���A�{�A�\�i�[�h���@���ĂR�V�R�����獑�Ɣ����ӔC��F�߂镶�����폜�����̂́A���Ɩ����ӂ̖@�����̗p���ꂽ���߂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł����āA���̍̔ۂ�ɂ䂾�˂��|�ł������Ƃ��鉪�c�Ӓ菑�̈ӌ��͎����ł���B
�S�@���s���@�V�P�T���̐���o�߂ɂ���
(�P)�@���c�Ӓ菑�́A���s���@�V�P�T���̐���o�߂����āA�u���Ɩ����ӂ̖��͂܂��������̂܂܂ł���A��R�@�̕��j���s���m�Ȃ܂܂ł���A�����I�ɓ��ʖ@�������đΏ����ׂ���肾�Ƃ����_�ł͈�v���݂Ă����A�Ƃ����Ă悢���낤�B�v(���c�Ӓ菑�Q�P�y�[�W)�Ƃ���B
(�Q)�@�������A���s���@�́A���Ɩ����ӂ̖@���Ɋ�Â��A���@��̍s�ׂɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ̗����̉��ɐ��肳�ꂽ���̂ł���B
���Ȃ킿�A���s���@�V�P�T���̐���o�߂͔�T�i�l��������(�P)�Q�Q�y�[�W�ȉ��ŏڏq�����Ƃ���ł���A���Ɩ����ӂ̖@���Ɋւ��A���ؖL�O�́A��ϒd�ɑ��A�������́u���܃m��p�v�ɂ��E���s�ׂɂ��āA���@�V�P�T����K�p���č��ɔ����ӔC�킹�邱�Ƃ͗l�X�ȕ��Q�������A����ł��邩��A���@�V�P�T���̓K�p�ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��ƁA�͂����蓚�ق���悤�ɔ������̂ɑ��A��ς́A���@�V�P�T���̓K�p�Ώۂł���Ƃ͌��߂Ă��Ȃ��Ƃ��A���ʖ@�ɂ���Ē�߂鎖���ł���A���ʖ@�𐧒肵�Ȃ��ꍇ�ɁA���@�V�P�T���̓K�p�ʼn����ʂ��Ƃ͍l���Ă��Ȃ��Ɠ����A����ɑ��A�����A���̓��قł悭���������Ɠ����āA���̓_�Ɋւ���@�T������̋c�_���I���Ă���B���̂悤�ɁA���s���@�V�P�T��(���ĂV�Q�R��)�̖@�T������ɂ�����R�c�̌��ʁA���̌��͓I��p���L���A���{�̊������E�����s���ɂ��āA���̐E�����u���@��̊W�v�łȂ��u�����̍�p�v�ł���ꍇ�ɂ́A���s���@�V�P�T��(���ĂV�Q�R��)�̓K�p���Ȃ����Ƃ��m�F����Ă���̂ł���B
���̂��Ƃ́A���s���@�̋N���҂̈�l�ł���~�����Y���A�����S�P�N�Q�����s�̖@�{�u����P�O����Q���ɂ����āA�����̐E����̕s�@�s�ׂɊ�Â�������̔����ӔC�ɂ��A�����̐E����̕s�@�s�ׂɊւ��ẮA���@�V�P�T���̓K�p���Ȃ����Ƃ����A���@�_�Ƃ��č��ɔ����ӔC�킹��ׂ��ƍl���Ă���|�𖾂炩�ɂ��Ă��邱��(�@�{�u�тP�O���Q���S�T�y�[�W�E����R�U����)�A�������N���҂̈�l�ł���x�䐭�͂��A�吳���N�ɓ����鍑��w�ōs�������@�̍u�`�Ɋւ���u�`�^�̖��@�V�P�T���̉���ŁA�����̉��Q�s�ׂɂ��āA���@�V�P�T���͓K�p�����A�s���@�K�Ɉς˂�Ƃ����̂����@��|�ł���A�s���@�̕���ł́A���ʋK�肪���鑼�́A��ʌ����Ƃ��āA���͔����ӔC��Ȃ��Ƃ���Ă���A�����̎��s�ɔ����ӔC�킹�邱�Ƃ͑傢�ɖ�肪���邪�A�����A�c�ƂƂ��Ď��Ƃ��Ȃ��ꍇ�ɂ܂ŁA�����ӂƂ��Ă��܂��͖̂��ł���A�ٔ�������̗l�ɔ������Ă��邪�A����͕s���ł���|�q�ׂĂ��邱��(�x�䔎�m�q�E�܊e�_���P�X�U�A�P�X�V�y�[�W�E����R�V����)���疾�炩�ł���B�����̖��@�N���҂͂�������A���Ƃ̌��͓I��p�ɂ��āA���@�̓K�p�͂Ȃ��A���@�_�Ƃ��čs���@�ȂǓ��ʖ@�ɂ���Ē�߂�ׂ��ł��Ƃł��邪�A�s���@�ł͈�ʓI�ɔ����ӔC�킹����ʖ@���߂Ă��Ȃ��Ɛ������Ă���A���Ɩ����ӂ̖@����O��Ƃ��Ă���̂ł���B
�Ȃ��A�����Q�W�N�P�O���S�ڂ̖@�T������ɏo�Ȃ��Ă�����ϔ����́A���@�{�s�O�̖����R�O�N�X�����s�̖@�{�����G����P�T����X���ɁA�u���p���y�і��@�v(��ϐl�����m�_���W�S�P�Q�y�[�W�E����V�W����)�Ƒ肷��_���\���A���̖`���ŁA�u���@�m����n�Ӄt�w�V���@�m���p�n�����T���w�J���X�䖯�@�m���K�n�s���m�����j���e�����m�y�j�}�e�N���Z���g�~�X���J�x�@�y�����m�����n�����i�����܃J�m�s���j���V���@�m���K�m�K�p���e�����m�P�n�i�V�Ճ����p�s���m�͚��j���L�e�n���m�������K���X���@�m�����J�����փ��m�@��j�d���X���J���X�j�V�e�^�����N�R�g���V�g�X���p���m���L�܃m�@�L�{�҃m�����j�d�Z�X�v�Əq�ׂĂ���B�������ϔ�������@�w�҂̍l���ɂ��A�����͂̍s�g�̓K�ۂ����ƂȂ�悤�Ȍ��@�I�@���W�ɖ��@��K�p���邱�Ƃ́A�܂��Ɂu���@�̗��p�v�ł���A�u�s���@�Ƃ����َ��Ȗ@�̈���@�̔��z�Ŕ��f���閯���@�鍑��`�I�Ȕ��z�v(�����ח��E�@�w�����Q�U�V���R�W�y�[�W)�Ƃ��ꂽ�̂ł���B
(�R)�@����ɑ��A���c�Ӓ菑�́A��ϒd���A�@�T������̋c�_�̍ŏI�i�K�ɂ����āA�u�����m�E�����s�m�ꍇ�j�����K�c���K�X�C�g��X�n�Ƀ��e�����k�m�f��X�K�����V�e�����g���g�V�e�n���@�j���C�e���������A���}�X�J�����������J�E�J�g�v�t�e���k�V�e���}�V�^�K�C�d�����ʖ@�K�o�҃��_���E�g�v�q�}�V�^�J���~���^�m�f�A���}�X���ʖ@�K�o�҃k�g�]�t�R�g�����z�V�e���f�˃L�ʃX�g�]�t�m�f�n�i�C��V���ʖ@���o�҃i�J�c�^�������K�h�E���׃T�����J�g�]�t�R�g����n���}�X�J�����ʖ@�K�i�C�ȏ�n��w�o�R�̓K��Ȑl�m���̐ӑD�g�Փ˃V�e���D�������^�g�J�]�t�T�E�]�t�l�i�ꍇ�j�������������g�]�t�j�n�����K�c���n�V�i�C�J�g�]�t�䑊�k���V�^�m�f���ʖ@���색�i�C�f�����f���ʃV�e�d���E�g�]�t��P�m���S�n��X�O�l���i�J�c�^�m�f�A�����V��V���ʖ@�K�i�J�c�^���o�����K�c���W�����E�g�]�t�l�w�n�O�l�����c�e�����v(����R�S���R�S�W�y�[�W��i)(���p�Җ�:�����̐E�����s�̏ꍇ�ɁA�{�����K�p�����̂��悢�Ɖ�X�͌��߂Ă��Ȃ��B��X���������Ă݂�ƁA���Ƃ��Ė��@�ɏ����Ă��鍑������܂�����A��������������Ǝv���đ��k���Ă݂܂������A���ʖ@���ł��邾�낤�Ǝv���܂�������~�߂��̂ł���܂��B���ʖ@���o���ʂƂ������Ƃ�\�z���Ă���œ˂��ʂ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�����A���ʖ@���o���Ȃ�������A�{�����ǂ����߂���邩�Ƃ������Ƃ����܂�����A���ʖ@���Ȃ��ȏ�A�Ⴆ�ΌR�͂���l�̏����D�ƏՓ˂��Ă��̑D�߂��Ƃ������悤�ȏꍇ�ɁA���������߂�Ƃ����ɂ͖{����������͂��Ȃ����Ƃ��������k�������̂ŁA���ʖ@�����Ȃ��ł���ʼn����ʂ��Ă��܂��Ƃ��������̌��S�͉�X�R�l�Ƃ��Ȃ������̂ł���B�������A�������ʖ@���Ȃ������Ȃ�A�{���������邾�낤�Ƃ����l���͂R�l�Ƃ������Ă���B)�ȂǂƔ������Ă��邱�Ƃɑ����āA�u���Ɩ����ӂ̖@���̖��͂܂��������̂܂܂ł�(����)�v(���c�Ӓ菑�Q�P�y�[�W)�Ƃ��邪�A�����ł���B
��ϒd�̏�L�����́A���ʖ@�����肳��Ȃ��ꍇ�ɁA�{�����ǂ̂悤�ɉ��߂����ׂ����Ƃ������ƂɊւ��āA�l�I�Ȍ������A���Ȃ̊�]�������߂ďq�ׂ��ɂ����Ȃ��B���Ȃ킿�A�����̍ٔ���̌X���́A���ؖL�O�̔����Ȃǂɂ���悤�ɁA��R�@�����ł́A���{�̊����̐E�����s�ɂ���O�҂ɑ��Q���y�ڂ����ꍇ�ɐ��{�̐ӔC��F�߂����̂͂Ȃ��A�ٔ���̈�ʓI�ȌX���Ƃ��Ă͐��{���ӔC��Ȃ��Ƃ�����̂ł�������(����R�S���R�S�V�Ȃ����R�S�X�y�[�W�Q��)�A��ώ��g�A�u�����m�����n�O�j�K��K�i�P���o�K�p�T�����E�g�v�q�}�X�K��R�@�j���N�h�K�p�T���k�g�v�q�}�X�v(���l�R�T�O�y�[�W��i)�Əq�ׂĂ���Ƃ���ł���A�����{���̓K�p���ے肳��邱�Ƃ͋��ʂ̔F���������̂ł���B
(�S)�@�ȏ�̂Ƃ���A���s���@�́A���Ɩ����ӂ̖@���Ɋ�Â��A���@��̍s�ׂɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ̗����̉��ɐ��肳�ꂽ���̂ł���A�����A���Ɩ����ӂ̖@���̍̔ۂ͂��܂��������ł������Ƃ��鉪�c�Ӓ菑�̏�L�ӌ��͎����ł���B
��R�@���Ɩ����ӂ̖@���͖@�߂ɂ���Č������t�^���ꂽ�s�ׂ݂̂ɓK�p�����Ƃ���_�ɂ���
�P�@���c�Ӓ菑�́A���Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�̗L���́A�u�����܂ł��@�߂ɂ���Č������t�^����Ă���s�ׂ������̂��ۂ��Ŕ��f�����v(���c�Ӓ菑�S�Q�y�[�W)�Ƃ���A�u�ۂ̎U�z�s�ׂ́A�@�߂ɂ���ĕt�^���ꂽ�����̍s�g�Ƃ������Ƃ͂ł����A�ނ��뗇�̖\�͂ɑ��Ȃ�Ȃ��v(���S�Q�A�S�R�y�[�W)����A�T�i�l��̎咣����{�����Q�s�ׂɍ��Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�͂Ȃ��Ƃ���B
�Q�@�������A�O�L��P�A�R�A(�Q)�ŏq�ׂ��Ƃ���A���������A�s�@�s��(��@�s��)�́A�@�ɂ�苖����Ȃ��s�ׂł���A�@�ɂ���ĕی삷�ׂ��s�ׂƂ͂����Ȃ����A�������@���ł́A���̈�@�s�ׂ����Ƃ̌��͓I��p�ł������A���@�̖{�@�s�K��̓K�p��r�����A���ɍ��ɔ����ӔC��F�߂�K�肪�Ȃ��������Ƃ��獑�̔����ӔC���ے肳�ꂽ�̂ł���B���Ȃ킿�A���������E���Ɋւ��čs�����s�@�s�ׂ����Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�ΏۂƂ����邩�ۂ��́A���̍s�ׂ̐��������͓I��p�ł��邩�ۂ��Ō�������̂ł����āA���̍s�ׂɖ@�I���������邩�ۂ��Ō���������̂ł͂Ȃ��B
���̓_�ɂ��ẮA�ō��ُ��a�Q�T�N�������A�u�_�|�͌������͖{�i�������͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�̔��������߂���̂ł���Ƃ��Ȃ���A���̌��͂��@���Ȃ���@��̖@�K���͏����ɂ���Ċ�b�Â����Ă��邩�𖾂��ɂ��Ă��Ȃ��Ǝ咣����̂ł���B�c�����āA���R�����̔����������R�ɂ���āA�{�i���������p���邽�߂ɂ́A���_�̂悤�ɔ@���Ȃ�@�ߖ��͏����ɍ�����������������K�v���Ȃ��̂ŁA�������ɂ͉�����@�͂Ȃ��B�v�Ɣ������Ă���Ƃ���ł���B
���c�Ӓ菑�́A���Ɩ����ӂ̖@���y�эō��ُ��a�Q�T�N�����𐳉����Ă��炸�A�����ł���B
�R�@�܂��A���Ɩ����ӂ̖@���̓K�p�̗L�����A�u�����܂ł��@�߂ɂ���Č������t�^����Ă���s�ׂ������̂��ۂ��Ŕ��f�����v(���S�Q�y�[�W)�Ƃ̈ӌ��́A���̍������K���������炩�łȂ����A��R�@����̕��͂Ɋւ���A�u���f����s�ׂ̖ړI����@�I����(�Ƃ��Ɍ����K��)�ւƈڂ����Ƃɂ���āu���́v���̔F������i�ɐR������悤�ɂȂ������Ƃł���B���Ƃ��A�������Ƃɂ��Ă�[�P�Q]�������A�R���֘A���Ƃɂ��Ă�[�Q�W]�������A�����g���ɂ��Ă�[�Q�R]������������Ȃ����̂Ƃ݂���B�v(���c�Ӓ菑�R�U�؈�W)�Ƃ̋L�q�ɏƂ炷�ƁA��R�@�吳�T�N�U���P������(��L[�P�Q]����)�A��R�@�吳�P�S�N�P�Q���P�P������(��L[�Q�R]����)�y�ё�R�@���a�V�N�W���P�O������(��L[�Q�W]����)�������Ƃ�����̂Ǝv����B
�������A�����̑�R�@�����͂��Ƃ��A���c�Ӓ菑�����͑ΏۂƂ��Čf���邻�̗]�̑�R�@�������݂Ă��A���Ɩ����ӂ̖@���͖@�߂ɂ���Č������t�^���ꂽ�s�ׂ݂̂ɓK�p�����|�����������̂͑����Ȃ�(���c�Ӓ菑�Q�T�Ȃ����R�T�y�[�W�Q��)�B���������āA���o�Ӓ菑�̏�L�ӌ��́A�����������Ǝ��̌����Ƃ����ق��Ȃ��B
�S�@����ɁA�T�i�l��̎咣����{�����Q�s�ׂ��@�߂Ɋ�Â������̍s�g�ł͂Ȃ��Ƃ��邱�Ƃ́A�T�i�l��̔�T�i�l�ɑ��鐿������b�t������̂ł͂Ȃ��B�T�i�l��̎咣����{�����Q�s�ׂ��A���������K�@�Ȍ����͍s�g���������݂��Ȃ��̂ɍs�������͍s�g�ł���Ƃ���̂ł���A����͌����͂̍s�g�ł͂Ȃ��A���l�ɂ����Ă������闇�̖\�͂ɂ����Ȃ��B���̓_�́A���c�Ӓ菑���A�T�i�l��̎咣����{�����Q�s�ׂ́A�u���̖\�͂ɑ��Ȃ�Ȃ��v(���c�Ӓ菑�S�Q�A�S�R�y�[�W)�Ɩ������Ă���Ƃ���ł���B��������ƁA�{���ɂ����ẮA���̌������̎����ɂ��s�ׂƂ��āA��T�i�l�͑��Q�����ӔC��Ȃ��A���ƂȂ낤�B
���������A���O���ɂ����āA���Ɩ����ӂ̖@���̍����Ƃ��ꂽ���̂̂ЂƂɁA��@�s�ׂ͍��ƂɋA�����Ȃ����Ƃ��������Ă����B���Ȃ킿�A�u��@�ȍ��Ƌ@�ւ̍s�ׂ́A���ƈӎv����@�K�Ɉᔽ����̂ɍ��Ƃ��\����@�֍s�ׂƂ͖@����F�߂�ꂸ�A���������āA(����)�@�I�ӔC�͍��Ƃɐ����Ȃ��v�Ƃ���Ă���(�Y���Y�E�s����̑��Q�����E�s���@�u����R���E�S�y�[�W)�B
���̂悤�ɁA�������Ɍ������Ȃ����Ƃ́A�ނ��덑�Ƃ̔����ӔC��ے肷�邱�Ƃ𐳓���������̂ł���A�������Ȃ�����Ƃ̔����ӔC���m�肳���ȂǂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�T�@�Ȃ��A�������ɂ��̌��͓I��p���s�����������������ۂ��́A��L�̂悤�ɁA���Y���������l�Ƃ��đ��Q�����ӔC�����ۂ�����������ɓ������Ă͈Ӗ�������B���Ȃ킿�A���Y�������ɗ^����ꂽ�����������͂̍s�g�ɌW����̂ł���A���̌������͑��Q�����ӔC��Ȃ���(���Ⴊ�A�s���ٔ��@�{�s�ȍ~�A��O�A��т��Ċ��������ӂ̗�����̂��Ă������Ƃɂ��A�F��E�O�f���ƐӔC�@�̕��͂S�Q�Q�Ȃ����S�R�O�y�[�W)�A�������S���Ȃ��ƕ]�������A���̌������̎����ɑ�����s�ׂƂ��āA�������l���������Q�����ӔC������ł���B
���c���F�������A�������@���ɂ����ẮA�u�x�@�A�R���A�Ŗ��A���p�Ȃnj����͂̍s�g�ɂ�����鎖���ɂ��ẮA���Ƃ����������s�@�s�ׂɂ���Đl���ɑ��Q���������Ă��A���A�����c�̂͂��ɔ����̐ӂ߂����ƂȂ��A�����������̖����Ȍ������p�△�����̍s�ׂɂ��Ă̂݁A���@�V�O�X���ɂ��������l�ɑ��锅���������F�߂�ꂽ�ɂ����Ȃ������B�v�Ǝw�E���Ă���(���c���F�E�s���@�v�_�S����ܔłQ�U�X�y�[�W)�B
�܂��A�O�f�ō��ُ��a�Q�T�N�������A�u�{���Ɖ��̔j�_�|�̂����悤�Ɍ������̏d��Ȃ�ߎ��ɂ���čs��ꂽ���̂ł����Ă��A���̂��߂ɖ{���Ɖ��̔j��s�ׂ��A���̎��l�Ɠ��l�̊W�ɗ��o�ϓI�����̐�����тт���̂łȂ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����Č����͂̍s�g�Ɋւ��Ă͓��R�ɂ͖��@�̓K�p�̂Ȃ����ƌ������̐�������Ƃ���ł����āA�����@���ɂ����ẮA��ʓI�ɍ��̔����ӔC��F�߂��@�����Ȃ������̂ł��邩��A�{���j��s�ׂɂ��č��������ӔC�����R�͂Ȃ��B���Ⴕ����Ɍx�@���������͂̍s�g�ɖ�������A�E���𗔗p���Ė{���Ɖ���j�����̂ł���Ƃ���A���ꓙ�x�@�������@��̕s�@�s�ׂ̐ӔC�����Ƃ͂��邩���m��Ȃ����A���̏ꍇ�E�̍s�ׂ͂��͂⍑�̍s�ׂƂ͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł����āA���X���������ӔC�����R�͂Ȃ��̂ł���B�v(�����͈��p��)�Ɣ������Ă���B
�U�@���̂悤�ɁA���ɍT�i�l��̎咣����{�����Q�s�ׂ��A���猠����L���Ȃ��������ɂ��Ȃ��ꂽ���̂ł���A�����l�̔����ӔC�̗L�������ƂȂ�ɂƂǂ܂�A��T�i�l�������ӔC�����Ƃ͂Ȃ��B���Ȃ킿�A������ꍇ�ɂ́A���Ɩ����ӂ̖@���������Ƃ���܂ł��Ȃ��A���ɑ��Ė��@�s�@�s�K��͓K�p����Ȃ��̂ł���B
���c�Ӓ菑�́A������ꍇ�ɂ��āA���Ɩ����ӂ̖@���͓K�p����Ȃ��Ƃ��A�������璼���ɍ��ɑ��Ė��@�s�@�s�K�肪�K�p�����Ƃ��邪�A�����Ƃ����ق��Ȃ��B
��S�@���Ɩ����ӂ̖@���͓��{���̓������̋y�Ȃ��O���l�ɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ���_�ɂ���
�P�@���c�Ӓ菑�́A�u���{�̎匠���ɂȂ��O���l�Ɠ��{�R�Ƃ̊ԂɌ��@��̊W�����݂��Ă��Ȃ��������Ƃ͖����ł��邩��A���Ɩ����ӂ̖@����K�p����]�n�͂Ȃ��B�v(���c�Ӓ菑�S�R�y�[�W)�Ƃ��āA���Ɩ����ӂ̖@���͓��{���̓������̋y�Ȃ��O���l�ɂ͓K�p����Ȃ��Ƃ���B
�Q�@���c�Ӓ菑�̏�L�ӌ��́A���Ɩ����ӂ̖@���͖@�߂ɂ���Č������t�^���ꂽ�s�ׂ݂̂ɓK�p�����Ƃ̗�����O��Ƃ�����̂ł��邪�A�����闝�������ł��邱�Ƃ́A�O�L��R�ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B���̓_�ŁA���c�Ӓ菑�̏�L�ӌ��́A�O��Ɍ�肪����Ƃ��킴����A�����ł���B
�R�@�܂��A��T�i�l��������(�P)�R�U�y�[�W�ȉ��ŏq�ׂ��Ƃ���A���������A�{���ɂ����Ė��ƂȂ��Ă���̂́A�����A�����Ȃ�҂ɑ��āA���͓I��p���y�ڂ����邩�Ƃ������(�{���ł́A�O���ɂ���O���l�ɑ��A���̓������Ɋ�Â��D�z�I�Ȉӎv�̔����Ƃ��Ă̋����I�E���ߓI��p��K�@�ɋy�ڂ����邩�Ƃ������)�ł͂Ȃ��A�O���ɂ���O���l�ɑ��āA���͓I��p���y�ڂ����ꍇ�ɁA�����A���̍����@��A���Q�����`�������ۂ��̖��ł���B
�����āA���Ɩ����ӂ̖@���́A�����͂̍s�g�ɂ��A���̍s�ׂ̐������l�����āA���̖@�ł��鎄�@�Ȃ������@�̓K�p���̂�r��������̂ŁA�s���ٔ��@�y�ы����@�����z���ꂽ�����Q�R�N�̎��_�ŁA�����͂̍s�g�ɂ��č��͑��Q�����ӔC��Ȃ��Ƃ������@���m���������̂ł���B���̂悤�Ȗ@������̗p���������̉䂪���̖@���ɂ����āA�O���l����Q�҂ł���ꍇ�ɂ͌��͓I��p�ɂ��A���@�̕s�@�s�K���K�p���č��ƐӔC���m�肵�A���{�l����Q�҂ł���ꍇ�݂̂ɖ��@�̕s�@�s�K��̓K�p��ے肵�č��Ɩ����ӂƂȂ�Ƃ���������̂��Ă����Ƃ͓���l�����Ȃ��B
�S�@���c�Ӓ菑�̏�L�ӌ��́A���Ɩ����ӂ̖@���𐳉����Ȃ��Ǝ��̌����Ƃ��킴����A�����ł���B

|