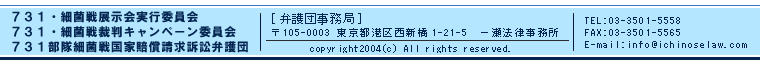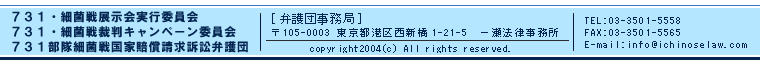�Q�O�O�Q�N�i�l�j��S�W�P�T���Ӎߋy�ё��Q���������T�i����
�T�i�l�i��R�����j ���@�G�@�Ł@�@�O�P�V�X��
��T�i�l�i��R�퍐�j�@���@�{�@��
�@�@�@�@�@�@�@
��P��������
�Q�O�O�R�N�S���Q�P��
���������ٔ�����Q�������@�䒆
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�i�l��i�ב㗝�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ٌ�m�@�@�@�y�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@��@�@�@���@�@�@�@�h�@��@�Y
�� �@�@�@�S�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@��
�� �@�@�@���@�@�@���@�@�@�@���@�@�@��
�� �@�@�@�� �@�@�@�c�@�@�@�@�@�@�@�@��
���@�@�@�Ł@ �@�@��@�@�@�@�G�@�@�@�V
���@�@�@���@�@ �@��@�@�@�@��@�@�@��
���@�@�@���@ �@�@�c�@�@�@�@�q�@�@�@��
���@�@�@�r�@ �@�@�c�@�@�@�@���@�@�@�q
���@�@�@�ہ@ �@�@��@�@�@�@�p�@�@�@�O
���@�@�@���@�@�@ ��@ �@�@�@�@�@�@�@�~
�� �@�@ �R�@�@�@ �{�@�@�@�@���@�@�@��
�@
�ځ@�@��
��P�́@�������̕s���`���ƍT�i�R�̉ۑ�
�@��P�@�������ɑ���T�i�l��̌������{��
�@��Q�@�������́u�ې펖���y�э��ƐӔC�v�̔F��ƍT�i�R�̉ۑ�@
�@��R�@�{���ې�̉��Q�s�ׂ̎c�s���A��Q�̏d�含�ɂ���
��Q�́@���{���@�Ɋ�Â��Ӎߋy�ё��Q��������
�@��P�@�{���ې�́A�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�i�P�X�Q�T�N�j����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ���A
�@�@�@�@ ���@�V�O�X���Ȃ����V�P�P���܂��͂V�P�T���̕s�@�s�ׂɊY������
�@�@�P�@��
�@�@�Q�@�s�@�s�ׂ̎��
�@�@�R�@�s�@�s�גn
�@�@�S�@��@��
�@�@�T�@��Q�̔����ƈ��ʊW
�@�@�U�@���Q��������������юӍߐ������̐���
�@��Q�@���Ɩ����ӂ̖@���́A�{���ې�ɂ͓K�p����Ȃ�
�@�@�P�@���Ɩ����ӂ̖@���̊m���͔F�߂��Ȃ�
�@�@�Q�@�{���ې�́A�u�K�@�Ȍ����͍s�g�����v�Ɋ�Â����u���Ɩ����ӂ̖@���v�͓K�p����Ȃ�
�@�@�R�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v�͊O���ł̊O���l�ɑ��錠�͍�p�ɂ͓K�p����Ȃ�
�@�@�S�@�n�[�O���̍����@���ɂ���āu���Ɩ����ӂ̖@���v�͔r������K�p����Ȃ�
�@�@�T�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v�͈�@���߂ɂ������A���݂̖@���߂Ɋ�Â��ٔ����ׂ�
�@�@�U�@�܂Ƃ�
�@��R�@�����E���˂̕s�K�p
�@�@�P�@�����͖����������Ă��Ȃ�
�@�@�Q�@�{���ې�ɂ����Ď����E���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����ׂ��ł���
�@�@�R�@���ˊ��Ԃ�K�p���Ȃ��ߎ��̔���
�@��S�@�u�������������ɂ������v�_�ɂ���
�@�@�P�@�������̔��f
�@�@�Q�@�������������ɂ�����u�푈�����̐���������v�ɂ���
�@�@�R�@���_
��R�́@�𗝂Ɋ�Â��Ӎߋy�ё��Q��������
�@��P�@�������͎Љ�I���`�ɔ�����
�@��Q�@�𗝂̖@����
�@��R�@�𗝂Ɋ�Â��⏞�����ɂ���
�@��S�@�{���ɂ�����𗝂̑���
�@��T�@�𗝂Ɋ�Â����ٔ���
��S�́@�������@�ɂ��ƂÂ��Ӎߋy�ё��Q��������
�@��P�@�@���P�P���P�����K�p����Ȃ��Ƃ̔F��������������̌��
�@�@�P�@�������̌��
�@�@�Q�@�������̌��͍s�ׂɍۂ��đ��l�ɗ^�������Q�̔����ӔC�̖@�I���i
�@�@�R�@���ݕۏ؎�`�ƍ��Ɣ����@�̐��i
�@�@�S�@���ێ��@�̓K�p
�@�@�T�@���_
�@��Q�@�@��P�P���Q���̓K�p�͂Ȃ�
�@��R�@�@��P�P���R���̓K�p�͂Ȃ�
�@��S�@�������@�̋K��Ƃ��̓K�p�W
��T�́@���@�s��ׂɂ��Ӎߋy�ё��Q��������
�@��P�@���̏���
�@��Q�@�n�[�O����R���Ɋ�Â��T�i�l�̍��ƐӔC�̐����Ƃ��̐����_
�@��R�@�n�[�O����R���Ɋ�Â������������Ɠ������������ɂ�����u���������̕����v�ɂ���
�@��S�@�n�[�O����R���Ɋ�Â��l�̑��Q�����������Ɠ�����������
�@��T�@�n�[�O����R���Ɋ�Â������̑��Q�����������Ɠ�����������
�@��U�@��T�i�l�ɂ͔�Q�Ҍl�ɑ��ė��@��̋~�ϋ`������������
�@��V�@���@�`���̕s���s�ɂ�闧�@�s��ׂ̐���
�@��W�@���_
��U�́@�s���s��ׂɂ�鎖�������E�~�ϋ`���ᔽ�̕s�@�s��
�@��P�@���̏���
�@��Q�@��`���̔����v��
�@��R�@�{���ې�ɂ������T�i�l���t�̎��������E�~�ϋ`���̕s���
�@�@�P�@�{����N�Q�@�v�i�{�����鐸�_�I��Ɂj�̏d�含
�@�@�Q�@�Z���̔�Q�̊g��p��
�@�@�R�@�Z�����g�ɂ���Q�����̕s�\��
�@�@�S�@�s���ɂ���Q�g��̗\���\��
�@�@�T�@�{���ɂ����鎖�������E�~�ϋ`���̔����ƍs���s��ׂ̐���
�@��S�@����
��V�́@�B���ɂ�錠���s�g�W�Q�̕s�@�s��
�@��P�@���̏��݂ɂ���
�@��Q�@�T�i�l��̔�N�Q�@�v�Ȃ��������ɂ���
�@��R�@��T�i�l�̖{���B���s��
�@��S�@���_
��W�́@�T�i�l��̐���
�@��P�@�Ӎߐ���
�@��Q�@���Q��������
�@��R�@����

��P�́@�������̕s���`���ƍT�i�R�̉ۑ�
��P�@�������ɑ���T�i�l��̌������{��
�@�P�@��N�W���Q�V���A���R�E�����n���ٔ��������P�W���͖{���V�R�P������
�ې�ٔ��Ō����s�i�̔����������n�����B�{���ې�ٔ��́A���{�R�ɂ��ې���ق��ٔ��j��ŏ��̍ٔ��ł��������A�������͈�R�����炪���߂Ă����Ӎ߂Ɣ����̐�����S�ʓI�ɑނ����B
�@�����ɓ��{�̍ٔ����́A�ې��Q�҂炪���\�N�����ߑ����Ă������{���̎Ӎ߂Ɣ�����ے肵���̂ł���B
�Q�@�������e�����T�i�l��́A�������ɐS�ꂩ��{�����B�T�i�l��̋C
������`����G�s�\�[�h���Љ�����B
�@�T�i�l��̑㗝�l�ł���ٌ�c�́A��N�P�P���ɖ{�ٔ��̍ې�̔�Q�n�̈�ł��鐒�R����K�˂��B
�@�ٌ�c�؍ݒ��̍�N�P�P���S���A���R���œ����n�ٔ��������W��J���ꂽ�B���̏W��ɂ́A���R�����炾���ł͂Ȃ��A�������]�Ȃ̒��̍ې�̔�Q�n�E�`�G�s�A�ˏB�s�A�J�g�s�Ȃǂ������R�����炪�Q�������B
�@���̒��ɂ͖�����������������肷��傫�Ȓr������A���̑��ɂ��鑺�̏W���̑O���L��ɂȂ��Ă��āA�����ɏW�܂����P�O�O�O�l���炢�̑��l��e�n�̍ې��Q�҂͈�R�����̕��A�܂����{�̍ٔ�����ٔ������v���v���ɔ����B
�@�R���Ԃ��炢���������̏W��I����Ă݂�Ȃ����f����������ォ���Â������Ă���e�ŁA���R���̑��l�̘V�������{�ٌ̕�m�ɋ߂Â��Ęb�������Ă����B�b���n�߂Ĕޏ����j�Ă���̂��킩�����B�Ƃ���Ƃ���ɘb���ꂽ���e�ٌ͕�c�ɒʖē`����ꂽ�B
�@�u���{�̍ٔ����Ƃ����͉̂��Ɨ�W�Ȑl�B���낤�B���{�̗L���ȍ�ƐX�����ꂪ�V�R�P�����ɂ��ĉ������{�����������Ƃ͒����l���m���Ă���B���{�̍ٔ����Ȃ�A�V�R�P�����������l�ɐl�̎���������čە�����J�����Ă������Ƃ��炢�A��Q�҂�������i����O����m���Ă������낤�B�ٔ����̕���c���̐���̓��{�R���A�킪�����̓��k�ɖ��B�����ł����グ�A�_�n�����D���ĂV�R�P�������������B�����čŌ�ɂ͂V�R�P�����͒����e�n�̊X�⑺�ɍۂ���܂����B�{���ɋ��낵�����Ƃ��B
�@��W�ȓ��{�l�́A���������������l�̂悤�Ƀy�X�g�a���T���ꂽ��ǂ��v�����z�����Ă݂�ׂ����B�M���ɂ́A����ꒆ���l�ɂƂ��āA����ȗ�W�Ȕ����͍ې��������x���ꂽ�̂Ɠ����ȂƂ������Ƃ�������܂����B�v
�@������������R���̑��l�́A�����̕��e�ƌZ����{�R�̍ې�̃y�X�g�ŎE���ꂽ�l�ł���B�ޏ��͈�R�����ł͂Ȃ����A��S�O�O�l�̎��҂��o�������R���ł́A�Ƒ����e�ʂɂ͕K���y�X�g�̋]���҂�����B
�@���̘V�l�͏��w�Z��w�N�Ǝv���鑷��A��Ă������A�ې�̎c�s�Ȕ�Q�Ƃ�������s�������{�R�̔؍s�A����ɎӍ߂Ɣ�����ے肵������̓����n�ٔ����̕s���`�͉i���ɓ`�����Ă����ł��낤�B
�R�@�ې��Q�҂����{�ɋ��߂��Ӎ߂Ɣ����͐��`���̂��̂ł���B��Q��
�����ɂƂ��āA�Ӎ߂Ɣ�����ے肵���������͕s���`���̂��̂ł���B
�@���������Ƃ����ԈႢ�͐[���ł���B�ې���ق��ŏ��̍ٔ����A�t�Ɂu���̍ې�v�ƂȂ������Ƃ��ٔ��������͂悭�m��ׂ��ł���B
��Q�@�������́u�ې펖���y�э��ƐӔC�v�̔F��ƍT�i�R�̉ۑ�
�@�������́A���_�Ŕ�T�i�l�̖@�I�ӔC��ے肷����̂��������A���ʂŁA�ȉ��̂Ƃ���A�����{�R�V�R�P�����������R�����̎w�߂ɂ�蒆���e�n�ōە��������g�p����������S�ʓI�ɔF�肵���B
����ɁA�������́A�ې�̎����Ƌ��ɁA�ȉ��̂Ƃ���A�����A�ې킪���ۖ@�Ɉᔽ���Ă���A��T�i�l�̍��ƐӔC�������������Ƃ�F�肵���B
�@�T�i�R�ٔ����ɂ����ẮA���������F��ɓ��܂��ċc�_��i�߂�ׂ��Ǝv������B
�P �������́A�ې�̎�����S�ʓI�ɔF��
�@�@(1) ���{�R�̉��Q�s��
�@�������́A�u�P�X�S�O�N����P�X�S�Q�N�ɂ����āA�V�R�P������P�U�S�S�������ɂ���āv�A�ˌ��i�ˏB�j�A�J�g�A�퓿�ɂ̓y�X�g�ۂ𓊉����A�]�R�ɂ̓R�����ۂ��g�p���Ē��ڍU�����A�u�ە���̎���g�p�i�ې�j���s��ꂽ�v�i�������R�O�Łj�ƔF�߂��B
�@�@(2) �`�d�ɂ��ې��Q
�@�������́A�u�ˌ��ł̃y�X�g�́A�`�G�A���z�A���R���A�����F�̂悤�ɂ��̎��ӂ̒n��ɂ��`�d���A�傫�ȋ]���������炵���v�i�������R�P�Łj�ƔF�肵���B�܂��u�P�X�S�Q�N�R���ȍ~�A�퓿�s�X�n�̃y�X�g���_�����ɓ`�d���Ă����A�e�n�ő����̋]���҂��o�����B�v�i�������R�S�Łj�ƔF�肵���B���̂悤�ɓ`�d�ɂ���Q�̊g�傪�F�肳��ې�̎c�s������w���m�ɂȂ����B
�@�@(3) �ې�̖��ߎw���n��
�@�������́A�u�ە���̎���g�p�́A���{�R�̐퓬�s�ׂ̈�Ƃ��čs��ꂽ���̂ŁA���R�����̎w�߂ɂ��s��ꂽ�v�i�������R�S�Łj���Ƃ�F�߂��B
�@�@(4) �ې�̋]����
�@�������́A�{���ٔ��̔�Q�n�W�����S�̂̍ې�ɂ�鎀�S�҂̐����P���l���邱�Ƃ�F�肵���i�������R�O�łȂ����R�S�Łj�B
�@�@(5) �ې�̎c�s��
�@�������́A�u�y�X�g�͎Љ�`�Ԃ���ē`�d���A�l�X�����X�Ɏ��ɒǂ���邱�Ƃ���A���ʂƂ��݂��̋^�S�ËS�������A�n��Љ�̕���������炷�ƂƂ��ɁA�l�X�̐S���ɐ[���ȏ��Ղ��c���B�v�u�q�g�Ԃ̗��s�����܂�������A�a���̂����R�̐����E�ŕۑ�����A�q�g�̊ԂɊ�������\���������c������B���̈Ӗ��ŁA�y�X�g�́A�n��Љ������邾���ł͂Ȃ��A�����������Ԃɓn���ĉ�������a�C�ł���v�ƔF�肵���B�܂��u�R�����́A�`���͂������A���X�Ǝ��҂��o��ƒn��Љ�ɂ����č��ʂ₨�݂��̋^�S�ËS���������Ƃ������B�v�i�������R�T�ŁA�R�U�Łj�ƔF�肵���B
�@�Q�@�������́A�ې��Q�ւ̔�T�i�l�̍��ƐӔC��F��
�@�@(1) ���{�R�̍ې�̍��ۖ@�ᔽ��
�@�������́u���Ƃ��ƍە���́A���ꂪ�퓬�̖ړI�Ɣ�r���ĕs�����Ȑ��i�̂��̂ł���Ƃ̏]������̏��Ȃ��Ƃ��َ��I�ȋ��ʔF����O��ɃW���l�[�u�E�K�X�c�菑�Ŗ����I�ɂ��̎g�p���֎~���ꂽ���̂Ɖ�����i�������͂P�Q�T�����ł���B�j�A���c�菑�͂P�X�Q�W�N�ɂ͔�����������A�x���Ƃ����̂���܂łɂ͑����̍��Ƃ̍s�Ԃ̒��ɓ��c�菑�ɑ���@�I�m�M���m�F�����Ɏ���A�����ē��c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@����������Ɏ����Ă������̂ƔF�߂�̂������ł���B�����āA�O�L�F��̋����{�R�ɂ�钆���e�n�ɂ�����ە���̎���g�p�i�{���ې�j���W���l�[�u�E�K�X�c�菑�ɂ����w�ۊw�I�푈��i�̎g�p�x�ɓ����邱�Ƃ͖��炩�ł���B�v�i�������R�W�Łj�|�������B
�@���̂悤�ɁA���{�������ōs�����ە���̎���g�p�̓W���l�[�u�E�K�X�c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ���Ă��邱�Ƃ�F�߂��B
�@�@(2) ���{�̍ې��Q�ɑ��锅���ӔC
�@�������́u�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�̂悤�ȏ��Ȃ����������Đ������鍑�ۊ��K�@�ɂ��Q�G��i�̋֎~���w�[�O����K���Q�R���P���ɂ����w���ʃm��ȃe�胁�^���֎~�x�ɊY������Ɖ�����̂������ł���B���������āA�W���l�[�u�E�K�X�c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ��ە���̋֎~�Ɉᔽ�����ꍇ�ɂ��w�[�O������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC��������Ƃ����ׂ��ł���B�v�Əq�ׂāA���ɖ{���Ɋւ��āu�퍐�ɂ͖{���ې�Ɋւ��w�[�O������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă����Ɖ�����̂������ł���B�v�i�������R�X�Łj�ƔF�肵���B
�@���̂悤�ɁA���{�������ōې���s�������Ƃɂ��āA�ې��Q�҂������Q������Ƃ����n�[�O�������R������e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC����T�i�l�ɐ����������Ƃ�F�߂��B
��R�@�{���ې�̉��Q�s�ׂ̎c�s���A��Q�̏d�含�ɂ���
�@�������́A��L�Q�A�R�̂Ƃ���{���ې�̎�����F�肵�A���A�ې킪���ۖ@�Ɉᔽ���A��T�i�l�̍��ƐӔC���������Ă������Ƃ�F�߂Ȃ���A�ŏI�I�ɂ͍T�i�l��̎Ӎ߂Ɣ����̐�����S�ʓI�ɑނ����B
�@���̌������̏d��Ȍ�����������ہA���̑O��ƂȂ�{���ې�̉��Q�s�ׂ̎c�s���A��Q�̏d�含�ɂ��āA���R��P�W�������ʑ�P����U�͋y�ё�Q����V�͂ŏڏq�������A�ȉ��S�A�T�Ŏw�E�������B
�@�P �ې�́A�z���R�[�X�g�ɔ䂷�ׂ��c�s�Ŕ�l���I�Ȕƍߍs��
(1) �����{�R�V�R�P�����Ȃǂ̍ې핔���������e�n�ōs�����ې�́A�����Đ푈�ƍ߂Ƃ������t�����ł͌����s�����Ȃ��A���ɂ����܂��������̏��ƂƂ����ׂ����̂ł������B
�@�ې�̂��߂ɌR����W�߂Ĕ閧������n��A���̍ې핔���̒��Ńy�X�g�ۂY���A�l���y�X�g�Ɋ��������A�y�X�g�Ɋ������������̔a���ʐ��Y���A����l�̏Z�ފX�⑺�ɓ�������Ƃ����A����퓬�Ƃ͑S�����W�̈�ʏZ�����y�X�g��R�����Ȃǂ̉u�a�Ɋ��������A���̒n���тɉu�a��嗬�s������Ƃ����s�ׂ́A�ە���J���̂��߂̐l�̎������܂߁A��ƐX�����ꂪ���t�����Ƃ���A�u�����̖O�H�v��f�i�Ƃ�����B
�@���炩�ɐ푈�Ƃ������{�������ōs�����ې�̎c�s���A��l���I�͐��E�j�I�ɂ݂ăh�C�c�E�i�`�X���s�����z���R�[�X�g�ɂ��䂷�ׂ��A�c�s�Ŕ�l���I�Ȃ��̂ł������B
�@�T�^�I�ȃW�F�m�T�C�h�ł���A�����̈�ʏZ���ɑ����ʖ����ʋs�E�s�ׂł���B�{���I�Ɍ����Ȃ�A�܂��ɍې�́A�i�`�X���Ƃ����A�E�V�����B�b�c���ł̓ŃK�X���ɂ�郆�_���l�E�|�[�����h�l�Ȃǂ̖������E�I�ȑ�ʋs�E�s�ׂƉ���قȂ�Ȃ��A�l�ގj��ł��c�s�ȍs�ׂȂ̂ł���B
(2) �ې핔���̖{���́A���{�鍑��`�̒������k�n��̐A���n�x�z�i���S�u���B���v�̂ł����グ�j�̎c�s���ƒ����N���푈�̖������ʓI�����ɂ���B�_�n�����D���čە��퐻���{�݂����݂��A�_����J�H�Ƃ��ċ����J�������A�X�ɂ͍R���h���܂ޒ����l����ʊč��ɓ������Đ��̎����̍ޗ��Ƃ����B�����͐A���n�x�z�̌̂ɉ\�������B�܂���ʎE�C����}�����ې�̖������ʐ��͖����ł���B
�@���́A���{���ې핔���̎��������܂��ɔF�߂Ȃ����@�́A�����A���n�x�z�̎c�s�Ȏ��Ԃ��\�I����邱�Ƃւ̋���A����Ƃ��Ē����ɑ��Ė������E���܂ޖ������ʐ�����Ƃ��Ă������Ƃ��\�I����邱�Ƃւ̋���ɂ������̂ł���B
(3) �V�R�P�����́A�ې�ɂ���āA���炩�ɌR���I���_�ł��Ȃ��A�܂��R���I�ڕW�������Ȃ������̕��ʂ̈�n���s�s��_���ɑ��āA�퓬�@����y�X�g�����a�𓊉������߁A���邢�͒n��Ŗd���I�Ȏ�����������ăR�����ۓ���̐H����H�ׂ�����Ȃǂ��āA�����ɕ�炷�����̖��O���ʂɋs�E�����̂ł������B
�@���̂悤�ȂV�R�P�����Ȃǂ̓��{�R�̍ې핔�����s�����ې�̎c�s���́A�i�`�X�̃A�E�V�����B�b�c�̎c�s���ɗD��Ƃ����Ȃ��A���ɋ���ׂ��c�s�s�ׂƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̂悤�ȏW�c�E�Q�s�ׂ́A�������獑�ۖ@��̐l���ɑ���߂ɊY�����A�܂����݂̍��ۖ@��̊T�O�ł̓W�F�m�T�C�h�ɂ��Y��������̂ł���B
�@�ە���́A���ʂ��g�p����Ă��傫�Ȕj��͂�L������ݗ͂������Ă���B���̔j���p�͒����Ԃɂ킽��A��x�����܂��Ă��A�ĂюO�x���s���邱�Ƃ�����B
�@�ۂ̑�ʔ|�{�ɂ��ە���́A��ꎟ���E��풆�A�h�C�c�ŊJ�������肳�ꂽ���A�ە���̖{�i�I�ȊJ���A�����A����g�p���s�����͓̂��{�R�̂V�R�P�����Ȃǂ̍ې핔�����͂��߂Ăł���B
�@�ە���́A���̊J���ߒ��ɂ����ĕs��I�Ɏc�s�Ȑ��̎���������B
(4) �V�R�P�����́A�P�X�R�R�N�A���{���A���n�x�z���s���Ă������u���B���v�n���r���s�x�O�̕��[�ɐڎ������U�P�O�w�N�^�[���̍L��ȓy�n�ɖ{����u���A�e��ۂ̔|�{�E�������A�a�E�������i�۔}�́j�̎��玺�A����č��A��p��s��A�h�ɓ��̑�K�͎{�݂����݂��āA�`�t�X�A�R�����A�ԗ��A�y�X�g�A�Y�s�A�����Ȃǂ̌����E�|�{���s�����B���̍ہA�펞�Q�O�O�l����S�O�O�l�́u�}���^�v���Ȃ킿�ߗ��̎����ɗp���đO�L�e��̍ۂ�|�{���A�ە�����J���E���������̂ł������B
�@�ې킪�����炷��Q�̓����́A���̖����ʐ��ƒv�����̍����ɂ���B�V�R�P�����̗p�����ە���́A�v�����̍����y�X�g�ۂ܂��̓R�����ۂł���B�����̍ۂ������N�����a�C�͌������A�����ԗ��s����B��Ƒ��A��n��̑唼���S�ł���Ⴊ�����B
����ɍې�̂����炷��Q�̓����́A�`�d�ɂ���Q�͈͂��ǂ�ǂ�g����Ƃ������Ƃɂ���B��Q�͈͂́A�l��l�̔a������a���ۂ̓`�d�ɂ��A���ڂ̍U���Ώےn��ɂƂǂ܂炸�A���ӂ̒n��ɂǂ�ǂ�g�����Ă����B
�@���{�R�́A���[�Ȃǂōs��ꂽ��ʂ̕ߗ����g�����l�̎����ɂ���ĊJ�����ꂽ�ە�����A�푈�j�㏉�߂āA��K�͂Ɏ���g�p�����̂ł��邪�A���̎����̎c�s���ƁA�ې�̎c�s���́A�\����̂��Ȃ����̂ł���B
�@�Q �{���ې�ɂ���Q�̏d�含
�@�@(1) �ې�ɂ��s�s�A���ł̉u�a�̗��s
�@���{�R�́A�ې�̎��s�ŁA���̈ڐA�ɂ��Ő������߂��y�X�g�ہA�R�����ۓ����ʂɐ�������Ƃ��Đ��Y�E�g�p���A�����S�y�̑���s�s�̏Z���ԂɃy�X�g�Ȃǂ̉u�a�𗬍s�������B�_���͔�퓬������Z���̑�ʋs�E�ɂ������B���̂悤�ȓ��{�R�ɂ��ې�́A�������O�ɑ���O�ꂵ���������ʂƔr�O��`�Ɋ�Â����̂ł������B
�@���{�R�ɂ��{���ې킪�s���Ă���Œ��A�P�X�S�Q�N�R���Ɋ֓��R�R��E�q���R�㒆���́A�u�ې�ɂ��āv�Ƃ����u���̒��ŁA�u�S�ʓI�ɂ͕�⋂ɗ���ł��邱�ƂɂȂ�s�s���U�����āA�s�s���Ђǂ��ڂɑ��킷�B����͏��������������ł���܂��B�R���W�̂��̂ɂ́A���ڂ��Ȃ��ő傫�ȓs�s�ɓ`���a�𗬍s�炵�Ă䂭�v�u�ې�̑_�����̈�́A��������������߂Đ��_��ɍ��������ƂɂȂ����ƌ����悤�ȊϔO��G�ɗ^���邱�ƂŁA�傫�ȓs�s������ƂЂǂ��ڂɑ��킷�Ƃ������Ƃ������ł���܂��v�Əq�ׂĂ���B
�@�q�͂��̑��ɍU���ΏۂƂ��āA�R���A�����̕�⋕⋋�n�A�R���v�ǁA���������n�A�R���H��A�q�{��_�Y���������������Ă���B
�@�ە���́A�l�ԁA�ƒ{�A�_�Y���ȂǁA����������̂������E������A�ł��c�s�ȑ�ʎE�C����ł���B���{�R�́A�����ʂɑ�ʂ̏Z�����s�E����A�l�ގj��A�ł��c�s�Ŕڗ�ȃW�F�m�T�C�h�𒆍����O�ɑ��čs�����̂ł���B
(2) ��Q�҂͈�ʏZ���ł���
�@�T�i�l��̓��e�����́A�s�s���邢�͔_���̏Z���ł��������A�V�R�P�����̍ە���ɂ��A�y�X�g�A�R�����ȂǂɊ������A���邢�͉����n�悩��̓`���ɂ�芴���������Ƃɂ��A�������ꂵ�㎀�S�����B���邢�͍T�i�l�玩�g���늳�����B
�@�܂��A�y�X�g���s�n��́A�J�g�Ȃǂ̗�ɖ��炩�Ȃ悤�ɁA�u��Ƃ��ĕ�������O�o�֎~�ƂȂ�A�P�l�ł��a�l���o��ƉƑ��S�����u���̑ΏۂƂȂ����B��������u�����ɓ���Ɛ��҂���]�݂�₽�������R�ł������B�늳����ƈ�t���狰��Ď��Â����ۂ����B���҂͘e�̉���l�a���̃����p�B�����オ�荂�M�Ɗ����ɋꂵ�݂ʂ��ĒZ���Ԃ̂����Ɏ��S�����B
�@����ɁA�ނ�̉Ɖ��́A�J�g�A�`�G�A���R���̗�̂悤�ɁA�h�u�̂��ߏ����E�j�ꂽ�B
�@�܂��ې핔���́A����A��Q�n��Ɂu�h�u�v�̖��ڂœ��荞�݁A���̉u�a�ɋꂵ�ޏZ���̉�U���āA�ې�̌��ʂ��m���߂�Ȃǂ����B
�@���̂悤�ɁA�ې�̔�Q�������������O�́A�M��ɐs�����������ꂵ�݂����̂ł���B
(3) �����v�����Ƒl�A�a�A�l����Ă̋���������
�@�ە���Ɏg�p�����y�X�g�ۂ́A�����o�H�ɂ���āA�B�y�X�g��x�y�X�g�Ȃǂ̏Ǐ��悷��A���ɋ���ȕa���̂ł���B
�@�B�y�X�g�́A�a�Ȃǂ�ʂ��ċۂ��l�̂ɓ��芴������B�M�ƈ��������ċ��E��Ԃ�悷��B�����ĉ��ǐ��̂͂���̂������p�B�ɂł���B�Ƃ��ɑ��ɋۂ����邱�Ƃ������̂ől�������̃����p�B�ɂł���B
�@�x�y�X�g�́A�A���`���ŋۂ��ċz�튯�ɓ����āA�x���Ɏ����Ǐ���N�����B�A���\ႂɑ�ʂ̋ۂ�����B
�@�y�X�g�ɂ�����ƁA�Q�A�R���Ŏ��S����B�o�����Ђǂ��A���͍̂��F��悷��̂ō����a�Ƃ�����B�ǂ�ǂ�`�����A�`�����n�܂�ƁA�����o�ł���̂�����a�C�ł���B�`���a�̒��ł͎��S�����ł��傫���B
�R�����́A�����튯��`���a�C�ł���B�����f�E�����̔��Ɍ��������̂ŁA���ɁA�������A���E�������N�����Ƃ���������������B�R�����ۂ́A����H��������ɓ����Ă���B�Ƃ��ɋ���ނ���������ē`�d����ꍇ�������B
�@�R���������S�������������`���͂����ɋ����a�C�ł���B
(4) ���ÂȂǖh����@�̍��
�ە���́A���e�̂悤�ɁA���ǂ��ɉ����g�p���ꂽ���Ƃ������Ƃ������ɂ͔������Ȃ��B�a�C�����s���Ă��A�ە���ɂ����̂��ۂ��������ɔ�������킯�ł͂Ȃ��B
�@�������A�ە���ɗp����ꂽ�a���ۂ́A�l�Ɋ������Ă��������Ԃ����邽�߁A�����������x���B�a�C���������Ă��A�̍������邽�߁A�g�p���ꂽ�a���ۂ̓��肪�e�Ղł͂Ȃ��B
�@�J�g�ɂ����ẮA�P�X�S�O�N�P�O���Q�V���A���{�R�̔�s�@����ʂ̏������┞���𓊉�������A�s���ł���܂Ō������Ƃ��Ȃ��^���ԂȔa����ʂɔ�ђ��˂Ă���̂��������ꂽ�B�P�O���R�O�����߂Ă̎��҂��o����A���҂����X�ƕa�@�ɋ삯�������A�ŏ��A�����}�����A�������ƌ�f���ꂽ�B
�@�ň��̓`���a�ł���y�X�g�̊m���Ȑf�f�Ƃ��̌��\�́A�����Ȃ��҂����̏d�含��F�����Ă��邪�䂦�ɁA�T�d�̂����ɂ��T�d�������B�ŏ��Ƀy�X�g�ۂ��������ꂽ�̂́A�P�P���Q���ɂȂ��Ă���ł������B
�@�����A�����{�Ɨ\�h�ψ���́A�����n��̕��������肵�����A����قnj��d�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����n�悩��͓��S�҂����o�����B���̌���ō�Ƃ��s��ꂽ���A�P�P�����ɉ����n��̌����͏ċp���ꂽ�B
�Ⴆ�y�X�g�ۂ��������ꂽ�Ƃ��Ă��A������h�����Ƃ͓���B�y�X�g�̔�Q�͒��ڂɎT�z���ꂽ�n��Ɍ��肳�ꂸ�A�l��l��}�̂Ƃ��Ċe�n�Ɋg�������B
�@�Ⴆ�A�T�i�l��̂����`�G�A���z�A���R���A�����B�̃y�X�g��Q�́A�ˏB�ɓ������ꂽ�y�X�g��Q���g�債�����̂ł���A�܂��A�퓿�̏ꍇ���A�s�X�n����A���Ӕ_���n��փy�X�g���s�͓`�d���Ă���B
�������A�y�X�g�ۂ́A�P��a�C�̗��s�����ɂȂ��Ă��A���������l������ƍė��s����B�l�ɕt�������a�̍s�����鎞���ɂȂ�ƁA�ēx�A���s���邱�ƂɂȂ�B���������l��o�ł���͍̂���ŁA���\�N�ƒ���������B
�@ (5) ���R���̔j��
���̂悤�ɕa�C����������ƁA���Â�����ŁA���������l���u�����āA�������g���Ȃ��悤�ɂ�����A�Ɖ��A�����ނ��ċp���邱�Ƃ��A�őP�̖h����@�ɂȂ�B
�@�������A������h������A�a���ۂ����S�ɖo�ł��邱�Ƃ͕s�\�ŁA��x��Q�ɂ����ƁA���̉e���͒����Ԃɂ킽���āA�l�ԎЉ�̂����鑤�ʂɋy�ԁB
�@�ې�ɂ���Q�́A�l�Ԃ̖���D���A�ߐH�Z�̊����������A����ɁA�l�Ԃ������邽�߂̏����ł���L�͂Ȓn��̎��R���̉����ƂȂ��āA�n��Z���ɉe����^����B
�@ (6) �n��Љ��j��
�@�����������j��ƂƂ��ɁA�ې�̔�Q�́A�l�Ԃ̎Љ�I�W�̔j��ƂȂ��ĉe����^����B�u�����ꂽ��A�������ꂽ�n��̐l�X�́A�Ⴆ�a�C�����������Ƃ��Ă������̎�i��D����B�܂��A�`���a�����s�����n��́A�����Ԃɂ킽���āA�s���Ŋ댯�Ȓn��Ƃ݂Ȃ���āA���ʂ���錴���ɂȂ�B
�@�`���a�́A�l�X���u��������a�J�������肷�邱�Ƃɂ���āA�l�Ɛl�̌𗬂���������A�����c�����l�̐��������j�Ă����̂ł���B
�@�ې�̎c�s���́A�`���a�ɂ���Đl�X���E�����A�p�j�b�N��Ԃɗ��Ƃ����߂�Ƃ��������łȂ��A�����Ԃɂ킽���āA�n��Љ�����ꂩ��j�Ă����Ƃ����_�ɂ���B�T�i�l��A�ې�̔�Q�n�Z���ɂƂ��āA�ې�ɂ���Q�́A�푈��ʂɂ���Q�ɂ͉����ł��Ȃ����̂ł���B�T�i�l���Q�҂ɂƂ��āA���\�N�o�Ƃ��ƁA���̎���Q�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���B
�@ (7) �ȏ�̒ʂ�A���{�R�ɂ��ە�����g�����W�F�m�T�C�h�̔�Q�́A�i�`�X�̃A�E�V���r�b�c�ł̎c�s���Ɠ��߂ł���A�ߋ��ɗႪ�Ȃ��قǂ̎c�s�Ȃ��̂ł������B
�@�R�@�ȏ�̂悤�ɁA�{���ې킪�l�ގj��A�ł��c�s�Ŕڗ�ȃW�F�m�T�C�h�ł���A�T�i�l���Q�҂̔�����r��Ȕ�Q�܂��āA���������ې�̎�����F�肵�A����T�i�l�̍��ƐӔC��F�߂Ȃ���A�T�i�l��̐�����ނ����@���_�ɂ��āA���͈ȉ��ŁA�����A���_��������B

�
��Q�́@���{���@�Ɋ�Â��Ӎߋy�ё��Q��������
��P�@�{���ې�́A�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�i�P�X�Q�T�N�j����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ���A���@�V�O�X���Ȃ����V�P�P���܂��͂V�P�T���̕s�@�s�ׂɊY������
�@�P�@��
�@���{���@�V�O�X���́A�̈ӂ܂��͉ߎ��ɂ�葼�l�̌������i��@�Ɂj�N�Q�����҂͑��Q�����ӔC�����Ƃ��߂Ă��邪�A�{���ې킱���A���̕s�@�s�ׂ��̂��̂ł���B
�@�Q�@�s�@�s�ׂ̎��
�@�{���ɂ����钼�ڂ̈�@�s�ׂ́A�P�X�S�O�N����P�X�S�Q�N�ɂ����ẮA��T�i�l�ɂ�钆���嗤�ɂ�����ې�̎��s�ł��邪�A���̈�@�s�ׂ́A��T�i�l�̌R�������̎w���n���ɂ��������Đ��s�����푈�s�ׂł���A��T�i�l���̂��̂̍s�����s�ׂł���B
�@����āA�{���ɂ������@�s�ׂ̎�̂́A��T�i�l�ł���B
�@���ɁA��@�s�ׂ̎�̂������{�R�\�����Ƃ��Ă��A��T�i�l�͎g�p�ҐӔC���B
�@�R�@�s�@�s�גn
�@�{���ې�̎��s�́A�V�c�̗����̂��ƂɁA���R�������w�����A���R�Q�d�{���y�ї��R�Ȃ̍��v��w���i�l�ނ̔h���A�\�Z�̎x�o���܂ށj�ɂ���Ď��s���ꂽ�s�ׂł���B�܂��ې�̎��s�̂��߂̌����A�J���A���퐻���́A�������n�ɂ�����V�R�P�������ƂƂ��ɁA���{�{�y�ɂ����Ă͗��R�R��w�Z�����ڂȘA�g���Ƃ�Ȃ��珀���������̂ł���B
�@���̂悤�ɖ{���ې�ɂ�������Q�s�ׂ́A���{�ɂ�������v��̗��āA�l�ނ̔h���A�\�Z�̎x�o�A�ې�̌����A�J���y�э��w���ƒ������n�ɂ�����ې�̌����A�J���A���s����̂ƂȂ����s�ׂł���A�s�@�s�ׂ̌������鎖�������������n�́A���̒��S�����{�ł���ƌ�����B
�S�@��@��
�@�O�͂ŏq�ׂ��Ƃ���A�������́A�{���ې킪�W���l�[�u�E�K�X�c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ���Ă��邱�Ƃ�F�肵�A���A��T�i�l�ɁA�ې��Q�҂������Q������Ƃ����n�[�O�������R������e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă������Ƃ�F�肵���B
�@�����ɐ푈�s�ׂł��낤�ƁA�y�X�g�ۓ��̕a���ۂ���U�z���A���邢�͒n�ォ���ː����ɍ������A�G���Z���̖����ʑ�ʎE�C��_�����s�ׂ́A���łɓ�������֎~����A�����������͂��͂Ȃ��A���̍s�ׂ̐ӔC��Ƃ�邢���Ȃ�@�������݂��Ȃ��B
�@���̂悤�ɁA�{���ې�̈�@���͖����ł���B
�T�@��Q�̔����ƈ��ʊW
�@��T�i�l�́A��L�ې�̌����A�J���A���s�ɂ���āA�T�i�l��̐e���ł��錴�����ʎ��R�u������̎咣�v�̕ʎ��u�����y�ю��S�e���v�́u���S�ҁv���L�ڂ̔�Q�҂ɑ�������D���A�܂���Q�Җ{�l�ł���T�i�l�V���i�T�i�l�ԍ��P�R�X�A�P�S�T�Ȃ����P�S�W�A�P�T�S�A�P�V�Q�j�̐g�̂�N�Q����Ȃǂ��āA���l�̐����A�g�́A���Y����N�Q�����B
�@��L�̍T�i�l��܂��͍T�i�l��̐e�����A�{���ې�ɂ���Q�������Ƃ͂��łɌ��������F�肵���Ƃ���ł���A��Q�̎����A�s�ׂƔ�Q�̈��ʊW�͖����ł���B
�@�U�@���Q��������������юӍߐ������̐���
�@�ȏ�ɂ��A�T�i�l��́A��T�i�l�ɑ��āA���@�V�O�X���Ȃ����V�P�P���܂��͂V�P�T���Ɋ�Â��đ��Q�����������A�y�тV�Q�R���Ɋ�Â��ĎӍߐ�������L����B
�@�ȉ��A�T�i�l��́A�@�{���ې�ɂ́u���Ɩ����ӂ̖@���v���K�p����Ȃ����ƁA�A�����E���˂��K�p����Ȃ����ƁA�B�������������y�ѓ������a���Ŕ�Q�Ҍl�̔�������������������Ă��Ȃ����Ƃɂ��ڏq���A�������̌����w�E����B
��Q�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v�́A�{���ې�ɂ͓K�p����Ȃ�
�@�P�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v�̊m���͔F�߂��Ȃ�
�@(1)�@�������̌��
�@�������́A�u��O�ɂ����ẮA�����͂̍s�g�ɂ�鎄�l�̑��Q�ɂ��ẮA���̑��Q�����ӔC��F�߂�@����̍������Ȃ��A���̂��Ƃ͌����͍s�g�ɂ��Ă̍��Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ƃ�����{�I�@����Ɋ�Â����̂ł���������A�����͍s�g����@�ł����Ă��퍐�͂���ɂ�鑹�Q�̔����ӔC��Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B������̎咣����{���ې���A���Ɣ����@����O�̔퍐�̌��͓I�s�ׂł��邩��A�����̖@�߂ɏ]���āA����ɂ�閯�@�V�O�X���A�V�P�O���A�V�P�P���Ɋ�Â����Q�����ӔC�͔ے肹����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B�v�i�������Q�S�Łj�Ɣ�������B
�@�������A���Ɩ����ӂ̖@���́A�@���̋K��ł͂Ȃ����A�m��I�Ȗ@���ł͂Ȃ��B
�@���̓_�A�������́A�u��O�̑�R�@����́A�͓I��p�ɂ��Ă͖��@�̓K�p�ɂ�荑�̑��Q�����ӔC��F�߂Ă������A�����͂̍s�g�i���͓I��p�j�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă͈�т��č��̔����ӔC��ے肵�Ă����v�i�������Q�Q�Łj�ƁA���ᗝ�_�Ƃ��č��Ɩ����ӂ��������Ă������̂悤�ɔ�������B
�@�������A����͌ʂ̎���ɑ��������߂ɉ߂��Ȃ��B���������A���ƐӔC���m�肵������̒��ŁA�{���ې�̂悤�ȍ��ۖ@�ᔽ�̌��͍�p�Ɋւ���ʎ���͑��݂��Ȃ��̂ł���B
�@���Ɩ����ӂ̍����́A�������@�U�P���Ō��͍s���ɂ��Ă͎i�@�ٔ����̊NJ���ے肵�A�s���ٔ��@�P�U���ő��Q�����������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��B
�@�������A���@�̋K�蒆�ɁA���̔����ӔC��ے肵���K��͂ǂ��ɂ��Ȃ����A����@��́A���Ɩ����ӂ̖@���L���������@�i����@�j�͑��݂��Ă��Ȃ��B�����āA���ۂɂ��A���̔����ӔC�ɂ��Ďi�@�ٔ����̊NJ����͔ے肳��Ȃ������B��O�ɂ����Ă����Ɩ����ӂ��m�肵���@���Ƃ��Đ������Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@(2)�@���ᗝ�_�Ƃ��āA���Ɩ����ӂ̖@���̊m���͔F�߂��Ȃ�
�A �s����̕s�@�s�אӔC�Ɋւ���ٔ���́A�����Q�Q�N�ɖ������@�����肳��Ă���A�ٔ����̔����ςݏd�˂钆�ŁA�l�X�ȕ���ō��y�ь����c�̂̑��Q�����ӔC��F�߂Ă����B
�@�ȉ��A�ٔ���̊T�v���q�ׂ邪�A����͍s����̕s�@�s�אӔC��F�߂镪����g�債�A�����͂̍s�g�i���͓I��p�j�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă��A���@��K�p���đ��Q�����ӔC��F�߂锻��������A���y�ь����c�̂̔����ӔC��ے肷�鍑�Ɩ����ӂ̖@�����m������Ă����Ƃ͓��ꌾ���Ȃ��B
�@�܂����������A�s����̕s�@�s�אӔC��F�߂Ȃ�����ɂ����āA���Ɩ����ӂ̖@���ő��Q������ے肷�鍪�����B���ł���B���Ɩ����ӂ̖@���́A�����͂̍s�g���V�c�̎匠�̍s�g�Ő_���ɂ��ĐN���ׂ��炸�Ƃ����Ƃ��납��_���Â���ꂽ���ߗ��_�̈�ɂ������A���̐������A�������͌��������������B
�@�ٔ���ɂ��Ă̏ڍׂ́A�����̔��ᕪ�̘͂_���ł���u�����茩����s����̕s�@�s�אӔC�v�i���a�P�Q�N���\�B�c����Y�w�s����̑��Q�����y�ё����⏞�x�Q�X�ŁA���䏑�X�j�y�сu�s����̑��Q�����ӔC�v�i���a�Q�P�N���\�B�O�����W�V�Łj���Q�Ƃ��ꂽ���B
�C�@����������A�����̎��o�ϓI�����Ɋւ��锅���ӔC��F�߂Ă���
�@�������@������̑����i�K����A���̎��o�ϓI�����ł���S���A�d�ԁA�����Ԃɂ��ẮA�c�����ƂƂ��ĂƂ炦�A���܂��͌����c�̂̕s�@�s�אӔC��F�߂Ă����B
�@�S���H�������r�Ɋ�Â��ӔC�ɂ��ẮA��R�@�����R�P�N�T���Q�V�������i���^�S�S�T���X�P�Łj���ŁA�����F�߂��Ă���B
�͐���C�H���i��R�@�����Q�X�N�S���R�O�������A���^�Q�S�S���P�P�V�Łj�A���H���C�H���i��R�@�����S�O�N�Q���Q�Q�������A���^�P�R���P�S�W�Łj�ɂ��ẮA���������̗��v�ƈ��S�̂��߂ɂ��錠�͍s�ׂł��邩��s�@�s�ׂɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă������A�K��������v���Ă����킯�ł͂Ȃ��B
�@�����g����詓���݂����ۂɁA���̍H�������S�ł͂Ȃ��������ߎ��@�{���̒n�Ղ��T�����Q��^�������Ăɂ����Q�����ӔC��F�߂��i��R�@�����R�X�N�V���X�������A���^�P�Q�S�P�O�X�U�Łj�B
�E�@�吳�T�N�����ȍ~�A�����̎{�݂̐ݒu�Ǘ����Ɋւ��锅���ӔC��F�߂�
�@�吳�T�N�A�����s�����w�Z�̕��������V���~�_�ŗV�Y���̎������ė����Ď��S�������ƂɊւ��鏬�w�Z�̊Ǘ���p�ɂ��āA��R�@�����i��R�@�吳�T�N�U���P�������A���^�P�O�W�W�Łj�́A�]���́u���@��̍s�ׁv�����͓I��p�Ɣ͓I��p�ɕ��ނ��A�͓I��p�ɂ͖��@��ސ��K�p����Ƃ����V�����������������B
�@���̌�A�������s�̐����H���Ɋւ����R�@�吳�V�N�U���Q�X�������i���^�P�R�O�U�Łj�A�������s�̉������ݔ������r�Ɋ�Â����Q�Ɋւ����R�@�吳�P�R�N�U���P�X�������i���W�R���Q�X�T�Łj�A���̒z�`�H���ɂ����Đl�H�ɋD�D�����グ�Ĕj�v���鎖���Ɋւ����R�@�吳�V�N�P�O���Q�T�������i���^�Q�O�U�Q�Łj�A�Ŋ֑q�ɂ̐ݒu�����r�ɂ�鎀�S�����Ɋւ��铌���T�i�@�吳�T�N�Q���Q�W�������i�]�_�U�����S�U�V�Łj�A�����g���̟��r���̐ݔ����l�̐�������N�Q���������Ɋւ����R�@�吳�P�S�N�P�Q���P�P�������i���W�S���V�O�U�Łj�́A�����͌����c�̂ɑ��锅���ӔC���m�肵���B
�@�����̔���̐ςݏd�˂ɂ��A���̍H�앨�̐ݒu�܂��͕ۑ������r�Ɋ�Â����Q�ɂ��ẮA��R�@�͖��@�̔����ӔC���m�肷��悤�ɂȂ�B
�G�@�吳�����珺�a�̏��߁A�R�{�݁A�w�Z���Ɋւ��锅���܂��͔����ӔC����F�߂�
�@�R�͂̏C���H�����ɐE�H�̒ė��H���ɂ��H���ē҂̏d��ȉߎ��𗝗R�Ƃ��Ĉ⑰�����ɑ��đ��Q�����𐿋����������Ɋւ���L���n�ٌ��x���吳�P�R�N�U���T�������i�V���Q�Q�W�Q���j�A�����Ђ̖��S�����n�̏��w�Z�̃X�P�[�g�w���̉ߎ��ɂ�莀�S���������ɂ����S�ɑ��đ��Q�����𐿋������֓����@�㍐�����a�V�N�V���Q�O�������i�V���R�T�R�X���j�́A���S�̎g�p�ҐӔC��F�߂��B
�@���̂悤�ɁA�R�{�R�͏C���H���ēҁA���w�Z�̎w���ғ��̎g�p�ҐӔC��F�߂��B
�@�܂��A���R���a���×{���p�w��H���ɂ�艷��̗��p���N�Q���ꂽ���Ƃ𗝗R�ɖW�Q�r����������\�����F�e����A�����A�w��H���͍��Ƃ̌��@�I�s�ׂł���A������̌����s�g�ł���s�@�s�ׂ��\�����Ȃ��Ƃ��ď㍐���������ɂ��A��R�@���a�V�N�W���P�O�������i�V���R�S�T�R���j�́A�u��@�Ȃ�s����p�ɂ���O�҂̌�����N�Q������ꍇ�Ȃ�Ƃɂ��قȂ鏊�Ȃ��B�W���s�@�s�ׂ̐ӔC�͑��̍s�҂̉��l�Ȃ��ɂ��V����ʂ�������ȂĂȂ�v�Ɣ������㍐��r�˂����B
�@����́A�s�@�s�҂����Ƃł��낤�����l�ł��낤����ʂ���Ȃ��Ƃ��āA���@�̕s�@�s�אӔC��F�ߖW�Q�r������������F�e�������̂ł���B
�@�R�{�݁A�w�Z���Ɋւ���s�ׂ́A�����͌����͂̍s�g�i���͓I��p�j�Ƃ�������̂ł���A�����͂̍s�g�i���͓I��p�j�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă��A���@��K�p���đ��Q�����ӔC��F�߂�悤�ɂȂ����B
�I�@���a�P�O�N��A���͓I��p�Ɋւ��锅���ӔC��F�߂�
�@���a�P�O�N��ɂȂ�ƁA�������̌����͍s�g�ł���o�[�����Ɋւ��锅���ӔC��F�߂锻�����o�Ă���B
�@���Ȃ킿�A�����������������g���̋��K�o�[�������A�����Ȃ����Ďؗp�؏����쐬����������̂���s�ɑ��Q��^���������Ɋւ����R�@���a�P�P�N�S���P�T�������i�V���R�X�V�X���j�A���������������`�̎ؗp�؏������U�����ċ��K�����悵�������Ɋւ����R�@���a�P�Q�N�P�O���T�������i�S�W�S�S�P�X���T�Łj�A�����̂Ȃ����s���ؓ��Ɋւ����R�@���a�P�T�N�Q���Q�V�������i���W�P�X���U���S�S�P�Łj�́A�����g���܂��͒����̔����ӔC��F�߂��B
�J ���a�P�T�N�y�тP�U�N�A��Z�������^�N�V�[����������R�@����
�@���@�����������ŁA�����͂̍s�g�i���͓I��p�j���̂��̂ł��钥�őؔ[�����ɂ��Ă��A��R�@�����́A��Z�������^�N�V�[���������ɂ����đ��Q�����ӔC��F�߂Ă���B
�@�ؔ[�����Ƃ��Ď����Ԃ����������l�ŏ��������Ƃ���A���̎����Ԃ͑�O�҂̎����Ԃł��葹�Q��^�����Ƃ��āA�����Ԃ̏��L�҂������s�y�ђS�������A��������퍐�ɂ��đ��Q�����𐿋����������ɂ��A���R�ٔ����́A�u���őؔ[���������@��̍����s�ׂȂ�ȏ㖯�@�s�@�s�ׂ̋K��̓K�p�Ȃ��A������������s�ׂɈ��鑹�Q�ɂ����Y�����ɔ����ӔC�S�����߂���@�K�Ȃ��������āv�����������Ƃ����B
�@�������A���a�P�T�N�P���A��R�@�́A�u�������тɌ����͑ؔ[�ŋ��̒����ɕK�v�Ȃ���x�ɉ��ĔV�����{���ׂ��A���ʂ̗��R�Ȃ����đ��̕K�v�ȏ�ɏo�Œ��������z�̍��Y�����������тɌ������邪�@���́A�k�ɑؔ[�҂ɋ�ɂ�^���ׂ߂̍s�ׂƖڂ���̊O�Ȃ��A�ؔ[�����Ƃ��ĔV�����e���ׂ����R�������B�̂ɒ����������ؔ[�����̍۔V���̍s�ׂɏo�ł���Ƃ��A���͑ؔ[�����Ȃ�ǂ����͐E�����p�ɂ��ĔJ��E���s�ׂɔ���̂ƈ����ׂ��A�]���ĕs�@�s��̐ӔC��Ƃꂴ����́v�i��R�@���a�P�T�N�P���P�U�������A���W�P�X���P���Q�O�ŁB�����͈��p�ҁj�Ɣ������Ĕj�����߂̔����������B
�@����́A���͓I��p�ɂ��āA���Q�����ӔC��F�߂����̂ł���B
�@���@���߂��������R�ٔ����́A��R�@�̔���ɉ����Ĕ퍐�R���̐ӔC���m�肵���B���Ȃ킿�A�����ɑ��A�u���͑ؔ[�����Ȃ�����͕s�@�s�ׂƔF�ނ�ɖW���Ȃ��v�Ɣ������A�����s�y�ь������ɑ��A�����́u�{�s�ׂ͊O�`�㒬�őؔ[�����̌`���������Ĉׂ��ꂽ��݂̂Ȃ炸��ϓI�ɂ����Œ����̖ړI�����Ĉׂ��ꂽ�邪�̂ɁA�{�����Q�͖��@�V�P�T���ɏ������Ƃ̎��s�ɕt��O�҂ɉ������鑹�Q�ƈ����ɉ����W���Ȃ��v�i�����͈��p�ҁj�Ɣ������A���͓I��p�ɂ�����s�A�������̑��Q�����ӔC��F�߂��B
�@����ɑ��A�����s�́A�{���ؔ[�����͌��͓I�����s�ׂł���A����������s�ׂɑ��Ă͖��@�s�@�s�ז@�̋K��̓K�p���Ȃ����Ƃ͏]���̑�R�@����Ƃ���Ƃ���Ǝ咣���ď㍐�����B
�@���@��R�@�́A�����̏㍐�����p�������ӔC��F�߂����A���������A�����s�A�������s�i�̕�����j�����A�����s�A�������ɑ��锅�����������p�����B
�@���Ȃ킿�����́A�u�������͌��������Ɩ��͌����c�̂̋@�ւƂ��ĐE�������s����ɓ�����s�@�Ɏ��l�̌�����N�Q���V�ɑ��Q��ւ炵�߂���ꍇ�ɉ��āv�i��R�@���a�P�U�N�Q���Q�V�������A�喯�W�Q�O���Q���P�P�W�Łj�A�S�������ɂ͕s�@�s�אӔC���F�肳���Ƃ��āA�����̏㍐�����p�����Q������F�e�����B
�@����A�������́A�u�����ɕs�@�s��̐ӔC����ƂāA�����c�̂����Z���ɂ͕s�@�s��̐ӔC���邱�ƂȂ��v�Ɣ������A�����c�̂ɖ��@�V�P�T����K�p���Ȃ����R���q�ׂ邱�ƂȂ��A���������A�����s�y�ь������ɔs�i�𖽂���������j���������ɑ��錴�����������p�����B
�@���̂悤�ɁA���͓I��p�ɂ��Ċ����̔����ӔC��F�߂Ȃ���A�����c�̂ɂ͖��@��K�p���Ȃ������I���R�́A�����́u���̐E���s�ׂ��������Ɋ�Â����͍s���ɑ�������̂Ȃ�Ƃ��́A���Ɩ��͌����c�̂Ƃ��Ĕ�Q�҂ɑ����@�s�@�s��̐ӔC�����ƂȂ����̂Ɖ�������ׂ��炸�v�Əq�ׂ邾���ŋ�̓I�ɂ͖��炩�ɂ���Ȃ������B���̂悤�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���ő��Q������ے肷�锻���́A���̍������ɂ߂ĞB���ł���B
���@����ɑ��A��L���߂���R�@�����ɂ��A�w���̋����ᔻ���������B���Ȃ킿�A�O��j�́A�u���|�́c�c���̌��ʂ͕K��������X�̖@����������ނ���̂ł͂Ȃ��B�v�u�����̐N�Q����@�Ɉׂ��ꂽ�ꍇ�Ɏ��@�K��ɏ]���Č��@�l�ɑ��锅���������������Ƃ����͓I��p�̖{�����ǂꂾ���Q������̂ł��낤���v�u���͓I��p�Ɉ˂���@�l�̔����ӔC���|�͓I�Ȍ��s���̏ꍇ�Ƌ�ʂ��ā|���@�͈̔͂���r�˂��˂Ȃ�ʎ����I���R�͑����Ȃ��v�i���@���ጤ����w���ᖯ���@�i���a�P�U�N�x�j�x�R�V�Łj�Ɣᔻ�����B
�@���@���̂悤�ɁA���őؔ[�����Ƃ������͓I��p�ɂ��Ă��A���R�ٔ�������R�@�����ߌ���R�ٔ�������R�@�ƁA���@�l�̑��Q�����ӔC��F�߁A�܂��ے肷��ȂǁA����̎p���́A�u��т��č��̔����ӔC��ے�v���Ă���Ƃ͓��ꌾ���Ȃ��B�������A�ŏI�̑�R�@�����ɂ����Ă��A�����ɑ��鑹�Q�����ӔC�͔F�߂Ă���̂ł���B
�@�L�@�ȏ�̂Ƃ���A�������@���̔���́A����̏W�ς̒��ŁA�l�X�ȕ���
�ō��y�ь����c�̂̑��Q�����ӔC���g�債�Ă����̂ł���A���������q�ׂ�悤�ȁu��O�̑�R�@����́A�͓I��p�ɂ��Ă͖��@�̓K�p�ɂ�荑�̑��Q�����ӔC��F�߂Ă������A�����͂̍s�g�i���͓I��p�j�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ă͈�т��č��̔����ӔC��ے肵�Ă����B�v�i�������Q�R�Łj�Ƃ͑S�������Ȃ��̂ł���B
�@�ނ���A���͓I��p���܂߁A���Ɩ����ӂ̓K�p�̊�͞B���ł���A�����͂̍s�g�ɂ�鑹�Q�ɂ��Ė��m�Ȋ�������č��y�ь����c�̂̔����ӔC��ے肷�鍑�Ɩ����ӂ̖@�����m������Ă����Ƃ͓��ꌾ���Ȃ��ł������B
�@���Ɩ����ӂ̖@���́A�V�c�匠�̖������@���ł̈�@���߂ɂ����Ȃ��B������������́A���Ɩ����ӂ̖@���̍����m�Ɏ��������Ƃ͂Ȃ��A����ɂ��̐������A�������͑S�����������������B
�@(3)�@�����̊w���Ƃ��Ă����Ɩ����ӂ̖@���̊m���͔F�߂��Ȃ�
�@�@�A�@���Z���B�g��
�@��O�̊w���̏��݂�ƁA�s���̕s�@�s�אӔC�Ɋւ��āA���@�ł��閯�@�̓K�p���Ȃ��Ƃ����������̂��Ă��Ȃ������B
�@�����w�h�̔��Z���B�g�́A�����̌����~�ς��m�ۂ��邽�߂ɂ́A���@�̗̈���g�����悤�Ǝ咣���Ă����B
�@�吳�P�R�N���s�́w�s���@�B�v�x�ŁA�u���v�ׂ̈ɂ��鎖�Ƃɕt�Ă͌��v��̕K�v������x�ɉ��Ė��@�̓K�p��r������嫂��A�����Ƃ��s�@�s�ׂɊ���Q�����̖��Ɋւ��Ă͍��Ɩ��͌��@�l�̎��Ƃɕt�Ă��V�����l�̎��ƂƋ�ʂ��đ��̓K�p�̖@�����قɂ��ׂ����R�Ȃ��A�����̎��Ƃ̎{�s�Ɋւ��s�@�ɑ��l�ɑ��Q�����ւ���ꍇ�ɉ��Ă͍��Ɩ��͌��@�l�͓��R���@�Ɉ˂葹�Q�����̐ӂɔC���ׂ����̂Ȃ�v�i���Z���B�g�w�s���@�B�v�x�㊪�P�T�O�ŁA�L��t�B�����͈��p�ҁj�Əq�ׁA���Ƃ̎��Ƃɂ��Ă��A�o�ϓI�W�����Ƃ�����̂ɂ��āA���Q������F�߂邱�Ƃ��咣���Ă����B
�@�O�q���������s�V���~�_�����̑�R�@�吳�T�N�U���P�������́A���˂Ă���̖����w�h�̎咣���������ꂽ���̂ł������i�L���M���w�s���@�̗��j�I�W�J�x�L��t�P�P�S�Łj�B
�@�@�C �c����Y��
�@�c����Y�́A���a�W�N�ɁA���Ɣ����ӔC�ɂ��āA�u�҂ӂɁA�]���A���Ƃ̖��ɉ��Ė��͌����̗��v�̖��ɉ��āA�@���㍑�ƐӔC�ɕt�ē���̗��_�\����^�ւ�Ƃ���X���͈ꉞ���R���鏊�ł͂��炤�B�����Ȃ�����́A���Ǎ����S�̂̕��S�ɉ��ċ�̓I�̌l�̓��ʂ̋]�������ӂׂ����A����Ƃ��l�̓��ʂ̋]���������S�̗̂��v�ׂ̈߂ɁA�߂ނ���]���Ƃ��ĔV���Î��ނׂ����̑I���̖��ł���A���̉��ꂪ��萳�`�Ȃ邩�̗��v�t�ʂ̖��ɋA���邱�Ƃ��l�ւ˂Ȃ�ʂ̂ł���B�v�u���̑��Q�������͂̍�p�Ɋ���̂Ȃ�Ƃ��闝�R�݂̂��ȂāA���Ƃ̔����`����ے肵���邱�Ƃ��ʂ��Đ����Ȃ��^�͂���Ȃ��B�v�u���̑��Q�����͓I��p�Ɋ�Â����A�͓I��p�Ɋ�Â����͌������S�̌�������́A���ɋ�ʂ���K�v�����Ȃ��̂ł���B�v�u���́A���@��̓��ʂ̋K��Ȃ�����A�o�ϐ����Ɋւ����b�K�����閯�@�ɉ����錴�����A���@�̗̈�ɂ��ސ��K�p����ׂ����̂Ɖ�����̂������ł͂Ȃ����Ɖ�������B�v�i�@������T���V���A�c����Y�w�s����̑��Q�����y�ё����⏞�x���䏑�X�Q�S�A�Q�T�ŁB�����͈��p�ҁj�Əq�ׁA�l�̑��Q�������͂̍�p�Ɋ�Â����̂Ƃ��闝�R�����ŁA���Ƃ̔����`����ے肷�邱�Ƃ�ᔻ���Ă����B
�@�@�E�@�n粏@���Y��
�@�n粏@���Y�́A���a�P�O�N���s�́w���{�s���@�x��ŁA�u������̉ߎ��͌����̐����セ�̑��݂�۔F�����Ȃ����̂ł���Ƃ���A���ƍs�ׂ����R�l�̍s�ȊO�ɑ������Ȃ�����A������ߎ��Ɉ����@�s�ׂ͏��@�֍s�ׂƂ��Ă̕i����۔F�����ׂ����̂łȂ��A�]���Ă��̍s�ׂ̌��ʂ����ƂɋA��������ׂ����̂ł��邱�Ƃ͈�@�Ȃ�@�֍s�ׂɂ�����ꍇ�ƈقȂ�Ƃ���͂Ȃ��B�v�u���Ƃ����Ȃ̈�@�s�ׂɈ˂��Ď��l�ɍ��Y��̑��Q����������ꍇ�ɂ͌ł�荑�Ƃ͂��������`���S����B���l�̗��v���@�Ɉ˂��Č����Ƃ��ĕی삳���ȏ�A����̈�@�̐N�Q����Ƃ��ɂ͂��̍s�҂̉��тƂł�����킸�����Ƃ��Ď��l�͂��̑��Q�̔����𐿋������ׂ��A�s�҂͔V�����ׂ��`�����B���ʂ̖@�̋K��Ȃ����荑�Ƃ�嫂����R�ɂ��̋`������Ə�������ƈׂ��Ȃ��̂ł���B�����Ă��̂��Ƃ͍��Ƃ̈�@�s�ׂ����@�s�ׂ���Ǝ��@�s�ׂ���ƂɈ˂��āA�܂����͍s�ׂ���ƑΓ��s�ׂ���ƂɈ˂��ĈقȂ�Ƃ���͂Ȃ��B�B�������@�s�ׂ����Ƃ̌��@�s�ׂɑ�����Ƃ��ɂ́A���Y�s��̂���s�����������Ƃ̔����`���𗚍s���Ȃ��ꍇ�Ɍ��s�@�㏮�V�ɑ��ċ`���̗��s����������~�ώ�i�������Ȃ��B����������~�ώ�i�̑����Ȃ����Ƃ͗��_�㔅���`���̑��݂�۔F���邱�Ƃ̍����ƂȂ蓾����̂ł͂Ȃ��B�v�u���l�������̌l�I�s�ׂɈ˂��Č�����N�Q������W�͎��@�W�ɑ����邪�̂ɁA��������l���`���𗚍s���Ȃ��ꍇ�ɂ́A���l�͖����i�葱�Ɉ˂��Ă��̋~�ς����ނ邱�Ƃ�B���l�͊������g�̎��͂��ȂĂ��Ă͊��S�ɂ��̑��Q������꓾�Ȃ����Ƃ����蓾��B������ꍇ�ɂ͎��l�͋�炭���Y�����̊ē�����ʂ��č��Ƃɑ��Ă��̕s���z�̔����𐿋����邱�Ƃ�B�����Ă��̏ꍇ�̍��Ƃ̔����`���̍����͓��Y�����̍s�ׂ����Ǝ��g�̍s�ׂƊŘ�邱�Ƃɍ݂�̂ł͂Ȃ����āA�������@�s�ׂ��s���҂����Ƃ������Ƃ��đI�C�����邱�ƁA�y�т����銯���̎����̊ē����Ƃ��ӂ肽�邱�Ƃɍ݂�̂ł���B�������E�̍��Ƃ̔����`�����s���z�����x�Ƃ����[�I�����̂��̂ł��邱�ƁA�y�э��ƂƊ����Ƃ̊W���̂��̂͏�Ɍ��@�W���\��������̂ł��邱�Ƃ���A�E�̗��_�����@��V�P�T���̓K�p�ł��蓾�Ȃ����Ƃ͂�����ւ��Ȃ��B�����Ƃ��E�̕�[�I�����`���𗚍s������ꍇ�Ɋ������g�ɑ��ċ��������s�g��������̂ł͂Ȃ����Ƃ́A���ꂪ���Ȃ̍s�ׂɑ���ӔC�ł��邱�Ƃ��疾�炩�ł���B�v�i�n粏@���Y�w���{�s���@�x�P�T�W�`�P�U�Q�ŁB�����͈��p�ҁj�Əq�ׂāA�����̑��Q�����͓I��p�Ɋ�Â����A�͍�p�Ɋ�Â����͋�ʂ���K�v���Ȃ��̂ő��Q������F�߂�ׂ��Ƙ_�����B
�@�G�@�O��j��
�@�O��j�́A�u�����̐N�Q����@�ɂȂ��ꂽ�ꍇ�Ɏ��@�K��ɏ]���Č��@�l�ɑ��鑹�Q�������������Ƃ����͓I��p�̖{�����ǂꂾ���Q������̂ł��낤���B�v�u���Ƃ̔����ӔC��F�߂邱�Ƃ͑��Q�������ɕ��z���錋�ʂƂȂ�A�ʏ�̏ꍇ�̕s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����ƈق鐫���������A������Ƃ����āA�s�@�s�ׂɂ�鍑�Ƃ̐ӔC��r�˂���K�v�͑����Ȃ��B�v����Ɍ��͓I��p�ɂ����@�l�̔����ӔC���|�͓I�Ȍ��s���̏ꍇ�Ƌ�ʂ��ā|���@�͈̔͂���r�˂��˂Ȃ�ʎ����I���R�͑����Ȃ��Ǝv���B�v�u�ȏ�q�ׂ��悤�Ɋ������̍s�ׂ����@�l�̌��͓I��p�ł���ꍇ�ɂ��A���@�l����@�Ȍ��͓I��p�ɂ�莄�@��̑��Q�����ӔC�����Ƃ𐳖ʂ���F�߂����Ǝv�����A�������ꂪ������ʂƂ��Ă����@��̐ӔC���S�R�l�����ʂ킯�ł͂Ȃ��B�v�u��@�Ȍ��͍�p�ɂ��A���������s�@�s�אӔC���̂͂��ꂪ�����ɔނ̌l�Ƃ��Ă̗L�ӈ�@�ł��邩��ł���B�c�c�c�c�]���āA����͎��@�I�����̂��̂ł���B�����Č��@�l�͔ނ̍s�ׂƂ��Ă̖@����̌��ʂ����@�ւ̍s�ׂɂ���ĐӔC��ʂƂ��Ă��A���������l�Ƃ��ĕs�@�s�ׂ��ׂ������Ƃɂ��g�p�҂Ƃ��Ď��@��̐ӔC�킹�˂Ȃ�ʁB�����ł͌��@�l�̌��͓I��p�Ƃ��Ă̖@����̌��ʂ͖��ł͂Ȃ����@��̕s�@�s�҂��銯�����̎g�p�҂ł��邱�Ƃɂ���ĂV�P�T���̓K�p����̂ł���B���@�l�Ɗ������Ƃ̊W���V�P�T���ɂ����g�p�W�ɊY��ʂȂ�A�c���I���Ƃ�͌��s���ɂ����銯�����̐E���s�ׂɂ��g�p�҂Ƃ��Č��@�l���ӔC�����Ƃ��ے肳��錋�ʂɂȂ�v�i�������ጤ����w���ᖯ���@�i���a�P�U�N�x�j�x�R�V�ňȉ��B�����͈��p�ҁj�Əq�ׁA���͓I��p�ɂ����@�l�̔����ӔC��r�˂��闝�R�͂Ȃ��Ɣᔻ�����B
�@�I�@�܂Ƃ�
�@���̂悤�ɁA�w���́A�O�߂ŏq�ׂ�������w������`�ŁA�������A�吳���A���a���̎���̐i�s�Ƌ��ɁA�����̌����~�ς��g�����闝�_��W�J���Ă����B
�@���Ȃ킿�A�吳���ɂ́A�͍�p�y�эH�앨�̐ݒu�A�Ǘ��Ɋւ���s���̕s�@�s�ׂɂ��ẮA���@�s�@�s�ז@�ɂ�葹�Q�����ӔC��F�߂�̂��ʐ��ɂȂ����B�����̊w���́A����̌����܂��A���邢�͌��@�⍑�Ɨ��_�Ƃ��Đ������Ă����u�@�֗��_�v�̎��_����A����ɂ́u�g�p�ҐӔC�_�v���܂��āA���̍l�@�̏�ɗ��_������Ă���B
�@����ɏ��a�P�O�N��ɂ́A���͓I��p�Ɋւ���s���̕s�@�s�ׂɂ��āA�͍�p�Ƌ�ʂ���K�v���Ȃ��A���@�s�@�s�ז@��K�p�����Q�����ӔC��F�߂�ׂ��Ƃ���̂��ʐ��ɂȂ�������Ǝv�������B
�@�������A���a�P�O�N��Ƃ��������ێ��@���̊w��A�v�z�ɑ���e�����ł����������������ɁA���Љ�ɂ�����s������i�@�I���`�̎����j���̓I�t�����A���Q�̎Љ�o�ϓI�t�����S�Ȃǂ̎��_�����\���ɓ��܂��Ĕ��\���ꂽ���Ƃ��l���ɓ����ƁA��L�̓c����Y�A�n粏@���Y�A�O��j�̊e�w���́A�w��̒ʐ��ɂȂ��Ă����Ǝv�������B
�@���������w���̑��݂��݂�A���Ɩ����ӂ̖@���͊m������Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@(4)�@�����͂̍s�g�Ɋ�Â����ƐӔC��ے肷�闧�@�҈ӎv�͑��݂��Ȃ�
�A �����@�ƌ����@�͑S���ʂł���A�����@���莞�̈��B�́u���@�ҁv�̈ӎv�͌����@�Ɏp����Ȃ�
�@�������́A�u�����@�R�V�R�����獑�ƐӔC�Ɋւ��鎚�傪�폜���ꂽ���Ƃ́A���Ȃ��Ƃ������͂̍s�g�Ɋ�Â����ƐӔC��ے肷�闧�@�҈ӎv�̕\��ł���Ƃ݂�̂������ł���A���s���@�ɂ����̗��@�҈ӎv���p�����ꂽ�Ƃ�����B�v�i�������Q�R�Łj�Ɣ������A����ɖ����Q�R�N�̎��_�ō��Ɩ����ӂ̖@�����m�����A�������@���ł͈�т��č��̔����ӔC��ے肵�Ă����|��������B
�@�������Ȃ���A���Ⴊ��т��č��̔����ӔC��ے肵�Ă����킯�ł͂Ȃ��A���a�P�O�N��ɂ́A�w���Ƃ��Ă͌��͓I��p�Ɣ͓I��p����ʂ���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ���̂��ʐ��ɂȂ��Ă������Ƃ́A�O�L(2)�A(3)�ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B
�@�������́A�����@���莞�ɁA���B�Ƃ����u���@�ҁv�̈ӎv�Ɋ�Â��āu�����m�������v�̕���������A���̈ӎv�����s���@�Ɏp���ꂽ�Ƃ����B
�@�������A�����@�͖����Q�R�N�S���Q�P���Ɍ��z���ꂽ���A�{�s����Ȃ��܂ܔp�~���ꂽ�B�����Q�X�N�A�V���ɋN�����ꂽ���ĂɊ�Â����s���@�i��P�҂����R�҂܂Łj�����z����A�����R�P�N�V���P�U������{�s���ꂽ�B
�@�����@�̗��Ăɓ���A�u�����ƃm�׃��j���l���g�p�X���ҁv�u�g�p�ҁv�Ƃ������I�Ԃɂ��Ă܂ň��B�́u��l�v�u�e���v�݂̂�I�ӎv���p���ꂽ�Ƃ͓���l�����Ȃ��B�u�g�p�ҁv�Ƃ�����́u��l�v�u�e���v�Ƃ����l�I�Ȍَ���L�َ͈͂̌��\����ł���A�召�̒c�́A�����̖@�l�����܂ݓ���Ӗ������B
�@���̂悤�ɁA���s���@�́A�����@�Ƃ͑̌n���������܂������قȂ闧�@�ł���A�����@�̗��@�҈ӎv�����s���@�Ɍp�����ꂽ�Ƃ����������̔��f�́A�܂��������̍������Ȃ��B
�@���������āA�O�L�u���@�҈ӎv�v�́A���R�ٔ����̓Ǝ��̉��߂ɉ߂��Ȃ��B
�C�@�s���ٔ��@�P�U���́A���Ɩ����ӂ̍����ɂ͂Ȃ�Ȃ�
�@���������A�������@���ɂ����Ă���A�O�L�u���@�҈ӎv�v�ȂǂƂ̉��߂͑��݂��Ă��Ȃ��B
�@���Z���B�g�́A�u��@�Ȃ�s����p�Ɉ���A���͌����̐ݒu��͕ۑ������r����Ɉ���A��O�҂̌�����N�Q������ꍇ�ɉ��āA���Ɩ��͌��@�l�̕����ׂ����Q�����̐ӔC�́A���̌������s�����̍s���Ɋ�Â����̂Ȃ邱�Ƃɉ��čs�������̐�����L����Ƌ��ɁA����Q�҂̌o�Ϗ�̗��v�ׂ̈ɂ��A������̔����ӔC�Ɩ@����̐�������������̂Ȃ邱�Ƃɉ��Ė��������̐�����L���B�V���s���ٔ������͖����ٔ����̉���̌����ɑ������ނׂ����͗��@����̖��Ȃ�B�䂪���@�͑��Ă̑��Q�v���̑i�����čs���ٔ����̌����O�ɒu���V�������Ƃ��Ė����ٔ����̊NJ��ɑ������ށB�@�����w�s���ٔ����͑��Q�v���̑i�ׂ������x�i�P�U���j�ƞH�ւ�͍��̈ӂ��������̂Ȃ�v�i���Z���B�g�w�s���@�B�v�x�㊪�T�R�S�ŁA�L��t�B�����͈��p�ҁj�Əq�ׁA���Ɩ��͌��@�l�̕����ׂ����Q�����Ɋւ��Ă͎i�@�ٔ����̊NJ��Ƃ����Ӗ��ł��邱�Ƃ�������Ă���B
�@���Ȃ킿�A���Z���B�g���_�q����悤�ɁA�������@�U�P���́u�s�������m��@�����j�R�����������Q�Z�����^���g�X���m�i�׃j�V�e�ʃj�@�����ȃe�胁�^���s���ٔ����m�ٔ��j���X�w�L���m�n�i�@�ٔ����j���e�X���m���j�݃��X�v�Ƃ����K��́A�ʂɖ@���������Ē�߂��s���ٔ����̍ٔ��ɑ����ׂ����̂́A�i�@�ٔ����ɂ����Ď��Ȃ����Ƃ��߂����̂ł����āA�����ł́A�s���ٔ����ɑ����邱�Ƃ��@���Œ�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��i�ׂ́A�i�@�ٔ����Ŏ��邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���Ă���B
�@�s���ٔ��@�P�U���́u�s���ٔ����n���Q�v���m�i�׃��Z�X�v�Ƃ����K��́A�i�@�ٔ����ɂ�鎄�@�I������ے肵���킯�ł͂Ȃ�����A���ߏ�́A�����͂ɂ��s�@�s�ׂ����@�̕s�@�s�ׂ̋K��ɂ�荑�̕s�@�s�ׁi�V�O�X���Ȃ����V�P�P���j�y�юg�p�ҐӔC�i�V�P�T���j��₤���̂ł������ɂ����Ȃ��B
�@���Ȃ킿�A�s���ٔ�����������̑��Q���������i�ׂ��t���Ȃ�����Ƃ����Ă��A�i�@�ٔ������A���Q���������i�ׂ�����̂ł����āA�s���ٔ����@�P�U���́A���Ɩ����ӂ̖@���Ƃ͑S�����̊W���Ȃ��A���̑��݂������āA���Ɩ����ӂ̖@���̘_���Ƃ��邱�Ƃ͂��������ł��Ȃ��̂ł���B
�E�@���Ɩ����ӂ́A�@�߂ł��Ȃ���Ίm�����ꂽ�@���x�ł��Ȃ�
�@���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K��̒��ɂ��A���̑��Q�����ӔC��ے肵���K��͂Ȃ��B���̂悤�ɁA��O�ɂ����ẮA���Ɩ����ӂ̖@���L���������@�i����@�j�͑��݂��Ă��炸�A���ۂɂ��A���̔����ӔC�ɂ��āA�i�@�ٔ����̊NJ������ے肳��邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�ȏ�̌o�܂ɏƂ点�A�����̗��@�҂̈ӎv�Ƃ��ẮA���̔����ӔC���߂�����ɂ��ẮA���@���K�p����邱�Ƃ�F�߂���ŁA��O�I�ɍ����Ɛӂ����ꍇ�ɂ��ẮA�i�@�ٔ����̔��f�ɂ䂾�˂��Ƃ�����B
�@�������A�i�@�ٔ����̍ٔ���̏W�ς��o�āA���a�P�O�N��̔���A�w���ł́A���͓I��p�Ɋւ���s���̕s�@�s�ׂɂ��āA���@��K�p�����Q�����ӔC��F�߂�����ɗ��Ă����̂ł���B
�@���������āA���������F�肷��悤�ȁu�����Q�R�N�̎��_�Ō����͍s�g�ɂ��Ă̍��Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ƃ�����{�I�@���m�������v�Ƃ͂����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@(5)�@����
�@�ȏ�(2)�Ȃ���(4)�ɏq�ׂ��Ƃ���A��P�ɁA�i�@�ٔ����͍��̔����ӔC�ɂ��āA���h���d�˂Ȃ��疯�@�̓K�p�͈͂��g�傷������ŕϑJ���A���a�P�O�N��ɂ͌��͓I�s�ׂɂ��Ă����@�̓K�p���m�肷��ٔ��Ⴊ���݂��Ă������A�t�Ɍ��͓I�s�ׂɂ��Ė��@�̓K�p��ے肷��ٔ���ɂ����Ă��̎����I�����͑S��������Ă��Ȃ��������ƁA��Q�Ɋw����ł��A���͓I�s�ׂɂ��Ė��@�̓K�p�Ȃ����ސ��K�p��F�߂錩�����̂��Ă������ƁA��R�ɁA�����̗��@�҂́A���̔����ӔC�ɂ��Ă͎i�@�ٔ����̔��f�ɂ䂾�˂Ă������Ƃ��������������ł���B
�@���������āA���Ɩ����ӂ̖@���Ȃ���̂̎��̂́A�v����ɖ��@�̓K�p�͈͂��߂���ٔ���̏W�ϓr��̖@���ł͂����Ă��A���a�P�O�N��ɂ͔ے肳��������̂ł���A�u����@�v�Ƃ����قǖ@�I���萫��L���Ă͂��Ȃ����A�m�����ꂽ�@���Ƃ͑S�������Ȃ��B
�@���Ȃ��Ƃ��A�������́u��O�ɂ����ẮA�����͂̍s�g�ɂ�鎄�l�̑��Q�ɂ��ẮA���̑��Q�����ӔC��F�߂�@����̍������Ȃ��A���̂��Ƃ͌����͍s�g�ɂ��Ă̍��Ɩ����ӂ̖@�����̗p����Ƃ�����{�I�@����Ɋ�Â����̂ł���������A�����͍s�g����@�ł����Ă��퍐�͂���ɂ�鑹�Q�̔����ӔC��Ȃ��v�i�������Q�S�Łj�ƒf��ł���悤�ȏ͑S�����݂��Ă��Ȃ������̂ł���B
�@�ނ���A�������@���̍ٔ����́A��̓I���Ă�ʂ��A���Ȃ��������c�̂ɔ����ӔC��F�߂Ȃ����Ƃ̕s���������o������Ȃ������Ǝv����B���̂��߁A�u���Q�̌����ȕ��S�v�Ƃ����s�@�s�א��x�̑匴�������炷�ׂ��A�l�X�Ș_�����Ă����Č��@�E���@�_��r�����悤�Ƃ��Ă����̂ł���B
�@���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA�u�������@����ł����A�����͂̍s�g�ɂ��Ė��@��K�p������߂����������ƂɏƂ炷�ƁA���_�I�ɂ́A�����̍ٔ����Ƃ��ẮA�����̔���ɏ]���Α����̂ł͂Ȃ��A�����̖@��̉��߂������_�ł��Ȃ����ׂ��ł��낤�B�v�i�����ח��w���ƕ⏞�@�x�S�P�Łj�Ƃ̎w�E���Ó��ł��邱�Ƃ���w���炩�ł���B
�@�Q�@�{���ې�́A�u�K�@�Ȍ����͍s�g�����v�Ɋ�Â����u���Ɩ����ӂ̖@���v�͓K�p����Ȃ�
�@�@(1)�@�������́A�{���ې�ɑ��A���Ɩ����ӂ�K�p��������̂ł���
�Ƃ������f�������ɂ������āA�{���ې�́A�u�����{�R�����̑��ݖړI���̂��̂ł���퓬�s�ׂƂ��čs�������̂ł���Ƃ����̂ł��邩��A���̍s�ׂ͌����͂̍s�g�i���̓������Ɋ�Â��D�z�I�Ȉӎv�̔����Ƃ��Ă̋����I�E���ߓI�s�ׁj���̂��̂ł���A�������@�̓K�p�ΏۂƂȂ��Ă����͓I��p�ɕ��ނ����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɣ�������B
�@�������́A�����͂̍s�g�ł���Η�O�Ȃ��ɍ��Ɩ����ӂ��K�p�����Ƃ��������ɂ����A�{���ې�́u�퓬�s�ׂƂ��čs�������́v�ł��邩��A���Ɩ����ӂ̓K�p���������͂̍s�g�ł���Ƃ��Ă���B
(2)�@�������A���ɍ��̌����͂̍s�g�ɂ��č��Ɩ����ӂ̖@�����F�߂���Ƃ��Ă��A�{���ې�́A���Ɩ����ӂ̌������O��Ƃ���u�����͂̍s�g�v�ɂ͊Y�����Ȃ�����A���̌����͓K�p����Ȃ��B
�@���Ɩ����ӂ̖@���́A�����Ŗ��Ƃ���鍑�Ƃ̍s�ׂ������̂��߂̌��͍�p�ł���ꍇ�ɁA���Y������ی삷�邽�߂̂��̂ł����āA���Y�s�ׂ������̂��߂̌��͍�p�ɂ�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̍s�ׂɂ��Ă����@��̕s�@�s�אӔC���������邱�ƂR�̂��ƂƂ��Ă�����̂ł���B���Ƃ��s���s�ׂ��s�@�s�ׂł���ꍇ�ɂ́A�ی삷�ׂ����͍�p�ł͂Ȃ��A���Ɩ����ӂ͓K�p����Ȃ��B
�@�{���ې킪�A���Ɩ����ӂ̌������K�p����邽�߂̗v���Ƃ��Ắu�����͂̍s�g�v�ɊY�����邽�߂ɂ́A�������̔�������u���̓������Ɋ�Â��D�z�I�Ȉӎv�̔����Ƃ��Ă̋����I�E���ߓI�s�ׁv�ł��邱�Ƃɉ����āA�{���ې킪�A�u�K�@�Ȍ����͂̍s�g�v�ƕ]�������悤�Ȍ����ɂ���čs��ꂽ�s�ׂł��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�Ȃ��Ȃ�A�{�������ɂ����Ă��A���������ɑ����̍s�ׂ𖽗ߖ��͋֎~��������������Ƃ�������I�ȗD�z�I�x�z�����@������邽�߂ɂ́A�@���ɂ���Đ��肳�ꂽ�����Ɋ�Â����Ƃ��K�v�Ƃ��ꂽ����ł���B
�@�������́A�u�����@�̗��Ăɐ[���֗^�������B���A�O�L�̂Ƃ��荑�Ɩ����ӂ̖@���̍������s�����̉~���ȉ^�p�ɋ��߂Ă����v�Ǝw�E���Ă���B�u�s�����̉~���ȉ^�p�v�Ƃ́A�@�Ɋ�Â����s�����Ӗ����邱�Ƃ́A�@����`�̌������瓖�R�ɓ�����邱�Ƃł���B�@�Ɋ�Â����s�����̉~���ȉ^�p���A���Ɩ����ӂ̖@���̍����ł���Ƃ���Ȃ�A�u�K�@�Ȍ����͍s�g�����v�����������Ƃ̍s�ׂ́A���Ɩ����ӂ�K�p�����鍪���������̂ł���B
�@�@(3)�@�����{���ې�ɂ��Č���ƁA�푈�s�ׂɂ�鑊�荑�̐l�Ԃɑ���E�������@�W�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�Ƃ��Ă��A����́u�K�@�Ȍ����͂��s�g���錠���v�͈͓̔��Ɍ��肳���̂ł���A�푈�s�ׂ����牽������Ă��悢�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�u�K�@�Ȍ����͂��s�g���錠���v���������s�ׂ́A�����Ƃ��Ă̐푈�s�ׂɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�{���ې�́A���������F�肷��悤�ɁA�W���l�[�u�E�K�X�c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ������@�s�ׂł���A���A��T�i�l�ɁA�ې��Q�҂������Q������Ƃ����n�[�O�������R������e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă����̂ł���B
�@���������āA���̂悤�ȋ��x�̈�@����тт��{���ې�́A�u�K�@�Ȍ����͂��s�g���錠���v���������s�ׂł��邱�Ƃ͖����ł���A���Ɩ����ӂ�K�p���鍪�����Ȃ��B
(4) �{���ې�̈�@���̋����A��������������P�_�́A�{���ې�́A��T�i�l���g����@�Ȑ푈�s�ׂł��邱�Ƃ��[���Ɏ��o���A���m���Ȃ���A��T�i�l�ɂ��g�D�I�A�v��I�s�ׂƂ��čs��ꂽ��K�͂Ȑ푈�s�ׂ��Ƃ����_�ɂ���B�{���ې퓖������A��T�i�l�́A�ې킪�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�Ɉᔽ���A���c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ���A�������ӔC���߂��n�[�O�������R���Ɉᔽ���邱�Ƃ��n�m���Ă����B
�@���̂��߁A���{�R�͍ې핔���̑n�݂ɂ������āA�\�����͌R���ɂ�����u�h�u�v��u�����v�A���Ȃ킿�`���a�̗\�h�Ə̋������f����u�֓��R�h�u���v�Ƃ��đn�݂��A���̎��Ԃ́A�ە���̊J���Ǝ��p�����߂����閧������n�����B�܂����ۂɍې�����s����ɂ������ẮA�O�ꂵ���閧���Ƃ��čs�����B
�@�܂��A��T�i�l�́A�\�A�Q��ɒ��ʂ��s�F���Z���ƂȂ������_�Œ����ɕ��[�̂V�R�P�����̌����j���A�ߗ���S���s�E���铙�̏؋��B�ł�}�����B���̏؋��B�ł́A���R�����̎w���ɂ��s��ꂽ�B
�@����ɁA��T�i�l�́A�������̈�@�s�ׂȂ������A�����ɂ�����܂ŁA�������B���������Ă���B
�@�@(5)�@�{���ې�̈�@���̋����A��������������Q�_�́A�{���ې킪�A��ʔj��ɂ���퓬�������ʏZ���ɑ��閳���ʂȎE�����Ƃ����_�ɂ���B�ې킪�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�y�уn�[�O�������R���Ɉᔽ���闝�R�͂��̓_�ɂ���B
�@���{�R�ɂ��{���ې킪�s���Ă���Œ��A�P�X�S�Q�N�R���Ɋ֓��R�R��E�q���R�㒆���́A�u�ې�ɂ��āv�Ƃ����u���̒��Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B
�@�u�S�ʓI�ɂ͕�⋂ɗ���ł��邱�ƂɂȂ�s�s���U�����āA�s�s���Ђǂ��ڂɑ��킷�B����͏��������������ł���܂��B�R���W�̂��̂ɂ́A���ڂ��Ȃ��ő傫�ȓs�s�ɓ`���a�𗬍s�炵�Ă䂭�v�u�ې�̑_�����̂P�́A��������������߂Đ��_��ɍ��������ƂɂȂ����ƌ����悤�ȊϔO��G�ɗ^���邱�ƂŁA�傫�ȓs�s������ƂЂǂ��ڂɑ��킷�Ƃ������Ƃ������ł���܂��v�i���B�鍑�R��c�w�R��c�G���x�B�b�Q�X�̂P�X�W�Łj�B
�@���̂悤�ɁA��T�i�l���A�ŏ������ʏZ���̑�ʎE�C��ړI�Ƃ��čە�����J���������Ƃ͖��炩�ł���B
�@���ہA�{���ې�́A�P�X�S�O�N���]�Ȋe�s�s�ւ̃R�����ہA�`�t�X�ہA�y�X�g�ۂ̋ۉt�T�z�A�y�X�g�����m�~�̓����A�P�X�S�P�N�Γ�ȏ퓿�ւ̃y�X�g�m�~�̓����A�P�X�S�Q�N�]���ȁA���]�Ȃł́A�y�X�g�ەt���̕āA�y�X�g�m�~�A�l�̒n�ォ��̎U�z�A��˂�H���ւ̃R�����ے����ȂǁA���̎��s�ԗl�́A���荑�̌R���{�݂�R���Ƃ͂܂������W�̂Ȃ���ʏZ���̎E����ړI�Ƃ������̂ł������B�{���T�i�l����A�s���A�_���Ȃǔ�퓬���̏Z���ł���B
�@�@(6)�@�{���ې�̈�@���̋����A��������������R�_�́A�{���ە���̌����A�J�������̎������̈�@�s�ׂ����Ƃɂ���āA���E�ŏ��߂Ė{�i�I�ȍە���̊J�����\�Ƃ��A����g�p�������Ƃł���B
�@�V�R�P�����́A���[�̖{���Ń`�t�X�A�R�����A�ԗ��A�y�X�g�A�Y�s�A�����Ȃǂ̌����E�|�{���s�������A���̍ہA�펞�Q�O�O�l����S�O�O�l�̕ߗ��̎����ɗp�����B�ߗ��́u�}���^�i�ۑ��j�v�ƌĂ�A�P�{�A�Q�{�Ɛ�����ꂽ�B�ނ�́A�u�������v�̒��̉�U�����O�̎�����ŁA�l�̎����Ɏg��ꎟ�X�ɎE����Ă������B
�@�܂��A�{����Q�n�ł��鐒�R���Ȃǂł́A���{�R���A�ې�����{�����n��Ɂu�h�u���v�Ƃ��ē���A�늳������Q�҂̉�U���čې�́u���ʁv�������銈�����s���ȂǁA�ې�̎��s�ɂ���Q�҂��������ޗ��Ƃ��đ�ʎE�C��������肠�����̂ł���B
�@�@(7)�@�ȏ�̂悤�ɁA�{���ې�́A���ۖ@�Ɉᔽ���邤���ɁA���̈�@���͋ɂ߂ċ����A�����ł���A�����Ȃ�Ӗ��ł�����������Ȃ��c�s�s�ׂł���B�{���ې�́A�u�K�@�Ȍ����͍s�g�����v�Ɋ�Â��s�ׂƂ������Ƃ͂ł����A���Ɩ����ӂ̖@���͓K�p����Ȃ��B
�@�R�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v�͊O���ł̊O���l�ɑ��錠�͍�p�ɂ͓K�p����Ȃ�
�@�@�@�@
�@�@(1) �������̌��
�@�������́A�u�䂪���ɍ��Ɩ����ӂ̖@�����m�����������Q�R�N�ȍ~�ɂ����āA�����̉䂪���̖@�̌n���A���͓I��p�̔�Q�҂��O���l�ł���ꍇ�ɂ��̊O���l�ɑ��Q������������t�^���Ă������Ƃ����������͉���F�߂�ꂸ�A���{�l���O���l�����������Ɩ����ӂ̖@���̓K�p���Ă������̂ƍl������v�i�������Q�T�Łj�Ƃ���B
�@�������A���Ɩ����ӂ̖@���́A�{���ې�̍s��ꂽ�����푈�̍Œ��ɂ����Ă����A���ɔj�]�𗈂��Ă���B
�@�����A�P�X�R�V�N���{�R�̓싞�U����ɍۂ��A�g�q�]�����ɒ������̕ĖC�̓p�i�C���ƕăX�^���_�[�h�I�C���Џ��D�R�ǂɑ��A���{�̌R�@���딚�������A�R���̎��ҁA���\���̕����҂��o���������i�p�i�C�������j�ɓ���A���{���{�͂�����Q�Ҋe�l�̎����Q�ɂ��A�����ɎӍ߂��A���ꂼ�ꌵ���Ȍv�Z�ɂ���ĎZ�o�������z�̔��������̗��N�ɍs�����̂ł���B
�@�������͂��̌��ɂ��A���ƍ��Ƃ̊Ԃʼn��߂��ꂽ����ł����Ĕ�Q�҂̌l���������F�߂�ꂽ��ɓ���Ȃ��Ƃ������A���Ȃ��Ƃ��l�̍��ۖ@��̎�̐����F�߂�ꂽ�Ƃ����ׂ��A����ȏ�ɁA�悸�A���Ɩ����ӂ̖@���Ȃǂ͔މ䋤�Ɉ�ڂ��ɂ���Ȃ��������Ƃ𖾂炩�Ɏ����Ă���B�}���A�č��l��Q�ҁi�����T���͒����l�j�ɑ��Ă͎咣���Ȃ����Ɩ����ӂ̖@�����A�����l�ɑ��Ă͎咣����Ƃ��������A���ʂ�@���ɐ�������Ƃ����̂��B
�@���ۂɂ͌l���Ƃɖ����I�ȑ��Q���������̎菇�Ƃ����ŕ⏞�z���Z�肵���肵�Ă��邱�Ƃ�������B
�@�܂��Z��ɂ������Ắu���p�ł�����v�Ƃ��Ċe��̔��Ⴊ�Q�Ƃ���Ă��邪�A�Q�Ƃ��ꂽ�T�S��͂��ׂČl�̔�Q�i�푈�A�����A�����̕s�@�s�ׂȂǂɂ��j�ɑ��A���Q�O�����{�ɑ��Q���������߂��P�[�X�ł���B�ȉ��A�ڏq����B
(2) �p�i�C�������ł́A�l���������ɉ����Ă���
�@�@�@�A�@�p�i�C�������ɑ�������������Q����̂P�Q���P�S���A���{�̍L�c�O���́A�A�����J�̃O���[������g�ɑ��A�����̐ӔC��ӂ��A�u��̑��Q�ɂ�������⏞�v�A�ӔC�҂̏����A�Ĕ��h�~�[�u��\������A�Q�U���A�����J���{�����������Ĉꉞ�̌������݂��B�i�u�O���[�č���g���L�c�O�������v�P�X�R�V�N�P�Q���P�S���t�A�O���Ȓ����ǁw�č��R�̓p�i�C�������x���a�Q�P�N�P���A�S�P�`�S�R�Łj�B
�@�p�i�C�������̑��Q�����ɂ��āA���P�X�R�W�N�R���Q�P���t�ɁA�A�����J��g��ʂ��đ��z�Q�Q�P���S�O�O�V�h���R�U�Z���g���v������A���{���{�͂S���Q�Q���A���̔����z�����؎�Ŏx�������B
�@�@�@�C�@�����z�̓���́A���Y���Q�z�A�P�X�S���T�U�V�O�h���P�Z���g�A�������������z�A�Q�U���W�R�R�V�h���R�U�Z���g�ł���B
�@�����̑ΏۂƂȂ������Q�Ƃ��ē��{�̊O���Ȃ��m�F�����̂́A
�@���v�͑D�i�C�́u�p�i�C�v���A�u�X�^���_�[�h�E���@�L���[���v�� �БD�T�ǁj�A
�A����D���i�u �X�^���_�[�h�E���@�L���[���v��БD�Q�ǁj�A
�B���ҁi�u�p�i�C���v��g���Q�����P���j�A���ҁi�͑D��D�҂V�S���j�A
�C���i�X���ȋy�э����ȕ��тɌl���Y��Q�j�ł���B
�@��Q�Ҍl�����łȂ��l���Y��Q�܂Ŕ����̑ΏۂɂȂ����i�O�o�w�č��R�̓p�i�C�������x�A�R�P�`�R�Q�Łj�B
�@�����ǂ̂悤�ɕ⏞�z���Z�肵�����́A�A�����J�̍����������ُ�
���̎����i�u�P�X�R�V�N�P�Q���P�Q���A���{�ɂ�鍇�O���R�̓p�i�C���y�уX�^���_�[�h�E���@�L���[���E�I�C���БD�̍U���ƒ��v���甭�����������Ƒ��Q�v�Ƒ肷��u�@���ږ�o���v�i�����ԍ��R�X�S�D�P�P�T�@PANAY/�S�O�W�j�Ŗ����ɍ��������㗝�̏��������邱�Ƃ���A�����Ȃɒ�o���ꂽ���̂Ǝv����B���t�͂P�X�R�W�N�Q���P�U���t�ł���j�ɂ���Ĕ����z�̎Z�o���ǂ̂悤�ɂ����Ȃ�ꂽ�����݂邱�Ƃ��ł���B
�E�@�܂��C�R�̕��ł́A���Q�́A
���͑D�̑����i�S�T���T�V�Q�V�h���W�V�Z���g�j
�������y�ы����i�̑����i�X���V�V�U�U�h���S�W�Z���g�j�A
���l
�ɕ����čl�@����Ă���B
�@�o���̑啔�����u���l�v�Ɉ��Ă��Ă��āA��Q�Ҍl�ɑ��鑹�Q���������S�ɂȂ��Ă���B
�@�u���l�v�͂���Ɏ��ҁi�Q�l�j�A�����ҁi�d���P�P���A�y���R�Q���j�A�V���b�N����ѕ��u�Ɉ˂��Q�i�P�S�l�j�ɕ����ĎZ�肳��A���z�P�S���Q�O�O�O�h���ł���B
�@����ɂ������Ă͔�Q�҈�l���ɂ��āu���p�ł��鎖���v�i��Q�̑ԗl�A�����̏ꍇ�ɂ͎���̌o�߁A��Âɗv�����o��A���ǂ̗L���A���^�A�Ƒ��̐��v�ێ��ɉʂ��������Ȃǁj�A�u���p�ł�����v�A�u�C�R�Ȃ̊����v�A�u���_�v�̏��ɏڍׂɎZ��̍�����������A�����z�����肳��Ă���B
�@�C�R�̎��ɗX���Ȃ̑������v�Z����Ă��邪�A�V�͐؎�A���A���t��Ȃǂ̕�������ł���B
�@�p�i�C���ɏ�D���Ă��Ĕ�Q���đ�g�و��i�����S���j�ɂ��Ă����l�Ɍʂɏڂ�����������ĕ⏞�z�����肳�ꂽ�B�����Ă���Ƃ͕ʌɔ�Q�����l�̏����i�ɂ��Ă������̑ΏۂƂ���A�⏞�z���Z�肳�ꂽ�B
�@�@�@�G�@�X�^���_�[�h�E�I�C���Ђ̏��D�̔�Q�ɂ��Ă����l�Ȏ菇�ŎZ��
�������Ȃ�ꂽ�B��g���̐l�I��Q�͂W�l�ł��������A���̂����͌y�������T�l�̒����l���܂܂�Ă���B�R�l�̏ꍇ�Ɣ�ׂČ����͊ȗ��ɂ����Ȃ�ꂽ���A�����l�T�l�i�����͍ō��P�T�h���A�Œ�W�h���Q�T�Z���g�j�ɂ͈�l������P�O�O�h���̕⏞�z�����肳�ꂽ�B����ɃX�^���_�[�h�Ђ͏�g���A�Ј��̏����i��ƒ�p�i�ɂ��Ă��ُ��Ƃ��ĂR���U�O�R�S�h���𐿋������B
�@���̑��̃P�[�X�ł́A���Ԑl�A���Ԋ�Ƃɑ���P�R���̕⏞���Z�肳��Ă��邪�A���̂Ȃ��ɂ͏�D���̒������Ԋ�Ɓi�����A�o�����ЁAYee�@Tsoong�����z���Ёj�̎Ј����܂܂�Ă���B
�@��ޒ��̒ʐM�ЁA�f���Ђ̎Ј�����Q�ɂ��������A�ނ�̎������A�f�ʋ@�A�����Y�A�l�K�t�B�����Ȃǂɕt���Ă������������Q�z���Z�o����Ă���B
�@�@�@�I�@���Ƃ��Q�Ƃ��ꂽ���̂̂������Ԑl�̐푈��Q�ɑ��鐿������
���Ɋւ����̂���Ⴞ���Љ�Ă������B����Ƃ��Ă͑O�ɏq�ׂ����A��ꎟ��풆�̂P�X�P�U�N�R���Q�R���A��D���̃C�M���X�D�D�T�Z�b�N�X���h�C�c�̐����͂̋����U�������ہA���l�̃A�����J�l��q���������A���h�C�c���瑹�Q���������P�[�X�ł���B
�@�Ⴂ��ҁi�C���^�[���j���C���_�[�E�O���C�u�X�E�y���t�B�[���h�̎���Q�́A�����I�Ȑ_�o��Q�ƕG�߂��܂ލ��������܋y�щE����Ԃ��̔P���ł���B���@�P�����A���t��ł̕��s�R�����A��ɂ����s��S�����A�ƕĂɂ�鍬���������ψ���P���T�O�O�O�h���̕t�^���ْ肵���Ƃ��ɂ܂��G�̋@�\�͉��Ă��Ȃ������B
�@�����łQ�S�ł��������A��l�O�Ƀs�A�j�X�g�ł������G���U�x�X�E�t�H�[�h�E�X�`���\���͐��T�ԍ�����Ԃɂ����������B���ɉi�v�I�ȑ����A�����\���߂͖����I�j�ӏ�ԁi"mushroom
fracture")�ł��̂��ߏ�Q�������E�Ƃ̐��s���s�\�ɂȂ����B�S���h����t�^���ꂽ�i�r��M��u���{�̉��Q�s�ה�Q�҂̌l�����������ɂ��Ă̗��j�I�l�@�v�Q�Ɓj�B
�@�@(3) ���{���̊NJ��ɕ����Ȃ��O���l�ɑ��鍑�Ɩ����ӂ̕s�K�p
�@�T�i�l��́A���R�ɂ����āA���Ɩ����ӂ̖@���_�I�����Ƃ��āA�Q�̘_�����������B��P�ɁA�匠�҂͉����̂ɂ��S�����ꂸ�ɖ@���쐬���邱�Ƃ��ł���̂ł��邩��A�匠�҂͏�ɖ@�Ɉᔽ���邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ����匠�����ӂ̍l�������A�ߑ㍑�Ƃɂ����ẮA�匠�҂ł��鍑�������Ƃ͖@��N�Ƃ����Ȃ����A�@��N�Ƃ��邱�Ƃ͍l�����Ȃ��Ƃ���A���Ƃ̕s�@�s�אӔC���ے肳���u�x�z�҂Ɣ�x�z�҂̎������v�̘_���ł���B
�@��Q�ɁA��@�ȍ��Ƌ@�ւ̍s�ׂ́A���ƈӎv����@�K�Ɉᔽ���邪�̂ɖ@���㍑�Ƃ��\����@�֍s�ׂƂ͔F�߂�ꂸ�A���Ƌ@�ւ��\������l�̌l�I�ӔC�̖�����̂Ɏ~�܂�A���Ƃ̖@�I�ӔC�͐����Ȃ��Ƃ����A��@�s�ׂ̍��ƋA����۔F����u���ƂƖ@�����̎������v�̘_���ł���B
�@�����āA�����̍��Ɩ����ӂ̖@���_�㍪������A���Ɩ����ӂ̓K�p�ɂ͖��炩�ɏꏊ�I���E�����邱�Ƃ��咣�����B
�@�u�x�z�҂Ɣ�x�z�҂̎������v�́A���̍��Ƃ̊NJ��i�������j�ɕ�����҂͈̔͂ł̋c�_�ł����āA�������̋y�Ȃ��O���ł̊O���l�Ƃ̊W�ɂ����Đ��������Ȃ����̂ł��邱�Ƃ͓��R�ł���B���Y���Ƃ͎����̊NJ��O�ɂ��鑼���̍����̈ӎv�ɂ��s������̂ł͂Ȃ�����A���̊W�Ɂu�x�z�҂Ɣ�x�z�҂̎������v�ȂǑ��݂���͂����Ȃ��̂ł���B�@�܂��A�u���ƂƖ@�����̎������v�ɂ��Ă��A���Ƃ̍s�ׂ�K�@������@�́A�匠�̋y�Ԏ����̊NJ����Ɍ�����̂ł��邩��A�����̊NJ��͈͓��ɂ����Ă̂ݑÓ�������̂ł���A�K�@���̋y�Ȃ��O���ł̊O���l�ɑ���s�ׂɂ����Đ������Ȃ��͓̂��R�ł���B
�@�{���ې�́A��T�i�l�̓��������y�Ȃ��O���ł̊O���l�ɑ���s�ׂł���A���Ɩ����ӂ��K�p���ꂤ��͈͂���͂���Ă���̂ł���B�@�Ƃ��낪�A�������́A�u�m���ɁA���ĂŎ匠�����ӂ̖@�����p����Ă����ߒ��ɂ����āA������̂����w�x�z�҂Ɣ�x�z�҂̎������x��w���ƂƖ@�����̎������x�̘_�������@�����x������̂Ƃ��ď�����ꂽ���Ƃ��������Ɖ������v�i�������Q�R�Łj�ƁA�w�x�z�҂Ɣ�x�z�҂̎������x��w���ƂƖ@�����̎������x�����Ɩ����ӂ̖@���_�I�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�F�߂Ȃ���A�����̖@���_�I��������K�R�I�ɍ��Ɩ����ӂɂ͏ꏊ�I���E�������邱�Ƃɂ��Ă͌��y�����A�_�_�����炵�āA�u�����̉䂪���̖@�̌n���A���͓I��p�̔�Q�҂��O���l�ł���ꍇ�ɂ��̊O���l�ɑ��Q������������t�^���Ă������Ƃ����������͉���F�߂��v�Ȃ����Ƃ������āA�u���{�l���O���l�����������Ɩ����ӂ̖@���̓K�p���Ă������̂ƍl������v�Ƃ�����������_���o���Ă��܂��Ă���B
�@���������������A�O�q�����u�p�i�C�������v�ł́A���Ɩ����ӂ͓K�p���ꂸ�A��T�i�l�́A���Q�������s���Ă���̂ł��邩��A�������̔����́A�����ƈقȂ��Ă���B
�@�@(4) �O��̂Ȃ��{���ې�
�@�������́A�u���{�l���O���l�����������Ɩ����ӂ̖@���̓K�p���Ă����v���Ƃ̍����Ƃ��āA�u�����@�̗��Ăɐ[���֗^�������B���A�O�L�̂Ƃ��荑�Ɩ����ӂ̖@���̍������s�����̉~���ȉ^�p�ɋ��߂Ă������Ƃɂ���Ă����t������v�Ɣ�������B
�@�{���ې�́A�u���{�̓������̋y�Ȃ��O���ł̊O���l�ɑ���s�ׁv�ł��邪�A����ɂƂǂ܂炸�A�푈�s�ׂł���A�܂���@�Ȑ푈�ƍߍs�ׂł���B���Ɂu�s�����̉~���̉^�p�v���A�O���ł̊O���l�ɑ���s�ׂƂ��đ��݂����Ƃ��Ă��A����͉��炩�̓����s�ׂƂ��Ă݂̂��肤��̂ł����āA�{���ې�̂悤�Ȑ푈�s�ׁA�܂��ēG���̏Z�����ʂɎE������Ƃ����O��̂Ȃ��푈�ƍߍs�ׂ��A�u�s�����̉~���ȉ^�p�v�ƌĂׂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ͖����ł���B�������̘_���ɏ]�����Ƃ��Ă��A�{���ې�ɍ��Ɩ����ӂ�K�p������]�n�͂܂������Ȃ��̂ł���B
�@�@(5) ���{�ɂ����闧�@�҈ӎv
�@�Ƃ���ŁA�������́A�w�x�z�҂Ɣ�x�z�҂̎������x��w���ƂƖ@�����̎������x�̖@���_���A���Ăɂ����č��Ɩ����ӂ̗��_�I�����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�F�߂Ȃ���A���{�ɂ����ẮA�u�s�����̉~���ȉ^�p�v�Ƃ������@�҈ӎv�����Ɩ����ӂ̍����ƂȂ����Ɣ������Ă���B
�������A����������ƈقȂ��Ă���B
�@�u�@���撲�ψ���E���@���č��Y�ґ�R�V�R���Ɋւ���ӌ��v�ɂ��A�@���撲�ψ��̍����ψ��́A���Ƃ��u�l���m�����v��N�Q�����ꍇ�ɁA�����ӔC�����Ƃ����������グ�āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u����ɍ��Ƃ̐������u����҂͐���X�����嫂��v����ɑ��̎傽��ړI�͐l���̌�����ی삵�y�эK���i����ɍ݂�Đl���ɊQ��������҂ɔ̂Ɉ���w�҂͞H�����Ƃ͈����ׂ����Ɣ\�͂��Ɛ��ɑR�营�����č��Ƃ��ӂɔC����ꍇ�Ȃ��v�i���{�ߑ㗧�@�p���Q�X�ňȉ��j�B
���̍l���͑��̈ψ��ɂ����ʂł������B���̂悤�ɁA���Ɩ����ӂ̍����́A�����@���蓖���̗��@�҂̌����ɂ���Ă��A�u���ƂƂ͐l���̌�����ی삵�A�K���i��������̂ł���v�Ƃ����O��̂��ƂɁA���Ɩ����ӂ��_�����Ă���̂ł���A���Ɩ����ӂ̍����́A��͂�A�u�x�z�҂Ɣ�x�z�҂̎������v�u���ƂƖ@�����̎������v�Ȃ������Q�̈�v�ɋ��߂��Ă����̂ł���B
�@�����Ō����u�l���v�Ƃ́A���Ƃ����̌�����ی삵�A���̍K���i����ΏۂƂȂ�҂ł���A����͎����̊NJ��ɕ�����u�l���v�ł����āA�O���̊NJ��ɕ�����l�����܂܂Ȃ��B�O���̊NJ��ɕ�����l���ɑ��ẮA���Ƃ����̌�����ی삵����A���̍K���i���邱�Ƃ͑z�肳��Ă��Ȃ�����ł���B
�@�{���ې�ɂ����āA��T�i�l�ł�����{���ƁA�T�i�l�璆���l���Ƃ̊W�ɂ����ẮA���Ƃ��u�l���̌�����ی삵�y�эK���i����v�Ƃ����W�ɂȂ��ǂ��납�A��T�i�l�́A�����ʑ�ʎE�C�Ƃ�������Ȉ��A�Q���T�i�l��ɉ����Ă���̂ł���A���Ɩ����ӂ̑O��������Ă���̂ł���B
(6) �ȏ�̂悤�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���_��̍���������A���{�̗��@�҈ӎv������A���{���̊NJ��ɕ����Ȃ��O���l�ɑ��č��Ɩ����ӂ͓K�p����Ȃ��B
�@�O�q�̂Ƃ���A���̌��͍�p�ɂ���Đ�������Q�ɑ��Ă͍��͔����ӔC��Ȃ��Ƃ����̂����Ɩ����Ә_�ł��邪�A���͍�p�Ƃ́A���Ƃ��l�ɑ��Ė��߂����]�����������p�ł���B�����ł���A���߁A�������̋y�Ȃ������ɍݏZ���鑼�����A�������A��́A�x�z���ɂ���Ƃ������Ȃ��������ɂ܂ŁA�����ӂ̍R�ق��ʗp����ȂǂƂ������Ƃ�����悤�����Ȃ��B
�@�������ł���A�u�{���ې�ɂ���Q�͐��ɔߎS���r��ł���A�����{�R�ɂ�铖�Y�퓬�s�ׂ͔�l���I�Ȃ��̂ł������v�ƕ]�����A�u�w�[�O�i�n�[�O�j������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă���Ɖ�����̂������v�ƒf���Ă���B
�@�{�����܂ݖ}���ǂ̂悤�Ȏc�s�A�ȍs�ׂł����͍�p�̖��ɂ����đS�ĐӔC�����Ȃ��ȂǂƂ������s�s���Í������ɒʗp���锤���Ȃ��B���{�̎i�@�������A���̂悤�ɍ��ێЉ�ɒʗp���Ȃ��u��̂Č�Ɓv�̋�_�����Ɏ����ĂȂ��㐶�厖�Ɉێ����Ă��錻��́A�܂��Ƃɒp���ׂ��Q���킵������ł���B���{�����ېl���Љ��Ǘ������߂鏊�Ȃł���B
�@�S�@�n�[�O���̍����@���ɂ���āu���Ɩ����ӂ̖@���v�͔r������K�p����Ȃ�
�@ (1)�@�n�[�O���́A�P�X�O�V�N�I�����_�̃n�[�O�ɂ����ĊJ���ꂽ��Q��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ�B�����ɂ́A����c�ɎQ�������S�S�������������A���̌��͂͂P�X�P�O�N�P���ɔ��������B���{�͂P�X�P�P�N�ɔ�y���Ă���B
�@����A�P�X�Q�T�N�U���ɐ����u�W���l�[���E�K�X�c�菑�v�Ƃ����ɂ����čې�͋֎~����A�x���Ƃ����ꂪ���������P�X�Q�W�N����ɂ́A���ۊ��K�@�Ƃ��Ă��m�����Ă����B���{���{���A���c�菑�ɐ��蒼��ɏ������Ă���i�������A��y�����̂͂P�X�V�O�N�j�A���c�菑�����ۊ��K�@�̐������Ă��邱�Ƃ��[���ɔF�����Ă����B
�@���ۖ@�̍����@���y�э����@�ɋy�ڂ��e���ɂ��Ăِ͈��͂Ȃ��A���ۏ��ɒ�G���鍑���@�́A���ɓK������悤�ɉ��߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃɂ��ẮA�������@���̓��{�ɂ����Ă���e����Ă����B
�@���ۖ@�Ɉᔽ����s�@�s�ׂ����ƐӔC�������邱�Ƃ͈�ʍ��ۖ@�̌������炵�ē��R�ł��邪�A�{���ې�ɂ��āA�������́A�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�Ɉᔽ����s�@�s�ׂł���A��T�i�l�ɂ́A�n�[�O���R���Ɋ�Â����ƐӔC�������Ă����ƔF�肵���B
�@ (2)�@�Ƃ���ŁA���ۊ��K�@�Ƃ��Đ������Ă����n�[�O���y�уW���l�[�u
�E�K�X�c�菑�������@�����Ă���@�����ɂ����ẮA���Ɩ����ӂ̖@���͎咣�����Ȃ��B
�@�Ȃ��Ȃ�A�n�[�O���y�уW���l�[�u�E�K�X�c�菑�������@�������Ƃ������Ƃ́A���̎��̋K�肪�����@�I���͂�L���邾���łȂ��A���̈�@�s�ׂɔ����Đ��܂�鍑�ƐӔC�����Ɋւ��錠���`���W�����R�����@�����Ă���̂ł���B��T�i�l�ɔ��������n�[�O���R���Ɋ�Â����ƐӔC�́A���ۖ@�I���ʂɂ����ĂƋ��ɁA�����@�I���ʂɂ����Ă��������Ă���̂ł���B
�@���ɍ��Ɩ����ӂ̖@�������݂��Ă����Ƃ��Ă��A�{���ɓK�p���ꂤ�邩�ۂ��́A�u�����@�͍��ۖ@�ɓK������悤�ɉ��߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����m�������@�����ɂ���ĉ��߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B����́A���ۖ@�������@�����A�������@��������ʂɈʒu�Â�����{�̖@�������ł̓��R�̖@�I�v���ł���B���{���{���炪���R���K��ψ���̏�Ŗ��������悤�ɁA�u�ٔ����������@�Ə��Ƃ���������Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A��҂��D�悵�A�֘A�����@�͖����Ƃ���邩�C������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i�����_�ȁw���ېl���̒n���x�Q�U�S�ŁA����l���Ёj�B����́A�������@���ɂ����Ă��Ó����Ă����B
�����ꂩ�̍����@�̉��߂ɂ�荑�ۋ`���ᔽ�����������]�n������̂ł���A�i�@�ɂ́A���ۖ@�K���I�ȉ��߂��̗p���邱�Ƃ����߂��Ă���B���@�̕s�@�s�K����A���ۖ@�ᔽ�ɂ���Đ��������ƐӔC�E���Q�����𐿋�����@�ߏ�̍����Ƃ��ĉ��߂��邱�Ƃ́A�܂������\�ł���B��O�̔���ɂ����ẮA�w���ƈقȂ�A���ۖ@�ƍ����@�ʂɈʒu�Â��Ă����悤�����A���̏ꍇ�ɂ͌�@���D�悷��̂ł���A�{���ł͂P�W�X�W�N�ɐ����������@�ɑ��A�P�X�P�O�N�ɔ��������n�[�O���@�Ƃ��ėD�ʂɗ��B
�@�Ƃ��낪�A�������́A��T�i�l�Ƀn�[�O���Ɋ�Â����ƐӔC���������Ă��邱�Ƃ�F�肵�Ȃ���A���Ɩ����ӂƂ��������@�̖@���������āA��T�i�l�̔����ӔC��ے肵�A�u�����@�͍��ۖ@�ɓK������悤�ɉ��߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����@�̉��ߌ����ɔ����Ă��܂��Ă���B
�@���Ɩ����ӂƂ��������̖@���ƁA�n�[�O���Ƃ������ۖ@����G�����Ƃ��A���Ɩ����ӂ́A���ۖ@�ɓK������悤�ɉ��߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A�{���ɓK�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B�܂��āA���������ꂽ�K�肪�Ȃ��A�P�Ȃ����߂ł��鍑�Ɩ����ӂ̖@�������ۖ@�ɗD�悵�ēK�p���A��T�i�l�ɔ����������ƐӔC��ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�T�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v�͈�@���߂ɂ������A���݂̖@���߂Ɋ�Â��ٔ����ׂ�
�@ (1)�@���Ɩ����ӂ͓K�p���ꂸ���@�̕s�@�s�K��̓K�p�ɂ���Ĕ�T�i�l�̑��Q�����ӔC�͐�������B
�@��L�P�T���S�ɂ����āA�{���ې�ɍ��Ɩ����ӂ��K�p����Ȃ����Ƃ�_���Ă����B���Ȃ킿�A��P�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���́A������u����@�v�ɂ���Ă��A�����̊w���ɂ���Ă��A�܂����@�҈ӎv�ɂ���Ă��A�m�����Ă͂��炸�A�K�p���R���B���ł������B�܂���Q�ɁA�{���ې�̂悤�ȍ��ۖ@�ᔽ�̎c�s�Ȑ푈�s�ׂ́A�u�K�@�Ȍ��͍s�g�����v�Ɋ�Â��Ȃ����ƁA��R�ɁA���Ɩ����ӂ̖@���̏ꏊ�I���E���i�O���ł̊O���l�ɑ���s�ׂɂ͓K�p����Ȃ��j�A��S�ɁA�n�[�O���̍����@���ɂ��A���ۖ@�ɓK�����������@�̉��ߓ��ɂ���āA�{���ې�ɍ��Ɩ����ӂ̖@���͓K�p����Ȃ��̂ł���B
�@���Ɩ����ӂ��K�p����Ȃ��ꍇ�A���s���@�̕s�@�s�K��ɂ���āA��T�i�l�̔����ӔC���������邱�Ƃ́A��O�̔��Ⴉ������炩�ł���B
�@����ɁA��L��P�����S�̖{���ې�ւ̍��Ɩ����ӕs�K�p�̍����́A�{���ې킪�A���{�����@���̌����_�ł̖@���߂ɏ]���čق����ׂ��ł��邱�Ƃ����̂ł���B
�@�u�ߋ��̖@���̉��߂́A�ߋ��̎��_�ł̉��߂ɏ]���ׂ����A�����_�ł̓����̖@�߂̉��߂����ׂ������_�_�ł��邪�A�������@����ł����A�����͂̍s�g�ɂ��Ė��@��K�p������߂����������ƂɏƂ炷�ƁA���_�I�ɂ́A�����̍ٔ����Ƃ��ẮA�����̔���ɏ]���Α����̂ł͂Ȃ��A�����̖@�߂̉��߂������_�ł��Ȃ����ׂ��v�i�����N���w���Ɣ����@�x�L��t�S�P�Łj�Ȃ̂ł���B
�@�@(2)�@�i�ז@��̋~�ώ葱�̌��@�Ƃ��Ă̍��Ɩ�����
�@���Ɩ����ӂ̖@���́A�����@�i����@�j��̉��߂Ƃ��ẮA�i�ז@��̋~�ώ葱�����@���Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����i��̖@���ł���Ɖ�������Ȃ��B���̓_������A���Ƃ̔����ӔC�́A�����_�ł̖@���߂ɂ���ĂȂ����ׂ��ł���B
�@���Ɩ����ӂ̖@���́A���̖��m�ȍ��������߂悤�Ƃ���ƁA�s���ٔ����@�P�U���Ŕ�����������ߏo�������ƁA����і������@�U�P���Ō��͍s���ɂ��Ďi�@�ٔ����̊NJ���ے肵�����Ƃɂ��ڂ���B
�@�v����ɁA�����̍��Ɩ����ӂ̖@���̍����́A��������ٔ��NJ��Ƃ����葱�@�̗̈�Ɋւ�����̂ł����āA���̖@�㖾�m�ȍ����Ɋ�Â����̂ł͂Ȃ��B
�@��O�̑�R�@�̍ٔ���̒��ɂ́A���̓I�����ɂ��Ă͉����q�ׂ��ɖ��@�̓K�p��r�����Ă�����̂����邪�A�ٔ���̒��ɂ́A��������̖@�̖��ł͂Ȃ��A�葱�@�̖��Ƃ��Ĕ�������������݂���̂ł����āA�������@���ɂ�����ٔ���́A���Ɩ����ӂ̖@���̎��̓I������S���������ƂȂ��A���NJ��͈̔͊O�̖��ł��邱�Ƃ������ɓK�p�@���������|��錾���Ă����ɂ����Ȃ��Ƃ�������B���Ȃ킿�A���Ɩ����ӂ̖@���́A�i�@�ٔ����̊NJ��O�ł��邽�߂Ɏi�@�ٔ����Ƃ��Ă͓K�p�@���������Ƃ����i�葱�@��̗��R�������ƂȂ��Ă����ɂ����Ȃ��Ƃ�������̂ł���B
�@�����ł���A���{�����@�̉��ɂ����ẮA�s���ٔ������p�~����A�i�ׂ��i�@�ٔ����Ɉꌳ������Ă���ȏ�A���Ɩ����ӂ̖@����K�p���鍪���͑S���Ȃ��A�܂��A���Ƃ̔����ӔC�ɂ��Č����_�ł̖@���߂Ɋ���Ƃɉ��̎x����Ȃ��ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@(3)�@���Ɣ����@�����U���́u�]�O�̗�v�ɂ���
�@�������͍��Ɣ����@�����U���́u�]�O�̗�v�̋K��ɂ���āA�{���ې��ɍ��Ɩ����ӂ��K�p�����Ɣ�������B�������A���Ɣ����@�����U���́u�]�O�̗�v�Ƃ́A���@�����݂��Ȃ��]�O�̎��̖@�ɂ�邱�Ƃ��Ӗ����A��O�̈�̔�����߂ɏ]���K�v�͂Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��āA�ŋ߁A�����n���ٔ���������Q�T���Q�O�O�R�N�R���P�P�������́A�����l�����A�s�����Ɋւ��āA�u���Ɣ����@�����U���ɂ����āA�w���̖@���{�s�O�̍s�ׂɊ�Â����Q�ɂ��ẮA�Ȃ��]�O�̗�ɂ��B�x�ƋK�肳��A���@�̋K��̑k�y�K�p���ے肳�ꂽ�ȏ�A���@�{�s�O�̌������̌����͂̍s�g�̈�@�𗝗R�Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�Ɋւ��ẮA���@�̕s�@�s�ׂɊւ���K�肪�������̌����͂̍s�g�ɂ��Ă��K�p�����邩�ۂ��Ƃ������@�̉��߂ɂ䂾�˂��Ă����Ɖ�������ق��͂Ȃ��v�Ƃ��������ŁA�u��O�̍ٔ���y�ъw���ɏƂ炷�ƁA�w���Ɩ����Ӂx�Ȃ�s���́w�@���x���m�����Ă���Ƃ̗�����w�i�Ƃ��āA��L�̂悤�ȉ��߂��̂��Ă������Ƃ�������������̂́A�����_�ɂ����ẮA�w���Ɩ����ӂ̖@���x�ɐ������Ȃ�����������������������Ƃ��A�����炪�咣����Ƃ���ł���B���ٔ��������Ɣ����@���{�s�����ȑO�̖@�̌n�̉��ɂ����閯�@�̕s�@�s�ׂ̋K��̉��߂��s���ɓ�����A����@�㖾���̍�����L������̂ł͂Ȃ���L�s���̖@���ɂ���Ď���@�ɂ��̂Ɠ��l�̍S�����A���̍S���̉��ɖ��@�̉��߂��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͌���������v�ƁA�u�]�O�̗�ɂ��v���Ƃ��A���Ɩ����ӂ�K�p�����鍪���ƂȂ�Ȃ����Ƃ����Ă���B
�@�@(4)�@�����@���ɂ�����u���`�����̌����v�ɂ�����
�@���{�����@�P�V���́A���̔����ӔC�L���A���Ɩ����ӂ̖@����ے肵���B���݂̍ٔ����͓��{�����@�̉��l�����ɑ����Ė@�߂̉��ߓK�p�����ׂ��ł���A�ߋ��̖@�߂̉��߂ɂ��Ă��A�����_�œ����̖@�߂̉��߂��������ׂ��ł���B
�@�{���ې�́A���������F�肷��悤�ɁA�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�Ɉᔽ���A���c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ���A�������ӔC���߂��n�[�O�������R���Ɉᔽ����푈�ƍ߂̒��ł����ʂȎc�s���������Ă���B
�@�ە���̓����́A���̔�Q�͈̔͂�\�����邱�Ƃ����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƁA��퓬���ł����ʎs���̑�ʎE�C��_�����̂ł��邱�ƁA�퓬�s�I����ɂ����Ă����̐��ݓI�j��͂䂦�ɂQ�����s�A�R�����s�������N�����A�����Ԃɂ킽���Ēn��Љ�S�̂��`���a�̔����E�����̊댯�ɂ��炳��邱�Ƃɂ���B
�@�{���ې�̔�Q�n�̓��A���]�Ȃ̋`�G�s�A���z�s�A�`�G�s�̐��R���A�`�G�s�����F�́A���{�R���ˏB�s�ɓ��������ۂɂ���Ĕ��������y�X�g���`�d���A����̋]���҂��̂ł���B�ˏB�s�ł͐��ɂ�����܂Ńy�X�g�̗��s���������̂ł���B
�@���̂悤�ȑO��̂Ȃ��c�s�Ȕ�l���I�s�ׂ��A���Ɩ����ӂ̖@�����ɂ���Ă��̐ӔC�����ꂸ�A��Q�҂��~�ς���Ȃ����Ƃ́A�u���`�����̌����v�ɒ�������w����B
�@��O�̖@�I�A����I����̉��ł��A�@�̐��`�̌��n���疯�@�̓K�p�͈͂��g�債�āA�u���A�����c�̂̑��Q�����ӔC�Nj��̓��v���J������O������̓w�͂̉ߒ������邱�Ƃ́A���łɏq�ׂ��B�����������Ɣ����@�́u�]�O�̗�v�Ƃ����K��������āA���Ɩ����ӂ�K�p���A�T�i�l��̔��������̓�������Ă��܂����Ƃ́A��L��O����̓w�͂̉ߒ��ɋt�s������̂ł���A������܂����`�����̌����ɔ�������̂ł���B
�@�{���ې�̂悤�ɁA���Q�s���ƍٔ����ŁA���̔����ӔC�ɂ��Ẳ��l�����͑傫���]�����Ă���A�������A���Q�s���ɂ����āA���̔����ӔC��ے肷�鍑�Ɩ����ӂ̖@�����A�m�肵���@���Ƃ��Ċm�����Ă����킯�ł͂Ȃ��A��@���߂ɂ����Ȃ����̂ł����Ȃ��ꍇ�A����ɁA���̉��Q�s�ׂ��j��ޗ�̂Ȃ��c�s�Ȑ푈�ƍ߂ł���ꍇ�A���ʂƂ��ē��{�����@�̉��l�����Ɛ^�������甽���錋�_�����Ƃ́A�@�̉��ߓK�p�Ƃ��ċ�����邱�Ƃł͂Ȃ��B�ٔ����́A���݂̓��{�����@�̉��l�����Ɋ�Â��Ė@���߂��ׂ��A�����_�̖@�����ɓK�����錋�_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�U�@�܂Ƃ�
�@�T�i�l��y�т��̑㗝�l��́A�{���ɂ��ē��{���{����Q�҂ɎӍ߁A�������邱�Ƃ��A���{�̍��ۓI�M�������߁A�����Ƃ̐^�̗F�D�A���a��z�����Ƃɒ������A�]���ċ��K�ɑւ�����v�ƂȂ�Ɗm�M����̂ł��邪�A��T�i�l�͕K���������̂悤�ɍl���Ă͂��Ȃ��悤�ł���B
�@�������A�ٔ����́A���ꂪ���v�ɉ������ȂǂƂ��������I�z��������K�v���Ȃ��A�ނ���z�����ׂ��ł͂Ȃ��B�ٔ����ɖ]�ނ��Ƃ́A���v�@���ɍS�炸�A�����܂ŏ����ɁA���`���������Ă������������Ƃ������Ƃɐs����̂ł���B
�@���ꂱ����R�@���E�����ی��ȗ��̎i�@�̂���ׂ��p�ł���B
��R�@�����E���˂̕s�K�p
�@�P�@�����͖����������Ă��Ȃ�
�@�@(1)�@���@�V�Q�S��O�i�y�ь�i�̖@�I����
�@���@�V�Q�S����i�̂Q�O�N�̊��Ԃ̖@�I���i�́A���̗��@�̉��v�A���@��|�A�@���̕����A�s�@�s�אӔC�ɂ��Ď����Ƃ��ē�d�̊��Ԑ�����݂��Ă��鏔�O���̗��@��A�y�є�Q�҂̌����s�g�͗\�����Ȃ��O���I����ɂ��W�����邱�Ƃ��������Ƃ��l������ƁA�������Ԃ��߂����̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@�����āA���@�V�Q�S��O�i�ɒ�߂�R�N�̎������Ԃ́A�����҂̌����s�g�̌�������̓I�ȉ\���̑��݂Ƃ�������ȏɑΉ��������ȒZ�������ł���̂ɑ��āA������i�ɒ�߂�Q�O�N�̎������Ԃ́A���̂悤�ȓ���Ȏ���̗L���Ƃ͖��W�ɁA�������̐���������i�s���J�n���A�Q�O�N�̌o�߂ɂ�芮������ʏ�̎����ł����āA�s�@�s�אӔC�́A�����Ƃ��Ēʏ�Q�O�N�̎����ɂ�����A���ɔ�Q�҂ɂ����đ��Q�y�щ��Q�҂�m��A�����s�g�̌����I�\��������ꍇ�Ɍ����āA�ʏ�̂Q�O�N�̎����̊�����҂����ɂR�N�̎����̊�����F�߂�Ƃ������Ƃɂ����Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B
�@�@(2)�@���@�V�Q�S���̒�߂���Ԃ̋N�Z�_
�@�@�@�A�@���_
�@���@�V�Q�S��O�i�̂R�N�̊��Ԃ̋N�Z�_�́A��Q�҂��A�q�ϓI�Ɍ����s�g���\�ȏ̉��ɂ����āA��̓I�Ȏ����W�Ɋ�Â��ĉ��Q�҂ɑ��錠���s�g���ł��邱�Ƃ�F�������Ƃ��Ɖ����ׂ��ł���B
�@�܂��A���@�V�Q�S����i�̂Q�O�N�̊��Ԃ̋N�Z�_�ɂ��ẮA���Q�s�ׂ̎��ł���Ƃ��錩�������邪�A�����������Ă��Ȃ������̎����i�s��F�߂邱�ƂɂȂ肩�˂��A�s���ł���B�s�@�s�ׂ̑����́A�\�����Ȃ��ɔ���������̂ł���A�܂������s�ׂƑ��Q�Ƃ̈��ʊW�̔����E��������ȏꍇ��������A��i�܂Ŏ��Ԃ̂�������̂������B�܂��푈�ȂǎЉ�I�Ȏ���ɂ��A��Q�҂̌����s�g�������Ԃɂ킽���ĕs�\�ɂȂ�ꍇ����ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���@�V�Q�S���̗��@��|�́A�s�@�s�ׂɂ���đ��Q��ւ�����Q�҂̕ی�ɂ���A������i�̂Q�O�N�̊��Ԃ̋N�Z�_�́A�s�@�s�ׂ̍\���v�����[�����ꂽ�Ƃ��A���Ȃ킿�A���Q�s�ׂ݂̂Ȃ炸�A���Q���������Ĕ�Q�҂̌����s�g���q�ϓI�A��ʓI�Ɋ��҂ł���ɂȂ����Ƃ��Ɖ����ׂ��ł���B
�@�����āA���Q�s�ׂ��玞�Ԃ��o�߂��đ��Q����������ꍇ�ɂ́A���̑��Q�̔������_�ł��鑹�Q�����������̐������_����A�����̐i�s���J�n������̂ƍl����ׂ��ł���B
�@�@�@�C�@�{���ɂ����閯�@�V�Q�S��O�i�̎������Ԃ̋N�Z�_
�@�@�@�@���@���ؐl�����a���́A�P�X�S�X�i���a�Q�S�j�N�ɐ������A�����{�y�������I�Ɏx�z���Ă����ɂ�������炸�A�P�X�T�Q�i���a�Q�V�j�N�ɒ������ꂽ�T���t�����V�X�R���a���̒�����O���ꂽ���߁A���{�ƒ����́A����f��̏�Ԃ��������B
�@���̌�A�P�X�V�Q�i���a�S�V�j�N�̓��{���{�ƒ������{�̋��������i�ȉ��u�������������v�Ƃ����B�j�ɂ���āA���������퉻����A����ɁA�P�X�V�W�i���a�T�R�j�N�P�O���Q�R���A�������a�F�D���̒����ɂ���āA���߂Ė{�i�I������ȍ��ƊW�̊�b���m�����ꂽ�B
�@���{�ɑ��钆�����Ԑl�̑��Q���������̖��́A�P�X�X�P�i�����R�j�N�R���A��V���S���l����\����S���c�ɂ����āA���ƊԂ̐푈�����Ɩ��Ԃ̔�Q��������ʂ��A�O�҂͓������������ŕ������ꂽ���̂́A��҂́A�����̖��Ԑl��Q�ҋy�т��̈⑰�́A���{�ɑ��đ��Q�����������ł���|�̉Ȋw�H�ƕ������Ǘ��w�@�@�w�������̈ӌ����ɂ��A���߂Č��̏�Ŏ��グ��ꂽ�B
�@���̌�A�]���Ǝ�Ȃ́A�P�X�X�Q�i�����S�j�N�S���A�����푈���̖��Ԕ�Q�ɂ��ẮA���݂ɋ��c���ď𗝂ɂ��Ȃ��`�őÓ��ɉ������ׂ��ł��邱�Ƃ��咣���Ă����|�̔������s�����B����ɁA�K��?�O���́A�P�X�X�T�i�����V�j�N�R���X���A�Γ��푈�������ɂ��āA�������������ŕ��������͍̂��ƊԂ̔����ł����āA�l�̔��������͊܂܂ꂸ�A�����̐����͍����̌����ł���A�������{�͊����ׂ��łȂ��|���������B
�@���̂悤�ɁA�T�i�l�炪�A��T�i�l�ɑ��A�{�i���N���邱�Ƃ������I�Љ�I�ɉ\�ƂȂ����̂́A��L�K��?�O���̂P�X�X�T�i�����V�j�N�R���̔����ȍ~�ł���A����ȑO�ɍT�i�l�炪�{�i���N���邱�Ƃ͕s�\�ł������Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@�@�@���@�T�i�l�炪�{�i���N����ɂ́A�X�ɖ{���ې�̋�̓I�Ȏ���
�W�𖾂炩�ɂ��A����𗠕t���鎑�����K�v�ł��������A��T�i�l�͐���т��čې�̎������B�����Ă����B�����Q�҂ł����T�i�l�̐ӂɂ��A�T�i�l��͖{����i��j�Q����Ă����̂ł���B
�@�P�X�X�R�N�ɁA�g���`�������炪�h�q���h�q�������}���ق����J������{�����ȂǁA���R�����̒������Z�̈�{�F�j�卲���̋Ɩ���������A�ە���̎���g�p�����R�����̎w���ōs��ꂽ���Ƃ��������A���̓��e���P�X�X�T�i�����V�j�N�P�Q���Ɋ�g�u�b�N���b�g�w�V�R�P�����ƓV�c�E���R�����x�Ƃ��ďo�ł���A�ە���̎���g�p�����炩�ɂȂ����B
�@����܂ł́A���{�����ł́A�V�R�P�������ە���̌����̎����ōs���Ă��邱�Ƃ͎��m�̎����ɂȂ��Ă������A�ې�͎��m�̎����ɂȂ��Ă��Ȃ������B��T�i�l�́A�ې�̎��������{�����ɒm����悤�ɂȂ��Ă�����A�������m�F�ł��Ȃ��Ƃ��āA���̐ӔC��ے肵�������B
�@���̂悤�Ȕ�T�i�l�̑ԓx�ɋ^���悵�����{�l�ٌ�m�炪�A�P�X�X�T�i�����V�j�N�P�Q���ȍ~�A�͂��Ȏ肪��������Ƃɖ{���ې�̔�Q�҂��K�ˁA�����̗L�����m���߂邽�ߕ������݂Ȃnj��n�������J��Ԃ����B���̌��ʁA�{���ې�̎������m�F�����B
�@�ې��Q�҂炩��{���i�ׂɂ��ċ��͂����߂�ꂽ���{�ٌ̕�m��́A�{���i�ׂɔ����@�I�Ȗ��_�⏔��p�̕��S��������������A�P�X�X�V�i�����X�j�N����{���i�ׂ���C���邱�Ƃ����߁A�����ȈϔC���A�P�X�X�V�i�����X�j�N�W���P�P���ɑ�ꎟ��i���N�����B���̌�A�����e�n�ɒ����ψ���ݒu����A�ې��Q�̎��Ԓ������s���A�P�X�X�X�i�����P�P�j�N�P�Q���X���ɑ�Q����i���N����Ɏ������B
���@���̂悤�Ȍo�߂ɏƂ点�A�ې��Q�҂炪�A�{���ې�̋�̓I�����Ɋ�Â��čې��Q�҂�ɑ����T�i�l�̕s�@�s�ׂ���肷�邱�Ƃ��ł��A��T�i�l�ɑ��鑹�Q�����������̍s�g���\�ƂȂ����̂́A�����Ɠ��{�ٌ̕�m�̎x���A���͂����t���邱�Ƃ��ł����P�X�X�V�i�����X�j�N�̎��_�ł���B
�@���������āA���@�V�Q�S��O�i�̂R�N�̎������Ԃ̋N�Z�_�́A�P�X�X�V�i�����X�j�N�̎��_�ł���A�{����P���i�ׂ̒�N�͓��N�W���P�P���A��Q���i�ׂ̒���͂P�X�X�X�i�����P�P�j�N�P�Q���X���ł��邩��A������ɂ����Ă������͊������Ă��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@�@�E�@�{���ɂ����閯�@�V�Q�S����i�̎������Ԃ̋N�Z�_
���@�P�X�V�W�i���a�T�R�j�N�P�O���Q�R���̓������a�F�D�������܂œ��������͖@�I�ɐ푈��Ԃɂ������B
�@�T���t�����V�X�R���a���̕t���c�菑�u�a�@�������ԁv�̑�P���ɂ́u�l���͍��Y�ɉe������W�ŁA�푈��Ԃ̂��߂Ɏ��Ȃ̌�����ۑS����̂ɕK�v�ȑi�s�ז��͎葱�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̋c�菑�̏������̍����ɌW����̂ɂ��đi�̒�N���͕ۑ��[�u�����錠���Ɋւ��邷�ׂĂ̎������Ԗ��͐������Ԃ́A���̊��Ԃ��푈�̔����̑O�ɐi�s���n�߂������͌�ɐi�s���������킸�A������{���̗̈�ɂ����āA�푈�̌p�������̐i�s���~���ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��B�����̊��Ԃ́A�{���������ꂽ���a���̌��͔����̓�����Ăѐi�s���n�߂�B�v�ƋK�肳��Ă���B
�@����́A�푈��Ԃɂ���Ԃ́A���̓������̍��������荑���ɑ����Ȃ̐��������s�g���邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ŁA�푈�̌p�����i�������a����܂ł̊ԁj�͎������͐������Ԃ��i�s���Ȃ��Ƃ����@�����m�F�I�ɋK�肵�����̂ł���B�����̓T���t�����V�X�R�u�a���̓����҂ł͂Ȃ����A���̎����K��̖@���́A�����Ƃ̕��a�������ɂ����Ă����p���ꂤ��̂ł���A���Ȃ��Ƃ������������@�I�ɐ푈�p����Ԃɂ������P�X�V�W�i���a�T�R�j�N�P�O���Q�R���܂ł́A�����͐i�s���Ȃ������B
���@�܂��A�O�q�����悤�ɁA�Q�O�N�̊��Ԃ̋N�Z�_�́A�s�@�s�ׂ̍\���v�����[�����ꂽ�Ƃ��A���Ȃ킿�A���Q�s�ׂ݂̂Ȃ炸�A���Q���������Ĕ�Q�҂̌����s�g���q�ϓI�A��ʓI�Ɋ��҂ł���ɂȂ����Ƃ��Ɖ����ׂ��ł���B
�@���̓_�ŁA�T�i�l��͎�����̐ӂɋA���Ȃ����R�ɂ��A�{����i���s�\�ȏɂ�����Ă����B���Ȃ킿�A��T�i�l�̉B���s�ׂɂ���āA�O�L��{�����̔��������P�X�X�R�N�܂ł́A�T�i�l��͖{����i�̉\����j�Q����Ă���A�܂��A�O�L��L�K��?�O���̂P�X�X�T�i�����V�j�N�R���̔����܂ł́A�T�i�l�炪�{�i���N���邱�Ƃ͐����I�Љ�I�ɕs�\�ł������B���������āA�Q�O�N�̊��Ԃ̋N�Z�_�́A�T�i�l��̌����s�g���q�ϓI�ɉ\�ɂȂ����P�X�X�T�N�ɂ����ׂ��ł���B
���@����ɁA�{���ې�́A���ۖ@�Ɉᔽ����푈�ƍߍs�ׂł���A���Q�҂����T�i�l�́A�T�i�l���Q�҂ɑ��A��Q�̌p���E�g���h���ׂ��ی�`�����Ă����̂ł���A�{���ې�ɂ�萶������Q�̉�}��[�u���̂�ׂ��ł������B�������A��T�i�l�́A�����̕ی�`�����ʂ����Ȃ��������肩�A���A����쐬�����V�R�P�����W������p���������ď؋��Ǝ����̉B����}��A������̏�ɂ����Ă��ې�̎�����F�߂��A�����ɑ���푈�ӔC���ے肵�����Ă����̂ł����āA�T�i�l��ɑ��A��̔����A�Ӎ߂��s���Ă��Ȃ��B
�@��T�i�l�̂����̍s�ׂɂ��A�ې��Q�҂�͑����̉Ƒ��������A���ɂ����čK�������c�����ې��Q�҂�����ʁA�Ό���A���_�I�Ȃ����g�̓I��ɂɋꂵ�߂��A���̔�Q�͂��܂��p�����Ă���B
�@���������āA�T�i�l��̎咣�����T�i�l�̉��Q�s�ׂ́A���݂��p�����Ă���̂ł����āA��T�i�l�ɑ��鑹�Q�����������ɂ��ẮA���������͐i�s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�@
�@�Q�@�{���ې�ɂ����Ď����E���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����ׂ��ł���
�@�@(1)�@�����E���ˊ��Ԃ̐��x�ɂ����鐳�`�ƌ����̗v��
�@���Q�҂ɂ�閯�@�V�Q�S���̎������p�y�т��̌��ʂ��A���������`�A�����ɔ�����Ƃ��́A���̎������p�͌����̗��p�ɓ�������̂Ƃ��Ĕr�˂����ׂ��ł���B
�@�܂��A���ɁA������i����̂Q�O�N�̊��Ԃ����ˊ��Ԃł���Ƃ��Ă��A���̓K�p�����������`�A�����ɔ����A�𗝂ɂ��Ƃ�Ƃ��́A������i�̋K��͓K�p�����ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�����āA���@�V�Q�S���̓K�p�����������`�A�����ɔ����邩�ۂ��́A��̓I�ɂ́A�@��Q�҂̌����s�s�g�ɑ�����Q�҂̉��S�A�A�����҂̌����s�s�g�ɑ�����̌��@�A�B�����ɂ����Q�ҕی�̕s�K�i���A�C�����E���ˊ��Ԃ������炷���ʂ̒������s���`�E�s�����Ƃ�������������l�����Ĕ��f���ׂ��ł���B
�@�@(2)�@�{���ɂ����鎞���E���ˊ��Ԃ̓K�p�̐���
�@�@��Q�҂̌����s�s�g�ɑ�����Q�҂̉��S�ɂ���
�@�T�i�l�̖{���s�@�s�ׂ́A���{�̒����N���푈�ɂ�����ې�̎��s�Ƃ����A�j��ޗ�̂Ȃ��c�s�ȍs�ׂł���B���̂��Ƃ́A���@�V�Q�S����i�̓K�p�ɓ������ď\���Ύނ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�f�ł���B
�@��T�i�l�̖{���s�@�s�ׂ́A��퓬�������ʏZ�����ʑ�ʂɎE�C���邱�Ƃ�_������@���̋ɓx�ɍ����c�s�s�ׂł���B�ې킪�����炵�������ǂɂ���ċ]���ҁA��Q�҂ƂȂ����T�i�l��ɂ͉��̗��x���Ȃ��A������ˑR�����s���̉u�a�ɂ���ċꂵ�߂��A�]���ƂȂ����̂ł���B���̔�Q�҂��Ȃ��~�ς��ꂸ�ɐ��\�N�ԕ��u����A����A���̉��Q�҂ł����T�i�l�����̐ӔC���ʂ������ɍ����Ɏ����Ă���Ƃ�������ɂ����āA���̌o�߂́A��Q�҂̌������ł������炷���̂ł͂Ȃ��A�ꍏ�������T�i�l����Q�������A�T�i�l���Q�҂��~�ς��ׂ����Ƃ𔗂���̂ł���B
�@����ɖ{���ې�̈�@�s�ׂɂ����āA�ɂ߂Č����ȓ����́A��T�i�l���A���ɂ����čې�̎������B�����A���ۓI�����I�ɓ��{�R�̍ې킪���m�̎����ƂȂ��Ă��錻�݂ɂ����Ă��A���̎�������F�߂Ă��Ȃ��Ƃ����_�ł���B
�@��T�i�l�́A�s�풼�O�ɁA�����ł͂V�R�P�����{�����̎{�݂�j�A�l�̎����̂��߂Ɏ��e���Ă����ߗ��́u�}���^�v��S���E�Q���A�V�R�P���������������P�ނ������B���{�ł́A�s��Ɠ����ɁA���R�ȌR���ۓ��̖��߂ɂ��ې�W���̓��{�R���������̏ċp�E�B�������B
�@�܂��A�P�X�S�V�N�A��T�i�l�́A�B�����Ă����V�R�P�����W�̕�����Ɛӂƈ��������ɕč����{�Ɍ�t���A�푈�ƍ߂̐ӔC�Njy�ꂽ�B
�@�P�X�W�O�N��ɓ���A�ې�̎������\�I����n�߂�ƁA��T�i�l�́A�{���ې�ɑ���ӔC��Njy����邱�Ƃ�����A��{�����Ȃǂ̖h�q���y�ѕč�����̕ԊҎ����̕ۊǎ������B�����A�{���ې�̎����m�F�Əؖ�������ɂ����B
�@�P�X�X�R�N�A�g���`�������炪�h�q���h�q�������}���ق����J������{�����Ȃǂ���ې�̋L�q�����A�P�X�X�T�N�P�Q���Ɋ�g�u�b�N���b�g�Ƃ��Ĕ��\���A�ې�̎������Љ�I�ɖ��炩�ɂȂ�ƁA��T�i�l�́A��{���������J�ɂ���[�u���Ƃ����B
�@��{�����́A��{�F�j����{�c�Q�d�{�����Ȃǂ̗���ŁA�V�R�P��������̒��ڂ̘A�����Ɩ������Ƃ��āA�{���ې�̌v��A�����A���s�y�т��̌��ʂɂ��ďڍׂɋL�ڂ������̂ŁA�Ⴆ�Ώ퓿�ې�̎��s�̓����A�ꏊ�A���s�����o�[�A�g�p�ۂ̎�ʓ��̓��e�͐��m�ł���A���̈�{�����Ȃǂ̔�T�i�l���ۊǂ��镶����p����A�{���ې�̎��Ԃ́A����w�𖾂����͂��ł���B
�@�������A�T�i�l��́A���R�ɂ����Ă��A��{��������{�F�j�l�̖h���^�ɂ����Ȃ��ȂǂƔF�߂�ɂƂǂ܂�A�����𖾂��s�����Ƃ�S�����Ȃ��B
�@�܂��A��T�i�l�́A�P�X�T�O�i���a�Q�T�j�N�R���̏O�c�@�@���ψ���ɂ����钮���c���̎���A�P�X�W�Q�N�S���̏O�c�@���t�ψ���̍匴�c���̎���A�P�X�X�V�N����P�X�X�W�N�̎Q�c�@���Z�ψ���ł̌I���N�q�c���̎���A�P�X�X�X�N�Q���̏O�c�@�\�Z�ψ���ł̓c���b�c���̎���ŁA�ĎO�A���������ɂ�������Ă���ɂ�������炸�A�����钲������ؑӂ��Ă���B
�@�����ɁA��T�i�l�́A�u���������݂��Ȃ��v���Ǝ����ƈقȂ铚�قŁA�{���ې�̎����𐳎��ɔF�߂Ă��Ȃ��B
���̂悤�Ȕ�T�i�l�̉B���s�ׂ́A�T�i�l��̌����s�g�����W�Q���Ă����B���ۂɑ��݂��Ă��鎑�����J�������A��{�������̑��݂��������Ă��A�Ȃ��u���������݂��Ȃ��v���ƌ�������悤�Ƃ���{���ې�̉B���s�ׂ́A�ɂ߂Ĉ����ŁA�T�i�l��̌����s�g���Ӑ}�I�ɖW�Q����V���ȕs�@�s�ׂł���B
�@�{���T�i�l��̌����s�s�g�́A��T�i�l���ꍑ�̌��͂������čT�i�l��̌����s�g��W�Q���A�s�\�ɂ��Ă������ʂȂ̂ł���B
�@�@�@�A�@�T�i�l��̌����s�s�g�ɑ�����̌��@
�@�T�i�l��̐��̐����́A���ɋꂵ�����̂ł������B���{�̐N���푈�ƁA���̌�̓���ɂ��s�s�A�_���̍r�p�ɉ����āA�T�i�l��́A�ې�̔�Q�҂ł��邱�Ƃɂ��ꂵ�݂��˂Ȃ�Ȃ������B�{���ې��Q�n�ɂ����āA�T�i�l��̑����́A��ʗ��s�̉u�a�ɂ��������҂Ƃ��Ĉ����A�푈�̔�Q�҂Ƃ��Ă̐����ȕ]�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�{���ې�ɂ���Q�n�Z���́A���������ɂ킽���ĉu�a�̋��|���瓦��邱�Ƃ��ł����A�n��Љ�Ƃ��Ă̕����͍���ƂȂ����B�܂��A�u�a�����n�Ƃ��ĎЉ�I�ȍ��ʂ��A�o�ϓI���Љ�I�s���v��ւ炴�邦�Ȃ������B
���̂悤�ɁA�O�L�T�i�l�ɂ��B���s�ׁA�P�X�V�Q�N�܂Œf�₵�Ă��������W�A�������������ɂ����钆�����{�̔������ւ̑Ή��Ȃǂ̋q�ϓI�Љ�I�ɉ����A�T�i�l��̂����ꂽ����������A�P�X�X�T�N���܂ł́A��T�i�l�ɑ��鑹�Q�������������s�g���邱�Ƃ͎�����s�\�ł������B
�@����ɁA�T�i�l�炪�{���i�ׂ��N���邽�߂ɂ́A�����Ɠ��{�ɁA������x�����A�㗝�l�ƂȂ��Ċ�������ٌ�m���K�v�s���ł������̂ł���A���̂悤�ȕٌ�m�̊��������{�ŋ�̉������̂͑�P���i�ׂ̍T�i�l��͂P�X�X�T�N�P�Q���ȍ~�ł���A��Q���i�ׂ̍T�i�l��ɂƂ��Ă͑�P���i�ׂ��N�����P�X�X�V�N�W���ȍ~�ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�T�i�l�炪�{����i�Ɏ���܂Ō����s�g���ł��Ȃ������Ƃɂ��āA�T�i�l��ɂ͑S���ӂ��Ȃ��A�T�i�l�炪�����̏�ɖ����Ă��̌����s�g���ԑӂ��Ă����Ƃ��������͂Ȃ��B�T�i�l��́A�i�ג�N���\�ƂȂ��A���₩�ɖ{���i�ׂ̒�N�ɋy�̂ł���B
�@�@�@�B�@�����ɂ���T�i�l�ی�̕s�K�i��
�@���������F�肷��悤�ɁA�{���ٔ��̔�Q�n�W�����S�̂̍ې�ɂ�鎀�S�҂̐��͂P���l����B���������̐����́A�ې�ɂ��]���҂̈ꕔ�ɂ����Ȃ��B
�@�ە���́A�퓬�̖ړI�Ɣ�r���ĕs�����Ȑ��i�̂��̂ł���Ƃ̋��ʔF����O��ɃW���l�[�u�E�K�X�c�菑�Ŗ����I�Ɏg�p���֎~���ꂽ���ۖ@�ᔽ�̕���ł���B���݂ł́A�P�X�V�Q�N�S���P�O���ɏ�������P�X�W�Q�N�U���ɓ��{����y�����͂����������ە���֎~���ɂ��A�g�p�݂̂Ȃ炸�J���A���Y�A�������A���ۖ@����֎~����Ă���B
�@�ې�́A�{�������~���ړI������w�I��i���A�����ʑ�ʂ̎E�C��i�Ƃ��Ďg���Ƃ����A�����Ȃ�Ӗ��ł������ꂴ��s�ׂł���B����́A�����̑����ɑ��镎�J�ł���A���̍���ɂ́A�����̐l������l�ԂƂ��Č��Ȃ���T�i�l�̖������ʂ��������B
�@���̂��Ƃ́A��T�i�l���A�����n���s���s���[�ɑn�݂��ꂽ�V�R�P�������̍ې핔���ɂ����āA���R�����̌v��A�w���̉��ŁA�R���^���̊W�ғ��ɑ��e��̐l�̎������s���Ȃǂ��āA�ە���̌����A�J���A�������s�������Ƃɂ�������Ă���B
�@�������Đl�̎����ɂ���ĊJ�����ꂽ�ە�����g���A��T�i�l�́A�����Z���ɑ��A�j�㏉�߂Ė{�i�I�ȍې�����s�����̂ł���B
�@���������āA�{���ې킪�A�����̍��ۖ@�͂��������{�̖@�K�ɏƂ炵�Ă���@�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͖����ł���B�܂��A��T�i�l�́A�|�c�_���錾����ɂ���āA�{���ې�ɂ��Ē����y�ы~�ϋ`���������A����𗚍s���邱�ƂȂ����݂Ɏ����Ă���B
�@�܂��A�{���i�ׂɂ����āA�T�i�l��́A��{�����y�ш�{�F�j�̏؋��ۑS��\���ċg���`�������̐l�؋y�ѓ������̒���̊�g�u�b�N���b�g�����Ƃ��Ē�o�����B�咣��������Ȏ���͑����Ȃ��ɂ�������炸�A��T�i�l�́A�T�i�l��̎咣�ɂ����鎖���ɑ��ĔF�ۋy�ы�̓I�Ȏ咣����؍s��Ȃ��B
�@�{����@�s�ׂ́A��r������ޗႪ�Ȃ��قLj����Ȉ�@�s�ׂł���B�����ɂ���T�i�l�ی�̗��R�͂܂������Ȃ��B�܂��A�������x�̑��ݗ��R���A�^�̌����҂�ی삵�A�ٍώ҂̓�d�ٍς�����邽�߂̐��x�Ɖ������Ƃ��Ă��A�܂��A�؋��U��ɂ��ؖ�������~�ς��邽�߂̐��x�Ɖ������Ƃ��Ă��A��T�i�l�̐ӔC�͖����ł���A��T�i�l�����Q�����ӔC���ʂ����Ă��Ȃ����Ƃ������ł���{���ɂ����ẮA�������͏��ˊ��Ԃɂ���T�i�l��ی삷�闝�R�͑S���Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@�@�C�@�����E���ˊ��Ԃ������炷���ʂ̒������s���`�E�s����
�@�{���ې�́A�����ɂ킽���čT�i�l��̐l�ԂƂ��Ă̑����݂ɂ���A�S�g�ɂ킽���ɂƔ�Q��^���������ɂ܂�Ȃ����Q�s�ׂł���B
�@�������A��T�i�l�́A���ɂ����Ă��T�i�l��ɑ��Ĉ�̎Ӎ߂��⏞�������A�{���ې�̎��������F�߂悤�Ƃ����A�T�i�l��̊�����������A��ɂ傳���Ă���B
�@�T�i�l��́A��������N�V���Ă���A�c���ꂽ�l���͒Z���B��T�i�l���T�i�l���Q�҂ɎӍ߂��A���̑��Q�������A��Q�҂��~�ς���K�v�͉}�̉ۑ�ƂȂ��Ă���B
�@�����̎�����l������ƁA�������͏��ˊ��Ԃɂ��A��T�i�l�����̐ӔC��Ƃ�邱�Ƃ́A���������`�A�����ɔ����A���̌��ʂ͏𗝂ɂ���������̂ł���B
�@�@(3)�@�ȏ�̂Ƃ���A�����ɂ���Ĕ�T�i�l�������ӔC��Ƃ�邱�Ƃ́A
���������`�A�����ɔ����A�𗝂ɂ��Ƃ邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�{���ې�̈�@�s�ׂ��A�����̓K�p�ɂ���Ă��̐ӔC��Ƃ�邱�Ƃ́A���{�����@�̍��ۋ�����`�A���a��`�ɂ���������̂ł���B���ۖ@�ɂ���Đ��������ƐӔC�ɂ́A���������˂��Ȃ��B��T�i�l�̍��ۓI�`���̕s���s�͏����邱�Ƃ��Ȃ��̂ł���B
�@�u���a���ێ����A�ꐧ�Ɨ�]�A�����ƕ���n�ォ��i���ɏ������悤�Ɠw�߂Ă��鍑�ۓm��ɂ����āA���_����n�ʂ��߂����Ǝv�Ӂv�i���{�����@�O���j�Ɛ��������{�����@�̖@�ӂɏƂ炷�Ȃ�A��T�i�l���A�ꍏ�������Ӎ߂������A���ۋ`���𗚍s���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���A�{���s�@�s�ׂɁA���@�V�Q�S���͓K�p�����ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�܂��A�{���ې�ɂ���Q�́A���̌o�߂Ƌ��ɖY����A���������̂ł͂Ȃ��B�ނ��뎞�̌o�߂́A���|�Ƌꂵ�݂̌p���ł���A�T�i�l��̑��Q�͐r��Ȃ��̂ɂȂ��Ă����̂ł���B
�@���������F�߂�悤�ɁA�푈�̎S�Q�͍ŏI�I�ɂ͌l�ɋA������̂ł��邩��A�n�[�O���y�ѓ��K���̋��ɂ̎�|�E�ړI�́A����̉ߒ��ɂ������퓬�����܂߂��l�̕ی�ɂ���B�{���ې�̂悤�Ȉ�ʏZ�����ʎE�C����푈�ƍ߂��A�����̓K�p�ɂ���Ă��̐ӔC��Ƃ�邱�Ƃ́A�푈�̎S�Q����l����鍑�ۖ@�̈Ӑ}�ɔ�������̂ł���A�l�̑����A�l���̑��d�������I�ȉ��l�����Ƃ�����{�����@�̖@�ӂɏƂ炵�A�{���ւ̖��@�V�Q�S���̓K�p�͔r�������ׂ��ł���B
�R�@���ˊ��Ԃ�K�p���Ȃ��ߎ��̔���
�@�@(1)�@���ˊ��Ԃ�K�p���Ȃ��ŋ߂̔���Ƃ��āA������\�h�ڎ펖�̂̍��Ɣ��������i�ׂ�����B�ō��ّ�Q���@�약���P�O�N�U���P�Q�������i�ȉ��A�u�����P�O�N�����v�Ƃ����B�����P�U�S�S���S�Q�Łj�́A���̂悤�ɏq�ׁA���ˊ��Ԃ̓K�p��r�������B
�@�u�������A����ɂ��A���̐S�_�r���̏틵�����Y�s�@�s�ׂɋN������ꍇ�ł����Ă��A��Q�҂́A���悻�����s�g���s�\�ł���̂ɁA�P�ɂQ�O�N���o�߂����Ƃ������Ƃ݂̂������Ĉ�̌����s�g��������Ȃ����ƂƂȂ锽�ʁA�S�_�r���̌�����^�������Q�҂́A�Q�O�N�̌o�߂ɂ���đ��Q�����`����Ƃ�錋�ʂƂȂ�A���������`�E�����̗��O�ɔ�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B��������ƁA���Ȃ��Ƃ��E�̂悤�ȏꍇ�ɂ����ẮA���Y��Q�҂�ی삷��K�v�����邱�Ƃ́A�O�L�����̏ꍇ�Ɠ��l�ł���A���̌��x�Ŗ��@�V�Q�S����i�̌��ʂ𐧌����邱�Ƃ͏𗝂ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�v
�@��L�����P�O�N�����́A���̉ߎ��ɂ���Ĕ�Q�҂��S�_�r���Ɋׂ茠���s�g���s�\�ł��������Ƃ���݂Ƃ��āA�����@�I�ӔC��Ƃ����̂Ƃ���A����͒��������`�����̌����ɔ�����Ƃ����l�����ɗ��r������̂Ɖ������B
�@�@(2)�@���̓_�A�K�p�������F�߂���̂��A�����P�O�N�����̎���Ɍ���
�����|�Ɖ����邱�Ƃ́A���̗��R�ɂ����ł���ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�A�@���̗��R�̑�P�́A���̔��������ˊ��Ԃ̉��I�E�@�B�I�K�p���u���������`�E�����̗��O�ɔ�����v�ꍇ�ɂ��̓K�p���u�������邱�Ƃ͏𗝂ɂ����Ȃ��v�Əq�ׁA����Ɂu���i�̎������Ƃ��́E�E�E�V�Q�S����i�̌��ʂ͐����Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B�v�Əq�ׂĂ��邱�Ƃł���B
�@���Ȃ킿�A�u���`�E�����v�u�𗝁v�u���i�̎������ꍇ�v�Ƃ�������ʌ������v���������A���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌������|�Ɖ����ׂ�������ł���B
�C�@���̗��R�̑�Q�́A���@�P�T�W�����ސ��K�p�ł���ꍇ���邢�͌����s�g�s�\�̌�����������̂����Q�Ҏ��g�ł���ꍇ�Ɍ��肷���|���Ƃ���ƁA�]���^�̍d���I�ȏ��˘_���������Ă������ׂ�����Ƃ����A�����P�O�N�����̖ړI�͒B�����Ȃ�����ł���B���Ȃ킿�A�l�X�ȕ��G�ȍ\����L���錻��̕s�@�s�ׂɏ_��ɑΉ����āA�����̓����ɓK��������̓I�Ó�����L���������Nj����Ă����A�]���^�̔������I�悵�Ă������ׁE�s���������������邱�Ƃ��ł��邩��ł���B���̏ꍇ�ɏ��߂Đ��`�E�����Ƃ����@�̊�{���O�����������̂ł���B
�E�@���̗��R�̑�R�́A������ɂ��u���Ȃ��Ƃ��E�̂悤�ȏꍇ�ɂ����ẮA�E�E�E�E���̌��x�Ŗ��@�V�Q�S����i�̌��ʂ𐧌����邱�Ƃ͏𗝂ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ���A�u���Ȃ��Ƃ��E�̂悤�ȏꍇ�Ɍ����āv�Ƃ͖������Ă��Ȃ��̂ł��邩��A���ˊ��Ԃ̓K�p�����̗Ꭶ�������̂ł����āA���肵����|�Ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�����P�O�N�����̑����ӌ��́A�u���ˊ��Ԃ̎咣���M�`���ᔽ���͌������p�ł���Ƃ����咣�v��r�˂��A����ɑウ�āu���������`�E�������̗��O�ɔ�������́v��u�𗝁v�ɂ��Ȃ����߂������Ă���B�u���������`�E�����̗��O�v�ᔽ�E�u�𗝁v�ɂ��Ă��A���قǂ̌��u������Ƃ͍l�����Ȃ�����ł���B
�@��̓I�ȍl���v�f�ɂ��ẮA�ȏ�̂悤�ȍٔ���܂��A�������E���ˊ��Ԑ��x�̑��ݗ��R�Ƃ����@�����̏�ɖ���҂͕ی�ɒl���Ȃ��A�A���̌o�߂ɂ�闧�E�̏̍���A�B�@�I���萫�Ƃ������v�A���l�����Ď����̉��p�Ȃ������ˊ��Ԃ̓K�p�����̈�ʓI�v���_�������Ύ��̂Ƃ���ł���B
�@���Ȃ킿�A�����s�s�g�ɂ������̏�ɖ���҂Ƃ̕]�����Ó������A�`���̕s���s�������Ŏ��̌o�߂ɂ��U���h��E�̏؏�̍���Ȃ��A�����̐�������Q�҂Ɣ�Q�҂̊W�Ȃǂ���A���̌o�߂̈ꎖ�ɂ���Č��������ł�������v���ɖR�����ꍇ�ɂ́A�ނ���ϋɓI�Ɏ������p�A���ˊ����̓K�p���������ׂ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@����ɁA�����n�ق��킫�x�������i�����Q�N�Q���Q�W���A����^�C���Y�V�P�X���Q�Q�R�Łj�́A�u���������`�ɔ����v�Ƃ��Ď������p�A���ˊ����̓K�p�������s�����B�������́A���@�퍐�ɂ�����`���ᔽ�̖��m���A�A�`���ᔽ�̑ԗl�̈������A�B������̌����s�g�ɂ��Ă̔퍐���̐ӔC�A�C�������]���ɂ��Ă̔퍐�̗��v�A���`���ᔽ�E���Q�������̑��݂̖������A����Q�҂̌����s�s�g�ɂ�������̕s�݁A����ɏd�����Ĕ��f���Ă��邱�Ƃ��Q�l�ɂȂ�B
�@�@(3)�@�܂��A�����P�R�N�V���P�Q�������n�ٖ����P�S���ɂ����ĉ����ꂽ�����闫�A�m��������������B����͂܂������A���`�����̌����ɔ�����Ƃ��āA���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����锻�f���������B
�@�u���̂悤�ȏ��ˊ��Ԑ��x�̎�|�̑��݂�O��Ƃ��Ă��A�{���ɏ��ˊ��Ԃ̓K�p��F�߂��ꍇ�A���łɔF�肵�����A�m�̔퍐�ɑ��鍑�Ɣ����@��̑��Q�����������̏��łƂ������ʂ����̂ł��邱�Ƃ�������炩�ȂƂ���A�{���ɂ����鏜�ˊ��Ԃ̐��x�̓K�p���A�������������Ƒi��F��ł��錠���̏��łƂ������ʂɒ��ڌ��ѕt�����̂ł���A���������ł̑ΏۂƂ����̂����Ɣ����@��̐������ł����āA���̌��ʂ���̂����ˊ��Ԃ̐��x�n�݂̎�̂ł��鍑�ł���Ƃ����_���l������ƁA���̓K�p�ɓ������ẮA���Ɣ����@�y�і��@���т��@�̑匴���ł��鐳�`�A�����̗��O��O���ɒu��������������K�v������Ƃ����ׂ��ł���B���Ȃ킿�A���ˊ��Ԑ��x�̎�|��O��Ƃ��Ă��Ȃ��A���ˊ��Ԑ��x�̓K�p�̌��ʂ��A���������`�A�����̗��O�ɔ����A���̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��𗝂ɂ����Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����邱�Ƃ��ł���Ɖ����ׂ��ł���B�v
�@�u���̂悤�Ȕ퍐�ɑ��A���Ɛ��x�Ƃ��Ă̏��ˊ��Ԃ̐��x��K�p���āA���̐ӔC��Ƃꂳ���邱�Ƃ́A���A�m�̔������Q�̏d�傳���l������ƁA���`�����̗��O�ɒ����������Ă���ƌ��킴��Ȃ����A�܂��A���̂悤�ȏd��Ȕ�Q���������A�m�ɑ��A���ƂƂ��đ��Q�̔����ɉ����邱�Ƃ́A�𗝂ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B����āA�{�����Q�����������̍s�g�ɑ��閯�@�V�Q�S����i�̏��ˊ��Ԃ̓K�p�͂���𐧌�����̂������ł���B�v
�@���̔����̘_�|�́A�܂������{���ɂ����Ă����̂܂ܑÓ�������̂ł���B
�@�{���ɂ������T�i�l�̕s�@�s�ׂ̓��e���\������V�R�P�������̍ې�́A��ʂ̕s�@�s�ׂƓ���ɘ_����ɂ͗]��ɂ���l���I�ȁA���ۖ@�ᔽ�̐푈�ƍߍs�ׂł���A���̐ӔC��P�Ɏ��Ԃ̌o�߂������āA���ł�����̂Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�{���A�{���̂悤�Ȑ푈�ƍ߂ɑ��ẮA�������邢�͏��˂Ƃ����T�O�͓K�p�ł��Ȃ��̂ł���B
�@���{�ƒ����Ƃ̕��a���������A�P�X�V�W�N�Ɏ���܂łȂ���Ȃ������Ƃ������Ƃ���݂Ƃ��āA��T�i�l�͖{���s�@�s�ׂɑ��鑹�Q�����ӔC���ق����ނ肵�Ă����B����A��Q�҂́A�����s�g���s�\�ȏ�Ԃɂ�����A���̂��Ǝ��g���A�܂��V���ȋ�ɂނ��ƂɂȂ��Ă����̂ł���B
�@�{�������܂��ɁA���`�ƌ����̗��O���������邽�߂ɁA���ˊ��Ԃ̓K�p�𐧌����Ȃ���Ȃ�Ȃ��P�[�X�ł���B
�@�@(4)�@����ɁA�����P�S�N�S���Q�U�������n�قɂ����ĉ����ꂽ������
�O��z�R�����A�s��������������B������A��L���l�A���`�����̌����y�ѐM�`�����珜�ˊ��Ԃ̓K�p��r�����������ł���B
�@�@(5)�@���̂悤�ɁA�ߎ��̔����̗���͏��ˊ��Ԃ̓K�p�r���̕����ւƑ傫����������ς��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āA�ٔ����͖{�����Ăɂ����Ă����ˊ��Ԃ̓K�p��r�����A���₩�ɍT�i�l��̑��Q����������F�߂�ׂ��ł���B
��S�@�u�������������ɂ������v�_�ɂ���
�@�P�@�������̔��f
�@�@�@�������́A�u�퍐�ɂ͖{���ې�Ɋւ��w�[�O������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă����v���Ƃ�F�߂Ȃ���A�u�{���ې�ɌW��퍐�̍��ƐӔC�́A�䂪���ƒ����Ƃ̍��ƊԂł��̏��������肳���ׂ����̂ł���v�Ƃ��āA�{���ې�ɌW��u�퍐�̍��ƐӔC�v�ɂ��Ă͓������������Ɠ������a�F�D���ɂ���āA�u���ۖ@��́v�u�����������̂Ƃ��킴��Ȃ��v�Ɣ������Ă���B
�@�������A�������������Ɠ������a�F�D���ɂ���āA�͂����Ĕ�T�i�l�̍��ƐӔC�����ۖ@�㌈�������ƌ�����̂ł��낤���B
�@�Q�@�������������ɂ�����u�푈�����̐���������v�ɂ���
�@�@�@�P�X�V�Q�N�X���Q�X���̓������������́A���{�����u�ߋ��ɂ����ē��{�����푈��ʂ��Ē��������ɏd��ȑ��Q��^�������Ƃɂ��Ă̐ӔC��Ɋ����A�[�����Ȃ���v�ƕ\���������Ƃ�O��Ƃ��āA���������u�������������̗F�D�̂��߂ɁA���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾�v�����B�P�X�V�W�N�������a�F�D���́A�u���������̏����������i�ɏ��炷�ׂ����Ƃ��m�F����B�v�ƒ�߂Ă���B
�@�����ɂ́A�O�̖��_������B
�@�@(1) �������������ł́u������������v�ł͂Ȃ�
�@��P�ɁA�������������ł́u�푈�����̐���������v�ƂȂ��Ă���A�u������������v�ł͂Ȃ��_�ł���B
�@�@�@�A�@�u�������͓��؏��ʼn����ς݁v�Ƃ������{�̗���
�@�@�@�@�@�������𐳏퉻�̌����Ƃ���Ă��������}�ψ����|���`���Ǝ������Ƃ̎��O���Ɋւ��āA�L���ȁu�|�������v�i�P�X�V�Q�N�V���Q�X���t�j���c����Ă���B���́u�����v�̒��ɂ́A����������������ꂽ���������Ăɂ́A��㏈���ɂ��āu�@���ؐl�����a���Ɠ��{���Ƃ̊Ԃ̐푈��Ԃ́A���̐��������\�������ɏI������B�A���{���{�́A���ؐl�����a������o�������������̎O�������\���ɗ������A���ؐl�����a�����{���A�������\����B��̍��@���{�ł��邱�Ƃ����F����B����Ɋ�Â��������{�͊O���W���������A��g����������B�i�����j�F���������l���̗F�b�̂��߁A���ؐl�����a�����{�́A���{���ɑ���푈�������������������v���Ƃ��������Ă����B
�@�Ƃ��낪�A���{���{�́A�푈��Ԃ̏I���ɂ��Ă��łɂP�X�T�Q�N�́u���؏��v�Ŋm�F����Ă���A�u��x���������Ƃ��J��Ԃ����Ƃ͍��ۖ@��ł��Ȃ��v�Ƃ������ꂩ��A�@��F�ɓ�F�������Ă����B
�@�P�X�V�Q�N�X���Q�T������̓c���p�h�̖K���̍ۍs��ꂽ��]��k�ł����̓_�����ɂȂ��Ă����B�Q�U���ߌ�̑�Q���]��k�Ŏ������́A�ߑO���̊O����k�ł̍������ǒ��́u�������͓��؏��ʼn����ς݁v�Ƃ������������̂悤�ɔᔻ�����B�u�Ӊ��������Ŕ���������������������ƂŁA���̂��т̋��������ɂ͔����������y����K�v���Ȃ��Ƃ������ǒ��̔����́A���ɉ�X�͊�قɊo����B�����Ӊ�͂��łɑ�p�ɓ����Ă����B�ނ͑S�������\���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͑��l�̍��݂ŋC�O�̗ǂ��������悤�Ƃ�����̂��B�푈�Ŕ�Q�����͎̂�ɑ嗤�ł���A��X�͗����̐l���̗F�D�W����l���A���{�l�����̎x���ŋꂵ�܂������Ȃ�����푈������������������悤�Ƃ����̂ł���B���ǒ��͋t�ɏӉ�����łɕ�����������Ƃ����ĉ�X�̋C����������ł���Ȃ��B����͉�X�ɑ��镎�J�ɂق��Ȃ�Ȃ��v�ƁB
�@�����������Ƃ�̂����A�X���Q�X���ɋ����������Ì������̂ł��邪�A���̌��ʁA�����̖��ł́A�u�푈�����̐���������v�ƂȂ�A�u���v���폜�����̂ł���B
�@���̓_�ɂ��A�啽�O���́A�����}���@�c������i�P�X�V�Q�N�X���R�O���j�ŁA�u�����������h�����������h�̕����Ƃ������t�ɂ������ƁA���ǂ��͂�������ȗ���ɂȂ�Ƃ��낾�������A�h���������h�Ƃ������t�ɂ��Ă��炢�A�h���h�Ƃ������t�͂��Ă��Ȃ��v�Əq�ׁA����Ɂu���؏��ɂ��łɒ����́h�Γ��푈�������̕����h���K�肳�ꂽ�̂ɁA�Ăсh�����������h�ƋK�肷��ƁA�ˑR�Ƃ��Ē����ɐ����������邱�Ƃ�F�߂邱�ƂɂȂ�A�������Ă��܂��v�Ɖ�������B
�@���Ȃ킿�A�P�X�V�Q�N�����̓��{���{�̗���Ƃ��ẮA���ؐl�����a���ɂ́A�������ׂ��u�����������v�͂Ȃ��Ƃ������߂������̂ł���B
�@�@�@�C�@�u��p������������������v�͓��{�����߁@
�@�@�@�@�@����ł́A�����̑Γ��푈�����������́A�P�X�T�Q�N�́u���؏��v�ɂ���ĕ������ꂽ�̂ł��낤���B
�@�P�X�T�O�N�㔼����n�܂����Γ��u�a�������́A�����̓����Η��̐����I�\�}�̒��ŁA���G�ȗl����悵���B�A�����J�͒��ؐl�����a���̑Γ��u�a�Q���ɔ����A��p�����𒆍��̐������{�Ƃ��đΓ��u�a�ɎQ�������悤�Ƃ������A�������������������A�p������p�̎Q���ɔ�����Ɏ���A�ŏI�I�ɕĉp�̑Ë��ĂƂ��āu�g��̐��{�h�Ƃ��������Ȃ��ŁA�Ɨ���̓��{�ɂǂ̐����ƍu�a���邩��C����v���Ƃ����߂��B����ɂ���Đ폟���ł������͂��̒����́A�Γ��u�a�ɍł��Q���̌�����L���Ă����ɂ�������炸�A�t�ɔs�퍑�ł�����{�̑I���ɂ��u�a�̑���ɂ͑I��Ȃ��Ƃ����O�㖢���̎��ԂɂȂ��Ă��܂����̂ł���B
�@�������āA�T���t�����V�X�R�Γ��u�a���́A�����̗������Ƃ��Q�����Ȃ��܂ܒ������ꂽ���߁A�����̔����������͂��ߑΓ��u�a�ɂ������㏈���̎�茈�߂̂��ׂĂ��A�����Ԃ̐푈�����ɓK�p���邱�Ƃ���ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂɂȂ����̂ł���B
�@���؏��̒������́A�P�X�T�Q�N�Q���Q�O������S���Q�V���܂ŁA�Q�����ȏ�������đ�k�ōs��ꂽ�B���̌��ɂ����āA�T���t�����V�X�R�u�a���̂悤�ȑS�ʓI�ȍu�a�����߂��p���ɑ��A���{���{�́A�u�a�����u�C�D���v�Ƃ��Ċȑf�Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ��Ă��A�����Ɋւ���������폜���邱�Ƃ����߂Ă����B���̂悤�Ȍ��ł̍j�����̌��ʁA���ǁA���؏��{���ɂ́A�������Ɋւ���K�肪�Ȃ��A���́u���̕s���̈ꕔ���Ȃ������v�Ƃ��Ă̏��c�菑�ɂ́A�u���ؖ����́A���{�����ɑ��銰���ƑP�ӂ̕\���Ƃ��āA�T���t�����V�X�R����P�S���i���j�P�Ɋ�Â����{�������ׂ��̗��v�������I�ɕ�������v�ƋL����邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A���؏��̑S���ƕt�������ɂ͔����Ƃ��������������Ȃ��A��p������������������������Ɖ��߂���邱�ƂƂȂ����̂ł���B
�@�@�@�E�@�K�p�͈͂̌��肳�ꂽ���؏��
�@���؏��ɂ��ẮA���{���{�͓�������K�p�͈͂ɂ��Č���I�ł���Ƃ͂�����F�߂Ă���B
�@�P�X�T�Q�N�U���Q�U���A�Q�c�@�O���ψ���ŁA�]�I�v�i�E�Ёj�c���́A�u������_�����ł��B�]���Ĕ��ɑ���Ő\���グ�܂��邪�A���̓��؏��̂��낢��ȃe�N�j�b�N�∻�ɍS��炸�A���̏��ɂ���ē��{���{�͂��̒��ؖ����������{�Ƃ������̂�S�ʓI�Ȓ����̎�l�Ƃ��ď��F�������̂ł͂Ȃ��A�����l���܂��邪�A���̓_�͑����̂͂����肵�����l�����A�C�G�X�E�I�A�E�m�[�ł������肢�����v�Ƌg�c�Ύɒ��ڂɎ������B���̎���ɑ��g�c�́A�u����͏��ɂ��͂����菑���Ă���܂����A���ɒ��ؖ��������̎x�z���Ă���y�n�������ؖ����Ƃ̊Ԃɏ��W�ɓ���B�����͏����ł���܂��B�����ړI�͏I���Ɉꒆ���S�̂Ƃ̏��ɓ��邱�Ƃ���]���Ă�܂Ȃ��̂ł���܂��v�Ɠ������B����ɑ]�I���u�������A�����i�}�}�j�ł��b�ɂȂ�Ȃ��ŁA����ƌ����A�S�ʓI�ȏ��F�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������܂��傤�v�Ɣ��₵�A�g�c�́u�����������Ƃł��v�Ƃ̔F�����������B�]�I���u���\�ł��v�Ɣ[�������B
�@�܂��A�P�X�T�S�N�P�Q���P�U���A�O�c�@�O���ψ���ł́A���ؖF�Y�i���i�j�c���̎���ɑ��A���c���ǒ��́u���@�����Ƃ��āA�������������B�v����ɓ��ؕ��a���ɂ����܂����{���{�̍��{�T�O�́A�������{�ƕ��a�������Ԃ���ǂ��A���̂��Ƃ͂����钆���̑S�̓y�ɂ��̏�K�p������̂ł���Ƃ��������͂Ƃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���܂��B�ł������܂�����A���w�E�̌��������ɂ����܂��āA���a���Ƃ͐\���Ȃ���A�K�p�̒n��I���E���͂����肠��Ƃ������Ƃ�F�߂���ł̏��ł������܂��v�ƁA���R��Y���t�̎������g�c���t�Ɠ����������Ċm�F�����̂ł���B
�@���؏��ɂ��ẮA�P�X�V�Q�N�̓������������ɂ���ē��{�����ؐl�����a�����{��B��̍��@���{�ƔF�ߍ��𐳏퉻�ɓ��ݐ������ʁA���؏��͏I�������A�Ƃ����`�œ��{���{�͖������������B���Ƃ��Ɩ����ł������Ƃ��钆�����̗����ƈقȂ�A���{���́A���܂ł����؏���ėL���ł������Ƃ��Ă���B�����A���̗L�����́A�P�X�T�Q�N�W���T���i�������j����P�X�V�Q�N�X���Q�X���i�������𐳏퉻�̓��j�܂łł���A���̌��͔͈͂͑S�����ł͂Ȃ��A�����̈ꕔ�ł����p�n��ɂ����y�Ȃ��i���؏�����������P���ɂ��j���ƂɂȂ�͂��ł���B���������āA���؏��Ɋ�Â���㏈���̌��͂��A��p�n��ɂ����y���A���؏��ɂ���āA�Γ��푈�����������̕������Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă��A����́A��p�n��̂���Ɍ��肳�ꂽ���̂ł����Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�G�@�u�����������v�͕�������Ă��Ȃ�
�@�@�@�@�@���������āA�����{�y�ɂ�����Γ��푈�����������́A�P�X�T�Q�N���ؕ��a���ɂ���Ă��A�P�X�V�Q�N�̓������������ɂ���Ă��A�����ĕ�������Ă��Ȃ��̂ł���B�������������Ɠ������a�F�D���ɂ���āA�u���ۖ@��́v�u�����������̂Ƃ��킴��Ȃ��v�Ƃ��錴�����̗����͌��ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@(2)�@�������������́u���������̕����v�ɂ͌l�̔����������͊܂܂�Ȃ�
�@�@�@�@��Q�ɁA�u�푈���������̕����v�́A�l�ɂ�鐿���܂ł��܂ނ̂��A�Ƃ����_�ł���B���̓_�ɂ��ẮA���Ƃ��ʂ̓��ӂȂ��A�l�̂����������̌���������ł���͂����Ȃ����Ƃ́A�����đ�����v���Ȃ��Ƃ���ł���B
�@���̓��R�̓������A�P�X�X�Q�N�S���A�]���Ǝ�Ȃ́A�����푈���̖��Ԕ�Q�ɂ��ẮA���݂ɋ��c���ď𗝂ɂ��Ȃ��`�őÓ��ɉ������ׂ��ł��邱�Ƃ��咣���Ă����|���������B����ɁA�P�X�X�T�N�R���X���A���ؐl�����a���K�����O���́A�������������ɂ�����푈���������̕����ɂ́A�u�l�̔����܂ł͊܂܂�Ȃ��v�A�����̐����͌l�̌����ł���A�������{�͊����ׂ��łȂ��Ɩ��������B
�@���R�̓����ł��邪�A���̑K�����O���̔����ɂ���āA�l��������������������������Ă��Ȃ����Ƃ͊m�肵�Ă���ƍl���Ă悢�B���������A�������������ɂ���Čl�̐������܂ŕ������ꂽ�Ƃ����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�@(3)�@�ې��Q�̔��������͕�������Ȃ�
�@�@�@�@��R�̖��́A�����Œ������{�����������Ƃ����u�푈�����v�̔�Q�͈̖̔͂��ł���B�푈�ƍߍs�ׁA�Ƃ�킯�A�ې�Ƃ����l���ɔ�����d��Ȑ푈�ƍߍs�ׂ܂ł��A�������{�������������Ɛӂ����̂��ǂ����ł���B
�@�Ƃ���œ������������ɐ旧���A�P�X�S�X�N�W���P�Q���ɐ��������W���l�[�u�����Ƃ��Ɂu�펞�ɂ����镶���̕ی�Ɋւ���P�X�S�X�N�W���P�Q���̃W���l�[�u���i��S���)���P�S�V���ɂ��A�u�E�l�A����Ⴕ���͔�l���I�ҋ��i�����w�I�������܂ށj�A�g�̎Ⴕ���͌��N�ɑ��Č̈ӂɏd����ɂ�^���A�Ⴕ���͏d��ȏ��Q�������邱�Ɓv�Əd��Ȉᔽ�s�ׂ��K�肵�A�����w�I�������܂ޔ�l���I�ҋ����̏d��Ȉᔽ�s�ׂɑ��āA���������̖Ɛӂ��֎~�����i�P�X�T�R�N���{�������B�j�B�{���ې�̂悤�ȁu�d��Ȉᔽ�s�ׁv�ɂ��ẮA������������ł��Ȃ��̂ł���B
�@�{���̏ꍇ�A�������{���A���{�ɑ���푈������������������̂́A����ɂ���ē��{�������ꂵ�߂邱�Ƃ������̗F�D�̖W���ɂȂ�Ƃ����ϓ_����ł���B�������́A�u��X�͗����̐l���̗F�D�W����l���A���{�l���ɔ����̎x���ŋꂵ�܂������Ȃ�����푈������������������悤�Ƃ����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B
�@���������āA�����őz�肳�ꂽ�����̓��e�́A�퓬�s�ׂɔ����������Ƃ��x�o��������A�ʏ�̐퓬�s�ׂɔ����������Ƃ���������I���Q�Ȃǂ�O���ɒu�������̂ł���A�����̖��Ԑl��������ʂ̓��ʂȑ��Q�Ȃǂ͂��Ƃ��Ɗ܂܂�Ă��Ȃ��B
�@�����Ȑ푈�ƍ߂ɂ���Ē������Ԑl����������Q�ɂ��Ă܂ŁA����������������Ĕƍߍs�ׂ�G������ȂǂƂ������Ƃ́A�_�O�̂͂��ł����āA����܂ŕ����̑ΏۂɊ܂߂�ȂǂƂ����l���͖ѓ��Ȃ����̂Ƃ����ق��Ȃ��B
�@���{�R�̏����ɑ��Ĕ�r�I����ł������������{���A�푈�ƍ߂ɑ��Ă͌������f�߂���p���������Ă����B
�@���ؐl�����a����������A�������{�́A�푈�ƍ߂ɑ��ẮA�����f�߂���ԓx�ł���A�\���Ȏ��Ȕᔻ�Ȃ��ɂ́A�Ɛl�������Ȃ������B
�@���������������{�̑Ή��́A�n�o���t�X�N�ٔ��ɂ����Ă����m�Ɍ���Ă���B
�@�����āA�������{���A�ې��Q�ɂ��Ă܂ŁA��������������������̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�Ȃ̂ł���B
�@�R�@���_
�@�������������ɂ���Ē������{�́A�ې�̂悤�Ȏc�s�Ȑ푈�ƍ߂ɂ��Ă܂Ŕ��������������q�ׂĂ�����̂ł͂Ȃ��B���������āA�{���ې�ɌW���T�i�l�̍��ƐӔC�́A���ۖ@�������������Ă��Ȃ��B�����������Ƃ�O��Ƃ����������̗��_�͌��ł���B
�@����āA�{���ې�́A�W���l�[�u�E�K�X�c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ���A���@�V�O�X���Ȃ����V�P�P���܂��͂V�P�T���̕s�@�s�ׂɊY������B

��R�́@�𗝂Ɋ�Â��Ӎߋy�ё��Q��������
��P�@�������͎Љ�I���`�ɔ�����
�@�������́A�{���ې��Q�҂�ɏd��Ȕ�Q�̎��������݂��邱�ƁA����ɍې�̍s�ׂ��A�s�ד������łɍ��ۖ@�ᔽ�ł��������Ƃ�F�߂��ɂ�������炸�A�܂��A�������@�����T�O�L�]�N���o�������Ɏ�������݂����A��Q�̋~�ς��S���ׂ���Ă��Ȃ�������ӂ܂�����ł��Ȃ��A�𗝂Ɋ�Â��T�i�l��̑��Q������������ѕ⏞�������A�ȉ��ɏڏq����悤�ȗ��R�ɂ���ĔF�߂悤�Ƃ��Ȃ��B
�@���̂��Ƃ́A�ې�̔�Q�̎�����F�肵�Ȃ�����A�ٔ�����������~�ς������ӔC�ɕ��u������̂ł���A���̂悤�Ȍ������́A�Љ�I���`�ɏƂ炵�ē��ꐥ�F�������̂ł͂Ȃ��B�@
�@����āA�ٔ����́A�v���ȋ~�ς̍��x�̕K�v���Ɋӂ݁A�[�I�ɏ𗝂Ɋ�Â��čٔ����ׂ��ł���B
��Q�@�𗝂̖@����
�@�@
�@�P�@�𗝂Ƃ́A����@�̌n�̊�b�ƂȂ��Ă����{�I�ȉ��l�̌n���Ӗ����邱�ƁA���ꂪ�P�ɍٔ����̎�ς̒��ɂ������݂�����̂ł͂Ȃ��A�q�ϓI�ɎЉ��ʂɑ��݂��Ă�����̂ł��邱�Ƃ́A���������F�߂�Ƃ���ł���B
�@�����W�N�������z���P�O�R���ٔ������S���R���́u�����m�ٔ��j�����m�@���i�L���m�n�K���j�˃��K���i�L���m�n�𗝃����l�V�e�ٔ��X�x�V�v�Ƃ����K��A�܂��A�X�C�X���@�P���́u������܂��͉��ߏケ�̖@���ɋK��̑�����@�����Ɋւ��ẮA���ׂĂ��̖@����K�p����B���̖@���ɋK�肪�Ȃ��Ƃ��́A�ٔ����͊��K�@�ɏ]���A���K�@���܂������Ȃ��ꍇ�ɂ́A���������@�҂Ȃ�Ζ@�K�Ƃ��Đݒ肵���ł��낤�Ƃ���ɏ]���čٔ����ׂ��ł���v�Ƃ����K�蓙�ɒ�߂��Ă���̂Ɠ��l�̈Ӗ����Ɖ������B
�@�������Ȃ���A�������́A�u��ʂɂ́A��̓I�Ȏ����̖@�I���l���f�ɓK����悤�ȋ�̓I�Ȕ��f��̌`���Ƃ���̂ł͂Ȃ��i�Q�U�łX�s�ځj�B�v�Ƃ���B�܂�A�������́A�𗝂͒��ۓI�A���`�I�A���ΓI�ϔO�ł���A�𗝂݂̂������Ƃ��ČX�l�ɋ�̓I�Ȑ������������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ���̂ł���B
�@�������A����@�⊵�K�@�̂Ȃ��ꍇ�ɂ��A�ٔ����͍ٔ������ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��i���@�R�Q���Q�Ɓj�B���̂悤�ȏꍇ�A�ٔ����́u�𗝃����l�V�e�ٔ��v���ׂ����̂Ƃ����B
�@�����āA�ٔ�������̓I�����̉����ɍۂ��ċ�̉������𗝂ɂ��Ă��A���Y�ٔ��̊����͓͂��Y�����ɂ����y�Ȃ�����A�����ɖ@�K�͂ɂȂ�Ƃ͂����Ȃ�����ǂ��A����ł��Ȃ��A�𗝂́A�ٔ������ٔ��ɍۂ��ċ���ׂ���̌���ł���A���̈Ӗ��Ŗ@���ł���Ƃ������Ƃ��ł���i�l�{�a�v�u���@�����v�V�y�[�W�Q�Ɓj�B
�@�܂�A����@�⊵�K�@�����Y�����̂��߂̔��f�����Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ٔ����͏𗝂ɏ]���čٔ����邱�Ƃ�v������Ă���A�]���Ă܂��𗝂������Ƃ��čٔ��̐������̘_�����邱�Ƃ�������Ă���B
�@�h�C�c�ł́A�ٔ����͂����Η����Ɂu�𗝂ɂ��v�A�u���S�ȍ�������ɂ��v�A�u�����̖@�I����ɂ��v�A���邢�́u���`�̊ϔO�ɂ��v�Ƃ������\���ōٔ����Ă��邱�Ƃ͂���߂Ē��ڂɒl����A�Ƃ���@�Љ�w�҂͕]�����Ă���B
�@���̓_�A�ٔ��͕K���@�ɂ��ׂ��Ƃ����O��ɌŎ�����A�𗝂͍Ō�̋K���Ƃ��Ă̖@�����Ƃ���˂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�������A�ނ��뎖�Ԃ����āA�𗝂͖@�ł͂Ȃ����A�ٔ��͍Ō�̋K���Ƃ��Ė@�łȂ��𗝂ɍ��������߂邱�Ƃ��������B�O�������̎v�z�����̌���ł͐��������Ƃ����̂��������Ǝv���Ƃ����w�E������i��ȉh�u�@���v�����@�w���T�P�W�Q�U�y�[�W�j�B
�@�܂��A���@�@�K�Ȃ������K�@�����݂��Ȃ��ꍇ�ɕ�[�I�ɏ𗝍ٔ�������ׂ��Ƃ������̂悤�Ȏw�E������B�u�𗝍ٔ��̖{���͐V���R�@�ł��邪�A�ǂ����ĐV���R�@�����A�����ɓK�p���邩�A�𗝍ٔ������Ď�ς̊댯�Ȃ��Љ�K���E�i���̉ۑ�����������߂邩�A�@�̐Ï�E����̓��v���̒��߂������ɂ��ĉ\�Ȃ炵�߂邩�̕��@�̊m�肪�̗v�ł���B������@�A���E���K�@�A�e�����ʂ̌X�����������@�A����A�w���A�@�K�s�ׂȂǂ̌������^���܂ސ��E�I���q�����̈��q�ƗZ�����đ�O�@�����鎩�R�@���`�����邩��A���̏����q�ƕs���a�ɂȂ�ʂ�����Ȃ�ׂ����E�I���q�d���A���@���e�̐��E�@���e�ւ̓�����������������֊e���@�̋]���I���_������ׂ��v�u���Y�@����ɂ����Ắw�������̔F�߂��@�̈�ʌ����x�����̎���K�͂Ȃ��ꍇ�ɓK�p�����ׂ��ł���v�i���R�����Y�u�@���Ɖ��߁v�P�O�R�`�P�O�T�y�[�W�A�V�Œ��ߖ��@�@�U�`�V�y�[�W�j�B
�@�������́A�u�𗝂̖��̉��ɍٔ���������̎�ϓI�ȐM�O�Ɋ�Â����f�����Ă��܂������ꂪ����B�v�ȂǂƔ������邪�A���������F�肵���{���ې�̎����W�̉��Ŕ�Q�҂�ɔ������s�����Ƃ́A�܂��Ɏ��R�@�ɂ��Ȃ������̂ł���u��ς̊댯�Ȃ��Љ�K���E�i���̉ۑ�����������߁v�u���E�I���q�d���A���@���e�̐��E�@���e�ւ̓����v��i�߂邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�@�Q�@�܂��A�����Ɂu�𗝁v�Ɋ�Â��čٔ������Ⴊ����B
�@���{�����ɉc�Ə���L����}���[�V�A�A�M�̍q���Ђ��^�s����q��@�̒ė����̂ɂ���Ď��S�������{�l�̈⑰���A�E�q���Ђ�퍐�Ƃ��āA�킪���̍ٔ����ɑ��Q���������̑i�����N���������ɂ����āA�����Ăɂ��킪�����ٔ�����L���邩�ۂ�������ꂽ�B�ō��ٔ����́u���ڋK�肷��@�K���Ȃ��A�܂��A���ׂ�������ʂɏ��F���ꂽ���m�ȍ��ۖ@��̌����������m�肵�Ă��Ȃ�����̂��Ƃɂ����ẮA�����ҊԂ̌����E�ٔ��̓K���E�v����������Ƃ������O�ɂ��𗝂ɏ]���Č��肷��̂������v�ł���A�u�����Ɋւ���i�����ɂ��A�퍐���킪���̍ٔ����ɕ�������̂��E�𗝂ɓK�����̂Ƃ����ׂ��ł���v�Ɣ��������i�ō��ّ�Q���@��P�X�W�P�N�P�O���P�U�������E���W�R�T���V���A�����P�O�Q�O���X�y�[�W�j�B
�@�܂��A�u�𗝁v�������Ƃ��ČX�l�ɋ�̓I�Ȑ�������������Ƃ����ٔ��Ⴊ���݂���B������Ђ̎���������C�����҂���̉�Ђɑ����������C�o�L�\���葱�ɂ��āA��t�n�قP�X�W�S�N�W���R�P�������i�����P�P�R�P���P�S�S�y�[�W�j�́A�𗝏�o�L�`����F�߂Ď��̂悤�ɔ������Ă���B�u�����́A�퍐�̎���������C�����̂ł��邩��A�퍐�́A���̎|�̓o�L�葱���Ȃ��ׂ��`��������̂ł����āA�퍐�������C�ӂɗ��s���Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA�𗝏�A�����́A�퍐�ɑ��A���̎|�̓o�L�葱�����邱�Ƃ��������邱�Ƃ��ł�����̂Ɖ�����̂������ł���v�Ƃ��Ă���B
�@�R�@����@�́A���Ƃ����K�@�ɂ���ĕ�[���ꂽ�Ƃ��Ă��A���Ȃ���ʂ����܁i��㞁j�������Ă���B
�@���Ƃ��A���@�҂�����߂Ē��ۓI�ȊT�O���g�p���A���̋�̉����ٔ����Ɉ�C���Ă���ꍇ�i���Ƃ��A���@�P���́u�����m�����v�u�M�`�����v�u�����m���p�v�Ȃǁj�A���@�҂��ӎ��I�ɂ����ӎ��I�ɂ��K���u���Ȃ������ꍇ�A���邢�͐����V���������W�����ꍇ�ȂǁA�v����ɐ���@�����ق��Ă���ꍇ�A���@�҂͋K���݂�������ǁA��������̂܂ܓK�p����Ƒ����ꏭ�Ȃ���s���Ȍ��ʂ��A�������@�҂����̂��Ƃ�m���Ă����Ȃ�A���̂悤�ɂ͋K�肵�Ȃ������ł��낤�ƍl������ꍇ�ɂ́A�ٔ����͐���@�����̂܂ܓK�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�E�̏ꍇ�ɂ́A���Ƃ̑g�D�K�͂��@�̓K�p���ٔ����ɈϔC�����Ƃ��A���łɁA�ٔ����ɂ��ٔ���̔������I�܂��َ͖��I�ɔF�߂����̂ƍl������B�E�̏ꍇ�ɂ͂��̂悤�ɂ͍l�����Ȃ����A�������A�ϔC�̖@���ɏ]���āA����@�̎w�����C�����邱�Ƃ��������ł��낤�B�ϔC�̖@���ɏ]���A�����҂̗\�����Ȃ���ʂ⌋�ʂ����������ꍇ�ɂ́A���Ƃ��ϔC�҂̎w�}�ɔ����Ă��A�ϔC�̖ړI�ƈϔC�҂̎v�l���@�ɓK�����A�����Ă��̎��Ԃ�m�����Ȃ�ΈϔC�҂͂����������ł��낤�Ɛ��F�����Ƃ���𐋍s���邱�Ƃ����A��C�҂̌������`���ł���ƍl�����邩��ł���B���������A���Ƃ̖@���茠���̂��Љ�̈ӎv�Ɋ�Â����̂ł���A����@�����݂��Ȃ�������A�Љ�̌�����Ó��ɋK���ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A�ٔ������Љ�ɑÓ�����K�͂ɏ]���čٔ����ׂ����Ƃ́A�@�̖ړI��B������䂦��ł���B
�@�v����ɁA�ٔ������ٔ��ɍۂ��Đ���@�E���K�@�̂ق��ɋ���ׂ�������甭�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���@�V�U���R���̕\���ɂ�������炸�i�ނ���u�@���v�̌�͋q�ϓI�@�K�͂Ƃ����Ӗ��ɍL�`�ɉ�����ׂ��Ȃ̂Łu�@���v�Ƃ���鎩�R�@��𗝂��܂܂��j�A���łɗ��@�Ǝi�@�Ƃ̕����Ƃ������Ƒg�D�̂����ɗ\�肳��Ă���ƍl������̂ł���B
��R�@�𗝂Ɋ�Â��⏞�����ɂ���
�@�P�@�������́A�T�i�l��̏𗝂Ɋ�Â����Q���������ɑ��A�u���Ɩ����ӂ̖@���v�������ɂ��Đ˂����B
�@���Ȃ킿�A�����ɂ����ẮA���̓��Y���͓I�s�ׂ���@�ł����Ă����Q�����ӔC��Ȃ��Ƃ����u�@�v���m�����Ă����B���̂悤�ɁA�{���ې�ɂ�鑹�Q�̔����ӔC�ɌW��ٔ��K�͂Ƃ��āu�@�v�������Ă����킯�ł͂Ȃ�����A�{���ɂ����ď𗝂ɂ���Ĉ�@�Ȍ����͂̍s�g�ɋN�����鑹�Q������������F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���B
�@�܂��A�������́A�𗝂Ɋ�Â������⏞���͓���ȕ⏞�����ɂ��Ă��u���Ɩ����ӂ̖@���v�������ɂ��Đ˂����B
�@���Ȃ킿�A�ې킪�s��ꂽ�����A�䂪���ɂ����Ắu���Ɩ����ӂ̖@���v�ɂ�荑�̌����͍s�g�ɂ�鑹�Q�����ӔC�͔ے肳��Ă����̂ł��邩��A�����̖@�̌n���ɂ���ɂ��đ����⏞���̑��̓��ʂȕ⏞�����ׂ��ł���Ƃ����𗝂����݂��Ă����ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���B
�@�Q�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v���咣���邱�Ƃ̕s�����ɂ��ẮA�ʍ��ŏڍׂɘ_���Ă���̂ŏ���Ƃ��āA�����ł͔O�̂��߂ɂ��̓_���w�E���Ă����B
�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v�́A�����̔�����j�~������̂ł͂Ȃ��A�����������������Ƃɑ��čs�g���邱�Ƃ������Ȃ��Ƃ����R�قł���B���������āA���ɖ{���ې킪�s��ꂽ�����A�u���Ɩ����ӂ̖@���v�����݂����Ƃ��Ă��A��㌛�@�y�э��Ɣ����@���{�s����A�u���Ɩ����ӂ̖@���v�����ł��Ĉȍ~�́A�����������������Ƃɑ��čs�g���邱�Ƃ�W����@����̏�Q�͂Ȃ��Ȃ����̂ł��邩��A�������̂悤�ɍ����̒i�K�ŁA�u���Ɩ����ӂ̖@���v���R�قƂ��ĔF�߂邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
�@�Q�O�O�R�N�R���P�P���ɔ����̂����������A�s�i�ׁi�����n���ٔ��������X�N��P�X�U�Q�T���j�ɂ����āA�ٔ����́A�ȉ��̂Ƃ��蔻�������B
�@�u��O�̍ٔ���y�ъw���ɏƂ炷�ƁA�w���Ɩ����Ӂx�Ȃ�s���́w�@���x���m�����Ă���Ƃ̗�����w�i�Ƃ��āA��L�̂悤�ȉ��߂��̂��Ă������Ƃ�������������̂́A�����_�ɂ����ẮA�w���Ɩ����ӂ̖@���x�ɐ������Ȃ��������������o�����������Ƃ��A�T�i�l�炪�咣����Ƃ���ł���v
�@���̔������A��O�E�풆�͂Ƃ������Ƃ��āA���̌����_�ɂ����āu���Ɩ����ӂ̖@���v���咣���邱�Ƃɐ������Ȃ������������Ȃ��|�������Ă���A��L�Ɠ��l�̍l�����Ɋ�Â����̂Ǝv����B
�@����āA���������A�T�i�l��̏𗝂Ɋ�Â��⏞�������A�u���Ɩ����ӂ̖@���v�������Đ˂������Ƃ́A�S������Ă���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�R�@���������𗝂Ɋ�Â��⏞�����ɑ��āA�u���Ɩ����ӂ̖@���v�͍R��
���肦�Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�𗝂Ɋ�Â��⏞�����́A���Ƃɑ����̕s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������߂�̂Ƃ͖@�I���i���قȂ邩��ł���B���R�ɂ�����Q�O�O�P�N�V���P�W���t�̍T�i�l��̏������ʂŏڍׂɏq�ׂ��Ƃ���A���s�@��̍��ƕ⏞�̔��e���l�@����ƁA�@�s�@�Ȍ����͂̍s�g�ɂ�萶���鑹�Q�ɑ��鍑�Ɣ����A�A�K�@�Ȍ����͂̍s�g�ɂ�萶����@�̗\�z���Ă������Y�I�����ɑ��鑹���⏞�A�B�P�Ɍ��ʓI����ɒ��ڂ��čs����Љ�ۏ�A�C��L�@�Ȃ����B�ƈقȂ����ȍ��ƕ⏞���x������B
�@�u���Ɩ����ӂ̖@���v���R�قƂ��ĈӖ�����������̂́A��L�@�Ȃ����C�̂����@�݂̂ł���B���Ȃ킿�A�s�@�Ȍ����͂̍s�g�ɂ�萶���鑹�Q�ɑ��鍑�Ɣ����ӔC��Ɛӂ���Ƃ����̂��u���Ɩ����ӂ̖@���v�̎�|�ł���B���������āA��L�A�Ȃ����C�̕⏞�̏�ʂł́A�u���Ɩ����ӂ̖@���v�͓����Ȃ��̂ł���B
�@�ȉ��A��L�C�̓���ȍ��ƕ⏞���x�ɂ��āA�Ę_�������ꂸ�������Ă����B
�A�@�\�h�ڎ�@�̋~�ϐ��x�̖@�I���i
�@�\�h�ڎ�@�́A���@�����ɋ`���Â����퓗�Ȃǂ̗\�h�ڎ�����������ƂɈ����āA���a�ɂ�����A��Q�̏�ԂƂȂ�A���͎��S�����҂ɑ��ď���̋��t���s�����̂Ƃ��Ă���i���@�P�P���`�P�W���j�B
�@��L���x�̋��t�̖@�I���i�͎��̂悤�ɐ�����Ă���i�Y�J�E�x�V���h�w��������\�h�ڎ�@�x�P�T�U�`�V�ŁE���傤�����j�B
�u�\�h�ڎ�������Ƃɂ�錒�N��Q�͓K�@�Ȍ����͂̍s�g�ɂ�錋�ʂƍl������̂ŁA�s�@�s�ׂɊ�Â����̂ł͂Ȃ��_�ō��Ɣ����ƈقȂ�A�@�����R�ɗ\�z������Y�I�����ł͂Ȃ��_�ő����⏞�Ƃ��قȂ�A�X�ɁA�P�Ɍ��ʂɒ��ڂ���̂ł͂Ȃ����������ł���\�h�ڎ���`���Â��Ă���Ƃ����_�ŎЉ�ۏ�Ƃ��قȂ�B���ǁA�\�h�ڎ�@�ɂ��\�h�ڎ�́A�Љ�h�q�̂��߂ɍ��Ƃɋ`���Â������̂ł���A�W�҂������ɒ��ӂ��Ă��ɔ����̊m���ŕs��I�Ɍ��N��Q�̋N���蓾�邱�Ƃ͌����w�������Ă��Ă��ے�ł��Ȃ������ł���A�����ł���Ȃ���A�����Ă�������{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ꐫ��L���Ă���̂ŁA���̂悤�ȎЉ�I�ɓ��ʂ̈Ӗ���L���錒�N��Q�ɑ��āA�Љ�I�����̗��O�ɗ����A���ƕ⏞�I���_�����������ė\�h�ڎ�ɂ�錒�N��Q�ɑ���~�ϐ��x���݂���ꂽ���̂ł���B�v
�@�@����ɂ����Ă��A���̓_�ɂ��Č����Ȍ��O�q���ǒ��������P�F�͎��̂悤�Ȏ�|�������s���Ă���B
�u�i���������{�ψ��j�@
�@�V���x�̖��̂́A�����܂ł��~�ϐ��x�ł������܂��B�����ŁA���̓��e�̐��i�ł������܂����A�͂�����\���グ�܂��āA���Q�������x�ł͂������܂���B�܂��A������Љ�ۏᐧ�x�ł��������܂���B���̂悤�ȍ���n�������c�̂̍s���s�ׂɊ�Â���Q�ɂ��܂��āA���ɐ����Ƃ��g�̂̔�Q�ɂ��܂��āA���������������ߎ��̏ꍇ�ɋ~�ς�����Ƃ����悤�Ȑ��x�͑S���V�������x�ł������܂��B���̂悤�ȊW����A�]���̔�����A������Ȃ��킯�ŁA���������X�Ƃ��Ă���킯�ł������܂�����ǂ��A���ǂ��Ƃ������܂��ẮA���I�⏞�̐��_�Ɋ�Â����~�ϐ��x�ł���ƍl���Ă���܂��v�i��V�V��E����a�T�P�N�T���P�S���O�c�@�Љ�J���ψ���c�^��X���Q�O�Łj
�@�܂��A���̂悤�Ȏw�E������B
�u���̂悤�Ȑ��x�́A�����̓`���I�_�̌n�̂�����ɂ������Ȃ���R���e�Ɉʒu�Â�����ׂ����̂ł��邪�䂦�ɁA���@�҂́w���ƕ⏞�I���_�Ɋ�Â��~�ς��s���A�Љ�I�������͂���x����ȕ⏞���x�Ƃ��Ĉʒu�Â����̂ł���v�B�i���c�����u�\�h�ڎ팒�N�~�ϐ��x�̖@�I���i�ɂ��āv�w���@�̊�{���i�c������搶����L�O�j�x�S�W�O�ŁE�L��t�j
�C�@�Y���⏞�̋~�ϐ��x�̖@�I���i
�@�ƍ߂̔�^�҂Ƃ��ė}���A�S�ւ��ꂽ��A���߂̍ٔ��������̂ɑ���Y���⏞���A�s�@�s�ׂɊ�Â����̂ł͂Ȃ��_�ō��Ɣ����ƈقȂ�B���@�͂P�V���ɋK�肷��������̕s�@�s�ׂɂ�鍑���̑��Q�����ӔC�̂ق��ɁA�Y���⏞���S�O���ɂ����ĔF�߂Ă���̂ł����āA�Y���⏞�͉ߎ���v���Ƃ����A�ނ��떳�ߎ��ł���A���Ȃ��Ƃ����ƍs�ׂ̂��̎��_�ɂ����锻�f�Ƃ��Ă͓K�@�s�ׂɊ�Â��Ă���̂ł���B�������Ȃ���A�@�����R�ɗ\�z���鐶���E�g�̂ւ̐N�Q�ł͂Ȃ��_�ő����⏞�Ƃ��قȂ�A�܂��Љ�ۏ�Ƃ��قȂ�B���ǁA�Y���⏞�́A�Ȋw�I�{�����@�����S�łȂ������ŁA�Y���i�@�̉^�c���ނȂ����̂Ƃ��āA���̌��^���F�肳�ꂽ�Ƃ��́A���R���S�����邱�Ƃ�K�@�Ƃ��錻�s���x�̂��ƂŁA��ɂȂ��ē��Y�S�����q�ϓI�ɂ͈�@�ƂȂ����ꍇ�ɂ����Ă��Ȃ����̍S����K�@�����A���R���S�����ꂽ���̂̌����N�Q������~�ς������u���邱�Ƃ͐l�����d�̐��_���猩�߂����킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ��납��݂���ꂽ�����~�ϐ��x�ł���B�����x�������̑̌n�̂�����ɂ������Ȃ����ƋN�����̋]���ɑ��鍑�ƕ⏞���x�Ƃ��Ĉʒu�Â�����ł��낤�B
�@���ƕ⏞�i�L�`�j�ɂ́A�ȏ�̂悤�ȍ��Ɣ����A�����⏞����юЉ�ۏ�̂ق��ɓ���ȍ��ƕ⏞�i���`�j���x��������̂ł���B
�@�S�@�푈�]���ɑ�����{�̕⏞���@
�@�u���{�̍s�ׁv�ɂ��u�푈�̎S�Ёv�̋]���҂ɑ��鍑�ƕ⏞�ɂ��Ă��A�l���I�ړI�Ɋ�Â������Ɣ�������ё����⏞�Ƃ͈قȂ����ȍ��ƕ⏞���x��������B
�A�@���q���e�픚�҂̈�Ó��Ɋւ���@���̍��ƕ⏞�̖@�I���i
�@������Ö@�́A�L���s�y�ђ���s�ɓ������ꂽ���q���e�̔픚�҂����̋��Z�n�i���Z�n��L���Ȃ��Ƃ��͂��̌��ݒn�|���@�R���P���j�̓s���{���m���ɐ\�����Ĕ픚�Ҍ��N�蒠�̌�t�����Ƃ��͏���̈�Ë��t������̂Ƃ��Ă���B
�@���̋~�ϐ��x�̐��i�ɂ��āA�s�@���������؍��l�픚�҂���̔픚�Ҍ��N�蒠�̌�t�\����F�e�����ō��ٔ����͎��̂悤�ɔ������Ă���B
�u������Ö@�́A�픚�҂̌��N�ʂɒ��ڂ��Č���ɂ��K�v�Ȉ�Â̋��t�����邱�Ƃ𒆐S�Ƃ�����̂ł����āA���̓_����݂�ƁA������Љ�ۏ�@�Ƃ��Ă̑��̌��I��Ë��t���@�Ɠ��l�̐��i�������̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�������Ȃ���A�픚�҂݂̂�ΏۂƂ��ē��ɏ�L���@�����ꂽ���Ȃ𗝉�����ɂ��ẮA���q���e�̔픚�ɂ�錒�N��̏�Q�����ė���݂Ȃ����ق��[���Ȃ��̂ł��邱�Ƃƕ���ŁA�������Q���k��ΐ푈�Ƃ������̍s�ׂɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���A�������A�픚�҂̑��������Ȃ��������ʂ̐푈��Q�҂����s����ȏ�Ԃɂ�����Ă���Ƃ������������������Ƃ͂ł��Ȃ��B������Ö@�́A���̂悤�ȓ���̐푈��Q�ɂ��Đ푈���s��̂ł�������������̐ӔC�ɂ�肻�̋~�ς��͂���Ƃ�����ʂ����L������̂ł���A���̓_�ł͎����I�ɍ��ƕ⏞�I�z�������x�̍���ɂ��邱�Ƃ́A�����ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�Ⴆ�A���@���픚�҂̎����Ȃ������Y�̏�Ԃ̂�������Ƃ킸��ɑS�z����S�ƒ�߂Ă��邱�ƂȂǂ́A�P�Ȃ�Љ�ۏ�Ƃ��Ă͍����I�ɐ������������Ƃ���ł���A��L�̍��ƕ⏞�I�z���̈�[���������̂ł���ƔF�߂���v�i��ꏬ�@�쏺�T�R�E�R�E�R�O�����ō����W�R�Q��Q���S�R�T�ŁE�����W�W�U���R�Łj
�܂��A��������
�u���@���픚�҂̂�����Ă�����ʂ̌��N��Ԃɒ��ڂ��Ă�����~�ς���Ƃ����l���I�ړI�̗��@�v
�ł���Ƃ��A���̂悤�ɔ������Ă���B
�u���@�R���P���ɂ͂킪���ɋ��Z�n��L���Ȃ��픚�҂����K�p�Ώێ҂Ƃ��ė\�肵���K�肪���邱�ƂȂǂ���l����ƁA�픚�҂ł����Ă킪�����Ɍ��݂���҂ł������́A���̌��݂��闝�R���̂������₤���ƂȂ��A�L�����@�̓K�p��F�߂ċ~�ς��͂��邱�Ƃ��A���@�̂����ƕ⏞�̎�|�ɂ��K��������̂Ƃ����ׂ��ł���B�v
�@�����́A�픚�҂ɑ��鋋�t�̖@�I���i����L�̂悤�ɐ������������A���Y���Ăɂ��āA
�u�s�@�����҂ł��邪�䂦�ɂ����������݂Ȃ����Ƃ́A������Ö@�̐l���I�ړI��v�p������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�Ƃ��āA�s�@���������픚�҂ɂ��Ă����@�̓K�p��F�߂Ă���̂ł���B
�@���̔�������Ƃ��납�疾�炩�ȂƂ���A�픚�҂�������u�푈�̎S�Ёv�̋]���́u���{�̍s�ׁv�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���A�푈���s��̂ł�������������̐ӔC�ɂ�肻�̋~�ς��͂���ׂ��ł���Ƃ������ƕ⏞�̐��_�Ɋ�Â��āA���@�͗��@���ꂽ���̂ł���B
�C�@�폝�a�҈⑰������@�i����@�j�̍��ƕ⏞�̖@�I���i
�@��L����@�P���́A���@�̖ړI�����̂悤�ɒ�߂Ă���B
��P���@���̖@���́A�R�l�R�����̌�����̕����Ⴕ���͎��a�܂��͎��S�Ɋւ��A���ƕ⏞�̐��_�Ɋ�Â��A�R�l�R�����ł������Җ��͂����̎҂̈⑰�����삷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
�@���@�́A�P�X�T�Q�N�S���A���a���̔����ɂ����{���匠������̂�҂悤�ɂ��Đ��肳�ꂽ���̂ł��邪�A��L�����́u���ƕ⏞�̐��_�v�Ɋ�Â�����̎�|�ɂ��Č�����b�g���b�s�͎��̂悤�ɐ������Ă���B
�u�i�g��������b�j�@
�@�����̐폝�a�ҁA��v�҈⑰���́A�ߋ��ɂ�����푈�ɂ����č��ɏ}�����҂ł���܂��āA�����̎҂������������������̂́A�������Ƃ��Ă̓��R�̐Ӗ��ł������܂��B�s��ɂ���ނ��鎖��Ɋ�Â��A�������R�ɂȂ��ׂ��Ӗ����ʂ������Ȃ������̂́A�܂��ƂɈ⊶�̂���݂Ɛ\���Ȃ���Ȃ�܂���B�������Ȃ��炷�łɕ��a���͒��������A���̌��͔����̎����́A���ʂ̊Ԃɔ����Ă����̂ł���܂��B���̍u�a�Ɨ��̋@��ɍۂ��܂��āA�����̐폝�a�ҁA��v�҈⑰���ɑ��A���ƕ⏞�̊ϔO�ɗ��r���āA�����̎҂����삷�邱�Ƃ́A���a���ƌ��݂̓r�ɂ���킪���Ƃ������܂��āA�ł��ٗv���ł��邱�Ƃ͌����܂��Ȃ��Ƃ���ł���܂��B���ꂪ���̖@���ɂ��폝�a�Ґ�v�҈⑰���̉�����s�����Ƃ��鍪�{�I��|�ł���܂��v�i��P�R��E���a�Q�V�N�R���P�R���O�c�@�����ψ���c�^��P�Q���W�Łj
�@�܂����̂悤�ȉ��������B
�u�����ɋN�����镉���A���a���͎��S�Ɋւ��āA���������͂��̈⑰�ɑ��A���̌o�ϓI�y�ѐ��_�I�����ɂ��ĕ⏞��^���邱�Ƃ́A���̓��R�ʂ����ׂ��Ӗ��ł���B�R��ɖ{�@�̑ΏۂƂȂ��Ă���R�l�R���₻�̈⑰�͐햱�ׂ̈��邢�͂��̑��̌R���̂��߂ɋ]���ƂȂ����l�X�ł���ɂ�������炸�A�I���̓���̍��ۊ��̂��߂ɁA�w�lj���̏�����������Ƃ�����Ȃ��A�킸���ɁA���a���R�l�ɂ��ĉ����@�ɂ��ɂ߂ď��z�̑����������x������A�������҂ɑ��Ė������ҋ��^�@�ɂ��×{�̋��t�����Ȃ���ė����ɉ߂��Ȃ������B�ߋ��ɂ�����R����`�I�ȓ��{�̎p�́A�ᔻ����Ȃ���Ȃ炸���R����`�I�ȓ��{���s�����푈������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł������Ƃ��Ă��A����͗v����ɍ��Ƃ��Ė��R�S�̂Ƃ��Đӂ�����ׂ����̂ł����āA���̋@�\�̒��ɂ����āA�����̍��ƌ��͂ɂ��R���ɕ������߂�ꂽ�X�̐l�X�ɂ݂̂��̐ӂ킹�āA�R���̂��ߋ]���ƂȂ����l�X�ɑ��ĕ⏞���s�����ƂȂ�����R�ƕ��u���邱�Ƃ́A�����Ƃ��ē���َ�����Ƃ���ł��낤�B�{�@�̗��Ă��ꂽ�̂����悤�ȕs���Ȏ������u�a�����ƂƂ��ɔr�����邱�Ƃ��Ӑ}�������̂ł����āA���̎�|�́A�܂����������ЊQ�ɑ���⏞���s�����Ƃ���Ƃ���ɂ���̂ł���B�����A�⏞�Ƃ�������ɂ́A���̖��ɒl���A���̌o�ϓI�A���_�I�������Ă�ɏ\���Ȃ��́A���Ȃ��Ƃ����̋Ɩ���̍ЊQ�ɑ���⏞�̏����x�Ə\���ɋύt�̂Ƃꂽ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�R��ɁA�ˑ�Ȑ��ɂ̂ڂ�Ώۂɑ��Ă��̖��ɒl���鍑�ƕ⏞�̐ӂ��������邱�Ƃ́A�����̉䍑�̍����͂��邢�͍�����������l���Ĉ⊶�Ȃ���]�ݓ�Ƃ���ł���B�����Ŗ{�@�́A���͂Ɍ��������x�ɂ����āA�⏞���ׂ��l�X�ɉ��}�I�ȉ���[�u���u���邱�Ƃɂ���āA�����⏞�̐ӂ����o���Ă���Ƃ������ӂ��З����A���킹�Ă��̑[�u�������̐l�X�̐��v�̈ꏕ�Ƃ��Ȃ邱�Ƃ����҂������̂ł���B�{���ɂ����āw���ƕ⏞�̐��_�Ɋ�Â��c�c���삷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�x�Ƃ������Ă���̂́A�ȏ�̂悤�Ȏ�|��\���������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��v�i�������������r�ӈ�A����؈�w�폝�a�Ґ�v�҈⑰������@�̉���Ɖ^�p�x�P�W�`�X�ŁE�����@�K�o�Łj
�@��L��|�����ɂ��Ɓu�R����`�I�ȓ��{�̋@�\�̒��ɂ����āA�����̍��ƌ��͂ɂ��R���ɕ������߂�ꂽ�X�̐l�X�v�ł���폝�a�ҁA��v�҂́u���{�̍s�ׁv�ɂ��u�푈�̎S�Ёv�̋]���҂ł��邪�䂦�ɁA�푈���s��̂ł�������������̐ӔC�ɂ�肻�̉�����Ȃ��Ƃ������ƕ⏞�̐��_�Ɋ�Â��āA���@�͗��@���ꂽ���̂Ǝ���B�����ł���Ƃ���A�����u���{�̍s�ׁv�ɂ��v�u�푈�̎S�Ёv�̔�Q�҂Ƃ��āA�{���ې�ɂ�茴�������F�߂��悤�ȔߎS�Ŏc�s�Ȕ�Q�������T�i�l��ɑ��Ă��A���ƕ⏞�̐��_�Ɋ�Â��ĕ⏞���Ȃ���đR��ׂ��ł���B
�E�@��p�Z���ł����v�҂̈⑰���ɑ��钢�ԋ����Ɋւ���@���̍��ƕ⏞�̖@�I���i
�@���@�P���ɂ��ƁA���̖@���̎�|�͎��̒ʂ�ł���B
��P���@���̖@���́A�l���I���_�Ɋ�Â��A��p�Z���ł����v�҂̈⑰���ɑ��钢�ԋ����Ɋւ��K�v�Ȏ������߂���̂Ƃ���B
�@���@�́A�^��}��v�̋c�����@�i���a�U�Q�N�X���Q�X���@����P�O�T���j�ł��������c�@���t�ψ���ψ����ΐ�v�O�͓��@�̋N���Ăɂ��Ď��̂悤�Ȏ�|�������s���Ă���B
�u�i�ΐ�ψ����j�@
�@�����m�̂悤�ɁA��Q�����E���ɂ����đ����̑�p�̐l�X�����{�̌R�l�R���Ƃ��ē�������A�펀���ꂽ�蕉�����ꂽ�肵���������Ȃ��Ȃ��̂ł���܂����A���{�l�̌R�l�R���ł�������v�҂̈⑰�y�ѐ폝�a�҂ɑ��ẮA���A�폝�a�Ґ�v�҈⑰������@���̐����R�l�����̕����ɂ��A�N���܂��͈ꎞ�������x������Ă���܂��B
�@������ɁA��p�̐l�X�́A���A���{���Ђ����������ʁA����@�܂��͉����@���K�p����Ȃ����ƂƂȂ����̂ł���܂��B
�@�������Ȃ���A��Q�����E��풆�A���{�l�̌R�l�R���Ƃ��ē������ꂽ��p�̐l�X�A���ɐ�v�҂̈⑰��d�x�̐폝�a�҂̕��X�ɑ��A����̂܂܂Ő��ڂ��邱�Ƃ́A�l���I�ϓ_�����������邱�Ƃł͂Ȃ��Ƒ����܂��B
�@���������܂��āA���̍ہA�����̕��X�ɑ��A���ԓ��̈ӂ�\�����|�Œ��ԋ��܂��͌��������x�����邽�߂̖@���𐧒肷�邱�Ƃ��}���ł���ƍl���A�����ɖ{�N���Ă��쐬��������ł���܂��v�i��P�O�X��E���a�U�Q�N�X���P�O���O�c�@���t�ψ���c�^��V���R�Łj
�@���{�l�̌R�l�R���ł�������v�҂̈⑰�y�ѐ폝�a�҂Ɠ��l�Ɂu���{�̍s�ׁv�ɂ��u�푈�̎S�Ёv�̋]���҂Ƃ��āA��p�Z�������v�҂̈⑰����ѐ폝�a�҂ɑ��āA�푈���s��̂ł��������Ƃ��l���I�ϓ_���珊��̋��t�����邱�ƂƂ��Ă���̂ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���u���{�̍s�ׁv�ɂ��u�푈�̎S�Ёv�̋]���҂ɂ��č��Ɣ�������ё����⏞�Ƃ͈قȂ����ȍ��ƕ⏞�@��������̂ł���B
�@�T�@�𗝂Ɋ�Â����ƕ⏞����
�@�T�i�l��ɑ���⏞���@����㞂��Ă��邱�Ƃ͂��̂Ƃ���ł��邪�A��L�e���������킹�l����ƁA�T�i�l��ɑ��𗝂Ɋ�Â�����ȍ��ƕ⏞���F�߂���ׂ��ł��邱�Ƃ͎����ł���B
�@�O�L���⏞�̏��@�̍���ɂ́A�����A�g�̂̈��S�A���_�I���R�A�����I�A�C�f���e�B�e�B�[�⑸���Ȃǐl���I�ɕی삳���ׂ��l�Ԃ̍ł���{�I�ȏ����l��N�Q���ꂽ�푈��Q�ɂ��āA�푈���s��̂ł��������Y���Ƃ�����̐ӔC�ɂ��⏞���ׂ��ł���Ƃ���𗝂��������邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@����ɁA�T�i�l��ɑ��ẮA�������@�y�ѓ��{�����@�̓`���I�̑����⏞���x�̍���ɂ��鐳�`�����̌����A���Ȃ킿�𗝂Ɋ�Â������ȕ⏞���Ȃ����ׂ��ł���B�ɂ�������炸�A���������u���Ɩ����ӂ̖@���v�Ƃ��������Ⴂ�̍R�ق������o���āA�T�i�l��̕⏞������˂������Ƃ͏𗝂Ɋւ�����ߓK�p����������̂ł���B
��S�@�{���ɂ�����𗝂̑���
�P�@�������́A�𗝂Ɋ�Â��⏞���@�Ƃ��čT�i�l�炪���R�Ŏ咣�����Ƃ���̇@���q���e�픚�҂̈�Ó��Ɋւ���@���A�A�폝�a�Ґ�v�҈⑰������@�A�B��p�Z���ł����v�҂̈⑰���ɑ��钢�ԋ����Ɋւ���@���A�C�h�C�c�A�A�����J�A�J�i�_�A�I�[�X�g���A�̑�Q�����E����ɂ�����e�⏞���@�ɂ��āA�����̕⏞���@���l���I�z���Ȃ������ƕ⏞�I�z���Ɋ�Â����̂ł��邱�Ƃ͔F�߂��A�����I�A�O��I�A�Љ�I�A�����I���̑��̌��n����̑����I�z���Ɋ�Â��A���A�l�X�����]�Ȑ܂��o�Đ��肳���Ɏ������̂��̂ł���Ƃ������R����A�������́u�䂪�����͍��ێЉ�ɂ�����@�̌n���ɁA���@��҂����ɓ��R�Ɉ�@�ȍ��ƌ��͂̍s�g�ɂ���Ĕ�Q�����l�X�����Q���ɑ��⏞�𐿋��ł���Ƃ������l�̌n���m�����Ă���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�i�Q�W�łP�s�ځj�v�Ƃ����B�܂��A�u�����_�ɂ����Ă��A������̎咣����{���ې�̂悤�Ȉ�@�Ȍ����͍s�g�ɂ���đ��Q������Q�҂����@��҂����ɓ��R�ɐ푈���s��̂ł��������ɑ��⏞�𐿋����邱�Ƃ��ł���Ƃ����𗝂͂��܂����݂��Ȃ��i�Q�W�łU�s�ځj�v�Ɣ�������B
�Q�@�������Ȃ���A����ł͂ǂ̂悤�Ȏ��Ȃ�Ώ𗝂����݂���ƌ�����̂��B
�@���̓_�ɂ��A��̂ǂ��܂ʼn��l�̌n�����߂�ꂽ��𗝂����݂���ƌ�����̂��Ƃ�����ɂ��ẮA�������͂Ȃ�疾�炩�ɂ��Ă��Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��ẮA�T�i�l��͌��R�ɂ����Ď��̗v�����咣�����B
�@�@�푈���s��̂ł��鍑�̐ӔC�ɂ����āA�푈�]���E��Q�ɑ����̔����E�⏞������ׂ��ł���Ƃ����F�����A���ۓI�ɂ������I�ɂ��������x�Ɉ�ʓI�F���ɂȂ��Ă���ƂƂ��ɁA���̈�ʓI�F���Ɋ�Â��Č����Ɉ��̕⏞���s�Ȃ��Ă����i���ꂪ���@�Ɋ�Â����̂ł���A������̂��̂ł���j�����ɑ��݂��邱�ƁB
�A�@�푈�]���E��Q���A�[�����d��ł���~�ς̍��x�̕K�v�����F�߂��A�Ȃ��̋~�ϑ[�u���Ƃ炸�ɕ��u���邱�Ƃ����������`�ɔ����邱�ƁB
�B�@�����E�⏞���t�̓��e���A�������x�ɋ�̓I�ł���A���A�������x�Ɉ�`�I�ɒ�܂邱�ƁB
�@�����̂R�v���ɂ��āA�ȉ��Ɍ�������B
�@�R�@�܂��A�v���@�ɂ��ẮA���������u�䂪���y�я��O���ɂ�������⏞�Ɋւ��闧�@�́A��Q�����E���ɂ����č��Ƃ̌��͂ɂ��]������������Q�����l�X�A���Ɉ�@�ȍ��ƌ��͂̍s�g�ɂ���Ĕ�Q�����l�X�ɑ��ẮA���Ƃ̐ӔC�ɂ����Ă��̋]���E��Q�ɂ��Ĉ��̕⏞�����ׂ��ł���Ƃ����l���I�z���Ȃ������ƕ⏞�I�z���Ɋ�Â����̂Ɖ������B�v�i�Q�V�łP�U�s�ځj�Ɣ������ĔF�߂�Ƃ���ł���B
�@���������āA���łɌ����_�ɂ����Ĕ�T�i�l���͐��⏞�����ׂ��Ƃ������l�̌n���𗝂ɂȂ��Ă���Ƃ�����B
�@�S�@���ɗv���A�ɂ��ẮA�������́A�ې�̎�����S�ʓI�ɔF�肵�Ă���A���̔F��́A�T�i�l�����咣�����ې�̎����S�ʂɋy��ł���B
�@�����ɂ��ẮA�Ȍ��ɏq�ׂ�ƁA�܂����ɁA���{�R�̉��Q�s�ׂ�F�߂��B�u�P�X�S�O�N����P�X�S�Q�N�ɂ����āA�V�R�P������P�U�S�S�������ɂ���āi�R�O�łP�R�s�ځj�v�A�ˌ��i�ˏB�j�A�J�g�A�퓿�ɂ̓y�X�g�ۂ𓊉����A�]�R�ɂ̓R�����ۂ��g�p���Ē��ڍU�����A�u�ە���̎���g�p�i�ې�j���s��ꂽ�v�i�R�O�łP�T�s�ځj�ƔF�߂��B
�@��Q�ɁA�`�d�ɂ��ې��Q��F�߂��B�u�ˌ��ł̃y�X�g�́A�`�G�A���z�A���R���A�����F�̂悤�ɂ��̎��ӂ̒n��ɂ��`�d���A�傫�ȋ]���������炵���v�i�R�P�łX�s�ځj�ƔF�肵���B�܂��u�P�X�S�Q�N�R���ȍ~�A�퓿�s�X�n�̃y�X�g���_�����ɓ`�d���Ă����A�e�n�ő����̋]���҂��o�����B�v�i�R�S�łR�s�ځj�ƔF�肵���B���̂悤�ɓ`�d�ɂ���Q�̊g�傪�F�肳��ې�̎c�s������w���m�ɂȂ����B
�@��R�ɁA�ې�̖��ߎw���n���ɂ��āA�u�ە���̎���g�p�́A���{�R�̐퓬�s�ׂ̈�Ƃ��čs��ꂽ���̂ŁA���R�����̎w�߂ɂ��s��ꂽ�v�i�R�S�łQ�R�s�ځj���Ƃ�F�߂��B
�@��S�ɁA�ې�̋]���҂ɂ��āA�{���ٔ��̔�Q�n�W�����S�̂̍ې�ɂ�鎀�S�҂̐����P���l���邱�Ƃ�F�肵���B�����S�̂̍ې�̋]���Ґ��͐��P�O���l�ɂ̂ڂ�ł��낤�ƍl������B
�@��T�ɁA�������͍ې�̎c�s����F�߂��B�u�y�X�g�͎Љ�`�Ԃ���ē`�d���A�l�X�����X�Ɏ��ɒǂ���邱�Ƃ���A���ʂƂ��݂��̋^�S�ËS�������A�n��Љ�̕���������炷�ƂƂ��ɁA�l�X�̐S���ɐ[���ȏ��Ղ��c���B�v�i�R�T�łP�R�s�ځj�u�q�g�Ԃ̗��s�����܂�������A�a���̂����R�̐����E�ŕۑ�����A�q�g�̊ԂɊ�������\���������c������B���̈Ӗ��ŁA�y�X�g�́A�n��Љ������邾���ł͂Ȃ��A�����������Ԃɓn���ĉ�������a�C�ł���v�i�R�T�łP�V�s�ځj�ƔF�肵���B�܂��R�����́A�u�`���͂������A���X�Ǝ��҂��o��ƒn��Љ�ɂ����č��ʂ₨�݂��̋^�S�ËS���������Ƃ������B�v�i�R�U�łQ�s�ځj�ƔF�肵���B
�@���������āA�푈�]���E��Q���A�[�����d��ł���~�ς̍��x�̕K�v�����F�߂��A�Ȃ��̋~�ϑ[�u���Ƃ炸�ɕ��u���邱�Ƃ����������`�ɔ����邱�ƂƂ����A�v���A�́A���R�ɖ�������Ă���Ƃ�����B
�@�T�@�Ō�ɗv���B�ɂ��ẮA�T�i�l��̐����̓��e���A��̓I����`�I�ɒ�܂��Ă��邱�Ƃ͑�����v���Ȃ��B
�@�ȏ�q�ׂ��Ƃ���A�{���ɂ����ẮA�𗝂Ƃ��ĔF�߂���ׂ��v���̇@�Ȃ����B�����ɏ[������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�ٔ����́A�[�I�ɏ𗝂Ɋ�Â��Ĕ������A�T�i�l��̐�����F�߂�ׂ��ł���B
��T�@�𗝂Ɋ�Â����ٔ���
�@�P�@�����P�S�N�V���P�Q���A�����n���ٔ���������P�S���ŁA�𗝂Ɋ�Â��ĂȂ��ꂽ�ƍl���������I�������������B����́A�����R���Ȃ̏Z���ł��������A�m���A�P�X�S�S�N�X���A���{���{�ɂ���Ėk�C���ɋ����A�s���ꂽ��ʼnߍ��ȘJ������������A����ɂ͂���ɑς����˂đ����m�푈�s�풼�O�̂P�X�S�T�N�V���ɍ�Əꂩ�瓦�����A���̌�P�R�N�Ԃ̒����ɂ킽���Ėk�C���̎R���œ���������]�V�Ȃ�����A����ɂ���đς�����_�I��ɂ������Ƃ��č��ɑ����̑��Q�̔��������߂����⏞�ٔ��̂ЂƂł���i�����W�N�i���j��T�S�R�T�����Q�������������j�B
�@�Q�@���̑i�ׂ̍ő�̑��_�́A���A�m���k�C�����łP�R�N�Ԃ��̒����ɂ킽
�蓦��������]�V�Ȃ����ꂽ���ƂɊւ��A�퍐���ɋ~�ϋ`�����F�߂��邩�Ƃ������ƂƁA���̂悤�ȋ~�ϋ`���ᔽ�Ɋ�Â����Q�������������F�߂���Ƃ��Ă��A���ꂪ���Ɣ����@�ŏ��p����閯�@�V�Q�S����i�̏��ˊ��Ԃ̓K�p�ɂ����ł����ƌ����邩�ł������B�ٔ����́A���̓�̑��_�ɂ��ĔF�肵�A�퍐�����~�ϋ`����ӂ����s��ׂ̈�@�𗝗R�Ƃ��鑹�Q������������F�߁A����ɁA���Ă̓��ꐫ���l�����Ė��@�V�Q�S����i�̋K��̓K�p�𐧌����锻�f���������B
�@�R�@�𗝘_�Ƃ̊֘A�œ��ɒ��ڂ��ׂ��́A���̌�҂̑��_�Ɋւ���ٔ����̔��f�ł���B�ȉ��ɓ��Y���_�Ɋւ��锻�����������p����B
�u�E�E�E�퍐�́A����̍s���������A�s�E�����J���ɗR�����A���������炪�~�ϋ`����ӂ������ʐ��������A�m�̂P�R�N�Ԃɂ킽�铦���Ƃ������Ԃɂ��A����̎�ł��̂��Ƃ𖾂炩�ɂ��鎑�����쐬���A��������͗��A�m�ɑ��锅�������ɉ�����@��������ɂ�������炸�A���ʓI�ɂ��̎����̑��݂����A��������s�킸�ɕ��u���āA�����ӂ������̂ƔF�߂���Ȃ��̂ł���A���̂悤�Ȕ퍐�ɑ��A���Ɛ��x�Ƃ��Ă̏��ˊ��Ԃ̐��x��K�p���Ă��̐ӔC��Ƃꂳ���邱�Ƃ́A���A�m�̔������Q�̏d�傳���l������ƁA���`�����̗��O�ɒ����������Ă���ƌ��킴��Ȃ����A�܂��A���̂悤�ȏd��Ȕ�Q���������A�m�ɑ��A���ƂƂ��đ��Q�̔����ɉ����邱�Ƃ́A�𗝂ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B����āA�{�����Q�����������̍s�g�ɑ��閯�@�V�Q�S����i�̏��ˊ��Ԃ̓K�p�͂���𐧌�����̂������ł���B�v
�@�S ���������F�肵���悤�ɁA�{���ې�̔�Q�́A��L���A�m�̎��Ăɔ䂵�Ă��A���̋K�́A�ߎS���A�c�s���ɂ����Ă���w�[���ł���B����ɑ��āA�����̕⏞���@���Ȃ����Ƃ𗝗R�ɕ⏞�����ۂ��邱�Ƃ͂܂��ɐ��`�����̗��O�ɒ����������Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�
��S�́@�������@�ɂ��ƂÂ��Ӎߋy�ё��Q��������
��P�@�@���P�P���P�����K�p����Ȃ��Ƃ̔F��������������̌��
�@�P�@�������̌��
�@�@(1)�@�܂��������́A�u������@�Ȍ����͂̍s�g�ɂ���đ��l�ɑ��Q��^�����Ƃ����@���W�́A�s�גn���O���ł���A�܂���Q�҂��O���Ж��͊O���ɏZ����L����҂ł����ďO�I�v�f��L���Ă���Ƃ��Ă��A�@�Ⴊ�ΏۂƂ��Ă���O�I���@�W�ɂ͓�����Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B��������ƁA�����͂̍s�g�������Ƃ��鍑�̑��Q�����ӔC�̖��́A�@��̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ�����A�@��P�P���P���́u�s�@�s�ׁv�Ƃ����P�ʖ@���W�ɂ͓����炸�A�������̓K�p������̂ł͂Ȃ��B�v�i�������Q�P�Łj�Ƃ��āA���Ɣ����@���K�p����鎖���͌��@�����ł��莄�@�͓K�p����Ȃ��̂ŁA���ێ��@���K�p���ꂸ�A�O���@���K�p����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ���B
�@���Ɍ������́A�u�퍐�i���j����@�Ȍ����͂̍s�g�ɂ�葼�l�ɑ��Q��^�����ꍇ�̖@���W�́A��Q�҂��猩��A����Q�̉̕K�v���ɂ����đΓ������ҊԂ̕s�@�s�ׂ̏ꍇ�ƕς��͂Ȃ����A���Q�҂ł���퍐���猩��A�����͍s�g����@���ǂ������傫�Ȗ��ƂȂ�A���̓_�����Ǝ匠�݂̍���ɂ��e�����y�ڂ����̂ł���B
�@���̂悤�ɁA�퍐�i���j�̌����͂̍s�g�ɋN�����鑹�Q�����ӔC�ɌW��@���W�́A��Q�҂̋~�ρA���Q�̌����ȕ��S�Ƃ������ʂ̖ʂł͖@��P�P���P���̕s�@�s�ׂƓ��l�̐��i�̂��̂Ƃ����邪�A�䂪���̌����͍s�g�̓K�@��@�i�K�ہj�����ɂȂ鐬���v���̖ʂłَ͈��ȗv�f������A���̓_�ŁA���̂悤�Ȗ@���W�͑Γ������ҊԂ̏��R���鎄�@�W�Ƃ͈قȂ�A���@�I�v�f���܂ނ��̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�i�������Q�O�Łj�Ƃ��āA��@�Ȍ����͂̍s�g�ɂ���Đ������@���W�́A��Q�҂̋~�ρA���Q�̌����ȕ��S�Ƃ������ʂ̖ʂł͖@��P�P���P���̕s�@�s�ׂƓ��l�̐��i�̂��̂Ƃ��Ȃ���A�����s�ׂ̌��@�I�F�ʂ��]�X����B
�@�@(2)�@�������A���̔����́A���ێ��@�ɑ��闝���Ɍ�����B���ێ��@�́A�����@�Ƃ͎������قɂ���A�قȂ����@�̌n�ł���A�������@��̉��߂ɂ���č��ێ��@�̉��߂��K�肳��A���̌��ʂƂ��Ď����@�̉��߂����ێ��@��̖@����������E����Ƃ����l���́A���ł���B���ɁA�������̖@�̌n�̒��̂P�ɂ����Ȃ����{�̎����@�ɂ���āA���ێ��@�̉��߂����肳���̂́A���ł���B
�@�m���ɁA�������@�̉��߂ƍ��ێ��@�̉��߂�����ƂȂ邱�Ƃ͑����B�������A����͌��ʘ_�ł���A���ێ��@��̖@������́A�����܂ł����ێ��@�Ǝ��̌��n����Ȃ����ׂ����̂ł���B
�@�@(3)�@�Ⴆ�A���̌���ɂ����āA���@�ł���ːЖ@�����ێ��@�ɂ���ēK�p����邱�Ƃ�����B
�@�����ɂ���ĕv�w�̎����ǂ��Ȃ邩�Ƃ������ɂ��ẮA�e�������@��A�v�w�����ƕv�w�ʐ����x������B�����āA���{�@�́A�v�w�������̗p���Ă���B
�@�����ɂ���ĕv�w�̐����ǂ��Ȃ邩�ɂ��ẮA���ێ��@���_��A���͌l�̐l�i�̖��ł���Ƃ��Ă��̑��l�@�ɂ��ׂ��ł���Ƃ�����ƁA�����̌��͂ł���Ƃ��č����̌��ʂ��K������@�ɂ��Ƃ�����Ƃ����݂��Ă��邪�A������ɂ���A���{�l���O���l�ƍ������ĕv�w�̏틏�������{�ɂ���ꍇ�ɂ́A���{�l�̎��ɂ��Ă͓��{�@���K�p�����͂��ł���i�����̌��͂ɂ��Ă͖@��P�S���j�A�]���ē��{���@���K�p����A�v�w�͓����ƂȂ�ׂ��ł���Ƃ���A���{�ːЖ@�͓��{�l�ƊO���l�Ƃ̍����ɂ����Ă͓��Y���{�l�̎��͕ς��Ȃ����ƂƂ��Ă���A���������ČːЖ@��͕v�w�ʐ��ƂȂ邱�ƂƂȂ��Ă���B
�@����́A�u�ːЖ@�͌��@�ł��邩��ːЖ@���ւ�镪��ɂ͍��ێ��@���K�p����Ȃ��v���ʂł͂Ȃ��A���ێ��@�ɂ�菀���@�����肵���A����Ɉ�������҂����{���Ђ�L����Ƃ����_��A���_�Ƃ��āA���ʂɌːЖ@���K�p����錋�ʂȂ̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���ۂɁA���@���ւ�镪��ɂ��Ă����ێ��@���K�p����邱�Ƃ́A�\���ɂ��蓾��B
�@�@(4)�@�܂��A���@�ł��邩��Ƃ����āA���A���ێ��@�ɂ���Ďw�肳��鏀���@�ƂȂ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ƍl�����Ă���B����ł́A��������@�̎��@���E���@�̌��@�����i�݁A�����������@�Ǝ��@�̋敪�����Ή����Ă���A�Ⴆ�ΘJ���@�̕��쓙�ɂ��ẮA���ێ��@��K�p���A�K�v�Ȕ͈͂ɂ����āA�e��̘A�����_��p���邱�Ƃɂ��A�{���͏����@�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��@�������K�p����Ƃ�����@��p���Ă���̂ł���B
�@�@(5)�@�ȏ�Ɍ����Ƃ���A���{�̎����@��s���@�Ƃ���镪��ɂ��Ă��A���ێ��@�㓖�R�ɍs���@�ł���A���ێ��@�̓K�p�͈͊O�ł���Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�Q�@�������̌��͍s�ׂɍۂ��đ��l�ɗ^�������Q�̔����ӔC�̖@�I���i
�@�@(1)�@���͍�p���̂��̂����@��̍s�ׂł���A���@�̑Ó����镪��̖��ł������Ƃ��Ă��A���̌��͍�p�ɂ���đ��l�̌�����N�Q�����Ƃ��ɁA���̑��l�̎����Q�����邽�߂̑��Q�����̖�肪���@�̕���̖�肩���@�̕���̖��ł��邩�́A�܂��ʘ_�ł���B
�@�����ő厖�Ȃ̂͌����s�ׂ̖��ł͂Ȃ��A��Q�ɂ������̂����v�ł���A���̔����Ƃ����ɂ߂Ď��@�I�F�ʂ��������ƂȂ��Ă����ʂ��Ƃ������Ƃł���B�����s�ׂ̌��@�I�F�ʌ̂ɁA���ێ��@��̖��Ƃ��Ė@��̓K�p��r�����ׂ����R�͑S���Ȃ��̂ł���A�������̗���ɂ͑S�����R���Ȃ����̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@��O�ɂ����āA���Z���B�g���m�́A�u�����`���n���m�s�׃m���ڃm���ʃj��X�V�e���m�s�׃m���ʃj��L�e���X����m���ʃ^���A���e���ߑ��m�����^���s�@�s�׃J���@��m�s�׃^���g�X�����V�J�׃j���R�j�V�����@�I�m�W�i���g�H�t�����X�B���V�e�l�m�������n�ꃉ�l�m���v�m�׃j�F�������A���m�@����m�����j���e�l���݊ԃj���P�����Q�����g�S�R���l�i�����m�i�����ȃe�A�V�����@�W�g�Ř�X�w�L�n���R�i���w�V�v�i���Z���B�g�u���{�s���@�㊪�v�X�P�W�Łj�ƁA��������s�@�s�ׂ����@��̍s�ׂł����Ă��A���̑��Q�����W�́A���@�W�ł���ƁA�����ɏq�ׂĂ�����B
�@�@(2)�@���̖��́A��㍑�Ɣ����@�̐���ɂ���āA�����@�̐��i�@���Ƃ��Ę_������悤�ɂȂ����B
�@���Ɣ����@�́A�����͂̍s�g�ɂ��č��E�����c�́i�ȉ��u�����v�Ƃ����B�j�̐ӔC��F�߂��@���ł���̂ŁA�s���@�̂P�ł���Ƃ���Ă���B
�@�������ɁA���̈Ӗ��ɂ����Ă͍s���@�ł���B�������A���̖@���́A�����̎g�p�ҐӔC�ɂ��Ė��@�̓K�p��r��������̂Ƃ��Ă���A�g�p�ҐӔC�ɂ����Ă͖��@�̓��ʖ@�ł���B���@�̓��ʖ@�ł���̂ł��邩��A���Ɣ����@���{���ɂ����Ă͎��@���鐫�������{�ɂ����ėL���邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�s���@���鐫������ʂɂ����Ă͗L����Ƃ͂����A���{�ɂ����Ă͎��@���鐫����L���鍑�Ɣ����@���K�p�����ׂ���ʂ́A���{�ɂ����Ă͎��@���K�p�����̈�ł���A���ێ��@�ɂ�菀���@�����肳��A���̏����@���K�p����邱�ƂɂȂ�̂́A���R�ł���B
�@���̂��Ƃ́A�R�������[�̌n���l����A��薾�炩�ƂȂ�B���Ȃ킿�A�R�������[�ɂ����ẮA�������̈�@�ȍs�ׂ͂��͂�����̔��e�ɂ͓���Ȃ����̂Ƃ���A���Y���������l�Ƃ��ĕs�@�s�אӔC�����̂Ƃ���Ă���B���̂��Ƃ�����A����������@�ȍs�ׂ��s�����ꍇ�́A�{���I�ɂ͎��@�̕s�@�s�ׂ̗̈�ł���A�������{�ɂ����Ă͍����̐ӔC��F�߂����ʖ@�����݂��Ă��邽�߁A�s���@���鐫���������������Ă���ɂ����Ȃ��̂ł���B
�@���{�ɂ����Ă��A�ٔ������t���鎖���ԍ��́A���Ɣ������������͒ʏ�̎��@��̎����Ɠ��l�ɁA��P�R�ɂ����Ắi���j�ł���B����́A�ٔ������̂����Ɣ��������������s�������Ƃ͈قȂ�A��ʂ̎��@��̑i�ׂƓ��l�Ɉ����Ă��邱�Ƃ��������̂ł���B
�@�@(3)�@���̓_�ɂ��āA�L�͂Ȋw���͈�v���č����@�����@�ɑ����邱�Ƃ�F�߂āA���̂悤�ɐ������Ă���B
�@�u���Ƃ�����c�̂ɑ��ĕs�@�s�ׂɂ�鑹�Q���������̑i�ׂ́A���ꂪ�����͂̍s�g�ɋN�����A���Ɣ����Ɋ�Â��ꍇ���A�Ȃ������i�ׂ̐�����L�����@��̓����ґi�ׂł͂Ȃ��B�s���s�ׂ̌��ʂƂ͒��ڂ̊W�͂Ȃ��A���v�̕ی삪���ƂȂ�Ɏ~�܂邩��ł���v�i�Y���Y�u�s�����ז@�v�@���w�S�W�P�P�R�Łj�B
�@�u���̐ӔC�ɂ́A�]���Ƃ͑S���قȂ����p�x����A���̓��ꐫ�������������Ƃ��ł���v�u����ǂ��A����́A��ʕs�@�s�ח��_�̔��W�̒��Ō������������ꐫ�Ȃ̂ł����āA���@�ɓ��L�̐ӔC���_�ƌ���ׂ��ł͂Ȃ��B�]���āA���Ɣ����@���A���@���x�̒��ŁA���@�̓��ʖ@�̒n�ʂɂ�����̂ƔF�ނׂ��v�i�������a�u���ƕ⏞�@�v�@���w�S�W�W�X�Łj�B
�@�u���Ɣ����ӔC�́A�`���I�ɖ����@�̗̈�ɑ�����B�������̐E���ᔽ�����Ƃ����Ƃ̌��@�I�܂��͎��@�I�Ȋ����̈�ōs���Ă���Ƃ��Ă��A���̂��Ƃɕς��͂Ȃ��B����͗��j�I�Ɍ������W�����@�I�ȈϔC�W�ƌ��闝�_���N�_�ɂ��邩��ł���v�i�R���҉�u�O����S�I�R�Łv�Q�T�U�Łj�B
�@�ٔ��������A���l�Ɏ��@�����̂�A���Ɣ�������������ʏ�̖����i�����Ƃ��Ă���B�ٔ���Ƃ��āA�u���܂��͌����c�̂��{�@�Ɋ�Â����Q�����ӔC���W�́A������A���@��̕s�@�s�ׂɂ�葹�Q�����ׂ��W�Ɛ����������邩��A�{�@�Ɋ�Â����Q�����������͎��@��̋��K���ł����āA���@��̋��K���ł͂Ȃ��v�i�Ŕ����S�U�E�P�P�E�R�O�A���W�Q�T�E�W�E�P�R�W�X�Łj�Ɣ���������̂�����B
�@���̂悤�ɁA���Ɣ����i�ׂ́A�Γ��̓����ҊԂő��Q�����������̑��ۂ𑈂����̂ł���A���̌����ƂȂ���@��̍s�ׂ𑈂��̂ł͂Ȃ�����A�����܂ŁA���v�̕ی�̂��߂Ƃ������i��L���A���@�̕���ɑ�������̂ƍl����ׂ��ł���B
�@�@(4)�@�������́A�u�퍐�i���j�̌����͂̍s�g�ɋN�����鑹�Q�����ӔC�̑��ۂ������ɂȂ�ꍇ�ɂ́A�퍐�̌����͂̍s�g�̓K�ۂ����ɂȂ邪�A���Y�����͂̍s�g�͂��ꂼ��̍����ƂȂ�䂪���̖@���Ɋ�Â��čs������̂ł���̂ɁA���̖@���W���@��P�P���P���ɂ���đ����̖@���ɏ]���Ĕ��f����邱�ƂɂȂ�A���鍑�̖@���ł͓K�@�Ƃ��ꑼ�̍��̖@���ł͕s�K�@�Ƃ���鎖�Ԃ����蓾�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�������A���̂悤�Ȏ��Ԃ��䂪���̖@����\�肳��Ă���Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������āA�����͂̍s�g�̏�ʂ́A���Ƃ��قȂ��Ă��݊��\�ł���Ƃ̑O��ɗ����@�Ƃ͐��i���قȂ�Ƃ����ׂ��ł���B�v�i�������Q�O�Łj�Əq�ׂāA�����͂̍s�g�ɂ��@���W�͑����̖@���̔ᔻ�ɂ��炳��Ă͂Ȃ�Ȃ��|��������B
�@�������A���̓_�́A�@��P�P���Q���ɂ��A���{�@�ň�@�Ƃ���Ȃ��ꍇ�́A�s�@�s�ׂƂȂ�Ȃ��Ƃ���Ă���A�����������_�ɂ��@��͔z�����Ă���̂ł��邩��A�S�����R���Ȃ��Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�܂��A���ɁA���Ɣ��������̖�肪���@�I�@���W�ł���Ƃ���ƁA�ɂ߂ĕs�����Ȃ��ƂɂȂ�B
�@���Ȃ킿�A���@�I�@���W�ł���Ƃ���ƁA���@�̑��n�I�K�p�̌������Ó����邱�ƂɂȂ�A�@���{�̍��Ɣ����@�́A�����Ƃ��ē��{�ɂ�������{�̌������̕s�@�s�ׂɂ̂ݓK�p����邱�ƂɂȂ�ƂƂ��ɁA�A�O���̌��@�i���Ɣ����@�j��K�p���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B��������ƁA���Ƃ��A���{�̌��������O���ɂ�����������Ɍ�ʎ��̂��N�����A��Q�҂����{���ɑ��鑹�Q���������i�ׂ���{�̍ٔ����ɒ�N�����Ƃ���B���̏ꍇ�A���Ɣ��������̖�肪���@��̖��ł���Ƃ���A���{�̍ٔ����͓��{�̍��Ɣ����@��K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̒n�͊O���ł���A�@�̌��������ɂȂ邩��ł���B�܂��A�A�̌�������A���Y�O���̍��Ɣ����@��K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂɂȂ�B�������Ȃ���A���̏ꍇ�������炷��ΒP�Ȃ��ʎ��̂ɂ������A���܂��܉��Q�҂����{�̌������̌������ł������ɂ����Ȃ��̂ł���B���̂悤�ȏꍇ�ɓ��Y�O���@�Ɋ�Â��������邱�ƂɂȂ錋�_�͖��炩�ɕs���ł���B���Ɣ����ӔC�̖������@�I�@���W�ƍl����Ƃ������Ƃ́A���̂悤�ȕs�s���Ȍ��ʂ���u������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł���B
�@
�R�@���ݕۏ؎�`�ƍ��Ɣ����@�̐��i
�@�������́A�u�䂪���̍��Ɣ����@�́A���̂U���ŁA�O���l����Q�҂ł���Ƃ��͑��ݕۏ�����Ƃ��Ɍ����ē��@��K�p����Ƃ��Ă��āA���@�����Ƃ̗��Q�ɐ[���W���Ă��邱�Ƃ������Ă���Ƃ�����B�v�i�������Q�P�Łj�Ɣ�������B
�@�������A���ݕۏ؎�`���Ƃ�Ƃ������Ƃ��A�������ɍ��̗��Q�ɒ��ڊW����̈���\�����A���@�̗̈�ƈقȂ邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃɂ͉��̍������Ȃ��B�Ⴆ�A���ݕۏ؎�`���Ƃ闧�@��ɂ́A�����@�Q�T���A���p�V�Ė@�Q���̂T��R���A�ӏ��@�U�W���R���A���W�@�V�V���R���������邪�A�T�^�I�Ȏ��@�I�����̖��ł���B
�@����ɁA�����@�U���́u���l���v�ƒ�߂錛�@�P�V���⌛�@�O���̍��ێ�`�̌����ɒ�G����̂ł͂Ȃ����Ƃ����A�L�͂Ȉጛ�_������i�L�q�ɋg�u�������Ɣ����@����v�Q�T�Łj�B
�@�܂��A���Ɣ������x�����y���Ă������݂̐��E�ɂ����āA����̐����Ƃ��đ��ݕۏ؎�`�͂��͂���ۓI�ł͂Ȃ����A����x��ł͂Ȃ����Ƃ����w�E���Ȃ����悤�ɂȂ��Ă��Ă���̂ł���B�������������ɂ��Ă̑��ݕۏ؎�`�̌�����l����Ƃ��A����������o���āA���@�Ƃ͈قȂ鍑�Ƃ̗��Q����������̂́A�؈Ⴂ�̋c�_�Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@���̏�A�����@�S�����u�����͌����c�̂̑��Q�����̐ӔC�ɂ��ẮA�O�R���̋K��ɂ��̊O�A���@�̋K��ɂ��B�v�ƒ�߁A�����@�̊�{�@���ق��Ȃ�ʖ��@�ł��邱�ƂL���Ă���̂ł��邩��A�����@���\�肷��@���W�ɂ����Ă��A�����܂ł��̐����͎��@�W����{�ƍl����ׂ��ł���A�����ł���ȏ�A�@��P�P���ɂ����s�@�s�T�O�́A���R�ɂ��������@���W������ۂ��Ă���Ƃ����ׂ��Ȃ̂ł���B
�S�@���ێ��@�̓K�p
�@�{���ɂ����ẮA���Q�҂́A���ۖ@�Ɉᔽ������̐����ȍ����Ȃ��A��Q�҂̐g�́E���N�E�������Q����s�ׂ��s���A���ۂɂ������Q�����̂ł���B���̖@���W�́A���ێ��@��A�s�@�s�ׂƐ������肳���B
�@�s�@�s�ׂɂ��ẮA�@��P�P���P���ɂ��A�u�����^�������̔����V�^���n�m�@���v�i�s�@�s�גn�@�j���K�p�����B
�@���������̔����n�Ƃ����A���_�ɂ��ẮA���̉��߂ɂ͕������蓾�邪�A������ɂ���A�{���ɂ����ē��{�R���ۂ��U�z���铙�̍s�ׂ������n���A��Q�����������n���A����������ؖ������ł���A�����ؖ����@����������L���Ă����n�Ȃ̂ł��邩��A���������̔����n�@�́A���ؖ����@�ł���B
�@�Ƃ���ŕs�@�s�ׂɂ��ẮA�@��P�P���Q���ɂ��A���{�@���d���I�ɓK�p�����B���́A���{�@���d���I�ɓK�p�����Ƃ����̂́A�s�@�s�ׂƂ����̂͌����Ɋւ����̂ł���̂ŁA�@��n�̌������l���������߂ł���Ƃ���Ă���B���Ȃ킿�A����́A�@��n�ɂ����Ĉ�@�ł���Ƃ���Ă���s�ׂɂ��ĕs�@�s�ׂł͂Ȃ��Ƃ��邱�Ƃ́A�@��n�̌����ɒ�G���邱�ƂɂȂ�A�s�K���ł���̂ŁA�@��n�@���d���I�ɓK�p���邱�Ƃɂ����̂ł���B�����āA�@�Ⴊ�K�p�����Ƃ������Ƃ́A�@��n�͓��{�ł���̂ŁA���{�@���d���I�ɓK�p�����|���K�肳�ꂽ�B
�@���̖@��n�@�̏d���K�p�́A��L�̂Ƃ���A�@��n�̌����d���Đ݂���ꂽ�K��ł���B���̊ϓ_���炷��Ȃ�A�����œK�p���ׂ��́A�ٔ����̖@��n�@�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�ٔ��ɂ����Ē�G�����ƂȂ�@��n�̌����́A���R�A�ٔ����̌����ł���A�ٔ����̌����Ɗւ��̂́A�ٔ����̖@��n�@������ł���B
�T�@���_
�@�ȏ�̂Ƃ���A�@��P�P���P���K�p��ے肷�錴�����́A�S���������Ȃ����̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��Q�@�@��P�P���Q���̓K�p�͂Ȃ�
�@�P�@�{���ې�́A���������F�߂�悤�ɁA�W���l�[�u�E�K�X�c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ������@�s�ׂł������B���{�R����@����F������т��Ĕ閧���ɂ�������������s�����B
�@�{���ې�́A��T�i�l�̓K�@�Ȍ����͍s�g�Ƃ͂������u�ی삷�ׂ����͍�p�v�ɂ͂�����Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���������ē��{�@�ɂ����Ă��u�s�@�Ȃ炴��Ƃ��v�Ƃ������Ƃ͂ł����A�@��P�P���Q���̓K�p�͂Ȃ��B
�Q�@�@��P�P���Q���́A�u�O���m�K��n�s�@�s�׃j�t�e�n�O���j���e�����V�^�������J���{�m�@���j�˃��n�s�@�i���T���g�L�n�V���K�p�Z�X�v�ƋK�肵�Ă��邪�A�{�����Q�s�ׂ́A���̑ԗl�ɂ����Ă���Q�̒��x�ɂ����Ă��A���j��H�L�Ȃ��̂ł���A�����鉿�l�����݂Ă�����e�F���ꂦ�Ȃ���@�s�ׂł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�܂��A���Q�҂̌̈ӂ����������Ƃɋ^���̗]�n�͂Ȃ��B���������āA�{���ې킪�A�q�ϓI�ɂ���ϓI�ɂ��A���{�@�̕s�@�s�ׂɊY��������̂ł���A�{���̏ꍇ�A�@��P�P���Q�����K�p�����]�n�͂Ȃ��B
�R(1)�@�u���ێ��@��A�s�@�s�ׂ̏����@�ɂ��ẮA�s�@�s�ׂɊւ���@�������ێ��@��̂���������@�ł���Ƃ������R����A�Â��͖@��n�@��`��������ꂽ���A�����ł��L���F�߂��Ă����`�͕s�@�s�גn�@�ł���v�i�R�c�`��A��،h�Y�ҁu���ێ��@�u�`�v�я��@�V�ЂP�T�O�Łj�B�s�@�s�גn�@��`�ɂ��A�s�@�s�ׂ̍s�҂Ɣ�Q�҂Ƃ��Ƃ��ɂ��̐ӔC��댯��\���Ȃ����]�����邱�Ƃ��ł���Ƃ��������b�g������B�܂��A�N�Q�s�ׂ̔��������n���A�s�@�ȐN�Q��h�~���A�N�Q�ɂ�鑹�Q���s�҂ɔ��������߂邱�Ƃɏd��ȗ��Q�W�����ׂ��ł���Ƃ������R�����藧�B���������Ƃ��납��A�s�@�s�גn�@���ł������I�ł���A���ۓI�ł���ƍl�����Ă���̂ł���B�������Ȃ���A�킪�@��P�P���Q���́A�s�@�s�גn�@�̓K�p��@��n�@�ɂ���Đ�������ܒ���`���̗p���Ă���B�����ŁA�@��n�@���ǂ̒��x�����邩�����ߏ���ƂȂ�킯�ł���B���̖@��n�@�̊��̒��x�ɂ��ẮA���@����l�X�ł���A�E�@��P�P���Q���̉��߂ɂ��Ă��A���낢��ȉ��ߘ_���W�J����Ă����B�������A�ߔN�́A�s�@�s�ׂɊւ��鏀���@����̎�|�A�ړI�ɏƂ炵�č����I�ɉ��߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���̂��L�͂Ȋw���̕����ł���B�@
�@�����ł́A�@��P�P���Q���́u�s�@�v�̉��߂����ɂȂ�̂ł��邪�A����ɂ��ẮA����܂ŁA�R�̐����咣����Ă����B
�@��P���́A�s�@�s�ׂ̐����v���ł���@�̈ӁE�ߎ��A�A�����N�Q�i��@���j�A�B���Q�̔����̂����A�@�̎�ϓI��@���݂̂����߂���̂ł���B�����́A�@��P�P���Q���́u�s�@�v���u�s�@�s�ׁv�Ɖ�����͓̂��ʂ̗��R���Ȃ��s���߂��ł���A�����ǂ���u�s�@�v�Ɖ�����Ƃ��ɂ́A�s�������y�ю����Ǘ��Ƃ̊W����A�������ϓI��@���A���Ȃ킿�̈ӁE�ߎ��Ɖ����ׂ��Ƃ���B���Ȃ킿�A�@��P�P���͂R��ނ̖@����̌������A�����Ǘ��ƕs�������ɂ��Ă͕s�@���]�X�����A�s�@�s�ׂɂ��Ă����s�@�ɂ����{�@�̊���F�߂Ă���̂ł��邪�A���̂R��ނ̖@����͖{���̐�����͎��Ȃ̌����͈͂����z����s�@�i�q�ϓI��@���j�Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă���A�s�@�s�ׂ�������Ɍ̈ӂ܂��͉ߎ��i��ϓI��@���j�����d����Ă���Ƃ����\�����Ƃ��Ă���̂ł��邩��A�����ł́u�s�@�v�Ƃ͎�ϓI��@���݂̂��Ӗ�����Ɖ�����ׂ��Ƃ���̂ł���B
�@��Q���́A�E�̇@�ƇA�݂̂����߂���̂ł���B����́A�B�܂ŗv�����邱�ƂɂȂ�ƁA�Ⴆ�A�p���̕s�@�s�ז@�ɂ����Ă͑��Q�̔������s�@�s�ׂ̗v���ɂȂ��Ă��Ȃ����߁A�p���ɂ�����s�@�s�ׂɂ��䂪���ő��Q�����������Ȃ��ꂽ�ꍇ�ɂ́A�������p�ƂȂ��Q�҂̋~�ς��}��Ȃ��Ȃ邵�A�p���Œ�i����Ώ��i���A�䂪���Œ�i����Δs�i����Ƃ������ƂɂȂ��āA��Q�ҋ~�ς̉ۂ����ۍٔ��NJ��Ƃ����葱�@�ɍ��E����Ă��܂��Ƃ����s���������邩��ł���B
�@��R���́A�@��P�P���Q���̋K��̎�|�͖@��n�@��ݐϓI�ɓK�p����Ƃ������Ƃł��邩��A�s�@�s�גn�@�̓K�p�̏�ɖ@��n�@������{�@�̕s�@�s�ׂ̗v�������ׂĖ��������Ƃ��K�v�ł���A�Ƃ��āA�E�̇@�A�A�A�B���ׂĂ�v��������̂ł���B�����āA���̐����]�O�������Ƃ���Ă����B
�@�������Ȃ���A���̂悤�ȉ��߂ɗ��Ȃ�A���������s�@�s�גn�@��`���̗p�����Ӌ`�͑S�������Ă��܂����ƂɂȂ�B�O�q�̂悤�ɂ��̉��߂ł͔�Q�ҋ~�ςɌ����Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł��邩��A�s�@�s�ז@�̊�{�I�w�����O����͔F�߂������Ƃ���ł���B���������āA�s�@�s�ז@�̗��O�d������A�ܒ���`���Ƃ��Ė@��n�@�ɂ����������F�߂����悤�Ƃ���@��̎�|���ӂ܂���Ȃ�A��Q�����Ó��ł���Ɖ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@(2)�@�ȏ�̂R���̂����A�P�P���Q���́u�s�@�v����ϓI�v���݂̂Ɍ��肷��Ƃ�����P���̗���ɗ��Ȃ�A�{���ł͍s�҂Ɍ����N�Q�ɂ��Č̈ӂ����������Ƃ͖��炩�ł��邩��A�������ɂ���T�i�l�̔����ӔC��ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�u�s�@�v���s�ׂ̈�@����ʂ��������̂ƂƂ炦���Q���ɗ��Ƃ��Ă��A�{���̂悤�Ȑl�ގj��H�ȍ��ۖ@�ᔽ�̋Ɉ��̍s�ׂ��A�q�ϓI�Ɉ�@�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�������́A�����ŁA���Ɩ����ӂ̌����Ȃ���̂������o���̂ł��邪�A���Ɩ����ӂ̌����́A�������̌����͍s�g�ɔ����s�@�s�ׂɂ��āA��̂ɂ���ē��ʂɐӔC��Ȃ��Ƃ������Ƃł��邩��A����͈�@���ɂ͑S���W�̂Ȃ����Ƃł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A�ӔC�j�p���R�Ȃ����Ɛӎ��R�ƍl����ׂ��ł���B��O�̔���A�w���ɂ����Ă��A�������̌����͍s�g�ɔ����s�@�s�ׂ���@����L���邱�Ƃ͔ے肳��Ă͂��Ȃ������̂ł���B���������āA��Q���ɗ��ꍇ���A�������ɂ���T�i�l�̔����ӔC��ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�X�ɁA�S�������āA���{�@�̕s�@�s�ז@���S�ʓI�ɗݐϓK�p�����Ɖ������R���ɗ����āA�@��P�P���Q���ɂ����{���@���ݐϓK�p�����Ƃ��Ă��A���̖@��n�@�̏d���K�p�́A�@��n�̌����d���Đ݂���ꂽ�K��ł��邩��A�K�p�����̂́A�ٔ����̖@��n�@�ł���A���Ɩ����ӂ̌����Ȃ���̂��K�p�������̂łȂ����Ƃ́A�ʍ��ŏڏq�����Ƃ���ł���B
�@�@(3)�@���ǁA�@��P�P���Q���́u�s�@�v�������ɉ������Ƃ��Ă��A�{���̂悤�ȏꍇ���u�s�@�i���T���g�L�v�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����āA�������@�̓K�p��W���闝�R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
��R�@�@��P�P���R���̓K�p�͂Ȃ�
�@�@�@�@��P�P���R���ɂ�閯�@�V�Q�S����i�̗ݐϓK�p�ɂ��Č�������B�����́u���Q���������m�����v�̒��Ɏ����⏜�˂̖�肪�܂܂��̂��ǂ����̖��ł���B
�@�P�@��������
�@�s�@�s�ׂ̌��͂́A���Q�����̕��@�y�ђ��x�ȊO�ɁA�����E���ˊ��ԁA�s�@�s���̏��n���E�������A�����s�@�s�ׂɂ�����ӔC�̕��S�ȂǗl�X�Ȏ������܂�ł���A���Q�����̕��@�y�ђ��x�́A�s�@�s�ׂ̌��͂̈ꕔ�ɂ����Ȃ��B�p��̒ʏ�̈Ӗ��ɏ]���A�u���Q���������m�����v�Ƃ́A���Q�����̖��Ƃ���ɗގ�������肾�����܂ނ͂��ł��邵�A�܂��u�����v�Ƃ�������ɂ́A���炩�̌��������̎�i���w���Ă�����̂ƍl������B
�@�@���������āA�u���Q���������m�����v�Ƃ��������́A�ނ��뎞���⏜�ˊ��ԂȂǂ̖����܂܂Ȃ��Ɖ�����ׂ��ł���A�@��P�P���R���́A���̕����ʂ�A�u���Q�����̕��@�y�ђ��x�v�ɂ��ē��{�@��ݐϓK�p���邱�Ƃ��߂����̂ł���B����ɂ�������炸�A�S�ʓI�ɓ��{�@�ɂ�鐧����F�߂����̂ł���Ƃ��邱�Ƃ́A���炩�ɕ����Ƃ����������̂ł���B
�@�Q�@���@�̌o��
�@�@��P�P���R���̗��@�o�܂ɏƂ炵�Ă��A����Ɏ��������܂܂��Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@��C���ė��R���ɂ��ƁA�P�P���R���̎�|�́A�s�@�s�ׂ̋~�ϕ��@�ɂ��āA�e���̖@�ɕs���ꂪ����̂ŁA�O���@�̋~�ϕ��@�Ɠ��{�@�̋~�ϕ��@���قȂ邱�Ƃ�����A���{�@���F�߂Ȃ��~�ϕ��@�͗^���Ȃ��Ƃ�����|�Ƃ���Ă���B������������A�����⏜�ˊ��Ԃ��܂܂��Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�c���^�ɂ��ƁA��ϒd�́A�P�P���R���̒�ė��R�����̂悤�ɐ������Ă���B���Ȃ킿�A��ςɂ��ƁA�@��P�P���R���́A���{�@���F�߂��ȊO�̑��Q������F�߂Ȃ��Ƃ�����|�ł���A���Ƃ��I�����_�@�ł́A���_�ʑ��̏ꍇ�ɁA�@��Ŕ�Q�҂ɎӍ߂�����Ƃ��A�ȑO�ɏq�ׂ����Ƃ��邢�͏����ꂽ���Ƃ����ł������ƌ������邱�Ƃ��~�ϕ��@�Ƃ��ĔF�߂��Ă��邪�A���Ƃ��s�@�s�גn���I�����_�ł������Ƃ��Ă��A���{�ɂ����Ă��̂悤�ȋ~�ϕ��@��F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���B
�@���������āA�@��P�P���R���̗��@��|�́A�����ʂ葹�Q�����̕��@�y�ђ��x�ɂ��Ă̂ݓ��{�@��ݐϓK�p���邱�Ƃɂ���A�����Ɏ����⏜�ˊ��ԂȂǂ̂��̑��̎������܂߂����͂Ȃ������Ɖ������̂ł���B
�@�R�@���_
�@�ȏ�̂Ƃ���A�����E���ˊ��Ԃɂ��ẮA�@��P�P���P���ɂ��s�@�s�גn�@�������K�p����A�����R���ɂ����{�@�̗ݐϓK�p�͂Ȃ��̂ł���B
��S�@�������@�̋K��Ƃ��̓K�p�W
�@��q�̂Ƃ���A�{���ɖ@��P�P���P���̋K�肪�K�p����邱�Ƃ����炩�ł���̂Œ������@�̋K��Ƃ��̓K�p�W�ɂ��Ę_����B
�@�P�@�@���P�P���P���ɂ�菀���@�ƂȂ钆���@�̓K�p
�@�{���̕s�@�s�ׂ̌������鎖���̔����n�́A��T�i�l���{���ې�Ƃ����s�@�s�ׂ��s�����s���n���A�T�i�l�炪��Q�ɂ��������ʂ̔����n���A�Ƃ��ɒ����ł���̂ŁA�{���s�@�s�ׂ̌������鎖���̔����n�͒����ł���B
�@���������āA�{���ɂ��ẮA�P�X�S�O�N�Ȃ����P�X�S�Q�N�����̒����̕s�@�s�ז@���K�p����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�Q�@�P�X�S�O�N�Ȃ����P�X�S�Q�N�����A�����ɂ����Č��͂�L���Ă��������W�@�́A�P�X�Q�X�N�P�P���Q�Q�����z�A�P�X�R�O�N�T���T���{�s�̒��ؖ������@�ł���B
�@���̕s�@�s�ׂɊւ���K��́A��P�W�S�������P�X�W���܂ł̂P�T�J���ł���B���̋�̓I�ȏ́A�T�i�l���P�R�̑�P�W�������ʂQ�Q�R�y�[�W�ȉ��Ɏ������B
�@�R�@���̂悤�ɁA���ؖ������@�P�W�S���͈�ʓI�����N�Q�̏ꍇ�̔����ӔC���߁A���P�X�Q���y�тP�X�S���͑��l�����S�������ꍇ�́A�܂��A���P�X�R���͐g�̂̈��S��N�Q�����ꍇ�̔����ӔC���߁A����ɁA���P�X�T���͉����āA�g�́A���N�A���_�A���R�����N�Q���ꂽ�ꍇ�̈Ԏӗ��A���_�[�u�̐ӔC�ɂ��Ē�߂Ă���B�����āA���P�W�W���́A�ȏ�̊e�s�@�s�ׂ���{�s�ׂƂ����g�p�ҐӔC���߂Ă���̂ł���B
�@�S�@�{���ɂ�����s�@�s�ׂ́A��T�i�l���̌R�������̎w���n���ɂ��������Đ��s�����푈�s�ׂł��邩��A�X�̌������̍s�ׂƂ��������A��T�i�l�����̂��̂̂Ȃ����s�ׂƌ���ׂ��ł���B�����āA�����Ȃ�Ӗ��ł���������L���Ȃ����j�I�Ȉ�@�s�ׁi�ƍߍs�ׁj�Ȃ̂ł��邩��A���ؖ������@�P�W�S���ɂ���āA����ɓ��P�X�Q���Ȃ����P�X�T���ɂ���āA��T�i�l���͍T�i�l��ɑ��đ��Q�����`����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���ɍ����̂��̂Ƃ��Ă̍s�ׂƂ����Ȃ��Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ����P�W�W���̎g�p�ҐӔC�ɂ���āA���͍T�i�l��ɑ��đ��Q�����`�������̂ł���B
�@�T�@����ɁA���ؖ������@�̂P�W�S���P���Ɍ����u���Q�����v�́A��������邽�߂̓K���Ȏ�i���Ӗ����A���K�����Ɍ��肳�ꂸ�A���Q�҂��鍑�Ƃɑ���Ӎߐ������F�߂���B����ɁA�{���ې�̔�Q�҂�́A�����Ȃ��ۍU���ɂ�茒�N��Q�����ɂ�������炸�A�a�C�ɂȂ������Ƃō��ʂ����Ƃ������_�N�Q�̔�Q�����Ă���̂ł����āA�P�X�T���ɒ�߂閼�_�ɕK�v�ȏ������F�߂�����̂ł���B���_�ɕK�v�ȏ����Ƃ��ĎӍߐ������F�߂��邱�Ƃ͓��R�ł���B
�@�U�@�������@�ɏ��ˊ��Ԃ̋K��͂Ȃ��A�܂��T�i�l��Ɏ����͊������Ă��Ȃ��B
�@�@(1)�@�O�q�����悤�ɁA�{���T�i�l��̔��������̎��ԓI�Ȑ����ɂ��ẮA�@��P�P���P���ɂ�蒆�ؖ������@�̎����̋K��݂̂��������ƂɂȂ�B
�@���ؖ������@�́A�P�X�V���P���ŁA�u�s�@�s�ׂɂ���Đ��������Q�����̐������́A�������҂����Q�y�є����`���҂�m����������N�Z���ĂQ�N�ԍs�g���Ȃ��Ƃ��͏��ł���B�s�@�s�ׂ̎�����N�Z���ĂP�O���o�߂����Ƃ����܂������ł���B�v�ƋK�肵�Ă��邪�A�O�i�i�Q�N�j��i�i�P�O�N�j�Ƃ����ˊ��Ԃł͂Ȃ��������߂��K��ł���Ɖ�����Ă���B����́A���a�W�N�S���ɔ��s���ꂽ��ȉh���E���ؖ����@��������s�u���ؖ������@�������v�P�S�O�łɁA�u��P���������Ȃ邱�Ƃ͑�Q�����疾�炩�ł���B�v�Ɩ��L����Ă���B
�@�܂��A���{���@�V�Q�S����i�̂Q�O�N�����ˊ��ԂƉ������傫�ȗ��R�Ƃ��āA�ʏ�̍��̏��Ŏ������P�O�N�ł���̂ɑ��āA�V�Q�S����i���Q�O�N�ƍő�������̊��Ԃ��߂Ă��邱�Ƃ��������Ă���̂ł��邪�A���̂悤�ȗ��͒��ؖ������@�P�X�V���P���̏ꍇ�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��B���@�P�Q�T���́A��ʐ������̏��Ŏ����ɂ��āA�u�������͂P�T�N�ԍs�g���Ȃ����Ƃɂ���ď��ł���B�A���@���ɒ�߂���Ԃ��A������Z���Ƃ��́A���̋K��ɂ��B�v�ƁA�P�T�N����ʍ��̏��Ŏ������ԂƂ��Ă���̂ł���B���@�P�X�V���P����i�̊��Ԃ́A�P�O�N�ł���A��ʍ��̏��Ŏ��������͂邩�ɒZ���̂ł��邩��A��������ˊ��ԂƉ�����]�n�͂Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@���ǁA���@�P�X�V���P���O�i�̂Q�N�̎����́A��ϓI�Ȍ����s�g�\���_����i�s���n�߂鎞�����Ԃł���A��i�̂P�O�N�̎����́A�q�ϓI�Ȍ����s�g�\���_����i�s���n�߂鎞�����Ԃł���Ɖ�����Ă���̂ł���B
�@�@(2)�@�{���T�i�l��́A���{�ɂ��N���푈�̂��ƂŁA���{�R�ɂ��c�s�ȐN�Q�s�ׂ��A�T�O�N���钷���Ԃɂ킽���ē��̓I���_�I�ɋ���Ă����̂ł��邪�A���̊Ԓ����͓��{�ƌ���Ԃɂ���A���������ɂ킽���āA���{�͒�����G����������f�₵�Ă������߁A�q�ϓI�ɂ������s�g���s�\�ȏ�Ԃ������Ă����B
�@�P�X�V�W�N�ɂ悤�₭�������a�F�D��������ꂽ���A�������������ɂ�����푈���������̖�������A���ؐl�����a���ɋ��Z����T�i�l��ɂƂ��āA�q�ϓI�Ɍ����s�g���\�ɂȂ����̂́A�����Ƃ��A�P�X�X�T�N�R���X���̑K���[�����O���̔��������������_�ł���B�������O���́A�������������ɂ�����푈���������̕����ɂ́u�l�̔����܂ł͊܂܂�Ȃ��v���Ƃ𖾂炩�ɂ��A����ɂ���āA�悤�₭�����ɏZ�ލT�i�l��̐������̍s�g���͂��߂ĉ\�ɂȂ����킯�ł���B���̎��_�����i�܂ł͂Q�N�]�肵���o�߂��Ă��炸�A�P�X�V���P����i�̎������Ԃ͌o�߂��Ă��Ȃ��B
�@����ɁA�{���Ɋւ��ẮA��T�i�l���{�����A����̍s�����ې�̎������B���������Ă����Ƃ�����������B���̔�T�i�l�̉B���H��ɂ���āA�T�i�l��̌����s�g���s�\�ȏ�Ԃɕ��u����Ă����̂ł���A���������炩�ɂȂ��Ă����̂��P�X�X�O�N��ɓ����Ă��炾�����̂ł���B���������Ӗ�������A�P�X�V���P����i�̎������Ԃ͌o�߂��Ă͂��Ȃ��̂ł���B
�@�����āA�T�i�l��́A�P�X�X�T�N������P�X�X�U�N���ɂ����āA�T�i�l�㗝�l��Əo����Ƃɂ��A�͂��߂āA���{���������`���҂ł��邱�Ƌy�є����������\�ł��邱�Ƃ�m�����̂ł���B���̎��_����͂��܂������҂łV�N�������o�߂��Ă��炸�A�P�X�V���P���O�i�̎������Ԃ��o�߂��Ă͂��Ȃ��킯�ł���B
�@�@(3)�@�Ȃ��A���������̌��ʂɂ��A���@�P�S�S���P���́A�u����������������́A���҂͋��t�����₷�邱�Ƃ��ł���B�v�ƒ�߂Ă���B���̏����̈Ӗ��ɂ��āA���a�U�N�P�P�����s�̒��ؖ����@��������i��\���{�~���j�u���ؖ������@�����v�Q�T�O�ł́A�u�{�@�͏��Ŏ����̌��͂ɂ��ēƖ��@�̎�`�P���čR�ٌ��̔����ƂȂ��錋�ʁA���{���@�̔@�����Ŏ����̌��ʂƂ��Č������̂̏��ł�����̂ƂȂ��Ƃ͗��_��傢�ɈقȂ邱�Ƃɂȁ@��B�v�Ƃ��Ă���A���҂������ɂ����ł��R�قƂ��Ē��Ȃ����茠�����ł̔��f�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ɖ������̂ł���B
�@�����āA���@�P�S�W���́A�����̗��p���֎~���Ă���̂ł���A�ې�̎������B�����āA�T�i�l��̒�i��W�Q���Ă�����T�i�l���A�������R�قƂ��Ď咣���邱�ƂȂǓ��ꋖ�������̂ł͂Ȃ��Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�V�@���������āA�@��P�P���P���̓K�p�ɂ��A�T�i�l��́A��T�i�l�ɑ��A���ؖ������@��P�W�S���A��P�W�T���A��P�W�W���A��P�X�S���Ɋ�Â��A�{���ې�ɂ��{���e��Q�ɂ����Q������������L����B
�@�܂��A�ې�ɂ�鑹�Q�́A�����g�̓��ւ̒��ړI�ȐN�Q�ɂƂǂ܂炸�A���݂Ɏ���܂ōۂ̋��|�͎��܂炸�A�܂��A�����ې�̎����𑬂₩�ɔF�߂ēK�ȗ��@���ɂ���^�ҋ~�ς��s�����Ƃ�ӂ��Ă������Ƃɂ��A���݂܂Ōp�����āA���Ȑ��_�I��ɁA�l�i���ւ̐N�Q���Ă����̂ł���A���̐l�i���ւ̐N�Q�̏d�含�́A���_���ւ̐N�Q�̏ꍇ�Ɣ䌨������B
�@�����āA�ȏ�̐N�Q�ɂ��ẮA���Q�����݂̂Ȃ炸�A���̐^���ȎӍ߂������Ă����A���߂Ĉ��S�������̂ł��邱�Ƃ́A�����ł���B
�@�]���āA�T�i�l��́A���Q�����݂̂Ȃ炸�A�����̎�|�L�ڂ̂Ƃ���̎Ӎ߂𐿋�����i���ؖ������@��P�X�T���j�B

��T�́@���@�s��ׂɂ��Ӎߋy�ё��Q��������
�@�T�i�l��́A��ʓI�ɁA�O�L��Q�͂����S�͂���уn�[�O�������R���Ȃ�тɍ��ۊ��K�@�Ɋ�Â����������i���̓_�Ɋւ��ẮA����A��Q�������ʂɂ����Ď咣����j���咣���A����炪�F�߂��Ȃ��ꍇ�A�\���I�ɑ�T�͂����V�͋L�ڂ̊e�����������咣����B
��P�@���̏���
�P�@��T�i�l�̍��ƐӔC�͖����������Ă���
�@�{�͂ōT�i�l�́A��T�i�l�̍ې��Q�̋~�ςɊւ��闧�@�s��ׂ��T�i�l�ɑ���V���ȕs�@�s�ׂƂȂ邱�Ƃ��咣����B���̗��@�s��ט_�̒��S�I�_�_�́A��T�i�l�i����j�ɍې��Q�~�ς̗��@�`�����F�߂��邩�ۂ��ł���B
�@���̗��@�`���̐��ۂf����ɂ������ẮA�{���ې킪�����ȍ��ۖ@�ᔽ�i�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�ᔽ�j�s�ׂł���A���ۖ@�i�n�[�O����R���B�����R������e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@���܂ށB�ȉ������j�ɂ���Ē�߂�ꂽ���Q�����ӔC����T�i�l�ɐ����Ă������Ƃ������̊j�S�ɂ�������ׂ��ł���B
�{���ې��Q�ɑ���n�[�O���R���Ɋ�Â���T�i�l�̍��ƐӔC�i���Q�����ӔC�j�́A�@�I�ɂ͂��łɖ{���ې킪�s��ꂽ�P�X�S�O�N�T���P�X�S�Q�N�̎��_�Ŕ������Ă����B��T�i�l�̍��ƐӔC�́A����ȗ����݂܂Ŏ��ɂU�O�N�ȏ�ɂ킽���ĕs���s��Ԃ������Ă���̂ł���B
�@���̂悤�Ȕ�T�i�l�̍��ƐӔC�s���s�Ƃ����ُ�ȏ�Ԃ̂䂦�ɁA�T�i�l��́A���ݐS�g�Ƃ��ɖ������Ƃ̂ł��Ȃ��[���ȋ�ɂ������Ă���B
�Q�@�u�{�����ꂽ��Ɂv�ɑ���@�I�ӔC
�@�T�i�l�炪��������Ă���ꂵ�݂́A�������ɂ����Ă͖{���ې�Ƃ������Q�s�ׂɋN��������̂ł���B�������A�T�i�l��̌��݂̋�ɂ́A����ɉ����āA��T�i�l���n�[�O���R���Ɋ�Â����Q�����`�����ۂ����Ă���ɂ��S��炸�A������s�����ې�̎�����F�߂��A�Ӎ߂����������Ȃ��ŁA���������I�ȏ�ɂ킽���čې��Q�������T�i�l���S���~�ς������u���Ă������Ƃɂ���Đ������u�{�����ꂽ��Ɂv�ł���B
�@�{�̗͂��@�s��ט_�y�ю��͂̍s���s��ט_�́A�T�i�l�炪���ݎĂ���u�{�����ꂽ��Ɂv�̖@�I�ӔC��₤���̂ł���B
�@���̓_�A�������́A�{���ې�Ɋւ����T�i�l�̍��ƐӔC��F�肵�Ȃ���A���̍��ƐӔC�͂P�X�V�Q�N�̓������������Œ��������������̂Łu�����������v�Ƃ����B
�@�������A�ȉ��ŏڍׂɏq�ׂ�悤�ɁA��T�i�l�̍��ƐӔC���������������ɂ���āu���������v�Ƃ����������̉��߂͌���Ă���B����������������R�O�N���o�߂������݂ɂ����Ă��A��T�i�l�̍��ۖ@�i�n�[�O����R���j�Ɋ�Â����ƐӔC�͑������Ă���B
�R �u�{�����ꂽ��Ɂv���������������͌����ď����Ȃ�
�@�Ȃ��A�����Ŋ����ĕt�����邪�A��T�i�l�́A�����l��������{���ې��Q�ւ̑��Q�����`���Ƃ�������̍��ƐӔC�ɂ��āA�{���ő�����ӂ�s�����Ă��q���ɑΉ�����ׂ��ł���ɂ�������炸�A���̎p�������S�Ɍ��������Ă����B���̂悤�Ȕ�T�i�l�̑Ή��i�s��ׁj�́A���Ɍ������́u�����_�v�̗���ɗ��Ƃ��Ă��A�T�i�l��̐l�i��[����������̂ł���A�r���⊶�ł���B
�@���Ȃ킿���Ɍ������̉��߂ɏ]�����Ƃ��Ă��A�ې�̎��s���ꂽ�P�X�S�O�N�T���P�X�S�Q�N������������������o���ꂽ�P�X�V�Q�N�܂ł̂R�O�N�ԁA��T�i�l�����ƐӔC�s���s�𑱂��Ă������Ƃ́A���{�̓��t�ɂƂ��Ă�����ɂƂ��Ă��[���ȉ��_�ł���A����ɉۂ���ꂽ�@�I�ȍ�`���ɔw���Ă������̂ƌ��킴��Ȃ��B
�@���̂R�O�N�ԂƂ��������ԁA�T�i�l��͍ې��Q�̋~�ς�S����ꂸ���u����Ă����B���̔�T�i�l�̕s��ׂɂ���čT�i�l�炪���Ԃ��̂��Ȃ��قǐ[���ȋ�ɂ��������Ƃ͂܂�����Ȃ������ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���A���Ɍ���������������P�X�V�Q�N�̓������������̎��_�Ō��������Ƃ����u�����_�v�̗���ɗ������Ƃ��Ă��A�T�i�l���{���ې��Q����R�O�N�Ԃ��i�u�a�Ɨ�����ł��Q�O�N�Ԃł���I�j�A��T�i�l���ې��Q�҂̔�Q�ɂ��đ��Q�������ׂ��`������u���A���̌��ʁA�T�i�l��̍ې�ɂ���ď�����ꂽ�l�i�̑������A�{���~�ςɂ���đ��₩�ɉ���ׂ��ł���ɂ�������炸�A�t�ɍ��ꂩ�珝���čT�i�l��Ɂu�{�����ꂽ��Ɂv���������A�l�i�̑���������ɐ[�������������͌����ď����Ȃ��̂ł���B
�@�T�i�l��́A��ɏڏq����悤�ɁA�P�X�V�Q�N�̓������������ȍ~���A��T�i�l�̃n�[�O���R���Ɋ�Â����Q�����`���͌��݂܂ő������Ă���Ǝ咣������̂ł��邪�A���Ȃ��Ƃ��������������Ŕ�T�i�l�̍��ƐӔC���k�y�I�ɏ��ł��邱�Ƃ͂Ȃ����A�܂����Ɍ������̗���ɗ����Ă���Q�Җ{�l�ł���T�i�l�ɑ��鍑�ƐӔC�͌����āu�������ꂽ�v�킯�ł͂Ȃ��̂ł���B�ȏ�A�t���Ƃ���B
�S�@�܂��������́A���@�s��ׂɂ�鑹�Q�����͂����Ȃ�ꍇ�ɔF�߂���
���Ƃ����_�ɂ��āA�ō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P����ꏬ�@�씻���i���W�R�X���V���P�T�Q�P�y�[�W�j�������������ŁA�u����̗��@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������̂́A���@���`�I�ɍ���ɓ�����e�̗��@������`�����ۂ���Ă���ɂ�������炸�A������̗��@���ӂ����Ƃ����悤�ȗ�O�I�ȏꍇ�Ɍ�����v�Ƃ����B
�������A���������{���ې�́A�c���Ŕ�l���I�Ȑ푈��i�ł���䂦�ɁA���Q�s�ׂ̈�@���̋����A�T�i�l�炪�ւ�����Q�̐r�傳�ɂ����đ��ɗޗ�����Ȃ����Ăł���B�������A�O�q�����Ƃ����T�i�l�̍��ƐӔC�̕s���s�������A�T�i�l���Q�Ҍl�ɑ��ĐV���ȋꂵ�݂�^���Ă���B
�@����ɁA�����̍ې��Q�҂ւ̋~�ϑ[�u�����u����Ă��邱�Ƃ��A���{�ƒ����̍��ƊW�̗F�D�I�Ȕ��W�����j�Q���A���{�����ƒ��������̗F�D�W�����ꂩ���@�ɂ��炵�����Ă���Ƃ����u�F�D���͂ސV���ȉΎ�v�ƂȂ��Ă���B
�@���������Č��_���猾���A��T�i�l�̍ې��Q�̋~�ςɊւ��闧�@�s��ׂ́A��L�ō��ٔ���̔��f��ɏƂ炵�Ă��A�܂��ɍō��ٔ���̂����u��O�I�ȏꍇ�v�ɊY��������̂Ɣ��f���ׂ��ł���B
�@�����ŁA�ȉ��ł́A�܂���T�i�l�Ƀn�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC�������������Ƃ��c�_�̏o���_�ɂ�������ŁA�@�n�[�O���R���̍��ƐӔC�̐����_�A�A�������������̓K�p�͈͘_�A�B���@�`���̐����v���_�Ȃǂɂ��Č�������B
��Q�@�n�[�O����R���Ɋ�Â���T�i�l�̍��ƐӔC�̐����Ƃ��̐����_
�@�P�@��T�i�l�ɂ��{���ې�̎��s�Ɣ�Q�̔���
�@���łɍT�i�l�炪���R��P�W�������ʂŏڏq�����Ƃ���A�P�X�S�O�N����P�X�S�Q�N�ɂ����āA�V�R�P�����������s�����Ƃ�����{�R�́A�y�X�g�ۂ�R�����ۂȂǂ�p�����ې�ɂ��A�T�i�l�炪���Z���钆���e�n�ɂ����āA�y�X�g���̉u�a�����s�����A����Ɏ��Ӓn��ɂ����̉u�a��`�d�������B���̌��ʁA�T�i�l��y�т��̐e����́A�y�X�g���ɜ늳���A��������M��ɐs�����������d�ĂȏǏ�ɏP���A���S�Ȃ��������ԕa���ɕ������Ƃ�]�V�Ȃ�������ꂽ�B
�@����ɍT�i�l��́A�����Ԃɓn���Ċ����ǂ̋��|�̂��Ƃɐ������邱�Ƃ��������Ă����B
�@�ȏ�̖{���ې�̎����ɂ��ẮA���������S�ʓI�ɔF�肵�����̂ł���B
�@�Q�@��T�i�l�ɍې��Q�ɂ��������ׂ����ƐӔC������
�@�{���ې�́A�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�ŋ֎~����Ă����u�ۊw�I�푈��i�̎g�p�v�ɂ�����A�����ȍ��ې푈�@�K�ɑ���ᔽ�s�ׂł���B
�@�n�[�O����R���́A���ې푈�@�K�Ɉᔽ����s�ׂɂ���đ��Q��ւ����l���~�ς��邽�߂ɁA���Q�����̐ӔC���߂����̂ł���A�{���ې�ɂ���āA��T�i�l�ɂ́A�T�i�l���Q�҂ɑ��锅���ӔC�����������B
�@���̓_�́A���������A�u�퍐�ɂ͖{���ې�Ɋւ��w�[�O�������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă����v�i�������R�X�Łj�ƁA�{���ې킪���ۖ@�ᔽ�̍s�ׂł���A��T�i�l�ɂ͍ې�ɂ���Đ�������Q�ɑ��锅���ӔC�������������Ƃ�F�肵���B
�@�R�@�n�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC�̐����Ɣ����������̎�̂ɂ���
�@�n�[�O����R���́A����P�W�X�X�N����̋��n�[�O���y�т��̕����K�����C�����Đ��肳�ꂽ�ۂɁA�V���ɑn�݂��ꂽ�K��ł���B�P�X�O�V�N�̑�Q��n�[�O���a��c�ŁA�h�C�c��\���A��̒n����O�ɂ����Ď����R���̍\�������n�[�O���̕����K���ᔽ�s�ׂ��Ȃ����ꍇ�A���̍����L�ӂł��邱�Ƃ�F�߁A���̋K���ᔽ�s�ׂɂ�葹�Q�����l�ɑ��ē��Y��퍑�����������邱�Ƃ�v�����Ē�Ă��ꂽ����ɐ��肳�ꂽ�B
�@���̏��̍쐬�ߒ��ɏƂ炵�Ă����炩�Ȃ悤�ɁA�n�[�O����R���̖ړI��|�́A��@�Ȑ푈�s�ׂɂ���Čl�������Q���~�ς��邱�Ƃɂ������B
���̓_�͌��������A�u�w�[�O������y�уw�[�O����K���̎�|�E�ړI�́C�����y�ѓ��K���̋K��ɏƂ炷�ƁC����ɂ����ČR���̏��炷�ׂ��������߁C�����Đ푈�̎S�Q���y�����悤�Ƃ���_�ɂ�����̂Ɖ������B���Ƃ��C�푈�̎S�Q�͍ŏI�I�ɂ͌l�ɋA������̂ł��邩��C�����y�ѓ��K���̋��ɂ̎�|�E�ړI�́C����̉ߒ��ɂ������퓬�����܂߂��l�̕ی�ɂ���Ɖ����邱�Ƃ��ł���v�i�������U�Łj�ƔF�߂�Ƃ���ł���B
�@�Ƃ���ŁA�n�[�O����R���Ɋ�Â������ӔC�ɑ��āA���������������̂��A�l�ɂ���̂��A���Ƃɂ���̂��Ƃ�����肪���݂��Ă���B
�@�T�i�l�炪���R�Ŏ咣�����悤�ɁA�n�[�O����R���́A�R���\�������푈�@�K�Ɉᔽ����s�ׂ������ꍇ�ɁA���̔�Q�Ҍl���A���Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋����錠�����߂����̂ł���B
�@�������A�������́A�u���ۖ@�ɂ�����`���I�ȍl�����ɂ��A���ۖ@��̖@��̐���F�߂���̂͌����Ƃ��č��Ƃł���v�u�w�[�O�����l�ɐ�������F�߂閾���K���݂��Ă��Ȃ��v�i�������T�Łj�Ȃǂ̗��R�������A�u��Q�Ҍl�̉��Q�҂̑����鍑�Ƃɑ��鑹�Q������������F�߂����̂ł͂Ȃ��C��Q�҂̑����鍑�Ɖ��Q�҂̑����鍑�Ƃ̊Ԃ̌����`���W�ɂ��Ē�߂����̂Ɖ����ׂ��ł���v�i�������P�V�Łj�Ɣ������A�l�̐�������ے肵���B
�@�������Ȃ���A�T�i�l�炪���R�Ŏ咣�����悤�ɁA�n�[�O����R���Ɋ�Â������������͌l�ɂ���A��T�i�l���T�i�l���Q�҂ɑ��āA����̋~�ϑ[�u�����s���Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�{���ې�Ɋւ��Đ�������T�i�l�̔����ӔC�͉ʂ�����Ă��Ȃ��B
�@�܂��A���Ɍ���������������悤�ɁA�n�[�O����R���Ɋ�Â����������������Ƃɂ���Ƃ��Ă��A��T�i�l�̍��ƐӔC�͂��܂��ʂ�����Ă��Ȃ���B
��R�@�n�[�O����R���Ɋ�Â������������Ɠ������������ɂ�����u���������̕����v�ɂ���
�@�������́A�ې�̎����ƃn�[�O����R���Ɋ�Â���T�i�l�̍��ƐӔC��F�߂Ȃ���A�u�{���ې�Ɋւ��퍐�̍��ƐӔC�́A�䂪���ƒ����Ƃ̍��ƊԂł��̏��������肳���ׂ����̂ł���v�Ƃ��������ŁA�P�X�V�Q�N�̓������������ɂ����āA���ؐl�����a�����{���A�u���{�����{�ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾�v�i�������T���j���A�P�X�V�W�N�̓������a�F�D�����u�i�����j���������Ɏ����ꂽ�����������i�ɏ��炳���ׂ����Ƃ��m�F�v���Ă��邱�Ƃ������āA�u���ۖ@��͂���������Ĕ퍐�̍��ƐӔC�ɂ��Ă͌��������v�Ɣ��������B
�@�������A�u��T�i�l�̍��ƐӔC�͓������������Ō����ς݁v�Ƃ����������̉��߂͌��ł���A�{���ې�ɑ����T�i�l�̍��ƐӔC�͌������Ă��Ȃ��B
�@���̖����l�@����ɂ������ẮA�Q�̘_�_�����݂���B��P�́A�n�[�O����R���̐����A���Ȃ킿�A�n�[�O����R���̂��ړI�E��|�ƁA�������������l�ɂ���̂��A���Ƃɂ���̂��A�Ƃ������ł���A��Q�́A�������������ɂ�����u���������̕����v�̈Ӗ��A���Ȃ킿�A�����ŕ������ꂽ�����������̐��i�A�͈͓��̖��ł���B
�@�������́A��P�̘_�_�̃n�[�O����R���̉��߂ɂ����āA�������͍��Ƃ݂̂��L����Ƃ�������ɗ����A��Q�̘_�_�̓������������́u�����̐���������v�Ƃ��������̈Ӗ����e�ɂ��Ă͂ӂꂸ�ɁA�{���ې�Ɋւ����T�i�l�̍��ƐӔC�́A�u�������������ɂ���Č����������v�Ɖ��߂��Ă��܂��Ă���B
�@�����ňȉ��A��L���̏��݂�F�����������ŁA�l�ɐ�����������ꍇ�i��S�j�ƁA���Ɓi�����j�ɐ�����������ꍇ�i��T�j�ɕ����āA�_�q����B�����Č�ҁi��T�j�ɂ��ẮA����ɂ������̏ꍇ�ɕ����āA������̏ꍇ���A��T�i�l�̍��ƐӔC�͉ʂ�����Ă��炸�A���݂܂ő������Ă��邱�Ƃ��q�ׂ�B
�@
��S�@�n�[�O����R���Ɋ�Â��l�̑��Q�����������Ɠ�����������
�@�T�i�l�炪���R��������(8)�ŏڏq�����悤�ɁA�n�[�O����R���́A��Q�Ҍl���A���Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋����錠�����߂����̂ł���B�Ȃ��A���̓_�ɂ��ẮA���R��Q�������ʂł���ɏڏq����B
�@���Ƃ̔����������ƌl�̔����������́A�{���ʌ̂��̂ł���B���������āA�������������i��T���j�ŕ������ꂽ�̂́A�����̍��ƂƂ��Ă̔����������ł���A�l�̔����������͂���Ƃ͕ʂɑ������Ă���̂ł���B�@�@���̓������ł��钆�����{�́A�O�L��Q�͂̑�S�̂Q�ŏڏq�����悤�ɁA�J��Ԃ��A��Q�Ҍl�̔�������������������킯�ł͂Ȃ��|�q�ׂĂ���B�@���Ȃ킿�A�P�X�X�Q�N�S���A�]���Ǝ�Ȃ́A�����푈���̖��Ԕ�Q�ɂ��ẮA���݂ɋ��c���ď𗝂ɂ��Ȃ��`�őÓ��ɉ������ׂ��ł��邱�Ƃ��咣���Ă����|���������B����ɁA�P�X�X�T�N�R���X���A�K�O���́A�S���l����\�ґ��̐ȏ�ŁA�������������ɂ�����푈���������̕����ɂ́A�u�l�̔����܂ł͊܂܂�Ȃ��v�A�����̐����͌l�̌����ł���A�������{�͊����ׂ��łȂ��Ɩ��������B
�@���̂悤�ȏ�����i�����j�������ɕ\�����Ă�����߂͑��d�����ׂ��ł���B�Ȃ��A���̓_�ɂ��ẮA��L��T�ŏڏq����B
�@���ۂ̂Ƃ���A�{���ې�Ɋւ��āA��T�i�l����Q�~�ϑ[�u���ʂ����������͂Ȃ��B
�@���������āA�{���ې�Ɋւ��Đ�������T�i�l�̃n�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC�͌��݂܂ő������Ă���B
��T�@�n�[�O����R���Ɋ�Â������̑��Q�����������Ɠ�����������
�@���ɁA�n�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC�ɂ��Đ������̎�̂����ɂ���Ƃ��Ă��A�������������ɂ����āA�{����T�i�l�̍��ƐӔC�͉ʂ�����Ă��炸�A�����͂��Ă��Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��ẮA�������������ɂ���ĕ������ꂽ�����������͈̔͂����̈قȂ�R�̌����ɑ����Ȃ��猟������B
�@��P�́A���������̂͐��̔����������ł���A�n�[�O����R���Ɋ�Â������������͊܂܂�Ă��Ȃ��Ƃ��錩���ł���B
�@���̏ꍇ�́A�n�[�O����R���Ɋ�Â������������͒������{�Ɏc���Ă���B
�@��Q�́A�n�[�O����R���Ɋ�Â��������������܂߂Ē��������������Ƃ��錩���ł���B
�@���̏ꍇ�́A����������������̂͊O��ی쌠�����ł���A�{���̔�Q�Ҍl�̑��Q�����������͑�������B
�@��R�́A��������������T���́u�푈�����v�̒��ɁA�{���ې�Ɋւ��锅���������͊܂܂�Ă��Ȃ��Ƃ��錩���ł���B
�@���̏ꍇ�́A�{���ې�Ɋւ��锅���������͌��݂��������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ɁA��L�R�̂ǂ̌����ɗ����Ă��A��T�i�l�̍��ƐӔC�͌��݂܂ő������Ă���̂ł���B��L��P�A��Q�A��R�̌����ɂ��āA�ȉ��A�P�A�Q�A�R�ŏڏq����B
�@�P�@�������������Ńn�[�O����R���Ɋ�Â������������͕�������Ă��Ȃ��i�O�L��P�̌����ɗ��ꍇ�j
(1) ��������������T���́A�������{���A�u�������������̗F�D�̂��߂ɁA���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾����v�Ƃ��������ł���B
�@���̏����ɂ���āA�����͓��{�ɑ���u�푈�����̐���������v�������A�����ŕ������ꂽ�u�푈�����v�͈̔͂́A���B���̐푈�����ɂق��Ȃ�Ȃ��B���������āA�n�[�O����R���Ɋ�Â��푈���������̂悤�ȁA�푈�@�K�Ɉᔽ�����@�s�ׂɂ���Đ������l�̔�Q�Ɋւ��鑹�Q���������͊܂܂�Ă��Ȃ��B
�@�����Ő푈�ɔ����������̕ω��̗���ɂ��Ď�w�E���Ă����B
�@���Ƃ��Ɛ푈��ɁA�폟�����s�퍑�ɗv�����锅���́A�푈�ɂ���������p�i���j�̏��҂ł������B�n�[�O����R���i�P�X�O�V�N��Q��n�[�O���a��c�j����������A���̌�A��ꎟ���E���ɂ����āA���Ԑl�̔�Q����K�͂ɂȂ������Ƃ���A�]���̐푈�����ɉ����āA�V���Ɂu���Q�����v�Ƃ����l���������������悤�ɂȂ����B
�@���ہA�n�[�O����R��������������̃��F���T�C�����a���i�P�X�P�X�N�j�ł́A�폟���̐������̂ق��ɁA�폟�����̐������A�s�퍑�i�h�C�c�j�̐������i���S�R�X���j�A����ɔs�퍑���́u���Y�A�����܂��͗��v�v�Ɋւ�������������ŋK�肳��Ă���i���Q�X�W��t������j�B
�@�Ⴆ�A����t������́A�u�ƈ퍑���͓ƈ퍑���́i�����j��������͘A��������Ƃ��Ė��͑��̍s������͎i�@�����ׂ̈ɖ��͂��̖��߂̉��ɍs��������҂���Ƃ��Đ������͑i�ׂ��N���邱�Ƃ��v�ƋK�肵�Ă���B����́A�A�����Ȃǂɂ���čs��ꂽ��ׂ܂��͕s��ׂɂ���ăh�C�c�����Ɍ����������������݂������ƁA���̌������͖{���i�ד��ɂ���Đ����ł��邱�Ƃ��ł������Ƃ�O��Ƃ��āA��L���ɂ���đi�ׂ̒�N���ł��Ȃ��������̂ł���B
���̎����́A�n�[�O����R�����A�푈�̏��s�ɊW�Ȃ����y�э����̌�����n�݂������ƁA���̂��߂ɕ��a���ɂ���Ă���琿���������ł�����|�̋�̓I�K�肪�K�v�ɂȂ������Ƃ��Ӗ�����B
�@
(2) ���̂悤�ȍ����̌��������K�肵�����a���́A����E���ɂ�����C�^���A�ƘA�����̕��a���ɂ�������B�����V�U���ł́A�P���Łu�C�^���A���͘A�����ɑ��邢���Ȃ��ނ̐����������C�^���A�����{���̓C�^���A�����̂��߂Ɉ�ؕ�������v�Ƃ��Đ������������K�肵�������ŁA�Q���Łu���̏��̋K��́A�����ɏグ���Ă����ނ̈�̐����������S���ŏI�I�ɑł���B���̐������͗��Q�W�҂����l�ł��邩���킸���ケ������ł�����v�ƋK�肷��B�����ł��A�����̐����������݂��邱�Ƃ�O��ɁA����������Ɍ������ď��ł�����K��ɂȂ��Ă���̂ł���B
(3) �ȏ�̂悤�ɁA�P�X�O�V�N�̃n�[�O����R��n�݈ȍ~�́A�����l�̐��������F�߂���悤�ɂȂ�A���̌����͍ٔ���ōs�g�\�ƍl�����Ă����̂ł���A��������ł����邽�߂ɂ́A���ɂ��̎|���L����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�A����ɁA�P�X�S�X�N�W���l�[�u���ȍ~�́A�u�d��Ȉᔽ�s�ׁv�ɂ��A���Q���̐ӔC��Ƃꂳ���Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ����̂ł���B
�@���������āA�������������ł́A�n�[�O����R���Ɋ�Â����������l�̐������͕�������Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�Ȃ��A�T���t�����V�X�R���a���i�P�X�T�P�N�X���W�������j�ł��A��͂荑�̐������ƍ����̐����������L����Ă��邪�A�����a���ɂ��Ă͎��̂Q�ŏڏq����B
�@�Q�@�������������ŕ������ꂽ�̂͊O��ی쌠�ł���l�̐������͕�������Ȃ��i�O�L��Q�̌����ɗ��ꍇ�j
�@�@(1)�@���ɁA�������������ł����u�����̐����̕����v���A�n�[�O����
�R���Ɋ�Â����Q�������������܂ނ��̂��Ƃ��Ă��A�����ŕ������ꂽ�̂́A�����̍��ƂƂ��Ă̊O��ی쌠�ł���A�l�̐������͍��Ƃɂ���Ă͕�������Ȃ��B
�@�������́A�n�[�O����R���̌����̋A����̂ɂ��āA�u�l�������̍��ۈ�@�s�ׂɂ���đ��Q�����ꍇ�ɂ́A���Y�l�͉��Q���̍��ېӔC��Njy���邽�߂̍��ې������o�������̂Ƃ��Ă͔F�߂�ꂸ�A���̌l�̑�����{�����A���Y�l�̎��������グ�O��ی쌠���s�g���邱�Ƃɂ���āA����ɑ���@�I�ȐN�Q�Ƃ��Ĉ����A���ƊԊW�ɐ�ւ��đ��荑�i���Q���j�ɍ��ƐӔC��Njy������̂Ɖ�����Ă���v�Ɣ������Ă���B
�@���̉��߂ɗ��Ƃ��Ă��A�n�[�O����R���̖{���̖ړI���A��Q�Ҍl�ɑ��锅���ɂ���A���Ƃ͊O��ی쌠���s�g���Ă�����������悤�Ƃ���̂ł��邩��A���Ƃ������ł���̂́A�O��ی쌠�ł����āA���Q���ɑ����Q�Ҍl�̑��Q�����������܂ŕ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
�@�{���ې�ɂ����ẮA�T�i�l���Q�҂ɑ����T�i�l�̔����`�����܂��������s����Ȃ������ɁA���������ƂƂ��ĊO��ی쌠������������ƂɂȂ�B
�@�������A�������O��ی쌠��������Ă��A��Q�҂̋~�ςƂ������͎c��̂ł���A��Q�Ҍl�̔�������������������̂ł͂Ȃ��B�n�[�O���R���̏�L�����_����A���Ƃ��O��ی쌠����������ꍇ�ɂ́A�l�����Q�����������̎�̂ƂȂ�Ɖ�����̂����R�ł���B
�@�@(2)�@�l�̐������͕�������Ă��Ȃ��Ƃ����������{�̌����ɂ���
�@�P�X�X�Q�N�S���A�]���Ǝ�Ȃ́A�����푈���̖��Ԕ�Q�ɂ��ẮA���݂ɋ��c���ď𗝂ɂ��Ȃ��`�őÓ��ɉ������ׂ��ł��邱�Ƃ��咣���Ă����|���������B����ɁA�P�X�X�T�N�R���X���A�K���O���́A�S���l����\�ґ��̐ȏ�ŁA�������������ɂ�����푈���������̕����ɂ́A�u�l�̔����܂ł͊܂܂�Ȃ��v�A���������͌l�̌����ł���A�������{�͊����ׂ��łȂ��Ɩ��������B
�@������A�̔����ɂ���āA�������{���l������������̑ΏۂƂ��Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B����ɂ�蒆�����{���������������ŕ��������̂͊O��ی쌠�ł���Ɨ������邱�Ƃ��ł���B
�@�������{�́A���ۂɋ~�ς���Ă��Ȃ���Q�Ҍl���u�c���ꂽ���v�i�������̕\���́u�◯���v�j�Ƃ��đ��݂��Ă��邱�ƁA��T�i�l�̍��ƐӔC���������Ă��邱�ƁA��Q�Ҍl����T�i�l�ɑ��đ��Q�����𐿋��ł��邱�Ƃ��A�����ɔF�߂Ă���̂ł���B
�@�@(3) �T���t�����V�X�R���a���ɂ�����O��ی쌠�̕���
�@�n�[�O����R���Ɋ�Â��i���������Đ푈�@�K�Ɉᔽ����s�ׂɂ���Čl����Q�����ꍇ�́j�����ӔC�ɑ��āA���������ł���̂͊O��ی쌠�ł��邱�Ƃ̗�Ƃ��āA�T���t�����V�X�R���a���̔�����������������B
�@������P�S�������͎��̂悤�ȏł���B
�u���̏��ɕʒi�̒肪����ꍇ�������A�A�����́A�A�����̂��ׂĂ̔����������A�푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�����A�����y�т��̍����̑��̐��������тɐ�̂̒��ڌR����Ɋւ���A�����̐��������������v
�@��L�����́A�����������ɂR�̎�ނ����邱�Ƃ������Ă���B���Ȃ킿�A�@�A�����̂��ׂĂ̔����������@�A�푈�̐��s���ɓ��{���y�т��̍������Ƃ����s�����琶�����A�����y�т��̍����̑��̐������@�B��̂̒��ڌR����Ɋւ���A�����̐������A�ł���B
�@���Ȃ킿���Ȃǂ̏��҂Ƃ��č��Ƃ����ڎ�锅���i�@�j�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ��āA�u�A�����y�т��̍����̑��̐������v�i�A�j���K�肵�Ă���̂ł���B���̇A�̋K��́A�n�[�O����R���Ɋ�Â��悤�ȁA���Q���̈�@�s�ׂɂ���Čl�̎����Q�ɑ��锅����������z�肵�Ă���Ƃ�����B
�@���̂����ŁA�����ł́A�ꊇ���ĕ�������K��ɂȂ��Ă���B
�@�ꊇ���ĕ�������Ă���Ƃ͂����A�����Łu�����̐������v���K�肳�ꂽ���Ƃ̈Ӗ��͑傫���B�܂�A���Ƃ��ƍ����̂��̂��L���Ă��鐿�����i�@�j�Ƃ͕ʂɁA�n�[�O����R���Ɋ�Â��悤�Ȑ푈�@�K�ɑ���ᔽ�s�ׂɂ���Čl�����Q�����ꍇ�́A�l�̐����������݂��Ă���A���͊O��ی쌠���s�g���ĉ��Q���ɑ��Ĕ����𐿋����錠�������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B
�@����ɁA�O�L���F���T�C�����y�уC�^���A�ƘA�����Ƃ̕��a���ł́A�����̑��Q�����������ɂ��Ă������ɂ킽���ď��ł��邱�Ƃ����L���ꂽ���A�T���t�����V�X�R���a���ł́A���̓_�͖��L����Ȃ������B
�@���������āA�T���t�����V�X�R���a��u�����̐������v�L���������ŁA���������������Ƃ����̂́A�O��ی쌠���������Ƃ����Ӗ��������̂ŁA�����̌������̂����ł�������̂ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�@(4)�@�T���t�����V�X�R���a���������Ɍl�̐���������������Ȃ����Ƃ�F�߂����{���{
�@�O��ی쌠�̕����ɂ���Ă��A��Q�Ҍl�̐������͕�������Ă��Ȃ����ƁA���Q���̑��̍��ƐӔC���ʂ�����Ă��Ȃ����Ƃ���������Ƃ��āA�T���t�����V�X�R���a���ɂ�����I�����_�̗Ⴊ����B
�I�����_�̓T���t�����V�X�R���a���ɒ������A���̍ہA���{���ɑ��A�I�����_���@�͐��{�Ɏ����v���̌�����^���Ă��Ȃ��̂ŁA���������������͍����̎��������ł�������̂ł͂Ȃ��A�����͓��{�̍ٔ����œ��{���{�܂��͓��{������i�ǂł���Ƃ������߂������A�܂��A���̌��ʂ����{�̊O��ی쌠�̕����Ɍ����邱�Ƃ����炩�ɂ��������œ����ɒ����B
�@�I�����_�̊O���́A�u�c���{�����{���A�ǐS�Ȃ����ǎ�����X��i�̖��Ƃ��āA�����I�Ɏ���̕��@�ŏ��u���邱�Ƃ�]�ނ��̂Ǝv����A���������̂����̎��I������������܂��v�Əq�ׁA�T���t�����V�X�R���a���ɂ���Ă���������Ȃ������̌l���������u�����I�Ɂv�������鎖�����߂��B����ɑ��A�g�c�́A�P�X�T�P�N�X���W���t�I�����_�O�������ȂŁA�u�I�����_�����{����������@���A���{�����{�������I�ɏ��u���鎖����]����ł��낤�A���������̂����̎��I�����������݂��邱�Ƃ������Ɏw�E���܂��v�Əq�ׁA�T���t�����V�X�R���a���̔����������������ɂ���Ă��A�l�̐������͎c�邱�Ƃ�F�߂��̂ł���B
�@���̌�A���{�̓I�����_�ƂP�X�T�U�N�Ɂu�I�����_�����̂����̎��I�������Ɋւ�����̉����Ɋւ�����{�����{�ƃI�����_���{�Ƃ̊Ԃ̋c�菑�v�����сA�u����E���̊Ԃɓ��{�����{�̋@�ւ��I�����_�����ɗ^������ɂɑ��铯��ƈ⊶�̈ӂ�\���邽�߁v�A���ԗ}���҂̐������̏����Ƃ��āA�P�O�O�O���h��������B
�@�ȏ�̌o�߂��疾�炩�Ȃ悤�ɁA���{���{�́A�l�̔�Q�ɑ��锅���̖��̓T���t�����V�X�R���a���ɂ���Ă��ŏI�I�ɉ��������킯�ł͂Ȃ��A�u�����̎��I�������v���c�邱�Ƃ�F�߂Ă����̂ł���i�r��M��w���{�̉��Q�s�ה�Q�҂̌l�����������ɂ��Ă̗��j�I�l�@�x�����Љ�Ȋw�@���{�������w�ߑ���{�̓��O����1931�`1945�x��o�����Q�Ɓj�B
(5)�@��T�i�l�̓��؏��Ɋւ���u���������̂͊O��ی쌠�v�Ƃ̖���
�@�����������̍��̈�@�s�ׂɂ�葹�Q�������ꍇ�A�{�����Ƃ������ł���̂͊O��ی쌠�̍s�g�����ł����āA��Q�Ҍl�̈�g�ɐꑮ���錠�������ł�����킯�ł͂Ȃ����Ƃ́A�Ⴆ�Γ��ؐ���������Ƃ̊֘A�ł��A�ȉ��̓��قɌ�����悤�ɁA���{���{�ł����F�߂Ă���Ƃ���ł���B
�u�i����r��O���ȏ��ǒ��j��������ؐ���������ɂ����܂��ė����Ԃ̐������̖��͍ŏI�����S�ɉ��������킯�ł������܂��B���̈Ӗ�����Ƃ���ł������܂����A�i�����j����͓��ؗ��������ƂƂ��Ď����Ă���܂��O��ی쌠�𑊌݂ɕ��������Ƃ������Ƃł������܂��v�i�P�X�X�P�N�W���Q�V���Q�c�@�\�Z�ψ����c�^��R���P�O�Łj�B
�@�R�@�{���ې�͓����������������������u�푈�����̐����v���珜�O����Ă���i�O�L��R�̌����ɗ��ꍇ�j
�@�������������ɂ����ẮA�ȉ��ɏڏq���闝�R����A�{���ې��Q�̖��͕����̑ΏۂɊ܂܂�Ă��Ȃ������B
�@�@(1)�@�ې�͍��ۖ@�Ɉᔽ����c�s�s�ׂł���u���������̕����v�ɓ���Ȃ�
�@�{���ې�́A�����ȍ��ۖ@�ᔽ�ł��邤���A��T�i�l���Ӑ}�I�Ɍv�悵�g�D�I�Ɏ��s���ꂽ�푈�ƍ߂ł���B����ɁA�ې�̎��s�́A�ŏ������퓬�������ʏZ�����ʑ�ʂɎE�C���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���A�����Ȃ�Ӗ��ł����������ꂦ�Ȃ��s�ׂł���B
�@�{���ې�̂悤�Ȉ�@�s�ׂɂ���čT�i�l�璆���̈�ʏZ������������Q�ɂ��ẮA�������㏈���Ƃ��āA���ƊԂŎ�茈�߂���ʏ�́u�푈�����v�̏����̒��ɂ͊܂܂�Ȃ��B�������������ɂ����Ē������{�����������u�푈�����v�́A�ʏ�̈Ӗ��ł̐푈�����Ɍ�����̂ł���A�{���ې�̂悤�ȍ��ۖ@�ᔽ�̎c�s�ȍs�ׂɂ��ẮA�Ԉ��w���Ɠ������A�܂܂�Ȃ��Ɖ�����ׂ��ł���B
(2) �Ƃ���ŁA�P�X�S�X�N�W���P�Q�����������W���l�[�u�����Ƃ��ɁA�u�펞�ɂ����镶���̕ی�Ɋւ���P�X�S�X�N�W���P�Q���̃W���l�[�u���i��S���j�v�i�P�X�T�R�N���{�������B�ȉ��A�u��S�W���l�[�u���v�Ƃ����j�́A��L�����̌����A�������̍��ɂ������A���łɏd��ȉe����^����K���n�݂����B
�@���Ȃ킿�A��S�W���l�[�u���ł́A��P�S�V���ŁA�u���̏�ی삷��l���͕��ɑ��čs���鎟�̍s�ׁA���Ȃ킿�A�E�l�A����Ⴕ���͔�l���I�ҋ��i�����w�I�������܂ށj�A�g�̎Ⴕ���͌��N�ɑ��Č̈ӂɏd����ɂ�^���A�Ⴕ���͏d��ȏ��Q�������邱�Ɓc�c�c�������B�v�Əd��Ȉᔽ�s�ׂ��K�肵�A��P�S�W���ŁA�u�������́A�O���Ɍf����ᔽ�s�ׂɊւ��A�����������ׂ��ӔC��Ƃ���A���͑��̒����������Ă��̍��������ׂ��ӔC����Ƃ��ꂳ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�A�����w�I�������܂ޔ�l���I�ҋ����̏d��Ȉᔽ�s�ׂɑ��āA���������̖Ɛӂ��֎~�����B
�@����ȍ~�A�u�a���̂�������傫���ύX���ꂽ�Ƃ�����B
�@���̑�S�W���l�[�u���ň�w���m�����ꂽ�l��������e�F����l�������A�O�L�T���t�����V�X�R���a���ɋ����e����^�����f����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�������������́A��L��S�W���l�[�u���̒����ȍ~�ł��邩��A�{���ې�̂悤�ȁu�d��Ȉᔽ�s�ׁv�ɂ��ẮA������������ł��Ȃ��̂ł���B
�@�@(3)�@�������������̌��ߒ��ōې�̎����͉B������Ă���
�@���Ƃ��ƊO��ی쌠���������邽�߂ɂ́A�����̍��������̍��̈�@�s�ׂɂ���đ��Q���A��Q�҂��������{�ɑi���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�������A�����������������A�{���ې�ɂ��ẮA��T�i�l�̓O�ꂵ���B���s�ׂɂ���āA�T�i�l��͎�����̖ւ�����Q�����{�R�̍ې�ɂ����̂ł��邱�Ƃɂ��Đ^����m�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���������čT�i�l��́A�����i�����j���{�Ɏ���̍ې��Q��i���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�{���ې�Ɋւ��鑹�Q���������́A���������������_�ł͊O�����̑O�鎖���Ƃ��ĔF������Ă��Ȃ��������Ƃ���A�������ꂽ�u�푈�����v��������O����Ă����B�Ȃ��A�������̂����u�◯���v�̒��ɍې��Q���܂߂��Ă���B
�@�@(4)�@�������������́u�ӔC��Ɋ������Ȃ���v�ɔ������T�i�l�̍s��
�@�������������́A���̑O���œ��{�����u�ߋ��ɂ����ē��{�����푈��ʂ��Ē��������ɏd��ȑ��Q��^�������Ƃɂ��Ă̐ӔC��Ɋ����A�[�����Ȃ���v���Ƃ�O��Ƃ��āA��T���Œ��������u�푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾�v�������̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�{���ې�Ɋւ����T�i�l�̑Ή��́A�������������ɂ�����u�ӔC��Ɋ����[�����Ȃ���v�Ƃ����O���ɒ�������������̂ł���B�ې�̎�������F�߂��A�Ӑ}�I�ȉB���s�ׂ��J��Ԃ��Ă�����T�i�l�̑ԓx�́A�u�ӔC��Ɋ����[�����Ȃ���v���ƂƖ���������̂ł���B�܂���{�����Ƃ��Ă������ۂ̑ԓx�́A����̐ӔC��ے肵�A�܂��������Ȃ����A�T�i�l���Q�҂��͂��߁A�����̐l�X��[����������̂ł���B���̔�T�i�l�̖{���ې�ɑ���ԓx�́A�����W�̐i�W��j�Q����傫�ȗv���ƂȂ��Ă���B
�@�������������ɂ����钆�����{�́u���������̕����v�́A���{�����u�ӔC��Ɋ����[�����ȁv���邱�Ƃ�O��Ƃ��Đ錾���ꂽ�̂ł��邩��A�{���ې�Ɋւ����T�i�l�̑ԓx�́A�������������̑O�������s�ׂł���A���Ȃ��Ƃ��{���ې�Ɋւ��ẮA�u���������̕����v�͐��������A���O�����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�S�@�ȏ�A�n�[�O����R���Ɋ�Â����Q�����������͍��Ƃɂ���Ƃ����������̗���ɗ����āA�R�̌��������Ă������A������̏ꍇ���A��T�i�l�̍��ƐӔC�͑������Ă���A�����������́A�l�̏ꍇ�ɂ���A���Ƃ̏ꍇ�ɂ���A������ɂ��摶�����Ă���B�������́A�{���ې�Ɋւ����T�i�l�̍��ƐӔC���A�u�������������ɂ���Č����v�����Ƃ������߂͐��藧���Ȃ��̂ł���B
��U�@��T�i�l�ɂ͔�Q�Ҍl�ɑ��ė��@��̋~�ϋ`������������
�@�P�@��T�i�l�̍��ƐӔC���������Ă���ȏ�A��Q�ҋ~�ς͗��@�`���Ƃ��ĉۂ�����
�@�ȏ�A��S�A��T�ŏq�ׂ��悤�ɁA�n�[�O����R���Ɋ�Â���T�i�l�̍��ƐӔC�ɑ��鐿�������A�T�i�l���Q�Ҍl�ɂ���ɂ���A���邢�́A����������������悤�ɁA���Ƃɂ���ɂ���A������ɂ����T�i�l�̍��ƐӔC�͑������Ă���A��T�i�l�̔����`���͕s���s�̂܂ܑ����Ă���B
�@����A��T�i�l�ɂ�鉽�炩�̎�i�ɂ��T�i�l���Q�҂̋~�ς͍s���Ă��Ȃ��B����ǂ��납�A��T�i�l�ɂ����Q�����̔F�肷��s���Ă��Ȃ��B
�@�T�i�l���Q�҂̋~�ϑ[�u���K�v�ł��邱�Ƃ́A���������u�{���ې�ɂ���Q�͐��ɔߎS���r��ł���A�����{�R�ɂ�铖�Y�퓬�s�ׂ͔�l���I�Ȃ��̂ł������Ƃ̕]����Ƃ�Ȃ��Ɖ������v�u�{���ې��Q�ɑ��䂪�������炩�̕⏞������������ƂȂ�A�䂪���̍����@�Ȃ����͍����I�[�u�ɂ���đΏ����邱�ƂɂȂ�ƍl������Ƃ���A���炩�̑Ώ������邩�ǂ����A���ɉ��炩�̑Ώ�������ꍇ�ɂǂ̂悤�ȓ��e�̑Ώ�������̂��́A����ɂ����āA�ȏ�ɐ��������悤�Ȏ���̗l�X�Ȏ����O��ɁA�����̍ٗʂɂ�茈���ׂ����i�̂��̂Ɖ������v�ƔF�߂�Ƃ���ł���B
�@���炩�̋~�ϑ[�u���Ƃ���K�v������A���̕��@������ɂ����Č�������ׂ����̂ł��邱�Ƃ́A�Ó��Ȕ��f�ł���B
�@�Ƃ��낪�A�������́A����u�����̍ٗʂɂ�茈���ׂ��v�Ƃ��A���@�`���܂ŕ������̂ł͂Ȃ��Ƃ������f�������Ă���B
�@�������A���̌������̔��f�́A��T�i�l�̃n�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC�����łɌ��������Ă���Ƃ����O��ł̂��Ƃł���A��T�i�l�̍��ƐӔC���������Ă����Ԃ̂��Ƃł́A�T�i�l���Q�҂̋~�ς́A���@�`���Ƃ��ĉۂ�����Ƃ�����B
�@�Q�@���ۖ@�̋`���ᔽ�̉����͍���̐Ӗ�
�{���ې�Ɋւ���n�[�O����R���Ɋ�Â��������́A�O�q�����Ƃ���A�@�n�[�O����R���̖ړI�͌l�̋~�ςɂ���B�A��T�i�l�̓n�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC���ʂ����Ă��炸�A�T�i�l���Q�҂̋~�ς͂��܂��Ɏ��s����Ă��Ȃ��B
�n�[�O���R���́A�����Ɋ�Â����Q���̍��ƐӔC�̗��s�̂��߂ɂ����Ȃ�葱�I�ȉ\�����r�����Ă��Ȃ��B���������āA���Q�����A�~�ϑ[�u���������邽�߂̐V���ȗ��@�ɂ���ċ~�ς��������邱�Ƃ͉\�ł���A�܂��K�ȕ��@�ł���B
�@����ɁA��T�i�l�̑��̍��ۋ`���̕s���s��Ԃ̌p��������A�����ɁA��Q�҂̑��̋~�ς���Ȃ���Ԃ̌p��������A�O���ɂ���Ă͂��̉������}��Ȃ��ꍇ�A�������������B��̕��@�́A��T�i�l�̍�����炩�̗��@�[�u�ɂ���āA��Q�Ҍl�ɑ��锅���ӔC���ʂ������Ƃł���B
�@�����āA���ꂪ�Ȃ���Ȃ��ȏ�A��T�i�l�ɂ����鍑�ۋ`���̕s���s�͉�������Ȃ��̂ł��邩��A����ɂ͗��@�`���������Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�R�@���������ŗL�̑��Q�����������̑��݂Ɣ�T�i�l�̔�Q�ҋ~�ς̗��@�`��
�@�������ɂ��Ζ{���ې�̔�Q�͐��ɔߎS���r��ł���A�����{�R�ɂ�铖�Y�퓬�s�ׂ͔�l�ԓI�Ȃ��̂������Ƃ̕]���͖Ƃꂸ�A�����{�ɂ̓n�[�O�������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�����������Ƃ����̂ł���B���������āA�������̌������f��ɏ]�����Ƃ��Ă��A��{�I�l���̑��d���|�Ƃ��A�����ۋ�����`�ɗ����{�����@�ɂ����ẮA���̂悤�ȏd��Ȑl���N�Q�ɂ�荑�ƐӔC���悤�ȏ�Ԃ���u���邱�Ƃ͓��ꋖ����Ȃ��̂ł��邩��A�{���ɂ����āA���@�s�ׂ̍��Ɣ����@��̈�@�����F�߂���ׂ���e�Ղɑz�肵��悤�ȗ�O�I�ȏꍇ��ł���ƕ]���ł��邱�Ƃ͖����ł���B
�@�������Ȃ���A�������́A�ې�͍��ۊ��K�@�Ɉᔽ���A��T�i�l�������ƐӔC���ƔF�߂Ȃ���A��T�i�l���̍��ƐӔC�́A�������������i�P�X�V�Q�N�j�y�ѓ������a�F�D���i�P�X�V�W�N�j�ɂ���Ċ��Ɍ������Ă���Ƃ̗�����O��ɁA���@�s��ׂ̈�@���ɂ��ď��ɓI�ɔ��f���Ă���B����́A�������������y�ѓ������a�F�D���ɂ���Ē����y�ђ��������̑��Q���������������ɕ�������Ă���Ɨ����������̂Ɖ������B
�@�������A���̌������̗����͌���Ă���B���Ȃ킿�A���łɑ�T�ŏq�ׂ��Ƃ���A�������{�����������̂́A���ƊԂ̔����ł���A���������ŗL�̑��Q�����������́A�������{�ɂ���ĕ������ꂽ���̂ł͂Ȃ��B���������āA��T�i�l�ɂ́A��Q�Ҍl�ɑ��ė��@��̋~�ϋ`������������B
�@�܂��A�������́A���{�ɂ̓n�[�O�������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�����������Ƃ����̂ł��邪�A�����������̂悤�ȍ��ƐӔC�́A�ې�Ƃ����A�ʏ�̐푈�ɂ����đz��ł��Ȃ��ُ�ȍs�ׂɊւ��鍑�ƐӔC�ł���B���������������ɂ����ĕ������ꂽ�̂́A�ʏ�̔����������ł���ƍl�����邩��A���̂悤�Ȉُ�ȍs�ׂɂ�鍑�ƐӔC�Ɋւ��钆�����Ƃ��L���锅���������ɂ��ẮA�������{�ɂ����Ă��A���������������ɂ���ĕ��������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
���������āA���Ɍ����������f����悤�ɁA�{����T�i�l�̍��ƐӔC���u���ƊԊW�ɂ����ď��������ׂ��v���̂��Ƃ��Ă��A��T�i�l�̍��ƐӔC�͉��痚�s����Ă��炸�A�����͂��Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�����āA�n�[�O�������R���̋K��̋��ɂ̎�|�E�ړI�́A�������̌����悤�Ɍl�̕ی�ɂ��邩��A���ɔ�T�i�l�ɂ�闧�@���A���ƊԊW��ʂ��������̌`���Ƃ�Ƃ��Ă��A���̖ړI�͔�Q�Ҍl�̋~�ςł���A���̒������Ƃ��L���锅�������������s����ׂ̓K�ȗ��@���Ȃ���Ȃ����Ƃɂ��A�T�i�l���Q�҂��V���ȋ�ɂ��邱�Ƃ��܂����炩�ł���B
�@�S�@�ō��ٔ���i���a�U�O�N�P�P���Q�P���j�̊�ɂ���
�@�@(1) �������̔������锻�f�
�@�������́A���@�s��ׂɂ�鑹�Q�����͂����Ȃ�ꍇ�ɔF�߂��邩�Ƃ����_�ɂ��čō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P����ꏬ�@�씻���i���W�R�X���V���P�T�Q�P�y�[�W�j�������������ŁA�u����̗��@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������̂́A���@���`�I�ɍ���ɓ�����e�̗��@������`�����ۂ���Ă���ɂ�������炸�A������̗��@���ӂ����Ƃ����悤�ȗ�O�I�ȏꍇ�Ɍ�����v�Ƃ��Ă���B
�@�����Č������́A�u���{�����@���̗p����c������`�̉��ł̍���c���̗��@�ߒ��ɂ�����s���́A����c���e���̐������f�ɔC����A���̓��ۂ͍ŏI�I�ɍ����̎��R�Ȍ��_��I���ɂ�鐭���I�]���Ɉς˂���̂������ł��邩��A����c���́A���@�Ɋւ��ẮA�����Ƃ��āA�����S�̂ɑ���W�Ő����I�ӔC���ɂƂǂ܂�A�ʂ̍������̑��̎҂̌����ɑΉ������W�ł̖@�I�`�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���v�Ɣ������A���̊��{���ɂ��Ă͂߂ė��@�s��ׂ̈�@����ے肵���B
(2) �{���ې�̔�Q�́u�e�Ղɑz�肵��悤�ȗ�O�I�ȏꍇ�v�ɑ�������
�@�@�@�A�@�������������������p�����L�̍ō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P�������́A���Ƃ��Ɨ��@�ٗʂɂ䂾�˂��Ă���Ƃ���̍���c���̑I���̓��[���@�Ɋւ�����̂ł���A�ە���̎g�p�Ƃ������炩�Ɉ�@�ł����ɔ�ނ̂Ȃ��悤�ȋɂ߂ďd��Ȑ����g�̓��ւ̐N�Q�Ɋւ���{���Ƃ́A�S�����Ă��قɂ���B�܂��A���̌�̍ō��ٔ����̎��Ă��A��ʖ��Ԑl��Ў҂�ΏۂƂ���i�엧�@�����Ȃ����ƂɊւ�����́i���a�U�Q�N�U���Q�U����Q���@�씻���E�ٔ��W�����P�T�P���P�S�V�Łj�A�����̗A�������Ɋւ�����́i�����Q�N�Q���U����R���@�씻���E�ז�����R�U���P�Q���Q�Q�S�Q�Łj�A���@�V�R�R���̍č��֎~���ԂɊւ�����́i�����V�N�P�Q���T����R���@�씻���E�ٔ��W���W�P�V�V���Q�S�R�Łj���ł���A�{���ɕC�G����悤�Ȃ��̂͑S����������Ȃ��B
�@�@�@�C�@�����Ƃ��A��L��A�̍ō��ٔ����́A���@�s�ׂ����Ɣ����@��ጛ�ƕ]�������̂́A�e�Ղɑz�肵��悤�ȗ�O�I�ȏꍇ�Ɍ�����ׂ��ł���|�������Ă���B�����A�ō��ٔ������a�U�O�N�P�P���Q�P���������̏�L��A�̍ō��ٔ����̕��������������Ȃ悤�ɁA�u���@�̓��e�����@�̈�`�I�ȕ����Ɉᔽ���Ă���v���Ƃ́A���@�s�ׂ̍��Ɣ����@��̈�@����F�߂邽�߂̐�Ώ����Ƃ͉�����Ȃ��B��L��A�̍ō��ٔ������u���@�̓��e�����@�̈�`�I�ȕ����Ɉᔽ���Ă���v�Ƃ̕\����p�����̂��A���@�s�ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������̂��A�ɂ߂ē���ŗ�O�I�ȏꍇ�Ɍ�����ׂ��ł��邱�Ƃ��������悤�Ƃ����ɂ����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���(��L�ɂ��Ă̓n���Z���a�Ɋւ���F�{�n���ٔ��������P�R�N�T���P�P���������Q��)�B
�@�@�@�E�@�܂��A�ō��ٔ������a�U�O�N�P�P���Q�P�������́A�P���ɋc���
���`�𗝗R�Ƃ���݂̂Ȃ炸�A�I�����Ɋւ��闧�@�{�̍ٗʂ��������Ă��邱�Ƃ��番����悤�ɁA�u���@�̓��e�����@�̈�`�I�ȕ����Ɉᔽ���Ă���v�ꍇ����̗�Ƃ��āA��e�Ղɑz�肵��悤�ȗ�O�I�ȏꍇ��ɂ́A���@�s�ׂ̍��Ɣ����@��̈�@����F�߂��|�ł��邱�Ƃ́A���炩�ł���B
�@���̓_�A���������A�ō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P����������������ŁA�u���@���`�I�ɍ���ɓ�����e�̗��@������`�����ۂ���Ă���ɂ�������炸�A������̗��@���ӂ����Ƃ����悤�ȁv�u��O�I�ȏꍇ�v�ɂ́A����̗��@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������Ɣ������Ă���̂́A�u���@���`�I�ɍ���ɓ�����e�̗��@������`�����ۂ���Ă���ɂ�������炸�A������̗��@���ӂ����Ƃ����悤�ȁv�ꍇ����̗�Ƃ��āu��O�I�ȏꍇ�v�ɂ͗��@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������Ƃ��Ă���̂ł���A��L�ō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P�������̗����Ƃ��āA�T�i�l�̗����Ɠ��l�ł���Ɖ������B
�@�@(3) ��s�@�v�N�Q�Ɋ�Â��~�ϋ`��
�@�{���ې�̂悤�ɁA�����ȍ��ۖ@�ᔽ�s�ׂɂ���āA�T�i�l��ɂ����Č��@�����̍����Ɋւ��l���N�Q�����ɋN���Ă���A����ɍ��ۖ@�Ɋ�Â����ۋ`���̕s���s��Ԃ����ɑ����Ă���悤�ȏꍇ�́A����c���̐����I�ӔC�ɉ����ł��Ȃ��̈�ɂ����āA���@�s��ׂ𗝗R�Ƃ��鍑�Ɣ����̖�肪������B
�@�����āA�d��Ȑl���N�Q�Ƌ~�ς̍��x�̕K�v�����F�߂��A���̂����ŁA�������t�����̕K�v�����\���ɔF�����A���@�\�ł������ɂ�������炸�A���̍����I���Ԃ��o�߂��Ă��Ȃ��������u�������̏ꍇ�ɂ́A�L�����@�s��ׂɂ�鍑�Ɣ������F�߂���ׂ��ł���B
�@���̓_�A�@�̉��ߌ����Ƃ��āA���邢�͏𗝂Ƃ��āA��s�@�v�N�Q�Ɋ�Â����̌�̕ی�`�����E�@�v�N�Q�҂ɉۂ��ׂ����Ƃ���ʂɋ��e����Ă���ƍl����ׂ��ł���B���{�����@����O�̒鍑���{�̍��ƍs�ׂɂ����̂ł����Ă��A����Ɠ��ꐫ���鍑�Ƃł���퍐�ɂ́A���̖@�v�N�Q���^�ɏd��ł������A��Q�҂ɑ��A���ȏ�̔�Q�̑���������炳�Ȃ��悤�z���A�ۏ��ׂ��𗝏�̖@�I�`�����ۂ����Ă���Ƃ����ׂ��ł���A���ɁA�l�̑��d�A�l�i�̑����ɍ����I���l�������A���A�鍑���{�̌R����`���Ɋւ��Ĕے�I�F���Ɣ��Ȃ�L������{�����@�����́A�܂��܂����̋`�����d���Ȃ�A��Q�҂ɑ��鉽�炩�̑��Q�[�u���̂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł���B
�@���Ȃ킿�u��s�@�v�N�Q�v�����@�I�����̍����Ɋւ��N�Q�Ƃ��čs��ꂽ�ꍇ�A�u�ی�`���v����������B��Q�҂����̌���ی��̂Ȃ��ꂵ�݂Ɋׂ��Ă��邱�ƁA���Q�ґ��̋~�ύ�`�����ʂ����ꂸ�s��ׂ̂܂ܕ��u�������Ƃɂ���āA���@�s��ׂ͔�Q�҂̐l�ԂƂ��Ă̑�����������V���ȐN�Q�s�ׂɂȂ�̂ł���B
�@�{���ې�Ɋւ��ẮA�u��s�@�v�N�Q�v�ł���ې�̎��s�ɂ�鑹�Q���A�܂��Ɍ��@�����̍����Ɋւ��N�Q�ł���Ƌ��ɁA��s�@�v�N�Q�ɂ�������Q�s�ׂ̈�@�����ɂ߂Č����ł��邱�ƁA���ۖ@�Ɋ�Â��`���̕s���s�������Ă��邱�Ƃ������̂ł����āA���@�s��ׂ̈�@���͖��炩�ł���B
�@�@(4) �{���ې�ɂ�����~�ϗ��@�`��
�@�{���ې�ɂ����āA�T�i�l�炪��������̓I�E���_�I��ɂ͋ɂ߂ĉߍ��Ȃ��̂ł��������A���ɂ����Ă��A��T�i�l���ɂ���āA�Ȃ���Q�̋~�ϑ[�u���邱�ƂȂ����u����Ă������߁A�T�i�l��͍����Ȃ��S�g�Ƃ��ɖ������Ƃ̂ł��Ȃ���ɂ̂����ɂ���B
�@����ɁA�ە���́A�ۂ̂����͂ȓŗ͂Ɗ������ɂ��A�L�͂������ɂ킽���Ĉ����ȓ`���a�𖠉������ċ�ɂ������炷���̂ł��邽�߁A�T�i�l��͌��݂ɂ����Ă��A�����ۂɂ�鎾�a�̗��s������Ă���B�{���ې�́A���̎c�s���A��Q�̍L�͂�������l���āA����z��������ʂȂ��̂Ƃ�����B
�@�{���ې킪���ۖ@�Ɉᔽ����s�ׂł��邱�Ƃ́A���łɌ��������F�肵�Ă���Ƃ���ł��邪�A���̂����ŁA�{���ې�́A��ʏZ�����ʑ�ʂɎE������ړI�������Ď��s���ꂽ�ƍߍs�ׂł���A�T�i�l�̐e���瑽���̔�퓬���̖����D��ꂽ�B�܂��T�i�l�琶���c�����l�X�ɑ��Ă��A�ې�̗^�������|�́A�z����₷����̂�����B
�@�T�i�l�炪�ې�ɂ���ċ�����ꂽ���|�́A�܂��A�y�X�g����уR�����Ɋ��������l�Ԃ����ɍ����䗦�Ŏ��S����Ƃ������|�ł���B�܂��A�ЂƂ��ъ����҂���������Ƃ��̉Ƒ���ߐe�ҁA����ɂ��̒n��ɋ����`���������ċ}���ɗ��s���邱�Ƃ����|��{���������B
�@����ɁA�y�X�g��R�����Ɋ��������l�Ԃ�n��́A������u�����ꂽ��Ό��������Ă݂��A�����ēO�ꂵ���Љ�I�ȍ��ʂ��邱�Ƃł���B�Љ�̒��Ő�����l�ԂɂƂ��āA�y�X�g��R�����̂䂦�Ɏ鍷�ʂ̋��|�́A���̋��|�Ɠ��������A����ȏ�Ɏc���Ȃ��̂ł���B���̂����A�Ĕ��A�ė��s�̋��낵��������B���Ƀy�X�g�́A�쐶��ꖎ��ނ̒��ł̗��s�����\�N����������ŁA�����̃m�~����Đl�ԂɊ�������댯���������Ă���B���������ăy�X�g�͂ЂƂ��ї��s����ƁA���̗��s�n��Ǝ��Ӓn��ɑ��āA�h�u�����Ƃ��ĉ��\�N���y�X�g�ۂ����������Ă��邩�ۂ����ώ@���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@���{�R�ɂ��ې�́A�y�X�g��R�������A�܂��Ɉȏ�ɏq�ׂ��悤�ȋ��Ђ𒆍��̏Z����n��Љ�ɋy�ڂ����Ƃ�_���āA���s���ꂽ���̂ł���B�ې�̎��s�́A�T�i�l��ɐr��Ȕ�Q��^�������肩�A�T�i�l��̂��̌�̐l���ɑ���ȉe����^���A�����m��ʋ��|�ƕs���A���J�̒��Ő����邱�Ƃ��������̂ł���B
�@���̂悤�ȍT�i�l��̋�ɂ́A�ꍏ���������@�ɂ���ċ~�ς��}����ׂ������̂��̂ł����āA���̕K�v���͍��x�ł���B
�@�܂��A�{���ې�͋ɂ߂ē��قȈ�@�s�ׂł���B��w�Ƃ����{���A�����~�����߂ɗp��������@���A��ʂ̐l�Ԃ��E�����邽�߂ɗp����ꂽ�̂ł���B�����ǂ����{�R�ɂ���Đl�דI�Ɉ����N�����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ�m�������̍T�i�l���Q�҂̎��Ռ��A���|���܂��A�z����₷����̂�����B�Ȃ��A���̂悤�Ȏ����N�����̂��A���Q�҂ł���T�i�l���A���Q��������F�߂��A�Ӎ߂����A���������A���̋~�ϑ[�u���Ƃ邱�Ƃ�������Q�҂���u�������Ă��邱�Ƃɂ���āA�T�i�l��͖����Ɉł̒��ɂ���B
�@�T�i�l�ɂ��~�ϋ`���̕s���s�́A���{�����@�̍����I���l�Ɋւ���{�I�Ȑl���N�Q�������炷�A�V���ȕs�@�s�ׂƂ��āA�T�i�l��̐l�ԂƂ��Ă̑����������Ă���̂ł���B
�@�]���āA�{���́A���炩�Ɉ�@���z������ɂ߂ďd��ȐN�Q�s�ׂɂ���Q�������ԕ��u����Ă������ĂŁA�l���N�Q�̏d�含�Ƃ��̋~�ς̍��x�̕K�v�������炩�ɔF�߂��邩��A���@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������u�e�Ղɑz�肵��悤�ȗ�O�I�ȏꍇ�v�i�ō��ُ��a�U�O�N�P�P���Q�P�������j�ɊY������̂ł���A�������Ɍ����Ƃ���́u��O�I�ȏꍇ�v�ɊY������B
�@�@(5) �������̌��
�@�Ƃ��낪�A�������́A���@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������Ƃ���́u��O�I�ȏꍇ�v�ɊY�����Ȃ��Ɣ������Ă���B�������A����́A�펯�I�Ȕ��f�Ƃ��đS�������ł��Ȃ��B
�@�������́A�{���ې�̔�Q�͐��ɔߎS���r��ł���A�����{�R�ɂ�铖�Y�퓬�s�ׂ͔�l�ԓI�Ȃ��̂������Ƃ̕]���͖Ƃ�Ȃ��Ɣ������A�����ē��{�ɂ̓n�[�O�������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�����������Ƃ܂Ŕ������Ă���̂ł��邩��A�l���N�Q�̏d�含�Ƃ��̋~�ς̍��x�̕K�v�������炩�ɔF�߂���B�����āA��Ɍ��������悤�ɁA���̂悤�ȃn�[�O����R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�Ɋւ��Ē������Ƌy�ђ��������̓��{���ɑ��锅���������͕�������Ă��Ȃ��̂ł��邩��A���@�̍��ۋ�����`�̋K��(���@�X�W���Q��)����l���āA�������ۊ��K�@��̍��ƐӔC���ȏセ�̐����̗��@�`�������Ƃ͈�`�I�ɖ��炩�ł��邩��A���@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������Ƃ���́u��O�I�ȏꍇ�v�ɊY�����邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@���̂悤�ȏꍇ�ł������A�E���@�s��ׂ����Ɣ����@���@�ƕ]�������Ƃ���́u��O�I�ȏꍇ�v�ɊY�����Ȃ��Ƃ���̂ł���A�������������u��O�I�ȏꍇ�v�Ƃ����P�[�X�͑��݂��Ȃ��ƌ����ׂ��ł���A�������́A�_�����j�]���Ă���Ƃ��킴��Ȃ��B
�@ (6) �{�����@�s��ׂ͌��@�X�W���Q���ɔ�����
�@���ɁA���@�s��ׂ��A�������̔�������u���@���`�I�ɍ���ɓ�����e�̗��@������`�����ۂ���Ă���ɂ�������炸�C������̗��@���ӂ����Ƃ����悤�ȗ�O�I�ȏꍇ�v�Ɉ�@�ƂȂ�Ƃ��Ă��A�{�����@�s��ׂ̈�@���͖����ł���B
�@��T�i�l���A�{���ې�Ɋւ���n�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC���͂������A���ۋ`���̕s���s�𑱂��Ă��邱�Ƃ́A���@�X�W���Q���́u���y�ъm�����ꂽ���ۖ@�K�v�̏���`���Ɉᔽ���Ă���B
�@�n�[�O����@�X�W���Q���̋K�肷��u���y�ъm�����ꂽ���ۖ@�K�v�ɓ��邱�Ƃ͖����ł���B�����āA���̌��@�X�W���Q���́A���{�������������u���v��u�m�����ꂽ���ۖ@�K�v�́A���̋@�ւ���э��������炷�ׂ������@��̋`�������Ƃ��߂����̂ł���B�܂��A���ۖ@�����炵�A���̎��������邽�߂ɁA�K�v�Ȃ�����ɂ����Ď��{�ɕK�v�ȑ[�u���u�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��߂����̂ł���B���̏����ɂ���āA����́A�n�[�O����R�������炷�邽�߂ɕK�v�ȗ��@���[�u���s�����Ƃ��`���Â����Ă���̂ł���B
�@�܂���T�i�l�̖{���ې�Ɋւ��鍑�ۋ`���̕s���s�́A�������������́u�ߋ��ɂ����ē��{�����푈��ʂ��Ē��������ɏd��ȑ��Q��^�������Ƃɂ��Ă̐ӔC��Ɋ����A�[�����Ȃ���v�i�O���j�ɔ�������̂ł���B�������ɓ������������ɂ�����u�ӔC��Ɋ����A�[�����Ȃ���v�Ƃ��������ɂ́A�����`���͊܂܂�Ă��Ȃ��B�������A�{���ې�Ɋւ���n�[�O����R���Ɋ�Â����ƐӔC�̐��s�ɂ́A���R�̑O��Ƃ��Ĕ�T�i�l�����Q������F�߁A�Ӎ߂���Ƃ������Ƃ��܂܂�Ă���B��T�i�l�́A������F�߂邱�Ƃ������Ȃ��̂ł��邩��A�u�ӔC��Ɋ����A�[�����Ȃ���v�ɔ�����s�ׂł��邱�Ƃ͖����ł���B
�@�܂��P�X�V�W�N�̓������a�F�D���ł́A�u���������Ɏ����ꂽ�����������i�ɏ��炳���ׂ����Ƃ��m�F�v���Ă���̂�����A��T�i�l�̍��ۋ`���s���s�́A�������a�F�D���̏���`���ɂ��ᔽ���Ă��邱�ƂɂȂ�B����́A�������������y�ѓ������a�F�D�������炷�邽�߂ɁA�{���ې�Ɋւ��鍑�ƐӔC���ʂ����ׂ����@���[�u���s���`�����Ă���̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA����{���ې�Ɋւ��鍑�ƐӔC���ʂ����ׂ����炩�̗��@�[�u���Ƃ�Ȃ��������Ƃɂ��A���y�э��ۖ@�̏���`���ɔ������Ԃ������ɂ킽���đ��������Ƃ́A�������̔��������ɏ]���Ă��A���@�s��ׂ̈�@�ƕ]���������̂ł���B
��V�@���@�`���̕s���s�ɂ�闧�@�s��ׂ̐���
�@�P�@�{���ې�ɂ����āA�T�i�l�炪��������̓I�E���_�I��ɂ͋ɂ߂ĉߍ��Ȃ��̂ł��������A���ɂ����Ă��A��T�i�l���ɂ���āA�Ȃ���Q�̋~�ϑ[�u���邱�ƂȂ����u����Ă������߁A�T�i�l��͍����Ȃ��S�g�Ƃ��ɖ������Ƃ̂ł��Ȃ���ɂ̂����ɂ���B
�@���̂悤�ȍT�i�l��̋�ɂ́A�ꍏ���������@�ɂ���ĉ������ׂ������̂��̂ł����āA���̕K�v���͍��x�ł���A�������u���邱�Ƃ́A����ɁA���{�����@���ۏႷ�鍪���I�ȍT�i�l��̐l����N�Q���Â��邱�ƂɂȂ�B
�@�Q ����ōې�̖�肪���߂Ď��グ��ꂽ�̂́A�P�X�T�O�N�̂R���ł���B
�@�P�X�S�X�N�P�Q���A�\�A�E�n�o���t�X�N�ōs��ꂽ�ٔ��́A���{���ߗ��̒��ŁA�ە���̏����Ǝg�p�Ɋւ�����P�Q���ɑ���ې�ٔ��Ƃ��čs��ꂽ�B�V�R�P�����̖{���E�x���̐ӔC���闧��̂��̂Ƃ��āA�쓇���A����\�O�v�A���r�p�A���㐳�j�����ق���A�ؐl�q��ł͂P�Q�����،������B
�@�ې�Ɋւ��鑽���̎��������炩�ɂ��ꂽ�����L�^�́A���P�X�T�O�N�ɓ��{��ł��o�ł��ꂽ�B���̃n�o���t�X�N�ٔ��Ŗ��炩�ɂȂ����ې�̎�������ɁA����₪�s��ꂽ�B
�P�X�T�O�N�R���P���O�c�@�O���ψ���ŁA�����c�����ې�̎����ɂ��Ė₢���������̂ɑ���T�i�l�̐��{�́A�u���{�l�̐푈�ƍߐl�ɑ���ٔ��́A�|�c�_���錾�̎���ɂ��A�����ɂ���čs���邩��A���{�͐푈�ƍߐl�̖��Ɋ֗^���ׂ��ł͂Ȃ��B���{�͒������錠�\���������A�܂���������K�v���Ȃ��B�v�i�B�c�r�g�@�����فB�b�R�V�j���Ɠ��ق����B
�@����́A���̎��_�ōې�̎�����m��A��Q�҂ɑ���~�ϋ`���̔������邱�Ƃ�m�蓾���̂ł���B���ɁA���{�̓��قɏ]���āA��̉��ɂ����Đ��{���A�푈�ƍ߂ɂ��āu�������錠�\�������Ȃ��v�Ƃ��Ă��A������炩�̗��@�[�u���Ƃ肤��]�n�͑��݂������A���ɍ���ɂ����Ă���̉��ł��邱�Ƃ̐����݂����Ƃ��Ă��A�P�X�T�Q�N�̃T���t�����V�X�R���a���̔����ɂ���āA���̐���͂܂������Ȃ��Ȃ����̂ł���B������@�[�u���Ƃ肤�鍇���I���Ԃ��Q�N�ԂƂ���ƁA�P�X�T�S�N�Ȍ�́A��T�i�l�̗��@�s��ׂ͍��Ɣ����@�����@�ƂȂ����Ƃ�����B
�@�R�@����ɁA�P�X�X�R�N����̈�{�����̔����Ƃ��̓��e�̌��\�A�y�т���Ǝ����I�ɑO�シ��ې핔���̋��������⒆���l��Q�҂�̑̌����q�Ȃǂ�P�X�X�S�N�y�тX�T�N�g�p���ȏ��̂������ōە���̎���g�p�����炩�ɂȂ�A���̌�P�X�X�V�N�W���̉Ɖi���ȏ��ٔ��ɂ�����ō��ٔ����ɂ����āA�ې�̎����ɂ��č���ł���薾�m�ɔF������邱�ƂɂȂ����B
�@�P�X�X�T�N�U���X���A����́u���T�O�N����c�v���̑������B���̌��c�́A�u���E�̋ߑ�j��ɂ����鐔�X�̐A���n�x�z��N���I�s�ׂɎv�����������A�킪�����ߋ��ɂ����Ȃ������������s�ׂ⑼�����Ƃ��ɃA�W�A�̏������ɗ^������ɂ�F�����A�[�����Ȃ̔O��\������v�Əq�ׂĂ���B
�@�܂����N�W���P�T���A�u���50���N�̏I��L�O���ɂ������āv�̑��R������b�̒k�b�����\����A���̒��ő��R�́A�u�킪���́A�����Ȃ��ߋ��̈ꎞ���A��������A�푈�ւ̓������ō����𑶖S�̊�@�Ɋׂ�A�A���n�x�z�ƐN���ɂ���āA�����̍��X�A�Ƃ�킯�A�W�A�����̐l�X�ɑ��đ���̑��Q�Ƌ�ɂ�^���܂����v�u�^���ׂ����Ȃ����̗��j�̎����������Ɏ~�߁A�����ɂ��炽�߂ĒɐȔ��Ȃ̈ӂ�\���A�S����̂��l�т̋C������\���������܂��B�܂��A���̗��j�������炵�����O���ׂĂ̋]���҂ɐ[�������̔O������܂��v�Əq�ׁA�u���ݎ��g��ł����㏈�����ɂ��Ă��A�킪���Ƃ����̍��X�Ƃ̐M���W����w�������邽�߁A���́A�Ђ����������ɑΉ����Ă܂���܂��v�Əq�ׂĂ���B
�@���̍���c�y�ё��R�k�b�ɂ���āu��㏈�����ւ̐����ȑΉ��v�̈�Ƃ��Ă̍ې��Q�҂ɑ���~�ς́A����ɂ����Ă����m�ɔF�����ꂽ�͂��ł���ƍl������B
�S�@�ȏ�̌o�߂ɂ���āA�x���Ƃ���L�ō��ٔ�������Q�N���o�߂����P�X�X�X�N�W���ɂ͍����I���Ԃ��o�߂��Ă����Ƃ����邩��A���@�s��ׂ����Ɣ����@�����@�ƂȂ����Ƃ�����B
��W�@���_
�@��L���R�ɂ��A����T�i�l��ې��Q�҂ɑ���~�ϑ[�u���@��ӂ��Ă������Ƃ͈�@�ȕs��ׂɓ�����A��T�i�l�͍��Ɣ����@�̋K��Ɋ�Â��T�i�l�ɑ��ĎӍ߁i���@�S���A���@�V�Q�R���j�ƈԎӗ��x���i���@�P���P���j�̋`�����B
�@���������āA�������̔��f�͎����ł���B
 � �
�@
��U�́@�s���s��ׂɂ�鎖�������E�~�ϋ`���ᔽ�̕s�@�s��
��P�@���̏���
�@�P�@��T�i�l�ɂ�鍑�ƐӔC�ƍs���s���
�@�@�@���łɖ{���ʂł���Ԃ��q�ׂĂ���Ƃ���A���{�R���P�X�S�O�N����P�X�S�Q�N�̊Ԃɒ����e�n�ōs�����{���ې�́A�W���l�[�u�E�K�X�c�菑���邢�͓��c�菑����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɉᔽ����B���������Ĕ�T�i�l�ɂ́A�u�{���ې�Ɋւ��n�[�O������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă����v�i�������R�T�Łj�B
�@�{���ې�́A���{�R���s�����j��ޗ�̂Ȃ��푈�ƍߍs�ׂł���B�ە���́A�ŏ������퓬���ł����ʏZ�����ʂɎE�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����ʔj��ł���A���̔�Q�͎��s�҂��\�������Ȃ�����ׂ����̂ł���B�ې��푈�s�ׂƂ��Đ����������邢���Ȃ闝�R���Ȃ��A�ە���́A�����Ďg�p����Ă͂Ȃ�Ȃ�����ł���B
�@�{���ې�́A���{�R�ɂ��j�㏉�߂Ă̖{�i�I�ȍە���̎g�p�ɂ���Đ��s���ꂽ�B�ە���̎g�p�́A���Ƃ�荑�ۖ@�i�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�j�ɂ���ċ֎~����Ă������A���ۖ@�Ɉᔽ���čە��������g�p������T�i�l�̈�@���E�ƍߐ��́A���̐푈�ƍ߂ɔ䂵�Ă��ɂ߂đ傫�����̂ł���A�����ł��̔�Q�҂ɑ���~�ς̕K�v�����܂��A�ɂ߂đ傫�����̂�����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ې�����s������T�i�l�́A����̔Ƃ����푈�ƍ߂�^�ɔ��Ȃ��A��㒼���Ɏ����������Ȃ���Q�҂���~�ς���[�u���Ƃ�˂Ȃ�Ȃ������B
�@�Q�@�s���s��ׂɂ��V���Ȕ�Q�i�{�����ꂽ���_�I��Ɂj�̔���
�@�@�@���̔�T�i�l�̍��ƐӔC���琶�����s�@�s�ׂ́A���@�E�s���̗��ʂɂ����Ė��ƂȂ邪�A�{���ɂ����Ă͗��҂̕s��ׂ��s�@�s�ׂƂȂ�B�����ŁA���̑O��ƂȂ��`���̓��e���`���̗��s��i�́A���@�E�s���̗��҂ł��ꂼ��قȂ邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�s���{�ɂ������`���ɂ́A�\����瑹�Q���������x�o���čې��Q�҂̑��Q�������������Ƃ����łȂ��A����������Ӎ߂��s���ې��Q�҂̐��_�I��ɂ����S���邱�Ɠ��̋~�ϋ`�����܂܂��̂ł���B
�@�����ŁA���҂�ʁX�ɘ_���邱�ƂƂ��A��T�i�l�̗��@�̕s��ׂɂ��ẮA���łɑ�T�͂ɂ����ďڏq�����B
�@�ł́A�s���ɂ����Ă͂ǂ��ł��������ȉ��ڏq����B��T�i�l�̍s���@�ւł�����t�i�ȉ��u��T�i�l���t�v�Ƃ����j�́A�Ƃ肤��~�ϑ[�u���������i��㒼��ɂ����Ă����Ȃ��Ƃ����������𖾂��邱�Ƃ͉\�ł������j�ɂ�������炸�A���̋~�ϑ[�u���Ƃ�Ȃ��������肩�A����Ƃ����ې�̐푈�ƍ߂��B�����������̂ł���B
�@�{���ې�́A�푈�ƍ߈�ʂɂ͉����ł��Ȃ��c�s���������A���̔�Q���܂��A�푈��Q��ʂɂ͉����ł��Ȃ��[���Ȃ��̂ł���B
�@�{���T�i�l���Q�҂̑��}�ȋ~�ς��K�v�ł��������ƁA�~�ς͋����{�R�������p��������m�闧��ɂ�������T�i�l���t�ɂ���Ă����Ȃ����Ȃ����ƁA�ې��Q�Ƃ����ɂ߂ē���Ȑ푈�ƍߔ�Q�ɑ���~�ϑ[�u�́A�܂��ە�����T�z�����ꏊ��ە���ɗp�����ۂ̎�ʁi�y�X�g�ۓ��j�A�ʁA�T�z���@�̓�������A���c�����Ă����Q�̏ꏊ�A���x��m�点�āA��Q�̊g���h�~���A�s�����������邱�ƂȂǁA�P�Ȃ���K�I�Ȕ��������ł͂Ȃ��A���p�I�ȑ��ʂ���̋~�ϑ[�u��K�v�Ƃ������Ɠ�����A�~�ϋ`���́A�܂���T�i�l���t�ɔ��������Ƃ����ׂ��ł���B
�@��T�i�l���t�̏�L��`���̕s���s�ɂ��A�T�i�l��ɂ́A�P�X�S�O�N��̖{���ې�ɂ���Q�̂ق��ɓ�Q�Ƃ������ׂ��ʌ̐V���Ȕ�Q�i���_�I��ɂ̔{���j���������Ă���B
�@�T�i�l��́A�{���ې�Ƃ������ڂ̉��Q�s�ׂ������ē��e�S�ɎE���ꂠ�邢�͎�����늳���Đ����̋������܂悢���낤���Ĉꖽ����藯�߂��҂����ł��邪�A����ɉ����Ĕ�T�i�l�������Ɏ�����{���ې�̎�����F�߂��A�Ӎ߂����������Ȃ��Ő��̔����I�ȏ�ɂ킽���čT�i�l��ې��Q�҂������~�ς��邱�ƂȂ����u���Ă������Ƃɂ���āA�T�i�l��̋�ɂ͔{�����Ă���̂ł���B�����������ۊ��K�@�Ɋ�Â����ƐӔC�ɂ�锅���`�����������Ă���ɂ�������炸�A�����Ɏ���܂ŗ��s���ꂸ�A�Ȃ��ׂ��~�ϋ`�����s���Ă��Ȃ������ɑ��ẮA��T�i�l�̐V���ȉ��Q�s�ׂƂ��Ė@���\�����ׂ��ł���A��T�i�l�͒����ɋ~�ϑ[�u���Ƃ�ׂ��ł������B
�@���̓_�ɂ��A�~�ϑ[�u���Ƃ邩�ۂ��́A�s���{�̍ٗʂɈς˂��Ă���A�~�ϑ[�u���Ƃ邱�Ƃ͍s���{�ɂ͋`���Â����Ă��Ȃ��Ƃ��錩��������B
�@�������Ȃ���A���̂悤�ȉ��߂́A�����Ȃ�d��Ȗ@�v�N�Q��s���{�ɂ���ӂ��s��ꂽ�Ƃ��Ă��s���{�͋~�ϑ[�u���Ƃ�Ȃ��Ă��������ƂɂȂ��Ă��܂��A���`�ɔ�����B�����ŁA�s���ٗʂ̕��͌����ČŒ肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�ɉ����ĕω�������̂ł���A���̏̂��Ƃł́A���̍ٗʌ��̓[���Ɏ��k���č�`����������Ɖ�����̂��Ó��ł���B
�@���邢�́A�s��ׂ��������s�����ȏꍇ�ɂ́A�s�����̌��E����E���Ă���A���͂�s���ٗʂ͈̖̔͂��ł͂Ȃ��A��@�ł���Ɖ�����̂��Ó��ł���B���́A�ǂ̂悤�ȏ��ō�`���������邩�ɂ��A�����Œ�߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��_�ɂ���A��`����������v�������߂ɂ���Ċm�肵�Ă����K�v������B
�@�����ŁA�ȉ��ō��ٔ�����������A��`���̔����v���������Ă����B�@
��Q�@��`���̔����v��
�@�P�@�܂��A��s�s�ׂɊ�Â���`���̃P�[�X�ŁA�s���s��ׂ̐�����F�肵���u�V���Y���C�e���������v�Ɋւ���ō��ُ��a�T�X�N�R���Q�R����������������B
�@�u�V���Y���C�e���������v�́A�C���ɓ������ꂽ���{�����R�̖C�e���C�݂ɕY�����Ă����̂��E���ĕ����ɓ��������ߔ������A���w����Q�l�����������Ƃ��������ł���B��R�A��R�A�ō��قƂ��A�x�@���Ɋ댯�h�~�[�u�̜�ӂ�����Ƃ��āA�����s�̑��Q�����`����F�߂��B
�@�Q�@��L�ō��ٔ����́A�u���������Z���Ă���n�悩�炳�قlj����炸�A���C������Ƃ��Ĉ�ʌ��O�ɗ��p����Ă���C�l�₻�̕t�߂̊C��ɖC�e�ނ��������ꂽ�܂ܕ��u����A���̊C��ɂ���C�e�ނ����N�̂悤�ɊC�l�ɑł��グ���A�������C�e�ނ̊댯���ɂ��Ă̒m���̌��@����s�p�ӂɎ�舵�����Ƃɂ���Ă��ꂪ�������Đl�g���̓��̔�������댯������A�������A���̂悤�Ȋ댯�͖��N�̂悤�ɊC�l�ɑł��グ���邱�Ƃɂ���Čp�����đ��݂��i�����j�������Ƃ��Ă͂��̊댯��ʏ�̎�i�ł͏������邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�������u����Ƃ��́A�������̐����A�g�̂̈��S���m�ۂ���Ȃ����Ƃ������̊W�R���������ė\�����ꂤ��ɂ����āA��������x�@�����e�Ղɒm�肤��ꍇ�ɂ́A�x�@���ɂ����ĉE������K�ɍs�g���A���疔�͂�����������錠���E�\�͂�L����@�ւɗv������Ȃǂ��ĐϋɓI�ɖC�e�ނ��������Ȃǂ̑[�u���u���A�����ĖC�e�ނ̔����ɂ��l�g���̓��̔����𖢑R�ɖh�~���邱�Ƃ́A���̐E����̋`���ł���Ɖ�����̂������ł���v�Ɣ�������B
�@�������ɂ����ẮA�C�e�����ɂ��P�������S�A���̂P�����ዅ�j�����̏d��Ȑg�̔�Q���Ă���B
�@��L�ō��ٔ����́A�@��N�Q�@�v�̑傫���ɉ����āA�A�Z���ɐl�g���̓��̔�������댯���p�����đ��݂��Ă������Ɓi�댯�̌p���I���݁j�A�B�Z���������̊댯��ʏ�̎�i�ł͏������邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ɓi�ʏ��i�ɂ��댯�����̕s�\���j�A�C���̏��x�@�����e�Ղɒm�肤�邱�Ɓi�\���\���j���A�댯�h�~�[�u�`���̔�������v���Ƃ��������ŁA�x�@�����u�C�e�ނ̊댯���ɂ��Ă̌x����C�e�ނ������ꍇ�̓͏o�̍Í��Ȃǂ̑[�u���Ƃ邾���ł͂��肸�v�ƁA���Y�������̔\�͂̌��E���A��`����Ɛӂ��邱�Ƃɂ͂Ȃ炸�A�u�����E�\�͂�L����@�ւɗv������Ȃǂ��ĐϋɓI�Ɂv�댯�h�~�[�u���u����ׂ��ł������i�ϋɓI�[�u�̕K�v�j�Ɣ������Ă���B
�R�@���̓_�A��L�����̍T�i�R�ŁA���́u�C�e�ނ����S�ɏ���������@���Ȃ�����댯�h�~�`���͂Ȃ��v�Ǝ咣���Ă����B
�@�������A�������ُ��a�T�T�N�P�O���Q�R�������́A���̎咣��r�˂��A�u�������Ƃ̎��{�ɂ��A���C�݂ɂ����锚���ɂ��l�̎����̊댯�̊W�R���͌�����������̂ł���A���̑[�u���댯���F���ɂ�����̂łȂ����Ƃ�O��Ƃ��Ċ댯�h�~�̋`���͂Ȃ����ɂ������̎咣�͍̗p�̌���łȂ��v�Ƃ��āA�u�댯�̊W�R����������������v����A�댯�h�~�`��������������̂ł���Ɣ������Ă���B
�@�������ł́A���ɂ��C�e�̉���`���̕s��ׂ��F�߂Ă���B
�@�����n�ُ��S�X�N�P�Q���W�������́A�u�댯�������̍��{�I�Ȍ����́A���Ɣ퍐���̋@�ւł��������{�����R���A�A�����R�̎w�߂Ɋ�Â����������̈�Ƃ��Ď��{�����C�e�ނ̊C�������̍ہA�������̍�p�ɂ��e�ՂɊC�݂ɑł��グ���邱�Ƃ��[���ɗ\�z�����C�݂ɋɂ߂ċߐڂ����ꏊ�ɑ�ʂ��댯�ȖC�e�ނ𓊊����āA���̌ケ�����u���Ă������Ƃɂ���Ƃ����ׂ��ł��邩��A���̂悤�ɑ�ʂ��댯�ȖC�e�ނ��E�̂悤�ȏꏊ�ɓ������Ċ댯�������̌��������肾���������҂Ƃ��Ă̔퍐���́A���̌�A�C���ɕ��u����Ă���C�e�ނ��C�݂ɑł��グ���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�܂��ł��グ��ꂽ�Ƃ��Ă�����ɂ�锚�����̂��N����Ȃ��悤�ɁA�����̖C�e�ނ𑁋}�ɉ�����āA���̂̔����𖢑R�ɖh�~���ׂ��@����̍�`�����Ă����Ƃ����ׂ��ł���v�ƁA�����ɁA���u�����C�e�̉���ɂ��댯�h�~�`�������Ă���B
�S�@�ȏ�̔��ᕪ�͂���A�{���ې��Q�҂ɑ���~�ϋ`���Ɋւ��čs���s��ׂ��������邽�߂ɂ́A�@��N�Q�@�v�̏d�含�A�A�Z���̔�Q�̊g��p���A�B�Z�����g�ɂ���Q�����̕s�\���A�C�s���ɂ���Q�g��̗\���\���̂S�_����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����ŁA�ȉ��A�{���ې�̔�Q�ɂ��āA��T�i�l���t�Ɏ��������E�~�ϋ`���̍s���s��ׂ������������ǂ�����������B
��R�@�{���ې�ɂ������T�i�l���t�̎��������E�~�ϋ`���̕s���
�@�P�@�{����N�Q�@�v�i�{�����鐸�_�I��Ɂj�̏d�含
(1) �ە���́A�P�X�Q�T�N�W���l�[�u�E�K�X�c�菑�ł��̎g�p���֎~��
��Ă�����ʔj��ł���B�������A�ە���͂����ς��ʏZ���ɑ��Č������A���̔�Q���ǂ��܂Ŋg�傷�邩�́A���s�҂��\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����낵������ł���B
�@��퓬���ł����ʏZ�����A�����̐푈�s�ׂɂ���Ď鑹�Q�ɔ�ׂĂ��A�T�i�l��ې��Q�҂��鑹�Q�͓���Ȑ[�����������Ă���B
�@�T�i�l���Q�҂ɂƂ��āA�ې�ɂ��u�a�̔����́A�푈���̓G�̍U���Ƃ��ė\�������Ȃ����Ԃł������B�܂������̖��O�̂Ȃ��ł̓y�X�g���u�a�Ɋւ���m���͂���قǍ����Ȃ������B�{���T�i�l��ې�̔�Q�҂́A������ˑR�����s���̕a�C�ɏP���A���a����Ɛ����Ԃ̂����Ɏ��X�Ɏ��S���Ă����Ƃ������Ԃɒ��ʂ�����ꂽ�̂ł���B
�@��ʂɔƍߓ��ɂ���Q�҂ɂƂ��āA���̌�����������Ȃ����ƂقNjꂵ�����Ƃ͂Ȃ��B�{���ې�́A��Q����������{�R�ɂ����̂ł͂Ȃ����Ɨ\���͂���Ă������A�ې킪�閧���Ƃ��čs��ꂽ���ƁA���̔�T�i�l���t�ɂ��B���H��Ɠ����ɔ�T�i�l���t��������F�߂Ȃ����Ƃɂ���āA�{���T�i�l���Q�҂́A���炪����Q�ɂ��āA�^�̌�����m�炳��邱�ƂȂ����u����Ă����B
�@�푈�G���Ƃ͂����A��ʏZ�����ʂɑ�ʎE������ە�����g�p���邱�Ƃ́A�l�ԎЉ�̏펯����͑z�������Ȃ��c�s�Ȕ�l���I�s�ׂł���B���{�R��������Ȃ������̂́A�Ȃɂ��������̖��O��l�ԂƂ��Ă݂Ȃ��������ʂ�����ɂ��������Ƃɂ��B
�@�Ƃ���ŁA�{���s���s��ׂɂ������N�Q�@�v�́A��T�i�l�̒����E�~�ϋ`���̕s���s�ɂ���Đ�����{���������_�I��ɂɂ��邪�A�u�����ʑ�ʎE�C�v�̍���ɂ��閯�����ʂ́A��T�i�l�������[����������̂ƂȂ����B���Q�҂ł����T�i�l���A�푈�I����ɂ����Ă��A���炪�ې���s�����������B���ĎӍ߂����A����̋~�ϑ[�u���Ƃ�Ȃ��������Ƃ́A�ې�̎��s���A�푈�Ƃ����̒��Ő��܂ꂽ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��荪�̐[����l�ԓI�A�������ʂɊ�Â����̂ł��������Ƃ������Ă���B
�@��T�i�l�̒��ɂ���u�����l�͊F�E���ɂ��Ă����܂�Ȃ��v�Ƃ����p���́A�{���T�i�l���Q�҂̐l�ԂƂ��Ă̑��������ꂩ�珝������̂ł���B���ɂ������T�i�l���t�̕s��ׂ́A����������l�ԓI�A�������ʓI�p���Ƃ��ĕς�邱�ƂȂ��A�T�i�l��̐l�i�����W���������̂ł���B��T�i�l���t�̕s��ׂ́A�₦���T�i�l��ɐ��_�I�ȏd���Ƃ��Ă̂�������A�T�i�l�炪�l�ԂƂ��Đ����Ă��������ŁA����ȍ���������A�u�{�����鐸�_�I��Ɂv��^�����B
(2) �T�i�l��ɑ����s�@�v�N�Q�͂ƂĂ��Ȃ��傫�����̔�Q�͏d��ŗe�Ղɉ����Ȃ����̂ł���A���}�ȋ~�ς��K�v�Ƃ���Ă������Ƃ͖����ł���B
�@��T�i�l���t�ɂ���Q�҂ɑ���~�ϑ[�u���܂������Ƃ��Ȃ��������ƁA���Q�҂ł����T�i�l���t���Ӎ߂��Ȃ����ƁA������F�߂Ȃ����Ƃ́A��Q�҂̐����E�g�̂��댯�ɂ��炵�A��Q�҂����|�ƕs���Ɋׂ�A�n��Љ�Ő������邤���ő���ȍ������������̂ł������B�����āA��T�i�l�̋~�ϋ`���̕s���s�́A���̂悤�ȏd�w�I�\�������B
�@��P�ɍې�ɂ���čL�͂Ȓn��ɉu�a�������N�����Ƃ������Ԃ͑O�㖢���ł���A�`�d�y�эĔ��̊댯�����ǂ̒��x���������͗\���s�\�Ȗʂ����邪�A���Ȃ��Ƃ����������Ԃ͌p�������댯�����݂������Ƃ͖����ł���A�T�i�l����͂��ߍL�͂Ȓn��̏Z���S�̂��A�����A�g�̂̍����������댯�ɂ��炳��Ă����̂ł���B���̋��|�ƕs���͑z����₷����̂�����A��s�@�v�N�Q�Ƌ��ɁA��T�i�l���t�̕s��ׂɂ��@�v�N�Q������B
�@����ɁA��Q�ɔ�T�i�l���t�̕s��ׂ��A�����I�ȏ�ɂ킽���đ��������Ƃɂ��A�T�i�l��ɑ����{�I�l�������W�̌p���Ȃ����T�i�l��ɋ�����Љ�I���ʂ̔E�]�����_�I��ɂ͑��債�A���̔�@�v�N�Q�͐r��Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B
�@���̂悤�ɖ{���ې�̔�Q�ɑ����T�i�l���t�̕s��ׂɂ���čT�i�l��̐��_�I��ɂ͔{�����A���₪�����ɂ����܂��Ă���Ƃ��킴��Ȃ��B
(3) �O�L�A�u��T�i�l���t�̔����I�ȏ�ɂ킽��s��ׁv�̌o�߂̒��ŁA�P�X�V�Q�N�̓������������A�y�тP�X�V�W�N�̓������a�F�D���ɂ���āA�������������A�����ɂ킽��Q���Ԃ̐푈��Ԃ͏I�������B�������������̑O���Ŕ�T�i�l�́A�u�ߋ��ɂ����ē��{�����푈��ʂ��Ē��������ɏd��ȑ��Q��^�������Ƃɂ��Ă̐ӔC��Ɋ����A�[�����Ȃ���v���Ƃ�\�������B���̌��t��^�Ɏ��s���邽�߂ɂ́A��T�i�l�͋~�ϋ`�����ʂ����˂Ȃ�Ȃ������B
�@�������A��T�i�l���t�́A�{���ې�̎����ɂ��ĉ��疾�炩�ɂ����A�܂�����������~�ς̂��߂̕�����Ƃ�Ȃ������B
�@�@(4) �{���ٔ��̊J�n�Ȍ�����������̊e�n�Ŕ�Q�������s���Ď��X�ƐV���Ȕ�Q�������m�F����Ă���B
�@�������A�T�i�l����͂��߂Ƃ���ې��Q�҂�́A�{���ٔ���ʂ��Ĕ�T�i�l���t�̎p��ڂ̓�����ɂ��邱�ƂƂȂ����B�ٔ�������d�˂邲�ƂɁA��T�i�l���t�́A�ې�̎������F�߂Ȃ��A�Ӎ߂����������Ȃ��Ƃ����s��������܂�Ȃ��Ή��ɁA���炦����Ȃ��{�肪�[�����������O�ł���B
�@���̂悤�ɔ�T�i�l���t���A�T�i�l��ɑ��A��`���𗚍s���Ȃ����Ƃɂ���Đ��̐V���ȉ��Q�s�ׂ������N�����T�i�l��̐��_�I��ɂ�{�������߂Ă���̂ł���B
�@
�@�Q�@�Z���̔�Q�̊g��p��
(1) �{���ې�ɂ���Q�̓����́A���e���ɂ���Q�ƈقȂ�A�T�i�l���Q�ҁA�Z���̐����A�g�̂ɑ���댯���A���Ԃ̌o�߂Ƌ��Ɍp���E�g�傷�邱�Ƃɂ���B�u�a�����̋��|�́A��Q�����������n�悾���łȂ����Ӓn������p�j�b�N��ԂɊׂ��B�܂���x�u�a�����������̂��́A�������s�����܂��Ă����Ĕ����邩�킩��Ȃ��Ƃ����댯�Ƌ��|�̒��Ő������邱�Ƃ�������ꂽ�B����䂦�A�u�a�����������s�����Ƃ��ɑ̌��������|�́A�ߋ��̂��̂Ƃ��ĖY�ꋎ�邱�Ƃ͍���ł���A�₦�����݂̋��|�Ƃ��čĐ������̂ł���B
(2) ���ہA�{���ې�̌��ʁA�ˏB�s�̊e���̂قڂ��ׂĂ̒����łP�X�S�W�N���܂ŁA�y�X�g�A�R�����Ȃǂ̉u�a�̗��s���������B�ˏB�e���h�u�ψ���̓��v�ɂ��ƁA�P�X�S�O�N����P�X�S�W�N�̂W�N�ԂŁA�ˏB�s�S��Ńy�X�g�A�R�����A���`�t�X�ƃp���`�t�X�A�ԗ��A�Y�s���̓`���a�ɂ��������l�͂R�O���l�ȏ�ɒB�����B
�@���̂悤�ɁA���{�R�̍ې�ɂ��u�a�Ĕ����̊댯���p���I�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃɂ���āA�ˏB�s���Njy�яZ���́A�����Ȃ��h�u�������������Ă���B�ˏB�s�ł͂P�X�S�O�N�ȗ����N�A���O�����đl�A�m�~�A墁A�S�L�u���̋쏜���s���Ă���B�܂��A�������ƈ��p���̏��ŁA���A�̊Ǘ��A�y�X�g���N�`���A�R�������N�`���Ȃǂ̗\�h���ˁA�u�a���҂̊u�����ÁA���҂̉Ƒ��̎��e�����Ȃǂ̖h�u���Â̑[�u���A���݂܂Ōp�����čs���Ă���B�����̔�p�͔���ł���A�{����T�i�l���⏞���ׂ����̂ł���B
(3) ���������āA�O�L�P��(2)�ŐG�ꂽ���ƂƏd������ʂ����邪�A���߂Ĕ�Q�̌p���g��̏d�含���w�E����Ȃ�A�{���ې��Q�ɑ����T�i�l�̋~�ϋ`���́A���`�I�ɂ́A��Q�̌p���Ɗg��̖h�~�A��Q�n�y�ю��Ӓn��Z���̐����A�g�̂̈��S�̊m�ہA���|�ƕs���̏����Ƃ��Đ�������̂ł���B
�@����ɑ��`�I�ɂ́A��T�i�l���ې��Q�҂̔�Q�ɂ��ĎӍ߁E���Q�������ׂ��`������u���A���̌��ʁA�T�i�l��̍ې�ɂ���ď�����ꂽ�l�i�̑������A�{���~�ςɂ���đ��₩�ɉ���ׂ��ł���ɂ�������炸�A�t�ɍ��ꂩ�珝���čT�i�l��Ɂu�{�����ꂽ��Ɂv���������Ă���̂ł��邩��A���́u�{�����ꂽ��Ɂv���������ׂ��`��������B
�@�R�@�Z�����g�ɂ���Q�����̕s�\��
(1) �u�a�̔����Ƃ������Ԃɑ��āA��ʏZ���͂Ȃ����ׂ��Ȃ��A�ʏ�̎�i�ɂ���Ă͊댯�������s�\�ł��邱�Ƃ͖����ł���B
�@�댯�̏����́A�T�i�l��ɂƂ��Ă͓��ʒ����̌��n���{���s���@�ւɂ��h�u�������B��̎�i�ł��邪�A���̍ہA�ې�����s���������҂���̂ǂ̂悤�ȍۂ��ǂ��Ŏg�����̂����̏�������I�ɏd�v�ȗv�f�ł������B
�@�{���ې��Q�ɑ���~�ϑ[�u�̈�Ƃ��āA���������A�����̉𖾂͋ɂ߂đ傫�ȈӋ`�������Ă���̂ł���B
�@��T�i�l���t�́A�{������h�u�����ɐϋɓI�ɋ��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���Ȃ��Ƃ��������������āA�ۂ��T�z���������A�ꏊ�A�T�z�����ۂ̎�ޓ��̏������n�ɓ`����K�v���������B
(2) �Ƃ��낪�A��T�i�l���t�́A������������������ׂ�����ɂ���Ȃ���A�t�Ɏ������B�������B���̕s��ׂ́A���n�̖h�u����������Ɋׂ�A�T�i�l���Q�n�y�т��̎��Ӓn��̐l�X�̐����A�g�̂��A���������ɂ킽���Ċ댯�ɂ��炵�A�s���Ƌ��|���������̂ł���B
�@�������𖾂��A���n�Z���ɉu�a�̌�����`�B���邱�Ƃ́A��Q�҂�̖ւ�����Q�����Ă��������ŋɂ߂ďd�v�ȗv�f�ł������B
�@�{���T�i�l���Q�҂̋~�ς́A���Q�҂����T�i�l���t�̎����F��ƎӍ߂��O��ł���A���̕s��ׂɂ���Ă����炳��鑹�Q�̏����́A��T�i�l���t�݂̂��Ȃ�������̂ł��邱�Ƃ͖����ł���B
(3) �T�i�l��́A�ٔ��Ƃ����`��ʂ��Ă��邢�͐��{�W�Ȓ��ւ̐\������s���Ȃǂ�ʂ��āA��T�i�l���t�ɑ��A�{���ې�̔�Q�ɂ��đi���A����������v�����Ĕ�T�i�l���t�̍�`���̗��s�𑣂��ȂǁA�T�i�l�玩�g�ɂ��ő���̓w�͂�ςݏd�˂Ă����̂ł���B
�@�������Ȃ���A��T�i�l���t�́A���琽�ӂ���Ή����Ȃ����A�@��ɂ����Ă������F�ۂ��炵�Ȃ������B
�@�T�i�l��̐��_�I��ɂ�����ȏ�{������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�B���T�i�l���t�̍�`�����s������邱�Ƃ�葼�ɂȂ��̂ł���B
�@�S�@�s���ɂ���Q�g��̗\���\��
(1) ��s�s�ׂ̏d��Ȗ@�v�N�Q�Ɣ�Q�g��̗\���\��
�@�T�i�l��̐��_�I��ɂ̔{���Ƃ��Ĕ������Ă���d��ȑ��Q�́A����Ԃ��q�ׂĂ���悤�ɁA��T�i�l���t�����������Ƌ~�ςƂ�����`���������Ȃ��������Ƃɂ���Ĕ����������̂ł���B
�@�T�i�l��̐��_�I��ɂ����S����邽�߂ɁA��T�i�l���t�́A�Œ�����������A���n�Z���ɐ^����`����`�����������B
�@�{���ې�́A���R�����̎w���E�����̉��Ŕ閧���Ƃ��Đ��s���ꂽ���̂ł���B���Ƃ�肻�̖ړI���̂��̂��A�n��Z�����ʑ�ʂɎE�����A�l�X���ɂ킽���ċ��|�ɗ��Ƃ����߂邱�Ƃ�_�������̂ł���A�{����Q�n���͂��ߍې�����{�����n��Ɍp�������댯�����݂��Ă���́A�e�Ղɗ\���ł��邱�Ƃł������B��T�i�l���t�́A�ې�����s�����鍑���{�̓��t�������p�����̂Ƃ��āA���{�R�̍ې�̎��s��m�肤�闧��ɂ���A�܂��A�����������܂߂��~�ϑ[�u���Ƃ�Ȃ����Ƃɂ��A�{���ې��Q�n���܂ނ��ׂĂ̍ې���s�n��y�ю��Ӓn��̑����̏Z�����A��L�̏d��Ȗ@�v�N�Q���邱�Ƃ�\�������闧��ɂ��������̂Ƃ��āA���R���̍�`����s�����ׂ��ł������B
(2) �n�o���t�X�N�ٔ��Ɣ�Q�g��̗\���\��
�@��T�i�l���t�ɑ���~�ϋ`�������̗v���́A��������ɂ߂č����A��T�i�l���t���|�c�_���錾��������A�~�������ɏ��������P�X�S�T�N�X���Q���ɂ́A��T�i�l���t�̋~�ϋ`�����������Ă����B
�@�~�������ɂ���āA��T�i�l�͘A���R�̐�̉��ɂ������̂ł��邪�A����͊Ԑړ����Ƃ����`�Ŕ�T�i�l���t�͌p�����đ��݂����̂ł���A��̌R�̋��Ȃ��ɐ�������s������]�n���Ȃ������Ƃ��Ă��A��T�i�l���t�ɖ{���ې��Q�҂ɑ���~�ϋ`�����Ə������킯�ł͂Ȃ��B�ނ���A���������Ƌ~�ϑ[�u�͘A���R�̐�̐���Ƃ����v������̂ł���A��̉��ɂ������T�i�l���t�̋~�ϋ`���͓��R����������B
�@�Ƃ���ŁA�P�X�S�X�N�P�Q���A�\���B�G�g�A�M�͓Ǝ��ɁA�n�o���t�X�N�ōە���̏����Ǝg�p�Ɋւ�������{�R�ߗ��P�Q�����ٔ��ɂ����i�b�P�S�O�j�A�V�R�P�����̖{���E�x���̐ӔC���闧��̂��̂Ƃ��āA�쓇���A����\�O�v�A���r�p�A���㐳�j���ق��ꂽ�B�ؐl�q��ł͂P�Q�����،����A�Ós�ǗY�������ɂ�����ێT�z��l�̎����ɂ��āA�x�c�����B�ɂ������O�l�̎����ɂ��ď،������i�b�Q�O�B�b�P�S�P�j�B
�@���Ȃ킿�A���̃n�o���t�X�N�ٔ��ɂ���āA��T�i�l���t�́A�{���ې�̔�Q�̏d�傳�Ɣ�Q���g�債�Ă��邱�Ƃ��\���ɗ\�����������A�\�����Ă����Ƃ�����B
�@�Ƃ��낪�A��T�i�l�́A�P�X�T�O�N�R�����{�̍���Ńn�o���t�X�N�ٔ��Ŗ��炩�ɂȂ����ې�ɂ��Ă̎��^�̓��قŁA�u���{�l�̐푈�ƍߐl�ɑ���ٔ��́A�|�c�_���錾�̎���ɂ��A�����ɂ���čs���邩��A���{�͐푈�ƍߐl�̖��Ɋ֗^���ׂ��ł͂Ȃ��B���{�͒������錠�\���������A�܂���������K�v���Ȃ��B�v�i�B�c�r�g�@�����فj�Əq�ׂ��B���ۂɂ́A���̂悤�ȓ��ق̗��ŁA��T�i�l���t�͕ČR�Ƃ̊ԂŖƐӎ�����s���A�B���H����s���Ă����̂ł���B
�@�@(3) �P�X�W�O�N��ȍ~�̐^���\�I�Ɣ�Q�g��̗\���\��
�@��T�i�l���t�́A���ۖ@�Ɋ�Â������`�����ʂ������A����т��āA�{���ې�Ɋւ��钲���A�~�ϋ`����ӂ��Ă����B
�@�P�X�W�O�N��ɓ����āA�V�R�P�����̑��݂Ɋւ��錤�����}���ɐi�݁A�����̊w�p���E�֘A�}�����o�ł��ꂽ�B
�@�܂��P�X�W�O�N�ɓ���ƁA�W�����E�p�E�G���ɂ���āA�A�����J�̌������L�^����A���̐�̊��ɂ�����f�g�p�̎����������E���\����i�b�T�Q�j�A�V�R�P�����̐푈�ƍ߂ƁA���̉B���H�삪����݂ɏo���ꂽ�i�b�Q�X�̂P�Q�ŁB�b�S�W�̂P�A�Q�j�B
�@�P�X�W�P�N�ɂ́A�X������́u�����̖O�H�v�i�b�R�O�Ȃ����b�R�Q�j���x�X�g�Z���[�ɂȂ�A�V�R�P�����̏Ռ��I�Ȏ������A�L�����ɒm����悤�ɂȂ����B
�@�����ɂ����ẮA�P�X�W�X�N�ɁA���������ۗL���Ă����������܂Ƃ߂��w�ې�^�ŋC��x�����s���ꂽ�B�����ł́A������ƊǗ����̓��{�l��Ƃ̋��q����A�ۍU���̔�Q�ɂ����������̏Z���̏،��Ȃǂɂ���āA���{�R�̍ێT�z�ƒ����e�n�ɂ�����y�X�g���̗��s�̈��ʊW�����ؓI�ɖ��炩�ɂ���Ă���i�b�P�O�T�̂P�A�R�R�Łj�B
�@�X�O�N��ɓ����āA�\�A����ɔ��������J�ŁA���V�A�̍����������فi�����Y�}�����فj�Ɠ��ʌ������فi���j�f�a�����فj����A�n�o���t�X�N�ٔ��̋N�i�������ʁA�y�ы����{�R���O�]�������̕����������ꂽ�B���̕�����V�R�P�����ɂ��l�̎����̋]���҂̎��������������B�]���҂̈⑰�����͂P�X�X�T�N�W���ɁA���{���{��ɔ��������߂�ٔ����N�������B
���{�ł́A�P�X�W�X�N�V���A�����s�V�h��ˎR�̋����{�R�R��w�Z�Ւn����P�O�O�̈ȏ�̐l�����������ꂽ���Ƃ���A�l���ƂV�R�P�����Ƃ̊W���^���A�V�h�斯���u�l���������������v���������Đl���ۑ��̊č���������ɒ�o�����B
�@�P�X�X�R�N�V������́A�V�R�P�����W�����悳��A���{�S���ŏ���E�J�Â��ꂽ�B����҂͂P�X�X�T�N�R���܂łłQ�R���l�ɒB�����B���̒��ɂ͌������̐l�������吨�����B���̂قƂ�ǂ͏��N�����Ȃlj����̑������������A�����̐l�������A�����W�����ĉߋ��̎��������n�߁A�^���̉𖾂��傫���i�B�P�X�X�U�N�ɂ͌��������̏،��W�w�ې핔���x�i���ߎЁj�����s�����Ȃlj��Q�����҂���̐^���\�I�ɂ���ĂV�R�P�����̎����͂���ɐ[���L�Ăɒm���邱�ƂƂȂ����B
�@���������āA��T�i�l���t�́A�P�X�W�O�N��ȍ~�́A�{���ې�̔�Q�̏d�傳�Ɣ�Q���g�債�Ă��邱�Ƃ��\���ɗ\�����������A�܂��\�����Ă����Ƃ�����B
�@�@(4) �R���Ԉ��w�A����ŃK�X����̒����J�n�Ɣ�Q�g��̗\���\��
�@��T�i�l���t�́A�P�X�X�O�N��ɓ���ƁA�R���Ԉ��w�A����ŃK�X���퓙�̐푈�ƍ߂ɑ��钲�����J�n�����B
�@�R���Ԉ��w���ɂ��ẮA���{�͓����A�u���ԋƎ҂��s���Ă������̂ŁA�R�̊֗^�������悤�Ȏ����͂Ȃ��v�ƌ����Ă����i�X�O�N�U�����{���فj�B
�@�P�X�X�P�N�W���A�؍��Ō��Ԉ��w�������������A���N�P�Q���ɂ͊؍��̌��R���Ԉ��w�R�����A���߂ē��{���{�ɎӍ߂Ɣ��������߂ē����n�قɒ�i�����B�����������Ԃ��A��i�̂Q����ɓ��{���{�́A�R�E���{�̊֗^�Ɋւ��钲�����J�n�����B
�@����A�P�X�X�Q�N�P���A�g���`���͓Ǝ��̒����Ŕ����������������\�����B���̐�����ɉ������[�����́u�R�̊֗^�͔ے�ł��Ȃ��v�Əq�ׂ�Ɏ���A�����K�����{������؎�]��k�ɂ����āu���l�тƔ��Ȃ̋C�����v��\�������̂ł���B
�@�P�X�X�Q�N�V���U���A���{�̑�P���������ʂ����\����A�P�Q�V���̎��������\���ꂽ�B����ɂP�X�X�R�N�W���S���A��Q���������ʂ����\����A�͖슯�[�����k�b�����\���ꂽ�B
�@�����t���[�����k�b�ł́A�u���������̌��ʁA�����ɁA���L�͂Ȓn��ɂ킽���ĈԈ������ݒu����A�������̈Ԉ��w�����݂������Ƃ��F�߂�ꂽ�B�Ԉ����́A�����̌R���ǂ̗v���ɂ��ݒu���ꂽ���̂ł���A�Ԉ����̐ݒu�A�Ǘ��y�шԈ��w�̈ڑ��ɂ��ẮA�����{�R�����ڂ��邢�͊Ԑڂɂ���Ɋ֗^�����v�Əq�ׂ��Ă���B���Ȃ킿�A����܂ł̐��{���������S�ɕ����A�R�̊֗^��F�߂��̂ł���B
�@�܂��A�ŃK�X������ɂ��Ă��A���{�͑Ή�����ς����Ă���B�ŃK�X������ە���Ɠ��l�ɋɓ����یR���ٔ��ł͍ق��ꂸ�A��㒷���ԕs��ɕt����Ă����B
�@�������Ȃ���W�O�N��̏I���ɂȂ��āA�������A�����{�R�������嗤�Ɉ�����Ă����ŃK�X����̏�������{���{�ɗv�����A�X�O�N����Q���Ԍ����s��ꂽ�B�����A���{���͞B���ȑԓx�ɏI�n���A�s�����Ȓ��������s���Ă��Ȃ������B
�@�P�X�X�Q�N�Q���̃W���l�[�u�R�k��c�ł̉��w����֎~���̌����A���������̖�����A������w����̏����`�������ɐ��荞�ނ悤��Ă����B������ĂP�X�X�R�N�ɉ��w����֎~���������i�P�X�X�T�N�ɔ�y�j�A�P�X�X�V�N�ɔ����A���̒��ň���ŃK�X����̏����`�������L���ꂽ���Ƃ���A���{���{�͒����嗤�Ɉ��������ʂ̓ŃK�X����̏������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�A�������n�ɂ�����{�i�I�������J�n�����B
�@��L�̂悤�ɁA��T�i�l�̐푈�ƍ߂Ɋւ��鎖�������A�e��̌���A��Q�⏞�����J�n������邱�Ƃ́A�{���ې�ɂ��Ă��A���̎��������ɂ��킾���Ďc�s�ł��邱�ƁA��Q�̋K�͂��傫���A�N�Q�ԗl�̐[���ł��邱�Ƃ���A���R�ɔ�T�i�l���t�́A��T�i�l�̒����E�~�ϋ`���̕s���s�ɂ���āA�T�i�l���Q�҂̔�Q���g�債�A�u�{�����ꂽ���_�I��Ɂv�������Ă��邱�Ƃ��A�\���ɗ\�����������A�\�����Ă����B
�@�@(5) ��{�����̔����E���\�ɂ���Q�g��̗\���\��
�@�P�X�X�R�N�A�g���`��������w������ɂ���āA�h�q���̖h�q�������}���قɂ����āA�푈�����A�Q�d�{�����ۈ��Ƃ��čې���{�ɂ�����A�������Ɋ֗^���A���̍��̌o�܂��ڂ����L������{�F�j�卲�̋Ɩ��������S�̋Ɩ��������������ꂽ�B
�@���̓��e�́A�P�X�X�R�N�P�Q���Ɂw�G���E�푈�ӔC�����x�Q���i�b�P�j�Ɂu���{�R�̍ې�v�Ƒ肷��_���Ƃ��Ĕ��\����A����ɁA�P�X�X�T�N�P�Q���ɂ́A��g�u�b�N���b�g����w�V�R�P�����ƓV�c�E���R�����x�i�b�Q�j�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B
�@�{���ې�Ɋւ����{�����L�ڂ̎����́A�O�L��Q�͂ɏڂ����q�ׂ��Ƃ���ł��邪�A���̈�{�������̔����ɂ���āA���͂���{�R�̍s�����ې�͓�����������Ƃ��Ċm�肵�A�܂���T�i�l���V�R�P�����y�эې�Ɋւ��鎑����ۗL���Ă��邱�Ƃ��A�ے肷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ƂȂ����B
�@����ɂ��A��T�i�l���t�́A�{���ې�̔�Q�̏d�傳�Ɣ�Q���g�債�Ă��邱�Ƃ��\���ɗ\�����������A�\�����Ă����Ƃ�����B
�@�T�@�{���ɂ����鎖�������E�~�ϋ`���̔����ƍs���s��ׂ̐���
(1) �{���́A�O�L�P�Ȃ����S�̗v���ɂ���������Ă͂܂�B����āA��T�i�l���t�ɂ́A��T�i�l�ɂ��ې���s�s�ׂƂ��鎖����������ы~�ϋ`�����A�x���Ƃ��P�X�X�T�N�P�Q���̈�{�����̔����E���\�̎����ɂ͔������Ă����̂ł���A���̋`���̐��s��ӂ������Ƃɂ��A��T�i�l���t�ɂ͍s���s��ׂ����������Ƃ�����B
(2) ����ɁA�P�X�X�V�N�W���A�ō��ٔ����́A�P�X�W�R�N�̌��菈���𑈂����Ɖi���ȏ��ٔ��ŁA�V�R�P�����̊����Ɋւ���L�q���폜���������Ȍ������@�Ƃ��锻�����������B
�@�ō��ٔ����́A�u�֓��R�̒��ɍې���s�����Ƃ�ړI�Ƃ����w�V�R�P�����x�Ə̂���R�������݂��A���̎��������đ����̒����l�����E�Q�����Ƃ̑�́A���ɖ{�����蓖���̊w�E�ɂ����Ĕے肷����̂͂Ȃ��قǂɒ�������Ă������̂Ƃ����ׂ��ł���A����ɖ{�����莞�܂łɂ͏I�킩����ɂR�W�N���o�߂��Ă��邱�Ƃ��������l����A������b���A�V�R�P�����Ɋւ��鎖�������ȏ��ɋL�q���邱�Ƃ͎��������Ƃ��āA���e�L�q��S�ʍ폜����K�v������|�̏C���ӌ���t�������Ƃɂ́A���̔��f�̉ߒ��ɁA���蓖���̊w���̔F���y�ы������Ɉᔽ����Ƃ̕]���Ɋʼn߂���ߌ낪����A�ٗʌ��͈̔͂���E������@������Ƃ����ׂ��ł���B�v�Ɣ��������B
�@���̂悤�ɁA�P�X�X�V�N�W���̎��_�ɂ����Ă��łɁA�ō��ٔ����́u�ې���s�����Ƃ�ړI�Ƃ����V�R�P�����v�̑��݂�F�肵�Ă����̂ł���A�ō��ٔ����́A��T�i�l�̓��t�y�э���ɑ��A�ې�̎��������A��Q�ҋ~�ς��d�w�I�ɋ`���Â����Ƃ�����B
(3) ���̂悤�ɔ�T�i�l���t�̒����A�~�ϋ`���̕s��ׂɂ�������炸�A�V�R�P�����̍ې�̎����𖾂��l�X�Ȍ`�Ői�݁A�܂��{���i�ׂ���N����A���n�ł̔�Q�������s���钆�ŁA�P�X�X�V�N�P�Q���Ȃ����P�X�X�X�N�Q���A�S��̍���^���s��ꂽ�i�b�R�V�Ȃ����b�R�X�A�b�P�Q�X�j�B
�@�@�@�@�@�P�X�X�V�N�P�Q���P�V���̍���^
�@�P�X�X�V�N�P�Q���P�V���A�I���N�q�c���́A���N�W���̉Ɖi���ȏ��ٔ��ɂ�����ō��ٔ����܂��āA�ې��Q�ɂ����₵���B���{�����Y�i�����j�́A����ɑ��A�u������V�R�P�����A���m�ɂ͊֓��R�h�u�������Ƃ������̂ɂ��܂��ẮA�]�����炳�܂��܂ȕ��Ȃ���Ă��邱�Ƃ͏��m���������Ă���܂��B�v�u�ߋ��̐푈�ɂ�����䂪���̍s�ׂ������̐l�X�ɑ��ς��������ꂵ�݂Ɣ߂��݂������炵���Ƃ����[�����Ȃ̏�ɗ����Ă���т�\���グ��v�Ɠ��ق��A�������̖��̏��������g�ނ��Ƃ�����B
�@�A�@�P�X�X�W�N�S���Q���̍���^�@
�I���N�q�c���́A��{�������̑��݂܂��āA�����A�m�F�A�J���̋`���ɂ����₵���B�����������[�����i�����j�́A�u����܂ł̐��{�����̒����ł͐��{�ۑ��̕������ɂ�����V�R�P�����̊��������������͌������Ă��Ȃ��v�Ɠ��ق������A�u�V���Ȏ��������������ꍇ�ɂ͗��j�̎����Ƃ��Č��l�ɎƂ߂Ă��������v�Ɠ������B
�@�B�@�P�X�X�W�N�S���V���̍���^
�@�������A�I���N�q�c���́A��{�����̍ې�̋L�ڂ����邱�Ƃ���̓I�Ɏ��₷��ƁA�h�q���������́A�u���w�E�̈�{�����ɂ��܂��ẮA������������ɊY��������̂ł͂Ȃ��Čl�̓����ł���Ƃ������Ƃŗ������Ă���܂��B�i���j���݃v���C�o�V�[�ɂ������Ƃ����ϓ_������J���Ă���܂���B������ɂ������܂��Ă��A�h�q���̗��ꂩ�炻�̓��e�ɂ��ăR�����g���闧��ɂ͂������܂���B�v�Ɠ��ق��A�m�[�R�����g���J��Ԃ����B
�@�������[�����i�����j�́A�u�ԓ��ɍ������v�ƌ떂���������A���ۂ́A���͂�u�������Ȃ��v�Ȃǂƌ������ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ����̂ł���B��T�i�l�́A����܂Łu�������Ȃ����画�f�ł��Ȃ��v�ƌ����Ă����B
�@�C�@�P�X�X�X�N�Q���P�W���̍���^
�@�c���b�c���́A�B���������J����Ă��Ȃ��Ƃ̖₢���������B��C�c�h�q�������́A����ɑ��A�u��̓I�Ȋ������w�E�̐��̎����Ɋւ��鎖�����m�F�ł��鎑���͊m�F����Ă��Ȃ��v�Ɠ��ق��A�����������s���ӎv���Ȃ����Ƃ��q�ׂ��B
�@��L�̂Ƃ���A��{�������̂悤�ɁA�V�R�P�������ې���s�������Ƃ����������Ȏ����������Ă��A������F�肵�Ȃ����Ƃ����Ȃ̂ł���A���̔�T�i�l�̑ԓx�́A���������A�~�ϋ`���Ɉᔽ�������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ɍ���ŕp�ɂɂƂ肠������悤�ɂȂ������Ǝ��́A�V�R�P�����Ɋւ��Ă��͂�u�m��Ȃ��v�ł͍ς܂���Ȃ����Ƃ̏؍��ł���A��T�i�l�ɏd�w�I�Ɏ��������A�~�ϋ`�����������Ă������Ƃ��������̂ł���B
(4) ��T�i�l���t������������������R�O�N���o�������Ɏ����Ă��A�ې���s�̎�������F�߂Ȃ����Ƃ́A�������������Ɉᔽ���A�������������̐����̑O���˂������s�ׂł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�{���ې�ɂ������T�i�l�̒����A�~�ϋ`���̕s��ׂ��������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
��S�@����
�@���������āA��T�i�l�̍s���s��ׂ́A�ʼn߂��邱�Ƃ��ł��Ȃ���@�s�ׂł���B�����ɍT�i�l��́A�{���i�ׂɂ����āA��T�i�l���t�̍s���s��ׂɊ�Â����Ɣ��������Ƃ��āA���Ɣ����@�P���P���Ɋ�Â��A��T�i�l�ɑ��A���Q���������߂�B�܂����Ɣ����@�S�������p���閯�@�V�Q�S���ɂ��Ӎ߂����߂�B
�@

��V�́@�B���ɂ�錠���s�g�W�Q�̕s�@�s��
��P�@���̏��݂ɂ���
�P�@��T�i�l���{���ې�̏؋����B�ł�����ې�͍s���Ă��Ȃ��Ȃǂ̋��U�̋��q���s���Ȃǂ��āA���Ƃ���݂őg�D�I�ɍې�̎������B�������s�ׂ��A�T�i�l��̐����Ȍ����Ȃ������v��N�Q�����Q��^���Ă���A��T�i�l�ɂ͍T�i�l�ɑ��鍑�Ɣ����@��̔����ӔC����������B
�Q�@�������́A�u��T�i�l�̍ې�B���ɂ�鑹�Q���������v�ɂ��āA�ٔ����Ǝ��̔��f�ŁA���̎����A�y�ѓ��e���������ŁA��T�i�l�̉B���s�ׂ��A�@���Ɣ����@�{�s�ȑO�̍s�ׂɂ��ĂƇA���Ɣ����@�{�s�Ȍ�̍s�ׂɂ��Ăɕ����A���ꂼ��ɂ��āA��T�i�l�̉B���s�ׂ��̂��̂ɂ͂܂������G��邱�ƂȂ��A�T�i�l��̑��Q����������ނ��Ă���B���Ȃ킿�A��P�ɁA���Ɣ����@�{�s�ȑO�ɂ��āu���Ɩ����ӂ̖@���v��K�p���A�T�i�l��̑��Q����������ے肵���B
�@��Q�ɁA���Ɣ����@�{�s�Ȍ�̔�T�i�l�̍s�ׂɂ��āA�u���Ɣ����@��̈�@���F�߂��邽�߂ɂ́A�@����ی삳�ꂽ���v���N�Q���ꂽ���Ƃ��K�v�ł���v�i�������S�S�Łj�Ƃ��������ŁA���Q�����E�⏞�������ɂ��ẮA�u������͔퍐�ɑ������̖@�I������L���Ȃ�����A������̂����B���s�ׂ�������̌�����N�Q�����Ƃ����W�ɂ͂Ȃ��Ƃ��킴��Ȃ��v�i�������S�S�Łj�Ɣ�������B�n�[�O���R���͌l�ɑ��Q������������^�������̂łȂ��Ƃ����ٔ����̉��߂������ɂ��āA�B���ɂ�鑹�Q�ɑ��锅�������������ے肷��̂ł���B
�@�܂��u���̑��̂��́A���Ȃ킿�A������̔�Q�Ɋւ���Љ�I�E�����I�ȗv����ӔC�҂̏����v�������N�Q���ꂽ�Ƃ���_�v�i�������S�S�Łj�ɂ��Ă��A�u���Ɍ�����̂����B���s�ׂɂ���Č����炪�����̏��v�������邱�Ƃɉ��炩�̎x�Ⴊ�������Ƃ��Ă��A���ꂪ�@����ی삳�ꂽ���v�̐N�Q�ɓ�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��v�i�������S�S�Łj�ƁA�T�i�l��̑��Q����������ے肵���B
�R�@�������́A���Ɣ����@�{�s�O�̔�T�i�l�̍s�ׂɂ��āA�u���Ɩ����ӂ̖@���v�ɂ���Ĕ�T�i�l�͑��Q�����ӔC��Ȃ��|�������邪�A���łɑ�Q�͂ɂ����ďq�ׂ��Ƃ���A�{���̑��Q�ɑ��āu���Ɩ����ӂ̖@���v�͓K�p���ꂸ����Ă���B
�@�������́A�T�i�l��̑��Q�������������ɂ��āA���������u������͂����̖@�I������L���Ȃ��v���Ƃ������āA�����N�Q���������Ȃ��Ɣ������Ă���B
�@�������A���ɍT�i�l��ɂ́u�n�[�O���Ɋ�Â������E�⏞���������̖@�I�����͂Ȃ��v�Ƃ����������̔��f�ɗ������Ƃ��Ă��A��T�i�l�ɂ��B���Ƃ�����ׂ́A�T�i�l��̏d��Ȍ����s�g�i�ې��Q�̊g��h�~�A��Q�ҋy�щƑ��̐l���N�Q�̉[�u�A�Ӎߋy�ё��Q�����Ɋւ���@�I�Ȑ����A�܂����l�̓��e�Ɋւ���Љ�I�E�����I�ȗv���A����ɐӔC�҂̏����v���Ȃǁj�����W�Q�Ȃ����s�\�Ȃ炵�߂���̂ł���A�����̌X�̉B���s�ׂ́A������ɑ���V���ȉ��Q�s�ׂ��Ȃ��̂ł���A�������ɂ́A�T�i�l�炪�ւ��������s�g�W�Q�̓��e�ɂ��Ă̏d��Ȍ�F������B
�@�����ŁA���̏��_�����ƂȂ�B
�@��P�́A�T�i�l�炪�N�Q�����Ƃ��������Ȃ����@�v�͂����Ȃ���̂ł���A���ꂪ�@����ی삳�����̂ƌ����邩�Ƃ����_�ł���B
�@��Q�́A��T�i�l�̂����Ȃ�s�ׂ��B���s�ׂƂ��A��T�i�l��ɑ���N�Q�s�ׂł���Ƃ���̂��Ƃ����_�ł���B
�@��R�́A�����Ȃ��̓I�ȑ��Q�����������ƌ����邩�Ƃ����_�ł���B
�@�T�i�l�́A���łɌ��R�ł����̏��_�ɂ��Ď咣���Ă���̂ŁA�{�͂ł́A��������ᔻ����ϓ_����A�������܂��čT�i�R�ٔ����ɓ��ɒ��ӂ�ꂽ���_�ɂ��Ĉȉ��̂Ƃ���ڏq����B
��Q�@�T�i�l��̔�N�Q�@�v�Ȃ��������ɂ���
�@�@�@
�@�P�@���_�I��ɂ̔{��
�@������́A�{���B���s�ׂɂ���āA��ꎟ�I�ȉ��Q�s�ׂł���{���ې�ɂ���Ď����_�I�ȋ�ɂ��Ԃɓn�苭����ꂽ�����łȂ��A����ɖ{���B���ɂ���Ĕ퍐�ɑ���l�X�Ȍ����s�g�����W�Q�Ȃ����s�\�ɂ��ꂽ���Ƃɂ��V���ȋ�ɂ�������ꂽ���̂ł���B
�@�@�@���̓_�A�������́A�T�i�l��̑��Q�������������ɂ��āA���������u������͂����̖@�I������L���Ȃ��v���Ƃ������āA�����N�Q���������Ȃ��Ɣ��������B���Ȃ킿�A�������́A��T�i�l��ɐ��������_�I��ɂ́A���܂��@�I�ی�ɒl������̂ł͂Ȃ��A��E���x�͈͓��̐��_�I��ɂł���Ɣ��f�����̂ł���B�������́A�{���ې�ɂ��A�ې�̎�����F�߁A�n�[�O������R���̋K�����e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�ɂ�鍑�ƐӔC�������Ă����ƔF�肵���ɂ�������炸�A���̎������B�����邱�ƂŐ����鑹�Q�ɂ��Ă͎�E���x���̑��Q�ł���Ƃ���̂ł���B
�@�@�@�������Ȃ���A�ې�̎�����F�߂Ȃ���A����ʼnB���ɂ�鑹�Q��F�߂Ȃ����Ƃ́A���Ȃ킿�ې��Q�҂ɋ����Q����������Ă��邱�ƂƓ��`�ł���A�^�̈Ӗ��ōې�̐r��Ȕ�Q��F�߂����Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̂悤�Ȍ������̔��f�́A�ې��Q�҂������ɏ����邱�ƂɂȂ����B
�@�Q�@�B���ɂ�鍑�ƊԊW��ʂ����⏞�������̖W�Q
�@���łɌ��������F�肵�Ă���Ƃ���A��T�i�l���s�����ې�Ɋւ��ẮA�n�[�O����R������e�Ƃ��鑹�Q�����ӔC�𗚍s���ׂ���T�i�l�̍��ƂƂ��Ă̋`���������������Ƃ͋^���Ȃ��B
�@���̏ꍇ�ɔ�T�i�l���������ƐӔC�̑��肪��Q�Ҍl���A���͔�Q�����͌������������B�������A������ɂ��Ă���T�i�l�������鍑�ƐӔC�������Ƃ����炩�ł���B
�@�������́A�u���Ƃ��A�푈�̎S�Q�͍ŏI�I�ɂ͌l�ɋA������̂ł��邩��A�����y�ѓ��K���̋��ɂ̎�|�E�ړI�́A����̉ߒ��ɂ������퓬�����܂߂��l�̕ی�ɂ���Ɖ����邱�Ƃ��ł���v�ƔF�߁A�u�l�������̍��ۈ�@�s�ׂɂ���đ��Q�����ꍇ�ɂ́A���Y�l�͉��Q���̍��ېӔC��Njy���邽�߂̍��ې������o�������̂Ƃ��Ă͔F�߂�ꂸ�A���̌l�̑�����{�����A���Y�l�̎��������グ�O��ی쌠���s�g���邱�Ƃɂ���āA����ɑ���@�I�ȐN�Q�Ƃ��Ĉ����A���ƊԊW�ɐ�ւ��đ��荑�i���Q���j�ɍ��ƐӔC��Njy������̂Ɖ�����Ă���v�Ƃ��������������Ă���B
�@���̌��R�̔��f�ɏ]���A��@�Ȑ푈�ƍ߂̔�Q�҂́A�������{��ʂ��đ��Q�̕⏞���錠���A���Ȃ��Ƃ��A�������{�ɑ��Q��i���錠����L���Ă���B
�@�{���T�i�l��́A�P�X�V�Q�N�̓������������y�тP�X�V�W�N�̓������a�F�D���̍ۂɂ��̋@��������B
�@�u�l�̑�����{�����A���Y�l�̎��������グ�v�u����ɑ���@�I�ȐN�Q�Ƃ��Ĉ����v�邽�߂ɂ́A�܂���Q�҂�����̔������Q�̌�����m��A�������{�ɑi���邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A��T�i�l�̉B���s�ׂɂ��A�T�i�l��͎���̔�Q���{���ې�ɂ������������m�邱�Ƃ��ł����A�������������y�ѓ������a�F�D���̌��ߒ��ŁA�����̒������{�ɔ�Q��i���錠����N�Q���ꂽ�B
�@�R�@�B���ɂ�鑹�Q���������̒�i�̌����s�g�̖W�Q
�n�[�O���R���́A��@�Ȑ푈�s�ׂɂ���Ĕ�Q�����l�ɑ��Q������������t�^���Ă���Ɖ�����邩��A�T�i�l��́A���ڂɉ��Q���ɑ��đ��Q�������������s�g���邱�Ƃ��ł����̂ł��邪�A��T�i�l�̉B���s�ׂɂ�茠���s�g��W�Q���ꂽ�B
�@�Ƃ��ɂP�X�W�O�N�ォ��P�X�X�O�N��ɂ����āA��T�i�l�̉B���s�ׂ́A������ۗL���Ă���ɂ�������炸����J�ɂ��ĉB��������A������˂������Ă������铙�A���Ɉ����ňꍑ�̐��{�Ƃ��Ēp���ׂ��ԓx�������Ă���B
�@�P�X�X�O�N��ɓ���A���̗��̏I���ɂ���āA�푈��Q�A�푈�ƍ߂ɑ���⏞��肪���E�I�ɘ_�c����A���{�ɂ����Ă��A�P�X�X�P�N�P�Q���Ɋ؍��̌��R���Ԉ��w�������n�قɒ�i����ȂǁA��T�i�l�̐푈�ƍ߂ɑ��鑹�Q���������߂铮�����V���ȓW�J���������B��T�i�l���ې�̎�����F�߂�A���R�ɂ��A�����̔�Q�҂����Q���������߂邱�Ƃ͕K���ł������B��T�i�l�͂��̂悤�Ȏ��Ԃ�����A���R�ɖh�~���邽�߂�舫���ȉB���s�ׂ��p�������̂ł���B
�@��L�̂P�X�W�O�N�ォ��P�X�X�O�N��ɂ����Ă̌X�̉B���s�ׂ́A���̂ЂƂЂƂ��T�i�l��ې��Q�҂̌����s�g��W�Q����Ӑ}���������s�ׂł���B
�@�Ƃ���ŁA�x���Ă��P�X�V�W�N�̓������a�F�D��������́A�����Ԃ̍��������S�ɉ���A��T�i�l�̉B���s�ׂ��Ȃ���A�T�i�l��́A��T�i�l��ɎӍ߂Ƒ��Q�����𐿋�����ٔ����N���邱�Ƃ��\�ƂȂ�͂��ł������B
�@��T�i�l�́A�������������y�ѓ������a�F�D���Ȍ�A��Ɍ�������ق�A��j�����̔���J�[�u�ȂLj����ȉB���s�ׂ����߂��̂ł���B���̌��ʁA�T�i�l��ې��Q�҂͒�i���錠�������W�Q����A�{����i�̂P�X�X�V�N�ɂ�����܂ŁA�ٔ����錠����N�Q���ꑱ���Ă����B
�@�T�i�l��ې�̔�Q�҂��l�Ƃ��ĉ��Q����ɑ��Q���������߂錠�������邩�ۂ��ɂ�����炸�A�T�i�l�炪��T�i�l��ɒ�i���A���̔��f���ٔ����ɋ��߂錠���܂ł�ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��T�i�l�̉B���s�ׂ́A���̍ł���{�I�Ȍ�����N�Q���������̂ł���B
�@�܂��A�T�i�l��́A������ې�̐ӔC�Njy�̋@��A���ɍې�̉��Q�s�ׂ̒��S�l�����������{�l��̌Y���ӔC�Njy�̋@���D��ꂽ�B�T�i�l��́A���V�R�P���������ł͐Έ�l�Y��k�쐭����̕������╔���N���X�̌Y���ӔC������邱�Ƃ�]��ł����B�܂����R�Ȃ◤�R�Q�d�{���̍ې�Ɋւ�������Z�̌Y���ӔC�������]��ł����B
�@�������A�ې�ɂ��ẮA��T�i�l�̉B���s�ׂɂ���āA�������یR���ٔ��ł͑S���ق���Ȃ������B����͓싞��s�E�����ٔ��ōق��ꂽ���ƂƑΔ䂵�Ē������s�����ƌ�����B
��R�@��T�i�l�̉B���s��
�@�P�@���ۖ@�ᔽ�̐푈�ƍ߂Ɋւ���B���s��
�@ ���j�I�o�߂Ƃ��Ĕ�T�i�l�͂R�̎����ɂ����ĉB���s�ׂ������Ȃ��� �����B
�@��P�̉B���́A�P�X�S�T�N�W���P�T���̔s���O�シ��؋��B�łł���B
�@���N�W���P�O���|�c�_���錾��������肳���Ƃ����ɁA��T�i�l���t�͊t�c����Ō������̏ċp�����肵���B�����̃n���r���x�O�̕��[�ɂ������V�R�P�����̎{�݂ɑ��ẮA�|�c�_���錾�ȑO�̂W���X���A�\�A���Q�킵���i�K�ŏ؋��B�ł��J�n�����B�{�݁A�����A���ނ͂��Ƃ��Ƃ��j��ċp����A�u�}���^�v�ƌĂ�Ă��������l��V�A�l�Ȃǂ̕ߗ��́A�S���A�u�؋��B�Łv�̂��ߎE�Q���ꂽ�̂ł���B
�@��Q�̉B���́A�P�X�S�T�N�W������P�X�T�Q�N�܂ł̕ČR��̊��ɍs��ꂽ�B���̎����̉B���s�ׂ́A�푈�ƍ߂̏�����Ƃ�邽�߂ɍs��ꂽ���A���ړ����҂̗��Q�Ɋ�Â��čs��ꂽ�����łȂ��A��T�i�l�ɂ��g�D�I���ϋɓI�s�ׂƂ��čs��ꂽ�̂ł���B����ɂ��̉B���ɂ́A�A�����J���{�E��̌R���֗^���Ă����B
�@���Ȃ킿��T�i�l�E���{����эې�W�҂́A�ČR�ɑ��ې핺�팤���E�J���̕����E������S�ʓI�ɒ��A�ČR�̍ې핺��J���ɋ��͂����̂ł���A����ƈ����ւ��ɁA��ƂƂ��Ă̑i�ǂ�Ƃꂽ�̂ł���B
�@��R�̉B���́A�P�X�T�Q�N�̍u�a����A��̊��̏I�����獡���Ɏ���܂ł̉B���s�ׂł���B
�@�P�X�W�O�N��ɓ����āA�ې�E�V�R�P�����̎��Ԃ̉𖾂�����I�ɐi�B�������A���̎��ԉ𖾂́A�����Ĕ�T�i�l�ɂ���čs��ꂽ�̂ł͂Ȃ������B�W�O�N��̎��ԉ𖾂̐i�W�́A���V�R�P�����̑����ł������l�X���،����n�߂����ƁA�����̔�Q���n�ɂ����钲���̐i�W�A�A�����J���ۗL���Ă����̊������̌��J�A�����{�R��w���ɂ����l�X���ۑ����Ă���������A��w�E�̕����̔����Ȃǂɂ���ĉ𖾂��}���ɐi���ƂɋN������B
�@�����̎��ԉ𖾂�����ɂQ�O�N�ȏ���̍Ό����o�߂��A�����ł͍ې핔���̔ƍߍs�ׂ͍��ۓI�ɂ������I�ɂ��펯�ƂȂ��Ă����B�������̌����n���ɂ���Ă���ɎЉ�̋��X�ɂ܂Ŗ{���ې�̎����͓`����ꂽ�B
�@����ɂ�������炸�A��T�i�l�́A����т��čې킨��тV�R�P�����ɂ��ĉB���������Ă���̂ł���B
�@�Q�@�s��O��ɂ�����B��
�@�P�X�S�T�N�W���P�T���A�|�c�_���錾�����������T�i�l�́A������u�I��ْ̏��v�������ē��{�����ɐ푈�̏I���𖾂炩�ɂ����B
�@�ČR�́A�X���P�P���A�����p�@�ڑߕ߂���ȂǂR�X�l�̐�Ƃɑߕߗߏ�������A�푈�ƍ߂̏������J�n���ꂽ�B��T�i�l�́A���ۖ@�Ɉᔽ����ې�Ɋւ��ẮA�O��I�ɉB�����邱�Ƃɂ���āA�푈�ƍ߂ɖ���邱�Ƃ�悤�Ƃ����B
�@���ʂƂ��āA�ې�Ɋւ��Ă͂����Ȃ�Ӗ��ł��߂ɖ���邱�Ƃ͂Ȃ������B�ČR��̉��A�P�X�S�U�N�T���R������n�܂��������ٔ��̑S�ߒ���ʂ��āA��T�i�l�́A���ێЉ�ɑ��čې�̎������B�����������̂ł���B
�@���̍ې�̉B���́A���Ƃ���݂̉B���s�ׂƂ��Ă����Ȃ�ꂽ�B����ɂ��̉B���́A�퍐���A�����J���{�E��̌R�Ǝ����������邱�Ƃɂ���Đ��������B
�@�R�@��̉��ɂ�����B��
�@�A�����J�́A�P�X�S�T�N�W������P�X�S�V�N�̏I���ɂ����āA�S��ɂ킽����{�ɒ�������h�����푈�ƍ߂Ɋւ���撲���s�����B���Ȃ킿�ČR�́A�ė��R�����핔���i�L�����v�E�f�g���b�N�j����T���_�[�X�A�g���v�\���A�t�F���A�q����S�l�̒�������h�����Ă���B
�@�������{���́A�ČR�������T���_�[�X�y�уg���v�\���ɑ��A�V�R�P�����̑g�D�\�����������x���炩�ɂ������A�ە���̎���g�p����ѐl�̎����ɂ��Ă͉B���ʂ����B���{���́A�O�ꂵ���B���H����s���A���������킹�čې�B���̂��߂ɋ��U�̋��q�������B
�@�܂����{�@�ւƂ��Ă͏I��A���ψ���E�L���@�ւ��A�����Ĕ�����̐��{�@�ւƂ��ċ����R�S�̂ɉe���͂��s�g���Ă��������@�ւ��B���H��̒��S�ƂȂ����B
�@����A�ČR�̒ʖ�Ƃ������ꂩ��B���H��̒��S�ɍ������̂������Lj�ƋT��ш�Y�ł������B�ނ�͒ʖ�Ƃ��ĕČR�T�C�h�ɐg�������Ȃ���ČR�̓������f���A���{���̑Ή������肵�Ă������̂ł���B�����R�Ȃ̉Ȋw�Z�p�S���Ƃ������ꂩ��q��ҊԂ̘A���Ԃ������Ă������̂��V�Ȑ���ł���B
�@�ȏ�̔s�풼��Ɍ`�����ꂽ�B���H��̑g�D�I�\���́A���̎����̉B�����ŏI�I�ɐ�������P�X�S�V�N���܂Ŋ�{�I�ɑ������B
�@�P�X�S�V�N�ɃV�x���A�}�����̂V�R�P������������ې�̎��������\�A�́A�Έ�l�Y��ɑ���q���v�������B�ې�̎������\�I����邱�Ƃ����ꂽ��T�i�l�́A�V�R�P�������ł������Έ�l�Y���ČR�Ƃ̖��ڂȊW�������A�ې핺��J���̂��ߕČR�ւ̑S�ʑS�ʓI���͂��s���A�ČR�������t�F���A�q���́A�ې�Ɋւ��鎑������肵���B��T�i�l�͂��̕ČR�Ƃ̎������ɂ���āA�����ٔ��ł̑i�ǂ�Ƃ�A�B���H��𐬗�������̂ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�P�X�S�T�N����P�X�S�V�N�ɂ�����푈�I������̉B���s�ׂɂ���āA�ې�͐푈�ƍ߂Ƃ��čق���邱�ƂȂ������Ɏ����Ă���B
�@�S�@�n�o���t�X�N�ٔ��ł̖\�I�Ɣ�T�i�l�̉B��
�@�P�X�S�X�N�P�Q���A�\�A�͓Ǝ��Ƀn�o���t�X�N�ŁA�ە���̏����Ǝg�p�Ɋւ�������{�R�ߗ��P�Q�����ٔ��ɂ������B�ې�̑����̎������\�I���ꂽ�����L�^�́A�P�X�T�O�N�ɓ��{�ł��o�ł��ꂽ�B�������A�A�����J�����̃\�A�̖\�I�ɑ��A�u�t���[���A�b�v�ł���v�Ƃ����������o�������Ƃ���݂Ƃ��āA��T�i�l�͍��ێЉ�ɑ��čې�𖾂炩�ɂ��邱�ƂȂ��B���𑱂����B
�@�n�o���t�X�N�ٔ��̕���ɂ��āA�P�X�T�O�N�R���ɓ��{�̍���ŁA�ې�̖�肪�Ƃ肠����ꂽ�B��T�i�l�͂��̎��̓��قŁA�u���{�l�̐푈�ƍߐl�ɑ���ٔ��́A�|�c�_���錾�̎���ɂ��A�����ɂ���čs���邩��A���{�͐푈�ƍߐl�̖��Ɋ֗^���ׂ��ł͂Ȃ��B���{�͒������錠�\���������A�܂���������K�v���Ȃ��B�v�i�B�c�r�g�@�����ٓ��فj���Ɠ��ق����B��T�i�l�͂��̂悤�ȓ��ق̗��ŁA���ۂɂ͕ČR�Ƃ̊ԂŖƐӎ��������s���A�B���H����s���Ă����̂ł���B
�T�@����
�@���̌�T���t�����V�X�R�u�a���������A��̊����I������i�K�ŁA��T�i�l�͎���̎�ōې�̎����𖾂炩�ɂ��A�푈�ƍ߂Ƃ��čق����Ƃ��ł��闧��ɗ��������A������ׂ����ƂȂ������Ɏ����Ă���B
�@����������T�i�l�̍s�ׂ́A�P�Ɂu�B�����v�Ƃ��A�u���炩�ɂ��Ȃ��v�Ƃ��������̖��ł͂Ȃ��B�ɂ߂č��x�Ȉ�@�����������g�D�I�s�ׂƂ��čs��ꂽ�B���A�؋��B�ōs�ׂƂ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@������T�i�l�ɂ��B���s�ׂ��Ȃ��ꂸ�ɓ��R���ٔ��ɂ����ĐR������Ă����Ȃ�A��T�i�l�̔�Q�҂ɑ���c�s�s�ׂ̎��������ׂĖ��炩�ɂȂ�A�~�ϋ`�������R�ɔF�߂��A�T�i�l���Q�҂́A�ӔC�҂̏����Ƒ��Q�����𐿋����邱�Ƃ��ł����͂��ł������B
�@�������A���̔�T�i�l�ɂ��B���ɂ���āA�T�i�l���Q�҂́A������̎���Q�ɂ��āA�����𐿋�����ǂ��납�A���{�R�̍ې�ɂ����̂ł��邱�Ƃ���m�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B
�@�U�@�P�X�V�O�N��������������y�ѓ������a�F�D���ɂ�����ې�̉B��
�@�P�X�V�Q�N�̓������������y�тP�X�V�W�N�̓������a�F�D���ɂ����āA�����Ԃ̔�����肪�Ƃ肠����ꂽ�B��T�i�l�́A���̌��ߒ��ōې�̎��������炩�ɂȂ邱�Ƃ��ɓx�ɋ��ꂽ�B�������ߒ��ōې�̎��������炩�ɂȂ�A�T�i�l�猻�n��Q�҂͓��R�������������A�������{����T�i�l�ɑ��锅���������s�킴������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͕K���ł������B���̎��Ԃ�����āA��T�i�l�́A���ߒ��ɂ����čې�̎�����O�ꂵ�ĉB�����A�T�i�l���Q�҂̌����s�g��W�Q�����B
�@���ʓI�ɂ́A�������������ɁA�������{�ɂ���āu�푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾����v�Ƃ��������������ꂽ���A����͂��̎��_�Ŕ�T�i�l���ې�̎�����O��I�ɉB����������ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�V�@�P�X�W�O�N��̐^���\�I�Ɣ�T�i�l�̉B���s��
�@�@(1) �ې�̎����̖\�I�@
�@��L�̂悤�ɔ�T�i�l�ɂ��O�ꂵ���B���s�ׂ��Ȃ���A�ې�̎����͐�㒷���ɓn���Đ��Ԃ̒m��Ƃ���Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B
�@�������Ȃ���A�P�X�W�O�N�ɓ����āA�W�����E�p�E�G���ɂ���āA�A�����J�̌������L�^����A���̐�̊��ɂ�����f�g�p�̎����������E���\���ꂽ��A�P�X�W�P�N�ɂ́A�X������́u�����̖O�H�v���x�X�g�Z���[�ɂȂ�ȂǁA�V�R�P�����̊����̎c�s�Ȏ��Ԃ̖\�I�E�������}���ɐi�B
�@�Ƃ��낪�A��T�i�l�́A�ې�̎������\�I����n�߂����Ƃɑ��āA������F�ߎ��玖��������ǂ��납�A����Ɉ����ȉB���s�ׂ��s�����B
�@�@(2) �P�X�W�Q�N�����ɂ�����B��
�@�V�R�P�����̐^���̖\�I�E�������i�ޒ��ŁA�P�X�W�Q�N�S���U���A�O�c�@���t�ψ���ŁA�V�R�P�����Ɋւ��鎿�₪�s��ꂽ�B�嗘�v�c���́A�V�R�P���������m�̎����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������A�V�R�P�����Ɋւ�����{���{�Ƃ��Ă̑S�ʒ�����v�������B
�@����ɑ��Ĕ�T�i�l�́A�V�R�P�����̑��݂����������Ƃ��āA�����Ȃ��ۊǂ��Ă���u���畔������v�Ɓu���������v�������A���疼��Ɂu�֓��R�h�u�������A�ʏ̐Έ䕔���v������A���Z�P�R�R�����̌R�l�̍��v���P�T�T�O���A�R���i�ٗb�l�j���Q�O�O�X���ł��邱�ƁA�܂��u���������v�ɂ́A�{�����n���r���ɂ���A�n�C�����A���O�A�����A�ь��A��A�e�x���ւ̔z�u���L�ڂ���Ă���Ɠ��ق����B
�@�������Ȃ���A�ې�̌�����l�̎����ɂ��ẮA�u���畔������╔�������ɂ́A�L�ڂ��Ȃ��A���Ɏ������Ȃ��v�Ƃ����B
�@�܂��A�O���Ȃ́A�V�R�P�����ɂ��āA�u�R�O�N�ȏ�O�̐�̉��̘b�ł���v�u�L�^�����邩�ǂ����A���m���Ă��Ȃ��v�u�X�̏����ł���Ƃ��A�_���Ȃ����͓`���Ɋ�Â��Ƃ������悤�Ȃ��̂ɂ��āA���̓��e�����������ΕďƉ������Ƃ�������͂Ƃ��Ă��Ȃ��v�Ɠ����A�S�ʎ������������ۂ��B���������Ă���B
�@�@(3) �P�X�W�Q�N�h�q���h�q�������̍ې�L�^�̔���J��舵��
�@���A���R�W�̎����́A�h�q���h�q��������j���ɏW�߂��A�P�X�T�O�N��㔼����A��ʂɌ��J����Ă����B
�@�P�X�W�Q�N�P�Q���A��T�i�l���E�h�q���h�q�������́A�u��j�����̈�ʌ��J�Ɋւ�����K�v���߂��B����͂P�X�W�O�N�T���Q�V���t�́u���Ɋւ�����P�[�u�ɂ��āv�Ƃ����t�c������A�u�h�q���{���ɂ�������Ɋւ�����P�[�u���ɂ��āv�i���a�T�T�N�X���P�W���h������S�T�P�W���j�Ƒ肵���ʒB�Ɋ�Â��Ē�߂�ꂽ���̂ł���B
�@���̓��K��S���ŁA�Ώێ����̂����A�R���̌��ʁA�@�v���C�o�V�[�̕ی��v������́A�A���v�Ȃ����́A�B�D�܂����Ȃ��Љ�I��������N���邨����̂�����́A�C���̑����J���s�K���Ȃ��́A�Ɣ��肵���ꍇ�A���J���Ȃ����Ƃ��߂��B
�@�h�q���͓����̓��t�ŁA�u�������̌��J�R�����{�v��v���쐬���A�R���̎��{�v�̂��ׂ����K�肵���B���̂Ȃ��ŁA�A�u���v�Ȃ����́v�Ƃ��āu�O���l�i�ߗ����܂ށj�̋s�ҁv�u���D�y�ыs�E�Ȃǁv�u�L�ŃK�X�̎g�p�v�A�B�u�D�܂����Ȃ��Љ�I��������N���邨����̂�����́v�Ƃ��āA�u�ە���̎����ɂ��Ă̕E�L�^�v�u�ە���g�p�̋^�������������́v���u�E�o�v�̑ΏۂƂ���Ă���B�u�E�o�v�Ƃ́A�R����c�̐R���ɂ����邱�Ƃ��Ӗ����邪�A�c��Ȏ����̂Ȃ�����A�Y�����镔�����`�F�b�N����̂ł���B
�@��T�i�l�́A���̑[�u�ɂ���āA�h�q��������j���ɐ��W�߂�ꂽ�����̂Ȃ��ɑ��݂���V�R�P�����E�ې�̎������`�F�b�N���āA����J�ɂ��A�ې�̎������B�������̂ł���B
�@�@(4) �P�X�W�R�N�Ɖi���ȏ�����ł̂V�R�P�����L�q�폜
�@�P�X�W�R�N�X���A�Ɖi�O�Y�́A������b�ɑ��āA�P�X�W�O�N�x�Ɍ���ς݂ƂȂ������ȏ��̋L�q���A�W�S�����ɉ������������������̐\���������B
�@���̉����̂P�ɁA�r���Ƃ��āA�u�܂��n���r���x�O�ɂV�R�P�����Ə̂���ې핔����݂��A����l�̒����l����Ƃ���O���l��߂炦�Đ��̎����������ĎE���悤�ȍ�Ƃ��\�A�̊J��ɂ�����܂Ő��N�ɂ킽���ĂÂ����v�Ə���������������������B
�@����ɑ��ĕ�����b�́A�u�V�R�P�����̂��Ƃ͌����_�ł͂܂��M�p�Ɋ�������w��I�����A�_���Ȃ������������\����Ă��Ȃ��̂ŁA��������ȏ��Ɏ�肠���邱�Ƃ͎��������ł���v�Ƃ������R�ŁA�S���폜�̏C���ӌ���t�����B���̂��߁A�Ɖi���͂��̕�����S���폜����������Ȃ������B
�@�W�@�P�X�X�O�N��̐^���\�I�Ɣ�T�i�l�̉B���s��
�@�@(1) �ې�̐^���\�I���}���ɐi��
�@�P�X�X�O�N��ɓ���A��U�͂ŏڏq�����Ƃ���A�ې�̐^���\�I���}���ɐi�B
�@�����ɂ����ẮA�P�X�W�X�N�ɁA�w�ې�^�ŋC��x�����s����A�X�O�N��ɓ����āA�\�A����ɔ��������J�ŁA���V�A�̍����������فi�����Y�}�����فj�Ɠ��ʌ������فi���j�f�a�����فj����A�n�o���t�X�N�ٔ��̋N�i�������ʁA�y�ы����{�R���O�]�������̕�����������A�V�R�P�����ɂ��l�̎����̋]���҂̎��������������B
�@���{�ł́A�P�X�W�X�N�V���A�����s�V�h��ˎR�̋����{�R�R��w�Z�Ւn����A�P�O�O�̈ȏ�̐l������������A�l���ۑ��̊č���������ɒ�o�����B�P�X�X�R�N�V������́A�V�R�P�����W����悳��A�S��������E�J�Â��ꂽ�B
�@�������Ȃ���A���̂悤�ɍې�̎������\�I����A�B���s�ׂ��j�]�����ɂ�������炸�A��T�i�l�́A�V���Ɉ����ȉB���s�ׂ��s�����B
�@�@(2) ��{�Ɩ������̔����E���\�Ɣ�T�i�l�ɂ�����J�[�u
�@�P�X�X�R�N�A�g���`��������w������ɂ���āA�h�q���h�q�������}���قɂ����āA�푈�����A�Q�d�{�����ۈ��Ƃ��āA�ې���{�ɂ��ĘA�������Ɋ֗^���A���̍��̌o�܂��ڂ����L������{�F�j�卲�̋Ɩ��������S�̋Ɩ���������������A�P�X�X�R�N�P�Q���Ɂw�G���E�푈�ӔC�����x�Q���i�b�P�j�ɔ��\����A����ɁA�P�X�X�T�N�P�Q���ɂ́A��g�u�b�N���b�g����w�V�R�P�����ƓV�c�E���R�����x�i�b�Q�j�����s���ꂽ�B
�@���̈�{�������̔����ɂ���āA���͂���{�R�̍s�����ې�͓����������������Ƃ��Ċm�肵�A�܂���T�i�l���V�R�P�����y�эې�Ɋւ��鎑����ۗL���Ă��邱�Ƃ��A�ے肷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ƂȂ����B
�@�������A��T�i�l�́A��{�������g�������炪����������A�����������J�[�u�Ƃ��A�����čې�̎����̉B�����p�������B
�@�@(3) �V�R�P�����̊�����F�肵���ō��ٔ����������B���s��
�@�P�X�X�V�N�W���A�ō��ٔ����́A�P�X�W�R�N�̌��菈���𑈂����Ɖi���ȏ��ٔ��ŁA�ې��ړI�ɂ��Ă����V�R�P�����̑��݂�F�肵���B���̍ō��ٔ����́A�s���{�A���@�{�ɑ��A�ې�̒������`���Â��Ă����Ƃ�����B��������T�i�l�́A���̌�̍���قȂǂł��A�B���𑱂��Ă���B
�@�@(4) �R���Ԉ��w�A�ŃK�X���̐푈�ƍ߂ɑ���Ӎ߁E�����ɋt�s����ې�B��
�@��T�i�l���{�́A�P�X�X�O�N��ɓ���ƁA�R���Ԉ��w���A����ŃK�X������̐푈�ƍ߂ɑ��钲�����s���悤�ɂȂ�B
�@�R���Ԉ��w���ɂ��ẮA�P�X�X�Q�N�V���U���A���{�̑�P���������ʂ����\����A�P�Q�V���̎��������\���ꂽ�B����ɂP�X�X�R�N�W���S���A��Q���������ʂ����\����A�͖슯�[�����k�b�����\����A�R�̊֗^��F�߂��̂ł���B
�@�܂��A�ŃK�X������ɂ��Ă��A���{�͑Ή�����ς����Ă���B�ŃK�X������ە���Ɠ��l�ɋɓ����یR���ٔ��ł͍ق��ꂸ�A��㒷���Ԗ��Ƃ���邱�Ƃ��Ȃ������B
�@�P�X�X�Q�N�Q���̃W���l�[�u�R�k��c�ł̉��w����֎~���̌����A�����������{�R�������嗤�Ɉ�����Ă����ŃK�X����̏�������{���{�ɗv�����A������w����̏����`�������ɐ��荞�ނ悤��Ă����B����������ĂP�X�X�R�N�ɉ��w����֎~���������A�������n�ɂ�����{�i�I�������J�n������Ȃ��Ȃ����Ƃ�����B
�@�������Ȃ���A��L�̂悤�Ȑ푈�ƍ߂ɂ��Ă̒����A�e��̌���A��Q�⏞�����J�n������钆�ł��A�ې�̎����ɂ��ẮA��T�i�l�͓��ɓO�ꂵ�Ă�����B�����悤�Ƃ��Ă���B
�@���̂��Ƃ��Ӗ����Ă���̂́A�푈�ƍ߂̒��ł��A�ې�̎��������ɂ��킾���Ďc�s�ł��邱�ƁA��Q�̋K�͂��傫���A�N�Q�ԗl���[���ł���Ƃ������Ƃł���B
�@�@(5) �P�X�X�V�N����قł̔�T�i�l�̉B���s��
�@�V�R�P�����̍ې�̎����𖾂��i�݁A�푈��Q�ւ̎����������s���钆�ŁA�P�X�X�V�N�P�Q���Ȃ����P�X�X�X�N�Q���A�S��̍���₪�s��ꂽ�i�b�R�V�Ȃ����b�R�X�A�b�P�Q�X�j�B
�@��T�i�l�̑Ή��́A�u�������Ȃ�����킩��Ȃ��v���A��������ɏI�n���Ă���B�܂��A���̍����ŁA��T�i�l���V���ȉ��Q�s�ׂƂ��ĉB���𑱂��Ă���Ƃ������������炩�ɂȂ����B
�@�@�u�V�R�P�����̊��������������͂Ȃ��v�Ƃ�����T�i�l����
�@�V�R�P�����Ɋւ��鎑���ɂ��āA�u����܂ł̐��{�����̒����ł͐��{�ۑ��̕������ɂ�����V�R�P�����̊��������������͌������Ă��Ȃ��v�i�P�X�X�W�N�S���Q���������[�������فA�b�S�O�j�A�u��̓I�Ȋ����₲�w�E�̐��̎����Ɋւ��鎖�����m�F�ł��鎑���͊m�F����Ă��Ȃ��v�i�P�X�X�X�N�Q���P�W����C�c�h�q�������A�b�P�Q�X�j�Ƃ����̂��A��T�i�l�̓��قł���B
�@�������A��{�������S�̋Ɩ������̑��݂ɂ���āA�u�V�R�P�����̊����ɂ��Ă̎����͂Ȃ��v�ƌ����Ă�����T�i�l�̍���ق����U�ł��邱�Ƃ͖����ł���B
�@��T�i�l�͌��݂܂ň��ӂ���B���s�ׂ��s���Ă������߁A��L�̂悤�Ȕj�]�������ق����āA�ӔC�Njy��悤�Ƃ��Ă���̂ł���B
�A�@��{�����Ɋւ���u��m�[�R�����g�v�Ƃ�����T�i�l����
�@���̈�{�����̑��݂ɂ��ẮA�X�W�N�S���V���̍����łƂ肠����ꂽ�B��T�i�l����{�����̑��݂�m���Ă������Ƃ͖��炩�ł��邪�A�u�m���Ă���v�Ƃ��u�m��Ȃ��v�Ƃ��������A�P�X�T�X�N�ȗ����炪�ێ����w��j�p���x�Ҏ[�Ɋ��p���Ă����������u�l�̓����v���Ƌ��ق��A�u�R�����g�͂��Ȃ��v�Ɖ����ۂ��Ă���̂ł���B
�@��T�i�l�́A�����u�����͂Ȃ��v���ق��Ă����ɂ�������炸�A��{�����̑��݂ɂ��Ắu��m�[�R�����g�v�Ƃ����Ή������Ă���B
�@���̂悤�ɁA��T�i�l�͎����̑��݂����A�ӔC��������悤�Ƃ���ԓx�ł���B����́A��T�i�l���ې�̎�����O��I�ɉB�����悤�Ƃ���ӎv�̕\��ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�B�@�n�b�`���[�،��i�A�����J����̕ԊҋL�^�j�ے�̔�T�i�l����
�@�P�X�W�U�N�A�����J�̉��@������Ŗ��炩�ɂȂ����A�u�V�R�P�֘A�����͂P�X�T�O�N�㖖���P�X�U�O�N�㏉�߂ɔ��l�߂ɂ��ē��{�ɑ���Ԃ����v�Ƃ����n�b�`���[�،��ɂ��āA�X�V�N�P�Q���P�V���̍���^�łƂ肠����ꂽ�B�u���̎����͌��݂ǂ��ɕۑ����Ă���̂��v�Ƃ����I���N�q�c���̎���ɑ��āA��T�i�l�́A�u�č����Ԋ҂����S�����̎����v��ʂ̘b���ɂ��肩���A����ɁA�u�i�n�b�`���[�،��ɂ��āj���،��ł͕č����V�R�P�����Ɋւ��鎑���ł��邱�Ƃ��m�F���������œ��{���ɕԊ҂����|���q�ׂĂ���킯�ł͂Ȃ����̂Ǝ��ǂ��͏��m���Ă���܂��B�v�i�b�R�X�j�Ƃ��ăn�b�`���[�،����̂�ے肵�Ă��܂��Ă���̂ł���B
�C�@�V�R�P�����̊������e�f��͍���Ƃ�����T�i�l����
�@�V�R�P�����̐푈�ƍ߂̎����ɂ��āA��T�i�l�́A�u�����_�Ő��{�Ƃ��Ă�����V�R�P�����̋�̓I�Ȋ������e�ɂ��Ēf�肷�邱�Ƃ͍���ƍl���Ă���v�i�X�W�N�S���V���������[�������فA�b�S�P�j�Əq�ׂĂ���B
�@�������A��{�����̑��݂ɂ��ẮA�u�ԓ��ɍ������v�Ɠ�����ȂǁA���̓��ق͖��炩�ɔj�]���Ă���B
�@�X�@�܂Ƃ�
�@�ȏ�̂Ƃ���A��T�i�l�́A����s�������ۖ@�ᔽ�̍ې�ɂ��āA����т��ĉB���������Ă���B
�@��T�i�l�́A�{���B���s�ׂ��A���Ƃ��������g�D�I�Ȑ푈�ƍ߂Ɋւ���؋��B�ōs�ׂƂ��ĊJ�n���A������т��āA��L�Ɠ��l�̖ړI�̉��ɁA�ې���͂��߂Ƃ���ې핔���̊�����ϋɓI�ɉB������s�ׂ��p�������B
�@���̂悤�ɁA���j�I�o�܂Ɋӂ݂�A��T�i�l�ɂ��{���B���s�ׂ͋��łȉB���ӎu�Ɋ�Â����ƓI��ׂ��̂��̂ł���ƕ]��������B
�@��T�i�l�̉B���s�ׂ́A���j�I�e�����ɂ����č�ׁE�s��חl�X�ȑԗl��悵�Ă�����̂́A��ɖ��m�ȉB���ӎv��������̂ƔF�߂���B
�@���̂悤�Ȍ̈ӂɊ�Â���ׁE�s��ׂ̉B���s�ׂ��A�T�i�l���Q�҂̑��Q�����������̌����s�g��W�Q���V���ȑ��Q��^�������Ă����̂ł���B�@���̂��Ƃ��A���݂Ɏ���܂ŏd��Ȑl���N�Q�������炵�A�T�i�l��̐l�ԂƂ��Ă̑����������Ă���B�B���ɂ�錠���s�g�W�Q���Ȃ��ꂽ���Ƃɂ���āA�T�i�l��͎��Ԃ��̂��Ȃ��قǂ̏d��ȑ��Q��ւ����B
�@�܂��A�{����i�����T�O�N�ȏ�o�߂����P�X�X�V�N�ɂȂ��ď��߂čs��ꂽ�Ƃ��������́A��T�i�l�ɂ��B���s�ׂ��A�̈ӂɊ�Â��g�D�I�ň����Ȃ��̂ł��������Ƃ��������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@
��S�@���_
�ȏ�̂悤�ɁA��T�i�l�̉B���s�ׂ́A�T�i�l��̑O�q���������s�g��W�Q����Ƌ��ɁA�T�i�l��ɐV���ȋꂵ�݂�^���A�T�i�l��̏d��Ȗ@�I���v��N�Q���A����ȑ��Q��^�����B�ې�ɂ�鑹�Q�́A�����g�̓��ւ̒��ړI�ȐN�Q�ɂƂǂ܂�Ȃ��B���݂Ɏ���܂ōۂ̋��|�͎��܂炸�A�܂��A�����K�ȗ��@���ɂ���^�ҋ~�ς�ӂ��Ă������Ƃɂ��A������͌��݂܂Ōp�����Ĕ��Ȑ��_�I��ɁA�l�i���ւ̐N�Q���Ă����̂ł���B
�@�܂��A�ې��Q�҂́A�l�X�ȎЉ�I�]���̒ቺ�Ƃ������_�N�Q�������B���̖��_�N�Q�Ƃ�����Q�́A���̍R���푈�ɂ��펀�҂╉���҂Ƃ͈قȂ���ʂȕs���v�ł���B���̂悤�Ȗ��_�N�Q�̔�Q�́A��T�i�l����㑬�₩�ɐ^���𖾂炩�ɂ��A�K�ȎӍ߂Ɣ��������s���Ή����ꂽ���̂ł��邪�A��T�i�l���ې�̎������B���������Ƃɂ���āA���_�N�Q�͌p������A�ނ���t�ɍT�i�l��̋�ɂ͔{�������B
�@�ȏ�̂悤�ȍT�i�l��̔�������_�N�Q�́A���Q�����݂̂Ȃ炸�A�^���ȎӍ߂������Ă����A���߂ĈԎӂ������̂ł���B
�@
 � �
�@
��W�́@�T�i�l��̐���
��P�@�Ӎߐ���
�@�ې�ɂ�鑹�Q�́A�����g�̓��ւ̒��ړI�ȐN�Q�ɂƂǂ܂�Ȃ��B���݂Ɏ���܂ōۂ̋��|�͎��܂炸�A�܂��A�����K�ȗ��@���ɂ���^�ҋ~�ς�ӂ��Ă������Ƃɂ��A������͌��݂܂Ōp�����Ĕ��Ȑ��_�I��ɁA�l�i���ւ̐N�Q���Ă����̂ł���B
�@�܂��A�ې��Q�҂́A�l�X�ȎЉ�I�]���̒ቺ�Ƃ������_�N�Q�������B���̖��_�N�Q�Ƃ�����Q�́A���̍R���푈�ɂ��펀�҂╉���҂Ƃ͈قȂ���ʂȕs���v�ł���B���̂悤�Ȗ��_�N�Q�̔�Q�́A��T�i�l����㑬�₩�ɐ^���𖾂炩�ɂ��A�K�ȎӍ߂Ɣ��������s���Ή����ꂽ���̂ł��邪�A��T�i�l���ې�̎������B���������Ƃɂ���āA���_�N�Q�͌p������A�ނ���t�ɍT�i�l��̋�ɂ͔{�������B�ȏ�̂悤�ȍT�i�l��̔�������_�N�Q�́A���Q�����݂̂Ȃ炸�A�^���ȎӍ߂������Ă����A���߂ĈԎӂ������̂ł���B
�@���������āA�T�i�l��͔�T�i�l�ɑ��A�Ӎ߂𐿋�����i���@�V�Q�R���܂��͍��Ɣ����@�S���܂��͒��ؖ������@�P�X�T���j�B
��Q�@���Q��������
�@�T�i�l��́A�펞���̔�T�i�l�̍ې�ɂ���Ĕ�������_�I��ɂ����K�ɕ]������ƁA���ꂼ��e�P�O�O�O���~������Ȃ��B
�@�܂��A�T�i�l�炪��T�i�l�̗��@�s��ׂɂ���Ĕ�������_�I��ɂ����K�ɕ]������ƁC���ꂼ��e�T�O�O���~������Ȃ��B�T�i�l�炪��T�i�l�̍s���s��ׂɂ���Ĕ�������_�I��ɂ����K�ɕ]������ƁA���ꂼ��e�T�O�O���~������Ȃ��B����ɁA�T�i�l�炪��T�i�l�̉B���s�ׂɂ���Ĕ�������_�I��ɂ����K�ɕ]������ƁA���ꂼ��e�T�O�O���~������Ȃ��B
�@�����ŁA�T�i�l��́A��ʓI�ɁA��Q�͂����S�͂���уn�[�O�������R���Ȃ�тɍ��ۊ��K�@�Ɋ�Â������i���̓_�Ɋւ��ẮA����A��Q�������ʂɂ����Ď咣����j�����A�\���I�ɑ�T�͂����V�͋L�ڂ̊e���������A��T�͂����V�͂̊e�����͕���I�Ɏ咣����B
�@����āA�T�i�l��́A�T�i�l�炪��������Q�ɂ��āA��Q�͂����S�͋L�ڂ̐�������уn�[�O�������R���Ȃ�тɍ��ۊ��K�@�Ɋ�Â������Ɋ�Â��e���P�O�O�O���~�����ꂼ�ꐿ�����A�܂��\���I�ɁA��T�͋L�ڂ̐����Ɋ�Â����T�O�O���~�Ƒ�U�͋L�ڂ̐����Ɋ�Â����T�O�O���~�Ƒ�V�͋L�ڂ̐����Ɋ�Â����T�O�O���~�Ƃ̍��v�̓��e���P�O�O�O���~���A���ꂼ�ꐿ������i���@�V�O�X���Ȃ����V�P�P���܂��͂V�P�T���A�܂��͍��Ɣ����@�P���܂��͒��ؖ������@�P�W�S���A�P�W�T���A�P�W�W���A�P�X�S���j�B
��R�@����
�@���`�̔�����ǂ����K�͐ςݏd�˂�ׂ��ł���A�l���ƕ��a����Ƃ��錛�@���ɂ���ٔ����͂��̐ςݏd�˂ɋ��͂���̂��g���ł���B�ςݏd�˂ɂ���Ċ��K�@����������ȏ�A�ςݏd�˂�������ɉ��ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�ٔ������k��ɋ����̖@���߂ɌŎ�������@�̌����Ă��邱�Ƃ𗝗R�ɂ����肵�Đ��`�̔��������ނƂ���A����͂܂��Ɂu�i�@�s��ׁv�ł���B�s���A���@�A�i�@�̎O�����A��������悤�ɕs��ׂ𑱂��A���͊Ԃ݂̔������ɂ���Đ��`����ڂ�w����悤�Ȍ�����A�����č��ێЉ�͂��܂ł������͂��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@��

|