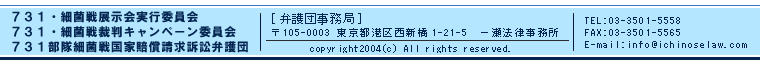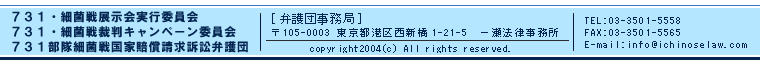|
|
�Q�O�O�Q�N�i�l�j��S�W�P�T���Ӎߋy�ё��Q���������T�i����
�T�i�l�i��R�����j ���@�G�@�Ł@�@�O�P�V�X��
��T�i�l�i��R�퍐�j�@���@�{�@��
�@�@�@�@�@�@�@
��Q��������
�Q�O�O�R�N�V���R�P��
���������ٔ�����Q�������@�䒆
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�i�l��i�ב㗝�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ٌ�m�@�@�@�y�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@��@�@�@���@�@�@�@�h�@��@�Y
�� �@�@�@�S�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@��
�� �@�@�@���@�@�@���@�@�@�@���@�@�@��
�� �@�@ �� �@�@�@�c �@�@�@�@�@�@�@�@��
���@�@�@�Ł@ �@�@��@�@�@�@�G�@�@�@�V
���@�@�@���@�@ �@��@�@�@�@��@�@�@��
���@�@�@���@ �@�@�c�@�@�@�@�q�@�@�@��
���@�@�@�r�@ �@�@�c�@�@�@�@���@�@�@�q
���@�@�@�ہ@ �@�@��@�@�@�@�p�@�@�@�O
���@�@�@���@�@�@ ��@ �@�@�@�@�@�@�@�~
�� �@�@ �R�@�@�@ �{�@�@�@�@���@�@�@��
�@
��P�� �͂��߂�
�@ �������́C�n�[�O�������R���́C�n�[�O����K���ᔽ�ɂ���đ��Q�������l�����Q���Ƃɑ��Ē��ڑ��Q�����������邱�Ƃ܂ł�F�߂����̂ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@�������Ȃ���C�������̂��̉��߂́C���炩�ɓ����̉��߂���������̂ł���B�ȉ��ɁC�������̌����w�E���C�T�i�l�炪��T�i�l�ɑ�������R���C����т������e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�Ɋ�Â��C���Q�������𐿋����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B

��Q�́@�n�[�O����R���Ɋ�Â��Ӎߋy�ё��Q��������
��P�@�n�[�O���y�т������e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@�̐���
�P�@�u����m�@�K����j�փX�����v�i�ȉ��C�u�n�[�O���v�Ƃ����j�́C�P�X�O�V�N�I�����_�̃n�[�O�ɂ����ĊJ���ꂽ��Q��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ���ł���B�����ɂ́C����c�ɎQ�������S�S�������������C���̌��͂͂P�X�P�O�N�P���ɔ��������B���{�͂P�X�P�P�N�ɔ�y���Ă���B
�@�푈��Q�̔����Ɋւ��āC�n�[�O����R���͎��̂Ƃ���K�肷��B
�@�u��O���@�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^����퓖���҃n�C���Q�A���g�L�n�C�V�J�����m�ӔC�����t�w�L���m�g�X�B��퓖���҃n�C���m�R�����g���X���l���m��m�s�׃j�t�ӔC�����t�v
�@���̃n�[�O����R���́C��q����Ƃ���C�R���\�������푈�@�K�Ɉᔽ����s�ׂ������Ȃ����ꍇ�ɁC���̔�Q�Ҍl���C���Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋����錠�����߂����̂ł���B
�Q �n�[�O������e�Ƃ���̍��ۊ��K�@�̐���
�@(1) �Ƃ���Ńn�[�O���́C���蓖�����łɍ��ۓI���K�Ƃ��Đ��E�e���ŏ��F����Ă������e�����ɂ������̂ł���C��P��n�[�O���ۉ�c�̎Q���������鐢�E�̎�v�ȂS�S�������Q���������ۓI�ȕ��a��c�̑���ɂ����đS����v�ō̑����ꂽ���ł���B�܂��C���E�e���́C�n�[�O���̐���ȍ~�C�����̏����\�������Έӎv��\�����鍑���Ȃ��C�������̓��e�͌����ɗ��s����Ă����B����ɁC�����Ɉᔽ����s�ׂ��푈�ƍ߂��\�����邱�Ƃ͍��ۓI�ɏ��F����Ă����B���{���C��y��̑�ꎟ���E���ɎQ�킷��Ƃ��C�����̏����\������Ɠ����Ɋe���ɂ��̗��s��v�������B
�@�ȏ�̎�������C�n�[�O���̓��e���C�x���Ƃ����̌��͔������ȍ~�C���ۊ��K�@�Ƃ��Ă��������Ă������Ƃ͖��炩�ł���B
(2) ���̓_�͌��������C�u�x���Ƃ����̂���܂Łi�P�X�P�P�N�P�Q���P�R���ɂ킪���������Ɋւ����y����������������j�ɂ͑����̍��Ƃ̍s�Ԃ̒��ɓ����ɑ���@�I�m�M���m�F�����Ɏ���C�����ē�������e�Ƃ��鍑�ۊ��K�@���������Ă������̂ƔF�߂�̂������ł���B�v�Ƃ��Ă���B
(3) ���������ăn�[�O����Q���ɂ́C�u�����j�f�P�^���K���y�{���m�K��n�C��퍑�J���N�{���m�����҃i���g�L�j�����C���ԃj�m�~�V���K�p�X�v�Ƃ����鑍��������������C��Q�����E����퍑���ɂ͓�����������Ă��Ȃ��������݂��Ă������C���̏����̌̂Ƀn�[�O���̓K�p���r���������̂ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ́C�j���[�����x���O���یR���ٔ����y�ыɓ����یR���ٔ����ɂ����Ă���������Ă���C�^��̗]�n�͂Ȃ��Ƃ���ł���B
��Q�@�ې�̗���K���ᔽ
����K�����C�ې�ɂ��ẮC������Q�R�����W����B���̂P���{���́C���̂Ƃ���K�肷��B
�@�u���O���ꍀ�@���ʃm��ȃe�胁�^���֎~�m�O�C���j�֎~�X�����m���m�@�V�v
�@���̋֎~�����̊e�����C�C���ƃz���͎��̂Ƃ���ł���B
�@�C�� �u�Ŗ��n�Ń��{�V�^�����탒�g�p�X���R�g�v
�@�z�� �u�s�K�v�m��Ƀ��^�t�w�L����C���˕����m���m�������g�p�X���R�g�v
�@�Ƃ���ŁC�ە���́C�ۂ̂����͂ȓŗ͂Ɗ������ɂ��C�l�Ɋ������l�̂ɒv���I�ȑ�����^���邱�Ƃ���}��������ł��邩��C�O�L�C���ɊY������B�܂��C�ە���́C�L�͂Ȑl�X�ɑ��Ē����ɂ킽���Ĉ����ȓ`���a�𖠉������āC��ɂ������炷���̂ł��邩��C�O�L�z���ɂ��Y������B
�@����C�ې�́C�P�X�Q�T�N�U���ɏ������ꂽ�u�������K�X�C�Ő��K�X���͂����ɗނ���K�X�y�эۊw�I��i�̐푈�ɂ�����g�p�̋֎~�Ɋւ���c�菑�v�i�ȉ��C�u�W���l�[���c�菑�v�Ƃ����j�ɂ����Ă��֎~����Ă����B
�@���Ȃ킿�C�u���̋֎~���ۊw�I�푈��i�̎g�p�ɂ��Ă��K�p����v�Ɩ����ōې�͋֎~���ꂽ�B
�@�W���l�[���c�菑�ɂ��ẮC����ɔ�����ӎv��\�����鍑�Ƃ��Ȃ��C�e�����ە�����g�p���Ȃ����Ƃ͌����Ɏ���C���ە���̎g�p���푈�ƍ߂��\�����邱�Ƃ͍��ۓI�ɏ��F����Ă����B���������ăW���l�[���c�菑�́C�x���Ƃ����ꂪ���������P�X�Q�W�N����ɂ́C���ۊ��K�@�Ƃ��Ă��m�����Ă����B���{���{���C���c�菑�ɐ��蒼��ɏ������Ă���i�������C��y�����̂͂P�X�V�O�N�j�C���c�菑�����ۊ��K�@�̐������Ă��邱�Ƃ��[���ɔF�����Ă����B
�܂��C����K����Q�T���́C�u�h��Z�T���s�s�C�����C�Z��n�����n�C�@���i����i�j�˃����C�V���U�����n�C���X���R�g�����Y�v�Ɩh�炳��Ȃ��s�s�̍U�����֎~���Ă��邪�C�{���ې킪����Ɉᔽ���Ă��邱�Ƃ������ł���B
�@����Ĕ퍐�����s�����{���ې�́C����K����Q�R���P���C���y�уz���C����Q�T���Ɉᔽ����Ɠ����ɁC�P�X�Q�T�N�̃W���l�[���c�菑�ɂ��ᔽ���C���炩�ɐ푈�@�K�ᔽ�ł���B
��R�@�n�[�O����R�����F�߂锅���������̋A�����
�@�P�@�n�[�O����R���́C��퓖���҂��푈�@�K�Ɉᔽ����s�ׂ��Ȃ������Ƃɂ��l�ɑ��Q��^�����ꍇ�ɂ́C���Q���͔�Q�Ҍl�ɑ����ڂ̑��Q�����ӔC�����Ƃ�F�߂����̂ł���Ƃ����ׂ��ł���B�ȉ��ڏq����i�n�[�O���̉��ߑS�ʂɂ��Ă͍b�S�Ȃ����W���؎Q�Ɓj�B
�@�Q�@�n�[�O����R���̎�|�́C�R���\�����Ƀn�[�O�K�������炳���邽�߂ɂ́C�P�߈ᔽ�𗝗R�Ƃ���R���Y���@�K�ɂ�鏈�������ł͕s�\���ł���Ƃ̍��{�I�ȔF���ɗ����āC�K���ᔽ�s�ׂɂ���Čl�ɐ��������Q�ɂ��ẮC��Q�Ҍl�����Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋��ł��邱�ƁC����сC���̌l�̑��Q���������ɑ��C���Q���́C�w�����ߌn���̊Ǘ��E�ē̉ߎ��������Ă��C���ߎ��̐ӔC�S���邱�Ƃ����ۖ@�̖����ŋK�肵�āC�R���\�����Ƀn�[�O�K�������O�ꂳ���悤�Ƃ������̂ł���B���̂悤�ɓ�����R���́C�R���\�������s�����n�[�O�K���ᔽ�s�ׂɂ��āC���@��̕s�@�s�ׂɊւ���g�p�ҐӔC�Ɩ��ߎ��ӔC�̍l�������C���Q���ɓK�p���悤�Ƃ�����̂ł������B�@
�@���������āC�n�[�O����R�����C�R���\�������푈�@�K�Ɉᔽ����s�ׂ������ꍇ�ɁC���̔�Q�Ҍl���C���Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋����錠�����߂����̂ł��邱�Ƃ͖����ł���B
�@�R�@���̉��߂́C�n�[�O����R���̐���o�߂ɏƂ炷�ƁC��w���炩�ł���i�n�[�O���̐���ߒ��ɂ��Ă͍b�S���C�b�Q�P�U���؎Q�Ɓj�B
�@(1) �n�[�O����R���́C����P�W�X�X�N����̋��n�[�O���y�т��̕����K�����C�����Đ��肳�ꂽ�ۂɁC�V���ɑn�݂��ꂽ�K��ł���B���n�[�O���ɂ́C�푈��Q�̕⏞�Ɋւ��鍑�Ƃ̐ӔC���߂��K��͂Ȃ������B�����t���K���ɐ�̌R���s������Z�����璥����ۖ������ꍇ�ɂ��āu����ׂ������ɂĎx�����C�R�炴��Η̎����ȂĔV���ؖ����ׂ��v�i�T�Q���j�Ƃ��C��̌R�����l����R���i�����������ꍇ�ɂ��āu���a�Ɏ���C�V���ҕt���C���V�����������肷�ׂ����̂Ƃ��v�i�T�R���j�ƒ�߂Ă��������ł������B
�@(2) �����łP�X�O�V�N�̑�Q��n�[�O���a��c�ŁC�h�C�c��\���C��̒n����O�ɂ����Ď����R���̍\�������n�[�O���̕����K���ᔽ�s�ׂ��Ȃ����ꍇ�C���̌�퍑���L�ӂł��邱�Ƃ�F�߁C���̋K���ᔽ�s�ׂɂ�葹�Q�����l�ɑ��ē��Y��퍑�����������邱�Ƃ�v�����āC�n�[�O���Ɏ��̂Q�̏�lj����邱�Ƃ��Ă����B
�@�u��đ�P���@�t���K���̏����Ɉᔽ���Ē����̎҂�N�Q������퓖���҂́C���̎҂ɑ��Đ��������Q�����̎҂ɑ��Ĕ�������ӔC���B��퓖���҂́C���̌R����g������l���̈�̍s�ׂɂ��ӔC���B
�@�����ɂ�鑦���̔������\�肳��Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ����āC��퓖���҂����������Q�y�юx�����ׂ������z�����肷�邱�Ƃ��C���ʌ��s�ׂƗ������Ȃ��ƌ�퓖���҂��F�߂�Ƃ��́C�E������������邱�Ƃ��ł���v
�@�u��đ�Q���@�t���K���̏����Ɉᔽ�����s�ׂɂ���푊�葤�̎҂�N�Q�����Ƃ��́C�����̖��́C�a���̒������ɉ���������̂���v
�@(3) �E��Ă̗��R�Ɋւ��āC�h�C�c��\�́C���̂悤�Ȏ�|����������B
�@�u����̖@�K����Ɋւ���K���̈ᔽ���s��ꂽ�ꍇ�̋K���t�����邱�Ƃɂ��C���K����⊮���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���h�C�c��Ă̗��R���ȒP�ɐ����������B
�@����̖@�K����Ɋւ�����ɂ��C�e�����{�́C�����t���̋K���ɏ]�����w�߂����̌R���ɑ��ďo���ȊO�̋`����Ȃ��B�����̋K�肪�R���ɑ���w�߂̈ꕔ�ɂȂ邱�Ƃɂ��݂�C���̈ᔽ�s�ׂ́C�R�̋K�������Y�@�ɂ�菈�f�����B�������C���̌Y�����������ł́C������l�̈�@�s�ׂ̗\�h�[�u�Ƃ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͖����ł���B���K���̋K��ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́C�R�̎w���������ł͂Ȃ��B�m���C���m���C�ꕺ���ɂ��K�p����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āC���{�́C���炪���ӂɏ]���Ĕ������P�߂��C�펞���C��O�Ȃ����炳��邱�Ƃ�ۏႷ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B
�@������ɂ����āC���K���̋K��̈ᔽ�s�ׂɂ�錋�ʂɂ��āC�������Ă����ׂ��ł���B
�@�w�̈ӂɂ�邩���͉ߎ��ɂ�邩���킸�C��@�s�ׂɂ�葼�l�̌�����N�Q�����҂́C����ɂ�萶�������Q������`�������̑��l�ɑ��ĕ����B�x�Ƃ̎��@�̌����́C���ۖ@�́C���c�_���Ă��镪��ɂ����Ă��Ó�����B�������C���Ƃ͂��̊Ǘ��E�ē̉ߎ���������Ȃ�����ӔC��Ȃ��Ƃ����ߎ��ӔC�̖@���ɂ��Ƃ���̂ł͕s�[���ł���B���̂悤�Ȗ@�����Ƃ�ƁC���{���g�ɂ͉��̉ߎ����Ȃ��Ƃ����̂��قƂ�ǂł��낤����C�t���K���ᔽ�s�ׂɂ�葹�Q�����҂����{�ɑ��Ĕ����𐿋����邱�Ƃ��ł��Ȃ����C�L�ӂ̎m�����͕����ɑ����Q�������������ׂ��ł���Ƃ��Ă��C�����̏ꍇ�͌����ɂ͔����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤�B
�@���������āC�����́C�R����g������҂��s�����K���ᔽ�ɂ���̕s�@�s�אӔC�́C�R����ۗL���鍑�̐��{�������ׂ��ł���ƍl����B
�@���̐ӔC�C���Q�̒��x�C�����̎x�������@�̌���ɂ������ẮC�����̎҂ƓG���̎҂ŋ�ʂ����C�����̎҂����Q�����ꍇ�́C���s�ׂƗ�������ł��v���ȋ~�ς��m�ۂ��邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u����ׂ��ł��낤�B����C�G���̎҂ɂ��ẮC�����̉�����a���̉̂Ƃ��܂ʼn������邱�Ƃ��K�v�s���ł���B�v
�@(4) �R�c�ł́C�E�̃h�C�c��Ă̔�Q�Ҍl�����Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋��ł��C���Q���͖��ߎ��̐ӔC���Ƃ�����{�I���e�ɂ͑S�Q�����Ɉ٘_�͂Ȃ��C���V�A��X�C�X�̑�\���^���̔����������B
�@����C�������̎s���ƌ�퍑�̎s���Ƃŏ��Ă����_�ɂ��ăt�����X��C�M���X���玿�₪���������C�h�C�c��\�̒�Ă̎�|�́C�������̎s���ƌ�퍑�̎s���Ƃ̊Ԃő��Q�����ɂ��ċ�ʂ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��C�B�ꔅ���̎x�����@�ɂ��Ă����Ⴂ��݂������̂������B
�@(5) ���ǁC�R�c���s�����n�[�O���a��c�̑��ψ���́C��̃h�C�c��\�̒�Ē��̎��ł����đ�P���̕�������{�ɂ��āC��͒������ƌ�퍑�Ƃ���ʂ��Ȃ��`�ŁC���̂悤�ȋK��ɂ܂Ƃ߂��B
�u�{�K���̏����Ɉᔽ�����퓖���҂́C���Q���������Ƃ��́C���Q�����̐ӔC���B��퓖���҂́C���̌R����g�D����l���̈�̍s�ׂɂ����̐ӔC���v
�@����́C�E�̋K���S���v�ō̑������B�N���ψ���́C��������̕t���K���ł͂Ȃ��C���{���ɒu���ׂ��ł���Ƃ��C�n�[�O���̑�R���Ƃ��ꂽ�K�肪����őS���v�ō̑�����C�O�L�n�[�O����R���̋K��ƂȂ����B
�@���̂悤�ɁC�n�[�O����R�����C���̐R�c�ߒ�������C����K���ᔽ�s�ׂɂ���Čl�ɐ��������Q�ɂ��ẮC��Q�Ҍl�����Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋��ł��邱�Ƃ��߂����̂ł��邱�Ƃ͖����ł���B

��R�� �������̖@�߉��߂̌��
��P�@������
�P�@��L�̒ʂ�C�n�[�O����R�����C����K���ᔽ�s�ׂɂ���Čl�ɐ��������Q�ɂ��ẮC��Q�Ҍl�����Q���ɒ��ڂɑ��Q�����𐿋��ł��邱�Ƃ��߂����̂ł��邱�Ƃ͖����炩�ł���B
�@������ɁC�������́C�n�[�O����R���́C�l�ɑ��Q���������̎�̂�F�߂����̂ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@���̗��R�Ƃ���Ƃ���́C���悻���̒ʂ�ł���B
�@�@�@�@���ۖ@��̖@��̐���F�߂���̂͌����Ƃ��č��Ƃł���C�l�́C���ۖ@�ɂ����Ă��̌����`���ɂ��ċK�肳��C���C�l���g�̖��ɂ����č��ۓI�ɂ��̌������咣�����鎑�i���^�����ď��߂ė�O�I�ɍ��ۖ@��̖@��̐����F�߂���B
�@�@�A�@�l�������̍��ۈ�@�s�ׂɂ���đ��Q�����ꍇ�ɂ́C���Y�l�͉��Q���̍��ېӔC��Njy���邽�߂̍��ې������o�������̂Ƃ��Ă͔F�߂�ꂸ�C���̌l�̑�����{�����C���Y�l�̎��������グ�O��ی쌠���s�g���邱�Ƃɂ���āC����ɑ���@�I�ȐN�Q�Ƃ��Ĉ����C���ƊԊW�ɐ�ւ��đ��荑�i���Q���j�ɍ��ƐӔC��Njy������̂Ɖ�����Ă���B
�@�@�B�@�w�[�O������R���́C�����K���i�w�[�O����K���j�Ɉᔽ�������ɑ��Q�����ӔC���ۂ��Ă��邪�C���̑�����i���Q������������L����ҁj�ɂ��Ă̕����͑��݂��Ȃ��B
�@�@�C�@�w�[�O������y�уw�[�O����K���ɂ́C�l�����Ƃɑ��đ��Q�����𐿋����邱�Ƃ�O��Ƃ����葱�K������݂��Ȃ��B
�@�@�D�@���̂悤�ɁC�w�[�O�����l�ɐ�������F�߂閾���K���݂��Ă��Ȃ����Ƃ́C�O���̂悤�ȍ��ۖ@�̊�{�I�Ȑ��i�ɏƂ炵�Ă݂�Ȃ�C������ۖ@��̌����ǂ��荑�Ƃƍ��ƂƂ̊Ԃ̌����`�����߁C�l�̐�������F�߂����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���Ɨ�������̂����R�ł���B
�@�@�E�@�w�[�O������y�уw�[�O����K���̎�|�E�ړI�́C����ɂ����ČR���̏��炷�ׂ��������߁C�����Đ푈�̎S�Q���y�����悤�Ƃ���_�ɂ�����̂Ɖ������B
�@�@�F�@�ȏ�̏��_�ɏƂ炷�ƁC�����Ə��̎�|�E�ړI�ƂɏƂ炵�ė^������p��̒ʏ�̈Ӗ��ɏ]���ĉ��߂������C�w�[�O������R���̋K��́C�w�[�O����K���̏�������������邽�߁C���K���Ɉᔽ������퍑�̑��Q�����ӔC���߂����̂ł���C���K���ᔽ�ɂ���đ��Q�������l�����Q���Ƃɑ��Ē��ڑ��Q�������������s�g���邱�Ƃ܂ł�F�߂����̂ł͂Ȃ��Ɖ������B
�@�@�G�@�w�[�O������R���̍쐬�ߒ��ɂ����Ċe����\���Ӑ}���Ă����̂́C�w�[�O����K���̎��������m�ۂ��邽�߁C�R���\���������K���ᔽ�s�ׂ��s�����ꍇ�ɂ́C���Y�R���\�����̏������鍑�Ƃ̐��{�Ɏ�ϓI�ȗL�Ӑ����Ȃ��Ă����Y���Ƃɔ�Q�҂̑����鍑�Ƃɑ��鑹�Q�����ӔC�킹�邱�Ƃɂ���C�e�����C�����̓`���I�ȍ��ۖ@�̘g�g�݂̗�O�Ƃ��āC�l�̉��Q���Ƃɑ��鑹�Q������������n�݂��邱�Ƃ܂ł��Ӑ}���Ă������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@�@ �H�@�w�[�O����K���T�Q���R���́C�����̑�����ƂȂ����Z�����ɂȂ�ׂ������Ŏx�������Ƃ����߂Ă��邪�C��̌R�������̎x�������Ȃ��ꍇ�ɏZ�������̋~�ς����߂邽�߂̍��ۖ@��̎�i�݂͐����Ă��Ȃ�����C����������̍s�ׂ����ƊԂō��ӂ������̂Ɖ�����̂��Ó��ł���B�����̋K��������āC�l�����荑�ɑ����ډ��炩�̐����������邱�Ƃ�F�߂����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�I�@�w�[�O������ѓ�����K���ɂ́C�l�����Q���ɑ��钼�ڂ̑��Q������������L���邱�Ƃ���������K�蓙�͈�ؑ��݂��Ȃ��B
�@�@�J�@�n�[�O����R���Ɋ�Â��l��������F�߂邾���̎��s�Ⴊ���݂��Ȃ��B
�@�Q�@�������Ȃ���C�������̂����邱���̏��_�́C��������@�߂̉��߂���������̂ł���B
�@�ȉ����̗��R���q�ׂ�B
��Q�@�l�̍��ۖ@��̖@��̐�
�@�P�@�������́C���ۖ@��̖@��̐��ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@�u���ۖ@�ɂ�����`���I�ȍl�����ɂ��C���ۖ@��̖@��̐���F�߂���̂͌����Ƃ��č��Ƃł���C�l�́C���ۖ@�ɂ����Ă��̌����`���ɂ��ċK�肳��C���C�l���g�̖��ɂ����č��ۓI�ɂ��̌������咣�����鎑�i���^�����ď��߂ė�O�I�ɍ��ۖ@��̖@��̐����F�߂���Ɖ�����Ă���B�v
�@�Q�@�l�̍��ۖ@��̖@��̐��ɂ���
�@(1) �m���ɁC���������q�ׂ�悤�ɁC���ۖ@�͓`���I�ɍ��ƊԊW���K������@�ł��������Ƃ���C�l�̍��ۖ@��̖@��̐���F�߂�ɂ́C�܂����ۖ@�ɂ����Čl�̌����`���ɂ��ċK�肳��Ă��邱�Ƃ������Ƃ��ĕK�v�ł���B���̌���ŁC�������̔��f�͌��ł͂Ȃ��B
�@ (2)�@�������Ȃ���C�������͂���ɉ����āC�u�l���g�̖��ɂ����č��ۓI�ɂ��̌������咣�����鎑�i���^�����ď��߂ė�O�I�ɍ��ۖ@��̖@��̐����F�߂���Ɖ�����Ă���B�v�Əq�ׂ�B
�@���̌����́C���ۖ@���l�̌��������F���邱�Ƃ̂ق��ɁC�����N�Q�̏ꍇ�ɔ�Q�Ҍl�����ۍٔ������̋@�ւɒ�i�ł��邱�Ƃ����ۖ@��̖@��̂��邱�Ƃ̗v���Ƃ���̂ł���B
�@���������āC���̂悤�ɍ��ۓI���x���ł̌����~�ώ葱�̗L���ō��ۖ@��̖@��̐��肷��Ƃ����̂ł���C�l�͒ʏ킻�̍��ۖ@��̖@��̐���ے肳��邱�ƂɂȂ�B�������͌����I�ɂ��̗l�ȗ���ɗ����Ă���B
�@(3) �������C�������̂悤�ɁC���ۓI���x���̌����~�ώ葱���̗L���ŁC�l�̍��ۖ@��̖@��̐��f����̂͌��ł���B
�@���Ȃ킿�C���Ƃ��C�푈�ߗ��͍��ۊ��K�@�y�уW���l�[�u��̏��ɂ���č��ۖ@��̌����`���̋��L�҂��邱�Ƃm�ɔF�߂��Ă���B���̈Ӗ��ō��ۖ@��̖@��̂Ƃ��Ă̒n�ʂ����F����Ă���̂ł���i�L���P�j�w�ߗ��̍��ۖ@��̒n�ʁx���{�]�_�ЁC1990�N�C20�|21�Łj�B
�@�ߗ��l�����ۖ@��̌����`���̎�̂ł��邩�ǂ����́C���̏�ɂ��̎��̓I�����`���Ɋւ���K�肪���݂���Α����̂ł����āC����ɂ��̏�ō��ۓI�ȃ��x���ł̐������̍s�g�@��i�葱���j���^�����Ă��邩�ǂ����Ƃ͊W���Ȃ��̂ł���B
�@�܂��C���Ƃ��C���ېl���K�C�l�̌����𖾕��ŏ��F�����l�����ɂ����ẮC�����̕ێ��҂Ƃ��Ă̌l�̖@��̐��́C���ۓI�Ȏ葱�̗L���ɂ�����炸�F�߂��Ă���B
�@�܂�C�l�����̏ꍇ�C�l�͍��ۖ@��̎��̓I�����m�ɔF�߂��Ă���C���ۓI���ʂł̌��������葱����������Ă��Ȃ��Ƃ��C�e���̍����@�̐��ɏ]�������I���ʂł��̎��������߂邱�Ƃ��ł���B
�@���{�͎s���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK����y���Ă������ŁC���ۓI�Ȍl�ʕ�葱���߂����K��̑��I���c�菑�ɂ͉������Ă��Ȃ��B�@�������C����ɂ����{�̊NJ����ɂ���l�͓��c�菑��̎葱�͗��p�ł��Ȃ��ɂ��Ă��C���{�ł͍��ۏ������̂܂܍����@�Ƃ��Ď�e����̐����Ƃ��Ă���ȏ�C���{�̍����ٔ����œ��K������p���Č����̎��������߂邱�Ƃ͂ł���B���K��̋K��Ɋ�Â��Čl�̌�����F�߂�����܂ł̓��{�̑����̔���͂��ׂāC�K��Ƃ������ۖ@��̌l�̌����������I���x���Ŏ������Ă���̂ł���i�b�Q�Q�R�C�Q�Q�S���j�B
�@(4) ���̂悤�ɁC���ۖ@��̖��ɑ���NJ����́u�K���������ۍٔ������̑��̍��ۋ@�ւɐꑮ����킯�ł͂ȁv���C�u�����ꂩ�̍��̍����ٔ����ł����Ă��C���̍����@�ɂ�荑�ۖ@��̖��ɑ���NJ������^�����C�����ۖ@�ɏ������Ă��̊NJ������s�g���Ă������́C���ۊNJ����̍s�g�S���Ă���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���v�̂ł���i�R�{����w���ۖ@�i�V�Łj�x�L��t�C1994�N�C166�Łj�B
�@���������Ă��̏ꍇ�ɂ́C�����ٔ����ɂ���Ă��l�̍��ۖ@��̌����`���̎����Ǝ��s��S�ۂł���̂ł���B
�@���ǁC�l�̍��ۖ@��̖@��̐�������́C���Y���ۖ@���l�̎��̓I�Ȍ����`����F�߂Ă��邱�Ƃ���{�I�Ȕ��f��Ƃ��C�����`���̎����Ȃ����Njy�͓I�Ȓi�K�Ƃ��āC���ۓI���͍����I�@�ւ����ꂩ�Ɉς˂��Ă���̂ł���B
�@(5) ���������C���ۖ@��̌l�̖@��̐���F�߂邽�߂ɂ́C���̎��̓I�Ȍ����`���̏��F�����ł͑��肸�C���̎����̂��߂̍��ۖ@��̎葱�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����͖̂��炩�Ɍ��ł���
��R�@�l�̍��ۖ@��̑��Q���������ƊO��ی쌠�ɂ���
�@�P�@�������́C���̓_�Ɋւ��ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@�u�l�������̍��ۈ�@�s�ׂɂ���đ��Q�����ꍇ�ɂ́C���Y�l�͉��Q���̍��ېӔC��Njy���邽�߂̍��ې������o�������̂Ƃ��Ă͔F�߂�ꂸ�C���̌l�̑�����{�����C���Y�l�̎��������グ�O��ی쌠���s�g���邱�Ƃɂ���āC����ɑ���@�I�ȐN�Q�Ƃ��Ĉ����C���ƊԊW�ɐ�ւ��đ��荑�i���Q���j�ɍ��ƐӔC��Njy������̂Ɖ�����Ă���B�v
�Q�@�������Ȃ���C�������̂�������߂����ł���B���̓_�Ɋւ��ẮC��̑�X�ɂ����Ĕ��_����B
��S�@�������̃n�[�O���R���Ɋւ�����߂̌��
�@�P�@�������́C�w�[�O����R���̕����Ɍl�����Q������������ۗL���邱�Ƃɂ��ċL�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��ȂāC�����̎�|������������Â��Ȃ����̂ƕ������߂��Ă���B���Ȃ킿�C
�u�w�[�O������R���́C�w�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^����퓖���҃n�C���Q�A���g�L�n�C�V�J�����m�Ӄ����t�w�L���m�g�X�B��퓖���҃n�C���m�R�����g���X���l���m��m�s�׃j�t�ӔC�����t�B�x�ƋK�肵�āC�����K���i�w�[�O����K���j�Ɉᔽ�������ɑ��Q�����ӔC���ۂ��Ă��邪�C���̑�����i���Q������������L����ҁj�ɂ��Ă̕����͑��݂��Ȃ��B
�@�܂��C�w�[�O������y�уw�[�O����K���ɂ́C�l�����Ƃɑ��đ��Q�����𐿋����邱�Ƃ�O��Ƃ����葱�K������݂��Ȃ��B
�@���̂悤�ɁC�w�[�O�����l�ɐ�������F�߂閾���K���݂��Ă��Ȃ����Ƃ́C�O���̂悤�ȍ��ۖ@�̊�{�I�Ȑ��i�ɏƂ炵�Ă݂�Ȃ�C������ۖ@��̌����ǂ��荑�Ƃƍ��ƂƂ̊Ԃ̌����`�����߁C�l�̐�������F�߂����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���Ɨ�������̂����R�ł���B�v�Əq�ׂ�B
�@�Q�@�������C�܂��n��O����R���̕����ɂ��āC�����������҂���Q�Ҍl�ł���̂��C��Q�҂̏������鍑�Ƃ݂̂��Ƃ����_�ɂ��āC�������̂悤�ɁC�l�ɑ��Q������������F�߂����̂ł͂Ȃ��ƒ����Ɍ��_����̂́C���߂͈̔͂𖾂炩�Ɉ�E���Ă���B
�@�����̋N���ߒ��ɂ�����h�C�c��\�̒�Ắu��P���@���̋K���̏����Ɉᔽ���Ē����̎҂�N�Q������퓖���҂́C���̎҂ɑ��Đ��������Q������ӔC���v�ɂ́C�u���̎҂ɑ��āv�Ɣ�������Ώۂ����m�ɕ\������Ă������C�̑����ꂽ�n��O����R���ɂ����ẮC���̕����������Ă���B
�@��������ɏڂ����q�ׂ�Ƃ���C�R�c�̌��ʁC��Q�Ҍl�����Q�������������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����u���̎҂ɑ��āv�Ƃ����������폜���ꂽ�̂ł͂Ȃ��C�P�Ȃ�p��̎g�p���@�̖��Ɖ�����ׂ��ł���B
�@�����C�h�C�c���@���C�s�@�s�ׂ��K�肷���{�W�Q�R���P���́C�u�̈Ӗ��͉ߎ��ɂ�葼�l�̐����C�g�́C���N�C���R�C���L�����͂��̑��̌�������@�ɐN�Q�������̂́C���̑��l�ɑ��Ă���ɂ���Đ��������Q������`�����v�Ƃ���̂ɑ��āC�������C�t�����X���@�T�̑�Q�W�Q���́C�u���l�ɑ��Q��������l�̍s�ׂ͂����Ȃ���̂ł����Ă����ׂāC�ߎ��ɂ���Ă���������炵���҂ɁC���������`���킹��v�ƋK�肷��ɂ������C�������ׂ�������ɑ���L�ڂ��Ȃ��B�t�����X���@�ő������肷��������Ȃ�����Ƃ����āC�`���̑�����̓h�C�c���@�Ɠ��l�C�����N�Q�����҂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł����āC����͒P�Ƀh�C�c��̕\���̔@���ׂ��Ɍ��t�̏�ŕ\�����Ă��Ȃ������ɂ����Ȃ��B���Ȃ݂ɁC���̓_�̓t�����X���@���p���������̂Ƃ����䍑�̖��@�V�O�X���C���Ɣ����@�P�������l��.�C�����`���̑�����͒��ڕ\������Ă��Ȃ����C������ƌ����Ė��@�V�O�X���⍑�Ɣ����@�P���̐������҂ɂ��ċ^�₪�����Ȃ��̂Ɠ��l�ł���B
�@�n�[�O���̐����������ł��邱�Ƃ��l�����킹��C���������C����R���ɁC�u���̑�����i���Q������������L����ҁj�ɂ��Ă̕����͑��݂��Ȃ��v���Ƃ���C�����������҂ɔ�Q�Ҍl�͊܂܂Ȃ��Ɖ��߂���͖̂��炩�ɁC�������߂͈̔͂���E�������̂ł���B
�@�R�@���Ƀn�[�O����K����T�Q���R��������ƍ��̂Ƃ���ł���B
�@���K��́C�w���i�m�����j���V�e�n�����w�N�����j�e�x�L�q�R���U���n�̎��ރ��ȃe�V���얾�X�w�N�������w�N���j�V�j�c�X�����z�m�x�������s�X�w�L���m�g�X�x�Ƃ���B
�@���K��́C���̒n�̎s�撬���܂��͏Z���ɑ��钥���ɂ��āC���̑Ή����C�����łȂ���Η̎��s���ĂȂ�ׂ����₩�Ɏx�����ׂ����̂Ƃ�����̂ŁC�x�����̑���͒��������s�撬���܂��͏Z���l�ł��邱�Ƃ͖����ł���B
�@�������C�����ł͎x�������鑊����͕ʒi��������Ă��Ȃ��̂ł���B
�@���̂悤�ɂ��Ă݂�ƁC�l�����Q������������ۗL���邱�Ƃɂ��ċL�ڂ��Ȃ����Ƃ������āC�����ɔ�Q�҂̏������鍑�ɂ̂ݐ�������^�����݂̂ł���Ɖ��߂��邱�Ƃ́C�������߂͈̔͂���E���Ă���Ƃ������Ƃ����炩�ƂȂ�B
�@�S�@���������āC���@����R�P���P���̕������߂ɂ���ẮC�n�[�O����R�����C�����������҂ɔ�Q�Ҍl��F�߂����̂��C��Q�҂̏������鍑�Ƃ݂̂��ɂ��ẮC���m�ɂ����Ȃ��̂ł���B
�@��������Ə��@����R�P���R���y�ё�R�Q���Ɋ�Â��C���̋N�͉ߒ��⎖��̊��s�������s�ᓙ���l�����ĉ��߂���K�v������B
��T�@�n�[�O���̎�|�E�ړI�ɂ���
�@�P�@�������́C���̓_�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@�u�w�[�O������y�уw�[�O����K���̎�|�E�ړI�́C�����y�ѓ��K���̋K��ɏƂ炷�ƁC����ɂ����ČR���̏��炷�ׂ��������߁C�����Đ푈�̎S�Q���y�����悤�Ƃ���_�ɂ�����̂Ɖ������B���Ƃ��C�푈�̎S�Q�͍ŏI�I�ɂ͌l�ɋA������̂ł��邩��C�����y�ѓ��K���̋��ɂ̎�|�E�ړI�́C����̉ߒ��ɂ������퓬�����܂߂��l�̕ی�ɂ���Ɖ����邱�Ƃ��ł���B�������C���ۖ@�̑��`���Ƃ��Ắu���v�̊�{�I�Ȑ��i��w�[�O������y�уw�[�O����K���̋K����e�ɏƂ炷�ƁC�����y�ѓ��K���̒��ړI�Ȏ�|�E�ړI�́C�e���̌R���̋K���̓_�ɂ���Ɖ�����̂������ł���B�v
�@�u�ȏ�̏��_�ɏƂ炷�ƁC�����Ə��̎�|�E�ړI�ƂɏƂ炵�ė^������p��̒ʏ�̈Ӗ��ɏ]���ĉ��߂������C�w�[�O������R���̋K��́C�w�[�O����K���̏�������������邽�߁C���K���Ɉᔽ������퍑�̑��Q�����ӔC���߂����̂ł���C���K���ᔽ�ɂ���đ��Q�������l�����Q���Ƃɑ��Ē��ڑ��Q�������������s�g���邱�Ƃ܂ł�F�߂����̂ł͂Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B�v
�@�Q�u��|��ړI�v�ɂ�����
�@�������́C��L�̒ʂ�C�u���Ƃ��C�푈�̎S�Q�͍ŏI�I�ɂ͌l�ɋA������̂ł��邩��C�����y�ѓ��K���̋��ɂ̎�|�E�ړI�́C����̉ߒ��ɂ������퓬�����܂߂��l�̕ی�ɂ���Ɖ����邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ��Ȃ���C�u�������C���ۖ@�̑��`���Ƃ��Ắw���x�̊�{�I�Ȑ��i��w�[�O������y�уw�[�O����K���̋K����e�ɏƂ炷�ƁC�����y�ѓ��K���̒��ړI�Ȏ�|�E�ړI�́C�e���̌R���̋K���̓_�ɂ���Ɖ�����̂������ł���B�v�Ƃ��Ă���B
�@�������C�u���ۖ@�̑��`���Ƃ��Ắw���x�̊�{�I�Ȑ��i��w�[�O������y�уw�[�O����K���̋K����e�ɏƂ炷�Ɓv�Əq�ׂ镔���́C���̈Ӗ����܂������s���ł���B�n�[�O���̊�{�I�Ȑ��i�₻�̋K��̓��e���m�肷�邽�߂̍�ƂƂ��ď��̎�|�E�ړI���𖾂��悤�Ƃ��Ă���Ƃ��C���̉𖾂̖ؓI������̊�{�I���i��K��̓��e�������Ɏ����o���͖̂��炩�Ƀg�[�g���W�[��Ƃ��Ă���B
�@�n�[�O���̎�|�ړI�́C���������q�ׂ�悤�ɁC���ɂɂ͗���̉ߒ��ɂ������퓬�����܂߂��l�̕ی�ɂ���Ƃ������Ƃ��ł��C���̂��߂Ɋe���̌R���̍s�ׂ��K�������邾���łȂ��C���̋K����S�ۂ�����Q�����l���~�ς��邱�Ƃ����܂މ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�@�����ł���C�n�[�O���̎�|�ړI���炾���ł́C����l��������F�߂����̂ł��邩�ǂ������m�肷�邱�Ƃ͍���ł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C�l�̑��Q������������F�߂����̂ł���Ɖ��߂��邱�Ƃ��C�����̎�|�ړI�ɖ���������̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@��������Ƃ����ł��C���@����R�P���R���y�ё�R�Q���Ɋ�Â��C���̋N�͉ߒ��⎖��̊��s�������s�ᓙ���l�����ĉ��߂���K�v������̂ł���B
��U�@�n�[�O����R���̋N���ߒ��ɂ���
�@�P�@�������́C���̓_�ɂ��āC�ȉ��̒ʂ�q�ׂ�B
�@�u�w�[�O������R���̍쐬�ߒ��Ɋւ��C����(�A)����(�P)�܂ł̎�����F�߂邱�Ƃ��ł���B
�@
�@(�A)�@�w�[�O������R���̋K��́C�P�W�X�X�N�̑�P��w�[�O���a��c�ɂ����č̑����ꂽ����̖@�K����Ɋւ�����i�ȉ��u���w�[�O������v�Ƃ����B�j�y�ї���̖@�K����Ɋւ���K���i�ȉ��u���w�[�O����K���v�Ƃ����B�j�̏C���Ƃ��āC�P�X�O�V�N�i�����S�O�N�j�̑�Q��w�[�O���a��c�Ō������ꂽ�B
�@�܂��C�h�C�c��\���C�ȉ��̂悤�ȋK���V���ɐ݂��邱�Ƃ��Ă����B
�@��P���@���̋K���̏����Ɉᔽ���Ē����̎҂�N�Q������퓖���҂́C���̎҂ɑ��Đ��������Q�����̎҂ɑ��Ĕ�������ӔC���B��퓖���҂́C���̌R����g������l���̈�̍s�ׂɕt���ӔC���B�i�����͈��p�ҁB�ȉ������j
�@�����ɂ�鑦���̔������\�肳��Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ����āC��퓖���҂����������Q�y�юx�����ׂ������z�����肷�邱�Ƃ��C���ʌ��s�ׂƗ������Ȃ��ƌ�퓖���҂��F�߂�Ƃ��́C�E������������邱�Ƃ��ł���B
�@��Q���@�i���K���́j�ᔽ�s�ׂɂ���푊�葤��N�Q�����Ƃ��́C�����̖��́C�a���̒������ɉ���������̂Ƃ���B
�@(�C)�@�h�C�c��\�́C��ė��R���ȉ��̂Ƃ�����������B
�@�u����̖@�K����Ɋւ�����i���w�[�O������j�ɂ��C�e�����{�́C�����t���̋K���i���w�[�O����K���j�̋K��ɏ]�����w�߂����̌R���ɑ��ďo���ȊO�̋`����Ȃ��B�����̋K�肪�R���ɑ���w�߂̈ꕔ�ɂȂ邱�Ƃɂ��݂�C���̈ᔽ�s�ׂ́C�R�̋K�������Y�@�ɂ�菈�f�����B�������C���̌Y�������i�����j�ł́C������l�̈ᔽ�s�ׂ̗\�h�[�u�Ƃ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B���K���̋K��ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́C�R�̎w���������ł͂Ȃ��B�m���C���m���C�ꕺ���ɂ��K�p����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āC���{�́C���炪���ӂɏ]���Ĕ������P�߂��C�펞���C��O�Ȃ����炳��邱�Ƃ�ۏႷ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B
�@������ɂ����ẮC���K���̋K��̈ᔽ�s�ׂɂ�錋�ʂɂ��āC�������Ă����ׂ��ł���B�w�̈ӂɂ�邩���͉ߎ��ɂ�邩���킸�C��@�s�ׂɂ�葼�҂̌�����N�Q�����҂́C����ɂ�萶�������Q������`�����E���҂ɑ��ĕ����B�x�Ƃ̎��@�̌����́C�����@�́C���c�_���Ă��镪��ɂ����Ă��Ó�����B�������C���Ƃ͂��̊Ǘ��E�ē̉ߎ���������Ȃ�����ӔC��Ȃ��Ƃ����ߎ��ӔC�̖@���ɂ�邱�ƂƂ���̂ł͕s�\���ł���B�i���̂悤�Ȗ@�����̂�Ɓj���{���g�ɂ͉��̉ߎ����Ȃ��Ƃ����̂��قƂ�ǂł��낤����C���K���̈ᔽ�ɂ�葹�Q�����҂����{�ɑ��Ĕ����𐿋����邱�Ƃ��ł��Ȃ����C�L�ӂ̎m�����͕����ɑ��������������ׂ��ł���Ƃ��Ă��C�����̏ꍇ�͔����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤�B
�@���������āC��X�́C�R����g������҂��s�����K���ᔽ�ɂ���̕s�@�s�אӔC�́C���̎҂̑�����i�R����ۗL����j���̐��{�������ׂ��ł���ƍl����B
�@���̐ӔC�C���Q�̒��x�C�����̎x�����@�̌���ɓ������ẮC�����̎҂ƓG���̎҂ŋ�ʂ����C�����̎҂����Q�����ꍇ�́C���s�ׂƗ�������ł��v���ȋ~�ς��m�ۂ��邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u����ׂ��ł��낤�B����C�G���̎҂ɂ��ẮC�����̖��̉�����a���̉̎��܂ʼn������邱�Ƃ��K�v�s���ł���B�v
�@(�E)�@���V�A��\�́C�h�C�c��\�̒�Ă��x�����C���̂Ƃ���q�ׂ��B
�@�u��X�́C������̉�c�ɒ�Ă��s�����ہC�펞�ɂ����镽�a�s���̗��v��O���ɒu���Ă������C�h�C�c��Ă͂��̓������v�ɍ��v������̂ł���ƍl����B��X�̒�ẮC�P�W�X�X�N���i���w�[�O������j�̎��{�ɂ����肱���̎s���ɉۂ������ɂ�a�炰�邱�Ƃ�ڎw�����̂ł������B�h�C�c��ẮC���̏��̈ᔽ�ɂ�肱���s���ɑ������鑹�Q��z�肵�����̂ł���B�����Q�̒�Ă̍���ɂ��錜�O�͐����Ȃ��̂ł���C���ꎩ�̂Ƃ��č��ۓI���ӂ̑ΏۂƂȂ��đR��ׂ��ł���ƍl����B�v
�@(�G)�@�t�����X��\�́C�h�C�c��Ă��������̎s���ƌ�퍑�̎s���Ƃň������قɂ��Ă���_�ɋ^���悵�āC���̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u�h�C�c��ẮC���ɐ[���ȕʂ̍��{�I���������N�����B�����C���̒�ẮC���܂��ɑ�Q���ψ���c�_���Ă��钆�����̎҂̏����ɂ��Ẵh�C�c��ĂɌ�����C�����̖��Ɋւ���h�C�c��\�c�̔��ɂ͂����肵���咣�̒��ڂ̋A���ƍl����꓾��̂ł���B���̎咣�́C�������̍����ƐN���n���͐�̒n�ɋ��Z�����퍑�̍����Ƃ���ʂ��C�O�҂ɗL���Ȓn�ʂ�^���C�ނ�ɂ����钆���̔z����F�߂�Ƃ�����̂ł���B
�@���͂����ŁC����\�c�͔@���Ȃ�Ӗ��ɂ����Ă����̍l����������邱�Ƃ͂ł����C�l�̂��߂ɂƂ���ی�[�u�́C�w�����̎ҁx���w��푊�葤�̎ҁx���ɂ���ʂ�݂��邱�ƂȂ��C�S�Ă̎҂ɑ����l�ɓK�p�����ׂ��ł���ƍl����|�J��Ԃ������B�h�C�c��\�c�ɂ���Ă��ꂽ���ẮC�܂��ɂ��̋�ʂ��m������Ƃ��Ă���悤�ł���B�Ȃ��Ȃ�C���̑�P���ɂ����Ắw�����̎ҁx�ɑ��鑹�Q�ɂ��Ă������ꂸ�C�w��푊�葤�̎ҁx�͑�Q���ɂ����Ă��������Ă��Ȃ�����ł���B�c�c
�@�c�c����̐펞�K���ɂ�菙�X�Ɏx�z�I�ƂȂ����l�����C�����C�ی�I�[�u�ł���}���I�[�u�ł���C�G�s�ׂɎQ�����Ȃ��S�Ă̌l�����S�ɕ����Ɉ������Ƃ���l�����ɏ]���C�ی�I�[�u�������̎҂Ɍ��肳���͎̂�����Ȃ��B�v
�@(�I)�@�X�C�X��\�́C�ȉ��̂悤�ɏq�ׂāC�t�����X��\�̋^��ɔ��_���h�C�c��\�̒�Ăɗ��ۂȂ��^�������B
�@�u���̒�Ă��F�߂����悤�Ƃ��Ă��錴���͑S�������Ȃ��̂ł���C�P�W�X�X�N�K���i���w�[�O����K���j�̎��ۏ�̌��߂���̂ł���Ƃ�����B
�@�c�c
�@�h�C�c��Ă̓��e���̂��̂ɂ��ẮC���ꂪ�����̎҂ɋ����������^����Ƃ����̂͌��ł���B���̒�Ă����Ă��錴���́C���Q�����S�Ă̌l�ɑ��C�G���̍����ł��邩�������̍����ł��邩���킸�C�K�p�\�ł���B�����Q�̃J�e�S���[�̔�Q�ҁC���������ۗL�҂̊Ԃɐ݂���ꂽ�B��̋�ʂ́C�����̎x�����Ɋւ�����̂ł���C���̓_�Ɋւ��闼�ҊԂ̈Ⴂ�́C�����̐������̂��̂ɂ���B�����̎҂ɑ��锅���̎x�����́C�ӔC�����퍑����Q�҂̍��Ƃ͕����ɂ���C�܂��C���a�ȊW���ێ����Ă���C�����͂�����P�[�X��e�Ղɂ��x�Ȃ������������Ԃɂ��邽�߁C���̏ꍇ�C�����ɍs������ł��낤�B���̂悤�ȗe�Ղ��Ȃ����\���́C�푈�Ƃ����ꎖ�ɂ��C��퍑���m�̊Ԃł͑��݂��Ȃ��B�����������͒����̎҂Ɠ��l�e�X�̌�퍑�̎҂ɂ��Ă������邪�C��퍑���m�̊Ԃł̔����̎x�����́C�a����B�����Ă���łȂ���Ό��肵���{���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B�v
�@(�J)�@�h�C�c��\�́C�������g���ł��Ȃ��ō��ٖ̕������Ă����������ƁC�X�C�X��\�̔����ɑ����ӂ̈ӂ�\�����B
�@(�L)�@�C�M���X��\�́C�t�����X��\�̌��O�����L���C�h�C�c��Ă�����܂łȂ����������𒆗����ɗ^������̂ł��邱�Ƃ𗝗R�ɂ���ɓ��ӂł��Ȃ��Ƃ��C���̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u��P���������̎҂ɑ��C�����Q�̔�������퓖���҂ɗv�����錠����^���Ă���̂ɔ�ׁC��Q���ł́C��푊�葤�̎҂ɂ��Ă͔����͘a���̒������ɉ�������Ƃ��Ă���B���������Č�푊�葤�̎҂ɂƂ��ẮC�����͕��a���ɐ��荞�܂���������C��퍑�Ԃ̌��̌��ʂƂ��Ă̏�������Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���́C�i���j��̖@�K����̈ᔽ�̔�Q�҂ɑ���퓖�������������Ȃ��ׂ��ӔC��ے肷����̂ł͂Ȃ��C�p���͔@���Ȃ�Ӗ��ɂ����Ă����̐ӔC��Ƃ�悤�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����C���̂悤�Ȉᔽ�y�ѐ��������Q�͈̔͂��m�肷�邱�Ƃ��C�����Δ��ɍ���ł��邱�Ƃ��w�E�������B�������������Ƃ͂��₷�����C�����������ׂ����ƊԂ̗ǍD�ȊW���Q���锽�̐��������N�������ƂȂ��C���̌�����K�p���邱�Ƃ́C��ύ���ł���B�v
�@(�N)�@�h�C�c��\�́C�t�����X��\�y�уC�M���X��\�̔����ɑ��C�h�C�c��Ă̑�Q���̉��߂ɂ��Č��������Ƃ��C���̏��u�����̎ҁv�Ɓu��푊�葤�̎ҁv�Ƃ̊Ԃɐ݂��Ă���B��̍��ق́C�����̎x�����@�ɂ��Ăł���Əq�ׂ��B
�@(�P)�@�ȏ�̌������o�āC�����ψ���C�h�C�c��Ă��u�{�K���̏����Ɉᔽ�����퓖���҂́C���Q���������Ƃ��́C���Q�����̐ӔC���B��퓖���҂́C���̌R����g������l���̈�̍s�ׂɂ��ӔC���B�v�Ƃ̋K��ɂ܂Ƃ߁C���̋K�肪�S�̉�ɂ����đS���v�ō̑�����C�ŏI�I�ɋK�����ł͂Ȃ����i�w�[�O������j�̖{���ɂR���Ƃ��Đ��荞�܂ꂽ�B
�@�Ȃ��C���̋K��̍쐬�ߒ��ɂ����Ă��ꂽ�����̒��ɂ́C�����K���ᔽ�̍s�ׂɂ���đ��Q������Q�Ҍl�����Q���ɑ����ڑ��Q������������L���邱�Ƃm�ɍm�薔�͊m�F���������͂Ȃ��C�܂��C�l�����Q�������������s�g����葱��x�Ɋւ��锭�����Ȃ������B�v
�@�u�ȏ�̎����Ɋ�Â��Č�������ɁC��Q��w�[�O���a��c�ɂ����ăh�C�c��\�c����Ă����ĕ��ɂ́C���̑�P���ɂ����āu���̎҂ɑ��Đ��������Q�����̎҂ɑ��Ĕ�������ӔC�v�Ƃ����\��������C���̕����������݂����C��������ҁC���Ȃ킿������������L����҂͔�Q�҂ł���ƍl�����Ă���Ƃ����������S���s�\�Ȃ킯�ł͂Ȃ��B�������C�h�C�c��ẮC���̈ĕ��S�̂�����ƁC���������Q�y�юx�����ׂ������z���u���Ɗԁv�Łu����v����邱�Ƃ�O��Ƃ��āi��P���ɂ��u��퓖���҂����������Q�y�юx�����ׂ������z�����肷��v�Ƃ����������g�p����Ă���B�j�C��Q�҂��������̎҂ł���ꍇ�ƌ�퍑�̎҂ł���ꍇ�Ƃʼn��Q���Ɣ�Q�҂̑����鍑�Ƃ̊W�̑���Ɋ�Â����̌���̎�������ʂ���Ƃ������e�ł������Ɖ�����̂����R�ȗ����ł���B���ɁC�����z�̌���y�юx�������ƊԂōs���邱�Ƃ�O��Ƃ��ăh�C�c��ĂɎ^�ӂ��������X�C�X��\�̈ӌ��ɑ��h�C�c��\�c������٘_�����܂����ӂ̈ӂ�\�������Ƃ��C���̓_�𗠕t������̂Ƃ�����B
�@�����āC���̑��̊e����\�c�̒��ɁC�w�[�O������R���̋K�肪�w�[�O����K���ᔽ�̍s�ׂɂ���Ĕ�Q�����l�����Q�҂̑����鍑�Ƃɑ����ڑ��Q�������������s�g���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ����|���܂ނ��Ƃ��������̂͂Ȃ����C�l�ɂ��̂悤�Ȍ�����t�^���邱�Ƃ̐���₻�̋�̓I�Ȏ葱�ɂ��ċc�_����邱�Ƃ��S���Ȃ������B
�@����ɁC�h�C�c��Ăɂ������u���̎҂ɑ��āv�Ƃ��������́C�ŏI�I�ɍ̑����ꂽ�w�[�O������R���ɂ����Ă͍폜����Ă���̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ȏ��_�ɏƂ点�C�w�[�O������R���̍쐬�ߒ��ɂ����Ċe����\���Ӑ}���Ă����̂́C�w�[�O����K���̎��������m�ۂ��邽�߁C�R���\���������K���ᔽ�s�ׂ��s�����ꍇ�ɂ́C���Y�R���\�����̏������鍑�Ƃ̐��{�Ɏ�ϓI�ȗL�Ӑ����Ȃ��Ă����Y���Ƃɔ�Q�҂̑����鍑�Ƃɑ��鑹�Q�����ӔC�킹�邱�Ƃɂ���C�e�����C�����̓`���I�ȍ��ۖ@�̘g�g�݂̗�O�Ƃ��āC�l�̉��Q���Ƃɑ��鑹�Q������������n�݂��邱�Ƃ܂ł��Ӑ}���Ă������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�v
�@�Ƃ���̂ł���B
�@�܂��C�n�[�O����K���T�Q������ѓ��T�R���Ɋւ��āC�������́C
�@�u������́C�w�[�O����K���T�Q���C�T�R�����C�퉟���Ҍl�ɑ��ԊҐ������y�ё��Q�������̐�������t�^���Ă���Ǝ咣���Ă���B
�@�m���ɁC���K���T�Q���R���́C�����̑�����ƂȂ����Z�����ɂȂ�ׂ������Ŏx�������Ƃ����߂Ă���B�������C��̌R�������̎x�������Ȃ��ꍇ�ɏZ�������̋~�ς����߂邽�߂̍��ۖ@��̎�i�݂͐����Ă��Ȃ��B�܂��C���K���T�R���Q�����������ł́C���a�̎��Ɋҕt�┅�����u����v�����Ƃ��Ă��邩��C���̏����́C���a��̍��ƊԂ̌��ɂ��ҕt�┅�������肳��邱�Ƃ�\�肵�Ă���Ƃ݂�̂������I�ł���B���������āC�����̋K��́C����������̍s�ׂ����ƊԂō��ӂ������̂Ɖ�����̂��Ó��ł���B����āC�����̋K��������āC�l�����荑�ɑ����ډ��炩�̐����������邱�Ƃ�F�߂����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v
�@�Ƃ���B
�@�������Ȃ���C�ȉ��ɏq�ׂ�Ƃ���C�������̏�L���߂͂����������Ă���B
�@�Q�@�N���ߒ�����̉���
�@(1) ���������N���ߒ��Ɋւ�������p�����R�c���e�Ɋւ��鎖���ɏƂ点�C�������̔F�肪����ɔ�������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�����C�܂���P�ɁC�h�C�c��\�̏C���Ē�Ă̑�P���̕����ɂ́u���̋K���̏����Ɉᔽ���Ē����̎҂�N�Q������퓖���҂́C���̎҂ɐ��������Q�����̎҂ɑ��Ĕ�������ӔC���v�Ɓu���̎҂ɑ��Ĕ�������v���Ƃ����m�Ɍ���Ă���B�������������́C������̈ӂɖ������Ă���B����́C�������̋c���^�����̌���I�ȏd��Ȍ��ł���B
�@��Q�ɁC�������́C�R�c�ߒ��ɂ��Ď��̂悤�Ƀh�C�c��\�̒�ė��R���������p���Ă���B
�u�i���̂悤�Ȗ@�����̂�Ɓj���{���g�ɂ͉��̉ߎ����Ȃ��Ƃ����̂��قƂ�ǂł��낤����C���K���̈ᔽ�ɂ�葹�Q�����҂����{�ɑ��Ĕ����𐿋����邱�Ƃ��ł��Ȃ����C�L�ӂ̎m�����͕����ɑ��������������ׂ��ł���Ƃ��Ă��C�����̏ꍇ�͔����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤�B
�@���������āC��X�́C�R����g������҂��s�����K���ᔽ�ɂ���̕s�@�s�אӔC�́C���̎҂̑�����i�R����ۗL����j���̐��{�������ׂ��ł���ƍl����B�v
�@��L�̒�ė��R�̓��e�͖����ł���B���Ȃ킿�C�n�[�O����K���ɂ��R���Y���@�K�ɂ�鏈�f�����ł͈ᔽ�s�ׂ͗\�h�ł����C�ᔽ�s�ׂ͐�����B�����Ĉᔽ�s�ׂ�����������Q�Ҍl�̋~�ς��l�����ׂ��ł���C��Q�҂����Q�̔����邱�Ƃ����m���ɂ��邽�߂ɁC��Q�҂����ڂɌR���̍\�����̏������ɑ��Q�����𐿋��ł���悤�ɂ��ׂ��ł���C�����̏ꍇ�̍��̐ӔC�͖��ߎ��ӔC�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����̂ł���B
�@�܂��C���c���^�ɖ����ł���悤�ɁC�����ł́C�n�[�O����K���ᔽ�̍s�ׂɂ���Q�Ҍl���L�ӂ̎m���܂��͕����ɑ����Q�����𐿋��ł��邱�Ƃ��O��Ƃ���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ���ׂ��ł���B��Q�Ҍl���L�ӂ̎m���܂��͕����ɑ��Q�����̐�������L���Ă��邱�Ƃ͓��R�̑O��ł͂��邪�C���ꂾ���ł͎��ۏ㔅���邱�ǂ͂ł��Ȃ��ł��낤����C���Q�҂̏������鍑�Ƃɖ��ߎ��̐ӔC�킹��ׂ��ł���Ƃ����̂ł���B
�@(2) �ȏ�C���c���^�͔����������҂���Q�Ҍl�ł��邱�Ƃ𖾔��Ɏ����Ă���B���������g�����p���Ă���h�C�c�C���Ă̕����C�y�уh�C�c��\�̓��C���Ē�ė��R�����́C�������̔F��Ƃ͈قȂ�C�����������҂͔�Q�Ҍl�ł��邱�Ƃ��㖾�炩�Ɏ����Ă���̂ł���B
�@�������̔F��͖��炩�Ɍ��ł���B
�@(3) ����ɁC�����������������p���Ă���t�����X��\�C.�X�C�X��\�y�щp����\�̔����ɂ́C�S�Ĕ����������҂͔�Q�Ҍl�ł��邱�Ƃ������㖾������Ă���B�O�L�h�C�c�C���Ă̕����y�ѓ��C���Ē�ė��R�̐����ɂ��Ă̋c���^�̕�����O��ɂ��C���̕����ɂ����Ċe����\�̔��������߂���C���������������Ȃ��Ƃ���Q�Ҍl�ɂ��邱�Ƃ���{�ł��邱�Ƃ͗e�Ղɂ��m���ɗ����ł���B
�@�t�����X��\�́C�u�����̎ҁv���C�a���̉̎��܂ő҂����u���s�ׂƗ�������ł��v���ȋ~�ς��m�ۂ����v�̂Ɠ����悤�ɁC�u��푊�荑�̎ҁv���~�ς����ׂ����Ǝ咣���Ă���C���Q�����������҂���Q�Ҍl�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@�X�C�X��\�̔����́C�u�����������͒����̎҂Ɠ��l�e�X�̌�퍑�̎҂ɂ����Ă������邪�v�ƁC�����������҂��l�ł��邱�Ƃ𖾗ĂɎ����Ă���B
�@����ɉp����\�̔��������ƁC�u(��)��̖@�K����̔�Q�҂ɑ��C��퓖�������������Ȃ��ׂ��ӔC��ے肷����̂ł͂Ȃ��v�ƁC�����������҂���Q�Ҍl�ł��邱�Ƃ������I�ɑO��Ƃ���Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@(4) �ȏ�̂Ƃ���C�c���^�ɂ�����C���Ă̏C����ė��R�y�Ҋe����\�̔����ɂ�����_�_�C�������݂̊W������ƁC������������ۗL����͔̂�Q�Ҍl�ł��邱�Ƃ͋c�_�̑�O��ł��苤�ʂ̊�ՂȂ̂ł���B
�@�c���^�̌����ɂ����ẮC�e����\�̔��������̑��݂̊W�ɂ����āC���S�̂Ƃ��čl�@����ׂ��ł���B�������͂�������������ӂ��Ă���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@(5) �����āC�������́C�T�i�l��o�̃J���X�z�[�x���C�G���b�N��_���C�h�y�уN���X�g�t�@�[��N���[���E�b�h�̊e���ӌ������̈ӂɖ������Ă���B
�@�������Ȃ���C�n�[�O����R���ɂ��Ă̋c���^�̌�������C�l�������������Â���J���X�z�[�׃����ӌ����C�y�т�����x�����C���c���^��Ȗ��ɕ��ͥ���������G���b�N��_���C�h���ӌ�������������C�����R���Ɋւ���R�c�ɂ����āC��Q�Ҍl�̉��Q���ɑ��鑹�Q���������������݂��邱�Ƃ͎����̂��ƂƂ���Ă������Ƃ���w���炩�ɂȂ�B
�@(6) �������͂܂��C�h�C�c��Ăɂ������u���̎҂ɑ��āv�Ƃ��������́C�ŏI�I�ɍ̑����ꂽ�n�[�O���R���ɂ����Ă͍폜���ꂢ��Ƃ����_���l�������̔ے�̍����ɂ��Ă���B
�@�������Ȃ���C���ɏq�ׂ��悤�ɁC�h�C�c�̏C���Ă₱��ɑ���e���̑�\�҂̔������C��Q�Ҍl�ɑ��Q������������^���邱�ƂR�̑O��Ƃ��Ă������Ƃ͖��炩�ł���C�����̐R�c�ߒ��ɂ����āC���Q�����ӔC���ׂ��u������v���u�폜�v���邩�ǂ����C���Ȃ킿�l�ɐ�������F�߂邩�ǂ����ɂ��͂܂��������Ƃ��ꂨ�炸�C���̓_�ɂ��ĉ���R�c����Ă��Ȃ��Ƃ�������������C�̑����ꂽ�����ɁC�h�C�c�C���Ă̏�L�������Ȃ����Ƃ������āC�l�������ے�̍����Ƃ��邱�Ƃ́C����F�߂��Ȃ��̂ł���B
�@�R�c�ߒ��ʼn�����ɂ��Ȃ炸�C�폜�����ƂȂ�Ȃ������Ƃ����������炷��C�ނ���h�C�c�C���Ăƍ̑����ꂽ�n�[�O����R���́C�l�̑��Q������������F�߂�Ƃ����_�ɂ����ē���ł���Ɖ��߂���̂����R�ł���B
�@(7) �ȏ�̒ʂ�C�n�[�O����R���Ɋւ���R�c�ߒ����炷��C��������Q�����l�����ڂɉ��Q���ɑ����̑��Q�̔��������߂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ�F�߂��K��ł��邱�Ƃ́C�ɂ߂Ė����ł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����ے肵���������ɂ͏d��Ȗ@���߂̌�肪����B
��V�@�펞���ۖ@�ɂ�����l�̌����̏��F�F�펞���ۖ@�̓��ꐫ�ɂ���
�@�P �������́C�w�[�O������ѓ�����K���ɂ́C�l�����Q���ɑ��钼�ڂ̑��Q������������L���邱�Ƃ���������K�蓙�͈�ؑ��݂��Ȃ��C�Ƃ���B
�@�������Ȃ���C���̌������̉��߂����ł���B�ȉ��ɁC������펞���ۖ@�ɂ�����l�̌����̏��F�ɂ��Ďw�E���C�����ăn�[�O��܂��ɂ��̗l�ȈӖ��ł̐펞���ۖ@�ł���C�����ыK�����l�̑��Q������������F�߂����̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B
�@�Q�@�n�[�O���̂悤�Ȑ펞���ۖ@�Ȃ������@�K�͌����C�l�̌����`���̏��F�Ƃ����_�ŁC���ۖ@�̑��̕���ɔ䂵�ē��ʂ̐��i�����@�̌n�ł���B�ߗ����͂��߁C���]���҂͍��ۖ@��Ō��������L���`�����ۂ���Ă�����̂ł���B
�@���ɏ]������R���\���������@�K�ɒ��ڂɍS������C�ᔽ�s�ׂɂ��Ă͍\�����l�����荑�̂Ȃ������ۓI�ȌR���@��ŏ������ꂤ�邱�Ƃ́C���ۊ��K�@��m�����Ă���B���Ȃ킿�C�u�匠���Ƃ݂̂����ۖ@�̎�̂ł���Ƃ̊ϔO����ʓI�ł�������Q�����O�ɂ����Ă��C���@�K��ł͓��ʂ̃��W�[���Ƃ��Čl�ɑ��錠���̕t�^�Ƌ`���̕��ۂ������ɘj���ď��F����Ă����v�Ƃ����鏊�Ȃł���i�b�Q�R�P���@�L���P�j���w�ߗ��̍��ۖ@��̒n�ʁx�P�X�X�O�N23�Łj�B
�@���ł��C����Ɋւ��āC�G���ɂ���̎��ɂ�����Z���̎����i���l�̐����C�g�̋y�э��Y�j���d�ɂ��ẮC18���I�C���ď����ɂ����鎩�R��`�o�ς̔��W��[�֎v�z�̓o���w�i�ɁC�ł��������獑�ۖ@�̋K�����m�������B�ȉ��\�����̈ӌ����i�b�V�X���j�ɏ]�����̌o�܂����邱�Ƃɂ���B
�@�R �܂��G�����̎����̑��d��ԏ��ŏ��߂Ė����������̂́C1785�N�̕č��E�v���V�A�Ԃ̏��i23���j�ł���B�č��i�g�}�X�E�W�F�t�@�\���C�x���W���~���E�t�����N������j�̒�ĂɂȂ�{���́C���Ԃɐ푈�����������ꍇ�ɂ��C�u������h��̒��C�����͏ꏊ�ɋ��Z���邷�ׂĂ̏����Ǝq�ǂ��C�����镪��̊w�ҁC�_���C�H�|�ƁC�����ƎҁC���t�C�y�ш�ʂɁC�l�ނ̋��ʂ̐����Ɨ��v�̂��߂̐E�Ƃł��邻�̑��̂��ׂĂ̎҂́C���ꂼ��̌ٗp���p�����邱�Ƃ�F�߂��˂Ȃ炸�C�푈�̎��Ԃɂ���Ă��̌��͉��ɗ����邩������Ȃ��G�̌R���ɂ���Ă��̐g�̂��N���ꂽ��C�Ɖ��������͕��i���R�₳��������͂��̑��̕��@�Ŕj�ꂽ��C�c�����r�p������ꂽ�肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�A���C�����R���ɂ��g�p�̂��߂ɂ����ꂩ�̕��������̎҂����肽�Ă邱�Ƃ��K�v�ȏꍇ�ɂ́C�����I�Ȋz�Ŏx�������Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����B
�@�S�@���������펞�ɂ����鎄�����d�̌����̗L�͂ȗ��_�I�����ƂȂ����̂́C�u�푈�͐l�Ɛl�Ƃ̊W�ł͂Ȃ��āC���Ƃƍ��Ƃ̊W�Ȃ̂ł��v��C�u�������N��́C�G���ɂ����āC���L���Y�͂��ׂĖv�����Ă��܂����C�l�̐����ƍ��Y�͑��d����v�Ƃ����[�֎v�z�ƃW�����E�W���b�N�E���\�[�̐��ł������i�|�{���K�w���ېl���@�̍Ċm�F�Ɣ��W�x1996�N�C39�|40�Łj�B
�@����ɁC�������d�̊ϔO�́C�t�����X�v���̐l�����O�ɂ���Ĉ�w���m�Ɍ���Â���ꂽ�B1791�N�Ƀt�����X���@�c��́u�t�����X�����͂����Ȃ鎞�ɂ��C�����Ȃ�l�ɑ��Ă��C���l�ɓ���ł���Ƃ���̌����d���C�܂��t�����X�R����̒n�̐l���ɔ�点��s�{�ӂȑ��Q�ɑ��Ă͔������Ȃ��v�Ɛ錾���C���̌���펞�ɂ����Ă��̗��O����{�I�ɓ��P�����i���C41�Łj�B
�@�T�@19���I�ɂ́C�����̑��d�́C1863�N�̃��[�o�[�K���C1880�N�̍��ۖ@����I�b�N�X�t�H�[�h�E�}�j���A���Ȃǂɂ�閾�������o�āC�펞���ۖ@�̈�ʌ����Ƃ��Ċ��K�@��m�����Ă����B
�@���[�o�[�K���Ƃ́C�A�����J�̓�k�푈���C�����J�[���đ哝�̂��펞���ۖ@�̐��ƃ��[�o�[���m�i�R�l�ł�����j�Ɉ˗����C���{�R�̌P�߂̂��߂ɔ��s�������̂ł���C�펞���ۖ@�̖@�T���̏��̎��݂Ƃ��Ė��L�������̂ł���Ɠ����ɁC����ɂ����鍑�Ǝ��s�Ƃ��Ă��d�v�ȈӋ`�����B���[�o�[�K���́C���1874�N�̃u���b�Z���c�菑�i����y�j�C�y��1899�N�E1907�N�̃n�[�O���̖@�T���̊�b�ƂȂ����B
�@�I�b�N�X�t�H�[�h�E�}�j���A���i������j�Ƃ́C�������ۖ@����iInstitute of International Law�G1873�N�ɐݗ��B�e���̒����ȍ��ۖ@�w�҂���Ȃ�w�p�c�́j���펞���ۖ@�̖@�T����ړI�Ƃ��č쐬���������ŁC�I�b�N�X�t�H�[�h�ɂ������c�ōŏI�I�ɍ̑��������߂��̂悤�ɌĂ�Ă���B
�@�U�@1899�N�̑�P��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ�n�[�O������y�сC������Q��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ1907�N�̃n�[�O������́C�����̎�v���Ƃ̑啔���̎Q���̂��ƁC���K�@�Ƃ��đ��݂��Ă����펞���ۖ@�̋K����@�T�������W�听���Ȃ����̂ł���B �Ȃ��C�����̃n�[�O���̋N���ɂ������ẮC��q�̃��\�[�̍l�������̗p�����嗤�̑命���̍��ۖ@�w�҂̒ʐ����C�傫�ȗ��_�I�����ƂȂ����Ƃ����Ă���i�|�{�O�f���C�X�|10�C40�|41�C46�|47�Łj�B���ۖ@����ɂ��I�b�N�X�t�H�[�h�E�}�j���A�����\�ɑO�サ�āC�I�����_�C�t�����X�C�h�C�c�C�X�C�X�C�Z���r�A�C�X�y�C�����C��v�Ȋe���͎����̌R���ւ̌P�߂̂��߂̃}�j���A�������X�ƍ쐬����Ɏ��������C�n�[�O���̒�����́C�Ⴆ�C�M���X��1903�N�ɁC1899�N�n�[�O���𒆐S�I�ȓ��e�Ƃ���}�j���A���s���Ă���B
�@�ȉ��ɁC���[�o�[�K���Ɏn�܂�C�������d�����ɂ�������ȋK���������B
�@�@�@1863�N���[�o�[�K��
�@�u37�� �A�����J���O���́C��̂����G���ɂ����āC�@���y�їϗ���F�ߋy�ѕی삵�C���L���Y�����i�ɔF�ߋy�ѕی삵�C�Z���̐g�́C���ɏ����̐g�́C�y�э����W�̐_������F�ߋy�ѕی삷��B���̈ᔽ�́C���������������B...
�@38�� ���L���Y�́C���L�҂ɂ��ƍߖ��͈ᔽ�ɂ��v������Ȃ�����C�R���̓A�����J���O���̈ێ����͂��̑��̕։v�̂��ߌR���I�K�v�ɂ��ق��́C�������꓾�Ȃ��B���L�҂����S���Ă��Ȃ���C�w�����́C�������ꂽ���L�ҁiowner�j������(indemnity)����悤�̎��s����B�v
�@
�@ �A�@1874�N�u���b�Z���c�菑
�@�u38�� �Ɓifamily;�Ƒ��j�̖��_�y�ь����C�l�̐����y�э��Y�C���тɌl�̏@���I�M�O�y�ю��H�́C���d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���L���Y�́C�v�����꓾�Ȃ��B
�@42�� �����́C��̒n�ɂ�����w�����̋��ɂ���Ă݂̂Ȃ��ꂤ��B���ׂĂ̒����ɑ��ẮC����(indemnity)���^�����邩���͗̎������s�����B�v
�@�B�@1880�N���ۖ@����I�b�N�X�t�H�[�h�E�}�j���A��
�@�u49�� �Ɓi�Ƒ��j�̖��_�y�ь����C�l�̐����C���тɌl�̏@���I�M�O�y�ю��H�́C���d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@54�� ���L���Y�́C�l�ɑ�������̂ł����Ђɑ�������̂ł���C���d����Ȃ���Ȃ炸�C�ȉ��̏����Ɋ܂܂ꂽ�����̂��Ƃł̂ݖv�����ꂤ��B
�@55�� �A����i�i�S���C�D���̑��j�C�d�M�C����y�ђ�������́C��Ж��͌l�ɑ�������̂ł����Ă���̎҂ɂ�艟�����ꂤ�邪�C�a�����s����ۂɁC�\�Ȃ�Ίҕt����C�y�є���(compensation)�����肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@60�� �������i�́C�����Ŏx�������Ȃ����̂łȂ���C�펞�̎旧���ł��邱�Ƃ��̎��ɂ��ؖ������B...
�@�C�@1899�N�n�[�O���
�@�u46�� �Ɓi�Ƒ��j�̖��_�y�ь����C�l�̐����y�э��Y�C���тɌl�̏@���I�M�O�y�ю��R�́C���d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���L���Y�́C�v�����꓾�Ȃ��B
�@�{���̓u���b�Z���c�菑38���Ƃقړ���ł��邪�C�{���N���̍ہC�����̑��d���u�R���I�K�v�����e�������v�Ƃ��Đ������悤�Ƃ����h�C�c��\�̒�ẮC���������ɂ����ނ����Ă���B
�@�u52�� ���i�����y�щۖ��́C��̌R�̕K�v�̂��߂������ẮC�s�������͏Z���ɑ��ėv�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����y�щۖ��́C�n���̎��͂ɑ������C���l���ɂ��̖{���ɑ���R�����ɉ����`���킹�Ȃ������̂��̂ł��邱�Ƃ�v����B�E�̒����y�щۖ��́C��̒n���ɂ�����w�����̋��Ȃ���C�v�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���i�̋����ɑ��ẮC�Ȃ�ׂ������Ŏx�����C�����łȂ���Η̎������s�������̂Ƃ���B
�@53�� ��n�����̂����R�́C���̏��L�ɑ����錻���C����y�їL���،��C��������C�A���ޗ��C�ɕi�y�ѕ��i���̑��R�����ɗp����ꂤ�鍑�L���Y�ȊO�́C�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�C���@�ɂ���ċK�������ꍇ�������C�S���{�݁C����d�M�C�d�b�C���C�D���̑��̑D�C����������тɁC���ׂĂ̎�ނ̌R���i�́C��Ж��͎��l�ɑ�������̂ł����Ă��C�R�����̂��߂ɗp����ꂤ�铯�l�̕����ł���B�A���C�a���̒������Ɋҕt����C���������x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�@�D�@1907�N�n�[�O���
�@�u46�� �Ɓm�Ƒ��n�m���_�y�����C�l�m�����C���L���Y���@���m�M�y���m���s�n�C�V�����d�X�w�V�B���L���Y�n�C�V���v���X���R�g�����X�B
�@52�� ���i�����y�ۖ��n�C��̌R�m���v�m�׃j�X���j��T���n�C�s�撬�����n�Z���j�V�e�V���v���X���R�g�����X�B�����y�ۖ��n�C�n���m���̓j�����V�C���l�����V�e���m�{���j�X����퓮��j�����m�`�������n�V���T�������m���m�^���R�g���v�X�B�E�����y�ۖ��n�C��̒n���j���P���w�����m���������j��T���n�C�V���v���X���R�g�����X�B���i�m�����j�V�e�n�C�����w�N�����j�e�x���q�C�R���T���n�̎����ȃe�V���ؖ��X�w�N�C�������w�N���j�V�j�X�����z�m�x�������s�X�w�L���m�g�X�B
�@53�� ��n������̃V�^���R�n�C���m���L�j���X�������C����y�L���،��C��������C�A���ޗ��C�ɕi�y�Ɩ����m�����e��퓮��j���X���R�g�����w�L���L���Y�m�O�C�V�������X���R�g�����X�B
�@�C��@�j�˃��x�z�Z�������ꍇ�����N�m�O�C����C�C��y�j���e�m�`�����n�l��n���m�A���m�p�j���Z��������m�@�ցC�������푴�m���e��m�R���i�n�C���l�j���X�����m�g�C�G�h���C�V�������X���������B�A�V�C���a�����j�����C�V���ҕt�V�C���V�J����������X�w�L���m�g�X�B�v
�@�������āC1907�N�n�[�O���i�ȉ��C�u�n�[�O���v�Ƃ����j�ɂ��C��̒n�̌R�̌��͎͂����d����`�����i46���j�C���D�͌��ւ����i47���j�B�̓`�B���͐l�������͕��̗A���̗p�ɋ�������̌�ʋ@�ցC�������킻�̑��̌R���i�́C���l�ɑ�����ꍇ�ł����Ă��������邱�Ƃ��ł��邪�C���a��ɕԊҋy�є������Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��i53���Q�i�j�B�����ŁC��̌R�́C��̌R�̎��v�̂��߂Ɍ��i�����y�щۖ����Z���ɗv�����邱�Ƃ��ł��C����ɑ��Ă͂Ȃ�ׂ������Ŏx�����ƂƂ��ɁC�s�\�ȏꍇ�ɂ͗̎��s�����₩�ɑΉ����x�������̂Ƃ����i52���j�B���Ȃ킿�C����52���y��53���Q�i�ɂ�钥���E�����́C46���ɒ�߂�ꂽ�����̕s�N�̖����I�ȗ�O�ł���C46����⊮������̂Ƃ��Ĉʒu�Â�����B
�@�����āC�����̋K�����āC�����R���́C�u�O�L�K���m�����j�ᔽ�V�^����퓖���҃n�C���Q�A���g�L�n�C�V�K�����m�Ӄ����t�x�L���m�g�X�B��퓖���҃n�C���m�R�����g�D�X���l���m��m�s�׃j�c�L�ӔC�����t�v�ƒ�߂��̂ł���B
�@�����R���\�����ɂ���@�s�ׂɂ��č������ۓI�ȐӔC�����Ƃ͊m�����ꂽ���ۖ@�̌����ł��������C�����͌R���\�����́u��̍s�ׂɂ��v�ӔC���Ɩ������ɋK�肵�C�\�����̎��i�C�ߎ��̑��ݓ��̗v���Ȃ��ɍ\�����̂��ׂĂ̍s�ׂ̐ӔC�����ɕ��킵�߂Ă���̂ł���B
�@�V�@�ȏ�̒ʂ�C������펞���ۖ@�ɂ����ẮC�`���I�Ɍl�̌����̏��F���s���Ă���C�܂��ɁC�w�[�O������ѓ�����K���́C�����̐펞���ۖ@�̏W�听�Ƃ��āC�펞�ɂ�����l�̌����𖾂炩�ɂ��C�����̐N�Q�ɑ��ẮC��Q�Ҍl�����Q���ɑ��钼�ڂ̑��Q������������L���邱�Ƃ��������̂ł���B�������̉��߂�����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
��W�@�n�[�O���̎��s��ɂ���
�@�P�@�������́C�T�i�l�炪�������n�[�O���̎��s��ɂ��āC�ȉ��̂悤�ɏq�ׁC�����̔����̂����l�̉��Q���Ƃɑ��钼�ڂ̑��Q������������F�߂��ƕ]���ł��鍑�Ǝ��s��͂P�Ⴞ���ł��邩��C���̂悤�ȍ��Ǝ��s��̊ϓ_����w�[�O������R������Q�Ҍl�̉��Q���Ƃɑ��钼�ڂ̑��Q������������F�߂����̂Ɖ��߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����B
�@(1) �G�s���X��������
�������́C���̔����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׁC���s��ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@�u�M���V���ɐ�̂���Ă����g���R�̃G�s���X���̏Z�����M���V�����{��Ƃ��Ē����ɂ���������Q�̔����𐿋��������Ăɂ����āC�A�e�l�T�i�ٔ����́C�w�[�O����K���S�U���y�тT�R���ɑ̌����ꂽ���I���Y�̕s�N����F�߂鍑�ۖ@�̌������{���ɂ��K�p�����Əq�ׁC�����̐�����F�e������P�R�������x�������i�b�Q�O�X�̂P�E�Q�j�B
�@�������C���̔����́C�w�[�O����K���S�U���y�тT�R�������p���Ă�����̂́C�w�[�O������R���𐿋����̍����Ƃ��Č�����̐�����F�e�������̂��ǂ������炩�ł͂Ȃ��B���������āC���̔����������ăw�[�O������R���̋K�肪�l�̑��Q������������F�߂����Ƃ��������Ǝ��s��ł���ƕ]�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v
�@�������Ȃ���C���̔����́C�w�[�O������R���𐿋����̍����Ƃ��Č�����̐�����F�e�������̂ł���B���̓_�́C��ɉ��߂Ď咣������B
�@(2) �P�X�Q�S�N�V���P�T���C�M���X�T�i�@����
�������́C���̔����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׁC���s��ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@�u������́C��P�����E��풆�ɐ펞�������Ɋ�Â��C�M���X�ɍ��Y���������ꂽ�G�W�v�g�̏��Ђ��C�M���X���{�ɑ����Q���������߂������ɌW��C�M���X�T�i�@�̏�L�������C������̎咣����b�t���鍑�Ǝ��s��ł���Ǝ咣���Ă���B
�@�������C�{���ɂ����āC�����������ۖ@�Ɋ�Â��l�̉��Q���Ƃɑ��鑹�Q������������F�߂����̂ƓI�m�ɔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B�������āC�٘_�̑S��|�ɂ��C���������C�M���X�̍����@�Ɋ�Â��Č����̐�����F�e�����\�����ے�ł��Ȃ��B���������āC�������������ăw�[�O������R���̋K�肪�l�̑��Q������������F�߂����Ƃ��������Ǝ��s��ł���ƒ����ɔF�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v
�@�������Ȃ���C�����������ۖ@�Ɋ�Â��l�̉��Q���Ƃɑ��鑹�Q������������F�߂����̂ł���B
�@���Ȃ킿�C�{���ŃC�M���X�T�i�@�́C�펞�����́u���ƍs��(act of State)�v�ł����ăC�M���X�̍����@�Ŗ��L����Ȃ����葹�Q�����������͂Ȃ��Ƃ����C�M���X�̎咣��ނ��C���ۖ@�Ɋ�Â������ւ̑��Q������F�߂锻�����������B�����͂��̒��ŁC�u���ۖ@�́C�펞�������Ƃ����`�ŁC��퍑�����̗̈���ɂ��钆�������̕��������錠����F�߂Ă��邪�C����͊��S�Ȕ���(full compensation)���s�����Ƃ������ł���v�u���ۖ@�ŔF�߂��Ă���펞�������̏����̈���C�����̏��L�҂Ɋ��S�Ȕ������x�����邱�Ƃł���͖̂����ł���v�Ƃ��Ĕ����̋`�������C�u��X�̍����@�������̌�����F�߁C�����������Ŕ����̋`����r������Ƃ������R����������Ȃ��B�������f���邱�Ƃ́C�䂪���@��C�C�M���X�@�ɕ�����҂ƕ����Ȃ����������Ƃ̊ԂɌ����ȋ�ʂ�݂��邱�ƂɂȂ邾�낤�v�Ƃ��āC�������������R�ɍ��ۖ@��̌��������L���ׂ����Ƃ��q�ׂĂ���B
�@�C�M���X�͏��Ɋւ��Ắu�ό^�v�̐��i���������Ŏ��{���邽�߂ɂ͕ʓr�����@�̐����v����j���ł��邪�C�{���́C�m�����ꂽ���K�@�Ƃ��Ă̐펞�������Ɣ����`�����C�M���X�̍��@�̈ꕔ�ł��邱�Ƃ���C����ɏƂ炵�Č����̐�����F�߂����̂ł���B
�@���̂悤�Ɍ��������C�{���������ۖ@�Ɋ�Â��l�̉��Q���Ƃɑ��鑹�Q����������F�߂����̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂͌��ł���B
�@(3) �P�X�T�Q�N�S���X���̋����h�C�c�s���T�i�ٔ�������
�������́C���̔����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׁC���s��ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@�u��Q�����E����h�C�c���p���ɐ�̂���Ă��������ɉp����̌R�\�����̋N��������ʎ��̂̔�Q�҂����Q�����������h�C�c�ɋ��߂����ĂŁC�����h�C�c�̃~�����X�^�[�s���T�i�ٔ����́C�P�X�T�Q�N�S���X���C�u�����̑��Q�����̐����́C�������@���炾���łȂ��C���ۖ@����������o�������̂ł���B�P�X�O�V�N�w�[�O������R���ɂ��C���Ƃ͂��̌R���ɑ����邷�ׂĂ̐l�����Ƃ������ׂĂ̍s�ׁk���Ȃ킿�C�K���̈ᔽ�s�ׁl�ɂ��ĐӔC���B�v�Ɣ������āC�����̐�����F�e�����i�b�Q�O�W�̂P�E�Q�j�B
�@�������C�������́C���Q�s�ׂ������҂�������p���̑��Q�����ӔC��F�߂����̂ł͂Ȃ�����C����������ăw�[�O������R�����l�̑��Q������������F�߂����Ƃ��������s��ł���ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v
�������Ȃ���C�����̉p����̒n��ɂ����Ď{�s���ꂽ�V�X�e���ɂ��C���Q�����̐������͉̂p����̌R���ǂɒ�o����C���̐����������Ȃ��������R�����ŐR������C�@�I�Ɏx���ӔC������Ɣ��肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�Ƃ���Ă����B�������̔����z�̌���ɂ��Ă̂����h�C�c���Z�肷�邱�ƂɂȂ��Ă����̂ŁC���̎����ł͎x���z(�Ђ��Ă͑��Q�͈̔�)�ɂ��đ��������������߁C�ٔ��ɂ����Ă͐��h�C�c��������ƂȂ������̂ɂ����Ȃ��̂ł���B
�@�]���āC�������̂悤�ɍٔ��̑��肪�h�C�c���ǂł��邩��C��Q�Ҍl�����Q�����{��Ƃ��������ł͂Ȃ��Ƃ����s��ł͂Ȃ��Ƃ���̂͏�L�V�X�e����S������������̂ł����āC���ł���B
�{�ٔ���́C�n�[�O���R���ړK�p�������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@(4) �P�X�X�V�N�P�P���T���h�C�c�E�{���n���ٔ�������
�������́C���̔����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׁC���s��ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@�u��Q�����E��풆�ɋ������e���ɂ����ċ����J���ɏ]��������ꂽ���_���l�������̎x�����h�C�c���{�ɐ����������Ăɂ��āC�h�C�c�̃{���n���ٔ����͂P�X�X�V�N�P�P���T���C�u�N���҂̐ӔC�́C���łɗ����E���̊Ԃɍ��ۖ@�̗v�f�ƂȂ����B���̏�C��̒n�̕ߗ��ƈ�ʎs�����E�Q������z�ꉻ�����肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������������ۖ@�̈�ʋK���ɑ����Ă���Ƃ������Ƃɂ��Ă͈ӌ�����v���Ă���B���̈�ʋK���́C�P�X�O�V�N�P�O���P�W���̗���̖@�K����Ɋւ���w�[�O��S���i�w�[�O������j�ɂ��\������Ă���B�h�C�c�鍑�́C�w�[�O��S�����P�X�P�X�N�P�O���V���ɔ�y�����̂ŁC���̋K�������炵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̏��̕����K���i�w�[�O����K���j�T�Q���ɂ��ƁC��̒n�̎s���ɂ��ۖ��͐�̌R�̎��v�̂��߂ɂ���̂łȂ���Ηv�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����C�s�����ꍑ�ɑ���푈�s�ׂɎQ������`�����܂߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̏�C�S�U���ɂ��ƁC�s���̖��_�C�����C�M�E�@���͑��d�����ׂ��ł���B���������āC��풆�̃h�C�c�鍑�ɂƂ��ẮC���_���n�̎s�����R���H��ŁC�r�ł�ړI�Ƃ��Ĕ�l�ԓI�������ŋ����J�������邱�Ƃ��ւ����Ă����B�v�Ɣ������āC�����̐�����F�e�����i�b�Q�P�S�̂P�E�Q�j�B
�@�������C�������ł́C���Q�����̒��ڂ̍����������@�i���@�T�j�ɋ��߂Ă��邩��i�b�Q�S�U�E�T�Q�y�[�W�j�C���̎���������Č�����̎咣����b�t���鍑�Ǝ��s��ƕ]�����邱�Ƃ͑����łȂ��B�v
�@�������Ȃ���C���������C�n�[�O����ݎ�`�̉��ő��Q�����ӔC���ۂ��Ă���킯�ł͂Ȃ����ƁC�h�C�c�A�M���@�Q�T���ɂ���ăn�[�O������@������Ă��邱�ƁC�����������̌��͂��@��������ʂɂ�����Ă��邱�Ƃ������Ƃ��ăn�[�O���ɂ��h�C�c�鍑�������@�̋��߂鑊�ݎ�`�̓K�p��r�����邱�Ƃ��������Ă��邱�Ƃ��炷��ƁC���������n�[�O����K���ᔽ�̍s�ׂɋN�����鑹�Q�����ӔC���l�̂��߂ɉ��p�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ������̂ł��邱�Ƃ͋^���̗]�n�͂Ȃ��B
�@�����n���ٔ����Q�O�O�P�N�i�����P�R�N�j�V���P�Q���������u�������̓��e�ɏƂ炷�ƁC���������n�[�O������R�����l�̍��Ƃɑ��鑹�Q������������F�߂鍪���ƂȂ肤��Ƃ��錩�������������̂Ɖ�����]�n�͂���Ƃ����ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ���B
�@(5) �P�X�X�V�N�P�O���R�O���M���V���E���C�o�f�B�A�n���ٔ�������
�@�������́C���̔����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׁC���s��ł��邱�Ƃ�F�߂��B
�@�u�M���V����̒��̃h�C�c�R���s�����c�s�s�ׂɂ���Q�����M���V���l���h�C�c����Ƃ��ăM���V���̃��C�o�f�B�A�n���ٔ����ɒ�i���������i�������C�h�C�c�́C���i�ׂ��h�C�c���Ƃ̎匠���Q������̂ł���Ƃ̗��R����i��̎�̂����ۂ��C���i���Ȃ������B�j�ɂ����āC���ٔ����́C�P�X�X�V�N�P�O���R�O���C���i�ׂɑ���ٔ��NJ������m�肵����C�w�[�O������̓M���V���ɂ���Ĕ�y����Ă��Ȃ��������̓��e�̓M���V���y�уh�C�c���S�����鍑�ۊ��K�@�̈ꕔ�ƂȂ��Ă���C������̐����́C�w�[�O������y�уw�[�O����K���C�Ƃ�킯�����R���y�ѓ��K���S�U���ɂ�荇�@�I�ł����āC�����̐����͎匠���Ƃɂ��s����K�v�͂Ȃ��l�̎��i�ōs�����Ƃ��\�ł���Ƃ��āC�l�ł��錴����̑��Q����������F�߂��i�b�Q�R�O�̂P�E�Q�j�B
�@���̔����́C�h�C�c���i��̎�̂����ۂ����i���Ȃ������̂ɖ{�Ĕ��������C���C�匠���Ƃ̑�����̒��̍s�ׂɂ��Ď匠�Ə��̓�����ے肵���Ƃ������̂ł��邪�C�l�̉��Q���Ƃɑ��钼�ڂ̑��Q������������F�߂����̂ł����āC������̎咣�ɉ������Ǝ��s��ł���Ƃ�����B�v
�@(6) ���̑��̔����ɂ���
�@�������́C�T�i�l�炪���������̑��̔����ɂ��āC�{���؋��y�ѕ٘_�̑S��|�ɏƂ炵�Ă��C�����̔�������Q�Ҍl�̉��Q���Ƃɑ��钼�ڂ̑��Q������������F�߂����̂ƒ����ɔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����B
�@�������Ȃ���C�T�i�l�炪������ȉ��̔�����́C�n�[�O���Ɋ�Â��ĉ����ꂽ�����ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����̓_�ɂ��ẮC���T�i�R�ʼn��߂Ď咣������B
�@�@�@�h�C�c�R�ɂ��ݕ������Ԃ���������C�Ή��̎x�������̎��̔��s���Ȃ���Ȃ��������Ăɂ��C�t�����X�̃��[�A���T�i�ٔ�����1947�N5��17���̔����ŁC���̂悤�ɔ������āC���̏��L�҂ł��郍�[���ւ̕Ԋ҂�F�߂��B�u�h�C�c�̍s�ׂ͒����ł͂Ȃ��C�n�[�O���53���ɂ��������ł������B�{���́C���l�ɑ�����A����i�̉����́C�푈�@�ɂ���ĔF�߂���ꍇ�ɂ́C�����̌l���珊�L����D�����̂ł͂Ȃ��C�P�ɉ������ꂽ���Y�̎g�p����D���݂̂ł���ƒ�߂Ă���B���Y���Y�́C���̏I����C�ҕt����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v(Mortier v.Lauret,H.Lauterpacht ed.,Annual Digest of Public International Law Cases,Year 1947,1951,pp.274-275)�B
�A�h�C�c��̌R�̂��߂ɑ݂����n���C���̌���Ԋ҂��ꂸ�C���̌�C�M���X��̌R�C�����Ńf���}�[�N���{�ւƈ��n���ꂽ���߁C���̏��L�҂����L�����咣�������ĂŁC�f���}�[�N�̐��T�i�ٔ�����1947�N7��11���C�i����F�ߔn�̕Ԋ҂𖽂��锻�����������B�u�n�[�O�ł̑�Q�ە��a��c�ō̑����ꂽ����K���́C53���Q�i�ɂ����āC��̌R�́C���l�ɑ�������̂ł����Ă��C�Ƃ�킯�A����i���������邱�Ƃ��ł���ƒ�߂Ă���B�������C�{���́C���̂悤�ɉ������ꂽ���Y�́C�a���̒������ɂ͊ҕt����C�܂����Q��������߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƕt�������Ă���B�h�C�c��̌R�ɂ��n�̏������C��q�̋K���ɏ]���čs��ꂽ�����Ƃ����邩�ǂ����͕ʂɂ��āC�T�i�l�̏��L��������ɂ���Ď���ꂽ�Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v(Andersen v.Christensen and the State Committee for Small Allotments,H. Lauterpacht ed., Annual Digest of Public International Law Cases,Year 1947,1951,pp.275-276.)�B
�B�h�C�c�ɂ��k�C�^���A�̐�̒��C�h�C�c���ǂ��C�����̎x��������鏑�ނs���ĂQ���̋������C���̌�C�ʂ̎҂���̋��Q���̒����ɍۂ��čŏ��̋����Ƃ��ė^��������ŁC�C�^���A�̃{���[�j���T�i�ٔ�����1947�N5��4���C�������K�v�Ȍ��x���Ă������ƁC�����Ȃ�x�������Ȃ���Ȃ��������Ƃ𗝗R�Ƃ��āC�ŏ��̒�������@�ł��������Ƃ�F�߁C���̕Ԋ҂𖽂����iMaltoni v.Companini,H. Lauterpacht ed., Annual Digest of Public International Law Cases,Year 1948,1953,pp.615-618)�B
�C�h�C�c�R�ɂ��m���E�F�[�̐�̒��C�h�C�c���ǂ��������L�̎����Ԃ����C�̎��̔��s�������̎x�������Ȃ���Ȃ��������Ăɂ��C�m���E�F�[�̍T�i�ٔ���(Haalogaland Lagmannsrett)��1948�N3��4���C�n�[�O���52���ɂ�钥�����L���ł��邽�߂ɂ͌����̎x�������̎��̔��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��āC�����̏��L����F�߂�(Johansen v. Gross,H. Lauterpacht ed., Annual Digest of Public International Law Cases, Year 1949,1955,pp.481-482�j�B
�D�h�C�c�ɂ��I�����_�̐�̒��C�h�C�c�̍����Ŋ֊Ď������C�����x�������̎��̔��s�������ɂQ��̃I�[�g�o�C�������������Ăɂ��C�I�����_�̓��ʔj���@��1950�N2��6���C���Ƃ��A����i�Ƃ��ĉ����̑ΏۂɂȂ�Ƃ��Ă��C�n�[�O���53���Q�i�����炳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��āC��������@�ƔF�߂锻����������(In re Hinrechsen,H. Lauterpacht ed., Annual Digest of Public International Law Cases,Year 1949,1955,pp.486-487)�B
�E�h�C�c�ɂ��f���}�[�N�̐�̒��ɑ���̎x�����Ȃ���������C���C�M���X�R����f���}�[�N���{�̎�ɓn�����Q���̔n�ɂ��C���̏��L�҂����L�����咣�������ĂŁC�f���}�[�N�̃R�y���n�[�Q�����n���ٔ�����1947�N7��11���C���̂悤�ɏq�ׂČ����̎咣��F�߂��B�u��Q��n�[�O���a��c�ō̑����ꂽ����K����53���Q�i�́C�������̂����R���͂Ƃ�킯�C���l�ɑ�������̂ł����Ă��C�A����i���������邱�Ƃ��ł���ƒ�߂Ă���B�������C�����́C�������ꂽ���Y�́w�a���̒������Ɋҕt����C���������肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�ƕt�������Ă���B���̂��ƂɏƂ点�C�T�i�l�̏��L�������ł����Ɛ��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v(Statens Jordlovsudvalg v.Petersen,H. Lauterpacht ed., Annual Digest of Public International Law Cases,Year 1949,1955,pp.506-507.��Ƀf���}�[�N�ō��ق�������x���j�B
�F�C�M���X��̌R�̖��߂ɂ�蒥�����ꂽ�I�[�g�o�C�����̌�C�ȑO�ɒ��������҂ɑ��Ĕ����Ƃ��ēn����C���̎��傪�n�[�O���53���2�i�������ɏ��L�����咣�������ĂŁC�I�[�X�g���A�ō��ق�1951�N4��18���C1899�N�̃n�[�O�������p���āC�����̎咣��F�߂��B�u�n�[�O�K����53���P�i�ɂ��C��̌R�́C���̍��̏��L�ɑ�������̍��Y�����邱�Ƃ��ł���B��������Y�͂���ɂ���̍��̍��Y�ɂȂ����C���l�̋K���́C53���Q�i�Ɍ��y���ꂽ�l�╨�̗A����i���܂ގ��L���Y�ɂ͂��Ă͂܂�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�C�����鎄�L���Y�́C�a���̒������ɕԊ҂���C�܂������̖������肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B�D�D�D�I�[�g�o�C�͎��l�̍��Y�ł���������C��̍��́C�n�[�O�K���ɏ]���C�����ɂ���Ă��̏��L�����擾���Ă͂��Ȃ��D�D�D�]���Č����́C�����y�т��̌�̈ړ]�̌��ʂƂ��āC�I�[�g�o�C�ɑ��錠���������Ă��Ȃ��v(Requisitioned Property (Austria)(No.1)Case,H. Lauterpacht ed.,International Law Reports,Year 1951, 1957, pp.694-695)�B
�G�č��ɂ��h�C�c�̐�̒��C�ČR�ɂ���Ē������ꂽ�����Ԃ��C�ʂ̎҂̎g�p�Ɋ��蓖�Ă��C���̎҂��g�p���Ă���Ԃɓ���ɂ��������������߁C���L�҂����Y�̈편�ɂ��đ��Q���������߂����ĂŁC�h�C�c�A�M���a���i���h�C�c�j�A�M�ō��ق�1952�N2��13���C�g�p�҂������ӔC�����Ƃ�F�߂锻�����������B�ٔ����́C�n�[�O���53���Ɍ��y���Ĉȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�ČR�̂Ƃ����[�u�ɂ�������炸�������Ȃ��Ԃ̏��L�҂ł��������ǂ����̖��́C�m��I�ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�D�D�D�n�[�O�K����53���Q�i�ɏ]���C���l�̏��L�ɂȂ�A����i�ŁC��̌R�ɂ�蒥�����ꂽ���̂́C�a���̒������Ɋҕt����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�]���āC��������Y�̒����͎��p�ړI�ɋ����Ă͂Ȃ炸�C�g�p�҂̂��߂ɂ̂���������̂ł���C���ʂƂ��āC����ɂ��e�������l�͂��̏��L��������Ȃ��v�B�����āC�Ԃ��g�p���Ă����퍐�͂��̕ی�̂��߂̑[�u��ӂ����Ƃ��āC�����ӔC��F�߂�(Loss of Requisitioned Motor Car (Germany)Case, H. Lauterpacht ed.,International Law Reports 1952,1957,pp.621-622)�B
�H�h�C�c�R���t�����X���̒��C�t�����X�̉�Ђł��錴������C����߂ĕs�\���Ȋz�̎x�����������ČR�p��������������C��Ƀt�����X���{�@�ւɂ��G�����Y�Ƃ��Ėv�����ꂽ��Ɍ����ɔ��p���ꂽ���߁C����������̕����߂������߂����ĂŁC�t�����X�j���@�i�ō��فj��1957�N11��13���C�h�C�c�̍s�ׂ͗��D�Ƃ��Ĉ�@�ł���C�����͍��@�I�ȏ��L�҂Ƃ��Ċ��S�Ȕ����錠��������Ɣ�������(Etablissements Bracq Laurent S.A.v. Service Central des Domaines,H.Lauterpacht and E.Lauterpacht eds., International Law Reports 1957,1961,pp.978-979)�B
�@�Q�@�ȏ�݂��悤�ɁC�n�[�O���Ȃ����͂��̍��ۊ��K�@�Ɋ�Â��đ��Q�����̎x������F�߂锻�f�́C���ۓI�ȍٔ��@�ւ̂ق��C�e���̍����ٔ����ɂ����Ă���������I�ɍs���Ă��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@����瑽���̎��s�������C�n�[�O���R���͌l�����Q���ɑ��đ��Q�����������s���邱�Ƃ�F�߂����̂ł��邱�Ƃ͋^�������Ȃ��B
�@���������C�����̎��s��ɂ��āC�w�[�O������R������Q�Ҍl�̉��Q���Ƃɑ��钼�ڂ̑��Q������������F�߂����̂Ɖ��߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����̂́C�d��Ȍ��ł���B
��X�@���Ƃ̊O��ی쌠�ƌl�̐������Ƃ̊W
�@�P�@�������́C���̓_�Ɋւ��ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@�u�l�������̍��ۈ�@�s�ׂɂ���đ��Q�����ꍇ�ɂ́C���Y�l�͉��Q���̍��ېӔC��Njy���邽�߂̍��ې������o�������̂Ƃ��Ă͔F�߂�ꂸ�C���̌l�̑�����{�����C���Y�l�̎��������グ�O��ی쌠���s�g���邱�Ƃɂ���āC����ɑ���@�I�ȐN�Q�Ƃ��Ĉ����C���ƊԊW�ɐ�ւ��đ��荑�i���Q���j�ɍ��ƐӔC��Njy������̂Ɖ�����Ă���B�v
�@�Q�@�������Ȃ���C�������̂�������߂����ł���B
�@(1) ���Ƃ̊O��ی쌠�ƌl�̌ʂ̐������Ƃ́C�����܂ł��Ȃ��C�{���ʌ̂��̂ł���B���Ƃ̐������́C�O��ی쌠�Ƃ����`�ō��ƊԂōs�g�����̂ɑ��C�l�̐������́C���ʂ̍��ӂ�������ۓI�葱�ɂ��i���F���T�C�����̗�j�C����ȊO�̏ꍇ�ɂ́C�e���̍����@�ւɂ�����葱��ʂ��āC�\�ȕ��@�ōs�g���ꂤ��i��ɂ݂������̍����ٔ����̔����̗�j�B
�@(2) �������C��@�Ȑ푈�s�ׂɂ��l�����Q�����ꍇ�C���Ƃ��O��I�ɉ�����}��C���ʓI�ɔ�Q�Ҍl�ɏ\���ȋ~�ς��^����ꂽ�ꍇ�ɂ́C���Y��Q�����Ɋւ��ăn�[�O���R���͊��S�ɗ��s���ꂽ�Ƃ����Ă悢�ł��낤�B�������C�����łȂ��ꍇ�ɂ́C�l�̐������́C���Ƃ̊O��ی쌠�s�g�ɂ�������炸�c��̂ł���B
�@�n�[�O���R���̖{���̖ړI�͈ᔽ���̐ӔC�y�є�Q�Ҍl�ւ̔����ł���Ƃ������Ƃ��ł��邩��C���Ƃ��O��ی쌠���s�g���Ȃ��ꍇ�C���邢�͍s�g���Ă��l�̔�Q�������I�ɋ~�ς���Ȃ��ꍇ�ɂ́C��Q�Ҍl������̗���ŁC���Q�����̍����I��i����ʂ��ċ~�ς����߂邱�Ƃ�r��������̂ł͂Ȃ��Ɖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ̊O��ی쌠�́C�l�̐������ꊇ����Ӑ}�ō��ۓI���x���ōs�g���ꂤ�邪�C����́C�l�̈�g�ɐꑮ���鐿�����������葱�̃��x���ɂ����Ă����ł�������̂ł͂Ȃ��B
�@(3) ����������@�s�ׂɂ�葹�Q�������ꍇ�C�{�����Ƃ������ł���̂͊O��ی쌠�̍s�g�����ł����āC��Q�Ҍl�̈�g�ɐꑮ���錠�������ł�����킯�ł͂Ȃ����Ƃ́C�Ⴆ�Γ��ؐ���������Ƃ̊֘A�œ��{���{�ł����F�߂Ă��邱�Ƃł���B
�@���Ȃ킿�C�u��������ؐ���������ɂ����܂��ė����Ԃ̐������̖��͍ŏI�����S�ɉ��������킯�ł������܂��B���̈Ӗ�����Ƃ���ł������܂����D�D�D����͓��ؗ��������ƂƂ��Ď����Ă���܂��O��ی쌠�𑊌݂ɕ��������Ƃ������Ƃł������܂��v�i1991�N�W��27���Q�c�@�\�Z�ψ����c�^��R��10�Łj�Ɠ��{���{�͏q�ׂĂ���B
�@(4) 1977�N�̃W���l�[�u����P�lj��c�菑91���́C�n�[�O���R���̋K����قڂ��̂܂܈����p�����K��ƂȂ��Ă��邪�C�ԏ\�����ۈψ���͂��̋c�菑�ɑ��钍�ߏ��ŁC�u���a���̒������ɁC�������͌����Ƃ��āC�푈��Q��ʂɊւ�����...��K���ȕ��@�ŏ������邱�Ƃ��ł���B�����ŁC�������́C...[�W���l�[�u���n���y�ыc�菑�̋K���ᔽ�̔�Q��(victims)���錠��������(are entitled)����(compensation)��ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɩ������Ă���i�b�Q�P�Q���@Y.Sandoz et al. eds.,Commnetary on the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I),1987,p.1055�j�B�܂��C�����́C�ʏ�́u�����������̕s�@�s�ׂɂ���đ��Q�����C�O���Ђ̎҂́C�����̐��{�ɓ���������ׂ��ł���C������Đ��{�͈ᔽ���s�����������ɐ\���Ă��o����ł��낤�v���C�u1945�N�ȍ~�́C�l�ɂ�錠���̍s�g�����F����X���������Ă���v�Əq�ׂĂ��邱�Ƃɂ����ڂ��ׂ��ł���iibid.,pp. 1056-1057�j�B
�@(5) �����āC�ŋ߂ł́C���A�l���ψ���̉����@�ւł���l�����ψ���i�l���̑��i�y�ѕی�Ɋւ���ψ���j�́C1999�N�W��26���ɍ̑������u���͕������̑g�D�I�����y�ѐ��z����Ɋւ��錈�c�v�i���c1999�^16�j�̒��ŁC������u�]�R�Ԉ��w�v�̂悤�Ȑ펞���z�ꐧ�̔�Q�҂����������߂錠���ɂ��C���ƊԂ̕��a���͂����̔�Q�҂̌����D������̂ł͂Ȃ����Ƃ�����Ɏ����Ă���B
�@�R �l�̎����Q�̋~�ϕ��@�����Ƃɂ��O��ی쌠�s�g�݂̂ł���Ƃ��錴�����̗���́C���������l�̋~�ς��Ӑ}�����n�[�O���R���̎�|�ړI�̎�����j�ނ��ƂɂȂ邤���C��q�̓��{���{�̌��������ɂ����v���Ȃ��B�@���Q�ɑ��锅���Ƃ����n�[�O���̎�|�ړI���炵�āC���Ɗԉ����ł��ꂪ��������Ă��Ȃ�����C���̑��̍����I��@�ɂ��~�ς̓������R�ɊJ����Ă���Ƃ݂�ׂ��ł���B���Ƃ������ł���̂͊O��ی쌠�̍s�g�����ł����āC��Q�Ҍl�̈�g�ɐꑮ���錠�������ł�����킯�ł͂Ȃ��B��Q�҂��C���Q���̍����I�葱�ɂ���Ĕ��������߂邱�Ƃ͍��ۖ@�㉽��r������Ȃ��̂ł���B
�@�������̏�L���f�͌��ł���B
��P�O�@����
�@�ȏ�q�ׂĂ����Ƃ���C���������Ȃ����n�[�O����R���Ɋւ�����߂́C���炩�Ɍ���Ă���C���T�i�R�ɂ����Ă��̌��͐�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�n�[�O���R���́C���̗��s�̂��߂ɂ����Ȃ�葱�I�ȉ\�����r�����Ă��炸�C��Q�Ҍl�����荑�̍ٔ����ɂ����Ĕ����������N���邱�Ƃ��������Ĕr�����Ă��Ȃ��B�n�[�O���ᔽ�̏ꍇ�̔����ƐӔC�m�ɂ���Ƃ������̏��̎�|�E�ړI����́C���ꂪ������������Ă��Ȃ����݁C�ĉ��i�l��ɉ��Q�����ٔ����ł̋~�ς�^���邱�Ƃɂ͉���@�I�ɖ��͂Ȃ����肩�C�K�ł��萳�`�ɂ��Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@��

|