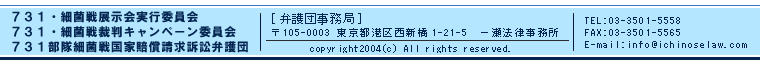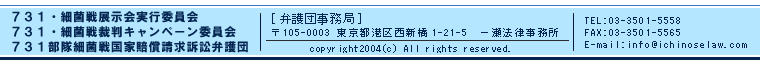2002年(ネ)第4815号謝罪及び損害賠償請求控訴事件
控訴人(一審原告) 程 秀 芝 外179名
被控訴人(一審被告) 日 本 国
第3準備書面
2003年12月4日
東京高等裁判所第2民事部 御中
控訴人ら訴訟代理人
弁護士 土 屋 公 献
同 一 瀬 敬 一 郎
同 鬼 束 忠 則
同 西 村 正 治
同 千 田 賢
同 椎 野 秀 之
同 萱 野 一 樹
同 多 田 敏 明
同 池 田 利 子
同 丸 井 英 弘
同 荻 野 淳
同 山 本 健 一
第1 はじめに
1 被控訴人は、第1準備書面、第2準備書面において、本件細菌戦の事実に全く触れずに、法律論を展開し、控訴人らの主張に縷々反論する。
被控訴人は、法律論からしか展開していないし、本件細菌戦の現実を全く踏まえないため、その根拠を欠く。
しかし、本質的な法解釈は、現実に起きた事実から出発すべきである。
2 旧日本軍731部隊などの細菌戦部隊が中国各地で行った本件細菌戦は、決して戦争犯罪という言葉だけでは言い尽くせない、実におぞましい悪魔の所業というべきものであった。
細菌戦のために軍医を集めて秘密部隊を創り、その細菌戦部隊の中でペスト菌を生産し、鼠をペストに感染させ、ペストに感染した昆虫の蚤を大量生産し、空中から人の住む街や村に投下するという、空中から戦闘とは全く無関係の一般住民をペストやコレラなどの疫病に感染させ、その地域一帯に疫病を大流行させるという行為は、細菌兵器開発のための人体実験も含め、作家森村誠一が名付けたとおり、「悪魔の飽食」を彷彿とさせる。
明らかに戦争という日本が中国で行った細菌戦の残虐さ、非人道的は世界史的にみてドイツ・ナチスが行ったホロコーストにも比すべき、残虐で非人道的なものであった。
典型的なジェノサイドであり、中国の一般住民に対する大量無差別虐殺行為である。本質的に言うならば、まさに細菌戦は、ナチスが犯したアウシュヴィッツ等での毒ガス等によるユダヤ人・ポーランド人などの民族抹殺的な大量虐殺行為と何ら異ならない、人類史上最も残虐な行為なのである。
3 しかも、原判決が、「ジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法による細菌兵器の禁止に違反した場合にもヘーグ陸戦条約3条の規定を内容とする国際慣習法による国家責任が生ずるというべきである。」「被告には本件細菌戦に関しヘーグ陸戦条約3条の規定を内容とする国際慣習法による国家責任が生じていたと解するのが相当である。」(原判決39頁)と認定したように、本件細菌戦が、細菌戦被害者が受けた損害を賠償するというハーグ陸戦条約第3条を内容とする国際慣習法による国家責任が被控訴人に成立しているのである。
このような重大な事実から、法律を解釈し当てはめなければならないことはいうまでもない。
4 本年9月29日、東京地方裁判所民事第35部は、旧日本軍が日中戦争中に中国に持ち込んだ毒ガス兵器や砲弾を敗戦前後に遺棄・隠匿し、放置したことにより、1974年、1982年、1995年に事故が発生し死傷者が出た損害賠償事件(いわゆる中国遺棄毒ガス被害事件)において、国の責任を認め、合計1億9000万円の賠償を認めた画期的な判決を下した(以下、「東京地裁2003年9月29日判決」という。甲491)。
毒ガス兵器は、国際法でも禁止された化学兵器である。旧日本軍は、日中戦争中に細菌兵器と毒ガス兵器の大量破壊兵器を実戦使用し、敗戦後遺棄し、その後60年に渡り、中国人民に被害を与え続けている。
東京地裁2003年9月29日判決は、「日本軍による毒ガス兵器や砲弾の遺棄行為は、日本軍が戦争行為に付随して組織的に行った行為であり、国の公権力の行使に当たる。その後の放置行為は、遺棄された毒ガス兵器や砲弾の処理について、被告が国家として行うべきことをしなかったという不作為を問題にするものであるから、この不作為も、国の公権カの行使に当たるということができる。」「毒ガス兵器や砲弾の遺棄は、単に物を置き去りにするという行為にとどまるものではなく、その物によって生命や身体に対する危険な状態を積極的に作り出すという行為である。危険な状態を作り出した者には、その危険な状態を解消して結果の発生を回避する措置をとることが要請されるのであり、そのような措置をとらないで放置する行為に対しては、遺棄行為とは別に、独自に法的な評価がされなければならない。したがって、本件で問題とされる遺棄兵器の放置行為については、国家賠償法施行後の行為として、国家賠償法1条の適用を考えることができる。」「本件において遺棄された毒ガス兵器や砲弾は、それ自体、高度の殺傷能カがあり,危険性の高いものである。中国における事故の発生状況や、日本国内における事故の発生状況を見ても、経年的な変化によりその殺傷能カが衰えるということもなく、毒ガス兵器の場合には、むしろ、腐食などにより内部のイペリットなどが流出しやすくなっていたとさえいえる。そのような毒ガス兵器や砲弾が、佳木斯市内を流れる川に投棄され、牡丹江市の市街地の地中に埋められ、あるいは双城市周家鎮東前村の畑の中に残存していたというのであるから、そこで生活する住民らの生命や身体に対する差し迫った重大な危険があったということができる。」と判示し、国の損害賠償責任を認めたのである。
この判決は、現実の出来事から出発し、法を適用することの重要性を指摘している。また、控訴人らの第1準備書面第6章の行政不作為による不法行為について、同判決をもって補充する予定である。
5 本件細菌戦の被害は、毒ガス兵器と同じ大量破壊兵器による被害であり、毒ガス被害者と同様、控訴人らが被っている精神的苦痛について、早急な被害回復が求められている。
このような本件細菌戦の特質から、法律を適用していく必要があることを踏まえて、以下、被控訴人の主張に逐次、反論し、従前の主張を補充する。
第2章 「国家無答責の法理」は、本件細菌戦には適用されない
第1 被控訴人の主張
被控訴人は、「国家無答責の法理」について、以下のとおり主張する。
① 行政裁判法及び旧民法は,国家無答責の法理に基づいて制定されたものであり,行政裁判法と旧民法が公布された明治23年の時点で,国家の権力的作用についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立したものである(被控訴人第1準備書面2頁)。
② 国家無答責の法理は,国の賠償責任を認めた規定が存在しないが故に国
が賠償義務を負わないというものであり,問題とされている権力的作用に法的根拠があるか否かは全く問題とならない(同35頁)。
③ 外国における軍人の行為も,国家主権に基づく行為であることに変わり
はなく,外国における外国人に対する行為であるからといって,民法が軍人の行為を私人の行為と同様に取り扱うことを予定しているものとは考え難い(同36頁)。
④ ヘーグ陸戦条約の規定が,そもそも被害者個人の加害国に対する損害賠
償請求権をその内容として保障していない以上,ヘーグ陸戦条約の規定が国内法的効力を有するとしても,それにより当該規定が保障していない個人の損害賠償請求権が国内法的に創設されるということはあり得ず,国家無答責の法理と何ら抵触を生ずるものではない(同40頁)。
⑤ 行為時を基準とすべきであるから、明治憲法下において合理性のあつた
国家無答責の法理を日本国憲法を前提とする現在の価値観によって否定して,特別の規定がないのに,無答責であつた行為につき,賠償責任を認めることは法の解釈として許されないというべきである(同43頁)。
⑥ 国賠法附則6項の「従前の例」に関する東京地方裁判所平成15年3月
11日判決は,国家無答責の法理について最高裁昭和25年判決の判断と相反する(同43頁)。
以下、逐次、反論する。
第2 「国家無答責の法理」の確立は認められない
国家無答責の法理について実定法上の根拠は存在せず,判例理論としても,当時の学説によっても,立法者意思によっても確立した理論ではないことは、第1準備書面において既に述べたとおりであるが、被控訴人の主張に反論しつつ、この点をさらに若干補充する。
1 明治23年の時点で、国家無答責の法理が確立していたとは認められないこと
(1) 被控訴人は、「行政裁判法及び旧民法は,国家無答責の法理に基づいて制定されたものであり,行政裁判法と旧民法が公布された明治23年の時点で,国家の権力的作用についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立したものである」と主張する(被控訴人第1準備書面2頁)。
しかし、下記のとおり、明治23年の時点で、国家の権力的作用についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立していたとは認められない。
(2) 第1準備書面においても指摘したとおり,実定法上,明確に国が不法行為責任を負わない旨を規定した法律は存在しない。
国家無答責の法理の法理の実定法上の根拠とされたのは,行政裁判法16条の「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」との規定のみである。そして,この規定により行政裁判所は国家賠償訴訟を受理せず,また事件の内容が行政行為に関わることから他の裁判所も国家賠償訴訟を受理せず,その結果として国に賠償責任を認める裁判が行われることはないということとなり,これをもって,国家無答責の法理の法理の表れであるとされる。
しかし、行政裁判法16条が「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」と規定しており、同条の規定は、実体法上は、公権力の行使に違法があった場合に国に損害賠償請求権が成立することを前提としている。
行政裁判法16条の存在は,逆に,国家無答責の法理が認められなかったことの表れと考えるべきである。もしも,真に国家無答責の法理が存在していたのであれば,このような条規の存在は不要であるばかりか,このような規定を設けること自体が立法技術上,不適切である。
国家無答責の法理が存在し確立していたのであるとすると,実体法上,国家に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は存在しないことになる。そうであれば,行政裁判所の構成及び訴訟手続等を定めた行政裁判所法において,敢えて訴訟を受理しない旨を定めるまでもないし,定めることは立法技術上不適切である。
逆に,実体法上は国家無答責の法理は認められず行政作用においても国が損害賠償責任を負うのであれば,組織法・手続法においてそれに触れ,行政裁判所が受理しない旨を定めることは,何ら不自然ではない。
したがって,行政裁判法16条は,国家無答責の法理がないことを前提とした規定であり,国家無答責の法理は実定法上は否定されていたと解するのが相当である。
(3) 被控訴人は、旧民法の制定過程の論議を縷々述べて、国家の権力的作用についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立していたと主張する。
しかし、旧民法は明治23年4月21日に公布されたが、施行されないまま廃止された。明治29年、新たに起草された草案に基づき現行民法(第1編から第3編まで)が公布され、明治31年7月16日から施行された。
現民法の立案に当り、立法者は、「使用者」という語は、大小の団体、公私の法人をも含み得る意味を持ち、後述するとおり、特別法が制定されない場合には民法715条を国にも適用すべきであると考えていた。
このように、現行民法は、旧民法とは体系も文言もまったく異なる立法であり、旧民法の立法者意思が現行民法に継承されたという被控訴人の主張は失当である。
(4) 以上に鑑みれば、国家無答責の法理は、天皇主権の明治憲法下での一法解釈にすぎないというべきであり、被控訴人が主張するように「明治23年の時点で、国家の権力的作用についての国家無答責の法理を採用するという基本的法政策が確立した」とはいえないことは明らかである。
2 判例理論としても、国家無答責の法理の確立は認められないこと
(1) 行政上の不法行為責任に関する裁判例は、明治22年に明治憲法が制定されてから、裁判所の判例を積み重ねる中で、様々な分野で国及び公共団体の損害賠償責任を認めてきた。
(2) 被控訴人は、「権力的作用について国が賠償責任を負わないことは,裁判例をまつまでもなく確立されており,裁判例により形成された法理ではなく,むしろ,それまで国が賠償責任を負わないとされていた非権力的公行政について,大審院判例によって国が賠償責任を負うとされ,いうなれば「非権力的公行政有責任原則」が判例法理として形成されたとでもいうべきである。」(被控訴人第1準備書面14頁)と主張する。
しかし、前述のとおり、国家無答責の法理は、天皇主権の明治憲法下での一法解釈にすぎず、明治23年の時点において、「裁判例をまつまでもなく確立されて」いたと断定できるような状況は全く存在していなかった。よって、被控訴人の主張は失当である。
もっとも、大審院時代の判例は,当初は,私経済活動を除く行政作用,すなわち権力的公行政及び非権力的公行政のすべての領域について,国家賠償責任を否定していた。よって、国家無答責の法理なるものが、明治期において、民法の適用範囲をめぐる裁判例の集積途上の法理であったことは認めざるをえない。
だとしても、控訴人ら第1準備書面において既に述べたとおり(第1準備書面21頁から27頁)、大審院時代の判例は、大正・昭和に至る判例の集積の中で、様々な分野で国及び公共団体の損害賠償責任を拡大することにより,国の責任を肯定してきたのであり、昭和10年代には、国家無答責の法理なるものは、否定されつつあったのである。
(3) これに対し、被控訴人は、「公務員が職務に関してなした不法行為は,大きく分類すれば,権力的作用についてなされた場合と,それ以外の作用についてなされた場合とに分かれる。後者には,①非権力的・非強制的な公行政の作用(例えば,国・公立学校における教育活動の作用や生活保護などのいわゆる給付行政の分野における作用など),②公の営造物の設置・管理の作用,③工事の施行(国の道路建設など)や事業の経営(鉄道・バス・水道・電気・ガスなどの事業の経営)の作用,④純然たる私経済的作用(たとえば官庁事務用品の購入・官庁建物の賃借など)などが含まれる。」と述べたうえで、「このうち判例は,権力的作用の場合については,一貫して,法律に特別の規定がない限り民法の不法行為法の適用がない(民法は対等な私人間の法律関係に関する法であり,国と私人との権力的関係に本来適用されるものではない)ものとして,国の賠償責任を否定していた。」として、「権力的作用については,民法の不法行為法の適用がないという国家無答責の法理は,判例上も当然の前提とされていたものである。」と主張する(被控訴人第1準備書面13頁)。
しかし、上記主張は、①国家無答責の法理を「権力的作用については,民法の不法行為法の適用がないという・・・法理」と定義している点と、②判例が、権力的作用の場合については,一貫して,国の賠償責任を認めていないとする点で、不適切である。
(4) 被控訴人が、国家無答責の法理を「権力的作用については,民法の不法行為法の適用がないという・・・法理」と定義している点について
明治期における大審院判例は,私経済活動を除く行政作用,すなわち権力的公行政及び非権力的公行政のすべての領域について国家賠償責任を否定していたのものである。
この点に鑑みれば、裁判例の集積途上にあった国家無答責の法理なるものが、「権力的作用については,民法の不法行為法の適用がない」というような狭い範囲を対象とした法理であったとは考えにくい。よって、被控訴人の定義の仕方は失当である。
むしろ、権力的作用についてなされた場合であると、それ以外の作用についてなされた場合であるとを問わず、公務員が職務に関してした不法行為につき国は賠償責任を負わないという法理であったものと考えられる。
しかも、かかる広い範囲を対象とした国家無答責の法理は、司法裁判所の裁判例の集積によって徐々にその範囲を縮小し、昭和10年頃にはほぼ否定されつつあったのである。すなわち、司法裁判所の裁判例の集積を経て、昭和10年代の判例、学説では、権力的作用に関する行政の不法行為について、民法を適用し損害賠償責任を認める方向に来ていたのである。
被控訴人は、このような判例・学説の流れを、国家無答責の法理を縮小・消滅させる流れであるとは認めずに、そもそも、権力的作用についてなされた公務員の不法行為のみが国家無答責の法理の対象だったのであると考えているようである。
しかし、国家無答責の法理を縮小させる判例の流れのなかでも、判例が一貫して国の賠償責任を否定してきたと被控訴人が考える部分(権力的作用についてなされ不法行為)のみを捉えて、はじめからその部分のみが国家無答責の法理の対象だったのであるということは、不当である。
(5) 被控訴人は、「判例は,(1)権力的作用の場合については,一貫して,法律に特別の規定がない限り民法の不法行為法の適用がない(民法は対等な私人間の法律関係に関する法であり,国と私人との権力的関係に本来適用されるものではない)ものとして,国の賠償責任を否定していた。」と主張する。
しかし、第1準備書面で述べたとおり、国家無答責の法理を縮小・消滅させていく判例の流れの中で、大正末から昭和の初めには、軍施設、学校等に関する賠償または賠償責任等が認められ、
昭和10年代には、権力的作用に関する賠償責任が認められたのである。
a 大正末から昭和の初めに、軍施設、学校等に関する賠償または賠償責任等が認められたことについて
被控訴人は、①軍艦の修復工事中の職人の墜落事故に関する広島地方裁判所呉支部大正13年6月5日判決(法律新聞第2282号5290頁)について、国が職工等の私人を使用して工事を行う場合は,その行為の性質上私法的行為であるから賠償責任があるとしたものであり、②関東庁高等法院上告部昭和7年7月20日判決(法律新聞第3539号8675頁)について,当該小学校の教育事業は,国の教育事業ではなく南満州鐵道株式会杜の事業である旨判示し,同株式会杜に賠償責任を認めたものであり、陸軍傷病兵療養所の井戸堀り工事に関する大審院昭和7年8月10日判決(法律新聞第3453号10983頁)
について、そもそも井戸堀工事が国の権力的作用に当たらないことからすると,上記「行政作用」とは井戸堀工事という非権力的作用をいうものと解されるので、同判決が,国の権力的作用について,民法の不法行為責任を認めたものとはいえないと主張する(被控訴人第1準備書面15頁、16頁)。
しかし、軍施設、学校等に関する行為は、当時は公権力の行使(権力的作用)といえるものであり、不法行為者が国家であろうが私人であろうが区別されないとして、公権力の行使(権力的作用)による損害についても、民法を適用して損害賠償責任を認めるようになったのであり、被控訴人の主張は失当である。
b 昭和10年代には、権力的作用に関する賠償責任が認められたことについて
被控訴人は、大審院昭和11年4月15日判決(新聞3979号)、大審院昭和15年2月27日判決(民集19巻6号441頁)は、金員の借入行為に関する事案であり、国の権力作用ではないと主張する。
しかし、出納事務は、財政権の公権力行使であり、いずれも民法44条を適用して賠償責任を認めた。
また、被控訴人は、千住町流しタクシー差押事件について、差戻し後大審院は,最終的には,東京市に対する賠償責任を否定していると主張する。
しかし、公権力の行使(権力的作用)そのものである徴税滞納処分に関する事件について,第二審裁判所→大審院→差戻後第二審裁判所→大審院と,公法人の損害賠償責任を認め,また否定するなど,判例の姿勢は,一貫して国の賠償責任を否定しているとは到底言えない。{大審院昭和15年1月16日判決(大審院民事判例集19巻20頁),大審院昭和16年2月27日判決(大審院民事判例集20巻118頁)}
大審院は,昭和15年1月16日に第二審に差し戻した際には,滞納税金の徴収のための差押及び公売といえども,それが限度を超えてなされた場合には「名は滞納処分なれども実は職権濫用にして寧ろ職権行為にあらざるもの」として,不法行為法の責任を負う可能性を認めている。しかも,その結論として,東京市の賠償責任を否定した原審を破棄したのである。
被控訴人が主張するとおりに,公権力の行使については国家無答責の法理が適用されることが確定的な解釈であったのであれば,大審院はこの時点で,東京市は不法行為上の責任は負わないものすればよく,東京市に対する請求については原判決を破棄する必要はなかったのである。
にもかかわらず,大審院は,上記のとおりの理由で,東京市に対する請求についても,それを認めなかった原判決を破棄しているのである。すなわち,昭和15年1月16日の大審院判決は,東京市の不法行為上の責任を認める(あるいは,少なくとも認める可能性がある)ことを前提としているのである。
被控訴人は,昭和15年1月16日判決について,「「公務員個人」の賠償責任について,…これを認めたものであり,国や公法人の責任について判示したものではなく」と評価する(被控訴人第1準備書面18頁)が,これは,上記のとおり,東京市の責任を否定した原判決を破棄したという点を看過するものであり,同判決を適切に評価しているとは言い難い。
また,同事件において,最終的に東京市の賠償責任は否定されたものの,そこには,戦前の訴訟構造として,行政裁判とその他の裁判が分けられていたことが,影響を及ぼしていると見るべきである。
すなわち,手続法的に,行政作用に関する損害賠償は,通常事件と行政事件の双方に関わるため,民事裁判手続きにおいて審理することが適切であるか否か,疑問がないわけではなかった。この観点から,実体法上の権利義務の存否とは別の次元の問題として,手続法上,民事事件として扱うことを否定するとの考えはあり得た。大審院は,同事件において,最終的にはその観点から,東京市の責任を民事訴訟においては否定したと理解することができる。
このことから,「戦前の大審院判例は,…公権力の行使(権力的作用)による損害については一貫して国の賠償責任を否定していた。」との被控訴人の主張は,大審院判例の評価を明らかに誤っている。
3 国家無答責の法理を否定する学説の存在について
被控訴人は、渡邊宗太郎教授、三宅正男教授が国家無答責の法理を否定する学説を展開していたことを認めながら、異説であって、美濃部達吉、佐々木惣一、田中二郎の各博士は、国家の権力的作用について国家の損害賠償責任が否定されるとしていると主張する。
しかし、上記の美濃部達吉、田中二郎を含め、学説は、判例を指導する形で、明治期、大正期、昭和期の時代の進行と共に、国民の権利救済を拡張する理論を展開してきた。
大正期には、非権力作用及び工作物の設置、管理に関する行政の不法行為については、民法不法行為法により損害賠償責任を認めるのが通説になった。これらの学説は、判例の検討を踏まえ、あるいは憲法や国家理論として成立してきた「機関理論」の視点から、さらには「使用者責任論」等を踏まえて、その考察の上に理論化されている。
さらに昭和10年代には、権力的作用に関する行政の不法行為について、非権力作用と区別する必要がなく、民法不法行為法を適用し損害賠償責任を認めるべきとするのが通説になりつつあったと思料される。
しかも、昭和10年代という治安維持法下の学問、思想に対する弾圧が最も激しかった時期に、実社会における市民感情(法的正義の実現)や具体的衡平性、損害の社会経済的衡平分担などの視点をも十分に踏まえて発表されたことを考慮に入れると、渡邊宗太郎、三宅正男の各学説は、学会の通説になっていたと思料され、被控訴人の主張は失当である。
こうした学説の存在をみれば、国家無答責の法理は確立されていないことは明らかである。
4 現行民法の立法者意思について 被控訴人は、民法715条について、「現行民法715条(草案723条)の法典調査会における審議の結果は,国の権力的作用より広く,政府の官吏が職務を行うについて,その職務が「私法上の関係」でなく「公権の作用」である場合には,現行民法715条(草案723条)の適用がないことが確認されているのである。」と主張する。
しかし、被控訴人の引用する起草委員の穂積陳重、梅謙次郎、富井政章の法典調査会での答弁及びその後の著作を検討しても、起草委員は,政府の官吏がその職務執行による賠償責任について,その行為が私法上の行為である場合には,本条の適用があるものと考えていたが,それ以外の公法上の行為については、民法の715条を適用するのではなく、後日制定されるであろう特別法に委ねるという意思を有していたもので、国が損害賠償責任を有することを前提にしていたと思われる。
しかも、穂積陳重が、「官吏の職務執行の場合に,本条が適用されるのがよいと我々は決めていない。我々が研究してみると,時として民法に書いている国もありますから,これも書こうかと思って相談してみましたが,特別法ができるだろうと思いましたから止めたのであります。特別法が出来ぬということを予想してこれで突き通すというのではない。もし,特別法が出来なかったら,本条がどう解釈されるかということを問われますから,特別法がない以上,例えば軍艦が一個人の商売船と衝突してその船を沈めたとかいうような場合に,賠償を求めるというには本条があたりはしないかというご相談をしたので,特別法を作らないでこれで押し通してしまうというだけの決心は我々3人ともなかったのである。しかしもし特別法がなかったならば,本条が当たるだろうという考えは3人とも持っている。」(被控訴人第1準備書面30頁、31頁)と答弁しているように、起草者らは、特別法が制定されない場合には民法715条を国にも適用すべきであると考えていたことが明白である。
第3 本件細菌戦は、保護すべき公務ではないから、「国家無答責の法理」は適用されない
1 被控訴人は、国家無答責の法'理の内容が,「①民法の不法行為の規定の適用がないことと,②その他賠償責任を認める規定がないことを含むもの」であり、「国の賠償責任を認めた規定が存在しないが故に国が賠償義務を負わないというものであり,問題とされている権力的作用に法的根拠があるか否かは全く問題とならない。」と主張する(被控訴人第1準備書面34頁から35頁)。
たしかに、明治憲法下では、現行の国家賠償法のような国の賠償責任を認める特別法はなかった。よって、「他に賠償責任を認める規定がなかった」ということはできる。
しかし、「民法の不法行為の規定の適用がない」ということは、一つの法解釈にすぎない。なぜなら、民法の不法行為に関する規定の中には、国の賠償責任を否定した規定はなく、また、戦前において、国家無答責の法理を明記した成文法(実定法)は存在していなかったからである。
被控訴人は、「他に賠償責任を認める規定がなかった」という事実と、「民法の不法行為の規定の適用がない」という一法解釈とを同列に並べたうえで、「このように、国家無答責の法理は,国の賠償責任を認めた規定が存在しないが故に国が賠償義務を負わないというものである」という。
しかし、一法解釈にすぎないものと、歴然たる事実とを同列に扱うことはできない。まして、「他に賠償責任を認める規定がなかった」という事実と、「民法の不法行為の規定の適用がない」という一法解釈とをひっくるめて、「国の賠償責任を認めた規定が存在しない」という事実に置きかえることはできないはずである。
2 そもそも、国家無答責の法理が、公務員の違法な行為について国の賠償責任を否定するのは、公務を保護するためである。とすれば、国家無答責の法理が適用されるためには、問題とされる行為が、保護すべき公務に向けられた行為である必要がある。よって、公務員の違法行為のうち、強度の違法性を有する公務に向けられた行為には、国家無答責の法理は適用されないものと解されるべきである。
これを本件細菌戦について見ると、戦争行為による相手国の人間に対する殺傷が公法関係として認められたとしても、それは一定の範囲内に限定されるのであり、戦争行為だから何をやってもよいということではない。
本件細菌戦は、原判決が認定するように、ジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法に違反した違法行為であり、かつ、被控訴人に、細菌戦被害者が受けた損害を賠償するというハーグ陸戦条約第3条を内容とする国際慣習法による国家責任が生じていたのである。
また、第1準備書面でも述べたとおり、本件細菌戦は、第1点に、被控訴人自身が違法な戦争行為であることを充分に自覚し、承知しながら、被控訴人による組織的、計画的行為として行われた大規模な戦争行為だという点、第2点に、大量破壊兵器による非戦闘員たる一般住民に対する無差別な殺傷だという点
、第3点に、本件細菌兵器の研究、開発が生体実験等の違法行為を伴うことによって、世界で初めて本格的な細菌兵器の開発を可能とし、実戦使用したという点において、強度の違法性、悪質性を有する公務であった。
したがって、このような強度の違法性を帯びた本件細菌戦が、保護すべき公務にあたらないことは明白であり、国家無答責を適用する根拠がない。
第3 「国家無答責の法理」は外国での外国人に対する権力作用には適用されない
1 被控訴人は、「外国における軍人の行為も,国家主権に基づく行為であることに変わりはなく,外国における外国人に対する行為であるからといって,民法が軍人の行為を私人の行為と同様に取り扱うことを予定しているものとは考え難い。(中略)国の権力的作用による以上,民法の不法行為規定は適用されず,国家無答責の法理によるべきである。」と主張する(被控訴人第1準備書面36頁)
しかし、命令、強制権の及ばない他国に在住する他国民、しかも、占領、支配下にあるともいえない他国民にまで、無答責の抗弁が通用するなどということがありよう筈がない。
原判決ですら、「本件細菌戦による被害は誠に悲惨かつ甚大であり、旧日本軍による当該戦闘行為は非人道的なものであった」と評価し、「ヘーグ(ハーグ)陸戦条約3条の規定を内容とする国際慣習法による国家責任が生じていると解するのが相当」と断じている。
本件を含み凡そどのような残虐、非道な行為でも権力作用の名において全て責任を問われないなどという理不尽が古今東西に通用する筈もない。日本の司法だけが、このように国際社会に通用しない「切り捨て御免」の愚論を今に至ってなお後生大事に維持している現状は、まことに恥ずべく嘆かわしい限りである。日本を国際人権社会から孤立せしめる所以である。
2 国家無答責の法理の法理が確立していたとしても,本件のような外国での外国人に対する権力作用には適用には適用されるべきではない。
たとえ国家無答責の法理が戦前において確立していたとしても,本件のごとく,戦争の相手国国民との間で,戦争行為による損害賠償請求に関しては,適用されるものではない。これは,被控訴人が引用する,国家無答責の法理の根拠に照らして,明らかである。
被控訴人は,「我が国の代表的な公法学者」の見解として,美濃部達吉博士,佐々木惣一博士及び田中二郎博士の見解を引用している(準備書面(1)19〜21頁)。このうち,佐々木博士の見解は国家無答責の法理の根拠を示した上での論ではないので,美濃部博士及び田中博士の見解について検討する。
これらの見解は,「統治權の作用は私人の行爲とは性質を異にし…國家はそれに付き損害賠償の責に任ずるものではない。…それが統治權に基づく強制權の作用である限り…國家に對して損害賠償を請求し得べきものではない。」(美濃部),あるいは「權力的作用とは國家が個人に對して命令し服從を強制する作用であり,…此の權力的作用によって違法に他人の權利を侵害することがあったとしても−特別の規定のない限り−國家としては一々責任を問わるべきではないと解する外はない。」(田中)というものである。
これらの見解を一読して理解できることは,ここで問題とされているのは,統治権の作用によって損害が発生したとしても,賠償義務は発生しないという点であり,すなわち,統治権の範囲であれば国家は無答責であるということである。
これは,国家の統治権が及ぶ範囲内の者との間の関係においてのみ,妥当しうる理論である。しかし,国家と外国に存在する外国人との関係においては,原則として国家の統治権が及んでおらず,これらの見解の拠っても,国家無答責の法理が適用される根拠がないことになる。
いわんや,戦争において,戦争相手国の国民に対する戦闘行為が,その被害者に対する関係で統治権による行為であると説明することは不可能である。
控訴人らは,日本人ではなく,大日本帝国の統治権に服していた者ではない。
したがって,たとえ国家無答責の法理が確立していたとしても,本件では,同法理が適用される余地はない。
第4 ハーグ条約の国内法化によって「国家無答責の法理」は排除され適用されない
1 被控訴人は、「ヘーグ陸戦条約の規定が,そもそも被害者個人の加害国に対する損害賠償請求権をその内容として保障していない以上,ヘーグ陸戦条約の規定が国内法的効力を有するとしても,それにより当該規定が保障していない個人の損害賠償請求権が国内法的に創設されるということはあり得ず,国家無答責の法理と何ら抵触を生ずるものではない。したがって,本件についてヘーグ陸戦条約の国内法的効力を論じてみても,これをもって,国家無答責の法理が排斥され,控訴人らの請求が法的に根拠づけられるものでもない。」と主張する(被控訴人第1準備書面40頁)。
2 しかし、ハーグ条約が、日本国内において、法律などと同様に適用されるためには、国内法による補完・具体化がなくとも条約の内容上そのままの形で国内法として直接に実施され、私人の法律関係について国内の裁判所と行政機関の法規範として適用できること、すなわち、「自動執行力」が認められなければならない。(なお、条約規定の自動執行性と直接適用可能性については、両者を同義のものとして互換的に用いる用法が多いため、ここでは一般的な用法に従う)
3 この点につき、条約規定が裁判所でそのまま適用できるためには、「主観的要件」と「客観的要件」とを充足していなければならないとする主張がある。
すなわち、主観的な要件として条約の作成・実施の過程の事情により、私人の権利義務を定め直接に国内裁判所で執行可能な内容のものにするという、締約国の意思が確認できることが必要であり、客観的要件として、私人の権利義務が明白かつ確定的、完全かつ詳細に定められていて、その内容を具体化する法令にまつまでもなく国内的に執行可能な条約規定であることが必要、という主張であり、被控訴人も同様の主張をする。
しかし、このうち主観的要件、すなわち国家が条約作成当時にそれが国内裁判所で直接適用できることを意図していたことという要件は不要というべきである。
国際法たる条約は元来、実現すべき結果を国家間で合意し、それを各国が実現する具体的な手法は、それぞれの国に委ねるという方式をとるものが普通である。従って、条約の締結にあたっても、条約の当事国は、条約が国内で実現されるという結果に最も関心をもち、実現方法については関心をもたないのが通常であるから、条約が直接適用可能であるとの当事国の積極的な意思が条約中に明示されることはほとんどない(甲221号証 岩沢雄司『条約の国内適用可能性』有斐閣、1985年、153頁)。条約の直接適用可能性の問題について詳細な研究を行っている岩沢教授によれば、直接適用可能性についての当事国の意思とされるものは、たいていは「全くの擬制的な意思」(同)にすぎない。条約起草時の当事国の主観的な意図を要件とすることは、端的に言って不適切である(甲219、甲222号証)。
4 また、客観的要件として、私人の権利義務が「明白、確定的、完全かつ詳細に」定められていることが挙げられるがあるが、そのような厳格な条件が必要かどうかは疑問である。条約を含め、法規定は本来的に、後に解釈により意味内容が発展せられることを予定して、ある程度一般的な用語で規定されているものである。国内実施を予定している条約であれば、その規定中の法概念がいかなる意味内容をもつかは、それぞれの締約国における国内判例の蓄積や学説の発展に応じて、確定されていくのである。
したがって国内裁判所は、条約の解釈・適用にあたっては、国際法上認められた条約の解釈原則(ウイーン条約法条約)に従い、条約の趣旨目的に照らして条約の文言を誠実に解釈し、求められている司法判断を行う目的からみて十分な明確性をもつと考えられる場合には、それに基づいて結論を下すことができる。条約が個人の権利を認めており、それが国家の作為によって侵害されたと考えられる場合には、その違法認定と救済は比較的容易なはずであり、条約の自動執行性の客観的要件に高い壁を設けることは不必要である。
5 そしてそもそも、条約は憲法上、国家による批准と交付を以て、国内的効力を有するのであるから、その条約が内容上明確に締約国に対して条約の実現のための立法または行政措置が必要であると明記している場合、又は規定の文言上その実施について国内立法又は行政措置を明らかに予定している場合、若しくは条約の文言上に現れた締約国の意思から直接適用が否定されていると考えられる場合以外は、原則として他の法令と同様に、裁判所において直接適用が可能であると解するべきである。
6 仮に、条約に自動執行力が認められるためには、主観的な要件と客観的要件が必要であるとしても、ハーグ条約3条はそのいずれをも充足しているというべきである。
すなわち、まず、締約国の意思については、前述した同条の制定過程、特にその提案理由をみれば、同条が加害国に対する被害者個人の損害賠償請求権を定め、かつ直接に加害国に損害賠償を求めることを締約国が承認して締結したことは疑いの余地はない。
次に、同条約3条の規定の内容も、極めて明確であるといえる。そもそも明確性が要求される根拠は、それが国内的に執行されることにより国内の法的安定性を害してはならないという要請からである。したがって、明確性の程度は、同種の国内法と同程度であれば足り、それ以上である必要はない。
わが国の不法行為の一般原則を定める民法709条は「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタ」と極めて一般的に不法行為の発生要件を定めているに過ぎないし、また、国の不法行為賠償責任を定める国家賠償法1条も、「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは」と極めて抽象的文言で規定されている。これらの条文中の各要件の具体的内容は、裁判所の判例の積み重ねによって決められている。
このようなわが国の制度に照らしてみるならば、ハーグ条約3条の規定の方がより具体的かつ詳細な要件を規定していることは一見して明らかである。ハーグ条約3条は、日本の国内法として充分な明確性を有している。
7 以上の検討から、ハーグ条約3条が自動執行力を有することは疑問の余地がない。
第5 「国家無答責の法理」は一法解釈にすぎず、現在の法解釈に基づき裁判すべき
1 被控訴人は、「明治憲法下において合理性のあつた国家無答責の法理を日本国憲法を前提とする現在の価値観によって否定して,特別の規定がないのに,無答責であつた行為につき,賠償責任を認めることは法の解釈として許されない」と主張する(被控訴人第1準備書面43頁)。
しかし、国家無答責の法理は、訴訟法上の救済手続が欠如していることを意味する訴訟上の一説にすぎない。明文(行政裁判所法16条)をもって否定されていたのは行政事件としての訴訟要件という点においてのみであり,行政作用に関しては別途行政裁判所が設けられているという事情から,民事訴訟の手続きにおいて判断することが差し控えられただけである。
そうであるならば,行政裁判所が廃止され,全ての事件を司法裁判所が審理することとなった現在の手続法の下においては,行政作用に関する損害賠償請求訴訟も司法裁判所が審理することになんの障害もなく,もともと実体法上は国家無答責の法理なるものは認められていなかったのであるから,戦前における行政作用に関する損害賠償請求訴訟について,現在,司法裁判所が現在の手続法の下で審理することには,なんの問題もない。
2 この点について、東京高等裁判所民事第16民事部平成15年7月22日判決は、アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求控訴事件に関して、「戦前において、上記のような解釈が採られていた根拠は必ずしも明らかではなく、結局、国の権力作用に伴う不法行為に基づく損害賠償請求訴訟については司法裁判所において民事裁判事項と認めず行政裁判所においても行政裁判事項として認めず、ともにその訴訟を受理しなかったため、その種の損害賠償請求を法的に実現する方法が閉ざされていただけのことであり、国の権力作用による加害行為が実体的に違法性を欠くとか有責性を免除されているものではなかったと解すべきである。いわゆる『国家無答責の法理』は、上記のような訴訟要件としての権利保護適格を否定する解釈が採られていたことによるものにすぎず、行政裁判所が廃止され、公法、私法関係の訴訟を司法裁判所において審理されることが認められる現行憲法及び裁判所法の下においては『国家無答責の原理』に正当性ないし合理性を見い出し難い。もともと国家賠償法は民法709条以下の不法行為法の特別法である性格も有し、国家賠償法の制定がなければ賠償請求権の実定法上の根拠がなかったと解すべきではなく、一般法としての民法709条以下の不法行為法が原則として適用されると解すべき余地が十分にあり得たものであり、民法715条の文言上は、公務員の公権力の行使が同条の適用から排除されているとはいえないこと、行政裁判法16条が『行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス』と規定しており、同条の規定は、実体法上は、公権力の行使に違法があった場合に国に損害賠償請求権が成立することを前提としながら、行政裁判所が損害賠償請求訴訟を受理しないという訴訟法上の規定を置いたにすぎないものと解され、他方、司法裁判所も前提問題として行政処分等公権力の行使の適否、瑕疵を判断しなければならない時は、行政裁判所による行政裁判手続きを設けた趣旨にかんがみ、結局司法裁判所が判断し得る司法上の民事裁判事項ではないとして権利保護適格を認めなかったにすぎないと解されるから、現行憲法及び裁判所法の下において裁判所が国家賠償法が施行される以前の法体系の下における民法の不法行為の規定の解釈・適用を行うに当たっては、訴訟手続き上の制約が解止されたものと考えるのが相当である」と、戦前における行政作用に関する損害賠償請求訴訟について、民法による損害賠償法理の適用があることを判示している。
第6 国家賠償法附則6項の「従前の例」について
被控訴人は、中国人強制連行事件に関する東京地方裁判所民事第25部2003年3月11日判決について、国家無答責の法理の根拠の理解が不十分であると縷々批判をし、国家賠償法附則6項の「従前の例」の規定によって、本件細菌性に国家無答責が適用されると主張する。
しかし、国家賠償法附則6項の「従前の例」とは、同法が存在しない従前の実体法によることを意味し、戦前の一つの判例解釈に従う必要はない。
この点について、東京地方裁判所民事第25部2003年3月11日判決は、「国家賠償法附則6条において、『この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。』と規定され、同法の規定の遡及適用が否定された以上、同法施行前の公務員の公権力の行使の違法を理由とする国の損害賠償責任に関しては、民法の不法行為に関する規定が公務員の公権力の行使についても適用があるか否かという民法の解釈にゆだねられていたと解するよりほかはない」としたうえで、「戦前の裁判例及び学説に照らすと、『国家無答責』なる不文の『法理』が確立しているとの理解を背景として、上記のような解釈が採られていたことがうかがわれるものの、現時点においては、『国家無答責の法理』に正当性ないし合理性を見いだし難いことも、原告らが主張するとおりである。当裁判所が国家賠償法が施行される以前の法体系の下における民法の不法行為の規定の解釈を行うに当たり、実定法上明文の根拠を有するものではない上記不文の法理によって実定法によるのと同様の拘束を受け、その拘束の下に民法の解釈を行わなければならない理由は見いだし難い」と、「従前の例による」ことが、国家無答責を適用しうる根拠とならないことを鮮明に判示しているといわねばならない。
この点について、前述の東京高等裁判所民事第16民事部平成15年7月22日判決は、「同法附則6項が民事裁判事項であることを依然として否定する訴訟手続規程であると解するのは疑問がある」と述べ、「従前の例による」ことが、国家無答責を適用しうる根拠とならないことを判示している。
第3章 除斥期間の適用制限について
第1 被控訴人の主張
民法724条後段につき、仮にこれを除斥期間であるとしても、その適用が著しく正義・公平に反し、条理にもとる場合には、これを適用すべきでないとの控訴人らの主張に対し、被控訴人は、次のとおり反論している。
1 最高裁平成10年判決は、時効の停止に関する民法158条を類推適用して、後見人就任後(権利行使が可能になった後)6ヶ月以内に権利を行使した場合を限定して例外的に救済したのであるから、これを一般に拡げて解すべきではない。
2 同判決は、他の法文に根拠を求めることができる例外的な場合に限られることを示したものである。
3 本件控訴人らにとって「権利行使が不可能」だったとはいえない。訴訟代理人の協力が得られなかったとか、訴訟準備が整わなかったとかいうことは、権利行使が不可能という理由にはならない。
4 本件では、時効の停止等のような除斥期間の適用を制限する根拠となるものは存在しないし、控訴人らはそのようなものの存在を主張もしない。
5 控訴人らの主張を容れるとすれば、極めて広範且つ無限定に除斥期間の適用が制限され、法的安定性を重視して民法724条後段の除斥期間を設けた法意に反する。
6 不法行為の悪質性や被害の重大さを理由とする除斥期間適用制限は最高裁平成10年判決の射程を超える。
第2 控訴人らの反論
前項各号に示した被控訴人の主張は正当ではない。控訴人らは各号毎に順を追って以下のとおり反論する。
1 最高裁平成10年判決を被控訴人のいうように狭く解釈しなければならない理由はない。そもそも被控訴人のいう如く、時効と除斥期間とを厳密に別扱いするという理論を前提とするのであれば、本来権利の上に眠るという主観的な事由によって保護を奪う時効の制度の中で例外として認められた救済規定(民法158条、161条等)を、無理に除斥期間適用制限の場面に類推適用すること自体が合理性を欠くのであり、同判決はその点では余分の判断をしたものということが出来る。即ち、同判決で強調したかったことは、心神喪失の常況が当該不法行為に起因する場合であるにも拘らず、被害者にとって権利行使が不可能であるのに、常に20年経過したというだけで一切の権利行使が許されないこととなる反面、心神喪失の原因を与えた加害者は20年の経過によって損害賠償義務を免れる結果となり、著しく正義・公平の理念に反するという点なのである。もともと権利行使が不可能であったとすれば、20年経過したとしても救済すべきであり、このことを除斥期間適用制限の理由としても何ら差支なかった筈であるのに、時効例外規定を利用したことが理論の混乱を導いたのである(尤も、心神喪失という個人的な事情の場合、本人には責任がなくとも周囲の者が長期間後見人を付する等の配慮を怠った点で、全く問題なしとはしない)。ともあれ、本最高裁判決は権利行使が不可能のまま20年経過した被害者を救うことが正義であり、加害者を20年経過したということだけで放免することが不公平であるという正義・公平の原則を謳ったものである。
2 他の法文に根拠を求めようとしたことに合理性がないのであり、正文規定が無い以上、正面から、正義・公平・条理を持ち込むべきであった。
3 本件控訴人にとっては正に客観的に「権利行使が不可能」であった。訴訟代理人不在とか訴訟準備困難とかは、権利行使不可能の理由の主なものではない。被害者らはいずれも中国に住む中国人(外国人)なのであり、中国の国内事情や国際的な諸事情の推移を考えれば、到底権利行使が不可能であったことは明白である。被控訴人が、被害発生後20年以内に行使が可能であったというのであれば、どのような方法があったのか教示されたい。
なお、東京地裁平成15年9月29日判決(甲491)では、「原告ら中国の国民は、1986年2月に中華人民共和国公民出国入国管理法が施行されるまでは、私事で出国することは制度的に不可能であった(甲203)。原告らが被告に対して権利行使をすることは、1974年10月の事故の時から法の施行までの11年余りの間は、客観的に不可能であったといえる。」として、1986年2月に中華人民共和国公民出国入国管理法が施行されるまでは、自ら訴状を携えて日本国の裁判所を訪れることは制度的に不可能であったとし、被害者らが権利行使することは客観的に不可能であったと判示している。極めて貴重な見解である。
4 時効の停止のような類推根拠規定がないという被控訴人の反論に対しては、上記3で述べたとおりである。
5 法的安定性は確かに除斥期間制度の根拠ではあるが、控訴人らは無限定にこの制度の例外を拡げようとする訳ではない。本来国内の市民間の法律関係を調整する法的安定性を本件のような国家による非人道行為の場面に持ち出すことがそもそも問題である。国際人道法、正義・公平の原則こそが、優先されるべきである。
先ず、加害国である日本国が自ら国内私法として設けた時効や、除斥期間の制度を、自己の外国人に対する義務の免脱のために利用しようとする考え方が矛盾している。
この点につき前記東京地裁判決は、「原告らが訴えを提起したのは、事故から20年が経過した時点から、約2年後である。それにもかかわらず20年が経過したということだけで権利行使を許さないとすることは、衡平を欠く(外国にいるために客観的に権利が行使できない期間という意味では、その期間について時効の停止を認める公訴時効の停止の考え方(刑事訴訟法255条1項)に合理性があり、参考になる)。」とし、正義公平の理念を法理に貫くものとして、刑事訴訟法255条1項の公訴時効停止の考え方を示している。
6 不法行為の悪質性・被害の重大性こそが本件において最大に重視されるべきであり、これが正義公平の理念に関する判断にとって決定的な要因になることはいうを待たない。本件は人類史上類を見ない悪質・残虐な国家行為であり、そのために奪われた無数の罪なき人々の生命、人間の尊厳、名誉の重大性は、測り知れないのである。自己が作った法で自己を守ることは、恰も「家法」を他人に強制するに等しい。
第3 本件細菌戦にこそ除斥期間の適用制限がなされるべきである
1 除斥期間の適用による被控訴人保護の不適格性と時効の停止
被控訴人の本件不法行為は、日本の中国侵略戦争における細菌戦の実行
という、史上類例のない残虐な行為である。このことは、民法724条後段の適用に当たって十分斟酌されなければならない要素である。
被控訴人の本件不法行為は、非戦闘員たる一般住民を無差別大量に殺戮することを狙った違法性の極度に高い残虐行為である。細菌戦がもたらした感染症によって犠牲者、被害者となった控訴人らには何の落度もなく、ある日突然原因不明の疫病によって苦しめられ、犠牲となったのである。その被害者らがなんら救済されずに数十年間放置され、一方、その加害者である被控訴人が何の責任も果たさずに今日に至っているという現状において、時の経過は、被害者の権利消滅をもたらすものではなく、一刻も早く控訴人が被害を償い、控訴人ら被害者を救済すべきことを迫るものである。
さらに本件細菌戦の違法行為において、極めて顕著な特徴は、被控訴人が、戦後において細菌戦の事実を隠蔽し、国際的国内的に日本軍の細菌戦が周知の事実となっている現在においても、その事実すら認めていないという点である。
被控訴人は、敗戦直前に、中国では731部隊本部等の施設を破壊し、人体実験のために収容していた捕虜の「マルタ」を全員殺害し、731部隊をいち早く撤退させた。日本では、敗戦と同時に、陸軍省軍事課等の命令により細菌戦関係等の日本軍公式文書の焼却・隠匿した。
被控訴人は、1945年8月にポツダム宣言を受諾し連合国側に無条件降伏した。翌1946年に行われたいわゆる東京裁判は、日本の戦争を侵略戦争と認定し戦争犯罪者らへの処罰を行ったものの、天皇を最高責任者とする細菌戦に関わった者たちのみは犯罪者としての糾弾から免れ、被控訴人が戦争遂行のために国家の政策として細菌兵器を開発したこと、これを用いて多くの捕虜を人体実験で殺害し、中国各地に撒布して何万という住民をペストで殺戮したという事実を、国家の方針として隠蔽したのである。
1947年、被控訴人は、隠匿していた731部隊関係の文書を免責と引き換えに米国政府に交付し、戦争犯罪の責任追及を逃れた。
以降、今日に至るまで、被控訴人は、本件細菌戦に対する責任を追及されることを恐れ、自ら所持する細菌戦関係資料を隠匿し、本件細菌戦の事実確認と証明を困難にしてきた。
このような被控訴人の隠蔽行為は、控訴人らの権利行使を著しく妨害してきた。実際に存在している資料を開示せず、井本日誌等の存在をつきつけられても、なお「資料が存在しない」等と言い逃れようとする本件細菌戦の隠蔽行為は、極めて悪質で、控訴人らの権利行使を意図的に妨害する新たな不法行為である。
本件控訴人らの権利不行使は、被控訴人が一国の権力をもって控訴人らの権利行使を妨害し、不可能にしてきた結果である。まさに被控訴人自身が、長きにわたって控訴人らの権利不行使を強要し、これによって時効を停止せしめている。
2 本件控訴人らの権利不行使に対する非難性の欠如
控訴人らは、日本の侵略戦争と、その後の内戦による都市、農村の荒廃に加えて、細菌戦の被害者であることによってさらに大きな苦しみを受けねばならなかった。本件細菌戦被害地において、控訴人らの多くは、一般流行の疫病にかかった者として扱われ、戦争の被害者としての正当な評価を受けることができなかった。
本件細菌戦による被害地住民は、戦後も長期にわたって疫病の恐怖から逃れることができず、地域社会としての復興は困難となった。また、疫病発生地として社会的な差別を受け、経済的かつ社会的不利益を蒙らざるえなかった。
このように、前記被控訴人による隠蔽行為、1972年まで断絶していた日中関係、日中共同声明における中国政府の賠償問題への対応などの客観的社会的状況に加え、控訴人らのおかれた生活状況からも、1995年頃までは、被控訴人に対する損害賠償請求権を行使することは事実上不可能であったのである。
除斥期間の適用制限について、前記東京地裁判決は、
「ア この除斥期間の適用の有無は、不法行為をめぐる法律関係を一定期間の経過によって確定させるという趣旨から考えれば、20年の経過という明確な基準で決すべきものではある。
しかし、このような除斥期間制度の趣旨を前提としても、その適用によって被害者の損害賠償請求権が消滅することになる反面で、加害者は損害賠償義務を免れる結果となるのであるから、そのような結果が著しく正義、公平の理念に反し、その適用を制限することが条理にもかなうと認められる場合には、除斥期間の適用を制限することができると考えるべきである。
イ 本件においては、除斥期間の対象とされるのは国家賠償法上の請求権であって、その効果を受けるのは除斥期間の制度を創設した被告自身である。ところが、被告が行った行為は、国際法的に禁止されていた毒ガス兵器を中国に配備して使用していた旧日本軍が、国際的非難を避けるためポツダム宣言にも違反して、終戦前後に組織的にそれを遺棄・隠匿したという違法な行為につき、戦後になっても被害の発生を防止するための情報収集や中国への情報提供をせず、1972年に中国との国交が回復された後も積極的な対応をしないで遺棄された毒ガス兵器を放置していたというものである。その行為には、わずかの正当性も認めることができない。」と被告国の違法行為を断罪している。さらに「これらの事情を考慮すると、本件において被告が除斥期間の適用によって損害賠償義務を免れるという利益を受けることは、著しく正義、公平の理念に反し、その適用を制限することが条理にかなうというべきである。」として除斥期間の適用制限を相当と判示している。
まさに上記判示の法理は、本件細菌戦にこそあてはまるものであるといわねばならない。
第4章 日中共同声明に関する被控訴人の主張に対する反論
第1 被控訴人の主張
1 控訴人らの従前の主張
控訴人らは、第1準備書面において、日中共同声明5項の「戦争賠償の請求を放棄」という条項に関して以下のように主張した。
① 日中共同声明では「請求権を放棄」したものではない。
② 日中共同声明の「賠償請求の放棄」には個人の賠償請求権は含まれない。
③ 細菌戦被害の賠償請求は放棄されない(第1準備書面74乃至81頁)。
さらに控訴人らは第1準備書面において、日中共同声明を論ずるにあたって、「この問題を考察するにあたっては、2つの論点が存在する。第1は、ハーグ条約第3条の性質、すなわち、ハーグ条約第3条のもつ目的・趣旨と、賠償請求権が個人にあるのか、国家にあるのか、という問題であり、第2は、日中共同声明における『賠償請求の放棄』の意味、すなわち、そこで放棄された賠償請求権の性格、範囲等の問題である」(第1準備書面128頁)とし、サンフランシスコ平和条約も踏まえたうえで、個人に請求権がある場合、国家(中国)に請求権がある場合に分けて詳細に論じ、いずれの場合も本件細菌戦に関する被控訴人の国家責任が存続しており、「日中共同声明によって決着した」という解釈は成り立たないことを論じた(同129頁乃至140頁)。
サンフランシスコ平和条約14条では、もともと個人の請求権が存在することを前提として、その「国民の請求権の放棄」が明文化されている。日中共同声明5項は、「中華人民共和国政府は、中日両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とうたわれているだけで、個人の請求権については明文化されていない。
控訴人らは、この日中共同声明で中華人民共和国政府が放棄した賠償請求権の範囲を、3つの異なる見解に即して検討した。すなわち、第1は、放棄したのは戦費等の賠償請求権であり、ハーグ条約第3条に基づく賠償請求権は含まれていないという見解。第2は、ハーグ条約第3条に基づく賠償請求権も含めて中国が放棄したという見解。第3は、日中共同声明5項の「戦争賠償」のなかに、本件細菌戦に関する賠償請求権は含まれていないという見解である(第1準備書面130頁)。控訴人は、これら3つの見解に即して論じ、いずれの場合も、中国国民の賠償請求権は放棄されておらず、被控訴人の国家責任は果たされていないことを論じた。
2 被控訴人の主張の骨子
これに対し、被控訴人第1準備書面は、「第8 日中共同声明について」(被控訴人第1準備書面93頁乃至125頁)という章を設け、反論を試みている。
被控訴人の主張は、「中国国民の日本国及びその国民に対する請求権は、国によって放棄されている。日中共同声明5項にいう『戦争賠償の請求』は,中国国民の日本国及びその国民に対する請求権も含むものとして,中華人民共和国政府がその『放棄』を宣言したものである」(被控訴人第1準備書面124頁)というものであるが、同第1準備書面においては、日華平和条約11条及びサンフランシスコ平和条約14条(b)をその根拠としていることが特徴的な点として指摘される。
すなわち、被控訴人は、以下のような段階論法で、中国国民の請求権も放棄されたことを主張する。
①1951年に締結(発効は1952年4月28日)されたサンフランシスコ平和条約14条(b)によって、連合国の国家としての請求権だけでなく、連合国国民の請求権も連合国によって「放棄」された(同107頁)。 ②1952年に締結された日華平和条約11条は、「この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外,日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は,サンフランシスコ条約の相当規定に従って解決するものとする」と規定しており、これによって中国及びその国民の請求権も放棄された(同119頁)。 ③1972年の日中共同声明5項にいう「戦争賠償の請求」は、「日華平和条約による処理と同じであることを意図したものである」(同121頁)。「したがって、共同声明5項は、『戦争賠償の請求』のみに言及しているが、ここには先の大戦に係わる中国国民の日本国及び日本国民に対する請求権の問題も処理済みであるとの認識が当然に含まれている」(同122頁)
この、被控訴人の主張が成り立つためには、第1に、サンフランシスコ平和条約14条(b)の条文によって、被害国国民、被害者個人の請求権は完全に消滅したこと。第2に、日華平和条約は、サンフランシスコ平和条約の枠内で締結された中国の合法政府との有効性をもつ講和条約であること。第3に、日中共同声明は、日華平和条約を受け継ぐものであること、の3点が前提とされる。
しかし、上記3点は、いずれも成り立たない議論であり、日中共同声明5項解釈の根拠を、サンフランシスコ平和条約と日華平和条約に求めるという被控訴人の主張は、それ自体失当である。
被控訴人の主張は、第1に、サンフランシスコ平和条約14条の解釈において、第2に、日華平和条約の解釈において、第3に、サンフランシスコ平和条約及び日華平和条約が日中共同声明の根拠となっているという解釈において、いずれも誤っている。
以下、上記3点について論じていく。
第2 サンフランシスコ平和条約14条の解釈について
1 サンフランシスコ平和条約14条、16条による賠償の軽減及び放棄
サンフランシスコ平和条約はその第14条(a)において、「日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛い対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在十分でないことが承認される」とした。
そして、被控訴人の賠償は、同(a)項1及び2に規定する役務提供(原材料は日本が負担しない)と連合国内の日本資産の没収に限定された。
さらに、同14条(b)では、「この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する」とされたのである。
また、同条約16条においては、「日本国の捕虜であった間に不当な苦難を被った連合国軍隊の構成員」に対する償いは、「非連合国にある日本資産」をもって充てることとされた。
この14条及び16条によって、第二次世界大戦において被控訴人国が連合国及びアジア、世界に与えた損害と苦痛の大きさに鑑みた場合、異例ともいえる賠償の軽減・放棄が行われたのである。ここで考慮しておかなければならないことは、被控訴人の戦争によって、最大の損害と苦痛を被ったのは中国・中国国民であるという点である。1949年に革命政権の成立した中国はアメリカの反共政策によりサンフランシスコ平和条約からは排除されていたが、上記14条は、中国及び中国国民にとって到底容認されないものであったことは明らかである。
2 ベルサイユ条約における失敗の反省から、第二次世界大戦後の賠償問題は軽減が図られた、という被控訴人の主張について
被控訴人は、「第一次世界大戦後に締結されたベルサイユ条約においては,ドイツは,交戦期間内に,陸上,海上及び空中の攻撃により同盟・連合国の国民やその財産に対して加えられた一切の損害を補償すべきものとされ(同条約232条),国家問の賠償責任が認められたほか,混合仲裁裁判所の制度を規定し,国民個人がドイツに対して,混合仲裁裁判所に提訴して,個人的な物的損害の賠償請求をすることを認めた」(被控訴人第1準備書面96頁)。その結果ドイツに対する賠償請求は巨額となり、ドイツ経済の破綻、ヒットラー政権の出現を招いた。
このベルサイユ条約の失敗の反省から、第二次世界大戦後の講和においては、「適正かつ妥当な解決を目ざすものとして位置づけられ」(同96頁)、その結果、「戦後賠償は,原則として国家間の直接処理,又は求償国内の旧敵国資産による満足の方法によることとして解決が図られ,個々の国民の被害については,原則として,賠償を受けた当該当事国の国内問題として,各国がその国の財政事情等を考慮し,救済立法を行うなどして解決が図られている」(同97頁)と主張する。
すなわち、被控訴人は、個人の請求を認めた場合には、賠償額は巨額なものとなってしまう。したがって「適正かつ妥当」な賠償としてサンフランシスコ平和条約14条が規定されたと、主張する。
しかし、周知のように、サンフランシスコ平和条約は、第二次世界大戦後のアメリカとソ連の冷戦構造、さらに1949年の中国革命政権の成立、1950年の朝鮮戦争の勃発という国際情勢の中で、アメリカの反共政策にもとづいて推し進められた講和であった。同14条における賠償の軽減も、冷戦構造の中での日本の戦略的位置からとられた措置であった。
この点は、被控訴人の提出した、「第二次世界大戦中の日本の強制労働訴訟」におけるアメリカ政府の提出した「利害関係声明書」(乙53号)にも明確に表されている。アメリカの「平和条約に署名し、批准するという国家的な決定は、日本が共産主義者の支配に落ちず、民主的で、経済的に成長しうる同盟国となることを確保したいという強い願望」(同1頁)に基づいてなされた。
サンフランシスコ平和条約14条によって日本の賠償が軽減された背景としては、次のようなことがいわれている。「賠償及びその他の戦争関連の請求権に関する合衆国及び連合国の取組は、日本国とその他の世界における状況の変化につれて、種々の外交政策及び公共政策の目的を反映するために占領期間を通じて発展してきた。合衆国の日本占領の初期においては、当然、日本人に対する戦争犯罪に係わる大きな怒りがあり、日本人が引き起こした損害に対する支払いを日本人に強制すべきであるという一般的な考え方があった。」しかし、「ソビエト連邦が極東において膨張政策を遂行していることが明白となってくるにつれて、トルーマン政権は、日本国は重要な同盟国として必要であり、合衆国は日本国を共産圏に墜ちることを許容することはできないとの結論に達した」(同3頁)。
被控訴人の提出した同訴訟の判決(乙63号)においても、この点は明らかにされている。「朝鮮戦争が日本との講和にはずみをつけたことは疑いない。日本との平和条約に関する会議におけるトルーマン大統領の開会演説は、主権国家日本をアメリカの同盟国にすることにより、朝鮮半島における共産主義の侵略に対する防波堤として役立てようというものであった」(乙63号8頁)。
上記文書にも示されているように、アメリカの対日政策は、占領期間を通じて変化した。アメリカは、当初、中国の蒋介石政権を軸に東アジアの戦後体制を想定していた。しかし、中国の内戦で蒋介石の敗色が濃厚になると、日本を中心とした体制へとアメリカの政策は転換する。冷戦の論理からアメリカの対日占領政策の転換を、当初国務省において推進したのは、政策立案部長ジョージ・ケナンであった。彼は1948年2月に国務長官に提出した報告書の中で、アメリカが極東諸国についての考え方を根本的に改めることを主張して、「人権とか文化的生活、民主化などという抽象的非現実的な目標について語るのはやめるべきであり、アメリカがとりうる政策は、現実的な効果を伴う軍事的経済的な手段に限られている」と述べた(『戦争責任論』荒井信一 184頁)。
こうしてアメリカの講和政策は、本来の戦争処理という目的とは離反し、日本を経済的軍事的にいわゆる「西側陣営」に取り込むことを目的としたものとなる。その結果、サンフランシスコ平和条約14条における賠償の軽減・放棄が図られたのである。
同14条で「国民の請求権」までが放棄されたのは、被控訴人が主張するように、個人の請求権を認めると賠償額が巨額になるからというようなことではなく、第二次世界大戦後のアメリカの世界政策、アジア政策に基づいて行われたものであり、もっぱらアメリカ主導で行われた対日講和において、個人の請求権は、アメリカの国益のために犠牲にされたというべきである。
3 サンフランシスコ平和条約に基づいて、日本は多額の賠償をおこなっているという被控訴人の主張について
被控訴人は、サンフランシスコ平和条約に基づいて日本は連合国に対して多額の支払いを行っていると主張し、同14条(a)1に基づく役務賠償、同14条(a)2に基づく連合国内の資産没収(約40億ドル)、同16条に基づく中立国の資産没収(450万ポンド)などをあげつらっている。
しかし、前記1、2で明らかにしたように、冷戦構造のなかで、アメリカのアジア政策に基づいて、対日賠償は極端な軽減が図られたのである。講和の前年の1950年、アメリカの国務長官ダレスは、アジア各国を回り、対日賠償放棄を認めさせていった。サンフランシスコ平和条約に参加したアジアの諸国にとって、対日賠償放棄は国民感情として容認しがたいものであったが、アメリカの圧力によって認めざるをえなかったのである。
しかも、前述したように、日本の戦争による最大の被害国である中国、植民地であった朝鮮、台湾は、サンフランシスコ平和条約には参加しなかった。
サンフランシスコ平和条約に参加した諸国のうち、同条約14条(a)1項に基づく、役務賠償を要求したのは、アジアの4カ国のみであり、ビルマ(1954年)、フィリピン(1956年)、インドネシア(1958年)、南ベトナム(1959年)との間で賠償協定が結ばれた。賠償の額と内容を敗戦国日本との協議・合意によって決めるという方式も異例である。賠償請求国の要求は、当初約300億ドルに達し交渉は難航した。しかし、結局、日本が21年間に支払った賠償額の合計は10億1208万ドル、準賠償というべき無償経済協力4億9576万ドルを加えても15億ドル余りにすぎず、国民一人あたりの負担は5000円強であった。支払いの実態を見ても、講和条約の規定した役務賠償はしだいに現物賠償となり、最終的には資本財による支払いの形をとって、日本の重化学工業製品のアジアへの販路を切り開く役割を担った。
なお、日本有数の財界人でしばしばフィリピンとの賠償交渉の立役者となった永野護という人物がいるが、賠償交渉が終局を迎えつつあった1956年1月、フィリピン上院は政府代表に擬せられた永野の任命を拒否した。永野は日本人という言葉の枕言葉として「すぐれた能力の」を繰り返す使うような人物であった。
しかし、その永野でさえ、1954年2月10日マニラで書いた報告書で次のような感慨をもらしている。
「この国をよく旅行して知るようになるにつれて、戦争中に日本軍がフィリピンで行った数多くの悪魔のような蛮行と残虐行為を知るようになった。私はその時、余りものショックに私の同胞によって本当にそのようなことが行われたことを信じることはできなかった。・・・このようなフィリピンに対する非人間的な残虐行為に対し金銭によってはいかなる罪の償いも適当でない。フィリピン人の受けた苦しみは金銭によっては、けっして測れないからである。したがって、われわれがこの件を金銭の問題として論じることは、ほとんど犯罪に近い。日本人は心の底から神に祈る以外償いの方法はない」(『戦争責任論』荒井信一 189〜190頁参照)。
永野がフィリピンで実感した日本軍の「悪魔のような蛮行と残虐行為」は、日本軍が侵略、占領支配したアジアの全地域での普遍的事実である。しかし、サンフランシスコ平和条約を貫くアメリカの冷戦の論理によって、日本は基本的に賠償責任を免れ、アジア各地の膨大な戦争犠牲者は何の償いも受けずに放置されたのである。
こうした現実を見る時、日本が多額の賠償を支払ったという被控訴人の主張は、国際常識と余りにもかけはなれた見解である。
では、なぜ被控訴人がこのような主張をするのか、それはいみじくも、被控訴人第1準備書面で引用されている当時の吉田茂首相の演説に示されている。吉田は平和条約受諾演説の中で、次のように、日本が多大な領土と資産を失ったと言っている。
「日本はこの条約によって全領土の45パーセントをその資源とともに喪失するのであります」「この平和条約は,莫大な在外資産を日本から取り去ります。条約第14条によれば戦争のために何の損害も受けなかった国までが日本人の個人財産を接収する権利を与えられます」(被控訴人第1準備書面102頁)。
しかし、ここで吉田がいう「45パーセント」とは、日本が侵略、略奪し、植民地化した他国の領土である。「莫大な在外資産」とは、植民地、占領地において他国の国民の犠牲のうえに築き上げた財産である。
被控訴人が現時点において、上記吉田演説を引用して、賠償問題について「誠実に対応してきた」(同103頁)と主張する姿勢には、侵略戦争に対する反省はまったくみられず、日本を多大な賠償を支払わされた被害者として描き出そうという意図がうかがわれる。この点もまた、国際常識から余りにもかけはなれた被控訴人の意識を示している。
4 サンフランシスコ平和条における個人の請求権問題についての被控訴人の解釈について
控訴人らは、第1準備書面において、サンフランシスコ平和条約14条に関し、「サンフランシスコ平和条約が『国民の請求権』を明記したうえでこれをも放棄するとしたのは、外交保護権を放棄するいう意味をもつもので、国民の権利自体を消滅させるものではない」(第1準備書面136頁)こと、その例として、同条約締結時のオランダの対応を示し、個人の被害に対する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約によっても最終的に解決したわけではないこと、「ある種の私的請求権」を日本政府も認めていたことを示した。
これに対し、被控訴人は、オランダとの交渉過程を示し(被控訴人第1準備書面104乃至106頁)、「最終的には、『日本国が自発的に処置することを希望するであろう連合国国民のあるタイプの私的請求権』が残るとしても、平和条約の効果として『かかる請求権につき満足を得ることはできない』との解釈で決着」(同108頁)したと主張する。さらに、この問題は、「平和条約締結の中心人物であったダレス米国代表も『救済なき権利』として問題を整理していた」(同108頁)ことを「決着」の根拠としてあげている。
しかし、被控訴人が示している資料によっても、最終的には、日本側の1951年9月8日付(平和条約締結当日)のオランダ宛書簡で、日本側の一方的な見解が示されているだけであって、オランダ側が納得したという証拠は示されていない。
また、アメリカは、当時の国際情勢から、同条約14条の賠償請求権放棄を連合国各国にのませたうえで、平和条約の締結を急いでいた。オランダが最終的に納得しなかったにもかかわらず、調印したのは、当時の国際的力関係の中で、アメリカの圧力に屈したという見方が成立するであろう。
日本側は、「ある種の私的請求権」を認めざるをえなかったのであるが、それが「救済なき権利」であり、「請求に応ずる法律上の義務が消滅したもの」(同109頁)であるとする解釈は、当時の国際情勢に規定され講和を急いでいたアメリカの全権大使ダレスの言葉によるものであり、現時点においてはその解釈の根拠は薄いものでしかない。
5 以上によって、被控訴人の、「日中共同声明によって中国国民の請求権も放棄された」という主張の前提である、「サンフランシスコ平和条約14条によって個人の請求権が完全に消滅した」という被控訴人の解釈は成り立たないものである。
第3 日華平和条約の解釈について
1 被控訴人の主張
被控訴人は、「日本と中国との間においては、戦争状態の終結、賠償並びに財産及び請求権の問題の決着については、当時の複雑な国際情勢を反映して紆余曲折があったが、両国政府の努力によって、サンフランシスコ平和条約における戦後処理の枠組みと同様の解決が図られた」と主張する(被控訴人第1準備書面117頁 下線は引用者)。
このいわゆる「サンフランシスコ平和条約枠組み論」の根拠として、被控訴人は日華平和条約を、「法律的には当時中国を代表する合法政府であった中華民国政府」(被控訴人第1準備書面120頁)との間で締結した有効な平和条約であり、日華平和条約がサンフランシスコ平和条約の枠組みで締結されたという解釈を示している。
ここでは2つの問題から、被控訴人の主張が成立しないことを明らかにしていく。第1に日華平和条約11条(サンフランシスコ平和条約の準用)等賠償請求権放棄の問題であり、第2に日華平和条約の有効性の問題である。
2 日華平和条約における賠償請求権の放棄について
日本の侵略戦争による最大の被害国である中国は、当然にも、戦後の講和に参加し、賠償問題の正当な解決を意図していた。戦争当時の蒋介石政権は、1943年頃から戦後賠償のための準備として、南京事件等の調査を行っていた。
1949年に成立した革命政権も、1950年12月4日周恩来首相が「①中華人民共和国政府が中国人民を代表する唯一の合法政府であって、対日講和条約の準備、起草、調印に参加すべきである ②台湾には中国人民を代表する資格はなく、対日講話に関与する資格もない ③中国の参加しない対日講話は不法であり、無効である」と表明していた(「日本の戦後処理ー日中・日台関係を中心に」殷燕軍『年報日本現代史』所収 90頁)。
しかし、対日講和を主導したアメリカは中国の革命政権を認めず、サンフランシスコ平和条約の締結過程から一切排除した。アメリカは、台湾の蒋介石政権を中国の正統政府として対日講和に参加させようとしたが、イギリスがこれに反対し、結局、台湾政府も参加させず、独立後の日本にどの政権と講和するかを任せることとなったのである。
日華平和条約の締結交渉は1952年2月20日から開始され、約2ヶ月にわたる交渉の末、同年4月28日に締結された。この交渉で日本側は、蒋介石政権に対し賠償請求権の全面的放棄を求めた。
前述したように、すでに戦争中から賠償問題の準備を開始していた中華民国・蒋介石政権は、戦後本格的に賠償のための調査を進めるとともに、実物賠償として中国の日本財産を没収していた。1949年台湾に逃亡した蒋介石政権をアメリカは、対日講和に参加させようとしていたが、そのためには、サンフランシスコ平和条約14条賠償請求権の放棄を蒋介石にのませなければならなかった。蒋介石にとって、賠償請求権の放棄は中国国民、台湾国民のコンセンサスを得られるものではなかった。しかし、講和条約に参加することによって、中国正統政府としての国際的認知を得ようとした蒋介石は、アメリカの説得に応じて「請求権の放棄」を受け入れた。最終的に、サンフランシスコ平和条約には参加できなかった蒋介石政権は、サンフランシスコ平和条約の発効する1952年4月28日前に日本との全面講和条約を締結し、連合国一員としての地位を保とうとしたのである。
日本政府は、このような蒋介石政権の弱みにつけこむ形で「賠償請求権の放棄」を迫り、日華平和条約11条(サンフランシスコ平和条約準用)に加え、サンフランシスコ平和条約14条(a)1項の役務賠償の放棄までを要求した。その結果、日華平和条約議定書1(b)で、役務賠償の放棄が規定された。蒋介石側は最後まで、この放棄に難色を示したが、1952年4月28日サンフランシスコ平和条約が発効する7時間前に日本側の条件をのむかたちで条約に調印した(『共同研究 中国戦後補償』奥田安弘・川島真 32頁)。
被控訴人は日華平和条約によって、中国国民の賠償請求権も放棄されたと主張するが、賠償請求権の放棄は、サンフランシスコ平和条約に参加したアジア諸国の場合と同様、当時の政治情勢の中で無理矢理のまされたものであった。とりわけ最大の被害国であった中国国民にとって、すでに中国政府としての合法性を失っていた蒋介石政権との間で成立した日華平和条約によって、中国国民の請求権が放棄されたという被控訴人の主張は到底容認しがたいものである。
3 日華平和条約の有効性について
この日華平和条約について、日本政府は調印直後に、限定的なもので全面的なものではない、とはっきり認めている。1952年6月26日参議院外務委員会での曾祢益議員の「この条約によって日本政府はこの中華民国国民政府というものを全面的な中国の主人として承認したものではない、こう考えまするが、その点は総理のはっきりしたお考えを、イエス、オア ノーでお答え願いたい」という質問に対し、当時の吉田首相は「現に中華民国政権の支配している土地をもつ中華民国との間に条約関係に入る。将来は将来であります。併し目的は終わりに中国全体との条約に入ることを希望してやまないのであります」と答えている。さらに曾祢益議員が、「ずばりと言えば全面的な承認ではないということございましょう」と質したのに対し、吉田首相は「そういうことです」と答えている。
1954年の鳩山内閣においても、1954年12月16日衆議院外務委員会で下田条約局長は「要するに日華平和条約におきます日本政府の根本概念は、国民政府と平和条約を結ぶけれども、そのことはいわゆる中国の全領土にこの条約が適応するものであるという見解はとらないということであります」と答弁している。
1972年の日中共同声明によって、日本は中華人民共和国政府を唯一の合法政府として認め、日中国交正常化の結果、日華平和条約は「終了した」という形で問題を処理した。しかし、日本政府は同条約の有効性については主張し続けている。
日華平和条約が締結された1952年4月28日(発効は同年8月5日)において、すでに蒋介石政権が中国の合法的政府とはいえないことは明白であり、少なくとも1972年の日中共同声明の時点で、日華平和条約は無効となったといわなければならない。
仮にそれが有効なものとしても、その時期は1972年9月29日(日中国交正常化の日)までであり、その有効範囲は、中国全土ではなく、台湾地域にしか及ばないものである。この点は、先にあげた条約締結後の政府答弁によって、日本政府も認めているところであり、日華平和条約自体にも、交換公文第一号という形で「この条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解」と明記されている。
4 以上によって、被控訴人の、「日中共同声明によって中国国民の請求権も放棄された」という主張の前提である、「日華平和条約は、サンフランシスコ平和条約の枠内で締結された中国の合法政府との講和条約であり有効性を持つ」という被控訴人の主張は成立しない。
第4 日中間の賠償問題はサンフランシスコ平和条約の枠組みと同じ解決が図
られたという被控訴人の主張について
1 被控訴人の主張
被控訴人は、日中間の賠償問題はサンフランシスコ平和条約の枠組みと同じ解決が図られたと主張する。この主張が成り立たないことは、すでに第1、第2で明らかにしたように、サンフランシスコ平和条約及び日華平和条約の被控訴人の解釈が成り立たないことによって明らかであるが、さらに、サンフランシスコ平和条約と日中共同声明及び日華平和条約と日中共同声明の関係を検討すれば、被控訴人の主張の破綻はより明白なものとなる
2 サンフランシスコ平和条約と日中共同声明
前述したように、1949年に成立した中国政府は、中国政府が対日講和に参加すべきであることを表明していた。サンフランシスコ平和条約から排除された中国政府は、中国抜きで行われた対日講和であるサンフランシスコ平和条約を認めていない。
サンフランシスコ平和条約締結に際して開催されたサンフランシスコ会議に関し,中国の周恩来首相兼外相は,「かつて日本に占領され,甚大な損害をこうむったことがあり,しかも自力で回復することの困難な国々は,賠償を要求する権利を保有すべきものである。」と述べた。また,中国政府は,外交部スポークスマンを通じて,「日本軍国主義者が,中国侵略戦争の期間中に,一千万人以上の中国国民を殺戮し,中国の公私の財産に数百億米ドルに上る損害を与え,また,何千何万もの中国人を捕らえて日本に連れて行き,奴隷のようにこき使ったり,殺害したりした。日本政府は,中国人民がその受けた大きな損害について,賠償を要求する権利を持っていることを理解すべきである。」と表明した。
サンフランシスコ平和条約14条による賠償請求権の放棄は、中国にとって容認しがたいものであった。20年後の日中共同声明において、中国政府による「賠償の請求の放棄」がうたわれたが、それはサンフランシスコ平和条約とは異なる国際政治情勢のなかで、まったく異なる枠組の中で行われたものである。
3 日華平和条約と日中共同声明
日本が蒋介石政権と日華平和条約を締結したことは、日中関係に大きな悪影響を与えてきた。中国政府は当然、日華平和条約を認めず、周恩来は「中国人民を公然と侮辱するものである」と厳しく批判した。
70年代に入り、日中関係も大きな転換局面を迎えた。ニクソン訪中によるニクソン・ショック、中国の国連復帰と台湾政権の国連追放に代表された国際社会の流れ、中国の「文化大革命」による政治的混乱の終息などにともなって、日中国交正常化の機運も急に高まったが、日華条約は大きなネックになっていた。
中国は日中国交正常化の条件として「日中復交3原則」を提示し、日華条約の廃棄を求めた。
中国側から提示された共同声明案には、戦後処理について「①中華人民共和国と日本国との間の戦争状態は、この声明が公表される日に終了する。②日本政府は、中華人民共和国が提出した日中国交回復の三原則を十分に理解し、中華人民共和国政府が、中国を代表する唯一の合法政府であることを承認する。これに基づき両国政府は外交関係を樹立し、大使を交換する……⑦日中両国人民の友誼のため、中華人民共和国政府は、日本国に対する戦争賠償請求権を放棄する」(1972年7月29日付「竹入メモ」)ことがうたわれている。
つまり、中国側は日華平和条約を破棄し、戦争状態の終了、賠償問題等の戦後処理を、この日中国交正常化で公式なものとするという考えであった。しかし、日本側は、日華条約問題については譲らず、最終的に、周恩来の「小異を残して大同を求める」という発言、「日中国交正常化で『日華条約』が自然に消滅し、日台関係も断絶する。われわれはこれを評価する」という発言によって、中国側が譲歩した形になった。このため、戦争終結問題について、日中共同声明は、第1項の「これまでの不正常な状態の終了」という表現となった。その結果、戦争終結問題について、中国国内では判然としないものが残る結果となったのである。
賠償問題についても同様である(次項で述べる)。日華条約の取り扱い、その結果としての戦争終結問題、賠償問題についての日本側の対応は、1972年の日中共同声明、1978年の日中平和友好条約以降も、日中間の戦後処理問題に禍根を残し、上記声明、条約で「日中間の戦後処理は決着済み」という日本政府の見解は、中国の国民感情としては受け入れられないものとなっている。
4 矛盾する日本政府の見解
第2で述べたように、1952年の日華平和条約締結後、日本政府は、同条約が限定的なものであるという見解にたち、吉田首相の国会答弁でも「目的は終わりに中国全体との条約に入る」ことが想定されていた。
ところが、被控訴人は第1準備書面において、これとは矛盾する主張を行っている。「戦争状態の終了については、日華平和条約第1条において、『日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する』と規定されているとおり、日中間の戦争状態は、日華平和条約により終了したというのが、我が国の一貫した立場である」(被控訴人第1準備書面120頁)。
賠償問題についても、「戦争状態の終結と同様、このような一度限りの処分行為については、日華平和条約によって法的に処理済みであるというのが、我が国の立場」(同121頁)であると主張するのである。
この日本政府の豹変は、1972年の日中共同声明の交渉過程から表れてきたものである。日中共同声明直後の1972年9月30日自民党両院議員総会で大平外相は、「もし中国が“賠償請求権”の放棄という言葉にこだわると、私どもはやっかいな立場になるところだったが、“賠償請求”という言葉にしてもらい、“権”という言葉はついていない」と解釈し、さらに「日華条約にすでに中国の“対日戦争賠償権の放棄”が規定されたのに、再び“賠償請求権”と規定すると、依然として中国に請求権があることを認めることになり、矛盾してしまう」と解説した。つまり日本側は、1972年の国交正常化の段階で、中国側にはすでに対日賠償請求権がないと解釈しているのである。
しかし、この問題に関する日本政府の対応は必ずしも一貫しているわけではない。
1978年10月13日、衆議院外務委員会で日中平和友好条約が審議された際、中川嘉美(公明)議員の「日中平和友好条約は戦後処理としての平和条約ではなくて、日中両国の友好関係というものを確認するための条約であるということは、これはもう疑問の余地はないわけです。もしそうであるならば、日中間の戦争処理というものは1972年のいわゆる共同声明であったと解すわけですけれども、この点間違いないかどうか御確認を頂きたいと思います」という質問に対し、園田直外相は「全くその通りでございます」とはっきりと答えた。
中川議員がさらに、「ただそうであるならば、これは伝統的な、いわゆる終戦処理の方式と若干異なる。いままでにない形といいますか、こういうわけですが、将来そういうことによって問題となることが出てこないかどうか、この点全くないのかどうか、一応この点も確認しておきたい」と詰め寄ると、園田外相は「必ずしも、問題がないわけではございませんが、この友好条約を基礎にして、両国が話し合えば、いろいろある問題は悪い方向には前進しない、お互いが理解できる方向に前進するということを考えております」との考えを明らかにした。
つまり、当時の園田外相は戦争問題の決着が1972年の日中共同声明であると明言し、さらに問題が残っていることも認めている。
ところが、同じ外務委員会で、寺前厳(共産党)議員が、日中間の戦争終結についての政府側の見解を求めたのに対し、大森誠一外務省条約局長は、「日中間の戦争終結の問題につきましては、法律的には、わが国と中国との間の戦争状態は日華平和条約第1条により終了したとするのがわが国の立場でございます。日中国交正常化に際しまして、わが国としては、日華平和条約を当初から無効なものとします中国側の主張は認めることはできないとの基本的立場を中国側に十分説明致しまして、日中国交正常化という大目的のために日中双方の本件に関しまする基本的立場に関連する困難な法律問題を克服しますために、共同声明の文言に双方が合意した次第でございます。このようなわけでございまして、日中間の戦争状態終結の問題は、日中共同声明により最終的に解決している次第でございます。」と答弁している。ここでは、日中間の戦争終結は、「基本的には1952年、最終的には1972年」という二段論法をとっている。
被控訴人が提出した1992年4月7日の衆議院内閣委員会での竹中繁雄外務省アジア局審議官の答弁では、「日本国に対する賠償請求に係わる問題については、政府の立場は、サンフランシスコ平和条約第14条並びに日華平和条約11条及びその議定書第1の(b)により処理済みであるというのが法律的にみたばあいのわれわれの立場でございます」(乙49号証7頁)と、被控訴人第1準備書面と同様の見解を示している。
5 日中共同声明5項の解釈のズレ
日中国交正常化交渉で、日本側が示した、「賠償問題は日華条約で解決済み」という見解に対し、中国側は激しく反発した。
26日午後の第2回首脳会談で周恩来は「蒋介石が日台条約で賠償請求権を放棄したことで、この度の共同声明には賠償問題を言及する必要がないという条約局長の発言は、実に我々は奇異に覚える。当時蒋介石はすでに台湾に逃げていた。彼は全中国を代表することはできない。これは他人の財貨で気前のよさを見せようとするものだ。戦争で被害を受けたのは主に大陸であり、我々は両国の人民の友好関係から考え、日本人民に賠償の支払いで苦しませたくないから戦争賠償請求権を放棄しようとしたのである。〔日本の〕条約局長は逆に蒋介石がすでに放棄したからといって我々の気持ちをくんでくれない。これは我々に対する侮辱にほかならない」と述べた(古川万太郎『日中戦後関係史』389頁、原書房)。
結局、前期大平発言にあるように、日中共同声明5項の文言となって妥協が成立したのであるが、この5項について中国側と日本側の解釈には大きなズレが生じ、賠償問題についてもまた、将来に大きな禍根を残すことになった。
被控訴人は、日中共同声明5項に関し「日中両国は、互いの立場違いを十分理解したうえで、実体としてこの問題の完全かつ最終的な解決を図るべく、このような規定ぶりにつき一致したものであり、その結果は日華平和条約による処理と同じであることを意図したものである」(被控訴人第1準備書面121頁)と言うが、このような解釈は妥当性を著しく欠く、日本側の一方的な解釈にすぎず、到底容認することはできない。
6 賠償問題は解決していないという中国世論の高まり
被控訴人にとって同声明5項はほとんど意味のないものでしかない。被控訴人の解釈によれば、「賠償問題は日華条約で解決済み」なのであり、1952年8月5日(日華平和条約発効の日)以降、中国政府及び中国国民の賠償請求権は存在しないからである。
このような日本の対応に対して、中国国内では、「日本は結局、中国国民の賠償請求権そのものを認めていない」という議論が起きている。つまり、1952年には、日本政府自身が日華条約の適用範囲を台湾に限定することによって、中国本土国民の賠償請求権は認めず、1972年には、「賠償問題は日華条約で解決済み」とすることで中国国民の賠償請求権を認めなかった、という議論である。
1980年代の後半以降、中国では、賠償問題はなんら解決していないという世論が高まっている。
7 中国政府の対応
1991年、中国人戦争被害者の中から日本国に対して損害賠償を請求しようとする動きが起こり、「対日民間賠償請求委員会準備会」が発足した。中国において対日民間賠償請求問題が初めて公の場で取り上げられたのは、1991年3月に行われた第7期全国人民代表大会第4会議の席上であった。
対日民間賠償請求委員会準備会の代表者の一人であった科学工業部幹部管理学院法学部教員・童増氏は、大会信訪局に対し、日本国が戦争の過程において戦争規則及び人道上の原則に違反し、中国人民およびその財産に対して犯した重大な罪業に関する賠償請求については、中国政府はいかなる状況においても放棄するとは宣言していない、とする意見書を提出した。その中で童増氏は、国家間の戦争賠償と民間の戦争被害賠償という2種類の賠償を法的に区別し、前者については、日中共同声明で中国側がこれを放棄したが、後者については、共同声明では触れておらず、それゆえ中国の民間人被害者およびその遺族は日本政府に対して賠償を請求できるはずだと主張した。
1992年4月、江沢民国家主席(当時)は、日本人記者の質問に答えて、「戦争が残したいくつかの問題に関し、我々は従来から事実に基づいて真実を求める、厳粛に対処するという原則を主張し、相互に協議してこれらの問題を情理にかなう形で妥当に解決するげきだと主張してきた」と発言した。
そして、1995年3月7日、全国人民代表大会で、銭其 外相は、対日戦争賠償問題について、1972年の日中共同声明で放棄したのは国家間の賠償であって、個人の賠償請求は含まないとの見解を示し、保障の請求は国民の権利であり、政府は干渉すべきではないと述べた。
前述したように、1972年の日中共同声明時点で、その5項の解釈については、日中間で解釈のズレが存在したが、1990年代以降、民間賠償請求問題についての、日中間の解釈の違いも表面化しているのである。被控訴人の「先の戦争の係わる日中間の請求権問題についての日中間の認識は一致している」(被控訴人第1準備書面123頁)は、事実として妥当性を欠くものである。
このような中国の国内世論と中国政府の対応の変化にふまえて、三井炭坑中国人強制連行福岡地裁平成14年4月26日判決では、「サンフランシスコ平和条約締結当時,中国は,中国国民が,日本政府に対して,日中戦争において被った損害の賠償を請求し得るとの立場を採っていたこと,また,昭和62年ころから,中国国内では,日本政府に対して上記損害の賠償を行い得るとの見解が支持されるようになり,当時の銭其?副首相兼外相は,平成7年3月9日,日中共同声明で放棄したのは国家間の賠償であって,個人の賠償請求は含まれず,補償請求は国民の権利であり,政府は干渉すべきではない旨の見解を示したことなどの事情を考慮すると,日中共同声明及び日中平和友好条約により,中国国民固有の損害賠償請求権が,中国政府によって放棄されたかについては,法的にも疑義が残されていたものといわざるを得ない。したがって,原告らの損害賠償請求権が,日中共同声明及び日中平和友好条約により,直ちに放棄されたものと認めることはできない」と判示している。
被控訴人は、上記福岡地裁判決に対し「中国政府の公式見解をも考慮せずに、原告らが適示したわずかな傍証的、断片的な事情のみに依拠して、日中間の外交関係の基盤をなす日中共同声明の条項を恣意的に解釈したものである」(被控訴人第1準備書面95頁)としているが、本項で示したのと同様、福岡地裁判決も、中国政府の対応を江沢民国家主席や銭外相の全人代などでの公式発言に基づいて判示しているものである。これに対し、被控訴人が第1準備書面「中国政府の見解について」(被控訴人第1準備書面123頁)で取り上げているのは、いずれも、外交部長、外交部新聞司長の記者会見での発言であり、むしろ被控訴人の方が傍証的、断片的事情に依拠しているといわなければならない。
第5 結語
1 以上、見てきたように、「日華平和条約11条及びサンフランシスコ平和条約14条(b)により、中国国民の日本国及びその国民に対する請求権は、国によって放棄されている。日中共同声明5項にいう『戦争賠償の請求』は,中国国民の日本国及びその国民に対する請求権も含むものとして,中華人民共和国政府がその『放棄』を宣言したものである」(被控訴人第1準備書面124頁)という被控訴人の主張は、いかなる意味でも成り立たない暴論である。
被控訴人らが第1準備書面で詳細に論じたように、また、正しくも中国の国民世論の高まりが示しているように、日中共同声明自体によっては、中国国民の賠償請求権を否定するいかなる根拠も見いだすことはできず、中国国民の請求権が存在していることは明白である。
2 そこで、被控訴人は、中国国民の請求権を否定するために、その根拠を日華平和条約とサンフランシスコ平和条約に求めてきたのである。しかし、その被控訴人の主張は、日本政府によるあまりに一方的で恣意的な解釈であり、また国際常識ともかけはなれたものである。
被控訴人の第1準備書面は、むしろ、被控訴人の主張を破綻を暴露するものであると同時に、中国国民の請求権を否定する根拠をサンフランシスコ平和条約と日華条約に求める被控訴人の立場は、1972年以降の日中友好関係の発展を逆行させかねない極めて危険なものであるといわなければならない。
以 上

|