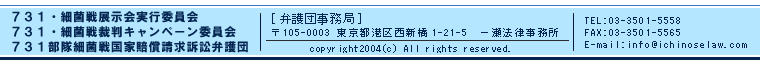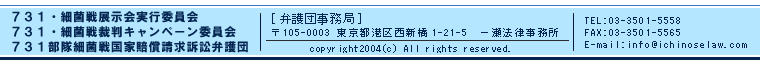|
�Ӓ�ӌ���
���Ӓ�ӌ����̃��j���[�ɖ߂�
�ې�̔�Q�L���Ɣ�Q�҈ӎ�
�\�\�Γ�ȏ퓿�n��ł̎��n�����܂��ā\�\
�������q��w���� �@�@��@�@�@�@�@�@仁@�@�@�
�ځ@��
��P�D�͂��߂�
��Q�D��Q�Җ{�l��e���̋L���ɂ���ې��Q
�P�D�ߎS�Ȏ��̘A��
�Q�D���|�Ɖ����̋ɂ܂�
�R�D����S�����悤�Ƃ��镶���̈���
�S�D���Q�ғ��{�R�ɑ���L��
��R�D�ې��Q�̂��̌�
�P�D�Ăщh���邱�Ƃ̂Ȃ��n��Љ�
�Q�D�u�^�������v�i�������Q�j�̏O����
�R�D��Q�҂̎q�ǂ�����
�S�D�O�����L��
��S�D��Q�L���̕ۑ�
�P�D�S�ɔ�߂Ă�����Q�L��
�Q�D�ې�i�ׂőh������Q�L��
�R�D�L���̋��L
�S�D�p�������L��
��T�D��Q�n�̐l�X�̍ې�i�ׂւ̎v��
�P�D����ꂽ����Ȃ��̂ւ̏���
�Q�D�c�߂�ꂽ���j�I�^���ւ̐����Ɣ�Q�҂̑����̉�
�R�D���{�E���{�l�ɑ���C���[�W�̕ω�
��U�D���������Q��^�������҂ւ̎��������@������{
�P�D�u�Y�p�̐��́v�Ɓu�������v
�Q�D���҂ւ̎����̌��@�Ɓu�W�c���m�v
�R�D���҂ւ̑z���͂̓W�J���u�m���v�̕��y�ƕs���s���ȓw�͂��K�v
�S�D���̒��
��V�D�q�����X�g
��P�D�͂��߂�
�@�퓿�n��́A�Γ�Ȃ̖k���A�����ő�̌̓���y�т��̎��ӂɍL�����������̐����ɂ���B���݁A�퓿�s�́A���ˋ�ƓC���̓��ƁA�������A��?���A�������A�������A?���Ȃǂ̌܌��A�Îs�s�̈�s���NJ����A�l����539���l�i1999�N���݁j�A�����퓿�s�X��̐l����50���l�قǂŁA�y�n�ʐς�18,200�����L�����[�g���ł���B
�@1941�N11���̓��{�R�ې핔���ɂ��y�X�g�ۓ����̌�A�s�X��ɐ�Ƀy�X�g�������A��ɔ�Q�͋}���Ɏ��ӂ̔_���n��֍L�������B���̌�A���N�ɂ킽���ăy�X�g�����s��A���̔�Q�͂���߂Ēɂ܂������̂ł������B
�@1941�N�����A�l��6���l�قǂ̏퓿�s�́A���������Ɠ��쒆���̕����≈�C�n��ƂȂ���v�Ղ̒n�ł���A�Γ�A�Ζk�A�l��A�M�B�Ȃǂ̏Ȃ��܂ލL��Ȕ͈͂ɂ����镨�Y���ʂ̏W�ϒn�ł������B
�@�퓿�s�ɂ�����o�ϊ����̏��ƓI�E��H�ƓI���i�ɂ��A�_���n��Ɠs�s���̊Ԃł͕�����l�̗��ꂪ����ŁA�헐���瓦��Ă����������̒n��ɂ������ꍞ�B�y�X�g�����̐l�E���̗���ɏ���āA�Љ���̃��[�g�ɉ����čL�������B
�@�܂�����A�����̍������{�̖h�u�H��̎w���͂��ォ�������Ƃ�A�u�d���v�i���J�ɑ������s���j�A�u�ۑS�r�v�i���҂̐g�̂����S�ȏ�ԂɕۑS���A���Ƃ���Â�h�u�ɂ��K�v�������Ă���̂Ɏ�������邱�Ƃ����ۂ���j�Ȃǂ̒n���̕����K�����A�h�u�H���W���A�y�X�g�̓`�d�Ɉ�����B�����āA�@���Ƃ��������J�������n�����̐e���W�c���Z�����A�n�拤���̂��`������Ƃ���������Ԃ̌`�Ԃ��A���Z�����W�����������ɂ�����y�X�g�̗��s��h���ɂ������̂ɂ������B
�@�y�X�g�͂��̒n��ɂ��������ӂ�����߂��B1996�N11���ɐ��������A��Q�҂�⑰�𒆐S�Ƃ���s���c�́u���{�R731�����ې��Q�퓿�����ψ���v�i�ȉ��u��Q�����ψ���v�j���k���Ȓ����ɂ��ƁA70�̋����A486�̑����ɋy��Q�n�ɂ������Q���Ґ��́A7,643�l*1�ł���B
�@���̐����́A�d�����j�I�Ȏ������Ƃ��Ȃ��A�y�X�g�̖ҁX������������Ă���B����́A7,643�l�̑���������ł͂Ȃ��A����قǂ̉ƒ낪�j��A�����l�ɋy�Ԉ⑰���A�e���̎��ɂ���ċꂵ�݈�w����Ȑ�����������ꂽ���̓������Ӗ����A�ނ��l��l�̐S�ɍ��܂ꂽ�[�����Ղ��Ӗ�����B
�@����A�퓿�ł́A��Q��������̌������F����@�ɂ��A�ې��Q�̒q���������̂́A���F���Ȃ��҂����Ȃ��Ȃ��B�����ψ���́A��Q�ҔF�������ہA��Q�҂̈⑰�������Ă���A�����̗אl��F�l�Ȃǂ̏ؐl�ɂ��،����邱�ƂŁA���߂Ĕ�Q�҂Ƃ��ď��F����Ƃ����K��*2��݂����B
�@���݁A15,000�ʂقǂ̔�Q�q���������ψ���ɕۑ�����Ă��邪�A��L�̏��������Ă��Ȃ��Ƃ������R�ŁA���łɔF�肳�ꂽ7,643�l�̂ق��A�c�����قڔ����̔�Q�\�����܂����F��̂܂܂ł���B�܂��A�Ƒ���e���W�c�S��������A�⑰�����n��Ɉړ]�����悤�Ȕ�Q�҂́A�o�^���邱�Ƃ����ł��Ă��Ȃ�����ł��炠��B���������āA���݂܂ł̒������ʂ̔�Q�Ґ��́A�����ē����̔�Q�𐳊m�ɔ��f�������̂��Ƃ͌����Ȃ��B
�@�{�Ӓ菑�͎�Ƃ��āA�M�҂�1998�N�ĂɎn�߂��A�퓿�n��ł̍ې푈��Q�Ɛ푈�L���Ɋւ��镶���l�ފw�I�����́A���N���̐��ʂɊ�Â��쐬�������̂ł���B1998�N8���ȗ��A�T��ɂ킽�茻�n�������s���A�������W���Q�n�l�@�̂ق��ɁA��ɔ�Q�҂�⑰��K�₵�A�ނ�ɑ��長����蒲��*3���s���Ă����B
�@�{�Ӓ菑�̎�|�́A���̂悤�Ȃ��̂ł���B���ɁA�ł��邾����Q�҂�⑰�̎�������ې��Q���l���A�ނ�̋L���ɂ����Q��`���B���ɁA��K�͂Ȑ푈��Q�́A�ʉ߂���ꎞ�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̌�A��Q�҂���͂̐l�X�̐l����S���ɁA�������Ԃɂ킽���ĉe����^��������̂ŁA��Q�҂̏،��Ɋ�Â��A��Q���ނ�̐l����Љ���ɗ^�����e�����ł��邾���q�ϓI�ɍČ�����B��O�ɁA�ې�̔������猻�݂܂ŁA�����N�����o���A��Q�Ɋւ���L�����l�X�Ȍ`�œ����҂ɂ���ĕۑ����ꂽ�B���̋L���ۑ��̂������L���̌p���ɂ��ď،�������B��l�ɁA���{�ōs���Ă�����{�R�ې퍑�Ɣ����i�ׂɂ��āA��Q�n�̔�Q�҂�⑰���͂��߂Ƃ���n��̏Z���͑���ȊS�Ǝv�����Ă����B���̊Ӓ菑����Ĕނ�̐���`�������B��܂ɁA���N���{�Ő������Ă��������������A�푈�◯�̏������߂����ē��{���{�A���{�Љ�ɂ�������̏��݂Ɋւ��A�����Ȉӌ����q�ׂ����B
��Q�D��Q�Җ{�l��e���̋L���ɂ���ې��Q
�@��Q�����ψ��������Q�Җ���ɂ��ƁA70�̋����ɋy�Ԕ�Q�́A
�܂̔�Q���ɕ�������Ǝv����B
�@����́A���ł̐}�ʁi�Γ�ȏ퓿�n��̍ې��Q�`�d�n�}�j�Ŏ����Ƃ���A�@�퓿�s�X��𒆐S�Ƃ����쓌�̛��Ƌ����܂ōL����傫�Ȓn��A�A�s�X��̖k����24�q�ɂ���Ό������𒆐S�Ƃ��������⑺�X�A�B�s�X��̓�ɂ��隱�����𒆐S�Ƃ����n��A�C�s�X��̐^�k��36�q�ɂ��鉩�y�X���𒆐S�Ƃ����n��A�D�s�X�悩��20�q���ꂽ�������n?�䋽�Ȃǂł���B
�@�y�X�g�̓`�d�́A���̂悤�Ȃ������̗ތ^�ɕ�������ƍl������B
�@���ɁA������Ȃǂ̎Љ���̒��S����A���ӂ̔_���ւƍL����B���ɁA�������H�␅�^������ȉ͐여��ɉ����āA������x���ւƓ`�d����B��O�ɁA�l�̈ړ��Ƌ��Ƀy�X�g�ۂ��^��A�����n��ł���щΌ^�ɓ`����悪�`
�������p�^�[���ł���B
�P�D�ߎS�Ȏ��̘A��
�i�P�j�����⑺�X�̔�Q��
�@�e���ɂ����鎀�S�Ґ���50�l�ȏ�̋���������ƁA���L�̒ʂ�ł���B
| �\�P�D�����ʂ̍ې��Q���S�Ґ� |
| �@ |
�퓿�s�X�敐�ˋ� |
297
|
�@ |
���ˋ戰���R�� |
224
|
| �@ |
���ˋ擿�R�� |
419
|
�@ |
���ˋ�O�F�� |
129
|
| �@ |
�C���Ζ勴�� |
541
|
�@ |
�C��拖�Ƌ��� |
136
|
| �@ |
�C���Ӊƕ܋� |
259
|
�@ |
��������Ƌ��� |
233
|
| �@ |
�������щƓ勽 |
493
|
�@ |
���������Ƌ��� |
101
|
|
| �A |
�C���Ό����� |
1,018
|
�@ |
�C���������� |
172
|
| �@ |
�C���،��n�� |
347
|
�@ |
�C�����ƓX�� |
1,683
|
| �@ |
�C���o���؋� |
151
|
�@ |
�C��撷�䛼�� |
118
|
| �@ |
�C��攒�ߎR�� |
58
|
�@ |
�@ |
|
|
| �B |
������������ |
224
|
�@ |
���������q�`�� |
125
|
| �@ |
�������э`�� |
148
|
�@ |
���������U�� |
71
|
|
| �C |
�C��扩�y�X�� |
77
|
�@ |
�@ |
�@ |
|
| �o�T�F�w���{�R731�����ې��Q���S�ҋy���⑰�����x���{�R731�����ې��Q�퓿�����ψ���ҁA2002�N8���B |
�@��Q�n�̒��ł��A��Q���ł��傫����������K�₵�����������A���̔�Q�́A���L�̒ʂ�ł���B
| �\�Q�D���X�̃y�X�g��Q��*4 |
| �@ |
���� |
�����l���� |
�������� |
���S�Ґ� |
���҂̔䗦 |
|
| �@ |
���R���������� |
650 |
1942.4 |
187�� |
29% |
| �@ |
�͕��������� |
56 |
1942.9 |
17�� |
30% |
| �@ |
�����R���މƒؑ� |
600 |
1942.5 |
201�� |
33.5% |
|
| �\�R�D���X�̃y�X�g��Q��*5 |
| �@ |
���� |
�����l���� |
������ |
���S�Ґ� |
���҂̔䗦 |
|
| �A |
�Ό������s�X�� |
2,000 |
1942.10 |
115�� |
5.7% |
| �@ |
���ƓX���F�Ƌ��� |
578 |
1942.10 |
152�� |
26% |
| �@ |
���ƓX����䑺 |
80(���S���ق�) |
1942.10 |
112(�Z��47��65) |
�� |
| �@ |
���ƓX�������� |
�@ |
1942.10 |
124�� |
�@ |
| �@ |
���ƓX���ӉƏ��� |
400 |
1942.10 |
144�� |
36% |
| �@ |
�،��n���� 蘑� 蘑� |
�@ |
1942.10 |
203�� |
�@ |
| �@ |
�o���؋���Ƙp�� |
371 |
1942.7 |
370�� |
99.7% |
|
| �@ |
�o�T�F��L�̎��S�Ґ��́A������蒲���A��Q�⑰�̒q���y�сw���{�R731�����ې��Q���S�ҋy���⑰�����x���𑍍��I�ɐ����������̂ł���B�ڍׂ́A�Y�t�����q���P�`�P�R�����Q�Ƃ̂��ƁB�A���A�l���q���ŏq�ׂ����S�Ґ��͂����ɋL�ڂ��������I�Ȕ��f�̌��ʂƂ��Ă̐����ƈ�v���Ȃ��ꍇ������B�܂��A�o���؋���Ƙp���̏ꍇ�A��ꑰ�͈�l�̒j���i����21�ˁj�ȊO�S�������S���A���҂̖��O�L���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��L�u�����v�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B
�@�L�ڂ��ꂽ���y�X�g�������Ԃ́A����ł���B
���F�Q�Ƃ̒q����Y�t�������ƁB |
�@��Q���傫�����X�ł́A�Z���̐l�����ɔ���S�������Ȃ荂���A�͔ߎS�Ȃ��̂������B�ȉ��ɁA��̑��̎���������A���̔�Q������̓I�Ɍ��Ă݂邱�ƂƂ���B
�i�Q�j�u���_���N�Ղ����v���ƓX����䑺
�@���҂�112���o�����ƓX����䑺�̌�����(1923~1999)�́A�y�X�g������̏����̂悤�ɕ`�ʂ����B
�@�u�y�X�g������A�l�X�̊炩��͏Ί炪�����A�̘̂a�₩�ȕ��͋C�͂�������Ȃ��Ȃ����B�l�X���J���ɒ��݁A�����q�►�A���e���e�ɗ܂̕ʂ��������B
�@�������i�M�Ғ��F���펀�ł͂Ȃ����҂̖����n�j�ɂ́A���҂������ӏ��ɐςݏグ���y�\������������ƕ��сA�e���̈�̂��n�ɑ���l�̎p�́A�閾����������܂ŁA����ꂩ��閾���܂Ő₦�邱�Ƃ��Ȃ��A�������Ԑ����쌴���ǂ�����B�e�͎��䂪�q��Q���A�q�͎��䂪�e��Q���A�S����X�ɍӂ������ł������B
�@����ɎS�߂Ȃ̂́A�Q���ċQ���ĐH�ו������߂�Ԃ���A���e�̐g�̂ɓ˂������ċ����A����V�҂��g�������Ȃ������Ă���Ƃ����p�������B���_���䂪�̋��ɌN�Ղ����B
�@���̌�A���ɂ̓j���g���⌢�̖������Ȃ��A�ƁX�͖������A�r��ʂĂČ���e���Ȃ��A��X���ɂ͂ǂ�����Ƃ��Ȃ��A�T�苃���̐����������Ă����B
�@�ȏ�q�ׂ������́A��A�������猩�����������̒n��̃y�X�g�̎S��ł���A���܂��̂S�ɂ���j���ł���A���J�̍Ό��ł���A���̂��ɂ����ł���B�v�i�q��8���j
�@�������̓y�X�g�ŌZ�ŁA��A���Ɨc�����������A�{�l�������������A�Ό����Ŗh�u��Ƃ����Ă����h�u���ɂ����^��A�h�u���Ɣ��͎m�Ɏ��Â��{����A��ꂽ�B
�@�y�X�g�̗��s�ŁA80�l�قǂ����������ꑰ�Ɏ��҂�47�����o�āA3�̉Ƒ������ł����B�����̕��e��1910�N�ォ��A�؎��S�}�A���^�̎킩����������H����J���A���N�ɂ킽��M���̂���o�c���s���A�����Ζk�Ȃ�Γ�Ȃ̓s������������l������悤�A����͈̔͂��g�債�Ă����B�y�X�g�������A�H��Ɏ���ɗ��Ă������l�������������Ŋ������܂�A�S���Ȃ����͖̂��O�𐔂�����҂����ł�9�Ƒ����v25���ł������B
����A�T���Ȍ����ꑰ�ɗ�������H��c���������B�����̒��V���������K���i�c��̈ʔv���J�錚���j��A�Ă�����������A���\�l�̌�H����Z���Ă����B���̌�H�������A���������b�ɂȂ������Ԃ��Ƃ��Č����ꑰ�̃y�X�g���Җ�������`�����B�����āA��H�������y�X�g�ɜ��A�ނ�̑唼���S���Ȃ����B
�܂��A��䑺�ɂ͒��ؕ��p��`������u���m�v������A�w�������\���قǂ����B���m�̋��t��k���y�X�g�̗��s�Ɋ������܂�A�Q�l�̋��t�Ə��Ȃ��Ƃ��\���ȏ�̊w�����S���Ȃ����i�������q��8���Ɩ{�l�ɑ��長�����j�B
�i�R�j���̐l����600������40���܂łɌ��������A�����R���މƒؑ�
1940�N��̌މƒؑ��́A�鎁�ꑰ���Z�����鑺�ł������B�y�X�g�̗��s�ŁA����600�l�قǂ������鎁�ɁA201���̎��҂��o���B�c�����l�X�͓��邽�߂ɉ��ɓ��������A�ЉЂ̌�A���̐l����40�����c��݂̂ł������B
�މƒؑ��̏Z���A�閾��(1921~)�́A���l�����X�Ǝ���ł����ߎS�ȏɂ��āA���̂悤�Ɍ�����B
�@�u���҂��₦�ԂȂ��o��̂ŁA�S������Ȃ������B��ɖS���Ȃ����l�̊����S�l�ŒS�������A���̌�A���҂��ǂ�ǂ����̂ŁA�Q�l�ŒS���A����ɂ��̌�A�P�l���V���_�łQ�l�̎��҂��^�Ԃ悤�ɂȂ����B
�@���҂����邽�߂̌����@���Ƃ��Ԃɍ���Ȃ��Ȃ�A�傫�Ȍ�����@��A�����̎��҂����ɖ��߂邱�Ƃɂ����B
�@�����Ă���l�����҂�S���o���Ă܂��Ȃ��A���̐l���|��Ă������B���̂��������Ă��閄���҂��A�d�̂ƂȂ��Ď���҂��Ă���l�ɑ��āA�w�����S���Ȃ��������ǂ��B�����Ȃ��ƁA���Ȃ�������l�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��x�Ƃ����悤�ɐ����������B
�@���̎S�߂ȗL�l�́A�S���炵���Č���ɔE�тȂ��B�v
�@�閾���̉Ƃɂ����҂�19�l�o���B
�@1942�N5�����{�A���Ɏ��҂��o�n�߂����A��������`�����ނ̔����钛�c���������A���ꗫ���}�ɂ��`�����A�v�w�Ƃ��ɖS���Ȃ����B
�@���̌�A�]�Z�����(12��)�A�����钛��(30��)�A���̍ȗ����p(29��)�A�]�Z����_(18��)�A�]�Z����C(16��)�A�]�o���錎�p(14��)�A�����钛��(15��)�A�����钛��(13��)�A�f����}(8��)�A�����钛��(29��)�A���ꉩ�~�x(28��)�A�]�o����G�p(9��)�A�]�o���錳�p(29��)�A�����钛�](35��)�A���̍ȉ����p(34��)�A�]�Z�����(14��)�A�]�o������(14��)�Ȃǂ��������Ńy�X�g�Ɋ������A�S���Ȃ����i�閾���q��3���Ɩ{�l�ɑ��長�����j�B
�Q�D���|�Ɖ����̋ɂ܂�
�i�P�j�����s���́uቁv
�@1941�N11���ȍ~�A�퓿�̊e�n��ő�K�͂ȃy�X�g���������Ă��������A��Q�n�Z���̃y�X�g�����̐^���Ɋւ�����̔c���͂܂��܂��ł������B�ނ�̘b��q���ɂ��ƁA����͂����悻���̂悤�ȗތ^�ɕ�������B
�@�s�X��̏Z���A���ɏ��l��H��哙�̂����肵������������s���́A���{�̖h�u�H����`�ɂ����(2)�A���ꂪ���{�R�ɂ��ې�̌��ʂł���Ɨ������A���{�̖h�u�[�u�ł������u�Α��v�u��̉�U�v���ɂ͒�R�����������A�l�Y�~�߂���|�����̖h�u�H��ɂ͊�{�I�ɋ��͓I�ł������B
�A�s�X��̕n���w�s���A���ɔ_��������̏o�҂��J���ғ��̓��̘J���ґw�́A�����ǂ߂��h�u��`���ɂ��Ȃ������̂ŁA�y�X�g�̏�h�u�H��̓��e�Ȃǂɂ��Ĕc�����邱�Ƃ��Ȃ������B
�B�_�����ɂ����Ď��҂���ʂɏo���Ό�������A���ƓX����䑺���̂悤�ɖh�u�����i�����u�d�u��v�Ƃ��Čx�@�ɕ������ꂽ�n��ł́A�h�u���Ƃ�x�@����̐����ɂ��A�y�X�g�����̗��R���l�X�ɓ`������B
�C���ɑ�ʂ̎��҂��o���ɂ��ւ�炸�A���{������h�u������������ꂸ�A���`���y�Ȃ������̂ŁA�������u�l�u�v�i�y�X�g���Ӗ����钆����j�ł��邱�Ƃ���m��Ȃ������l�X�B
�@�q����ǂ���ł́A�A�ƇC�͂��Ȃ葽�������B����́A�s�X��ł��_���ł��A�n���w����Α����ł������Ƃ��������̎Љ�I�ɋ�����̂ƍl������B�܂����̒��ɂ́A1990�N��̔��܂Łuቁv�̐^����m�炸�A�ې�i�ׂ̂��߂̒������n�܂��Ă��珉�߂ĕ��������l�����Ȃ��Ȃ����B
�@���j��y�X�g�������������Ƃ��Ȃ����̒n��ł́A�R�����ȂǁA���҂������o��u�a����������ƁA���K�I�ɂ�����uቁv�܂��́u�lቁv�ƌĂB�y�X�g���u�lቁv�Ƃ��ē`���A��Q�҂��S���Ȃ�ۂɐg�̂������Ȃ����̂ŁA�u�G��ǁv�ƌĂ�Ă����B
���̂悤�ɁA��x�ɑ吨�̎��҂��o���a�C�ɑ��āA�����̐l�͂��̕a�����������炸�A���ꂪ�����N�����ꂽ���R��������Ȃ������B�ނ�ׂ͈����ׂ��Ȃ��A�����������|�����������ł������B
�@�܂��A�����s���̎��ł������̂ɁA�l�X���ȋ^�����܂ꂽ�B�Ⴆ�A���䛼�����䛼���ɍݏZ�����A�l��60~70�l�̊玁�ꑰ�́A���҂�30�l���o�����̂ŁA�ꑰ�Ɂu�O���v�A�����u�lቁv�̗��s���O�̗��R��������N�����ꂽ�Ƃ��A���̎O�ɑ��Đ[�������������ꂽ�B
�@���ɁA�ꑰ�̑c����J��u�K���v�i�c��̈ʔv���J�錚���j�̕����B���ɁA�e�Ƃ̏Z��̕����B��O�ɁA�K���̂������ɐ����Ă�����̈ʒu�B����炪�������߂ɕa�C�����s�����̂��Ǝv���A�l�X�ɍ��܂ꂽ�B�i��؋��q��14���j�B
�i�Q�j�u�lቁv�̑�
�퓿�n��ɂ�����a�C��ގ�����ׂ̊��K�I�ȕ��@�ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂��������B
�@�A�u���n�r�E�V�i�q�E�_�k�v�B�����A�u�n�r�v�u�V�i�q�v�u�_�k�v�ȂǂƌĂ��V���[�}���������āA�a�C�������N�����������S��ǂ���������A���a�����̋V����s�����肷�邱�Ƃł���B
�A�u����v�B�����A�u���_�v�i�n���ŐM��Ă���_�X�j���J��_�ɎQ��A�_�ɉ�������肷�邱�Ƃł���B
�B�u��煎q�v�i�^�f�j�u���v�i�����M�j���̖�p���āA���������Ĉ���Ă��ĉ����������肷��悤�Ɏ��Â��{���B
�C�^��A�ցA?�����́u�����v�ɑ����鐅������*6��p���āA�a�l�̐g�̂��₵�Ȃ��玡�Â��{���B
�q���⌻�n�����ŕ������b�ɂ��ƁA�y�X�g�̗��s���A�����̓`���I���Ö@���p����ꂽ�����ł���B�Ⴆ�A�@�ɂ��ẮA���J���̒q���i15���j���A�A�ɂ��ẮA��؋��i14���j�����i15���j�A���j�h�̒q���i17���j���Q�ƒ��������B�B�́A�͕������������{�V�A���������Ƙp���ʐ�̘b�Ɋ�Â��Ă���B�C�ɂ��ẮA�\���P�̒q���i1���j�A���@�_�̒q���i18���j�ŏq�ׂ��Ă���B
�������A�������j�㒾�a����Ă��������̒m�b���A�y�X�g�̎��Âɂ͂قƂ�ǖ𗧂��Ȃ������B��e���J�G����^�f�X�[�v�ŕK���Ɋŕa���A��ՓI�ɐ����c�������{�V��A�v���X������Ñ��A�Y���A�ΊD�A�ւȂǂ̊�����Ő�������Ŋŕa�������ʐ�̂悤�ȁu�K���ҁv�i�K���ɂ��Đ����c�����ҁj�͂ق�̈ꈬ��ŁA�命�����S���Ȃ����B�܂��A�a�l�Ƃ̐ڐG�ɂ���āA�ގt�⊿����t�������S���Ȃ����B
�w�퓿���u�x�ɂ́A1939�N�ɑn�����ꂽ�퓿���������Ȋw�Z�����E�����A�y�X�g�̎��ÂɊւ��āA�`���I�Ȋ�����w�Ɋ�Â��Ɠ��Ȉ�Ö@���������J�������Ƃ����L��*7������B�������A���̂悤�ȕ��@�́A�L��Ȕ_���ɏZ�ޕn�����_���ɂƂ��Ă͉��̖������̂ŁA�ނ�ɂ͂܂������`���Ȃ������B
��ΓI�ȗ͂ƒ�R�ł��Ȃ����������uቁv�̑O�ɁA�l�X�͐�]���������A����͋��|��������ɑ����������B
�i�R�j�X��������
�@�@�@�l�X�̋L���ɂ���y�X�g�́A�ɂ߂ďX�������A�����̂��̂ł������B
�@�y�X�g�Ɋ��������l�X�̐g�̂ɂ́A��A�̕ω�������ꂽ�B����ɂ�
�ẮA�u�K���ҁv��⑰�̘b�́A���̂悤�Ȃ��̂ł���B
�ŏ��́A����ȓ��ɂ��Ȃ���A���M���o�����舫�����������肷��B
��ʂɊ��������A�悾�ꂪ�o��B���ꂩ��A�f���I�ɁA���Ɍ������z�������A���L����t�̏�̕��ւ�r������B�܂��A�畆�ɐF�Z�����_������āA�g�̂̐F�������ϐF���A�����猌�̍��������A��f���B���a���Ă��玀�ʂ܂ł̎��Ԃ́A�l�ɂ���č������邪�A�����҂������ԂŁA�x���Ƃ��R~�S���قǂł���B���̂悤�ɂ��āA��Q�҂͔��ɋ�ɂȏ�Ԃ̂��ƂŎ����}����B
�@�@�@������Ƒ���e�������̔ߎS�Ȏ����}����̂������Ƒ��́A�Ō�̕ʂꂪ�E�тȂ��������܂�A���X�ɂ��Ă�������Ǝ��҂�������߂��B���̂��߂ɉƑ����������A�S���Ȃ��Ă����B�������q���i8���j��A�\�Ŕ��̒q���i19���j�ɂ��̋L�q���݂邱�Ƃ��ł���B
�@�@�@�y�X�g�̎��Ƃ́A���ɂ����Ă���҂��h���X������ł͂Ȃ��A���҂ɕʂ��������Ƒ����A���l�Ԃ̏�Ƃ��āA���̍��Ɋ������܂�邱�ƂƂȂ�A����͖{���ɑ������ł���B
�@�@�@�܂��A��q�����悤�ɁA�������Ŏ��S���Ă������̐����A�����ɒǂ����Ȃ��قǂ̎��҂̑����A�n��������l�������Ȃ��Ȃ����e���Ȏ��ȂǁA�����߂��鏔�X�̎��Ԃ͑S�āA�l�X�̐S�ɐ[�����J����A���t�����B
�i�S�j�u�S�ɍ��܂ꂽ���|�v
�@���̂悤�Ȏ��̉Q�Ɋ������܂ꂽ�o�������u�K���ҁv�́A���\�N���o���������ł��A���Ǝ��̉���f�r�����ߋ��̈����ɔY�܂���Ă���B
1941�N11���Ƀy�X�g�Ɋ������A�퓿���x�O�̏��Ƒ�ƂƂ����ꏊ�̊u���a�@�ɓ����ꂽ�k�u�b�i����19�ˁj�́A���̂悤�ɉ�z�����B
�@�u��e�́A�l�𗊂�ŒS�˂Ŏ����u���a�@�ɉ^�B�a�@�́A�n�ʂɍY��ł��Ă��̏�ɘm�����ȈՂȌ����ŁA���J���Ղ���x�̑e���Ȃ��̂������B�a�@�ɂ́A200���قǂ̊����҂���������Ƙm��~�������ɕ���ŁA�ڂ�ڂ�̊��c��Â����Őg�̂������Ă����B
�u���a�@�ɓ������ŏ��̓��́A�ӎ����܂��͂����肵�Ă���A���͂������B�^�ꂽ�҂ɂ́A7~8�˂̎q�ǂ�������A60~70��̔N���������B�����҂��������ʼn^��Ă����̂��������A���M���z�����銴���҂��Α��F�ɉ^�яo���Ă䂭�l���݂��B
��ɂȂ�ƁA�����ɋS�̂悤�ȃJ���e���̌�������A�����҂����̂������f���o�����B�A�S�ł����Ƃ���悤�ȕs�C�����ł������B���_�����ɔ��藈���B
�u���a�@�ɓ����������A�����d�ǂ̑̂���������悤�ɔ����L���Ĉ�t��T���Ă������A�l�X���Q�����āA�߂��ݒQ���Ă����l������A�ߖ������Ă����l�������B��̊O����|�ő������S�˂�����S����Ă��āA�S�˂̏�ɂ͍����ۂ����̂��������B���̂���S�˂��ʉ߂������A���̍����ۂ����̂��A�R�[�N�X�Ɖ������`�̂˂��ꂽ�l�Ԃ̎��̂��ƕ��������B���̂��ɗ����Ă�����l�̏������ߖ������āA����Ŋ���������ċ������B���͓f�����Ƃ������A����ȓ��ɂɏP���ċC���������B�v�i�q��20���j
�@�k�u�b�́A�u�n���̂悤�ȎS�������̌����A�����̖ڂŌ����v�ƁA���Ɍ������B
�R�D����S�����悤�Ƃ��镶���̈���
�i�P�j�u�d���v�i���d�ɑ�����s�����Ɓj�̏K���Ƒ���
�@�����̒q���Ől�X�́A�����ɎQ���������ƂŊ��������Əq�ׂĂ���B
�퓿�n��ł́A�����������Z���Ă������̒n��Ɠ������A�����͒a���A�����A�o�Y�ƕ��Ԑl���ɂ�����l��V��̈�Ƃ���Ă���A���ɏd������Ă����B���d�Ɏ��ҁ\�\���Ɏ��҂������c����̏ꍇ�\�\�̑����������邱�Ƃ́A�́u�F�v�̋����Ɋ�Â������A�����I�Ȑ����̗։�ϔO��A�y���̗썰�M�ɂ����������Ƃł������B
�@���̒n��̑����́A�u��凁v�i�ՏI���Ŏ��V���j�A�u���\�v�i��̂����猺�ււƈړ�����V���j�A�u��r�v�i�e���⎀�҂̗F�l���]��𑗂�V���j�A�u��凁v�i�������u����u�쓰�v��ݒu�������̂����ɓ��ꂽ�肷��V���j�A�u������v�i���m��a���ɂ��s����ϓx�V��j�A�u�Ɨ�v�i�r�傪��m�������čE�q�̑��̑O�ō���s���V���j�A�u������v�i���҂̎q����e�������҂Ƃ̐e�a�W�ɂ��ܓ��ɕ������r���𒅈߂���V���j�A�u�O����v�i�e�������҂̈ʔv�̑O�ōs�����������������V���j�A�u�o��v�i����q���ʔv�̑O�ōs�����������������V���j�A�u�_���v�i���҂̈ʔv�Ɏ�F�̓_��t��������V���j�A�u�q��v�i��������⍒�������҂̎q���ɕ�����V���j�A�u����v�i�����t�Ɏ��҂��������I��ł��炤�V���j�A�u�o勁v�i�����Ƃ��疄���n�܂ŒS���o���V���j�A�u�����v�i���������V���j�ȂǁA*8��X�̋V���ɂ���č\�����ꂽ�B�����ł́A�e�V���Ɋւ���ڂ����Љ�͏Ȃ��A�{���Ɗ֘A����������̂ɂƂǂ߂�B
���ۂ̑��V�͉Ƃ̌o�ϗ͂ɂ���ĈقȂ��Ă����B�唼�̋V���������J�ɍs���T���ȉƒ������A���҂����ɓ����u��凁v�⎀�҂̗썰�������ɉA�ԁi���̐��j�֑��邽�߂́u������v��A�����n�܂ʼn^�ԁu�o勁v�A�����n�ɑ���u�����v�ȂǁA�ł��d�v�Ǝv����V�������s��Ȃ��n�����Ƃ��������B
�@�������A�����J�ɍs���Ƃł��A����̊̐S�ȋV�������s��Ȃ��Ƃł��A�����̎��ɂ́A�e�ʂ�F�l�������Q��̂���ʓI�ł������B�����ɎQ�A���̎�`�������邱�Ƃ́A�퓿�̐l�X�ɂƂ��āA���݂ɕt�������������ŏd�v�Ȏ����ł���A�`���l��̌���ł��������B
�@�����ł́A�u������v�̋K�͂���ԑ傫���B�퓿�n��ł́A�a���������m�������čs���̂���ʓI�ł������B������A�Ƃ̌o�ϗ͂ɂ���ď��������m�̐����قȂ�A2�l����4�l�A6�l�A8�l�ȂǁA�������ł���قǓ��m�͑����Ȃ�B�V���̎��Ԃ�1���A3���A7���Ȃǂ̍�������A�T���ł���قǁA�u������v�̊��Ԃ͒��������B
�@�����ɂ킽���čs����u������v�ɂ́A�܂��l�X�ȋV�����܂܂ꂽ�B���҂��j�����������ɂ���ċV��͈Ⴄ���A��{�I�ɂ́A���̂悤�ȋV���ō\�����ꂽ�B
�@�u�ŗ\���v�V���n���̐_�X���F�Ɏ��҂̖��O��������B
�A�u�ؓV�n�v�߉ނ�@���Ȃǂ̕��������̍ō��_�ʍc���ɏC�s�p�̓y�n�����A�_�����E�̏o������������V���B
�B�u�[�t�ȁv���ɉ��삵�Ă��炢�����_���ɉ��E�ɍ~��Ă��炤�V���B
�C�u��o�v�O���@�t���V���o�������ɍs���l��������V���B
�D�u�Ӗ�v���E�ɉ���Ă��炤�_���Ɩ����킷�B
�E�u�H���v�}�̐_�u�}���ꁁ�i����F�v�ɑ������s�����Ƃ�m�点��B
�F�u�[���v���̐_�����ɑ������s�����Ƃ�m�点��B
�G�u��d�v������d�����u�d�v�ƌĂ���P�ɕ������߂�V���B
�H�u���v���̐��̋S�_�Ɏ��҂Ɏ������������R��邱�ƂȂ�������V���B
�I�u�n���ȁv�n�����Ɏ��҂̓��������B
�J�u�J���j���v�n����ʂ��Ă��鎀�҂̗�������ɒʉ߂����邽�߂̋V���B
�K�u���S�v�����̎҂̍����Ăі߂��Đe���ƑΖʂ���B
�L�u���сv���҂̍��ɐH����^����B
�M�u��ɉȁv��ɕ����J��B
�N�u�[���v�����́u�����o�v�u�ω��o�v�u��Ɍo�v�Ȃǂ̌o��������B
�O�u�����v���҂̗�ɕʂ�������邽�߂ɁA�u�ω��o�v�u�ʍc�o�v�u���Όo�v�u�\���o�v�u���ߌo�v�u�����o�v�u�����o�v�u��Ɍo�v�u�n���o�v�u��l�o�v�ȂǏ\�o��������i�Ζ匧�ĉƍJ�����M���u�ǒd��ɑ��長����蒲���j�B
�u������v�Ƃ����V��ɂ́A�����E�����E�E�y���̐M�̏K����������B�l�X�ɂƂ��āA�u������v�͏d�v�ȈӖ������B�����ʂ��āA���̂悤�ȖړI��B�����悤�Ƃ���ƍl������B
�@�u���߁v�������҂������Ă���ԂɔƂ����߂���菜���B
�A���҂̍����A�Ԃւ̓��Ɉē����āA�����ɉA�Ԃ֗��o������B
�B�Ƃɖ��������邠�܂�A�Ԃɍs���Ȃ��������āA���̍����Ƃɂ���Ǝq�����������̂ŁA���m�͂��̍���߂܂��ē��̂ƂƂ��ɉA�Ԃɍs������B�C�A�Ԃ�腉��A��F���J��A�ނ�̋@�����Ƃ�A�c��̍����A�ԂŊy���������ł���悤�Ȋ���������B�c��̋C�������ǂ���A�q��������Ă����B
�D�����̍F�𐢊ԂɌ֎�����B
�E�s���̍Г�ɑ����Ď��ꍇ�A���҂ɜ߂����������ގ����āA���҂̍����Ԃ߂�B
�u������v�Ȃǂ̋V����s���ہA���m�����́A�o��N�����Ȃ��畑�x�⌀����I����B��y�̏��Ȃ��_���ł́A�����ɂ͉��X�ɂ��Đe���ȊO�ɂ��A�����l��₶�n�A�q�ǂ�����������������W�܂����B�y�X�g�Ƃ̊֘A���猩��A�Q��҂������A�����l���吨�ł��鑒���́A���傤�ǃy�X�g�ɓ`�����[�g������ƌ�����B
�i�Q�j�����ƃy�X�g�̓`�d
���ہA�����ɎQ�����邱�ƂŊ��������҂������������B�܂��A�u������v���s�������m�Ƙa����A�ق��Ċ���S���҂��������������S�����B
�ȉ��ɁA�����ƃy�X�g�����Ƃ̊֘A�̎�����Љ��B
����@�����Ɛe���̊���
�@1939�N�ɓ��{�R�̔����ʼnƑ�5�l�����S�������ؒ������R���̗��G�_���A���̌�A�퓿�s���ʼn����鏬�X���o�c���邱�ƂƂȂ����B
�@1943�N3���ɁA���G�_���y�X�g�Ɋ������A�S�˂ŒS������Ƃ̑��ɋA��A�����ɖS���Ȃ����B
���G�_�̏]�Z��̗��ȎR�A���ŎR�A�������y�я����̕v���H�R�����G�_�̊ŕa�����A����̑�������`�����B���G�_�̑������s��ꂽ��A���ŎR��A���G�_�̕v�̉�����������A�O�����Ɏ��S�����B���G�_�̑������s��ꂽ��A���ŎR��A���̕v�̉����������܂���A�O�����Ɏ��S�����B�������͌Z���ŎR�̑����ɎQ��������|��āA�����Ɏ��S�����B�����������S������A�������̕v�̌Z���ݏt�A���ݐ����`���̑�������`�������Ƃɂ���Ď��S�����B
�@����A�����������S������A�����e������11�l�̎��҂��o���i�������q��21���j�B
���҂�52���o�����ƓX�����ߎ����ł́A�ŏ��̎��ҁA���̏������K�����Ό������ɗ����̓�����ɍs���Ċ��������S������A�ނ̑���������ɍs��ꂽ�̂ŁA����ɎQ�����������̑��l���A�y�X�g�Ɋ��������i�M���Q�q��22�j�B
����@�u������v�̓��m�����S����
�͕����������̃y�X�g���S��17�l�́A�S�����̍ŏ��̎��҂ł��闛�����̑����ɎQ���㔭�a���Ă���B�܂��A���҂̒��ɂ͓��m���P�l�����i�����ؒq��2���j�B
�@���ƓX���z������ɋ������Ƃ��������������B���Ƀy�X�g���������Č�A���ɉƑ����������|�ꂽ�ꍇ�A�l�X�͕�F�ɉ��삷��悤�ɁA�p�ɂɎ��ɋF��ɗ����B�����ŁA����4�l�̘a�����������A�S�����S�����i�K�{��q��23���j�B
�@���G�_�̃y�X�g�ɂ�鎀�Ɋ������܂�ė����������S�������Ƃ͑O�q�̂Ƃ���ł���B���̗������̑����Ɂu������v�ɗ������m�������A�z�M���A���Ďł́A���ƂŖS���Ȃ����i�������q��21���j�B
����@�ق��Ċ���S����8�l�́u���v�v���S�����S
�퓿�s���x���ՉƘp���̈Փ��K�A�Փ��o�A�ՍF���A�ՍF�h�A�ՍF���A�Ӗю��y�сA�ב��̚g�����A�g�����Ȃnjv8�l�́A�퓿�̔g�~��Łu���v�v�i�^���J���ҁj�����Ă������A1942�N9���̂�����A��k�ɍݏZ�����ږk���Ɍق��āA�u�G��ǁv�i�����y�X�g�ɑ���Ăѕ��j�ɂ��������k���̕�e�������B8�l�́A���ƂŐH����������A���҂����ɓ����n�ɉ^�B���̌�A8�l��4���̊ԂɁA�S���S���Ȃ����B�����āA�ՍF���̔��̖��F�ŁA�Ӗю���9�̖������A�y�ё��̑��ɉł��ł��������q��A��Ď��Ƃ�K�˂��Ք~�����S���Ȃ����i�ՍF�M�q��24���j�B
����@���X�����̑����ƃy�X�g�̓`�d
���X�����̑��V�́A�������ȏ�Ɍ��i�ȗl���ɏ]���čs���A�u�V�t�B�v�i�C�X�����̋��`�ɂ���ė�q��V����i�Ղ���l�j�������̑S�̂��i�����B
�@���X�������L�̋V���ł���u���v�i�ʖ�j�A�u��r�v�i��̂𐅂Ő���Đ��߂�j�A�u��H�v�i��̂𔒂��z�ŕ�ށj�A�u�����v�i����ɂ�����p�̊��Ɉ�̂�����j�A�u�r�V�v�i�o��ǂ�Ŏ��҂ƕ������V���j�Ȃǂ��s����B
�@��n�Ɋ����^�ԁu�o���v�ł́A�ʏ�e�ʂ�אl�A�n��̎�҂�����S�����A�ނ�́u�r�v�v�ƌĂꂽ�B�C�X�������̑����ŋ��ʂ̊������g��ꂽ��A���҂̑̂�G�����肷��K�������邱�Ƃ́A�y�X�g���`�d���錴���ƂȂ����B���Ƌ����������̔�Q�҂͑S����61�l���������A����9�l�́u�V�t�B�v�̂���6�l���S���Ȃ�A�u�r�v�v�������l��8�l���S���Ȃ����i�����{�q��25���j�B
�i�R�j�u���r�v�Ɓu���y���v
�@���̒n��̊������Ɠ��l�A�퓿�l���u���r�v�A�������҂̐g�̂��K���ۑS����Ȃ���Ȃ炸�A�u���y���v�����y�����ꂽ���҂͈��y�ł���Ƃ����ϔO�����ɋ��������B
�@�����l�̐��E�ς̒����͎ł������B�g�̂̕ۑS�́A�̒��S�I�����̈�ł���u�F�v�ƂȂ������B�u�g�̔����A��V����A�����ʏ��v�i�g�́A���A�畆�Ȃǂ͕��ꂪ���������̂ŁA�����Ěʏ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��j�Ƃ����P���́A�̌o�T�w�F�o�x�ɋL�ڂ���Ă���B�̉e�����������̐l�X�ɂƂ��āA���҂̐g�̂���U���邱�Ƃ͎��ꂪ�������Ƃł������B
�܂��A�����̉e���ɂ��A��̂���U�����ƁA���҂̐g�̂����S�łȂ��Ȃ�A�u�A�ԁv�i���̐��j�ɂ����Ă����炩�ɂł��Ȃ����A�։��]�����ł��Ȃ��Ȃ�Ǝv���Ă����B����́A���҂ɂƂ��đ�ϋC�̓łȂ��Ƃł���A�����Ă���e���ɂƂ��ẮA�S�l����ꂸ���i���Ƃ������ƂƂȂ�B
�@����A�u���y���v�̊ϔO�́A�����l�̐��E�ςɂ��镗���v�z�Ƃ����ڂɊ֘A���Ă���B��n�̈̑�ȃG�l���M�[�ł���u�C�v���A�����ɖ������ꂽ�c��̍����o�R���Ďq���ɗ��ꍞ�݁A�q���̔ɉh��o���A���͂̒~�ρA�ꑰ�̗����ȂǗl�X�ȉ��b��^����B���̐��̐l�X�̕x�M�h�A�v���ޔp�Ȃǂ̉^���́A�c��̕�Ɉ����Ă���Ɖ��߂���l�X�ɂƂ��āA���������c���y������̂́A�u�V�o�n�`�v�i���ɓ�����O�̓����j�ł������B
�@�u���r�v��u���y���v�Ƃ����ϔO�⊵�K�����邽�߂ɁA���{�����{�������̉�U��Α��Ȃǂ̑[�u�͋���������������A�ƂɃy�X�g�ɂ�鎀�҂��o�Ă��A�h�u����{�ɕ����ɂ�������Ɩ��������Ƃ������������B
����@��҂ɂ����̏ؖ����������Ă������
�퓿�s�����͔\���ӂɍݏZ����������i�����Z�j�̑c�ꂪ1941�N11���Ƀy�X�g�Ɋ������ĖS���Ȃ�����A��҂��Ƃɗ��āA��̂��������y�X�g���Ɣ��f�����B���̕��e�́A��҂Ƀy�X�g���Ƌ�����ꂽ�r�[�A�������܈�҂̑O���삢�āA��̂��Α����Ȃ��悤�ɍ��肵�A�u�g��v�i����Ɉ˗����鎞�ɓn���Ԃ����ɕ���j����n�����B������������҂́A�Ƒ��̎���אl�ɒm�点�Ȃ��悤�ɖ������Ȃ����A�ƍ������B�܂��A��̂���O�։^�����鎞�Ɍ�������邱�Ƃ�\�z���A�u���펀�ł���v�Ƃ����菑���̏ؖ������n�����B�����ʼnƑ��́A�钆�ɂ�������Ƒc��̈�̂��̋��̓��R���i�L���̕�n�ɖ��������i������q��26���j�B
����@�ƂɎ��҂��o�����Ƃ��B������
�@1942�N4���̖^���A�퓿�s���ɍݏZ�������璉�̉ƂŁA�ނ̒퍑���i5�ˁj�ƍ����i3�ˁj���S���Ȃ����B���e�͎���l�̒킪�����Ă���悤�ɂ����ɓ���ĂӂƂ�������A�x�����ۂɁA��O�ɓ����l���݂ɂ܂���āA������O�̍Z��Ƃ����ꏊ�̓쑤�ɂ���r��n�ɂ�������Ɩ��������i���璉�q��27���j�B
�@�u�����l�ԂɂƂ��ĉ�v������v�ł���A�u���ݒn����Ɍ�����l�Ԃ̏��Љ�A���邢�͂��łɗ��j�Ɛ�j�̂Ȃ��ɏ������������Љ�̂��ꂼ�ꂪ�A������ʂ��Ď�����̖��Ƃ��Đݒ肵�A����ɂ���ɉ���Ă���v�B*9
�@�������A�n����Ɍ����鑼�̕����Ɠ����悤�ɁA�����Ȃ�Ɏ����߂����Ă̕��������グ�Ă����B�u�A�ԁv�╗���v�z���A�z���̗̈�ɂ�����W�J��ʂ��āA��̓I�ȌX�̐l�X���u���ʂ��Ɓv�͗l�X�ȃC���[�W�ɂȂ���A���������āA�u���ʂ��Ɓv�͑z���̐��E�ŕ��Չ�����A�X�l�̎��Ƃ����o�����ɂ܂��s����ߌ������z������悤�ɂȂ����B
�@�������A�{���l�ԂɈԂ߂������炷���̕������A�ې�Ƃ������̂��Ƃł́A�{���̋@�\���ʂ������Ƃ��܂������ł��Ȃ���������ł͂Ȃ��A�V���Ȏ��A��K�͂Ȏ��������炵���B����́A�{���Ɉ����ނׂ����Ƃł���B
�S�D���Q�ғ��{�R�ɑ���L��
�퓿�̐l�X�́A�ې��Q����{�R�ɂ���Q�̈ꕔ�Ƃ��ĂƂ炦���B
�@�S���w�҂́A�l�Ԃ̋L���́A�J��Ԃ��������o�������I�ɋL������X��������Ǝw�E*10���Ă���B�x�X���{�R����c�s�Ȗ\�s�����퓿�l�ɂƂ��āA�y�X�g��Q�́A���{�R�ɂ�钆���l�ɑ���l�X�Ȕƍߍs�ׂ̈�ł���ƌ�����B
���ہA�l�X�́A�y�X�g��Q�����X�ɂ��đ��̔�Q�ƑO�サ�Ĕ�����̂ŁA�L���������ƌ݂��ɍ��������o�����Ƃ��Ėa����Ă����B�������̋L���̒����ɐG���ƁA�����I�ȏ���O�̏o�������A��̗���A����A�����̉Q�����������ɂ���悤�ȑ����̂悤�ɁA�S�̒ꂩ�痬��Ă���B
�퓿�n��ł́A1938�N������{�R�̔������n�߁A���̌�A���N�ɂ킽���Ēn��̏Z�������e�̋��Ђ̂��ƂŐ������Ă���A�����҂������o���B
�@�܂��A1943�N11���ɂ́A���{�R��10���l�قǂ̕��͂����A�퓿��ɍU�ߓ����āA�퓿��������鍑���}�R���ƌ������퓬���s�����B*11
11�����{����12����{�̊ԂɁA���{�R�͏퓿����̂����B���{�R�͏퓿�s���y�ю��͂̔_���n��ŁA���Ƃɕ�����A�Z�����s�E����A�w�l�ɑ��銭���ȂǁA�l�X�Ȗ\����s�������B�����̒n��ɂ����ẮA�y�X�g���s�̑Ō�������A�܂��A���{�R�̖\�s���Ă����B
����@�������̘b
�@�͕�����������1942�N8���Ƀy�X�g�����������҂������o����A1943�N�ɓ��{�R�ɐ�̂��ꂽ�B���e���y�X�g�ŖS���Ȃ����������i����15�ˁj�́A���̂悤�Ɍ�����B
�@�u�Ƒ����������ŖS���Ȃ�����A���{�S�����ɂ���Ă����B�ނ�͂킪���Ƃ̌��z�ʐς̂�800�������[�g���̑傫�Ȏl���Ձi4���̌����Ŏl�p�`���\���������z�j�ɕ����ďĂ��Ă��܂����B�������͕����ǂ���Ɂu�Ɣj�l�S�v�i�Ƒ���S�����Ɖ����j���j�ł������B
�@�����āA���{���͑��̖������ɑ��Ďc�s�Ȗ\�s���������B���J���̖��͓��{���ɏW�c�ŗ��\���ꂽ��A�K����e�����h���ꍂ���グ���ē����E���ꂽ�B�A�Ƃ̖��͋͂�15�˂ŁA���ɉ��炵�������������A���{�R�ɕ߂܂��āA�W�c�Ŋ������ꂽ��A���̂܂܂Œr�ɓ������E���ꂽ�v�i28��
�͕������������k��L�^�j�B
����@���{���̘b
�@�͕������d�����̗��{���̒q���ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă���B
�@�u���{�R�͑��ɓ�������A�킪�Ƃ�700�������[�g���̎l���Ղɕ������̂ŁA��c�̍��Y������������u�Ŏ������B�����āA���{�R�͂킪�Ƃ��獒������ҁi1�ҁ�500�O�����j�A��3���Ɠ�4����D���Ă������B���d�������܂߂Ă��̕ӂ̑��X�́A�قƂ�Ǔ��{�R�ɏĂ���Ċ��I�ƂȂ����B
���{�R�́A�j����߂܂���ƎE���A������߂܂���Ɗ��������B
�@���̋߂��ɕ������Ƃ����r������A���ē��{�R���A�߂܂���72���̔_�������̒r�ɓ���A�N�������𐅖ʂ���o���ƁA�������ܓy�̂�����Ō����������A�S���M��Ď���ł��܂��܂ŁA�E�l���y���݂��ƂƂ����B
�@�܂��A���Ƒ剁�Ƃ����r�̂��ŁA���{�R�́A�ނ炪�߂܂��Ĕn����^���v�Ƃ��ē������Ă����j���y�сA�����̖\�s�����������������킹�Ė�150�l���E���Ď��̂�S���r�Ɏ̂Ă��B�E���ꂽ�j���̔����ȏオ�A�������Ȃ������̂ɑ��āA�����͂قƂ�ljA������e���Ŏh����Ď��S�����悤�ł������v�i���{���q��29���j�B
����@���璉�̘b
�@�����A�퓿�s���ɋ��Z�������璉�͒q���Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u1930�N��A���̉Ƒ�9�l��4�l�̕���l�A�k��ƈꏏ�ɏ퓿�s�̔ɉ؊X℈�����c�X�i���݂̍��R�J�������X�j�ɋ��Z�����B���e�͈�ӂ�����E�l�������B�r���D��Ă����̂ŁA�������ɉh���A�Ƃ̉Ɖ���200�������[�g���̍L�����������B
�@1938�N�̓~����A���{�R�̔�s�@�͏퓿�s������悤�ɂȂ����B
�@�ŏ��ɔ����������̌ߌ�A�s�������̊����X������ɏ\���l�̔�Q�҂̎��̂���ׂ��̂��A���͎���̖ڂŌ����B
�@�����A�u�V�����ꂸ�A�n�����ꂸ�A�������{�R�̔�s�@����ւ���i���e�𗎂Ƃ��j�������v�Ƃ������w���������B���̎��A�퓿�́A�قƂ�ǖ������{�R�̔�s�@�ɔ��������悤�ɂȂ��Ă����B
�@1940�N5��7����8���ɁA���{�R�̔�s�@�͔R�Ēe�𗎂Ƃ��A�䂪�Ƃ͏Ă���Ċ��I�ƂȂ����B���̌�A���e�͍��R�J���ɖؑ��̉Ɖ������B
�@1941�N�H�̂��钩�A�h��x���Ă����A��s�@�����ꂽ�B���ƕ��e�́A�߂��̖h�}�������A�r����̔��e���M���ɖ������A�X�̎�l���Ƒ��ƂƂ��Ɏ��̂������B���̍�������e���A�����~�܂�Ȃ������B���͑吺�ŋ��тȂ���A��O�̕��֑������B��O�l�L�����[�g���̈������ɂđc����e�ƍ��������B
�@�ߌ�A�x�������ꂽ��A�퓿�ɖ߂��Ă݂�ƁA���ɂ͕s���S�Ȏ��̂������������������A�d�M���ɂ��l�̎�⑫���������Ă����B���ɕ|�������B���̌�A���������������^���A�����Ԃɂ킽���Ď��炸�A1950�N�Ȍ�A����Ə��X�ɉ��n�߂��B
�@1942�N4���̂�����A�Ƃ̏����і��q�i����17�ˁj���a�C�ɂ�����A���M���o���B���̌�A��5�˂̍����A3�˂̍������a�C�������B��҂ɐf�Ă��炤�ƁA�u�y�X�g���v�ƌ���ꂽ�B����������́A�k�퉤�V�n�A���M�R�ɖ����Ėі��q��c�ɂɂ���ޏ��̎��Ƃɑ��点���B�і��q����������A��l�̒킪�S���Ȃ����B
�@�Ƒ��͔߂����A�אl��x�@�ɒm���Ȃ��悤�ɁA�吺�������ċ������Ƃ��ł����A�������������������������B�����A���͎���l�̒��Q�Ă���悤�Ɍ����Ă����ɓ���ӂƂ�������A�x�����ۂɁA��O�ɓ����l���݂ɂ܂��ꂱ��ŁA������O�̍Z��Ƃ����ꏊ�̓쑤�ɂ���r��n�ɂ�������Ɩ��������B
�@�c��́A���������̂��Ƃ��v���o���x�ɋ����A�߂��݂̂��܂�A�̂����������āA1942�N�̓~�ɖS���Ȃ����B�����ƌ̋��̊،��n���ɋ��Z���A�ꐶ�_�Ƃɏ]�������c�����A1943�N9���ɑ��Ƀy�X�g�����s�������ɁA�������Ď��S�����B
�@1943�N�̏H�A���{�R���U�߂Ă���O�ɁA���{���s���ɑ��ď���𗣂�A�_���n��ɑa�J����悤���������B�A��Ƃ��낪�Ȃ������Ƃ̏������_�i����40��j���A��l�Ŏc�藯��Ԃ������Ă���Ɨ��e�ɍ��肵�A���e�͏��������B
�@��P������A���{�R���P�ނ��A���������Ƃɖ߂�ƁA�Ɖ��͉�A�����̂��̂͂قƂ�ǒD���Ă����B�����āA���_����œ|��Ċ��Ɏ���ł���A�̂����s���n�߂Ă����B�����g�����ŁA�̂ɏe���Ŏh���ꂽ���Ղ��������B���{�R�̖\�s�ɂ���āA�䂪�Ƃł͂܂���l�����B
�@�ق�2�N�̊ԂɁA�䂪�Ƃł�6�l������ŁA�Ɖ����Ă��ꂽ��ꂽ�肵�A���Y���قƂ�ǎ������B���̑傫�ȑŌ����āA���͕a�̏��ɂ����B�ӎ��������A�A���l�ԂƂȂ����B1944�N�̏H�ɁA���͎��i���璉�q��27���j�B
����@�����т̘b
�@���Ƌ����������ɏZ�ޗ����т́A�Ƃ̔�Q�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ�����B
�@�u1942�N7���ɁA�퓿�s�ɋ���ɍs���A�߂��Ă܂��Ȃ����ĖS���Ȃ��������@���̗��斧�Ƃ����j�̑����ɑc�ꂪ�Q�������B���̒���A�c��͍��M���o���A�S�g�z�������A�傫�����A���ɋꂵ��ŖS���Ȃ����B
�@�c�ꂪ�S���Ȃ������N�̋�������ɁA�f�����s���Ƃ��č����}�R���ɕ߂炦���A����������ꂽ�B���N5���ɁA���{�R�Ɛ킢���Ő펀�����B�Ȃ������āA�܂����q���]���������c���́A���̑Ō��ɑς���ꂸ�ɐ��_������A��������H�~���Ȃ��Ȃ�A�������q�̖��O���Ăё�������肾�����v�i�����ђq��30���j�B
�@�펞�����{�R�̕��m��������R�O�Y���������w�����푈�]�R�L�\�\�]�R���L����x�i���ƔŁA2001�N2���j�ł́A�{�l���Q�������싞�U����̌o�܂��L�^����A���{�R���싞���Œ����̖��Ԑl���s�E���A�����l�����𗽐J����悤�ȁA�u�펞���ۖ@�ɂ܂��������ڒ��v*12�ł��������Ƃ��ԗ��X�Ɏʂ��o����Ă���B
�@���{�R�̓싞�ł̑�s�E���߂����āA���̔�Q�҂̐l���Ɋւ��ē����̊Ԃł͂܂��ӌ��̑��Ⴊ��������̂́A���̎����̑��݂͂��͂�ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���ہA�펞�����{�R�́A�싞�s�E�̂悤�ȑ傫�Ȏ��������ł͂Ȃ��A�����̊e�n�Ŏc�s�ȍs�ׂ������B
�@��L��1930�N��㔼����1940�N��O���̓��{�R�ɂ���Q�̋L���́A�����������{�R�̍s�����Q�҂̑�����،����Ă���B
��R�D�ې��Q�̂��̌�
�@�O�q�����Ƃ���A��K�͂Ȑ푈��Q�͒ʉ߂���ꎞ�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̌�A��Q�҂���͂̐l�X�ɒ������Ԃɂ킽���āA�ނ�̐l����S���ɉe����^���������B���ꂩ��́A��Q�҂̏،��Ɋ�Â��A��Q���n����Q�҂̂��̌�̎Љ����l���ɗ^�����e�����Č�����B
�P�D�Ăщh���邱�Ƃ̂Ȃ��n��Љ�
�y�X�g��Q�́A�n��Љ�ɑ傫�ȑŌ���^���A�O�ɏq�ׂ��Ƃ���A�قڑS�������S������������A���l���݂̂��c�������̂́A���̌�Ăт��Ă̔ɉh�͖K��Ȃ������n�����������B
����A�y�X�g���s�����{�R�̍ې�ɂ���ċN�������Ƃ����^�����m���Ă��Ȃ��������߂ɁA��Q�n���ӂ̑��X���Q�Ƒ��̗אl��e�����́A�y�X�g�̔����ɑ���l�X�ȉ������������B�����҂��u��?�v�����A�M��̐_��Ƃ������Ƃ�A����ɜ߂��ꂽ���Ƃ��������Ɖ\����Ă����B�����āA���̂悤�ɂȂ����̂́A�ނ玩�g�ɖ�肪���������炾�ƚ�����A��Q�̑����Q�҉Ƒ��͎��͂���Ǘ�����A�t����������������ꂽ���Ƃ����Ȃ��Ȃ������B
�i�P�j�Ό������̏ꍇ
�@�퓿�n��́u�\�喼���v�̕M���ɂ�����Ό������́A�Â����j�������ł���B���V�Ƃ����Ɉ͂܂ꂽ���́A������P�L�����[�g���̒ʂ�𒆐S�ɓ�k�ɍג����L����A�^�ɂ��鋴�����Ɂu���k�X�v�Ɓu����X�v�ƌĂ���̃u���b�N�ɕ�����ꂽ�B�ʂ�̗�����300�ȏ�̏��Ƃ��������сA1940�N�㏉�����̐l����2,000�l�قǂł������B
�@�̂���A�Ό������́A�Γ�Ȑ�����Ζk�Ȗk���ɂ܂�����L��Ȓn��ɂ��̖���m��ꂽ���Y�̏W�U�n�ł���A�e�n���珤�l���K��F�X�ȓ��Y�i���^��ł���Ɠ����ɁA�퓿�n��̕Ă�A�ȉԁA����̐��Y�i���^��ł������B
�@�܂��A�Ό������́A���Ӓn��̌o�ϓI���S�݂̂ł͂Ȃ��A�Љ�����y�̒��S�ł��������B���퐶���p�i�������G�ݓX��A�_��Ƃ���̓����b�艮�A�؊퉮�A?��i�|���i�j���Ȃǂ̍H��A�܂��A���فA�������A�q��A�A�K���A������������B�Ζk�Ȃ��犿���c��A�Γ�Ȋe�n����ԌۋY�c���㉉�ɖK��A��ɓ�ȏ�̌��c����Z�����B
�@�����āA���k�X�Ƌ���X�̒[�ɂ́A���ꂼ��u�k�ɋ{�v�Ɓu��ɋ{�v�ƌĂ�鎛������A���Ɏ߉ނ⑭�_�̖k�ɑ��Ȃǂ̐_���F���J���A�Ό������͒n��̏@���I���S���ł��������B
�@1942�N10���ɁA�Ό������̒��Ƀy�X�g�����s���A�Z����115���̎��҂��o���B�܂��A�y�X�g�͐Ό���������}���Ɏ��͂̔_���n��ւ��L����A�������̑����ЉЂɊ������B
�@���ӂ̑��X�̏Z���̒q���ɂ́A�y�X�g�����̗��R�Ƃ��ĐΌ�������K�ꂽ���Ƃ����������̂����Ȃ��Ȃ������B
�@����A�y�X�g��Q�҂ɂ́A���̒���K���l�X��ʉ߂���l�X�������������B�Ⴆ�A�Ζk�ȕ����s�����c�̖���2�l�A�Ζk�Ȗk���̈Վs����̋����l1�l�A�Γ�Ȓ�����縗z����̖ȉԏ��l1�l�A�Ζk�ȐΎ�̖����l�v�w2�l�Ȃǂł���B
�@�y�X�g�̔����I�ȗ��s�́A�Ό������ɑ傫�ȑŌ���^�����B���҂���ʂɏo�āA�Ƒ��������قƂ�ǎ��S�������Ƃ��������B
�@�Ⴆ�A���̏㗬���ƁA�Ȏ��E�āE�����̒������Ƃł́A��T�Ԃقǂ̊ԂɉƑ��ƕ���l�Ȃ�11�l���������ŖS���Ȃ�A�c���ꂽ�̂́A�����A�퓿�s���̊w�Z�ŕ����Ă������j���݂͂̂ł������B���͂́A�X��ߐΌ������狎�����B
�@���n��Ɉړ]���鏤�Ƃ͂ق��ɂ��������B���̒��ɁA�����z��������ۂɁA�D�����v���č��Y��S�Ď����Ă��܂������Ƃ��������B
�@�y�X�g�̗��s��������������A���v�𗧂Ă邽�߂Ɍo�c���ĊJ����X�͏��Ȃ������B�������┃�����q���������A���͎��Ă������B�Ό������y�X�g�����̌��Ǝv���Ă����̂ŁA�]���������A�l�X�͂��̎��������炵�����ɍĂё��݂��ނ��Ƃ��S�O�����B
�i�Q�j�����R���މƒؑ�
�@�މƒؑ��ł́A���҂�201�l���o���y�X�g�̗��s��A���l���������ő����痣�ꂽ�̂ŁA�c�����̂͂�����40�l�������B
�@���̌�A���̐l���͑����邱�ƂȂ��A1960�N��܂�40�l�O��̂܂܂������B���̗��R�́A���͂̑�����A�Ⴂ�����łƂ��Ă��̑��ɓ����Ă��Ȃ���������ł���B
�@�l�������Ȃ��k�n���Ă����̂ŁA�鎁�ƈ��ʊW�������A�ב��ɏZ��ł����d���◽���̉Ƒ����A���ɏ������ڏZ���Ă����B����ł��A���݁i2002�N�j�̐l���́A20��130�l�݂̂ł���B
�Q�D�u�^�������v�i�������Q�j�̏O����
�@�y�X�g�́A�����̐l�Ɏ��������炵������ł͂Ȃ��A�c���ꂽ�Ƒ���e���ɑ傫�Ȕ߂��݂�ꂵ�݂������炵���B
�@�퓿�l�̏������q���ɂ́A�u���N�r���A���N�r��A�V�N�r�q�v�i�N���̍��ɗ��e�Ɏ��Ȃ�邱�ƁA���N�ɂȂ��Ĕz��҂Ɏ��Ȃ�邱�ƁA�N���Ƃ��Ă���q���Ɏ��Ȃ�邱�Ɓj�Ƃ����l���̍ő�̔ߒɂ��`�e���錿���悭���p����Ă���B
�@�y�X�g�̗��s�ɂ���āA��������̏퓿�l�����̂悤�Ȑl���̔ߌ���̌������B���̋�ɂɑς���ꂸ�A�S���Ȃ����Ƒ���ǂ��悤�ɂ��Ď��S�����l�����Ȃ��Ȃ������B
�@�����c�����⑰�����ɂƂ��āA�y�X�g��Q�͐����ɂ�����傫�ȓ]���_�ł���A���̌�̐l�����]�V�Ȃ��ς�������ꂽ�B����́A���ꂼ��قȂ�ނ�̐l���O���ɂ������̋��ʓ_���ƌ�����B
�@�ȉ��ɁA���l�̈⑰�̎���������A�ނ�̂��̌�̋��ɖ������������Љ��B
����@�u���N�r��v�̔߂��݂ɑς����Ȃ������u���m�v�̍u�t
�@���ƓX���F�Ƌ����̌F┗C�̍ȗ����p���A�퓿�s���ɍݏZ����o�̑����ɎQ�����ċA���Ă���|��A�܂��Ȃ����S�����B�����u���m�v*13�̍u�t�����Ă����F┗C�́A���̎��A���̒n�ŋ����Ă���A14�̑��q�F�������e�̂��Ƃŕ����Ă����̂ŁA�����p�̂��ɂ͒N�����Ȃ������B�����p�����S����2�����o���Ă���A����Ɨאl�ɋC�t���ꂽ�B
�@�Ȃ��]������F┗C�́A�Q�Ăđ��q�ƈꏏ�ɑ��ɖ߂����B�Ȃ̌��p�����������A┗C�́A�X�ɉ䂪�q�̎������������B�Ƃ�ƂȂ���┗C�͖������������A����ɐ��_�����a�ƂȂ�A�e�n�𗬘Q���A���N��ɓ����ŖS���Ȃ����B┗C�̈�̂́A���炭���E����l����Ȃ����������ł���i�z�m���q��6���j�B
���� �v�Ɛe���̎���
�@�퓿�s����10km�قǗ��ꂽ��������Ƌ������Ɠ������Ƙp�W����31�̒j�����N�́A�����퓿�s���œV���_�ŕĂ�S���čs�����Ă����B
�@1943�N10���ɁA���N�͏퓿�s����Ƃɖ߂�������ɓ|��A����5����ɖS���Ȃ����B���̌�A���N�̉��g�@�q�i�^���j�A��e���t���A29�̒햾���A11�̑��q���Â��������ŖS���Ȃ����B
�@�Ȃ⑧�q�����������N�̕��e�́A���x���C�������A�������������������Ŗڂ������Ȃ��Ȃ����B���N�̍Ȃ́A�v�⑧�q����������A�̑Ō����āA���̖т��S�������Ă��܂��A���N�قǕa���ɂ������A�Ȃ�Ƃ������������i�����q�q��31���j�B
����@�u�V�N�r�q�v�̐���
�@�F�Ƌ�����22�̌F�������y�X�g�ŖS���Ȃ��Ĕ��N��A�ȕ��O�G���u���Łv�i�č��ʼnƂ��o�邱�Ɓj�������B�����̓���50��㔼�̕�e��2�̑���w�����āA�Z������*14�����ȑ��ő��X������A��H�̐����𑗂����i�z�m���q��6���j�B
����@��Ƃ̑单��������ꂽ��
�@�`���I�Ȓ����Љ�ɂ����ẮA�u�j��O�A������v�A�܂�A�v���ƌv�����Ă邽�߂ɓ����A�Ȃ͎�Ƃ��ĉƎ�������B���̂悤�ȎЉ�\���ɂ����āA�y�X�g�ŕv�E���e������ꂽ�Ƒ��́A�������邱�Ƃ����ɍ���ƂȂ����B
�@�u���ʘa��ݓX�v�́A�Ό��������k�X�ɂ���암�����̓��Y�H�i�������X�ł������B�X�̎�l�������͂Ȃ��Ȃ��̘r�����ŁA�����͔ɉh���Ă����B�u���ʘa�v�ɂ́A8�l�Ƒ��̊O�ɁA�o��1�l�ƕ���l2�l�������B
�@1942�N10���ɐΌ������Ƀy�X�g����K�͂ɗ��s�������A�u���ʘa�v�̐l�X���Ж��Ƃ�Ȃ������B�����Ɩ��ʕc�A�]�Z�킪�S���Ȃ������A����l�����������S�����B
�@�����̓ˑR�̎��ɂ���āA�u���ʘa�v�̌o�c�͍�����ԂɊׂ����B��c�����ݓX�Ƃ����ƋƂ��p�����������́A�Εׂɓw�߁A�o�c�K�͂͊g�傳��Ă����B�M�p�͍����A�܂����̒n��ɂ����鏤�ƊԂ̊��K�ɂ��A�u���ʘa�v��������q�Ƃ̊Ԃŏ�Ɂu�s�L���v�A�܂蒠������Ȃ��܂܁A����⏤�����s���Ă����B�܂��A�F�l�Ƃ̊ԂŁA����݂�����A�肽�肵�����Ƃ��A�L�^�Ɏc����Ă��Ȃ������B
�@�����̎���A�����̍Ȃ͕v�̎��ɑ傫�ȃV���b�N���āA���_�I�ɋɂ߂ĕs����ȏ�ԂɊׂ�������ł͂Ȃ��A�����ԍς��Ñ�����l�ɂ��ς킳�ꂽ�B�����͐��O�A�����̐l�ɋ���݂�����A�|�������肵�Ă������A�ނ̎���A�x�����ɗ���l�͈�l�����Ȃ������̂ɑ��āA�ԍς��Ñ�����l�͎R�̂悤�ɗ����B
�@�܂��A�����̋������A�����̐��O�A�ނɁu���m�v�i������1����݁j400����݂����ƌ����āA������ɕԍς��Ñ������B�Ȃ́A���̂��Ƃ����������m��Ȃ��������A�d���Ȃ��X�̕i�����ɂ��ĕԍς����B�����āu���ʘa�v�͔j�Y�����B
�@���̌�A�����̕ے��A�F�Ƃ����j���A�����ɋ���݂����ƌ����A�����ŕԍς���\�͂��܂������Ȃ��Ȃ����u���ʘa�v�ɁA�Ƒ����Z��ł���Ɖ��������ɔ���n���悤�v�������B�����̕�e���F�ے��ɂ�����ɍ��肵���ɂ�������炸�A���ǁA�Ɖ��̎��̕����̌܂�A����œ���������ނɓn�����B
�@�������Y���Ȃ��Ȃ��������̉Ƒ��́A�������ς��H�ׂ邱�Ƃ����ł��Ȃ��Ȃ����B����̐H���ɁA�H�א���̎q�������ɂƂ点���̂́A�Ă��قƂ�nj����Ȃ������̊��݂̂ł������B�����̍Ȃ́A�H��������x�ɗ܂����ڂ��āA���_���ڂ��肵���B���Ӕޏ��́u�������˂��������Ă���A�����˂������Ȃ����v�ƁA�q�������Ɍ��������B���̗��N�A�ޏ��͓|��ĖS���Ȃ����B
�@�����̍Ȃ��S���Ȃ�����A�Ƒ��̐����͂���ɍ���ƂȂ����B�����̕�e�́A��l�̗c��������A��āA��ō؉����J���A����͔|�����B�q�������͖��������N���āA�s��֖��ɍs�����B�~�ɂ́A�c��Ƒ������͎���a�����B�ꏊ���������āA�h�����Đ����c�����i����10�˂̜����̒����������ɑ��長�����ɂ��j�B
����@���e�ƌZ��4�l�������A�������ꐶ�a�C��g�ɓZ����
��������Ƌ�����N���o�g��50��̑Փ��삪30�̑��q�Չ����ƈꏏ�ɁA�퓿�s���吼�傠����ŎG�݂̍s���������B1942�N5���ɁA�����̓y�X�g�Ɋ������Ď��S���A��̂͗Վ��Α��F�ɑ����ĉΑ����ꂽ�B
�@���̌�A��������a�����B�퓿�s�Ŏ��ʂƕK���Α��ɂ����ƍl��������́A�}���Ő�N���ɖ߂����B����̋`��i�����j���~��������̊ŕa�̎�`���ɗ��āA�ՉƂœ|�ꂽ�B���~���̒���ƌ��Ƃ̕���l���~�����}���ɗ������A��l�Ƃ��A�邱�Ƃ��ł����A�������܊������Đ�N���ŖS���Ȃ����B
�@�܂��A���N8���ɁA�ՉƂ̎��j���F�ƍȁA�q�ǂ���l���y�X�g�ŖS���Ȃ����B����قǂ̎��҂��o�Ă��A�܂��ՉƂ̍Г�͏I����Ă��Ȃ������B
�@1944�N4���ɁA�퓿�s�ŕz�̏�����������ՉƂ̎O�j�������y�X�g�Ɋ������Đ�N���ɋA��A�Ƃɖ߂���3���ڂɎ��S�����B�����̖������̗����ɖS���Ȃ����B�����āA1944�N7���ɁA���̍s���������ՉƂ̎l�j�H�삪�퓿�s���Ńy�X�g�Ɋ������āA��N���ɉ^��ċA���Ă���܂��Ȃ����S�����B
�@���̌�A�ՉƂ̖����q�A�Z��̒��ɗB��Ɏc�����������y�X�g�Ɋ������ē|�ꂽ�B����̕�e�́A���q�Ƒ��������������Ŏ���ŁA�c�����Ō�̈�l���|�ꂽ�̂����Ĕ߂��݂ɒ��݁A�n�ʂ��삢�ēV�̐_�ɁA�u�V�̐_��A����ȏ㎀�Ȃ��Ȃ��ł���I�����ς����Ȃ��I�v�ƁA�吺�ł�����ɍ��肵���B
�@�����̂��߂ɁA��e�͂��������̈�҂𗊂�A�������{�����肵�ċブ�����o���A�Ȃ�Ƃ������͐����Ԃ����B�������A�����Ԃɂ킽�鍂�M�ƊP�������ŁA�x�������Ȃ�A�ċz����̏Ǐꐶ���܂Ƃ����B
�@����A�ՉƂ́A�����̃y�X�g��Q�҂̎��Â▄���̔�p���o�����߂ɁA�Ɖ�3���A�k�n20������o���āA���Y���قƂ�ǎg���s�������B���̌�A�c���ꂽ�Ƒ��̐����́A�ɂ߂č���ƂȂ����i�Ռd���q��32���j�B
����@�y�X�g��Q��̒��璉�Ƒ��̐���
�@���璉�Ƒ������y�X�g��Q�ɂ��āA��Q�̂S�ɂďڍׂɏЉ�����A�ނ̕��̎���A15�̌Z���F���Ƒ���{���d�ׂ�S�����B�Z�͏�����������A���Ɉ�ӂÂ�����w��ł������A�܂��r���ǂ��Ƃ͌������A�Ƒ���{�����Ƃ͂ł��Ȃ������B�d���Ȃ��A��͗璉�ƒ�̍��ۂ�A��āA�����e�ʂ̏f���̋��D�ŕ�������B
�@�f���͐��i�����\�ŁA�l�g�����r�������B�܂�10��ɂȂ�������̔ނ�Z��Q�l�ɏd���ו����^������A�t���̎��݂őD���������肳���A��������Ƃ����{���Ė_�⌝�ʼn����Ă���B������A�璉���d����������������Ƃ��A�f���ɂЂǂ�����ꂽ�B�ނ̓����ɂ͍��ł����̎��̏��Ղ��c���Ă���B
�@1948�N�ɁA�퓿�Ɏc�����Z���a�C�ɂ�����A�܂��ɐ��b������l����l�����Ȃ������̂ŁA�܂��Ȃ����S�����B�Z��19�˂������B
�@�Z�̎���A�Ƒ�3�l���퓿�s�ɖ߂�A�璉�͕��e�̓k��Ɉ�ӂÂ���������A�H��ŏ����ȘI�X���o�������A�q�����܂�Ȃ��̂ŁA�Ƒ���{�����Ƃ͂ł��Ȃ������B��e�́A���������������ċ��E���������B���̂悤�Ȑ����́A�V��������������܂ő������i�q��27���Ɩ{�l�ɑ��長�����ɂ��j�B
����@�Ƒ��}�{�̏d�ׂ��ꐶ���������p��
�@�퓿�s�X��Ƀy�X�g���T���ꂽ1941�N11���ɁA�s���ɏZ��ł������p���̉Ƒ��́A18���Ԃ̂�����6�l�����҂��o�����B
�@���Ƃ͂S����19�l�̑�Ƒ��ł������i�}�P�Q�Ɓj�B�ŏ��́A�p���̌Z�ŁA���̌�A�o�̕v�A�Z�̖��A��A��l�̔��i�f�j���̏��ɁA�������ŖS���Ȃ����B
�܂��A1943�N�ɌZ�����{�R�̋�P�Ŏ��S���A���e�͉Ƒ��̘A�����̑Ō��œ|��A1949�N�ɖS���Ȃ����B�o���ł����̂ŁA�N�V������e��A��l�̔��i�f�j��ƁA�܂��c������Â̐����̏d�����p���ɂ������Ă����B
�@�p���́A���Z��ފw���ƋƂ̊����̌o�c����`���A�܂��A1949�N�̕��e�̎������������ɂ��āA��Ƃ̑单���ƂȂ����B
�@�̓����ς̉e���ŁA�����Љ�ɂ́A�u�D���s�œ�v�v�i�ǂ��w�l�͈ꐶ��x�����������Ȃ��j�Ƃ����ϔO�����ԎЉ�ɂ������̂ŁA���i�f�j���l�͍č������ɉp���̉Ƃŕ�炵���B�����ʼnp���́A�����̕�e����ł͂Ȃ��A1962�N�̔���ƁA1965�N�̏f��̐����܂œ�l�̖ʓ|���ł��B
�@�܂��A�S���Ȃ����Z�v�w�̎q�ǂ������Ɋւ��ẮA����1950�N��㔼�ɖk���S�|�H�Ɗw�Z�𑲋Ƃ���܂ŁA�Â��قړ��������ɒ����n���w�Z�ɓ��w����܂ŕ}�{�������B
�@���̂悤�ȗ��R�ŁA�ޏ����g�̍����ɂ��e�����o�āA1962�N��28�˂ł���ƌ����������B����́A�����ł͂��Ȃ�̔Ӎ��ł������i�{�l�ɑ��長�����j�B
����@��Q�҂̎q�ǂ�����
�@�u���N�r���v�A�����A�N���̍����e�Ɏ��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�X�^�[�g��������̐l���ɂ����ĕ���̈����i���Ɏ����Ƃ����A�傫�Ȕ߂��݂𖡂키���Ƃ��Ӗ��������ł͂Ȃ��A�}�{�҂Ƃ��Ă̗��e�����Ȃ��Ȃ邱�ƂŁA�������܂����������Ȃ��Ȃ�Ƃ����������̂��̂��A�c���q�ǂ��ɂƂ��Ă͉����̊�@�ł���B
�@�y�X�g�̗��s�ɂ���āA���e���Ƃ��Ɏ������q�ǂ������Ȃ��Ȃ������B�ǎ������̂��̌�̐l���͋�ɂɖ��������̂ł������B
�@����A�u�`�@�ڑ�v�Ƃ����ϔO�����������l�ɂƂ��āA���n�������p������̂ɏd�v�ȒS����Ƃ��Ă̒j�̎q�̎��́A���ꂪ�������Ƃł���B���q���S�����S������A��������Ƃ��Ă��A���̐��т́u��ˁv�i�Ƃ̌����f�����j�ƌ�����B�ꐢ��ɒj�q��l�݂̂���ꍇ�A������ł́u�ƕc�v�i�ꗱ��j�Ƃ����B�y�X�g�̗��s�ɂ���āA���q�S��������Łu��ˁv�ƂȂ����ƒ낪�������A�Z��Ɏ��Ȃ�āu�ƕc�v�̂ݎc���ꂽ�ƒ�������������B���҂Ƃ������l�̓���̔O���������A���͂�������̖ڂŌ���ꂽ�B
����@6�˂Ŗq���ɂȂ���
�@�F�Ƌ����̌F�^���́A�ȂƎq�ǂ���l��4�l�Ƒ��ł������B30�̉^�����y�X�g�ŖS���Ȃ�����A�Ȃ͐������т邽�߂ɁA4�̎��j��A��āu���Łv�A�������̒j�ɉł����B
�@�c����6�˂̒��j�́A�f���̉Ƃɐg���A�G�p�⋍�̕��q������Ȃǂ̎�`�������邱�ƂŁA���т�H�ׂ����Ă�������B6�˂̖q���̐����͋ꂵ�����̂������B�H�������܂蕠��t�H�ׂ��Ȃ����肩�A�f��͂����ŁA�ނɑ���ԓx�͏�Ɍ����������i�z�m���q��6���j�
����@�c���Z���̂ݐ����c����
�@���R�����t�����̑������g�傪�A1942�N8���Ƀy�X�g�ŗ��e��4�̒�A2�̖��Ɏ��Ȃ�āA����11�̋g���6�̖��A��l�̂ݎc���ꂽ�B�Ƃɔ����������̂ŁA�e�ʂ̉Ƃɂ͐g���Ȃ������B
�@���́A�f����c���̌Z��ɍk���Ă��炢�A���n�������������X�����Ă��炤����ɁA�g��͏f�������̋����q�̐��b�������B�܂��Q�N�������ʂ��Ă��Ȃ��������w�Z�����ނ��A���̌�Ăъw�Z�ɍs�����Ƃ͂Ȃ������B
�@����̂��Ȃ������ɂ����āA�g��͓�̂��ƂɈ�ԍ����Ă����ƌ����B��́A�܂��c��������ɂȂ�ƁA�K����e�̂��Ƃ��v���o���āA�u���ꂳ��ɉ�����v�ƌ����ċ����~�܂Ȃ��������ƁB������́A�ߕ��ƌC���Ă�����e�����Ȃ��̂ŁA���镞�◚���C�ɔ��ɍ����Ă����Ƃ������Ƃł������B���������Ȃ��̂ŁA��̎c�������̂���łǂ��ɂ��Ԃɍ��킹�āA�����ڂ�ڂ�̐g�Ȃ�ł������i�������Ɖ��g��q��33���j�B
����@�o���u���{�P�v�ɏo����
�@���R�����������ɍݏZ����A����8�˂̉������̕��e�́A1942�N4���Ƀy�X�g�Ɋ������ĖS���Ȃ����B��e�P�l�ł�9�l�̎q�ǂ���{�����Ƃ��ł����A�����̈�ԏ�̎o�����R���̉��ƒؑ��Ɂu���{�P�v*15�Ƃ��ďo�����B
�@��e�͔��ɔ߂���ŋ����������̂ŁA�ڂ��܂����������Ȃ��Ȃ����B�n���������̒��ŁA�܂��A�����̂R�l�̌Z�킪�������ŕa�������i�������q��34���j�B
���� �u�ƕc�v���m
�@�Ζ勴���ω������ɍݏZ���鍂�ƌN�A�����h�v�w�́A�Ƃ��Ƀy�X�g��Q�҂̈⑰�ł���B�����āA��l�̕��e�͂Ƃ��Ƀy�X�g�̔�Q�ɂ���ĉƂ́u�ƕc�v�ƂȂ����̂ł���B
�@�����Ƒ��́A�퓿�s�����Ƒ铪�i�g�~��j�̋߂��ɏZ��ł����B7�l�Ƒ��ŁA���h�̑c���F�c�Ƃ��̌Z���S�A�폭����3�l���g�~��Łu���v�v�i�ݕ����^������J���ҁj�����A�ނ�̍Ȃ����́A�ƂŎh�J�̎d�������Ă����B1943�N10�����{�A�y�X�g���Ƒ����P���A��ɗF�c�ƍȗ��{�����S���Ȃ�A���̌�A���S�Ɨ��l���A�����ƒʗ��̓�g�̕v�w���������Ŏ��S�����B
�@�c�����̂́A�����Ⴉ�����F�c�Ɩ{���̑��q�A���h�̕��e��l�݂̂ł������B�u�o�V�V�s���A�o�n�n�s��v�i�V��n�ɉ��삷��悤�ɋF���Ă��܂����������Ă���Ȃ��j�Ƃ����Ǘ������̏ɂ��������h�̕��e�́A���炭�̊ԁA�|���Ɣ߂��݂ɕ�܂ꂽ�悤�Ȗ������߂������B
�@����A�ω������̍����Ƒ��́A�����Ƒ��Ɛ�����ɂ킽���Ĉ��ʊW�������A�ƌN�̑c������A���̒팚���́A�_�Պ��ɂȂ�ƗF�c��ƈꏏ�ɔg�~��œ����A�e���ɕt�������Ă����B���Ƃ̐l�������y�X�g�Ɋ��������ԂɁA���ƌZ�킪���x���������ɍs���A�������M�S�Ɏ�`�����B����ŁA����ƌ������y�X�g�Ɋ������A11���̉��{�ɖS���Ȃ����B
�@�u�ƕc�v�ƂȂ����ƌN�ƌ��h�̕��e�́A���̌�A���ꂼ�ꌋ�����A�u�d�U�ƋƁv�i�ĂщƋƂ��h���邽�߂Ɂj�̂��߂ɁA�q�ǂ����������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�������A��l�Ƃ��q�ǂ�����l����������Ȃ������B
�@�܂��A�ƌN�̉Ƃ��A���h�̉Ƃ��A�ƂĂ��n���������B�ƌN���A���h���A�q�ǂ��̍��w�Z�ɍs�����ɁA��l�����ƈꏏ�ɓ������B��l�Ƃ��A�������ǂ߂Ȃ����ӂŁA���l�ƂȂ�����A���e���m�̈ӎv�Ō����������i���ƌN�q��35���j�B
����@�u�ꂪ�ꂵ��Ŏ��v
�@1998�N8���ɏ��߂ď퓿�������������A�،��n���ō����Q�Ƃ����j���Əo������B�ނ́A�����̉Ƃ̃y�X�g��Q��������ہA���́A�ނ̊Ȍ��I�ł������C��ł���Ɠ��̌��t�ɋC�������B
�@�u����͎��ł͂���܂��v�ƁA���͖₢�������B
�@�u�����ł��B���́A�g�������đ̌��������Ƃ����ɂ��܂����v�ƁA�ނ͓������B
�@���̎���������x�������Ƌ����Ă��炤�ƁA���̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�L�ꐺ��I�_�����ŋ�A�@�@�@�@ �����A�ꂪ�ꂵ��Ŏ��A
�����O�V���l��A�@�@�@�@�@�@�@����ŎO���ԒN���K�˂ė��Ȃ������A
�e�ʘH��s���i��B�@�@�@�@�@�@�e�ʂ͖��������E�C���Ȃ��B
�H�f�l�H���l���A�@�@�@�@�@�@�@�������r�₦�l�e���܂�ŘH��ɂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���q��l�������炸�A�@
�ƁX�ˁX�ٖ�B�@�@�@�@�@�@�@�ƁX�͌ł��������B
�䋙�X���O�O�Đ��s�i�A �@ �����o�������x���������߂Ă�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�������A
�ƁX�ˁX��d�M�B �@�@�ǂ̉Ƃ��ł��f���B
�䋙�X�o���v���@�A�@�@�@�@�@�@����ł��d�����Ȃ��̂ŁA
�n�c�y�������y�B�@�@�@�@�@�@�@���͋��ԂɃX�R�b�v�Ō����@��B
��y���}�D���S�A�@�@�@�@�@�@�@�Ђƌ@�育�Ƃɋ����߂��݁A
�������|�n���`�B�@�@�@�@�@�@�@�C�������Ēn�ʂɕ��ꗎ�����B
�䎙��}���X���ۖ����ǁB�@�@�@�����܂��a�C���Ƒ��q�͑吺�ŋ������B
��S�ƌ܌���H�s�A�@�@�@�@�@�@�䂪�Ƒ��͌ܐl�ł���A
�ꖳ�Z����A�@�@�@�@�@�@�@��l���q�̎��ɂ͌Z������Ȃ��A
�O�����X�������X�A�@�@�@�@�@�@�o�������Ȃ��A
��I���X�����䖔�^�N�l�B�@�@�@���������̒N�ɗ�������̂��B
�X�����v�L�@�A�@�@�@�@�@�@�f������͂�����Ďd���Ȃ��A
�������N�c�B�y�B�@�@�@�@�@��l�̐N���@��ɂ��������B
��y��㖄�l�A�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���Ă��疄��������肪�A
���j�Z�q�A�]�g�B�@�@�@�@�@�@�@���𓊂��̂Ă����Ƃ����Ԃ�
�����������B
�Z�q���W�A�]�g�A�@�@�@�@�@�@�@���̊W��߂��ɓ������̂ŁA
�䎙�v�@�v���s�y�Z�A�@�@�@�@�@���������߂Ȃ���A
��m��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��nj������̂�H����������
�����Ă������낤�B
�c�_�X�I�Z�q�y�Z�䎙�A�]�g�A�@��̊��ɊW�����Ď��͂����Ƃւ�
�������A
�}�X��X��Ɩ�B�@�@�@�@�@�@�@�����Ȃ���Ƃ̖��������B
��ƔV�㋙�����A�@�@�@�@�@�@�@�Ƃɒ����Ă����͂܂��ڂ��o�܂��Ȃ��A
�A���O�����X�s����B�@�@�@�@�@���x�Ă�ł������͂����B
�䎙�}���V���n��`�B�@�@�@�@�@���͐�]����قNj������B
���X�`�X�썖�A�@�@�@�@�@�@�@�N�O�Ƃ��Ȃ���܂����ڂ��A
�`���n����腌N�B�@�@�@�@�@�@�@���ꗎ���Ă��̐��̈������҂ւ�
��ɍs���B
�V����I���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@��͎��̉ƁA
�n����I�ʁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@��n�͎��̂�肩���B
����I����q�A�@�@�@�@�@�@�@�@�r����ɂ��A
�W��I�݈ˍ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�]�������c���ɂ���B
�䋙�X�����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͂͂��Ɩڂ��o�܂��A
��I���X���\�A�@�@�@�@�@�@�@�@���̗ǂ��q��A
�������V�ۗC�A�@�@�@�@�@�@�@�@��Ȃ��q�ɐ_�̌������A
�䐶�����q�A������ƍ��B�@�@�@���̑��q�͂܂��ɓV�U�ǓƁB
�������V�ۗC�A�@�@�@�@�@�@�@�@��Ȃ��q�ɐ_�̌������A
�_��}�{��{���l�B�@�@�@�@�@�@�_�l�ǂ������h�ȑ�l�ɂ��ĉ������B
�@2001�N4����2��ڂ̏퓿�����̎��ɁA���͍����Q���ēx�K�˂��B�ނ́A���̎��̍쐬�Ɋւ��Ă��낢��Ƌ����Ă��ꂽ�B
�@���̕�e�́A1942�N�H�ɐΌ������𒆐S�ɂ����n��Ƀy�X�g��Q����K�͂ɔ����������A�S���Ȃ��������ł���B����11�˂������ނ́A�ڂ̑O�̕�e�̎����ڂ���Ɗo���Ă����B��e�̎���܂��Ȃ��A�c������S���Ȃ�A���Ƃ���5�l�̉Ƒ����A���e�ƈ�l���q�̔ނ݂̂ƂȂ����B���e�͔��d�������A�ނ͐H���̗p�ӂ�ƒ{�̐��b�������B
�@�ނ�15�˂̎��A���e���č������B�V������e���}����O�ɁA���e�͔ނɂ�����x��e�̎������A���ꂩ��������Ɣނ�厖�Ɉ�ĂĂ������Ƃ𐾂����B�������A�`��̔ނɑ���ԓx���]��ǂ��Ȃ��������߂ɁA���e�͋`��ƕv�w�W��f�����B
�@���̌�A���e�͂Q��قǍč����A��������ނɑ���ԓx�������Ƃ��������ŁA�Ȃ𗣉������B
�@���́A���e�̍č��A�����A�āX���A�܂������Ƃ������������āA�܂��A�`��Ƃ����������J��Ԃ��̌����Ă��������̐l���ɂ����āA���̕�e�̂��Ƃ������痣�ꂽ���Ƃ͂Ȃ������B
�@�ނ�60�˂ɂȂ������A���q�̌������@�ɁA���N�S�ɔ�߂���ւ̎v����䂪�g�̋������A�����������y����������������邩�̂悤�ɁA���̌��t�ŋႶ���B����𑧎q�Ɍ��A���q�����������Ȃ��ނ̑���ɋL�^�����i�����Q�ɑ��長�����j�B
����@���e�̐Ȃ鍧��Ő����c�������㔪�����̏���
�@1941�N11���ɓ��{�R�̔�s�@���y�X�g�ۂ��T������A�퓿�s���̌{��J�Ƃ����n��ł́A�y�X�g�̎��҂��������o���B
�@�{��J�ɂ́A�u���Ƒ剮�v�ƌĂꂽ�����Ƒ����Z��ł�����т��������B�����̑c��́A�������̊����ŁA�Ƃ̍��Y�͑c�悩��`����Ă������̂ł���B��тɂ́A�����Ƒ��̂ق��A��������Ƃ����ďZ�ސ��т��������B
���Ƒ剮����́A�y�X�g�̔�Q�҂������o���B�����A�`���̊g���h�����߂ɁA�x�@�����̂���������A�l�X�̏o������֎~�����B�N�z�̒n��Z���́A���ł����Ƃ��玀�҂��^�яo���ꂽ��ʂ�N���Ɋo���Ă���B
�@����������A�����ň�̉��l�������A���҂��N�Ȃ̂��Ȃǂɂ��āA�N�����o�߂��Ă���ׂɂ͂�����ƕ�����҂���l�����Ȃ��B�A���A�l�X�����Ƒ剮�̔�Q�����y���鎞�A�قڊm���ɐG���̂́A���Ƃ̉Œ��j�p�̎��Ɋւ��Ăł���B
�@���Ƃ̎�l������i����44�ˁj�́A�u��p���Q�v�ƌ���ꂽ�]���̗ǂ�������ł���A���j�u���i����21�ˁj�����e�̎w���̂��ƂŊ�����̕��ƌP�������Ă����B�j�p(20��)�́A�u���̍Ȃł���A���㔪�����̒����[�G�̎q��Ă̍Œ��A�y�X�g�ɏP��ꂽ�B11�����{�̂�����A�j�p�́A�Ɛl�������^�������甃���Ă��������^����H�ׂ���A��������Ȃ�A�����ɖS���Ȃ����B
�@���܂�ɂ��ˑR�̎��ɁA���Ƃ̉Ƒ��͜��R�Ƃ��A����ł��鐯����Ȃ��p��m��Ȃ���Ԃ������B�]������j�p�̗��e�y�ѐe���͍Q�ĂĒ��Ƃɕ����A�����̏����āA�߂��݂̂��܂�A�������ƂɓŎE���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɖ��^������A���Ƃ�n�������ɑi�����B�܂��A���Ƃ́A���㔪�����̌[�G���j�p�Ɓu�����v�i�}���҂Ƃ��Ĉꏏ�ɑ���j����悤���Ƃɗv�������B�u���́A�������Ď����ň�Ă�ƁA�n�ƌƂ̑O���삢�Đɍ��肵�A�[�G�̗c�����͊낤���~��ꂽ�B
�@����A�n�������́A�퓿�s�L���a�@�Ɉϑ����Čj�p�̈�̂���U�����B�y�X�g�ۂ��������ꂽ���ʁA�ŎE���͔ے肳�ꂽ�B����ł��A���Ƃ͒��Ƃɑ��鍦�݂����������A���̌㐔�\�N�ɂ킽���āA���Ƃƒ��Ƃ��݂��ɘb�����킵�����Ƃ����Ȃ������B
�@�V�������������钼�O�A���Ƃ͈�Ƃ�����đ�p�ֈڂ����B�j�p�̖��j�킪�Ăь̋��̏퓿��K�₵�A�����āA�o�j�p�̖����[�G��K�˂��̂́A�o�̎���54�N���o����1996�N�̂��Ƃł������i������蒲���ƒ��[�G�q��36���j�B
�S�D�O�����L��
�@���_��w�҂̒���v�v�́A�O�����L����10���x�̓���������*16�Ƙ_�����B���̒��̊���̓������A�퓿�n��̍ې��Q�҂ɂ悭����ꂽ�B
�@�Ⴆ�A(1)�Î~�I�f���ňٗl�ɑN���ł���B
�@(2)�s�ϐ��A�����o�����B���N�A���\�N�o���Ă�����̔@���Č�����B���́A���n�Ŏ����Q��������g���ɔ�Q�҂��o�����̌�����A�u�ڂ����ƁA���҂̎��č����Ȃ����g�̂��]���ɕ�����ł���v�Ƃ����悤�Șb�����B
�@(3)�z�N�͔��I�A�I�A�����ΐN���I�ł���B�ގ��̊��o�h���ɂ���ėU�������B
�@(4)����������ƘA�����Ă���B���̏�́A�����A�����A㵒p���ł��邱�Ƃ������B�����͍s���Ǐ�Ƃ��Ẳ���Ɛړ_�����B�ې��Q�҂��i�����̂́A�ߋ��̐h���o���ɐG��邽�тɁA�v�킸�g�̂��k������A�܂��~�܂�Ȃ��Ȃ����肵�A�܂��A�����ԐH�~���Ȃ��A����Ȃ����X���������Ƃł���B�܂��A��q���钚���͂̂悤�ɁA���_�I�ɗJ�T�ƂȂ�A�W���͂��������������Ƃ����Ǐ���A�O�����L���̉e���ɂ����̂̂ł͂Ȃ����ƍl������B
(5)��Ɛg�̊��o�Ƃ̋������߂��A�����Ί��o������̋�ʂ����ɂ����B�g�̓I���ۂƂ����s�����A���ۂɂ͐S�I�O���̋��ʊ��o�I�z�N�ł��邱�Ƃ������B��q����k�u�b�̂悤�ɁA��Q������A�g�̂��キ�A�����g�̂̂ǂ����̕a�C�ɋC���Ƃ��A�s����i���Ă������Ƃ��A�ޏ��̐S�̒�ɔ�߂����|�̋L���ƊW���Ă���ƍl������B
�@�ȉ��ɁA�����͂Ɨk�u�b��l�̎���������A�ނ�ɂ���O�����L��������̓I�ɕ��͂��Ă݂�B
����@��x�ɉƑ���������������
�@��q�����Ƃ���A�Ό������̒��̃g�b�v���x���̏��Ƃ̒������Ƃł́A��T�Ԃقǂ̊ԂɉƑ��ƕ���l�Ȃ�11�l���������ŖS���Ȃ�A�c���ꂽ�̂́A���̍ۏ퓿�s���̊w�Z�ŕ����Ă������j���݂͂̂ł������B
�@���̎��A�Ƒ��̎����]��������͂́A�܂��A�퓿�s�̋߂��ɂ��鍥��җ���}�̉Ƃɍs���A��}���ĐΌ������֕������B�A�r���A��}���A�u�ߒɂ�}���āA�`������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������B���������������Ă���A���Ƃ́u���v�i���j���f����邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƁA���͂ɌJ��Ԃ����������A�S�\�������������B
�@�y�X�g�����s���������A�Ό������֏o���肷�鋴�͌x�@�ɕ�������A�ʍs�l�����₳��A�\�h���˂����ؖ����������Ȃ��ƒʉ߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���͂Ɨ�}�́A��l�Ƃ��܂��\�h���˂��Ă��Ȃ������B������
�x�@���A���͂����Ƃ̒��j���ƕ����ƁA�u��ڌ����炷���ɖ߂��Ă��ĉ������v�Ƃ��������t���ŁA�ނ��ʉ߂������B
�@�Ό������ɓ���ƁA�l�Əo��x�ɁA�u���Ȃ��͒��Ƃ̗B��̐����c�肾����A���Ƃ̏����͂��Ȃ����S���B��������Ȃ��悤�ɂ��ЂƂ��C�����ĉ������B��������Ɛ����ĉ������v�A�Ƃ����悤�ɐ����|����ꂽ�B
�@���͂Ɨ�}�����Ƃ̉Ɖ��ɓ���ƁA���Ԃɂ́A�܂���������Ă��Ȃ�6�l�̉Ƒ��̈�̂�����ł���A��l�̕���l�������̍ۂɂ����B���̔ߎS�ȏɑł���āA���͂͗������܂ܕ�R�Ƃ��Ă���A�܂��Ȃ������B���҂̖�������`�������l���̗אl�́A�u�l�͖S���Ȃ�Ăѐ����Ԃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȃ��͂��ЂƂ��厖�ɂ��ĉ������B���Ȃ���������A���Ƃɂ͏���������B�\�h���˂��Ă��Ȃ��Ȃ�A��������ĉ������B���Ƒ��̖����́A�킽������������ɂ��邩��A�����S�������v�ƁA���͂��Ԃ߂��B
�@���̌�A�����̑����������ꑰ���K�����k�ƘV���ōs��ꂽ�B�����̑�����́A�����Ɍ�������ł�����A�����ŁA���͂Ɨ�}�����������������i�������A���x��ɑ��長�����j�B
�@��l�́A�����サ�炭�퓿�s���ŕ�炵�����A��N��ɐΌ������ɖ߂�A���l�Ƌ����ŏ����ȓX���J�����B�v���Ȍ�A���͂́u��������Ёv*17�Ƃ������{�@�ւœ������B
�@��l�̂��̌�̐l���́A�����y�X�g��Q�̈����ɂ��܂Ƃ�ꂽ�B
�@���͂̓������x��ɂ��ƁA��������Ђœ����Ă����Ƃ��̈��͂́A���i�͉��a�I�ł��������A���a�ŁA���ׂȂ��Ƃɂ��������܋��ꂨ�̂̂��A�l�Ƃ̐ڐG��������B
�@�܂��A���X���_�I�����̏�ԂɊׂ��āA�d���̔C�Ɋ����Ȃ������B���͂����̗ǂ��F�l�̊x��ɌJ��Ԃ��������̂́A�u���Ȃ����A�܂����B���Ȃ��ɂ͗��e�����邵�A�Z�������B�l�͉��������������B�l�͌ǓƂł��v�Ƃ������ł������B
�@1950�N��̔����A���_�I�a�C�ƌǓƂ��ɑς����Ȃ��������͂́A���疽�������i���x��ɑ��長�����j�B
����@�k�u�b
�u�n���̎S�������̌������v�Ƃ����k�u�b�́A1997�N�ɏ퓿�ې��Q��������ޏ��Ɍ����̈�l�ɂȂ��Ăق����Ɛ\���o���������A�����ς�Ƌ��B���̋��ۂ̗��R���A���ɑ��Ď��̂悤�Ɍ�����B
�u���R�͊������܂����B���ɁA���{�ٌ̕�m�������������l��Q�҂̂��߂ɖ{���ɐ��ӂ������ĕٌ삵�Ă���邩�ۂ��ɂ��ċ^���܂����B���{�R������ŁA���{�l�ɑ��Ă��s�M�ł����B���ɁA���ԑi�ׂɂ��Ē������{�̐��ǂ��Ȃ邩��m��܂���ł����B��O�ɁA����͈�ԏd�v�ȗ��R�ł����A�ߋ��̂��ƂɐG���x�ɁA�g�̑S�̂����̎��̋��|���ɏP���A�k���āA�����ԐH�~���Ȃ��A�������Ȃ���ԂƂȂ�܂��B�ڂ����ƁA�������܊u���a�@�̒n���̂悤�ȕ��i���ڂ̑O�ɕ����сA���҂̊��S�̂悤�ȘX�C�̌�������Ă��܂��B����́A�{���ɑς����Ȃ����Ƃł��B�v
�k�u�b�̕v�⑧�q�̘b�ɂ��ƁA�k�͒��N�ې��Q�̂��Ƃ��߂����Ɍ��ɂ��Ȃ������B������A�v���ޏ��̐g�̂̍��l�z���Ɏ�p�̏��Ղ�����̂ɋC�Â��A����ɂ��ĕ��������A�k�́A�y�X�g�Ɋ���������ł�����ᇂ��Ƃ邽�߂Ɏ�p�������Ɛ������A�ߋ��̐h���o�������߂ĕv�ɑł��������B
�܂��A�����v���̎���ɁA�퓿�n��ł͈قȂ�h���̍g�q���̊Ԃ̕��͓����������������B�e���C�Ȃǂ̕�����g�p����A���҂��o���B�a�@�ɋ߂Ă����k�́A�����҂��~�����邽�߂ɐ킢�̌���ɍs�����B���҂╉���҂��n�ʂɓ|��Ă����ʂɏo���킵���ہA�k�́A���́u�ގ��I���o�h���ɗU������v�A�ߋ��̍ې��Q���v���o�����B���̖�A�ޏ��́A���q�Ɏ����̔�Q�̌���������B
�k�́A�d���ɑ���ԓx�͐^�ʖڂŁA��Ɂu�N�x��i�H��ҁv*18�Ƃ��ĕ\�����ꂽ���A���ۂ̐��i�͈�{�C�ŗZ�ʂ������Ȃ��A���ɉƂł͍��ׂȂ��ƂŃp�j�b�N��ԂɊׂ肪���������B50��ɓ����Ă���A�g�̂̕s����i���邱�Ƃ������A���Y�ꂪ���X�ɂЂǂ��Ȃ�A�ڂ��肷�鎞�Ԃ������Ȃ����i�k�u�b�A�y�єޏ��̕v�A���q�ɑ��長�����j�B
�O���I�ɂ͓w�͉Ƃ̂悤�Ɍ�����k�u�b�ł��邪�A���ہA���i�I�ɂ́A��q�����O�����L���̓����Ƒ����������A����́A�ޏ��̐S�̒�̏��Ղ�������Ȃ��������Ƃ���Ă���ƌ�����B
��S�D��Q�L���̕ۑ�
�P�D�S�ɔ�߂Ă�����Q�L��
�ې��Q�́A�����ł́A���������ɔ��R���ĐN���҂Ɛ키���Ƃ���Ƃ��鍑�ƓI�C�f�I���M�[�̂��ƂŁA�X�l�A�Ƒ��A�n��̔�Q�́A���ƑS�̂̐푈��Q�Ɋւ��铝�v�f�[�^�̒��ɏW��Ȃ�����A���̋��̋L���͌��I�L���ɑg�ݍ��܂�Ă��Ȃ������B
�v���Ȍ�A�ې��Q�Ɋւ����z��Љ�́A1950�N�Ƀ\�A�ł̐�ƍٔ����s����ہA�����̐V��*19�ɏ퓿�̈�ÊW�҂��Q�҉Ƒ��ɂ�镶�͂��f�ڂ��ꂽ���̂́A���̌�A���̏�ɂ͂قƂ�Ǔo�ꂷ�邱�Ƃ��Ȃ������B
�@����A���{�́u���������ψ���v�i���Y�}�����ɂ�鋤�Y�}�ȊO�́u����}�h�v�����邽�߂̋@�ցj���o�ł����w���j�����x�ɂ́A����}�h�o�g�̈�ÊW�҂��Q�҉Ƒ�����̓��e���f�ڂ��ꂽ���A���Y�}��`���傪��ɂ�����O�����̏o�ŕ��ł́A�قƂ�Ǎې킪�G����邱�Ƃ͂Ȃ������B
���������āA��Q�Җ{�l��⑰�̋L���Ɏc����Ă���ې��Q�́A�K���������{�ɂ���ēW�J���ꂽ�R���푈�̌��I�L���ɊW�������̂ł͂Ȃ��A�l��Ƒ��▯�O�̃��x���ŁA���I�L���Ƃ��Ē~�����Ă������̂ł���B
�܂��A���̔�Q�L���́A�����Όl�̐S�̒�ɔ�߂��A�z��҂�q�ǂ��ɂ������������Ȃ������B
��q�������璉��A���p���A�������Ȃǂ́A�����̉Ƒ�������Q�N�z��҂ɋ����Ȃ������B3�l�Ƃ��A�ې��Q�������J�n����A���������̊����Ɍg����Ă���z��҂ɐg���̔�Q����������̂ł���B
�u�ǂ����ċ����Ȃ������̂��v�Ƃ������̎���ɁA���璉�́u���̋L���͋ꂵ������̂ŁA�S�̒�ɕ������߁A�W�������B�ې�ٔ����Ȃ���A���͂��̊W���J���悤�Ƃ����Ȃ������v�Ɠ������B
���p���́A�u�������D�����^�̎��́A���ɂƂ��đς�����̂ł������B�܂��A�Ƒ���6�l�����҂��o����A���e�͌��錩�邤���ɜܜ����Ă����ĂƂ��Ƃ��|��A�܂�10��̎����Ƒ���{���Ƃ����d�ׂ�w����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�{���ɋ��̘A���ł������B����A�����͉ƂɎ��҂��o���Ƃ����̂ŋߏ�������₽���ڂŌ����A���������A�ƂĂ��炩�����B���̐h�������̒��ŁA�����O�����ɂ��̂��l���A�߂������Ƃ����ɂ��Ȃ��K����g�ɂ����v�Əq�ׂ��B
�k�u�b�͕v��q�ǂ��Ɏ����̔�Q�o�������������̂́A�ې��Q�̂��Ƃ͌��ɂ��Ȃ��̂��A�k�u�b�̉Ƃ̈Öق̃��[���ł������B
�Q�D�ې�i�ׂőh������Q�L��
�@�퓿�ې풲���ψ����Q�������J�n���Ĉȗ��A�O�q�����Ƃ���A15,000�ʈȏ�̔�Q�q����������B
�@�q���ɂ́A��Q�҂�⑰���ƒ��n��̔�Q�X�����L�q���A���w�ɓO���ē`����Ă���̂́A�ނ�̎��Ƒ��ւ̈�����A�ˑR�̍Г�ň�����l�Ɖi���Ɋu����ꂽ���Ƃɂ��䩑R�����̊��A�ߎS�Ȏ��������炵�����{�R�ւ̉����ȂǁA�l�X�ȏ�O�ł���B
�i�P�j����̕��o���\�\����
�@��������̒q���ɂ́A���������Ă���B�����̎��̂́A���Ԃœ`��������̂����p�������̂�����A�q���쐬�҂��n�삵�����̂�����B���w�I�Ȏ��_�Ō����ƁA�ނ�̎��͕̂K���������x���������̂ł͂Ȃ����A���̂��Ⴖ�邱�Ǝ��g�́A�ނ�̓��ʂɒ~�ς��ꂽ����̔Z���f���Ă���ƌ�����B
�@�����ł́A���̂́u��̐��B�ƈӏۂ̏W��ł���v�ƌ����Ă���B
�@�u��̐��B�v�Ƃ́A�܂�Z���R��ŁA���̌��t�͑����Ȃ��B�u�ӏہv�Ƃ́A������̍l���⊴��ɋr�F����A���̐l�i������ݍ���ł���q�ϓI�Ȍ��ۂ̂��Ƃł���B
�@�Z�����̂ł��A�܂܂��u�ӏہv���L���ł��邩��A���̊���̗e�ʂ��傫��*20�B���������āA���ʂ̐l�X�ł��A�����̊���Ɛ藣���Ȃ��悤�Ȍ��ۂ��A�b�����t�╁�ʂ̌��t�ŕ\��������Ȃ��ꍇ�A�Ɠ��̂������������̂ŁA���̉��`��\�����Ƃ��ł���B
�ȉ��ɁA�q���ɏ����ꂽ���̂▯�w���Љ�A�ӏۂɉ������L�������Ă݂����B
�Η��i���҂��ÂԂ��߂̑�j�i���P�R�q��37���j
���p�N��s�ӉƐh�_�A�@�@�@�@�@���ďӉ�ɂ��h����Ȃߐs�����A
���ߏ��H�A��N�����H���B�@�@�ߐH�ɍ���A�N���ꂵ���d�����肾���� ���Ƃ��v���o���B
�ߍ����[�����m�l�u�A�@�@�@�@�@�����{�R�������炵���y�X�g�̔�Q�ɑ����A
�P�ŎE���A�r�����k�ɖ爣�B�@�@�ۂ��l���E���A�Ƒ���S�����ċ������� �҂̎p���ɂ܂����B
���w�i���P�R�q��37���j�@�@�@
�`���N�؎��S�d�A�@�@�@�@�@�@�@���{�R�͈����̂悤�ɒ�����N�����A
���k�l�u�E�l���B�@�@�@�@�@�@�@���{���͋������悤�Ƀy�X�g��
�����l���E���B
���l�`�d雉ƈ�A�@�@�@�@�@�@�@�H�ƞԂɂ��ӂꂩ�������y�X�g���҂����A
���s�Ґ��s�B�@�@�@�@�@�@�@���̍��͕K���⏞���Ă����˂Ȃ�ʁB
���w�\�\雉ƈ�i���P�R�q��37���j
�����ߖ͓V�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X�̈����͐r���d���A
���m���c�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�R�͋Ɉ��ł���B
���p�l���ƒ����A�@�@�@�@�@�@�@������N�����l�c�ɎE���āA
�l�u����雉ƈ�A�@�@�@�@�@�@�@�y�X�g���H�ƞԂɖ������A
�v��l���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�C���₦���B
�ؖk���ؓ�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؖk����ؓ�܂ŁA
�S�s�O���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̔ߎS���͌����\���Ȃ��B
���[�Ֆ썜�͎R�A�@�@�@�@�@�@�@���[�͖쌴��ʂɍ��͎R�̔@���ςݏオ��A
���X�V�A���S�}�A�@�@�@�@�@�@�@����Ƃ���܂��ɋS�̋�������
��������A
�����ҁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌��̍��͕K�������Ă��炤�B
�@
�u�Ŗ����v�\�\雉ƈ�i���P�R�q��37���j
�ƁX�֖�ˁA�@�@�@�@�@�@�@�@�ƁX�͌ł���˂�����A
�X�D�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�l�X�͐S�ɂ̖ʎ����ł���B
�V�I�}�������A�@�@�@�@�@�@�@�@�V�����҂͎q���v���ĔE�ы����A
���I����z���B�@�@�@�@�@�@�@�@�c���͕������������ċ�����߂��B
�ɋ����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����苃�����A
�ԍ����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ԑ��A
���X�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������߂��݂̐������ɓ����Ă���B
�]�V�œ������A�@�@�@�@�@�@�@�@�閾�����物����܂ŁA
���r�����l�Q����s�f�A�@�@�@�@��ӑ���̐l�̗�͓���₦�Ԗ����A
�R���㓞�������y�́B�@�@�@�@�@�R�̑�n�͂ǂ������������˂��炯�B
�ɐ}���k���l��A�@�@�@�@�@�@�@�ԚL�̐����l����h�邪���A
���_�ěu���Ƌ��B�@�@�@�@�@�@�@���_�����̌̋��ɕ������Ԃ����Ă���B
�l�S�k�X�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�̐S�͕s���Ƌ���ŗ����������A
���ǎ��Ǖ�A�@�@�@�@�@�@�@�@����ǎ��Ɩ��S�l�́A
��Ï��S�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ������ɐS��ɂ߂Â���B
������p�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ׂĂ������ĂȂ��Ȃ�A
�Ɣj�l�S�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��Ȃ����Ƒ��������B
���S��i�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ނ����炵�����i�A
���s�G�ڋ��S�B�@�@�@�@�@�@�@�@�ڂɐG�����݂̂ȐS��ɂ܂��߂�
���͖̂����B
�u�Ŗ����v�\�\���ƓX���F�Ƌ����i�k�m���q��6���j
�l�u�^����A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�X�g�ۂ͖҈Ђ��ӂ邢�A
�ŗ��^�ɐS�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڂ̓���ɂ��ċ�������������B
�S�i�^�a�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߎS�Ȍ��i�͖{���ɋ��낵���A
��ܗ����݁B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��j�������ċ��܂ŔG�炷�B
�L�I�ˎ����Ɣj�l�S�ꎞ��A�@�@���U���ċƂƂȂ����Ƃ���A
�L�I�ˎ����ȗ��q�U�s���c���A�@�Ȏq�������c�R����ʉƂ���A
�L�I�ˎ��������ǎ��Ǖꖳ�˖��^�A����Ƃł͎c���ꂽ��q���邠�Ă��Ȃ��A
�L�I�ˎ����P�g��l���g��A�@����Ƃł͈�l����łǂ̂悤��
�������т�̂��B
�җL�I������S�ˁB�@�@�@�@�@�@��ƑS�ł��Ďq���̓r�₦���Ƃ܂ł�����B
����i�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂悤�ȏ�i�A
��ڋ��S�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڂɐG�����݂̂Ȓɂ܂����B
���w�A�����̏ɂ��ā\�\���R�����������i�]���P�q��1���j
�㐶���s�����a�A�@�@�@�@�@�@�@��҂͉��f�ɗ������Ȃ��Ƃ����A
�e�F�s�����o��B�@�@�@�@�@�@�@�F�l�͐q�˂Ă���E�C���Ȃ��B
�H�㖳�����s�l�A�@�@�@�@�@�@�@�H����s��������l�e�͌������A
���N��s�o��B�@�@�@�@�@�@�@���ߏ��͒N���O�o���Ȃ��B
���m�J�H���s���A�@�@�@�@�@�@�@���m���ĂԂ��Ƃ��ł����A
�ꕛ���ږ����M�B�@�@�@�@�@�@�@���̂͑������ĉ^�т���Ȃ��B
�������j��A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ȃ���������A
�����䓾�a�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͎��̐g���a�ɓ|���B
������А}�����A�@�@�@�@�@�@�@���������ŋ������Ԑ��������܂��A
�ڋ����R�h�S�ɁB�@�@�@�@�@�@�@��ʂ̕��ڂɂ��ċ�������������B
���w�A�����̏ɂ��ā\�\�Ό��������q�����i�������q��38���j
�\��������S�ˁA�@�@�@�@�@�@�@�\���ɐ�̕悪�A�Ȃ�A
��Ɨ}���O�K�B�@�@�@�@�@�@�@��Ƃœ�O�x�����������B
��n�r�������n�A�@�@�@�@�@�@�@��nj����H���U�炩�����l�����U�����A
���c�V�r�������B�@�@�@�@�@�@�@�J���X������̂̌������X�����B
���A��������̕��i�ɂ��ā\�\���ƓX���i�J�v���q��39���j
�長�r���L�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�钆�Ɏr�̕��L���Y���Ă���A
�ڋ����l�M�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@������͖̂��l�ƂȂ����M����B
���ێ��\�\�퓿�n��i�j���C�q��40���j
�n�j�j�n�n�N�A�@�@�@�@�@�@�@�@�`�����h���h���`�����`�����A
�ŋ��ے��e�ׁB�@�@�@�@�@�@�@�@���ۂ�t�ł�̂ł݂Ȃ���悭�����āB
�����O�Z�N�����o�A�@�@�@�@�@�@���ؖ����O�Z�N�Ɋ���ȏo�������N�������A
���S�q���T�@�ՓV�Ǒr�A�@�@�@�@���{�̋S�����͘T��Ղ̂悤�ɗǐS�Ȃ��A
�ĎE�����s�Z���A�@�@�@�@�@�@�@�ē��E�E�l�E�����E���D�����ł͖��������A
�d���퓿�c�l�u�ە��B�@�@�@�@�@�퓿�Ƀy�X�g�ۂ��U�z�����B
�n�j�j�n�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�����h���h���`�����B
��D�R�͑��x��\�A�@�@�@�@�@�@�킵���R�͂��Г�ɑ�������A
�ˌːl�Ɛ}���V�B�@�@�@�@�@�@�@�ƁX����l�X�̋��������V��h�邪���B
�������R�V�S�l�A�@�@�@�@�@�@�@���͍̂��R�ƂȂ莀����̗썰��
���݂�����A
�S���l���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�썰��������i���Ă��܂���B
�n�j�j�n�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�����h���h���`�����B
�@
�E�Őe�y������A�@�@�@�@�@�@�@�e�ʂ���������ւƉ����čs���̂�
�ڂ̓���ɂ��A
��Q��p�L�S�Q�B�@�@�@�@�@�@�@���Q���ł��S�ɍ��݂���B
�V�������@��e�A�@�@�@�@�@�@�@���V���l�͂����ƌ��Ă���
�@�������ċ����͂��Ȃ��A
������q�V�ӓI�c���Z�I�c���Z�I�����K�����{�̒{����������
�Ђ�����I���������I
�n�j�j�n�I�n�I�n�I�n�c�c�@�@�@�`�����h���h���`�����I
�`�����I�`�����I�`�����c�c
�y�X�g�ŖS���Ȃ�����e�𓉂ގ��\�\�퓿�s�`�ׁi���Γ��A�`�V���q��41���j
�v��V�q��A�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Â�ł݂Ȃ������������A
���ȋv�s���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̋Ȃ͋v�������ɂ��Ă��Ȃ��B
�������ȁA�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̒��ň�Ȃ������A
��a���V���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�閾���܂Ŗ���Ȃ��B
�y�X�g�ŖS���Ȃ����c��𓉂ގ��\�\�퓿�s�`�אV���i�q��40���j
�����X�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͐X�ƁA
���y�ˁX�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�˂͗݁X�ƁB
�������ߐ��|��I����A�@�@�@�@�����߂͂���Q��̎����Ȃ̂ɁA
����I�ʁX���v�L����B�@�@�@�@���̑c��ɂ͕悪�Ȃ��B
�ʁX�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������A
�s�m��I���A�����I�@�@�@�@�@�@���Ȃ��̗썰�͂ǂ��ɂ���́I
�y�X�g�ňꑰ�����ł����S��\�\�o���؋��勴����@���i�q��13���j
�S�ˑ]����ˊ��A�@�@�@�@�@�@�@�����������͕̂S���Ɉꌬ�������A
�r�������������B�@�@�@�@�@�@�@�r�ʂĂ����ɓ������ݐ����̉��������Ȃ��B
�V����r�X�͓��A�@�@�@�@�@�@�@�V�����˂�����Ȃ��Đ���オ��A
�s���e�F�Ď��K�B�@�@�@�@�@�@�@���K���Ă��Ď��҂��F�l�̎p��
�����Ȃ��B
�i�Q�j���̂ői��������
�@��Q�҂ƈ⑰�����̂ői�����̂́A������ʂɖ��S�Ɏ����Ă����u�S�v�A���Ǝ��Ɋu�Ă�ꂽ���O���A�l�Ԑ��̂Ȃ��u���{�S�v�̍����Ȃǂ��Ǝv����B
�@���ɁA������ʂɖ��S�Ɏ����Ă����u�S�v�ɂ��āB�u�S�v�Ƃ��������́A������ł́A�@�ɂ܂����A�S�߂ł��邱�ƁA�A�r�������A�B�c���ł���Ȃǂ̈Ӗ���\���B
�@�u�����������Ƃ͕S���Ɉꌬ�������A�r�ʂĂ����ɓ������ݐ����̉��������Ȃ��v�u���̂͑������ĉ^�т���Ȃ��v�u���[�͖쌴��ʂɍ��͎R�̔@���ςݏオ��A����Ƃ���܂��ɋS�̋������������Ă���v�u��nj����H���U�炩�����l�����U�����A�J���X������̂̌������X�����v�Ȃǂ̕���́A�܂��Ɂu�S�v���̂��̂ł���B
�@���ɁA���Ǝ��Ɋu�Ă�ꂽ���O���ɂ��āB������ł́A�v�w��e�q�Ȃǂ̐e���̊Ԃɂ���e���Ȃ��O��\�����t�Ƃ��āu�e��v�Ƃ����ꂪ����B���́u�e��v���A�ˑR�ȍГ�ł��������S�Ȃ������ŁA������e����䩁X���鋫�ɂ��u����ꂽ���Ǝ��̓�̐��E�ɕ������A�i���̕ʂ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃ̂炳���A�l�X�͎��̂ői�����B
�Ⴆ�A�u�e�ʂ���������ւƉ����čs���̂�ڂ̓���ɂ��v�u�Ƒ���S�����ċ������Ԏ҂̎p���ɂ܂����v�u�V�����҂͎q���v���ĔE�ы����A�c���͕������������ċ�����߂��v�u����Â�ł݂Ȃ������������A�v�u����ǎ��Ɩ��S�l�́A�Ƃ������ɐS��ɂ߂Â���v�u���������A���Ȃ��̗썰�͂ǂ��ɂ���́I�v�ȂǁA���̖��O�̎v���̕\��ł���B
��O�ɁA���{�R�ɑ��鉅���ɂ��āB�Ⴆ�A�u���{�R�͈����̂悤�ɒ�����N�����A���{���͋������悤�Ƀy�X�g�Œ����l���E���v�u���X�̈����͐r���d���A���{�R�͋Ɉ��ł���v�u���{�̋S�����͘T��Ղ̂悤�ɗǐS�Ȃ��A�ē��E�E�l�E�����E���D�����ł͖��������A�퓿�Ƀy�X�g�ۂ��U�z�����v�ȂǁA���{�R�ɑ���ɗ�ȉ����̔O��`�����B
�i�R�j�G�Ŕ�Q�̏�\������
�@�����ł́A����͔�Q�҂ł���⑰�ł���Ȃ���A�ې��Q�����ψ���̉���ł����钣�璉�Ɖ��x�������G���Љ��B
�@��l�́A�G��`�����@�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ�����B�u�]���Ɏc���Ă��铖���̈�ۂ����ɑN���ŁA�������ق��G��̋Z�p���������Ă��Ȃ��Ă��A�ǂ����Ă���Q����̕��͋C��`�������ĕM���Ƃ�`�����v�ƁB
�@���璉�@����l�̒�����ɍs�����e
�@�O�q�����Ƃ���A���璉��5�˂�3�˂̒킪�y�X�g�ŖS���Ȃ�����A���e�͉Α�������邽�߂ɁA��l���Q�Ă���悤�ɑ��������ɓ���V���_�ŒS���A��O�̍r��n�ɂĂ�������Ɩ��������B���̊G�͂����`�������̂ł���B
�@�Èł̒��ŁA�������������e�̕\��͌����Ȃ��̂ɑ��āA���l�̊炪�͂�����ƕ`����Ă���B���璉�̔]���ɍ��܂ꂽ�킽���̎p�́A�i���ɂ��̉��炵���܂܂ł���B
�A���x��@�Ό�����
�@�����ƐΌ����ɍݏZ���A�������y�X�g�Ɋ������㎀�Ɉꐶ�����x��̔]���ɂ������A�y�X�g��Q����O�̐Ό������̂̂ǂ��Ȏp���`����Ă���B
�B���x��@�������Ƃ̃y�X�g��Q
�@�Ό������Ƀy�X�g��Q���������ہA�����̎Ⴓ�Ɛg�̂̏�v���Ɏ��M�����������x�A���������̎��҂��o���ƂŖ����̎�`���������B���̈ꗬ���Ƃ̒������Ƃ̔�Q���ڂ̓�����ɂ����B
�C���x��@�Ό������k�ɋ{������̔�Q�Җ������i
�@���x�ڌ������Ό������k�ɋ{������̔�Q�Җ������i�ł���B
�D���x��@�Ό�������ɋ{������̔�Q�Җ������i
�@���x�ڌ������Ό�������ɋ{������̔�Q�Җ������i�ł���B
�E���璉�@���R�̔�Q�ҕ�n
�@�G�ɕ`�����u���R���w�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
����Z�\���R�A�@�@�@�퓿�s�X�悩�痣�ꂽ�Ƃ���̒��R�A
���H������t�c�B�@�@ �R����t�c�����Ԃ��Ă���B
�O��s��u���A�@�@ �O��l�̒j���y�X�g�Ŏ���ŁA
���͕S���A�B�@�@�@���͂̕S���������Y���ɂ��ꂽ�B
�r�n�������A�@�@�@�Q���̍r��n����n�ɂ���A
�͈䊢�{�u�r�U�B�@�@ ��˂������}�����̂ł����ς��ƂȂ����B
��?����T���D�A�@�@ ��nj���T���r�𑈂��ĐH���A
�r���Ւn�L�O�V�B�@�@�@�������ʁA�l���̏L�����@�����B
�S�L�T?�l�����A�@ ��S�������T���i����n������A
��_�V���S�_���B�@�@�@�����������������Ɋ̂��ʂ�����B
�����͓y�n�ʐς̒P�ʂł���A�P����0,992�A�[���B
�����R������ɁA�����}�R����44�t486�c�����Ԃ��Ă����B1942~44�N�̊Ԃɂ��̒��Ԓn����y�X�g�Ɋ������Ď����m�������玟�ւƉ^�яo����A���͂̍r��n���ˁA�}�ɖ��߂�ꂽ�B�퓿�����ψ���́A���R������̑��X�ŕ�����蒲�����s���A���m�̑�������Ղ������m��a���A�y�ю��ӂ̌ØV���瓖���̎���悵���B���璉�����̒����ɎQ�������B
�F���璉�@���R�̔�Q�Җ������i�P
�@�ØV�����̘b�Ɋ�Â����A���璉�̔]���ɕ��������̒��R�ɂ������Q�Җ������i�B
�G���x��@��Q�҂̑���P
�@�y�X�g�ɂ�鎀�҂��o�n�߂�����̍��A�����͂�����Ǝd��������A8�l�Ŋ���S���ł����B
�H���x��@��Q�҂̑���Q
�@�y�X�g�ɂ���Q���g�傷��ɂ�A�e�ƂŎ��҂��o��悤�ɂȂ����B
�I���x��@��Q�҂̑���R
�@�Ƒ��Ǝ��҂Ƃ̔E�тȂ��ʂ�B
�J���x��@��Q�҂̑���S
�@���҂̖����ɒǂ���Ƒ��B
�K���x��@��Q�҂̑���T
�@�Ƒ��S�������S���u��ˁv�ƂȂ����B
�L���x��@��Q�҂̑���U
�@�y�X�g��Q���Đl�e���a��ƂȂ������B
�M���璉�@���{�R�̏퓿����
�@1938�N12��������{�R�̏퓿�������n�܂�A���N�ɓn���đ�������P�ɂ�肽������̎s�����S���Ȃ�A���璉�̉Ƃɂ���Q���o���B
�R�D�L���̋��L
�@2000�N�Ȍ�A�퓿�ې풲���ψ���̊����́A�����ȊO�̊����ɂ��L�������B2001�N�A�n���퓿�s���{�̌㉇�āA�ނ�́A�u���{�R731�����ɂ��ې�Ə퓿�n��ɂ������Q�v�Ƃ����W������J���A�s���̊X����A��w�⍂�Z�A�����w�Z�Ȃǂ������B���z�m�[�g�ɂ́A�s����w�������̊��z����������Ə������܂ꂽ�B���݁A���̓W���́A�퓿�s���Ċقŏ�ݓW������Ă���B
�@��Q�҂�⑰�������w�Z�ɏ�����A�w�Z����Â���u����Ŏ���̐푈�̌����Ⴂ����ɓ`���A�푈�̔ߎS�����i���ɖY��Ȃ��悤��҂Ɍ���Ă���B
2002�N�ɁA�����ψ���́A�u�ې�̍ߍs��F�߁A�Ӎ߁E�������s�����Ƃ���{���{�ɋ��߂鏐���^���v���퓿�n��œW�J�����B�����ψ���̉�������́A�X���ɗ����A����̔�Q�̌������Ȃ���A�s���ɏ������Ăт������B�܂��A�_���n����K��A���X�𑖂������B�ނ�́A30���l�̏������W�߂��B
�S�D�p�������L��
�@1941�N�ɋN�������ې킩��A���ł�60�N�ȏ�̍Ό����o�����B�����҂Ƃ��Ă̔�Q�҂�⑰�����͔N�V���āA���N�S���Ȃ��Ă����B
�@����1998�N�Ɉ��ڂ̒����ʼn�������X�ɁA���ځA�O��ڂɍs�������ɍĂщ�����������A�e������u�S���Ȃ����v�Ƌ�����ꂽ���Ƃ��A���������B�Ⴆ�A�q�������p�����������A�]���P���́A���������������x��ɍs�������͊��ɖS���Ȃ��Ă����B
�@�A���A�����̖S���Ȃ������X�̍ې��Q�̔�������{���{�ɋ��߂�Ƃ�����u�́A���q�⑼�̐e���Ɍp������Ă���B
�@��������1999�N10��25���ɐ���������A���j�ƐU�����e�̈ӎu���p�����A�����ƂȂ����B
�@�`�ׂ�1990�N1���ɐ����������A�ȏ��Γ��͐��O�`�ׂ��y�X�g�Ŏ���e���Â�ł���p�����Ă����̂ŁA���`�ׂ̑���ɎO�j�`�V���ƂƂ��ɒq�����������B�`�ׂ̋Ⴖ����e���ÂԎ��̂��q���ɏ������ꂽ�B
�@�܂��A�j���C�̂悤�ɁA�����݂ł��邪�A�����̗p�ӂƂ��č��̂����ɑ��q���u�i�p���l�v�Ƃ��ė��Ă��l�������B�j���C�́A���j���u�i�p���l�v�Ƃ��Ďw�����A�q���ɂ�����ɂ��Ė��L�����B
��T�D��Q�n�̐l�X�̍ې�i�ׂւ̎v��
�P�D�B���ꂽ���j�I�����𖾂炩�ɂ���
�@�����n�ق͍ې퍑�Ɣ����i�ׂɊւ��锻���ɂ����āA���{�R�ɂ��ې�̎������̂��̂�A����ɂ��l����n��̎Љ���ɑ���r��Ȕ�Q�͔F�߂����̂́A�����͔F�߂Ȃ������B�܂��A���{���{�ɂ�茵���ȑΉ��𑣂������A���{�ɑ���@�I���ق͗^���Ȃ������B
�����n�ق̔����y�ѓ��{���{�̑Ή��́A������x��Q�҂̐S��[���������B�퍐�Ƃ��ꂽ���{���{�́A�n�قł̑i�ׂ̑S�ߒ��ɂ����āA�I�n���ق�ۂ������A�������o���ꂽ����A�n�ق̑Ή�����悤�ȍÑ������Ă����B���̂悤�ȓ��{���{�̑ԓx�́A��Q�҂�⑰�Ɂu�ݑь��I�����㟭���v�A�܂�A�������ݏo���Ă��鏝�Ղ̏�ɐV�����������邱�Ƃɓ������B
�ނ炪�]��ł���̂́A���{���{���ې�̎�����F�߁A���܂ʼnB����Ă������j�I�����𖾂炩�ɂ��A�Ӎ߂��邱�Ƃł���B�c�߂�ꂽ���j�����߂Ȃ��ƁA��Q�҂̐S�ɐ[���c����J���͂ʂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��Q�҂̐l�ԂƂ��Ă̑����ւ̏��F�̑����́A���j�I�߂���F�߂����邱�Ƃɂ���B
�Q�D����ꂽ����Ȃ��̂ւ̏���
���{�R�̍ې�ɂ���āA�퓿�̐l�X�͑���Ȃ��̂��������B��������̑��������D���A�l�ԂƂ��Ă̑��������݂ɂ���ꂽ�B���Ɣ����i�ׂɑ��āA��Q�҂�⑰���v�����Ă���̂́A�܂��ɖ��Ƒ����ւ̏����ł���B
�@���ƓX�����ߑ��̋M���Q�́A�q���Ɂu�S����烁A�������ЁA���w��烁A��������v�A�����A�u���O�͉��̍߂������Ă��̂悤�ȍГ�ɑ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�q�ǂ��ɉ��̗����x�������čЂ��Ɋ������܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�A�Ə������i�M���Q�q��22���j�B
�����K�₵����Q�n�̐l�X���J��Ԃ������Ă���̂́A�u�퓬���ł��Ȃ��n��ɐ������閯�O�ɑ��Ă���قNjK�͂̑傫���A�c�E�Ȏ�i�̎E�C�́A���j��܂�Ȃ��Ƃł���B��Q������X�́A������v�����錠���������Ă���B�A���A���������炦���Ƃ��Ă��A���������͋A���Ă��Ȃ��B��X���������e���A�c�߂�ꂽ�l���A���Q���ꂽ���N�A�j�ꂽ���������X���A�����߂�Ȃ��B����ł����������߂�̂́A��X�ɂƂ��Ă��ꂪ�A�߂�Ƃ��������߂�F�߂�ł���A��X�̔Ƃ��ꂽ�����ȑ�����F�߂�ؖ��ƂȂ邩��ł���v�A�Ƃ������ł���B
�@��Q�҂����̏،��́u�����Q�҂Ƃ��ď��F����A�����A���̉Ƒ�������Q�������Ƃ��ĔF�߂�A�Ƃ����i���ɂ́A�@�I�F�m����j�I�����̔F�m�����߂�i���ƂƂ��ɁA����ɊҌ������Ȃ������Ƃ������I�ȗv���\�\�������g�̑������m�肷��Ƃ����v�����܂܂�Ă���̂ł���v�B*21
�@���̓_�Ɋւ��ẮA�ې��Q�҂���ł͂Ȃ��A�u�Ԉ��w�v��Q�҂�A�����A�s��Q�ҁA���w���Q�҂Ȃǂ��A��v���Ă���ƌ�����B
�R�D���{�E���{�l�ɑ���C���[�W�̕ω�
�@�ߋ��̐푈�́A���������̖����Ԃɑ傫�ȍa��o�����B���A���{���u�W�c�Y�p�v�̕��͋C�ɐZ���Ă����̂ɑ��āA�����́A�N�����ꕎ�J���ꂽ���j�̋L����A�R����`�ɑ���x���S�������Ă����B���{���{�̉ߋ��̐푈��푈�◯���ɑ���ԓx�́A���̂悤�ȍa�߂�ǂ��납�A�����̍����Ԃ̑��ݕs�M��A�u���������Ɋg�債���B
�@����A�ې��A���̐푈�����Ɋւ���i�ׂɌg�����{�ٌ̕�m��A�w�ҁA�s���c�̂́A���{�R�ɂ��푈�ƍ߂̗��j�I�������č\�����邽�߂̐ɂ��݂Ȃ��w�͂��A��Q�n�̐l�X�̓��{�ɑ���C���[�W��傫���ς��������B
�@�����ł́A�푈��Q�҂�⑰�����ł͂Ȃ��A��ʐl�������ԓ��{�R���u���{�S�q�v�ƌĂ�ł������A���{�������������Ƃ̂Ȃ���Q�n�̐l�X�ɂƂ��āA���{�l�̃C���[�W�͂܂��ɋs�E�́u�S�v�������B
�@�ې퍑�Ɣ����ٔ��ŁA���ӂ������ē��{�R�ɂ���Q�ׂɗ�����{�l�����߂Č��ꂽ���A�e��Q�n�ł͑傫�Ȕ������N�������B�ŏ��́A���^�A�s�M�A���������A�������ۂ����Q�҂��������A�ڂ��邤���ɁA�������ɉߋ��̓��{�l�ɑ���Œ�ϔO���痣��A�������l�̐l�ԂƂ��Č���悤�ɂȂ�A���͊W�����ꂽ�B
�@���j�I�����d���Ă͂��߂āA���������l�ԓ��m�̘A�т�n��o�����Ƃ��\�ƂȂ�B
��U�D��������Q�����������҂ւ̎��������@���Ă�����{
�@�����{���{�̉ߋ��̐푈�◯���ɑ���ԓx�́A�L�������A���{�Љ�̕a���Ɗ֘A����B�����ł́A���{�l��C�O�̊w�҂̓��{�Љ�a�����͂̋c�_�����p���Ȃ���A�푈�◯�̏������߂����ē��{���{�A���{�Љ�ɂ�������̏��݂ɗ����Ȉӌ����q�ׂ����B
�P�D�u�Y�p�̐��́v�Ɓu�������v
�@�A�����J�ɍݏZ������n�l�����l�ފw�҃��l���}�E���T���́A���̓��{�ɂ�����푈�L���ɂ��āA���̂悤�ɏ������B
�@�u�������̎��푈��Q�ƍL���E����̌��������������L�����A���̃A�W�A�����⑾���m�n��ɂ������čs�������X�̗̔��j���v���o���Ȃ����{�l�A�Ƃ����\���́A���ł͊C�O�̃��f�B�A�ɂ����Ă�������������g���Â��ꂽ�����ƂȂ��Ă��܂����B���{�鍑�̐A���n�x�z��A���{�b���̖��̂��Ƃɍs��ꂽ�c�s�s�ׂ��A���j�̈ꕔ�Ƃ��Ă����ĂЂ낭��낤�Ƃ��Ȃ������푈�I����̒����N�����x�z���Ă����̂́A�܂��Ɂw�Y�p�̐��́x�ł������Ƃ�����B�����Ƃ��A���́w�Y�p�̐��́x�͂������ĉߋ��̂��̂ƂȂ����킯�ł͂Ȃ��B����܂ʼnB����Ă������j���������@����A���Ƃ��ߋ��ɍs�������܂��܂ȍs�ׂ��w�߂��x�Ƃ��ĔF�m���邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃ��Ȃ��A���̖Y�p�𐳓�������_���͎Љ�̊e���ɕ��݂��Â��Ă���B�ނ���A�����Ɩ��炩�ɂ����鍑���{�̉��Q�s�ׂ̐��S����ڑO�ɂ��āA���������h�q�I�Ńi�V���i���I�ȓ�����ł���悤�Ɍ�����B�v*22
�܂��A���_��w�҂̖�c�������́A�����{�l�̐��_�\���ɂ��āA���̂悤�ɕ��͂��Ă���B
�@���A�ߋ��̐푈�̌��ɑ�����{�l�́u�����́A�w�������x�ł���B�푈�̉��S�҂��Ђ�����߂Ė��������A�����Ă������Ă��푈�͔ߎS�Ȃ��̂�����Ƒ����A���a�������铮�����������B�v�u���̓��{�̔��핽�a�^���́A��{�I�ɔ�Q�҈ӎ��̏�ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�B�v�u����ł��Ȃ��A�싞�̋s�E�����A���B�i�������k���j�����ł̋s�E�������A����������Ƃ��Ă̍߂��������A���邢�͔s���̂Ȃ��ʼnƑ��⓯�E��u������ɂ����߂��L�����l�͂���B�������A�ނ�̐��͐��̖������̈��͂ɉ���������Ă��܂����B�v*23
�@�����{�̂��������u�Y�p�̐��́v��u�������v�̌`���ɂ́A���܂��܂ȗ��R���l�����邪�A���́A���j�w�Ҋ}���\��i���̈ӌ�*24�Ɏ^������B�}���\��i���́A�싞��s�E�̋L���Ɋւ��āA���̂悤�ɘ_�����B
�@���{�ł́A�u���j�w�����̐��ʂ������̋L���Ƃ��ċ��L����Ȃ��Ƃ����[���Ȗ�肪����B�v�u���̑傫�ȑj�Q�v���͓��{�̎Љ�̒��ɁA�싞��s�E�̋L���E���悤�Ƃ������łȐ������͂������āA���ꂪ�E���ƌ��т��Ė\�͓I�ȋ��Ђ��s�����Ƃ����C����Ă���Ƃ���ɂ���B�������������`�Љ�ɓG���錾�_�}���̐��͂����{�̈ꕔ�ێ琭���Ƃƌ��т��Ċ����Ȋ��������Ă��邽�߁v�A���_�A�̒��Ɂu�싞��s�E�ے�̍\���v�����݂���̂ł���B
�Q�D���҂ւ̎����̌��@�Ɓu�W�c���m�v
�@�펞���A���{�̏����Ɛΐ�B�O�́A�싞�U����ɎQ�����������ɓ���A���m�Ɠ��s���Ȃ��疧����ނ����A���������ł����Ɂu�����Ă���v����`�����B�����w�����Ă�镺���x�́A�u���̂��邪�܂܂�`���v�A���{���̖\�s���A�u��̓I�ɂ͒����l��퓬���̎E�Q�A���ߗ��̎S�E�A�w�����x�Ə̂��闪�D�A�����A�����ĕ��v��`���A�܂��A�u���m���������̂悤�Ȕ؍s�ɋ�肽�Ă���̎c������`���o�����v�B���̏������u���J������C�v�Ƃ����߂ŋN�i���ꂽ���A�ނ́A���M�������@�����̐^���������ɓ`���邱�Ƃł���A���ꂪ�����́u���ƎЉ�ɑ���ǐS�v�ł���Ɣ��_�����B���ΐ�́A�u�����m�肽���͉̂R���B���������A�s�����Ǝc���Ƌ��\���Ƌ��|�Ƃɖ������푈�̗��̎p�ł���v�ƁA��z�����B
�@���A���{�Љ�ɂ����āA�w�����Ă�镺���x���߂����ėl�X�ȋc�_���������B������蒍�ڂ����̂́A���̂悤�ȁA�N������鑤�̐l�X���܂��������������Ƃ�����҂̗���ɑ���ᔻ�ł���B
�@�u�ΐ�B�O�́w�ǐS�x�͓��{���Ƃɑ���w�ǐS�x�ł���A�������z������̂ł͂Ȃ������B�v�u���̏����ɓo�ꂷ��l���̗B��l�A���������̐���Ă��铖�̑���ł���x�ߌR�A�x�ߖ��O�ɂ��čl������^�����芴��������Nj������肷�邱�Ƃ��Ȃ��B�v�u�e�����̍s�ׂ����̖{�l�ɂƂ��Ăǂ̂悤�ȈӖ��������͍l���Ă��A���̍s�ׂ�����i�������O�j�ɂƂ��Ăǂ̂悤�ȈӖ����������l����Ƃ��낪�Ȃ������B�v�u�N���푈�̎��Ԃ͊�̑O�ɂ��낪���Ă����͂��ł��邪�A�ΐ�B�O�͓��{�R���͐N���푈���Ȃ��Ă���Ƃ����{�������ނ��Ƃ��ǂ��܂ł�������Ă���B�v�u�N��������Ⴊ�Ȃ���ΐN������鑤�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v*25
�@�싞�s�E�ɂ��ẮA�O���R�I�v���u���O�v�Ƃ����^�C�g���̒Z�ҏ����������Ă���B�u���O�v�ɂ́A�u�싞�����ɂ����鋭���E�Q���Ƃ��Ēm������{�R���Z�̒����l�����ɑ��鐫�ƍ߁A���Q�s�ׂ��`����Ă��邪�v�A�u�O���ɂ��A�����l�����ɑ���c�s�s�ׁA���ƍߍs�ׂł������Ƃ����ӎ��͂قƂ�NJŁA�ނ���w���̊y���݁x�Ƃ��čm��I�ɕ`���Ă���v*26�B
�@��L��l�̍�Ƃ̐N���푈������ڂ́A���{�l�̉ߋ��̐푈�ɑ��錩�����f���o���Ă���ƌ�����B���������S��`�I�ɐ푈�𑨂��A�s�E����鑤�̐l�X�֎������������ɁA����ɐl�ԂƂ��Ă̔z�����������Ȃ������B�ނ�̂��̂悤�Ȏ����ɑ��āA��Ɉ��p�����Ƃ���A���{�Љ�A���Ɋw�E��m���l����ᔻ�̐����グ��ꂽ���A�c�O�Ȃ��ƂɁA����u�N������鑤�v�̗���ɗ����Đ^���Ɏ��g�l���Љ�Ȋw�I�������ʂ�A���w��i���������ɏ��Ȃ��A�������A���̐��ʂ������ɍL���`����Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@�N���҂Ƃ��đ��҂ɗ^������ɂ��A���̑��҂̗���ɗ����ė������悤�Ƃ���p�������@�������ʁA���{�l�̊Ԃł́A�N���푈�̐��ł̓��{�R�̏��Ƃ�A����ɂ���Ă����炳�ꂽ�ߎS�Ȍ��ʂȂǂ́A���Q�҂Ƃ��Ă̗̔��j�ɑ���m�������Ȃ��A�����ׂ����m�̏�Ԃł���B�ߋ��̐푈�Ɋւ��邩����A���{�l�͎��������Ȏ��g�݂̂̐��E�ɕ����߂Ă���B
�R�D���҂ւ̑z���͂̓W�J�ɂ́u�m���v�̕��y�ƕs���s���̓w�͂��K�v
�@���_���l�ł���A�A�����J�E���X�A���[���X�ɂ��郆�_���l���Z���^�[�A�T�C�����E���B�[�[���^�[���Z���^�[�̕��ْ��ł���G�u���C���E�N�[�o�[�́A��Q�������������グ�āA���������̎���Q�ɂ��Ắu�m���v���L���Ă����K�v������Əq�ׂ��B
�@�u�z���R�[�X�g�̐��Ҏ҂ł���A�w�i�`�n���^�[�x�Ƃ��Ă��L���ȃT�C�����E���B�[�[���^�[�����́A�w�L���̎���x�ƌĂ�Ă��܂����B����E��킪�I����ĉ��N���̊ԁA���E�̓i�`�X�̐�Ŏ��e���̋��낵�����v���o�����Ƃ��܂���ł����B�������A�T�C�����E���B�[�[���^�[�����́A�i�`�X�̔Ƃ����ƍ߂Ɛ��ʂ���������������Ƃ������A�h�C�c�����ƃ��_���l�̘a���̂��߂ɉ����d�v�ł���A�Ǝ咣���Ă����̂ł��B�ނ́A�ߋ��ɋN�����l���ɑ���ƍ߂ւ̒��قƖ��S���A�₪�ď����A���l�̔ƍ߂Ɍq�����Ă������Ƃ����ꂽ�̂ł��B�v
�T�C�����E���B�[�[���^�[���̂悤�ȃ��_���l�̓w�͂����������炱���A��
�Q�̋L��������A��Q�҂̑̌��Ɋ�Â������X������Q���Ԃ́u�m���v�����ɒm���A���ꂪ�A�h�C�c�ɂ����郆�_���l�s�E��푈�ɑ��锽�ȂɂȂ������B*27
�G�u���C���E�N�[�o�[�����������Ƃ���A�ߋ��̃z���R�[�X�g��ې�Ȃǂ̐푈�ƍ߂ɑ��锽�Ȃ�A���Q�����Ɣ�Q�����̘a���ɕK�v�Ȃ̂́A�܂��A�u�m���v�A�����u�ߋ��̎����v���̂��̂ł���B
�u�ߋ��̎����v�Ɋւ���u�m���v�̌`���́A�����҂Ƃ��Ă̔�Q�҂��ɂ͍l�����Ȃ��B��Q�҂̑̌��⎋�_��������ė��j���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�����̓����҂ɉ�z�����Ă������������x�̍ې퍑�Ɣ����i�ׂ́A�u�ߋ��̎����v���č\�����邱�Ƃɑ傢�ɈӖ��������Ƃł������B
�@�܂��A��Q�҂������グ�邱�ƂƓ��l�ɏd�v�Ȃ̂́A���̐��ɐ^���Ɏ����X���邱�Ƃł���B
�@�ې�̗��j����������w�҂�A�ې퍑�Ɣ����i�ׂ̂��߂̎������ׂٌ̕�m��s���c�̂̕��X�́A��Q�҂̐��������ƕ����Ă����B�ނ�̎p���̍���ɂ́A�l�Ԃ̑����A���J�I�ɂ��̐�����������Q�҈�l��l�̖��̑������m�肷��ӎu������ꂽ�B�܂��A��Q�҂̐S�g�ɍ��܂ꂽ���_�I���j�I���������߂�E�C�Ɣz�����������B�����āA�����̒����Ɉ��Ղɓ������Ȃ���ÓI�����I���f���������B���̂悤�Ȏp�����Ȃ���A�ې�̎��������グ���邱�Ƃ͂Ȃ������B�푈�ƍ߂̗��j�ɒ��ʂ���ۂ́A���̂悤�Ȏp�����K�v�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁA���͎v���B
�@����ɁA�}���\��i�����w�E���ꂽ�Ƃ���A���{�Љ�ł͐푈�ƍ߂̎����u���E���鐭���I�\���v�����݂���B�ߋ��̐푈�̕��̈�Y�𖢗��ւƌq�����������߂ɁA���̍\���I������������K�v������B����Ɋւ��āA���{�̍ٔ����ɑ傢�Ɋ��҂��A�@�w�I���n����̌����Ȕ��f�́A���{�Љ�́u�Y�p�̐��́v�̖��̍����Ɋ�^�ł���ƍl���Ă���B
�S�D���̒��
�@�ې�̐푈��Q�Ɛ푈�L�����������Ă�����w�҂Ƃ��āA�ٔ����ɑ��Ď��̂��Ƃ��Ă���B
�@��������̕⏞�v��������邱�Ƃ̂ق��ɁA���ɁA���{���{�́A�ې�̐푈�ƍ߂̎�����F�߁A��Q�҂̕��X�ɑ��ĎӍ߂����邱�ƁB���ɁA��Q�҂̐l�ԂƂ��Ă̑�����F�߁A�ނ�̖����̂��߂ɓ��{���{���o�����A���������Ŕ�Q�n�ɂ����Ĕ�Q�҂̕��X�̖��O�����ވԗ����������邱�ƁB��O�ɁA��������̍߈����𐢂Ɍ������A�l�ނ��i���ɐ�������̎g�p���������悤�x����炷���߂ɁA���{���{���o�����A���������Ŕ�Q�n�ɂ����čې�L�O�ق��������邱�ƁB
��V�D�q�����X�g�F
1. ���R�����������\���P�i2��)
2. �͕���������������
3. �����R���މƒؑ��閾��
4. �����R���މƒؑ������
5. �Ό������s�X�扩�x��
6.�@���ƓX���F�Ƌ����z�m��
7. ���ƓX����䑺���ƐU
8. ���ƓX����䑺������
9. ���ƓX�������F�P���i2���j
10. ���ƓX���ӉƏ�������
11. �،��n����?蘑�������
12. �C�����q�`�������]
13. �o���؋���Ƙp�����
14. ���䛼�����䛼����؋�
15. ���R�������������J���q��
16. ���ƓX������������
17. ���ؒ���ᨉ��j�h
18. �퓿�s�X�敷�@�_
19. ���ƓX�����k�p���\�Ŕ�
20. �퓿�s�X��k�u�b
21. ���ؒ���N��������
22. ���ƓX�����ߎ����M���Q
23. ���ƓX���z蘈����K�{��
24. ���x���ՉƘp���ՍF�M
25. ���Ƌ��������������{
26. �퓿�s�X�旛����
27. �퓿�s�X�撣�璉
28. �͕������������k��L�^
29. �͕������d�������{��
30. ���Ƌ���������������
31. ��Ƌ������ƚ��������q
32. ��Ƌ�����N���Ռd��
33. ���R�����t�������g��
34. ���R����������������
35. �Ζ勴���ω��������ƌN
36. �퓿�s�X��{��J���[�G
37. ���ƓX���F�Ƌ������P�R
38. �Ό��������q����������
39. ���m���i���ƓX���j�������i����j�J�v��
40. �퓿�s���z�H�j���C
41. �퓿�s���Γ��A�`�V��
|