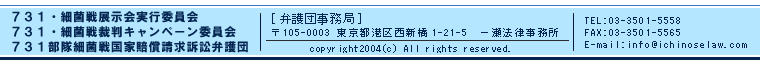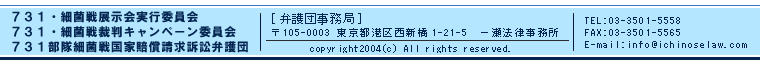|
鑑定意見書
>鑑定意見書のメニューに戻る
国家賠償法附則6項の「従前の例」と
国家無答責の法理
南山大学大学院法務研究科教授 岡 田 正 則
1.はじめに
最近、戦前の法体系の下では「国家無答責の法理」が実定法上の根拠を有していたという謬論が主張され、またこれを容認する下級審判決がいくつか出されている
。その際に論拠として挙げられるのは、行政裁判法16条が「損害要償ノ訴訟」を行政裁判所の管轄外としたことおよび旧民法373条から「公私ノ事務所」という文言が草案段階で削除されたことである。つまり、これら2つの規定の前提には「公権力の行使に基づく国家責任を否定する立法者意思」
があったので、これらの規定は「国家無答責の法理」の実定法上の根拠とみなすことができる、というのである。
わたしは、2004年7月13日付けの鑑定書「細菌戦と国の賠償責任--『国家無答責の法理』による国の免責可能性の検討--」において、行政裁判法・裁判所構成法・旧民法・現行民法などの立法過程および大審院判例をたどることによって、このような主張が史実の誤解と無根拠な推測から成り立っていること、「国家無答責の法理」と呼びうる考え方が確立したのは1930年代から40年代の大審院判決を通じてであったこと、それゆえ「国家無答責の法理」は実定法に根拠を持つ法理ではなく、判例法理に過ぎないことを明らかにした。本稿では、上記のような謬論が生じうる歴史的・理論的背景を解明することをとおして、「国家無答責の法理」が判例法理であって、国家賠償法附則6項にいう「従前の例」には含まれないこと、つまり、この法理は今日の裁判所が適用できる法理ではないことを再確認したい。
2.明治憲法体制確立期における国家活動の免責理論と国家無答責の法理との関係
(1)序
明治憲法体制の確立期である1880?90年代の時期には、たしかに立法作業等の中で、国は国家活動に起因する損害ついて賠償責任を負わなくてよいとする見解がさまざまな形で表明されていた。しかし、これらの見解をよく見てみると、その中では種々雑多な免責理論が未整理のままで用いられていること、しかもその理論の多くが今日でも維持されていることに気がつく。日本国憲法や国家賠償法の下でも主張できるような免責理論は、「国家無答責の法理」とは無関係だと想定できるのではなかろうか。
ここで本節の結論をあらかじめ述べておけば、この時期の立法作業等において国家活動についての免責理論が主張されたとしてもそれは必ずしも「国家無答責の法理」が存在していたことの証明にはならず、むしろ単に公権力概念の未成熟と理論的な混乱を示すものでしかない、ということである。以下、この時期に存在していた国家活動についての免責理論を順次検討する。
(2)明治憲法体制の確立期における国家活動の免責理論
1)主権(統治権)を根拠とする免責論
まず、国家活動の性質が主権の行使であること根拠とする免責理論が主張されていた。ここには、「主権は責任と矛盾する」とする原理的な主権免責の理論と、そこから派生した司法権謙抑の理論である統治行為論が含まれる。たとえば、大日本帝国憲法61条は「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」と規定していたが、同憲法の制定者はこの「行政官庁ノ違法処分」を、「法律又ハ法律上効力カアル命令ニ依ルノ処分」だけでなく「憲法上統治権ニ依ル所ノ大政ノ処分」も含むものと解していた
。つまり制憲者の解釈においては「行政処分」を司法裁判所の管轄外とする根拠の一つが、いわゆる主権免責だったのである。
とはいえこの時期すでに、たとえば近衛篤麿は、主権と国権を区別し、免責されうるのは前者に限られるとする見解を示していた。
「君主ノ大権ナルモノハ主権ト国権ノ二ニ分ツヘシ人往々此二者ヲ混合シテ同一視スルモノアリト雖モコレ全然別物タラサル可ラサルナリ何トナレハ国権トハ施政権ニシテ主権トハ統御権ナレハナリ之ヲ詳言スレハ国権ハ制限シ得ラルベク主権ハ制限シウベカラザルモノナレハナリ……君主ハ内外ニ向テ国家ヲ代表スル最高ノ機関ニシテ各般ノ政務ヲ統一スルノ地位ニアルモノナレハ其下位ニ在ル所ノ機関ニシテ之ニ責ヲ負ハシムルコトハ到底為シ行フ可ラサレハナリ故ニ君主ノ無責任ナルコトハ彼ノ『王ハ悪事ヲ為シ能ハス』ト云フ格言及ヒ『王ハ法ニ服セス』ト云フ法語ニモ基キシニハ非スシテ全ク彼ハ主権者ナレハ無責任ナラサル可ラスト云フ固有ノ一理由アルニ依ルナリ」「伊藤伯ハ其憲法義解ニ『大臣ハ其固有職務ナル輔弼ノ責ニ任ス而シテ君主ニ代リ責ニ任スルニ非サルナリ』ト説ケリ是正鵠ヲ失シタル論ト云ハサル可カラス……君主ノ政務上ニ関スル行為ニハ大臣之ヲ預リ知ラスト云フニ至テハ実ニ其不当ヲ鳴ラサヽル可ラサルナリ何トナレバ総テ君主ノ政務ニ関スル行為ニハ其責任ヲ負担スヘキ国務大臣ノ意見モ之ニ加ハリ始メテ法理上有効ノモノトナルモノナレハナリ」
。
すなわち、君主(主権者)は国家を代表し政務を統一する最高機関であるから、司法権のような下位の機関によって責任を問われないのに対して、国権は憲法の制約の下に置かれ、国務大臣がその責任を負うのであり、こうして憲法は「君主無責任ノ終ニ専恣ニ流レンコトヲ予防」しているのだ、とされている。国務大臣がどのような責任を負うのかは明らかにされていないが、いずれにしても、帝国憲法制定直後の時期に、統治権を根拠とする主権免責の理論は国権(国務大臣以下の官吏の活動)には適用できないとする見解が表明され、『憲法義解』の解釈--伊藤博文と井上毅の解釈--が批判されていたことは銘記されてよい。
行政裁判法は、上記の帝国憲法61条を承けて、「行政庁ノ違法処分」に対する訴訟か否かを裁判管轄の判別基準とした。すなわち立法者は、まず、行政裁判法15条において「行政裁判所ハ法律勅令ニ依リ行政裁判所ニ出訴ヲ許シタル事件ヲ審判ス」と定めて列挙主義によって行政裁判所への出訴を許すこととし、この規定の具体化法である「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」によって、所定の行政処分に関する訴訟に限って行政裁判所での救済を受けられることとした。つぎに、同法16条において「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」と定めたが、この規定は「法律に明文のあるものは[民事裁判所への]出訴を許し又は行政裁判所が取消す処分に依り直接に生ずべき損害の賠償は行政庁に於て処分する外、一般に行政訴訟を許さない」趣旨だと解されている
。要するに、行政裁判法の立法者は、行政処分に対する不服の訴訟はもちろん、行政処分から直接生じた損害についての補償・賠償請求の訴訟も司法裁判所の管轄外としたのである。
裁判管轄の基準となる「行政処分」という文言を立法者自身がどのように解していたかは必ずしも明らかではない。一方では、行政処分とは行政裁判所が適否の判断を下せる事柄だという理解の下で立法作業が進められていた、つまり講学上の行政行為と等しいものと理解されていたと考えることができる
。しかし他方で、立法過程では「独逸ニ於テハ行政処分ヲ両分シ、其主権及ビ警察権ニ属スル行政処分ハ一般ニ賠償ノ責ニ任ゼズ、而シテ国庫財産ニ係ル処分ハ民事トシテ賠償ニ任ズベキコトヲ定メタリ」
と、上記帝国憲法61条の場合と同様に主権と結びつける理解も示されていた。行政裁判法案の検討に参加していた今村和郎は井上毅に宛てた返書の中で、「行政処分」をめぐるこの種の概念的混乱について、「行政処分ト一言ニ申候得共、其中ニハ、上ミ勅裁ヲ仰キ施行スヘキモノヨリシテ、下一市一村ノ長ノ専断ニ任シタル事件ヲ含有シ、即チ外国ニ向テ宣戦スルヨリ一村内ノ道路ノ修築ニ至ルマテ、総テ之ヲ行政処分ト申候ヨリ極メテ混乱ヲ生シ候」
と述べて、警告を発していた。
以上のところから、明治憲法体制の確立期においては、一方で、「行政処分」という実定法の文言によって主権免責と広範な行政活動を結びつけ、裁判管轄配分をとおして免責をこれら全体に及ぼそうとする見解が主流をなす見解として存在したこと、他方で、これを概念的な混乱だと批判する有力な見解も存在したことを確認できる。「行政処分」についての前者のような見解はほどなくして姿を消すが、そこには三つの理論的背景があったと思われる。すなわち、第一に、主権と行政権を区別する見解、つまり主権の行使と行政訴訟の対象になる行政活動とを同列に位置づけられないという見解が支配的になったこと
、第二に、解釈論として問題になったのは、もっぱら行政処分以外の行政活動(国の不法行為)について提起される「損害要償ノ訴訟」であったため、行政処分概念の外延を論じる実益が乏しくなったこと
、第三に、後述のように(3参照)、この問題が裁判管轄の問題ではなく、公法私法二分論による民事裁判所での民法適用の可否の問題として扱われるようになったため、裁判管轄の規定である行政裁判法15条・16条に触れる必要がなくなったこと、である。
国家無答責の法理の根拠のひとつに主権免責の考え方があったことは確かである 。日本では、明治憲法体制確立期においては「行政処分」概念を通してこの法理と主権免責との接続が試みられるが、上述のように、この論理の道筋はひとまず断念された(その復活については後述3参照)。ひるがえって、主権の行使の一態様である「統治行為」について考えてみれば、それはそもそも司法権の管轄外の事項とされ、そこから生じる損害については今日なお損害賠償の対象とは考えられていない
。こうしてみると、主権免責は本来このようにごく狭い範囲でのみ成り立つものであることが分かる。それにもかかわらず、行政活動の免責法理である国家無答責の法理と主権免責とを結びつける考え方が存在した理由は、法制度が未成熟で法治主義が未確立であった時期において、行政活動の正当化根拠を主権という非実定法的な教義以外に見出しえなかったためだといえるだろう。
2)権力分立を根拠とする免責論
つぎに、権力分立を根拠として行政活動に対する司法裁判所の審査を排除することによって国の賠償責任を免除する理論がある。行政裁判法は「損害要償ノ訴訟ハコレヲ受理セス」と定めただけであったから、同法の制定直後の時期には「損害要償ノ訴ヲ司法裁判所ニ提起スルヲ得ヘシ」という主張も有力であった
。これに対して井上毅は、「我国ノ法理ハ果シテ行政官庁ニ対シ損害要償ノ訴訟ヲ司法裁判所ニ提起スルヲ許スヤ否[ヤ]疑ヲ容レサルヲ得ス抑モ当該官庁ニ於テ為シタル行政処分ハ国家ノ意思ナリ主権ノ施行ナリ之ニ対シテ訴訟ヲ提起セントナラハ宜シク法律命令カ特ニ許ス所ノ範囲内ニ於テセサ[ル]ヘカラス(行政裁判法ニ損害要償ノ訴訟ヲ許サザルハ司法裁判所ニ之ヲ提出スヘシト云フノ意味ニアラサルヘシ)……主権ノ作用ニ関シテハ訴訟ヲ許サストハ国法ノ原則ナリ(若シ損害要償ノ訴訟ヲ司法裁判所ニ提起スルヲ得ルトセバ司法裁判所ハ如何ナル手段ニヨリ其ノ裁判ヲ執行シ得ヘキヤ民事訴訟法ノ強制執行ハ行政官庁ニ適用シ得ヘカラサルニ似タリ若シ適用シ得ヘシトセンニハ是行政権ヲ以テ司法権ノ下ニ置クナリ)」と反論していた
。井上の考えによれば、行政官庁に対する損害要償の訴訟を司法裁判所の審査から除外する理由は、司法権が行政官庁に対して強制執行をなしえないこと、一般的には行政権を司法権の下に置くべきではないという点にあった。また翌1891年の論文では、「民法上ノ原則ヲ適用シテ政府其ノ損害賠償ノ責ニ任スヘシトセハ社会ノ活動ニ従ヒ公共ノ安寧ヲ保持シ人民ノ幸福ヲ増進センカ為メ便宜経理ヲ為ササル可カラサル行政機関ハ為ニ其ノ運転ヲ障礙セラレ危険ナル効果ヲ呈出スルニ至ラン」
、すなわち、民法上の賠償責任を行政機関に課すならばその活動に支障が出るという理由から賠償請求訴訟を排斥した(賠償請求は裁判所を通じてではなく行政官庁への訴願によって解決すべきだ、というのが井上の一貫した主張であった)。
しかし、権力分立論を用いて行政権の判断に対する司法権の介入を原則的に排除するという論理は、日本国憲法の下でも「司法権の限界」論として主張されているし
、裁判実務においても使用されている 。また、司法権の介入の可否と賠償責任の成否とは本来別次元の問題である。いずれにしても、上記の論理は国家無答責の法理を支えるものではない。
3)公法私法二分論に基づく免責論
1900年前後の大審院判決で、実体法理論として、国家活動について司法裁判所が違法判断をなしえないことを根拠とする免責理論が定着するようになる。つまり、司法裁判所は私法だけを争訟の裁断基準として用いることができるのであって、公法を扱う権限を有していないという公法私法二分論がこれにあたる。公法事件(行政事件)とみなされた訴訟については民法も公法も適用されない結果、(公法上)違法な国家活動についての賠償責任が免責されるわけである。
公法私法二分論には実定法上の根拠はなかった。行政裁判法の制定者は、「第二 行政裁判ノ権限ヲ民事裁判ト区別スルニハ独逸各国ニ依リ公法私法ヲ以テ分別スベキヤ、又ハ仏国ニ依リ行政上ノ処分ニ対スル訴訟ト云フヲ以テ行政裁判ノ権限ト為スベキヤ」という問題について、ドイツ流の公法私法の区別は例外が多くまた「錯雑ナル学術上ノ解釈」が必要であり「我ガ国民ノ簡単ナル脳裏ニ感触スルコト稍困難ヲ覚ユルヲ以テ」採用できず、むしろフランス流の「行政上ノ処分ニ対スル訴訟ハ行政裁判所之ヲ受理スト云ヘル単一ニシテ近実ナル釈義」を用いるほうが優れていると判断した
。このため、行政裁判所と司法裁判所の間の管轄配分は「行政処分」に該当するか否かを基準として判別されることとなり、また、行政裁判法および関係法令は、少なくとも明文上は公法・私法の言葉を用いなかった。公法私法二分論は、このようにいったん排斥されたが、上述のように大審院判決中に定着するようになる。この経緯の概略を述べれば、以下の通りである。
行政裁判法の施行後、同法15条に基づく「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」において列挙されていない行政処分に対する訴訟、違法な行政処分に起因する「損害要償ノ訴訟」、行政処分以外の行政活動に起因する「損害要償ノ訴訟」、および公法上の債権に関する訴訟を司法裁判所がどこまで扱えるかに疑問が提起され、理論的にも実務的にも混乱した
。ほどなくして、一つの操作が行われることにより、学説と裁判実務の双方で公法私法二分論が支配的となり、行政裁判法15条・16条の規定は上記の問題の処理にとって意味を持たなくなった。すなわち、いずれの裁判所の権限に属するかという裁判管轄の問題を、司法裁判所における実体法規の適用の可否という問題に組み替えるという操作が行われたのである。かくして公法私法二分論は、裁判管轄の場面では意識的に排斥されたにもかかわらず、実体法の適用という場面で復活したのである
。
公法私法二分論は、実定法上の根拠を持っていなかったため、何を基準として両者を区分するのかという難問を抱え込むことになった。学説では、権力関係説(穂積八束)、主体説(美濃部達吉)、生活関係説(佐々木惣一)などの議論が展開されるが、裁判実務においてとくに問題となったのは、公法上の権利義務関係(租税債権・債務、公所有権、公法人の事業活動上の法律関係)をどのように処理するかであった
。ドイツにおける国庫説の影響もあって、当事者が公法人である場合でも、財産的な法律関係については民法を適用して処理すべきだと考えられていたものの、実際にはさまざまな問題が生じていた。租税等を過大に徴収された場合には--滞納処分が介在するとしても--司法裁判所で不当利得返還請求訴訟を提起しうるのか、国等に一定の物資を提供したばあいそれを契約とみるのか徴発ないし収用とみるのか、公法人の非営利的事業活動に起因する損害についての賠償請求権は公法上の権利か私法上の権利か、等々である。こういった問題が顕在化した背景には、実定法整備の進展と法治主義の一定の定着とがあるといえるだろう。すなわち、国や公法人の公益目的の活動であって公法関係とみなされうる場合でも、実定法に即して個別の法関係を分析し、評価できる前提が整ってきたのである。周知のように、公法私法二分論の上記の混迷状況を転換させたのが、徳島市立小学校遊動円木事件判決
であった。この判決を契機として、司法裁判所は、公法関係か私法関係かではなく、権力的な関係か非権力的な関係か(私法の場合と同視できる対等当事者間の関係か)を基準として私法法規の適用の可否を判断するようになっていく。厳密にいえば、公法関係のうち非権力的な関係については私法法規を類推適用する、という方針を採用したのである。かくして、公法私法二分論は、権力的作用・非権力的作用の二分論(あるいは支配関係・管理関係・私経済関係という三分論)に道を譲ることになったわけである。
ここにおいて再び、なぜ権力的作用については、民法を適用できないのかが問われることになった。これに対する答えは、「統治権に基づく作用だから」という主権免責の論理であった
。
4)法治主義による免責論
国家活動の違法性が国に帰属しないことを根拠とする免責理論である。官吏の違法行為は官吏個人が責任を負うべきものであって、国家には違法行為の法効果は帰属しない--したがって当該行為は国家の行為とはみなされない--とされる。この背景には、法人理論(法人自身は職務行為違反をなしえないという理論)と委任理論(委託者が責任を負うのは契約によって受託者に委ねた事項だけだという理論)とがある。たとえば、前者の例として、「政府ハ過失又ハ職権濫用ニ付テハ官吏ヲシテ己レヲ代表セシメス法律ニ定メ且法律ニ従フタル職務ニ関シテノミ嘱托アリ」
という説を、後者の例として「予ヲ以テ之[官吏の違法行為についての国の賠償責任]ヲ見レハ国ハ其機関ノ適法ノ処置ニシテ其責ニ任ス可キモノヲ自己ノ処置ト認ムル義務ヲ生スルニ過キサルヤ明カナリ蓋凡ソ国ノ思意ハ法規ニ依テ明表セラルルモノナレハ官吏ノ処置若クハ怠慢ニシテ此法規ニ適応スル場合ニ限リ思意ト事実ト相合同シ為ニ国ノ責任ヲ生スルナリ」
という説をあげることができる。官吏の違法行為については、いずれにしても、国家に帰属せず、官吏の個人責任として処理すべきだとされることになる。主権免責とともにこの教義の克服が各国の国賠制度確立の課題とされていた
。
しかし日本においては、帝国憲法の制定当時から第二次世界大戦の終結に至るまで、行政庁も官吏も国家の代理人として主権を行使するので免責される
、という非実定法的な論理に国家無答責の法理が依拠していたため、法治主義による根拠づけは追究されなかった。また、この法理が公法私法二分論または権力作用・非権力作用二分論を通じて司法裁判所における実体法の適用という次元で用いられたため、公務員と私人との間の法関係も公法関係ないし権力関係とみなされ、公務員の個人責任も否定されていた
。つまり、日本の場合には、違法行為の国家への帰属自体は容易に認められたが、損害に対する救済は与えられなかったのである。
以上のように、日本の国家無答責の法理は、法治主義による免責論を採用していなかったのである。
5)「結果責任」免責論
国家の活動が適法であったか違法であったかを問わず、その結果として権利侵害がもたらされる場合がある。無実の者が起訴された後に無罪判決を得たような場合や被疑者として勾留された後に不起訴になった場合である。今日では「結果責任」に基づく補償に分類されるような事案であるが、明治憲法体制の確立期には、これらの損害についての賠償責任の免除が違法な国家活動の免責例として頻繁に挙げられた。たとえば、旧民法草案373条に関する意見において、政府の法律顧問であったロエスレルが国の賠償責任の否定例として「不正ノ公訴若クハ逮捕ヲ蒙ムリテ後遂ニ放免セラレタル者アルトキハ国ハ之ニ賠償ヲ与フヘシトハ近来人ノ多ク主張スル所ナリ然レトモ此説過激ナル新制ノ理論ニシテ未タ曾テ何国ニ於テモ採用セラレサル所ナリ」
と述べ、また、行政裁判法改正の審議において、穂積八束が「裁判ノ如キモ人違ノ為メ無罪ノ者ヲ被告人トシテ永キ間之ヲ勾禁シ審理ノ餘無罪放免ヲ言渡スコトアリテモ法律ハ之ニ対シ故ナク自由ヲ奪ヘリトシテ損害賠償ノ要求ヲ為スコトヲ許シテ居ラヌ要スルニ公共ノ機関ガ公共全体ノ為ニ為シタルモノ故少々違法ノ事アリテモ之ヲ忍バザル可ラズ理論[行政庁の処分による違法な権利侵害の場合には当然賠償すべきだとする穂積陳重による憲法27条の解釈論]ヲ以テ之ヲ貫クコトデキヌト思フ」
と主張していた。この後も「公法上ノ賠償」の一環として「司法損害」が論じられ、1932年の刑事補償法ヘとつながっていくことになる
。
「結果責任」の事案において国の責任をどのように位置づけるかは、今日でも議論が続いている問題であって、この種の免責を国家無答責の論拠に結びつけることはできない。
6)過失または職務義務違反の不存在を理由とする免責論
理論的には上記5)と密接にかかわるが 、国家の活動が違法であっても、個々の官吏の過失または職務義務違反が立証できないような場合には、国家は賠償責任を負わないとする免責理論である。
この免責論は、一面では、違法性相対説につながるものである。たとえば、穂積八束は「職務規程ノ要スル形式ト手続キトヲ充タシタ行為ハ事務繁劇ノ為知識ノ不足ノ為急迫ノ為等ニ依リ其実質ニ過失アリタリト雖尚職務違反ト見做サレス故ニ責任ヲ生セサルナリ又上官ノ訓令ヲ執行スル場合ニ於テハ其執行手続及形式カ下官ノ職務規程ニ依拠シタルトキ其実質ノ不法ナリシニモ拘ハラス其責任ヲ免カル」
として、違法な行為でも職務規程違反がなければ、賠償責任は成立しないとしている。今日の国家賠償法の下で、実体法上で違法な行政活動であっても国賠法上の違法にはならないという理由から検察官の活動や税務署の活動が免責された例があるが
、上記の穂積説はこれと重なるものだといえよう。他面で、今日では国の無過失責任の問題として扱われているような問題群も含まれる。井上毅は、「官吏カ其職務上ノ義務ニ背キタル命令ニ依テ成シタル権利毀損」や「国会議院ノ失火ヨリシテ居宅ノ類焼」といった免責例を挙げているが
、前者は上記の違法性相対説の、後者は無過失責任の事案といえよう。
いずれにしても、これらの免責理論は、今日まで継続しているものであって、国家無答責の論拠となるものではない。
7)「損失補償」免責論
最後に、損失補償と損害賠償の理論的混同ないし両者の理論的統合を根拠とする免責理論を挙げておく。明治憲法の下では財産権の侵害に対する補償の要否と程度は法律に委ねられていたが、損害賠償についてもこれと同様に考える理論である。1890年制定の行政裁判法16条が「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」と定めたのは、もっぱら損失補償請求訴訟を行政裁判所の管轄から除外する趣旨であったが
、たとえば実際には、適法な収用に係る補償額の争いなのか違法な収用に係る賠償請求の争いなのかを容易に判別しがたい事案が多かったこともあって
、同条は国家に対する損害賠償請求訴訟を行政裁判所の管轄から除外する規定だとも理解された。この結果、財産権の内在的な制約を根拠とする損失補償の否認のような事件も違法な(財産権を制約するがゆえに違法な)国家活動の免責の例と考えられたし、他方で、国が損害賠償責任を負うのは法律にその旨の規定がある場合に限られるとする理解も生じた
。付言すれば、損失補償に関する規定が公法に位置づけられることに異論はなかったが、損害賠償に関してはこの点が不明確で(それゆえに、旧民法はもちろん新民法の制定に際しても国家活動に対する民法の不法行為規定の適用が議論されたのである)、大審院判例はこの種の事件を受理した上でアド・ホックに国の免責の範囲を画定していったのである。
(3)小括
以上のように、当時の国家活動の免責理論は多岐にわたっていたにもかかわらず、理論的な整理がなされないままで、立法作業および裁判実務が進められていた。上記の免責理論の多くが日本国憲法・国家賠償法の下でも維持されていることから理解できるように、何らかの免責理論が主張されていたからといって、それらのすべてを国家無答責の法理だということはできない。
では、これらの中で同法理はどのような位置を占めるのだろうか。
本節(2)で述べたところから明らかなように、国家無答責の法理は、理論的根拠として主権免責の理論を援用しながら、実際の適用の場面ではこれにいくつかの異なった概念を接合することによって、国家の主権的活動以外の広範な活動についても違法判断の回避を可能にした。すなわち、(1)行政裁判法制定前後の時期にはきわめて広範な国家活動を含む「行政処分」概念を、(2)1900?20年ごろの時期には(暗黙裏に)公法私法二分論を、(3)それ以降の時期には権力作用・非権力作用二分論を、主権免責の理論に接合させて、違法な国家活動の免責を図る理論だったといえる。そして、国家無答責の法理は、裁判管轄の次元ではなく、司法裁判所での実体法の適用(不適用)という次元での免責理論であったため、帝国憲法61条や行政裁判法15条・16条とは無関係に成り立っていたのである。
3.行政裁判法・裁判所構成法・旧民法の制定経過と国家無答責の法理との関係
(1)行政裁判法16条と国家無答責の法理との関係
行政裁判法の立法者は、損失補償・損害賠償の訴訟について、「第三 要償ノ訴ハ一般ニ民事訴訟ニ譲ルベキカ、又ハ或ル部分ニ限リ行政裁判ニ於テ処分スベキヤ」という問題を立て、「君主ハ不善ヲ為スコト能ハズ。故ニ政府ノ主権ニ依レル処置ハ要償ノ責ニ任ゼントハ一般ニ憲法学ノ是認スル所ナレバ、人民ハ一個人トシテ官吏ノ故造処置ヲ訴ヘ、民事裁判所ニ要償スルヲ除ク外、行政庁ヲ相手取リ要償ノ訴ヲ為スノ権アルコトナシ。但シ法律ニ依リ政府ハ賠償ノ責ニ任ズベキコトヲ明言シタル条件(徴発令ノ如シ)ニ於テハ、行政裁判所は要償ノ訴ヲ受理スルコトヲ得ベシ」
という方針を決めた。
とはいえ、「損害要償ノ訴訟」を全面的に排除することは予定されていなかった。公法上の債権に関する訴訟は--債権の成立に行政処分が介在するという理由で--行政裁判所で審理すべきだという発想が依然として存在していた。「井上案」とされる草案
に対して井上毅が提出した修正意見をみてみよう 。井上は、「官有財産ト人民トノ間の争訟」および「政府ト官有物買受人又ハ政府ト工業買受人其ノ他諸般ノ契約ニ付テ起ル争訟又ハ国債ニ於ケル政府ト人民トノ間ノ争訟」(「井上案」9条)については、「此二件ハ、政府カ公権ヲ行フニ依リ生スル争訟ニアラスシテ、全ク民法上一個人ノ資格ヲ以テ人民ニ対スルトキニ生スルモノ」であるという理由から司法裁判所の管轄にすべきだとする一方で、官吏の俸給、租税の減免、法律上で政府が損害賠償(損失補償)の義務を負担する処分に対する損害要償、行政処分により直接加えられた損害要償を公法上の債権として挙げ、行政裁判所の管轄とすべきことを主張した。また、行政裁判法の直接の出発点となったといわれる「モッセ案」では、この点を、行政裁判所の判決(介在した職務行為等の違法判断)を経た後に民事訴訟を司法裁判所に提起すべきものとした
。
1890年6月に成立した行政裁判法は、行政処分のうち法律勅令が許容した事件だけを行政裁判所が管轄するものとし、「損害要償ノ訴訟」については、結局、私法上の債権か公法上の債権かを問わずすべての訴訟を行政裁判所の管轄外とした。「損害要償ノ訴訟」のすべてを管轄外としたのは、補償額等の算定について行政裁判所が信頼されていなかったからだといわれている
。しかし、法典調査会の行政裁判法改正案にもみられるように、その後も一定の「損害要償ノ訴訟」を行政裁判所で処理させようという方向が追求された。他方、土地収用の損失補償額に関する裁判は民事裁判所で行われていた。
以上のところから、損害要償の訴訟の排除は行政裁判の本質にかかわるものではないし、行政処分に関わる損害要償の訴訟を民事裁判所が管轄しないとすることも裁判制度の本質にかかわる事柄とは考えられていなかった、ということが理解できよう。行政裁判法16条は、このように、行政処分に関わる損失補償・損害賠償訴訟および公法上の債権に関する訴訟についての暫定的な裁判管轄配分の規定だったのである。
これに対して、上述のように、国家無答責の法理は、裁判管轄の問題とは無関係の実体法理であった。同法理と行政裁判法が結びつくのは、むしろ15条に関連する「行政処分」概念を通してであるが、同条も管轄規定で直接の根拠規定とはなりえず、また、その使用が断念されたことは既述の通りである。要するに、立法史的にも論理的にも、国家無答責の法理の実定法上の根拠を行政裁判法16条に求めることはできないのである。
(2)裁判所構成法の制定と国家無答責の法理との関係
裁判所構成法の制定過程において国に対する民事裁判の管轄規定が削除されたことが、国家無答責の法理の実定法上の根拠だとされることがある。この点については、先に提出した鑑定意見書の2(3)で詳論したが、若干の補足をしておく。
上記のような実定法説は、下山瑛二の推測、すなわち「この井上意見書の影響によるものか否かは詳らかになしえぬが、これらの意見が客観的に通った形で裁判所構成法が制定されたことは銘記されねばならない」、「したがって、憲法起草者の法意識としては、国にたいする賠償請求は、基本的には、司法裁判所においても否定する考えであったということができるであろう」
という記述をしばしば援用する。しかし、これも国家無答責の法理の根拠にはなりえないと思われる。
第一に、削除された規定も裁判管轄の規定であって、同法理が用いられる実体法の適用という次元とは関わらない規定である。第二に、井上が「[財産上の訴訟以外については]国にたいする賠償請求は、基本的には、司法裁判所においても否定する考えであった」ということは可能であろうが、憲法起草者の一人がこのように考えていたからといって、これを裁判所構成法の立法者意思とみなすことはできないはずである。第三に、井上も含めて、国に対する賠償請求のすべてを否定しているわけではないのであって、立法者側が表明した反論も考慮すれば、「地方裁判所の民事訴訟についての管轄に属するものの中、国より為し又は国に対してなすすべての請求と官吏に対してなすすべての請求を除いたのであるが、これは、民事訴訟において特に国をその他の個人と区別する必要がないものとみたからであろう」
というまとめが妥当だと思われる。
以上のところから、裁判所構成法制定の過程で国に対する民事裁判の包括的管轄規定が削除されたことは、国家無答責の法理が実定法上で確立されたということの根拠にはならない、と考えざるをえない。
(3)旧民法373条と国家無答責の法理との関係
1)旧民法の立法者と井上毅
旧民法373条の策定過程で「公ノ事務所」規定が削除されたことが、国家無答責の法理の実定法上の現われだという主張がある。その根拠としてしばしば援用されるのが、近藤昭三の「しかし結局、国家責任に民法原則を適用する主張は、最後の段階で敗退した。井上毅がいかなる方法で『再議ノ機会』をとらえて「未来ノ大問題」にとり組んだかは詳らかにしえないが、旧民法373条から国家責任の規定は姿を消した。井上毅は、旧民法公布の翌年、国家学会雑誌に「民法初稿三百七十三条ニ対スル意見」を発表し、国家責任の成立を認めるべきでない所以を公に定式化し、国家責任肯定論の敗退を確認するのである」
という記述である。
しかし、この推測は次の諸点において明確に誤りである。
第一に、井上の今村和郎宛書簡での内容が立法者に受け入れられたわけでもないし、井上が主張したような理由で「公ノ事務所」規定が削除されたわけでもない。「国家責任に民法原則を適用する主張は、最後の段階で敗退した」というのは無根拠の断定にすぎないのである。立法作業に当たった法律取調委員会自身のまとめによれば、(i)「公ノ事務所」の責任については明言せず、単に委託者は受託者の受託職務について責任を負うと規定するにとどめる、(ii)官吏が受託者として過失ある行為を行った場合には、政府・官庁は賠償責任を負う、(iii)いかなる場合に政府・官庁が委託者に該当するかという問題は裁判官の判断に委ねる、ということなのである
。これに加えて、旧民法の立案担当者らが執筆した注釈書において「公ノ事務所」規定の削除がどのように説明されているかをみてみよう
。
「本条草案ニハ公私ノ事務所ハ其属員ノ加ヘタル損害ニ付キ其責ニ任スル旨ヲ明言シタリシニ修正ノ際之ヲ削除シタリ然リト雖モ其意決シテ官署ヲシテ無責任タラシムルニ在ラス此事タル法文ヲ待タスシテ自カラ明カナリト看做シタルニ因リ遂ニ削除ニ至リタルナリ蓋シ国府県其他官庁モ義務成立ノ事ニ関シテハ普通法ニ従ハサルヘカラス其属員カ受任ノ事ヲ行フニ際シ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ之ヲ賠償スルノ義務ヲ免ル可カラサルヤ論者ノ普ネク認フ為メメタル所ナリ唯実際加害者ヲ以テ官署ノ受任者其受任ノ職務ヲ行又ハ之ヲ行フニ際シテ損害ヲ加ヘタルモノナルヤ否ヤヲ判別スルニ付キ多少困難アルヘキカ」
すなわち、「公私ノ事務所」規定を削除した趣旨は決して官署の免責のためではなく、法文で定めなくても自明だからであり、官吏が受任の仕事を行う際に他人に損害を与えたときは、官公庁が賠償責任を負うということは誰もが認めている、と。これが立法者意思であった。
第二に、井上を「この立法過程に参加した井上毅」とか「旧民法の起草者」 などとするのは論外だが、井上の1891年の論文をあたかも立法者の解説のように位置づけているのは誤解に基づくものであろう。繰り返しになるが、井上は法律取調委員会のメンバーではなかったし、彼らとはかなり異なった見解を持っていたわけであるから、けっして「国家責任の成立を認めるべきでない所以を公に定式化し、国家責任肯定論の敗退を確認する」立場にはなかった。
第三に、1891年の論文「民法初稿第三百七十三条ニ対スル意見」は、その表題からして理解できるように、旧民法373条の制定経過を解説したものでも、趣旨説明をしたものでもない。同論文はボアソナードの原案(改訂案初稿の第373条=1889年6月の時点)に対する批判論文であって、「公私ノ事務所」という文言が草案条文中に存在することを前提とした記述になっている。また、その記述の主要部分は、モッセの意見書(改訂以前の草案第393条に対する批判)の抜粋・要約ともいえるものであり、結論部分は今村宛の書簡に近似したものである
。それゆえ、執筆時期は1989年6月ごろと推定されるが、いずれにしても同論文は、旧民法草案737条がいかに外国の例とかけ離れていて「危険ナル効果」をもたらすかを述べているだけであって、制定経過に触れた部分も敗退を確認する文章もまったく含んでいない。すでに廃案となった「初稿」延々と批判した後に付加された「現行民法ニハ此ノ条ナシ」という文言だけをもって、「国家責任肯定論の敗退を確認する」とは評価できないだろう。
2)国の損害賠償責任に関する旧民法の立法者の意識
つぎに、この問題についての旧民法制定時における立法者の意識を確かめておく。旧民法制定時における議論(1888年2月の法律取調委員会での旧民法草案393条の審議)は、以下のようなものであった
。
「(尾崎委員) 官庁ノ役人抔ガ仕出シシテ損害ヲ掛ケレバ官庁ガ償ウカ
(南部委員) 小使ガ損害ヲ掛ケレバ司法ガ償ウ
……
(尾崎委員) 役人ガ御用デ旅行シテ損害ヲ与ヘタトキハ
(鶴田委員) 職務ト云フ見分ケガ付ケバ宜シイ
(南部委員) 一般ノ職務ヲ以テヤルノハ別デシヨウ、仮令バ会計ノ役人ガ普請ヲスル様ナトキハ
(鶴田委員) 戸長ガ奥印ヲシテ失錯ヲシテ自分ガ損害ヲ蒙リタルトカ、良シ故意ニシテモ戸長ノ名誉ガアルカラ職務上デ為シタルモノト見ナケレバナリマセン、損害賠償ヲ云テ来モノガ沢山アル、其レハ政府カラ出スカ、戸長カラ出スカト云フ論ガアル、種種論ジマシタガ出シ切レヌカラ出サヌコトニ裁判ヲシマシタガ、據ナイノガアルカラ内閣ニ迫テ到底出サナケレバナラヌト云タガ、出ソウトモ云ハズ、今以テ出サナイ
(南部委員) 行政ノコトハ別デ御座イマシヨウ
(尾崎委員) 司法カラ頼マシテ過ツテ損害ヲ掛ケタトキハ官庁ガ償ウノハ困ル
(栗塚報告委員) 兵隊ガ過ツテ人ニ怪我ヲサセタノハ
(鶴田委員) 林謹一ナドハ兵隊ニ茶畑ヲ荒サレタ
(栗塚報告委員) 尤モ適用スルニ困難モアルガ、原則ハドウシテモ之ガ本統ダロウト思ヒマス
(鶴田委員) 道理カラ云ヘバ之ガ原則ダロウ
(栗塚報告委員) 困難ニモセヨ、此裏ヲ考ヘテ見レバ職務ヲ行ウトキダカラ知ラヌト云フコトハ出来マセン
(尾崎委員) 其レハ役人ガ償ウ、役人ナドハ知識モ具ヘテ居ルカラ自分デ悪ルイコトヲシテ損害ヲ掛ケレバ自分デ償テ宜シイト思フ
(南部委員) 官ガ償ウ、役人ガ償ウト云フコトハ別ニ細カイ法律ガ出来ナケレバナラヌト思ヒマス
(栗塚報告委員) 唯箇様ナ原則ニ定メテ置クト云フノデ足リルト思ヒマス
(清岡委員) 司法省ノ普請ヲスルトキ怪我ヲシタ者ニ薬代デモヤルノハ今日デモヤツテ居ル
(渡委員) 仮令バ兵隊ガ調練ヲスルトカ、或ハ野外演習トカデ、畑ヲ踏荒シタトキハ皆軍馬局カラ償テヤルカラ理ニ於テハ同一ナル訳デアル
……
(委員長) ……親方ガ子分ノ為シタ責ニ任ズルカラ役所ヲ役人ノ責ヲ負ハナケレバナルマイ、之ハ原案トシテ先キヘ行キマシヨウ」
栗塚報告委員と鶴田委員は原則として国が賠償責任を負うべきだとする立場、清岡委員と渡委員は(実際に賠償類似の支給が行われていることをふまえて)これに同調する立場、尾崎委員は官吏の個人賠償を主張する立場、南部委員は賠償責任を国が負うべき場合と官吏個人が負うべき場合について詳細な法律が必要だとする立場である。要するに、この時点では、国は当然に賠償責任を負うべきであり、実情から見てもそれが当然だとだという考え方が支配的だったのである。
3)新旧民法の制定者および大審院からみた国家無答責法理の根拠
旧民法の制定者はもちろん、新民法の制定者たちも、国家無答責の法理を実定法理とは考えておらず、むしろ明確に判例法理ととらえていた。この点は、審議過程での彼らの発言をたどれば明らかである。
法典調査会による新民法の審議の中では、「公権ノ作用」について国が免責される根拠として、「慣習法になっている」(都筑委員)、「判決例で公法上の職務執行の過失による損害の賠償は行わないという例になっている」(同)、「公法と私法の区別」(横田委員)、「政府の賠償責任を認めた大審院判例はなく、これを認めないのが一般的傾向」(高木委員)、「法律違反の行為は一個人の行為であって国の為にやる行為ではない」(同)などの点が挙げられている。けっして「明治23年の旧民法制定時に決着済み」という態度はとられていないし、誰もこれを援用していない
。
つぎに大審院判決をみると、どの判決文を見ても明らかだが、とくに大判1943(昭和18)・9・30が「官吏又ハ公吏カ国家又ハ公共団体ノ機関トシテ職務ヲ執行スルニ当リ不法ニ私人ノ権利ヲ侵害シ之ニ損害ヲ蒙ラシメタル場合ニ於テ其ノ職務行為カ統治権ニ基ク権力行動ニ属スルモノナルトキハ国家又ハ公共団体トシテハ被害者ニ対シ民法不法行為上ノ責任ヲ負フコトナキモノト解セサルヘカラサルコト当院ノ判例トスル所ニシテ(昭和十五年(オ)第六二六号同十六年二月二十七日判決)之ヲ変更スルノ理由ナク又其必要ナキモノト認ム」と明言しているのを見れば、大審院が国家無答責の法理に実定法の根拠があるとは考えておらず、1940年ごろに確立した判例法と考えていることが分かる。判例による変更の余地も認めているのである。また、大判1941(昭和16)・11・26は同法理が適用されず国の賠償責任が認められる場合があり、その基準として「行政処分又ハ其ノ執行カ民法上ノ不法行為ヲ構成スル為メニハ其ノ範囲ヲ逸脱シ行政処分又ハ行政執行ト目シ難キ程度ニ至リ以テ他人ノ権利ヲ侵害シタルコトヲ要スト解スヘキ」ことを挙げている。付言すれば、最三小判1950・4・11も判例法説に立っているのであって、実定法説は近年の裁判例が捏造したものだといわざるをえない。
(4)King can do no wrongの法理と主権免責論と国家無答責の法理との関係
法制局長官に着任した井上毅は「裁判所構成法案ニ対スル意見書類」でブラックストンを引用している。
「第一 国ニ対スル訴訟ノ事 ブラクストン氏王権論ニ云ハク、王ニ対スル訴訟ハ民事ト雖モ之レヲナスコト能ハズ、蓋何ノ法院モ国王ヲ裁判スルノ法権ナケレバナリト。故ニ英国ニ於テ君主及ビ政府ニ対スルノ訴訟ハ唯請願ニ由リテ恩恵ノ許可ヲ得タル後始メテ裁判ヲ受クルコトヲ得。普国千八百三十一年十二月四日ノ閣令ニ云ク、君主ノ資格ニ於テ臣民トノ間ニ裁決ヲ要スルノ権利ノ争ヲ生ズルノ理ナク、又之レヲ裁決スルノ権限アル裁判所ハ全国ニ一モ存スルコトナシト。
政府ニ対スル訴訟ハ独逸ニ於テ国権ト区別シタル財産上ノ訴訟ヲ許シタルノミニシテ、単純ニ国ニ対スル訴訟トシテ之レヲ許シタルノ国アルコトナシ。今本案ニ国ニ対スル訴訟ヲ以テ裁判所ノ権内ニ帰シタルハ其ノ当ヲ得ザルノミナラズ、専ラ居留外国人ノ日本政府ニ対スル訴訟ノ爲ニ地ヲ爲ス者ナリ。」
上記の部分は、ブラックストンが「いかなる裁判所も国王に対する裁判権を持ちえないので、民事事件であっても、国王に対しては何らの訴訟も提起できない」
と述べているところを指していると思われるが、この節はまさしく国王の特権中の主権を論じている節であって、政府について(そして行政権について)述べているわけではない。
また、行政裁判法の立法過程で"king can do no wrong"という格言について、「君主ハ不善ヲ為スコト能ハズ。故ニ政府ノ主権ニ依レル処置ハ要償ノ責ニ任ゼントハ一般ニ憲法学ノ是認スル所ナレバ、人民ハ一個人トシテ官吏ノ故造処置ヲ訴ヘ、民事裁判所ニ要償スルヲ除ク外、行政庁ヲ相手取リ要償ノ訴ヲ為スノ権アルコトナシ」といった説明がなされたが、ブラックストンによれば、この格言は、主権免責ではなく、法治主義に基づく者である。
「主権という特質のほかに、法は、国王に対して、その政治的権能が完全無欠であることを認めている。国王は悪を為しえず(The king can do no wrong)。この古来のそして基本的な格言は、政府が行ったすべての行為があたかも当然に正当かつ合法だといったように理解されてはならず、単に、次のふたつのことを意味するに過ぎない。第一に、公務の遂行において問題視されうるような事柄はけっして国王の責に帰せられてはならないし、また、国王はその事柄について自国民に対してじきじきに責任を負ってもいない、ということである。というのは[もしこのように解釈しないならば]、わが国の自由で動態的な--それゆえさまざまな要素から成り立っている--憲法体制において権力の均衡のために不可欠である国王の憲法上の独立性を、この法理が完全に破壊することになってしまうからである。そして、この格言の第二の意味は、国王の大権は何らかの侵害をおこなう程度にまで拡張されることはない、ということである。なぜなら、国王の大権は国民の福利のために創設されているからであり、またそれゆえ、国民を侵害するために行使されることはありえないのである。」
すなわち、この格言の意味は、第一に、違法行為の帰属不能(クリーンハンドによる調停権力としての国王)、第二に、権力制約にあるとされている。日本では、法治主義の理論として理解されず、むしろ主権免責を裏づける格言と誤解された。
ここでは詳しい検討はできないが、上記の二例をみただけでもこの格言についてはかなりの誤解があるものと思われる。
4.おわりに
本稿は、第一に、明治憲法体制の確立期にさまざまな免責理論が主張されていたとしても、それは必ずしも国家無答責の法理が存在していたことの証明にはならないこと、日本における同法理は、主権免責に、(1)広範囲な国家活動を包含する行政処分、(2)公法私法二分論、(3)権力作用・非権力作用二分論をそれぞれの時期に接合して成り立っていたこと、を示した。第二に、行政裁判法16条、裁判所構成法制定時における国の訴訟に関する規定の削除、旧民法制定時における「公ノ事務所」規定の削除のいずれも、国家無答責の法理を裏づける実定法上の根拠とはならないこと、むしろ立法者および大審院の認識では判例法理に過ぎないこと、を明らかにした。
国家無答責の法理の適用に関する私の基本的立場は、「同法理は判例法理であるので、『従前の例』(国家賠償法附則6項)には該当せず、また今日の時点での法体系と理論をふまえれば、今日の裁判所において適用可能な法理ではない」というものである。この点で、今日の法体系をふまえて、現行法の下で同法理を適用する合理性・正当性を見出し難いとして、その適用を否定する最近のいくつかの裁判例を支持することができる。また、本件のような事案は「行政処分又ハ行政執行ト目シ難キ程度ニ至リ以テ他人ノ権利ヲ侵害シタル」(上記大判1941・11・26)ものであることは間違いなく、大審院の基準からみても救済の必要性が高い事案だといえるだろう。
|